〈ルポ〉 家族システム看護の実践
山口県立中央病院看護部の試み
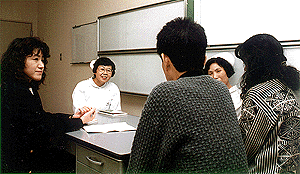 | |
| 協力: | 山口県立中央病院看護部(中野三輿子看護部長) |
| 森山美知子氏(前・山口県立大学看護学部) | |
山口県立中央病院看護部の有志らが森山美知子氏と「家族システム看護研究会」を結成したのは1994年のことであった。森山氏がアメリカ留学中に学んだカルガリー大学の「家族アセスメントモデル,家族介入モデル」を参考に,日本では最初に山口県立中央病院看護部で症例展開をしはじめた。
家族システム看護は北米の看護界において,1970年代からシステム理論を基礎として家族療法に看護的要素を加え発展してきたものである。これら家族への看護アセスメント・看護介入に関しては,『家族看護モデル―アセスメントと援助の手引き』(森山美知子著,医学書院,1995年)に詳しく紹介されている。
本紙では,同病院の6F南病棟で行なわれた家族へアセスメントのインタビューを取材した。


本来の家族の機能を取り戻すために

「人に迷惑はかけたくない」を信念に
今日インタビューをするAさんは糖尿病で,現在網膜症,腎症,神経症を合併している67歳の男性。2人の子どもが独立した後に離婚,仕事もやり終えた現在,1人で生活をしている。今回は,血糖コントロール目的で入院してきたが,1つの問題が解決しても次々と他の症状が出現し,入院が長期化している。退院に向けて外泊を試みると,嘔気が伴い食事ができないなど調子が悪くなっても誰にも伝えることなく,いつも低血糖で倒れ救急車で搬送されてくる。
Aさんは,これまで家庭を顧みず自分勝手な生き方をしてきたこともあり,家族に甘えることを良しとせず「人に迷惑はかけたくない」を信条にしている。これに対し,看護スタッフは「自分1人で対処しようという気持ちがストレスとなり,身体症状が出現するのではないか」,「誰かのサポートがあれば状況が変化するのではないか」と考え,インタビューの機会を持った。
インタビューにあたっては,Aさんおよび長女の家族(長女,長女の夫,孫)に参加を依頼したが都合がつかず,結局Aさんと長女だけのインタビューとなった。
「Aさんは『娘には迷惑をかけたくない』が口癖です。その気持ちがあまりに強いために,身体症状に逆効果となって現れるようです。これからの退院にあたっては,自分1人で何でもというよりは,ちょっとしたサポートがあれば,退院後の生活もよい方向に向かうのではないかと考えました」と,山口県立中央病院6F南病棟の石井周子主任は,Aさんにインタビューをするにあたって説明した。
Aさんは,
「せがれは忙しいしね,娘のほうがなんでも言いやすい。でも,よほどのことがなければ娘の家にも気兼ねするし,連絡はしない」と語る。
「娘なのに役にたてないという思いがありますが,自分の生活もありますしね。ここにいれば(入院していれば)安心という思いもあります」とは長女。
石井さんは,病床でAさんから聞いていた兄弟姉妹,息子,娘,孫のこと,そして隣人,友人とのかかわりなどを再確認するようにインタビューしていく。
1人暮らしをしていると,「病院にいるほうが楽」という患者が多い中,Aさんは「病院にも迷惑をかけるから早く退院しなければ」とのプレッシャーを感じており,早期退院をめざしているのだが,帰宅すると孤独であり1人では生活できないため帰れないでいる。それが気がかりだと石井さん。そんなAさんを,「生きていくことに前向き」と石井さんは評価する。
人を頼りにするのが嫌いという父親がいて,面倒をみたくとも時間がとれないというジレンマを抱える長女がいる。
「父が本当に食事療法がわかっているのかは疑問です。いつも友人が買ってくる寿司を食べたりしているけれど,そんなのでいいのかなと考えてしまいます。せめて食事の管理をしてくれるホームヘルパーさんかボランティアさんがいてくれたならと思っています」
今回のインタビューでは,自分が家庭を崩壊させたという,家族に対する罪悪感を娘に直接伝えることで,長女との距離を近づけることができた。戸井間充子婦長は,
「これからは,自分の健康を保つためにはどのようにすればよいのかを考えることも必要だと思います。次回にはそのあたりの話をお聞かせいただきたいと思います」 と,Aさんに宿題を課した。自分の健康を守るためにはどうすればいいのかの答えを出せる人。だからこそ宿題にした。
長女には,Aさんの精神的なバックアップと安否,在宅での様子をみてもらうことを依頼した。そして給食サービス,ヘルパー派遣などの地域のサポートを利用する体制を整えた。またAさんには,倒れる前に自分から人に助けを求めることも必要と諭し,悪循環の解消を図った。
Aさんの今回のケースは,家族の問題というよりも,本人の姿勢が問題だったと同席した森山さんは分析した。
家族システム看護の臨床応用
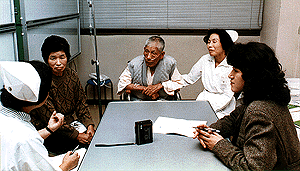
「婦長さん,私の話も聞いてください」
戸井間さんたちが,インタビューを取りはじめて実感できたのは,患者はどれほど孤独であり,寂しく思っていたのかということだった。配偶者に捨てられた人もいた。インタビューをした患者の隣のベッドの患者さんが,婦長をつかまえ「私の話も聞いてください」と言ってきたこともある。「新しい方式を取り入れるわけですから,最初から看護部の全員がそろって賛成というわけにはいきませんでした。中には疑問視する声もありました」と語るのは白石日出子副看護部長。白石さんから,家族システム看護の導入の経緯などをうかがった。
山口県立中央病院看護部の有志が研究会を組織し,「家族システム看護」の実践を始めたのは1994年。今もまだ試みの段階で,全病棟で実施しているわけではない。自主的に開催される家族看護の勉強会には,看護職の自由参加としている。
「第3者が家族に介入することで,それまでバランスを崩していた家族の機能を修復できますし,家族間の会話がスムーズになります。ターミナル期にある患者の家族はインタビューによって変化が見えやすいのですが,慢性疾患患者の家族は変化が見えにくく,効果の判定は難しいですね」と家族システム看護の効果を語り,家族を集める意味は,家族の意志疎通を図るためであり,家族がいかに機能するかを再確認させる役割があるという。さらに,
「家族システム看護を,日常の看護の一貫としてとらえることができるようになり,患者さんに語らせるという傾聴の姿勢ができました」と,看護職に及ぼした影響を語ってくれた。
家族に介入する意義
山口県立中央病院で実施しているインタビューの対象者は,(1)家族員の急な病気,入院,死などの危機に直面し感情的障害を体験している家族,
(2)病気の末期状態など危機に陥りそうなほど重大な問題を体験中の家族(悲嘆のプロセスがスムーズに経過しない,家族の誰かに過度の介護負担がかかっているなど),
(3)慢性疾患や脳梗塞後の障害,痴呆などで長期療養を必要とする家族員を抱え,適応に障害を来している家族(糖尿病で入退院を繰り返し,家族のサポートが足りないと感じた時など),
(4)精神科に入院しなければならない患者を持つ家族,
(5)患者の症状が家族員の悪循環の中から生じてきていると予測される家族,
(6)病気の患者を抱え,核家族,親戚などを含めた拡大家族の中で機能障害や人間関係に障害を来している家族,としている。また,この他にも入院中に家族介入した患者・家族の在宅訪問での展開もある。
例えば,食事療法が守れない患者には,家族を集めて,家族全体で患者を支えていくにはどうしたよいのかを話し合い,また告知するか否かで悩む家族に対しては,どうしたら互いに支えあうことができるのかを話し合う。看護職は,ここで関係する家族を一堂に集め,家族とのインタビューを中心に,家族への介入を行なう。
均衡のとれなくなった家族に対し,元の均衡を取り戻す援助をするのが家族システム看護であり,家族の自然治癒力を最大限に引き出すことを目的としている。
山口県立中央病院の看護婦有志は,この家族システム看護モデルを臨床応用し,慢性疾患患者,ターミナル期にある患者,脳梗塞で倒れた患者,ストレス性疾患に苦しむ患者,およびそれらの家族,そしてボディイメージの変容から夫婦関係に障害を来した家族などにかかわってきている(これらの症例報告は雑誌「訪問看護と介護」,「臨床看護」等で紹介されている)。
家族ではなく,患者の問題
2件目のインタビューを行なう前に,戸井間,石井,森山の3氏は,患者さんと妻の座る位置や仮説の確認をしている。「患者さんとインタビュアーの座る位置に意味はあるのですか」と尋ねた。
「あります。いつもは患者さんと家族が部屋に入ってきた時に,自由に座ってもらうのですが,その座る位置によって,家族の関係を知ることができます」と森山さん。
今回インタビューをする患者さんは,点滴もしており前もって配置を決めたが,インタビュアーの座る位置やライティングなどにも配慮をするとのこと。
インタビューの対象となった71歳のMさんは,喘息から肺炎を引き起こし退院が長引いている患者さんだ。69歳まで仕事一筋で生きてきたが,喘息が頻発するようになり,2年前に仕事を辞めざるを得なくなり退職。その後1年間に3回入院,約半年間を病院で過ごしている。Mさんには全快した肺結核の既往歴があった。
インタビューを始めてしばらくすると,これは家族に起因する問題ではなく,Mさん自身の生活リズムの悪循環が問題であることに気づいた。そこで,石井さんたちは病気にならないためにはどうしたらよいのか,生活のリズムを変えるにはどうすればよいのかを,こちらから提示するのではなく,患者が気づくように話を転換させた。
「このご夫婦の場合,家族モデルの対象にはなりませんでした。家族インタビューではなく,奥さまの不安の解消,Mさん本人の心機的な問題であり,その解決に向けた話となりました」と森山さん。
このケースのように,家族に病状悪化の要因があると思える患者でも,いざインタビューをしてみると患者本人の問題だったりすることも多いと言う。その場合には,家族インタビューから家族を帰し患者個人に対するカウセリングに切り替えることもあるとのこと。患者が話す(聞いてもらう)ことで,患者の持つ不安を解消できることもあり,それが治療へとつながっていく。
インタビューは2人で
ここで,理想的なインタビュー構成について戸井間さん,森山さんに尋ねた。「看護婦サイドは2人で入ります。そうしますと,どちらかが家族を客観的に観察でき,効果的なインタビューができます」と,相手の話に取り込まれず,中立性を保つことが大切なポイントであると語った。
患者から聞き出す話は,実はシステム看護のアセスメントモデルに沿うようにしている。そして,(1)家族が提示している問題は何かを見出し,(2)家族員の相互作用の悪循環とそれを生み出す考え方をを明らかにし,(3)問題を解決するためにこれまで家族が試みたことを話してもらい,その効果について評価し,(4)アセスメント後に続けて看護職が介入するか否かを決定し,介入するならば家族とともに治療目標を設定する,という段階を踏んでいる。
問題が家族のさまざまな下位システムにまたがる場合や問題が複雑な場合には,家族を分けて話し合うこともある。一堂に集まってもらった場合には,家族の一員が思わぬ展開を起こすきっかけを作ることも多いという。それがおばあちゃんだったり,子どもだったりする。彼女らの一言で,家族が変わる。劇的に変わる家族が多いとのことだが,そのきっかけとなる一言はどこで気づくのだろうか。
「悪循環を抱えている家族は,これだ!と,聞いていてわかります」と森山さんは言うものの,こちらはどこがポイントになるかはわからない。そこで,
「それは慣れているからであって,家族システム看護を実践していない一般の看護職も気づくものでしょうか」と伺った。
「いや,それは気がつかない場合が多いと思います。2人でインタビューに入る理由はここにもあります。1人だとその大切な部分を聞き逃してしまうこともありますが,2人ですと『あっ!』と気づくことができますから」と戸井間さん。
さまざまな症例から
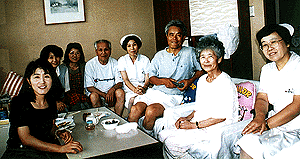
ボディイメージの変容に伴う夫婦間の問題も家族看護の対象になる。
結婚1年目に不妊外来を受診したところ乳癌がみつかり,乳房切除術を施行,8年後に転移から卵巣摘出を行なった,36歳の女性の例がある。
明るい性格の彼女は,同室の患者を楽しませる役割を担っていたが,ある日泣いている姿を担当の看護婦が目撃。話を聞くと,「乳房切除後,夫との性交渉が徐々になくなり,会話もなくなってきた。自分が原因……」と悩んでいる。そこで健康な夫婦の機能を取り戻すべく,家族システム看護の対象として,夫を含め話し合うことにした。
「男はあれこれしゃべるものではない」
「うん,ああ,だけの返答ではなく,成立する会話がほしい」という夫婦の考え方のすれ違い,その根底には,
「こんな身体になって……,子どもも産めなくなって……」という思い,「甘えたい,触れてほしい」という葛藤,会話なき生活,の悪循環があった。
3回のインタビューの結果,夫婦は寝室をともにするようになり,言語的コミュニケーションも密になるというように,夫婦関係に変化が生じた。
「人間の反応に包括的に対応する看護職は,家族のセクシュアリティの領域にも介入し,援助することにより,総合的な健康を増進させることも可能」と森山さん。
インタビューの中で,双方に平等の意見を求めること(中立を保つこと)で,お互いの思いを伝え合うことができるこの夫婦の場合は,ありのままの意見を述べ合うこと,悪循環を引き起こしたコミュニケーションパターンを再学習することで,悪循環パターンを修復することができた。
患者の死から学ぶこと
一方,告知に関連した事例も数多くある。離婚を考えるほど家族関係が崩壊したまま,突如癌により死に至った41歳の患者(夫,父親,息子の役割があった)とその家族の関係もある。姑・義兄弟の過干渉から夫婦関係も崩壊し,子どもたちは1度も見舞いにこなかった。告知に関連して,意見の対立したこの家族に,段階的に介入を行なう戦略を考えた。双方の家族関係が際立って悪かったために母親,妻それぞれにインタビューを行なった。その後,家族を一堂に集めてインタビューを行なう予定だったが,その前に患者は死亡した。
患者によりよい生のまっとうを,また家族には思い残しがないように,死にゆく患者とその家族のQOLにどのようにかかわるか,看護職の役割は大きい。
また,父親を亡くした3か月後に母親を亡くすという不幸に遭遇した未成年者(18歳女性)の例では,どのように子どもが親の死にかかわるかを考えさせられた。
患者(母親)は,入院中とてもいらいらしているにかかわらず,見舞いにくる娘には「心配しなくてもいい,早く帰りなさい」と追い返し,その後強い痛みを訴えていた。
一方,娘も見舞いにきても母親の強い言葉に圧倒され,すぐに帰っていた。母親とは,父親の死についての話はしていない。
患者は,娘や患者自身の姉妹に迷惑をかけたくない,心配させたくないとの思いの反面,そばにいてほしい,甘えたいとの思いがありながらもその思いを伝えきれず,痛みが増強していたのではないかと考え,家族介入を行なった。家族を招集したところ,中国・九州地区から12人の家族が集合。その場で母親の思い,子どもの思いを確認することができた。そして,拡大家族からの娘への支援も確認できた。結果,娘は「父親の時はなにもできなかったから」と,母親のそばにいるようになり,母親からの痛みの訴えもなくなった。
「臨床の中で看護職は,死に関連する話を避ける傾向にあります。その中にあって,患者は孤立してしまうこともあり得るのです。家族も同様に,死を話したがりません。生への希望は死ぬその瞬間まで持ちつづけます。その患者の希望を医療者も家族も維持しつつ,悲嘆の作業を進めていく必要があります」と森山さん。 そのためには,患者や患者を支える家族の状況をアセスメントし,どこが悲嘆のプロセスの障害となっているか,悪循環を明らかにし,家族内で痛みや苦しみを分かち合えるように働きかけていくことである。
家族システム看護の成果
戸井間さんは,これまでに行なってきた家族システム看護の成果について次のように語ってくれた。「家族看護をすることによって,看護そのもののみかたが変わりました。患者は家族の中の一員であり,家族員間の関係性が患者の健康回復に大きく影響していることがわかりました。家族にかかわることで,家族は自らが大きく変化していくことも学び,今までならば患者さんに『こうしたら』『こうしたほうがいいですよ』という指示的態度があったのですが,それも家族に介入した影響でしょうか,なくなりました。私自身も大きく成長しましたが,他の看護者も変わってきたのがよくわかります。私としてはこの家族システム看護を多くの看護職者に広めたい思いでいっぱいです。この方式ですと看護職ならば誰でもできることなのです。まずやってみることが重要ですね」
病院での看護職,患者関係がよい方向に変わった,看護職の意識向上がみられた,結果的に早期退院につながったと,山口県立中央病院看護部では着実に家族システム看護の成果をあげている。この試みは今後も大いに注目されよう。
