MEDICAL LIBRARY 書評・新刊案内


これ1冊で実地診療に役立つ内科学書
新臨床内科学 第7版 高久史麿,尾形悦郎監修《書 評》曽根三郎(徳島大教授・内科学)
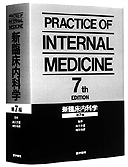 『新臨床内科学』(第7版)が内容をさらに充実して医学書院より上梓された。1974年に初版が出てから20数年になる。医学の急速な進歩により,この20数年は分子,遺伝子レベルでの病態解明と診断法,治療法の開発が目覚ましいが,本書は常に最新の情報を備えるべく改訂が繰り返され,今回第7版に至ったわけである。各専門分野にまたがる多数の編集委員の方々の英知を結集したたまものであり,その努力には敬意を表したい。
『新臨床内科学』(第7版)が内容をさらに充実して医学書院より上梓された。1974年に初版が出てから20数年になる。医学の急速な進歩により,この20数年は分子,遺伝子レベルでの病態解明と診断法,治療法の開発が目覚ましいが,本書は常に最新の情報を備えるべく改訂が繰り返され,今回第7版に至ったわけである。各専門分野にまたがる多数の編集委員の方々の英知を結集したたまものであり,その努力には敬意を表したい。
今回の改訂は,160名以上(全執筆者の1/3強)の新しい執筆者を加えてのものである。冒頭には「内科臨床のファンダメンタルズ」として内科学を理解するための必須項目が設定されている。このような企画は他書には見られないものであり,内科学の各論化,専門化が進みすぎとされる中で内科学の総論を重視した新鮮な編集方針である。また,POS(problem-oriented system)の取り組みは研修医のみならず,われわれ内科医にとり日常診療における基本的な考え方である。新しく取り入れられた「臨床決断科学」も耳新しい言葉であるが,今後臨床医学が科学として成長していく上で重要視されていくことと思われる。学生,研修医から内科を専門とする実地医家までの広い層を対象とした企画が全体を通して伝わってくるのも本書の特色である。
分子生物学的アプローチを随所に
今回,分子生物学的なアプローチとそれによって得られた最新の情報が各系統疾患別に病態生理として理解しやすく随所に盛り込まれており,免疫学,遺伝子医学,腫瘍学などの横断的なテーマも数多く紹介されているのも第7版の特色である。また,各疾患についての疫学,治療,予後に関する臨床成績も最新のものが数多く記載されており,疾患の位置づけや問題点が客観的に把握できるのも本書の利点である。各疾患を系統的に理解
本書は当初,ベッドサイドの場で使いやすいコンパクトなテキストとしてスタートしたが,今回カラー図譜などの画像情報が倍増され,疾患の分子生物学的アプローチを随所に取り入れたことから内容量が豊富となったため分厚くなっているが,これ1冊で実施診療に役立つ内科学書として診断から治療への展開を系統的にアプローチするのに十分な内容となっている。座右の書として利用すればするほど各疾患が系統的に理解できるのも本書の利点であろう。今回の改訂は,初版からの方針であるベッドサイドでの実践的なガイドブックという位置づけをしっかり受け継ぎ,ややもすれば複雑となりやすい専門的な内容が簡潔にかつ理論的に理解しやすいように編集されており,医学生,研修生のみならず内科を専門する医師にとっても必携の書として汎用されることと確信している。
B5・頁1886 定価(本体18,000円+税) 医学書院


腫瘍内科医が教えるがん診療の実際
がん診療レジデントマニュアル 国立がんセンター中央病院内科レジデント《書 評》田部井敏夫(埼玉県立がんセンター)
 がんに対する研究と治療は,ここ数年の間に目覚ましく進歩しており,現在では早期がんを含めると約50%のがんは治癒するようになっている。しかし,がんの罹患率は年々上昇しており,最近では3.5人に1人はがんで死亡している。がん治療の最前線では,機能温存を計りながら治癒率の向上をめざす外科治療や放射線治療,標準的治療法の確立と新規薬剤の導入により治癒や生存期間の延長をめざす内科治療を積極的に行なっている。また近い将来,遺伝子治療という手法も臨床に応用できると思われる。一方,治癒が期待できないがんに対しては,患者のQOLを低下させずに,人間らしさを保ったまま終末期を迎えることができるように緩和医療が実践されている。この日進月歩のがん医療の現場から内容豊富なマニュアルが編み出された。
がんに対する研究と治療は,ここ数年の間に目覚ましく進歩しており,現在では早期がんを含めると約50%のがんは治癒するようになっている。しかし,がんの罹患率は年々上昇しており,最近では3.5人に1人はがんで死亡している。がん治療の最前線では,機能温存を計りながら治癒率の向上をめざす外科治療や放射線治療,標準的治療法の確立と新規薬剤の導入により治癒や生存期間の延長をめざす内科治療を積極的に行なっている。また近い将来,遺伝子治療という手法も臨床に応用できると思われる。一方,治癒が期待できないがんに対しては,患者のQOLを低下させずに,人間らしさを保ったまま終末期を迎えることができるように緩和医療が実践されている。この日進月歩のがん医療の現場から内容豊富なマニュアルが編み出された。
がん診療の最前線で役立つ ハンドブック
現在,がん医療の分野においても専門化・細分化が顕著である。国立がんセンターのレジデントは,専門分野のがん治療のスペシャリストであると同時に,自分の専門以外のがんにも対応できる,がん医療のオールラウンドプレイヤーとなるように教育を受けている。この本は,国立がんセンター中央病院内科のチーフレジデントらが,日常の診療の場で行なっている治療内容をコンパクトにまとめたマニュアルである。患者の権利を尊重し,十分なインフォームド・コンセントのもとに治療を行なうことを原則としている。昨今,抗がん剤使用の是非についての問題提起もあるが,抗がん剤に精通した腫瘍内科医の著者らは,各種のがん(固形がん,悪性リンパ腫,白血病)を化学療法の有効性から分類して,抗がん剤の実際的な使い方を示している。治癒が期待できるがんに抗がん剤は絶対適応があり,効果があまり期待できないがんに対して一般臨床では,抗がん剤を単独使用すべきではない。これが実践できれば不必要な抗がん剤の使用はなくなるであろう。
標準的な治療法を詳細に記述
また各臓器のがんについて,疫学,症状,診断,組織分類,staging,予後因子,治療が簡潔に要領よくまとめてある。特に治療については標準的な治療法が詳細に述べてある。また,化学療法により引き起こされる有害事象とその対策も具体的に示してある。痛みに対する治療も明快である。「がんの終末期=痛み」という誤った考え方がまだ多いが,本書ではWHOがん疼痛治療法を詳しく説明している。痛みは我慢するものではなく,適切な鎮痛薬を適切な方法で用いれば80~90%は緩和できることを紹介している。本書は,腫瘍内科医を志すレジデントや研修医を主な対象としている。しかし,がんを専門としない病院で研修している医師やがん診療に従事している内科以外の医師にも役立つ本である。白衣のポケットに入ってしまう大きさなので,必要な時にいつでも取り出すことができる。内容も充実しており,常時手元に置きたい1冊である。
B6変・頁296 定価(本体3,800円+税) 医学書院


麻酔科学の発達にcatch upするのに最適
脳神経外科と麻酔ハンドブック D.J.ストーン,他/落合亮一 監訳《書 評》稲田英一(帝京大教授・麻酔科学)
ダイナミックで活力ある本に
本書はデビッドJ.ストーンらの“The Neuroanesthesia Handbook”(Mosby-Year Book)の翻訳である。著者の大部分は,脳神経外科や,脳神経外科麻酔を専門とするAssistant ProfessorやAssociate Professorである。臨床の中心となり最もアクティブに活動している人々の手になる本だけあり,非常に実際的なハンドブックになっている。著者らの自信は,“The Neuroanesthesia Handbook”という書名にも顕れている。“The”という言葉には,“これぞ脳神経外科麻酔のハンドブック決定版”という自負が込められているように思う。原書を真っ向から受けて立ったのが,落合亮一氏をはじめとする新進気鋭の先生方や,その道のエキスパートたちである。おかげで,本書は非常にダイナミックで,活力ある本に仕上がった。1989年に出版された本書の第1版である“Manual of Neuroanesthesia”と内容を比較してみると,随分と大きな変化がある。近年発展の著しい頭蓋顔面外科,頭蓋底外科,てんかん手術や定位手術に関する新しい章が盛り込まれている。内容的にも,わずか10年にも満たない間に,こんなにも医療や,麻酔学が発達したのかと驚かされる。麻酔薬関係の薬物の種類が豊富になり,理論的な背景が整ってきている。中枢神経系モニタリング分野は,10年ほど前までは脳波や頭蓋内圧くらいのモニタリングしかなく,ほとんど未発達といってもよかった。それが,誘発電位,演算処理した脳波,キセノンによる脳血流量測定,経頭蓋的ドプラー法(TCD)などの脳血流モニター,頸静脈酸素飽和度,近赤外線分光法(NIR)など脳代謝を経時的,非侵襲的に追跡できるモニターが発達してきた。本書を読むことにより,それらの発達のエッセンスを知ることができる。
術前に役立つ実際的なアプローチ
落合氏はその序文で原著のやや難解な英語について嘆いておられたが,訳文はこなれた読みやすいものになっている。おかげで,私も本書を手に入れてから,仕事の合間ながら2週間ほどで読破してしまった。通読しても,ためになる部分が多い。本書の持つ実際的なアプローチのおかげで,担当する脳神経外科手術前に読むと,非常に参考になった。ただし,薬物投与量など日本で使用されたり,薬事で認められているものと異なる場合があるので,注意が必要である。手術室だけでなく,MRI,血管造影のための麻酔など手術室以外の特殊な環境での麻酔にも詳しく触れられており,非常に役立つ。術後管理,集中治療のほか,患者の移送時の注意についても述べられている。脳神経外科医や,脳神経外科疾患を治療する集中治療医と共通の知識基盤を持つ配慮もいたるところになされている。中枢神経系の解剖については,豊富な図がついており,理解を大いに助けてくれる。脳血流量,脳代謝,頭蓋内圧などの基本的事項は,繰り返し述べられているが,その重要性からみても妥当に思える。
本書は,初めて脳神経外科の麻酔を担当するものは術前のquick consultとして,麻酔指導医試験受験者にとっては,脳神経外科麻酔に関わる知識のreviewに,さらに上級の医師にとっては,最近の脳神経外科麻酔の目覚ましい発達にcatch upするのに,最適の書であると考えられる。欧米では,脳神経外科の麻酔という専門領域が確立している。それがこの領域の高度化,専門化の動機となっている。平易に,高度な知識を書き下ろしてある本書は,読者を脳神経外科の麻酔という専門領域へと,やさしくいざなってくれるであろう。
A5変・頁432 定価(本体6,800円+税) 医学書院MYW


現代医学の分子的側面のすぐれた解説書
標準分子医化学 藤田道也 編集《書 評》山下 哲(群大教授・生化学)
序文によれば,本書の企画は20年前にさかのぼるという。その意味で本書はまさに編者のライフワークである。20年もかけて1冊の教科書を作るにはよほどの意志がないとできないと思われるが,編者の藤田教授は若いとき,クエン酸回路,尿酸サイクルの発見で有名なHans Krebsの研究室で勉強して,生化学の基礎を築いた巨人と直に接する機会を持ったことや,Albert Lehningerがあの有名な教科書『Biochemistry』を執筆していたときにポストドクだったことなどが影響しているのではないかと推察する。
本書は本文だけでも優に900頁を越え,図,表あわせて約1000枚の大著である。
全体の構成を知るために各章のタイトルを紹介しよう。第1章「生体の基本物質と基本代謝」,第2章「遺伝情報とその発現」,第3章「生体信号系の生化学」,第4章「生体の内部環境」,第5章「細胞小器官と細胞の動態」,第6章「臓器の生化学的特性と相関」,第7章「細胞増殖と発がんの生化学」,第8章「発生・分化,再生,老化の生化学」,第9章「遺伝子疾患」である。
分子基礎医学の各分野を網羅
以上を見ると,本書はいままでの生化学の教科書の範囲を超えて基礎医学のほとんどの領域を含んでいることがわかる。編者は「医学の分子化」という言葉で表現しているが,近年,生化学,分子生物学の方法と成果が大幅に取り入れられた結果,細胞生物学,内分泌学,免疫学,感染学,腫瘍学,発生学,神経科学が大きく発展した。この状況をふまえて本書は非常に大きな頁をこれらのためにさいている。おそらく,これほど広範囲に分子基礎医学の各分野を網羅して,しかも最新の知見を提示した教科書はほかに類を見ないであろう。その意味で,本書は生化学,分子生物学の教科書としてだけではなく,現代の医学,生物学の分子的側面のすぐれた解説書でもある。本書の題名が「分子医化学」といささか耳慣れないのはこのあたりに理由があるのだろう。学部学生にはもちろん,院生,研究者にとっても現代の生化学を全般的に勉強し直そうというとき,本書は非常に役立つと思う。本書でもう1つユニークなのは,各論に当たる部分が第一線の研究者による分担執筆になっているのに対して,本書全体の基本となる第1章「物質生化学と代謝学」と第2章「分子生物学」が編者の藤田教授の単独執筆であることである。例えば,Lehningerの教科書がそうであるように,古来名著といわれる教科書は1人,またはごく少数の著者によって一貫した視点で書かれているのが通例である。だがLehningerの時代には1人で書けたかもしれないが,今の生化学は進歩があまりに早く,しかも医学,生物学の広い分野をすべてアップツウデートに取り扱おうということになると,1人ではなかなか困難であろう。コアは単独執筆,現在発展中のところは第一線の専門家の分担で,という本書のスタイルは確かに生化学の現状にマッチしたものかもしれない。
初学者の理解を助ける工夫が 随所に
ところで本書のコアである第1章と第2章はページ数で全体の3分の1を占め,ここで生化学,分子生物学の基本原理が解説されている。本書を学部学生の教科書として使用するときにはおそらく1,2章を骨子にして,これに第3章以降から取捨選択したものをつけ加えるという形になるだろうが,代謝学は記載的な学問だからよほど工夫しないと,医学生は生化学というのは構造式の羅列で,特殊な科目だと思いこむ。したがって編者はできるだけ原理的,総論的であるように努めている。文章も読みやすい。読み進むと先生が1対1で諄々と語りかけてくれているような気になる。いちいち例はあげないが,学生が理解しにくいと思われるところには,図や説明にひと工夫あってなるほどと感心させられる。もう1つ随所にメモという囲みがあって(1,2章だけでも100以上ある),新しい概念,誤解しやすい点,注意すべき事柄,歴史,説明の補足,より高度なことなどが補足的に与えられている。2,3の例をあげるとランドル・サイクル,多点調節説,TCAサイクルの進化,メチル葉酸トラップ仮説等々,ここを読むだけでも結構楽しめる。また各節の終わりには参考文献があげられているが,それぞれには簡単な説明が付けられているので,さらに深く勉強したい人のためには便利であろう。1,2章の組み立てには著者の長年にわたる教育経験と深い学識を感じさせるものがある。学生は構造式と代謝経路の迷路に悩まされることなく生化学,分子生物学の基本を学ぶことができよう。またこの部分は確立されてはいるが今なお研究が続いており,本書では最新の知見にも考慮が払われているので,生化学,分子生物学をもう一度勉強し直そうという人にも好適と思われる。以上本書は初学者から研究者までそれぞれの目的に応じた使い方ができ,医学,生物系の学生,大学院生,研究者,医師と広い範囲の人々に教科書として推薦できる。価格も1万円と手頃である。
B5・頁1016 定価(本体10,000円+税) 医学書院


自然に論理的なCT読影法が身につく教科書
胸部CTの読み方 第3版 河野通雄著《書 評》池添潤平(愛媛大教授・放射線科学)
胸部疾患の画像診断は,種々の検査法や機器の出現にもかかわらず胸部単純X線写真とCTでなされることが多い。CTの出現で腫瘤性病変の診断が飛躍的に進歩した。また,肺野の病変では高分解能CTが診断に大きく貢献した。
本書は初学者を対象に胸部疾患の画像診断をCT像を中心にわかりやすく解説したものである。画像としては単純X線写真とCT像をあげ,症例によっては断層写真やMRI,血管撮影,摘出標本を追加していて,これらをきわめて簡潔にまとめ,手順に沿って読み進めば診断のポイントや鑑別診断が理解できるようになっている。著者の河野通雄教授は胸部画像診断の第一人者のお1人であるが,神戸大学のみならずその関連病院で経験された豊富な症例の中からとくに教育的な症例を厳選して用いられている。
全症例に胸部単純X線写真を提示
まず最初に,CTの原理,用語,撮像法,造影CTなどについて簡単に解説していて,初めて胸部CTを学ぼうとする者にとってはありがたい。正常CT解剖の解説に力を入れているのも本書の特徴の1つで,剖検肺の断面を使って詳しく解説している。疾患では,特に河野先生の専門領域である腫瘍性病変の部分は特に詳しく解説されている。すなわち,肺癌,縦隔腫瘍,治療経過観察,BAG-CT,などが詳しく記述されている。スパイラルCTの項目では,最新のCT気管支鏡の画像が示されているのもうれしい。全症例に,CT画像のみならず,よい画質の胸部単純X線写真が示されている。診療現場では最初に単純X線写真が撮影され,何らかの異常が発見されてCT検査に進むことが多い。したがって全例に単純写真が示されていることは,初学者や実地臨床医家にとっては非常にありがたい。胸部画像診断が単純X線写真にはじまるという認識と,CT画像から得られる情報を積極的に単純写真に還元しようとする画像診断に対する著者の姿勢,考え方が十分に伝わってくる。初学者や胸部領域を専門としない臨床医の先生方にも非常に理解しやすくまとめられていて,自然に論理的な読影法が身につく教科書である。ぜひ一読をおすすめしたい。
B5・頁302 定価(本体10,000円+税) 医学書院
