〔鼎談〕 メカニカルストレスと生体
-新しい理学診療の可能性をめぐって
 | ||
| 高垣裕子
神奈川歯科大 口腔生化学 |
黒川高秀
第9回日本理学診療学会長, 東大教授・整形外科 |
安藤譲二
東大助教授 脈管病態生理学 |


メカニカルストレスは生体にどう影響するのか
――きたる7月5-6日に,第9回日本理学診療学会(会長=黒川高秀氏)が,東京の国際フォーラムで開催されます。そのメインテーマとなるのが「メカニカルストレスと生体」ですが,この「メカニカルストレス」という言葉は,医学界ではあまりなじみのないものなのではないでしょうか。そこで本日は,メカニカルストレスが生体にどういう影響を及ぼすのかを主に,メカニカルストレスの医学上での可能性を含めお話しいただければと思います。まず,定義を含めまして,どういうものなのかをご紹介ください。19世紀から観察されていた現象
黒川 メカニカルストレスに生体の構造や機能を決める作用があることが,細胞や分子のレベルで知られるようになったのは割に新しいことです。しかし,生体に加わる力が生体の構造に作用を及ぼしているのではないかということは,古くからいろいろな分野の人が考えていました。そのことを最も明解に示したのは,Wolffというベルリンの整形外科医です。彼は1892年に,骨折が治った後の骨の形が,年を経るに従い変わっていく現象や,大腿骨頸部の骨梁の走行が特別であることを観察し,骨に加わる力の働き方と生体の構造に関係があることを示しました。この1892年という年はまだX線のない時ですから,骨折の後の骨の形がどうなっているかをみるのは非常に難しかったはずなんですね。Wolffの本は,標本写真とスケッチが主になっています。彼はストレス,つまり荷重のかかっている部分では骨が増えるけれど,力の加わっていない部分の骨は徐々に吸収されて骨が少なくなるという法則を示しました。「Wolffの法則」と呼ばれるものです。
その後,脚延長術などの臨床経験から,メカニカルストレスに応答しているのは骨だけではなく,血管や神経などを含めた多くの組織,器官が力学的な環境に反応しながら,形態と機能を維持しているのではないかと次第に考えられるようになってきました。
高垣 骨の細胞の分野からみますと,骨形成は力学刺激のあることが前提になっています。最近,研究が進むに従い細胞レベルでの結果も出てきました。例えばホルモンの影響ですが,これまではホルモン単独で働くとみられていたものが,もしかすると日常的には力学刺激が加わった上で協同的に働くことが骨形成の前提となっていると,考えられるようになりました。
私は,骨の細胞全体の約9割を占めるオステオサイト(骨細胞)を研究しています。この細胞は骨芽細胞の一部から分化するのですが,神経細胞のようによく発達した樹状突起を持っていて,骨内に緊密なネットワークを張りめぐらせています。さらにその突起は骨細管という細胞外液で満たされた管内にありますので,機械的外力の負荷により直接変形するばかりでなく,液流により生じるシアストレス(shear stress:剪断応力)にも応答して,骨全体にその情報を伝達するように特殊化した細胞といってもおそらく過言ではありません。骨形成ばかりでなく,運動をできなくした不動化の動物実験でもこの細胞が迅速に反応してコラゲナーゼを産生し,骨を減らす方向に働くことが最近示されました。
安藤 私は血管を対象に,メカニカルストレスの作用を研究していますが,血管の機能も機械的,力学的なストレスによって調節を受けているということがここ10年ほどの研究でわかってきました。血管内皮細胞を例にとりますと,細胞レベルでストレスが加わると,そこから出てくる生理活性物質の量が増えたり,あるいは逆にその産生が抑制されることがわかりました。現在もいろいろな細胞機能について詳しく調べられています。
実は血管に関しても,Wolffと同じ時期の19世紀後半に,Thomaという人が鶏胚,つまり鶏のエンブリオの観察をし,血液が多く流れているところの血管は非常に成長が早く血管がよく分岐をしている,ところが血流の遅い血管は,最終的には血管として存在できなくなり消失してしまうことを,これもスケッチですが著しました。現在,私が進めている研究のテーマというのは,この頃からもう始まっていたわけですね。ただ,それが細胞レベルで研究されるようになったのはここ10年のことです。
環境因子によって変わる性質
高垣 そういう意味で申しますと,私どもの研究分野でも,細胞レベルで力学環境が変わるといろいろな生理活性物質が出てくる,あるいは抑制されるというように注目されだしたのは,やはりここ10年ぐらいのことです。ただ血管,心臓関係の研究は進み方が早かったものですから,骨関連の研究は,そちらの仕事を手本にして追いかけているという状況です。骨になる基質を作る骨芽細胞は骨の表面にありますし,培養もたやすく研究が割りに早く進みましたが,実際にメカニカルストレスに応答している主な細胞は骨中のオステオサイトで,単離もしにくく研究が遅れていました。もちろんそれは骨芽細胞が分化してできるので,もともとは時間的に変化していくわけです。
オステオサイトの重要性については,形態学研究者(日本では新潟大の小澤先生のグループ)も生体力学の研究者も,両者がほぼ同じ頃に思いついています。そしてこの数年では培養が可能になったことも手伝い,細胞分裂をしなくなるオステオサイトが情報の処理や伝達にもっぱら従事しているとみられるようになりました。明海大の久米川先生のグループからは,Ca受容体の存在,骨吸収調節因子の産生も報告されています。中心となるのはやはりメカニカルな環境因子に対する応答だと思われます。
安藤 血管の細胞の場合は15年ほど前から細胞培養法がうまくいくようになり,体の外で培養細胞に特別に設計した装置でメカニカルストレスを加えるという実験が盛んに行なわれるようになってきました。さらに最近では,分子生物学など様々な面で細胞を研究するツールが増えましたので,研究が盛んになってきたのだと思います。
黒川 少し前のことですが,骨の超微細構造が示された時には,臨床の私たちも強い印象を受けました。骨細胞は,非常にたくさんの突起を持っていて,その突起の長さを合計すると長大なものになるわけですが,突起の先端同士がいわゆるギャップジャンクションを形成していて,それは神経細胞同士が関係を持っているのと似ています。骨細胞は突起の数が非常に多く,隣の細胞との距離は比較的短い。そういう構造が骨のメカニカルストレスに対する態度を支えているのではないかと考えられます。
高垣先生や安藤先生の言われるように,メカニカルストレスに対する生体の反応が,分子や細胞のレベルで研究されれば,メカニカルストレスを利用した新しい治療法や疾患予防も可能になるでしょう。
安藤 血管の場合,血管細胞にかかるメカニカルストレスというのは,1つには血液の流れが血管内面を覆っている細胞をこする力があり,これをずり応力,またはシアストレスと呼んでいます。それから血管には血圧があり,その血圧によって血管壁が伸展し,そのために細胞が引っ張られるという張力があります。大まかにこの2種類がありますが,これは人が胎児の段階からもうすでに常に存在するストレスです。
高垣 オステオサイトに関しましても,シアストレスと直接的な変形(伸展)とで起こる情報伝達を区別する試みが現在進行中です。
安藤 メカニカルストレスが,細胞の性質を決める環境因子として重要であるという点に関連して話をしますと,圧が高く血流の速い動脈と,圧が低く血流の遅い静脈があるわけですが,実は両者の細胞の性質は非常に違います。逆に言いますと,静脈の内皮細胞と動脈の内皮細胞が遺伝的に機能が分かれているというよりも,後天的にメカニカルストレスの環境が違うことによって,機能が分化していることを示すエビデンスがかなりあるのです。例えば冠動脈バイパス手術などで,静脈を圧が高く流速の速い動脈系に植えますと,それは静脈系の内皮の性質を失い,動脈系の内皮に変わってしまいます。そういった現象は,環境因子としてのメカニカルストレスがこの細胞の性質,あるいは細胞の分化を規定していく重要なファクターであることを示す例だと思います。
ストレスのかけかたで形態が変わる
――性質が変わるということですが,その具体例をお話しいただけますか。高垣 私は歯科大学におりますので,よく例に出されるのは,歯列矯正の場合です。矯正装置を着けて適正な力をかけると圧迫側で骨吸収が起こり,牽引側で骨形成が起こるために移動が可能なわけです。最低50g/cm2の矯正力をかけると歯が移動を始めると言われますが,ちょっと力学環境が変わるだけで短期間(3週間くらい)で形態が変わってしまいます。
また,例えば咬合に関しては,歯がなくなったり,噛むことができなくなると,歯槽骨がすっかり吸収されてしまい,顎として機能しなくなってしまうこともあります。これは実験的にも観察が可能ですし,軟食を好む最近の子どもたちに顎の発達が悪いことも問題になっていますから,かなり日常的にも観察されているわけです。
――そのような現象は,血管の分野でも起こり得るのでしょうか。
安藤 血管でも起こります。血流が変化しますと,血管の形態や構造が変わってきます。例えば,血流が増えますと血管の反応としては径が太くなり,血流が減ると逆に小さくなるという反応が起こります。
その他にも,血管は非常に多くの重要な働きをしていますが,この機能にも血流は影響を及ぼします。例えば,血管壁に血栓が起きると生体にとって非常に困るわけですが,この血流の刺激というのは,血管内皮が様々な生理活性物質を産生する働きを促進し,血栓をできないようにする作用があります。ですから,普通の状態で血流が正常に流れているということは,生体の機能の恒常性(ホメオスターシス)を保つ上で非常に重要な働きをしているという例がいくつもあります。
黒川 筋肉や靱帯がそうですね。運動をしないでいると,つまりストレスのない環境に筋肉を置くとたちまち萎縮してしまいます。関節が動かないようにギプスをしますと,靱帯にストレスや緊張力が加わらないために,靱帯が短縮してしまい,いわゆる拘縮という現象が起こります。
関節の軟骨も,実は軟骨同士が接触してこすられていないと,軟骨が表面からはげてやせていきます。かといって,じっと接したまま動かさないでいると,これもおかしくなります。生理的なシアストレスとコンプレッションストレスの両方が加わっているということが,関節の軟骨の構造を維持するために大事らしいということがわかっています。
そういう意味でこのメカニカルストレスは,私たちの健康保持と言いますか,体の構造を維持する上に非常に重要な作用を持っているのだと言えます。ただ,それに対する理解,認識がとても遅れていたと思いますね。特に物質的な背景を明らかにしていくという仕事は,実は始まったばかりと言ってもいいと思います。
メカニカルストレスは生体にどう生かされるのか
――メカニカルストレスが医学,医療の中で,どのように生かされるのかについてお話しいただきたいと思います。新しい組織を作ることも可能に
 黒川 メカニカルストレスが医学(医療)に利用されたのは非常に古く,現在でもマッサージや牽引,体を曲げたりあるいはツボを押すことや竹踏みなどが行なわれています。だだ,経験主義的になってしまっていて,メカニカルストレスによって生体に何が生じているのか,またどういうメカニズムで効果を発揮するのかがわからないままに行なわれてきたのが,つい最近までの状況だったように思います。
黒川 メカニカルストレスが医学(医療)に利用されたのは非常に古く,現在でもマッサージや牽引,体を曲げたりあるいはツボを押すことや竹踏みなどが行なわれています。だだ,経験主義的になってしまっていて,メカニカルストレスによって生体に何が生じているのか,またどういうメカニズムで効果を発揮するのかがわからないままに行なわれてきたのが,つい最近までの状況だったように思います。
ところが,メカニカルストレスを利用した医療というものが急に発展してきました。例えば,まったく正常な構造と機能と配置を持った体そのものを,メカニカルストレスをコントロールすることによって新たに作るということが可能になりました。上下肢の短い人がいる場合,20~30cmも伸ばす。つまり,身体を作ることができるようになったのです。それは骨の一部を切り,ある速さで引っ張る,つまりメカニカルストレスを加え続けるというだけのことなのですが,その刺激に対してそこにあるすべての組織が整然と応答してくるのですね。皮膚も,筋肉も,靱帯も,それから驚くべきことは末梢神経も,血管も,骨も,みんな一斉に応答して,矛盾のない配置で組織を新しく作ります。しかも今まであった組織との継ぎ目がありません。例えば,末梢神経が30cmぐらい伸びたとしますと,どこまでが元の組織でどこからが新しくできた組織なのかという継ぎ目がないのです。加えた刺激は,あくまで末梢だけで脊髄のレベルはいじってないにもかかわらず,末梢神経の軸索が伸びてくるという,驚くべきことが生じます。
脚延長術の場合は,さまざまな組織を一斉に形成させるのですが,皮膚だけですとか,骨だけというように,ある組織だけを増やしたい,あるいは減らしたいという問題もあります。それに対する治療法として,メカニカルストレスを利用できる可能性がかなりあると思います。
メカニカルストレスという方法は,生体に潜在する生理的な能力を引き出すものですが,作用する部位を必要に応じて選択できる,つまり空間選択性がよい,それから時間選択性も非常によくて,例えば持続も周期も時定数も,ミリ,秒単位から月単位まで広く選ぶことができます。そして,生体の反応をみながら,副作用があると思ったらすぐやめることもできます。このように薬物や手術にはない長所がありますから,疾病治療への利用価値が高くなる可能性が大いにあると思います。
――それに対して逆のストレスがかかるということはないのでしょうか。
高垣 それに当たるかどうかよくわかりませんが,歯の矯正の場合ですと,矯正装置を取ってしまった後に100%固定されるというわけではなく,場合によってはすぐにまた元に戻ってしまうこともあります。先ほど黒川先生がお話しになりました脚延長の場合ですと,それはもともと延長後は持続的に適正な刺激を受けるので,歩いたり運動する組織ですから,一度伸びたものはそのまま縮まないけれども,こちらの場合は咬筋も含めた新しい咬合環境がよくないと,安定な(元の)状態に変わってしまうということかもしれません。
安藤 メカニカルストレスを医学の中でどう生かすのかというのは,確かに重要なことだと思います。と言いますのは,私は医用生体工学の分野で仕事をしていますが,将来的に伸びる研究の分野として,ティシュエンジニアリングとセルラエンジニアリングという領域に今注目しています。
血管のことで言いますと,血管自体はいろいろな細胞からでき上がっていますが,もともとは1つの細胞に起源があるという考え方があります。それは幹細胞というものですが,実はそこから血管内皮細胞ができて,それが平滑筋細胞にも変わります。さらに血管ができた後,心臓がそこからできてきます。いわゆる血管系がある1つの細胞に由来するわけですが,それを血管,心臓というものに分化させていく重要な因子としてメカニカルストレスがあるのではないかと私は考えています。しかし,まだメカニカルストレスの作用のメカニズムがよくわかっていませんので,クリアカットな話にはなりませんけれど,将来的には生体の外に取り出した幹細胞を培養し,増殖因子などと一緒に流力や圧力などのメカニカルストレスを適当に作用させることで,血管細胞や心筋細胞への分任を誘導し,ひいては血管や心筋を人工的に作ることができるのではないかという夢をみています。これは,まさに最先端の研究と言えると思います。
血管新生のメカニズム
 高垣 血管新生に対する直接的なメカニカルストレスの影響というのはどの程度わかっているのでしょうか。先ほど触れました,歯槽骨の吸収や形成の場合でも,神奈川歯大の解剖の高橋先生のグループが,歯と骨をつなぐ歯根膜(periodontal ligament)の微小循環系を観察しているのですが,すごい速度でできたり,なくなったりしています。骨組織の再構築に先だって血管系が変化するのですね。
高垣 血管新生に対する直接的なメカニカルストレスの影響というのはどの程度わかっているのでしょうか。先ほど触れました,歯槽骨の吸収や形成の場合でも,神奈川歯大の解剖の高橋先生のグループが,歯と骨をつなぐ歯根膜(periodontal ligament)の微小循環系を観察しているのですが,すごい速度でできたり,なくなったりしています。骨組織の再構築に先だって血管系が変化するのですね。
安藤 まだはっきりとその役割がわかっているわけではありませんが,メカニカルストレスが血管新生に大きな影響力を持っていることは確かです。この問題を検討する時によく使われる手法として,血流を増やして血管新生がどうなるかをみる実験があります。1つは,実験動物に動静脈シャントを作る方法で,シャントを作ると血流量が増えるのですが,そこから枝分かれしていく血管が豊富に出てきます。それは血流が増えていない対象と比較して明らかに差が出るんですね。
それからもう1つ,プラゾシンという血管拡張薬で血流を増やす方法がありまして,それを長期投与した動物でいろいろな場所の毛細血管の数を調べますと,骨格筋や心筋でかなり増えてきます。ですから,直接的な証拠とはいえないのですが,生体の中で血流が増えて,シアストレスが血管壁に強くかかると,どうもその血管から新しい分岐が形成されたり毛細血管の数が増える,すなわち血管新生が非常に促進されるようです。
高垣 骨の新生は,まず血管の新生を必要とします。実際PGE2(プロスタグランジンE2)による骨新生では,骨芽細胞の増殖が起こると同時にVEGF(血管内皮細胞成長因子)の発現が骨芽細胞で上昇することも報告されています。ご存じの通り,PGE2は骨のメカニカルな応答において最も古くから研究されてきた局所因子ですので,そういう組織間の協同作用も興味のあるところですね。
病気の進展を防ぐことも可能に
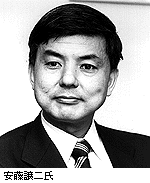 安藤 最近の研究で,シアストレスが血管細胞に作用した時に,多くの遺伝子の発現が大きく変化することがわかっています。そのメカニズムとして,遺伝子のある部分にどうもシアストレスに反応する応答配列,あるいはシスエレメントがあるということがだんだんはっきりしてきました。ということは,本来シアストレスに反応しない遺伝子にその応答配列を導入しますと,それが突然メカニカルストレスに反応する遺伝子に変わるということです。
安藤 最近の研究で,シアストレスが血管細胞に作用した時に,多くの遺伝子の発現が大きく変化することがわかっています。そのメカニズムとして,遺伝子のある部分にどうもシアストレスに反応する応答配列,あるいはシスエレメントがあるということがだんだんはっきりしてきました。ということは,本来シアストレスに反応しない遺伝子にその応答配列を導入しますと,それが突然メカニカルストレスに反応する遺伝子に変わるということです。
そのことから,動脈硬化の予防や治療への応用が考えられます。例えば抗血栓作用のある生理活性物質をコードしている遺伝子に,本来シアストレスに反応する応答配列がない場合にそれを入れ,生体の血管内皮に導入します。常に血流が流れシアストレスがかかっているわけですから,遺伝子の発現が高まり,そこの血管内皮の抗血栓活性とが常に高く維持されるわけです。そうすると,動脈硬化の後半で起こる血栓や,血管を狭窄してくるような疾患の進展をそこで止めることができようになります。
これは遺伝子治療の1つの可能性だと思います。そのように,メカニカルストレスの作用のメカニズムを明らかにしていくことで,今のところは医学の範疇ではありますが,応用範囲というのはそれ以外にも広がっていく可能性があると考えられます。 高垣 今,安藤先生がおっしゃったシアストレスの応答配列は,cfos, NO合成酵素,TGF-βなど,骨形成においても鍵となる蛋白質の遺伝子にあることがすでに判明しています。私どもの扱っている細胞は,力学刺激に応答して骨のマトリックスを作る骨形成,石灰化のプロセスも促進させますから,遺伝子の導入でもいいですし,あるいはすでに発現されているものを活性化するメカニズムもわかっていますので,それらを利用することによって,運動ができない状態でも,もしかすると同じ骨形成が保たれる可能性は十分あります。
運動とメカニカルストレスとの関連
黒川 メカニカルストレスというものは非常に多様なモードが可能で,例えば作用時間を脚延長のように何日,何年という単位で続けることもできますし,あるいは1000分の1秒といったようなストレスのかけ方もできます。また,その立ち上がりの時定数と言いますか,時間経過もさまざまに変えられますし,周期も方向も変えられるというように,非常に多様なモードがあり得る刺激方法だと思います。天然自然には絶対あり得ないモードを適用することによって,生体に潜在している,つまり自然には絶対に見えてこない生命現象を顕在化したのが,脚延長術です。脚延長は動物実験から始まったのではなく,臨床経験から始まったのですが,分子細胞レベルの応答と,刺激モードとの関係がわかれば,メカニカルストレスの利用法はさらに広がるでしょう。
高垣 例えば骨密度を上げたければ,インパクトが大きい柔道や体操をすればよい,背が高くなりたければ他のスポーツのほうがよいというように,現在までに集積された情報がありますし,また骨粗鬆症のリスクファクターと言われるビタミンD受容体の遺伝子多型の型を持つ人でも,運動の効果のほうが上回るという研究もありますね。ストレスの種類と体のレスポンスということがだんだんわかってくると,体の改造とはいかないまでも,いわゆるQOLを改善するために日常的にその情報が使われていくようになるだろうと思います。
安藤 血管に関してはシアストレスも,難しくとらえられてしまうと,関係のないものとして感じられてしまいがちです。しかし,例えば人が運動すると血流速度が速くなります。ということは,エクササイズは血管内皮によりシアストレスをかける作業なわけですから,血管内皮からは生体にとっては血管を拡張する物質とか,抗血栓活性の高い蛋白も出ますし,ある面でエクササイズのよい面というのは実はシアストレスから派生している部分もあると思います。そういう視点を持っていると,メカニカルストレスと生体という問題がより身近に感じてくるのではないかなと思います。
黒川 今まで運動は体によいというように,漠然と言われていたと思います。しかしなぜそれがよいか,なぜ必要なのかということが,安藤先生のお話で裏づけられると思います。
安藤先生,運動するとスカッとするじゃありませんか,気持ちいいですよね。あれはやはり関係ありますか。血管の内皮細胞から何か出ているのですか。
安藤 出ているのではないかと思います(笑)。
基礎から臨床へ,臨床から基礎へ
――基礎研究が臨床に応用される。逆に臨床例から基礎にという循環が医学研究にとっては重要になると思いますが,メカニカルストレスに関する相互研究はされているのでしょうか。臨床に重要な基礎医学研究
黒川 研究者同士の交流はむろんあります。しかし,メカニカルストレスを日常の臨床に応用し診療しているわれわれや,スポーツトレーニングに応用している方々には,分子細胞レベルの最先端の研究情報は必ずしもよく伝わっていません。基礎研究者と臨床家とが一堂に会して情報交換をすれば,お互いに啓発され,新しい見方や方法を思いつく契機はたくさんあると思います。安藤 そういう面をカバーする集まりとしてはバイオメカニクス学会があります。来年(1998年)の夏には,札幌市で国際バイオメカニクス学会が開かれます。しかしながら,メカニカルストレスをテーマにした臨床・基礎研究者の交流の場というのはまだ非常に少ないのが現実だと思います。
高垣 日米を比較すると,研究部門の組織のされ方に少し違いがあります。アメリカでは,必要が生じた時に研究組織を作り,基礎の研究者も臨床部門に大勢所属して同じ問題を様々な角度から研究するということが行なわれています。
黒川 内科系には,ご自身が基礎研究者であったり,臨床から少し遠ざかって基礎研究をされている方も多くいますが,外科系の場合は,診療が何といっても中心にならざるを得ないわけで,そこで見出される診療上の問題を解決するには基礎医学の方々にわれわれの見ている現象をお伝えしなくてはなりません。研究の技法をもってすれば,さまざまな有用な概念,着想をしてくださる研究者が臨床の問題を受けとめて,問題解決能力を発揮していただかないと進まないと思います。
余談ですが,日本にはすぐれた研究者もおられますし,お金もあって,東京湾にトンネルを掘る力がありますしね(笑)。国の財の量と質から言えば,医学を推進する力は十分あると思いますので,それを生かすメカニズムがほしいですね。非常に優秀な人々同士が協力し合うという体制がほしい。それは皆さん痛感していらっしゃるのではないでしょうか。
コメディカルを含めて話し合える学会に
――そういう意味では,今回の学会が基礎と臨床,コメディカルから工学関係者までが一堂に会して話し合える場となるかと思いますが,今学会のめざすところをお話しいただけますでしょうか。黒川 理学診療とは何かといいますと,物理的な手法によって診断と治療をしていく医学という意味なのですね。物理的な方法は,体の中に異物を残しません。物質,例えば薬を体外から与えたり,手のように生体の構造を直接に変えるものではなく,生体に備わっている生理的な能力を誘導するものと言えます。生体に負担の少ない医療であり,生体にもともと備わっている生命現象をよりうまく活用する医学であるという意味で,将来性が大きいと考えられています。にもかかわらず,現時点では非常に経験主義的な段階にあります。これからは,基礎医学の先生方の研究成果を早く学んで,新しい治療法を構成していくべき時期だろうと思います。
今回の学会では,物理的な方法の中で一番基本になると考えられるメカニカルストレスを取り上げ,それに対して生体がどのように反応をするのか,生体にとってメカニカルストレスがどういう意味を持っているのかというところまで掘り下げていただきたいと思います。
また,工学関係者をはじめ理学療法士や看護婦・士の方々にも参加を呼びかけています。ぜひ工学関係者に参加をいただき,生物学的にどういうストレスがどの部分に必要なのかという現状を知り,医学のニーズに応える無害なストレスの与え方ができる器械,装置をつくっていただきたいと思っています。また逆に,こういうストレスの加え方なら技術的に可能だということを示唆していただけば,私たちも活用を考えていけるかもしれません。
加えて,メカニカルストレスを生体に適用していく専門技術者が必要です。それは理学療法士や看護婦さんであり,コメディカルの方々です。その方たちから見て,どういうメカニカルストレスの適用の仕方がより患者さんに負担が少なくすみ,より合理的かという実地に役立つアドバイスも必要ですし,どういう原理に基づいて治療が行なわれているかも知っておいていただきたいと思います。
将来的には,コメディカルの方々からも,メカニカルストレスと生体の医学的応用に関する問題,課題などを提案されることを期待しています。
――メカニカルストレスはまだ研究段階ながら,QOLを含めた今後の可能性までお話いただけたと思います。7月に開かれます学会でどのようなことが話し合われるのかもとても興味のあるところです。本日はありがとうございました。
(おわり)
