日本小児科学会100周年記念座談会
小児科学・小児医療のこれから
社会に求められる小児科医の役割
 | ||
| 柳澤正義 東京大学教授 小児科学 | 前川喜平 東京慈恵会医科大学教授 小児科学 |
白木和夫 鳥取大学教授 小児科学 |
きたる4月18-20日,第100回の日本小児科学会総会・学術集会が,前川喜平氏を会頭に東京で開催される。本号では学会100周年を機に,前川氏の他,白木和夫氏(第101回総会会頭),柳澤正義氏(第102回総会会頭)の出席を得て,今後の小児科学,小児医療の展望,また小児科医に期待される役割について語り合っていただいた。


少子化の中で子どもを育てる
 白木(司会) いま世の中では,高齢化と少子化に話題が集中しています。また日本小児科学会ができてからの100年間には,小児科学の非常に大きな進歩がありました。したがって,やはり小児科医も変わっていく必要があります。本日はこれらを踏まえてお話をしていきたいと思います。
白木(司会) いま世の中では,高齢化と少子化に話題が集中しています。また日本小児科学会ができてからの100年間には,小児科学の非常に大きな進歩がありました。したがって,やはり小児科医も変わっていく必要があります。本日はこれらを踏まえてお話をしていきたいと思います。
小児人口と老人人口の逆転近づく
前川 全人口に対する小児人口(0~14歳)の割合は,昭和の初め頃までは30~35%くらいだったようですが,1990年には18.2%になり,同じ年の65歳以上の老人人口は12.1%です。1994年には小児人口が16.3%に減っていますが,老人人口は14.1%に増加しています。1997年には老人人口も小児人口も15.6%となり,ここを境に全人口に占める老人人口のほうが増え,小児人口が減ると考えられています。それに比例して日本人の寿命も延びています。例えば,1926(大正15)~1930(昭和5)年に生まれた女性が還暦を迎える率は45.8%でしたが,現在はこの率が非常に上がって,60歳まで生きる率が93.2%なんです。そして70歳まで生きる率は85.1%と,古稀,つまり「古来稀なり」という言葉にあてはまらないような現状です。
白木 少子化に関しても,すでに厚生省はエンゼルプランなどの施策を考えていますね。私たちのとるべき方向としては,1つにはいかにして少子化をくい止めるかを考える,そしてもう1つは,少子化を社会の当然の動きとして受けとめて,その上でどうすべきかを考える,この2つの道があると思うのです。
くい止めるか受け入れるか
柳澤 実際に子どもの数が少なくなっていることは,私たちにとって気がかりです。また老人人口が増えていることが大きな問題とされています。しかし,それを前向きに捉える面もあってよいのではないかと思っています。この現象をくい止めるのは非常に難しいですから,いまの状況の中でどうするかを考えるべきです。合計特殊出生率は1.50人くらいですから(図参照),もうしばらくたつと日本の人口は減っていくといわれています。しかしそういう状況は本当に日本にとってよくないのか。日本の狭い国土に1億2000万人いる人口が減るのはよくない状況なのかどうかということも考えなければいけないと思います。
むしろ小児科医にとっては,これからますます減っていくかもしれない子どもをどう大事に育てていくかを考えることが,重要ではないかと思っています。
白木 そうですね。当然,国も私たちも,子どもを育てやすい環境を作るというような努力によって,多少でも少子化傾向を減らす努力は必要だと思います。しかし,やはりすぐには少子化が止まるとは思えない状態ですから,その現実を踏まえて何をすべきかを考えることが必要でしょうね。
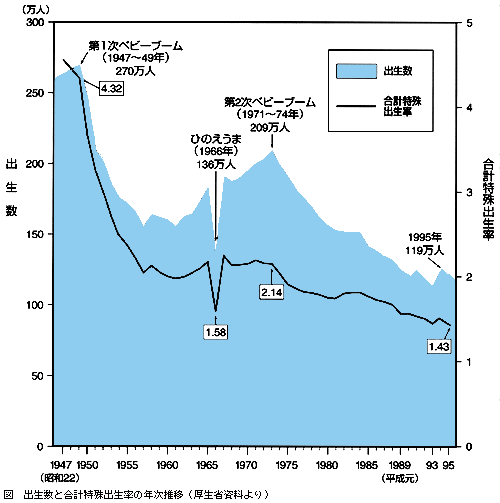
疾病を抱えながら大人になる子どもたち
白木 今後の日本の小児医療を考えるにあたって過去100年の進歩を見据えると,この100年間に本当にずいぶん変化しています。近年は,どちらかというと,先天性の障害をいかに治して延命するかということ,またいかに健康な子どもを育てていくかという方向に傾いてきていますね。そのベースにあるのはやはり小児科学の進歩であって,例えば,昔だったら成人まで育たずに死んでしまったような重い先天性心疾患でも,いまは手術によってほとんど正常に近い状況にもっていける場合が多くなりました。
前川 おっしゃる通りです。戦前のことはよくわかりませんが,教科書をみると,私たちが入局したころは,消化不良,栄養障害,感染症などで,子どもが数人いれば1人は亡くなる状態でした。現在はそういう疾患が影をひそめて,ほとんど慢性難治性の疾患になっています。
疾病や障害を踏まえた社会参加
 前川 これからの小児科のあり方を大きく分けると,いま私たちが扱っている慢性難治性の疾患をいかにケアするかという問題と,子どもをいかに育てるかという問題になると思います。その要点には,高齢社会を支える経済的基盤である将来の生産人口が子どもたちだということがあります。
前川 これからの小児科のあり方を大きく分けると,いま私たちが扱っている慢性難治性の疾患をいかにケアするかという問題と,子どもをいかに育てるかという問題になると思います。その要点には,高齢社会を支える経済的基盤である将来の生産人口が子どもたちだということがあります。
そこで,今度は私たちの立場からすると,「健康」の定義を変えてほしいのです。いわゆる「心身ともに健康で,病気でない子ども」が健康だというと,私が診ているような発達障害児や心身障害児は永久に健康ではないことになってしまいます。そうではなく,ある程度障害があっても他が健康で,社会的に生活できるのであれば,それも健康だというようにみてほしい。そして社会参加をして,税金も払う立場になるという発想が,これからは必要だと思います。
ですから,発達障害や神経疾患など,病気は病気ですが,その治療とともに,いかに子どもたちが社会生活を送るか,あるいは社会参加をするかが,これからの課題だと私は思っています。
低出生体重児と障害
白木 先生の専門の神経領域でいえば,脳性麻痺などは減っているようですか。前川 脳性麻痺の数は横這いか少し増えています。発生率も。スウェーデンの統計でもそうですし,日本の統計でもそうです。その中で増加しているのが低出生体重児(2500g未満)です。
白木 低出生体重児は,昔はあまり助かりませんでしたが,近年は多くが助かるようになったのでやむをえないでしょうね。低出生体重児の場合,国立小児病院ができた1965年頃は,それこそ1000gで生まれた子どもにはまず手が出せませんでした。ところが,今は私どもの教室のNICUでも,500gの子どもを助けています。
前川 低出生体重児が増えてもインタクトサバイバル(障害なき生存)ならよいのですが,その中で障害児の占める率が少しずつ増えています。これは日本だけでなく,先進7か国の統計など世界的な動向です。
白木 障害を持った人たちも,社会の中でともに生活し,ある意味で社会を支えていくようにもっていかなくてはいけないということになるわけですね。
新生児医療の重要性
前川 極低出生体重児(1500g未満)や超低出生体重児(1000g未満)をフォローしていると,普通の子どもと思われているうちの半分くらいに,確かに学習障害などなんらかの障害がみつかります。ところが,その子どもたちの親を指導して,他の子どもと一緒に育てていると,ほとんど学校などで問題が起きることはありません。医学というのは,昔は障害を治そう治そうと思っていました。ところがそうではなく,障害を認めた上で他のよい部分を親が励まして育てていくと,意外と社会適応できるのです。字がうまく書けない人はワープロを使い,計算ができない人は計算機を使い,またある部分はみんなが補う。そうすると社会適応が可能なのです。
インタクトサバイバル,インタクトとは何かということを,もう一度考え直さなければいけない時期にきているのではないでしょうか。子どもというのは非常に適応力があるものです。
柳澤 そういう意味で,新生児医療はこれからの小児科学の中でもますます重要な部分になっていかなくてはいけませんね。
白木 問題はマンパワーが現段階では足りないという点ですね。
小児医療の対象範囲
白木 昔は,小児医療の対象になる子どもがその疾病をかかえながら大人になることはあまりありませんでした。したがって小児医療の範囲を15歳までとすることも可能でした。しかし最近は成人する場合が増えています。私の研究領域でも,例えば先天性胆道閉鎖症などは,研究を始めたころは100人診て6人しか生きませんでした。いまは,早い時期に手術をすれば,80%はかなりよい状態で生存できます。もちろんそのあともケアが必要なわけで,ある意味で一生ハンディキャップを持つことになります。だからこそ適切なケアをするためには15歳で区切ってしまうのは問題になりますね。
前川 この点は,小児科医にはほとんどコンセンサスができていると思います。小児期あるいは生まれたときから慢性の疾患を持ち,小児年齢を超えて成人に至る人は非常に増えています。
そういう患者さんを継続して小児科医が診ていくのは,適切なケアを行なう上でより望ましいことだと思います。小児科医だけがそう言っていてもなかなか通らない面があるのかもしれませんが。
トータルに子どもを診ることが基本
白木 内科では臓器別診療が非常に進みましたよね。場合によっては,小児年齢でもそれらの専門科で診る傾向があります。確かに,医療を効率的に行なうという意味では非常によいのですが,私たちが子どもを診るときには常に,トータルに診るということが基本にあります。人間は1つの臓器でできているわけではありませんから。ライフサイクルに従ったような疾患に関しては,やはり小児科医がケアをしていくべきではないかと思います。もちろんその時々において,各科の専門の先生方と共同して行なうべきだと思いますが。循環器や消化器,神経などの専門科を横糸とすれば,私たち小児科医の立場は縦糸でなければいけないのではないでしょうか。
小児が成長・発達していく過程を診ていくのは小児科医です。そして思春期,更年期,老年期とライフステージが移行していくわけですが,東大の大学院はすでにそういう発想も持っておられるようですね。
柳澤 東大は大学院の重点化に伴い,100年の歴史を持つ講座制から,大学院大学に変化してきました。小児科学教室と小児外科学教室,産婦人科学教室,それに老年医学教室が加わって,生殖・発達・加齢医学専攻という1つのグループを作りました。
ライフサイクルという観点からまとまったグループを作ったことは,非常に画期的なことだと思いますし,これからはそういう学問の発展が期待できるのではないかと思っています。
国立成育医療センター開設へ
前川 日本では残念なことに,小児病院が大学などに所属していません。すべて地域に独立して存在し,総合医療センターの敷地にはないのです。そのため,小児病院でずっとケアしていても,ある年齢になると経過をみることができないのです。白木 それは病院として年齢で区切ってしまうからでしょうか。
前川 それに入院ができないのです。ですから,糖尿病やてんかんの患者さんが30歳になって来ても診られません。
そこで,今度できるのが,国立成育医療センター(2001年開設予定)です。成育医療とは,出生前から乳児期・幼児期・学童・思春期と,子どもの全年齢にわたって診る広範な概念です。構想の中心となった小林登先生(国立小児病院名誉院長)は,そういう意味で子どもを生殖・発達・加齢まで含めて広く捉えています。
白木 年齢の制限はどうなるのですか。
前川 ありません。そこには産婦人科もあるし,小児科,内科,外科もあり,小児を中心にすべての年齢が診療できるように構想された病院になっています。小児科医は,他の部門と共同すれば,脳性麻痺でも何でもずっと診ていかれるし,ベッドも利用できます。年齢はあってもなきがごときと解釈したほうがよいのではないでしょうか。
白木 やはりそういう方向に行くべきですね。
前川 内科の先生方も,糖尿病に興味があるとか,腎炎に興味があるとか,障害児に関心があるようであれば,ある程度私たちと一緒に子どもを診ていってもよいような気がします。
白木 ライフステージに応じた診かたをする医師は,なにも小児科医だけでなくてもよいですからね。
子どもたちのためになる病院に
前川 国立の小児医療センターは,いまの天皇陛下ご成婚の時にできたアイデアなのです。ところが種々の事情があって,国のセンターとしては最後になってしまいました。だからそれだけに私としては本物をつくってほしい。あえてここで言わせていただければ,学閥をまずなくしてほしいのです。本当に子どもたちのためになるような,ライフサイクルを視野に入れた,世界的な規模のものをつくってほしいと思います。
白木 今日のいろいろなお話の,1つの結晶のような形で,国立成育医療センターが機能してくれればよいと思います。
前川 それから,大学の教育や,卒後教育に結びつく場所であってほしいのです。
白木 国立の小児病院は日本で唯一ですからね。各都道府県が,国立小児病院を見て小児病院をつくってきたわけですから,国立成育医療センターのあり方は,当然各都道府県の施設にも影響してくると思います。また学閥に関しては,小児科は最も少ない領域だと思いますよ。
思春期の心の問題と子育て支援
 柳澤 子どもの心の問題については,従来から小児科医は関わってきましたが,特に思春期の心の問題は,これから非常に重要な分野ではないでしょうか。
柳澤 子どもの心の問題については,従来から小児科医は関わってきましたが,特に思春期の心の問題は,これから非常に重要な分野ではないでしょうか。
前川 例えば登校拒否やいじめ,家庭内暴力などの問題は,思春期になると急に竹の子みたいに出てくるような感じでマスコミは取り上げます。ところが実際はそうではなく,子育ての段階から出てくるのです。ですから,それを防止することは育児を通しての小児科医の役目でもあります。
柳澤 そこには子どもの虐待の問題も入ってきますね。虐待については,小児科医は非常に大きな関心を持っています。
「オシッコが青くない」
前川 また育児で問題になっているのは,子育て・・親業(おやぎょう)といいますが・・のノウハウを知らないお母さんが多すぎることです。変な話ですが,昔は医師が注意すれば気がついたのです。ところがいまは外来で注意しても,何を言われているかわからない。CMの影響で「オシッコが青くない」と心配したり,「離乳」というのは母乳も牛乳もまったくあげないことだと思っていたりするお母さんがいます。ですが,そういう人を怒ったりしてはいけないんです。小児科医としては,親になるべき人たちが本当の親になるように,関係者みんなで支援することが肝要です。それとともに,育児の本質をもう少し小児科医が勉強して関わるようにすると,おそらく思春期になって問題が起こることも減るのではないかと思います。
それと並行して,これから母親になるであろう女性に対しても,積極的に関わっていかないといけないでしょうね。
柳澤 極端な少子化の中では,中学生,高校生,あるいは大学生に,子どもに触れるような機会を学校教育の中で積極的に作らなければいけないと思います。
白木 育児は,本来は男女一緒にやるべきことですね。基本的な姿勢としては。
前川 体の構造上,お産をし,母乳をあげるのが女性だということですね。
白木 母性教育と同時に父性教育も必要です。
前川 父親については,いままで小児科ではあまり考えられていませんね。ですからそれも1つのテーマになるのではないでしょうか。
母子保健法改正の影響
白木 子育てに関しては,母子保健法が改正(1997年4月施行)になったこととの関係もあろうかと思いますが。前川 新しい母子保健法でいちばん焦点になっているのは,母子保健に関する基本的事業は市町村が行なうということです。そして専門的なことは県など上のレベルがやると。それは一見非常によいのです。ところが保健所を減らして保健センターを多くしている現状では,老人が多いために,地域では乳幼児健診さえまともにやれなくなってしまうのです。大都市や政令都市はまだよいのですが。
白木 地方はそこが非常に手薄になる可能性があります。
前川 もしそうなると,小児保健の衰退にまでつながります。それをいかに防止しようかということで小児保健関係者が検討していますが,日本小児科学会でも声をあげていく必要があります。
母子保健法がプラスに働くかマイナスに働くか。2020~30年になって初めて事態に気がつくことになるかもしれません。
白木 社会を支える大人を育てるには,子どものうちからが大切ですからね。20~30年前から手を打っていかなくては。
小児科医のやることはいくらでもある
白木 小児科医が担う役割は広がっています。研究,診療,また保健的なことが非常に大事になってきましたし,場合によっては子育てなどの教育面まで関わる必要があります。前川 子どもが少なくなることをポジティブにとると,いままでは小児科医が忙しすぎたと言えますね。健康な子どもの75%以上は小児科医以外の医師が診ていました。しかし子どもの数が減ると,今日話してきたようなことすべてに,小児科医が十分手をかけられるようになると思います。
総医療費に占める小児医療
前川 小児科医のやることはいくらでもありますが,お金に結びつかないことが多いですね。子どもの健康維持にしても。それがもしペイできれば,小児科はとても楽しくなると思います。白木 いままでの保険制度では,予防的医療は保険適応にならなかったのです。予防的医療で保険適応なのは狂犬病で,狂犬病の犬に噛まれた段階で適応になります。そしてB型肝炎の母子感染防止が昨年から適応になりました。一昨年までは公費負担として,国の事業でなされていたのですが。厚生省も,予防的医療でもそれがハイリスクであれば保険にしてよいという考えになってきたわけですね。
そういう風潮になってきましたので,小児保健でも当然保険適応にしていくようにしたいと思います。
前川 ここにおもしろい統計があります。1989(平成元)年の日本の一般診療医療費の総額は17兆円強で,15歳未満の小児人口で使っているのは1兆1000億円くらい(6.7%)です。そして65歳以上人口に使われたのが6兆9000億円(40.5%)。さて,1994年の一般診療医療費は21兆5000億円になっていますが,小児人口で使っているのはやはり1兆円強なんです。つまり総医療費が増大しても,子どもに使っている医療費はほとんど変わっていない。この事実からも,小児科医はもう少し発言しないとまずいと思いますね。
乳幼児健診を保険適応に
白木 昔から予防にまさる医療はないといいながら,実際には,予防にそれほどお金をかけていないように思います。前川 例えば公費の乳幼児健診がありますね。そうすると結局これは保険外で,自費扱いの収入になりますから,税金がかかるのです。そういうことを知っている大学教授はほとんどいません。開業医の方は収入の1/4~1/3が乳幼児健診や予防接種ですが,自費として税金がかかってしまうわけです。
同じ公費で入ったお金でも,老人保健法のものは保険診療として落ちます。ですから小児でせめてそれだけでも保険診療として扱ってくれれば,ずいぶん小児科医は楽になります。
柳澤 国として,子どもを健全に育てるための費用は惜しまずに注いでいただくことが,高齢化,少子化の時代を開いていく上でぜひ必要ですね。そのことを,小児科医がもっと主張し,日本小児科学会としても主張していくべきでしょう。
白木 厚生省の母子保健課にも頑張ってもらうよう,プッシュすることが必要ですね。
前川 これからの小児医学,小児医療を考える際には,いくつかテーマがあると思いますが,医学そのものは,すごい勢いで進歩すると考えられます。例えば遺伝子工学にしろ,未熟児,低出生体重児の成育限界にしろ,非常に費用のかかる医療がどんどん進んでくる。そうすると今度は,その医学の進歩をいかに医療として採用するかということが,21世紀の課題になると思います。
小児患者の長期的追跡データが必要
前川 それからもう1つ忘れてはいけないのは,先天性心疾患や脳性麻痺を治療して助かった子どもが,大きくなってどうなっていくかというデータがないことです。例えばファロー四徴症の根治手術などは,まだ30年たっていないでしょう。そういう人たちが,40歳,50歳になったときにどうなるかを調べる必要があります。昔,脳性麻痺の定義は非進行性の運動障害でした。ところがある年齢になると骨や筋肉がだめになって,退行していくのです。ですから最近は逆に,脳性麻痺のうちのある部分は遺伝的な疾患ではないかという概念も出ています。そういう小児期の慢性疾患の,大人になってからの経過は知られていませんね。そういうことも次の課題になると思います。
白木 そこを明らかにしていかないと,先の対策が立たないですからね。
積極的な国際協力を
前川 それからもう1つは,アジアをひっくるめた中での小児医療をどうしていくかに積極的に関わること。これがこれからの小児医療や学会の最大のテーマになると思います。白木 小児科学ならびに小児医療のレベルが,アジアの各国と日本とでかなり違う部分がありますね。疾患もかなり異なりますが。例えばこのあいだジャカルタでアジア太平洋小児栄養消化器病学会の教育セミナーがあったのですが,現地では,肝炎もかなりありますが,やはり下痢症がメインなのです。下痢症の治療をどうするかは非常に大きなテーマであって,それに対して,私たちが20~30年前に経験したことですが,その経験をある程度伝えることによって,かなりよいコミュニケーションができたと思います。
前川 世界では1日に4万人の子どもが死亡しています。その大部分が栄養障害や感染症です。そうするといま日本でなされている先進的医療は,ある意味で贅沢の極みなのです。これをあたかも使命としてやっていてよいかということも,これから考えなければいけないと思います。
白木 研究的な面と実際の医療とは,やはりどうしても別にせざるを得ないと思いますね。
小児科医は世界に通用する
前川 それから,日本の若い小児科医も,どんどん海外へ出て役に立ってほしい気がします。柳澤 日本がいままで行なってきた国際医療協力の中でも,小児科医の活躍は非常に目立ちます。それは裏返せば,世界から求められているのは小児科医だということにもなります。世界的なレベルでの医療・保健の向上には母子保健の向上が最も重要だということで活動してきていますが,とても十分ではないし,これからますます日本の小児科医が担わなければいけない大きな部分ではないかと思います。
前川 世界の災害地などに行けば,「自分の専門ではないから診療できない」というわけにはいきません。小児科医は,たとえ専門が何でも,トータルに診ることができます。柳澤先生がおっしゃった通り,小児科医は世界に通用するのです。ですから,人間全体を捉えることは,これからの小児医療にますます求められますね。
白木 研究という面では小児科も専門化が進んでいます。それはそれでどんどん研究として進めるべきですが,医療という立場からいえば,トータルに診ていく姿勢はずっと貫かなければいけないと思います。
柳澤 下痢や栄養障害,感染症など,日本や欧米ではほとんど克服されたと思われている状況が世界的にはそうではないし,また先進国においても,エマージング・インフェクション,すなわち新しい感染症や再び現れた感染症などが出てきています。研究面も臨床面も重要ですね。
前川 おっしゃる通りですね。医学というのは絶えず流動的で,本当に追いかけっこのような感じです。
小児科入局者数の偏在
前川 ところで,嬉しいことにいまでも小児科の入局者はそう減っていないと思うのですが。白木 非常に偏在しているのです。私どものような地方大学では減っています。
前川 各医学部の定員が120人から100人になったことも理由としてありますね。卒業生全体の数が減少しただけという。
柳澤 小児科学会の統計では,卒業して各大学の小児科に入局した数の合計はあまり減っていませんね。
白木 卒業生全体の中での数は減っていませんが,地方大学では減ってしまう。つまりシフトしているのです。出身大学に残らずに,東京や大阪へ行っている。人口が少ないから地方には残らないという人もいて,都会へ帰ってしまいます。
小児科学は,少子化のいまだからこそいろいろな意味での重要性が増した部分があります。また,子どもたちが成長して社会を支える,その元をつくるいちばん大事な学問だと思うんです。これからの100年を踏まえてさらに進歩・発展すべきですし,そういった意味では,小児科医になる人はむしろ増えなければいけないと思います。
前川 いまは医師の4~5%ですかね。
白木 それが20%くらいにならないといけないのではないかと思っています。
「小児科医になってよかった」と
前川 若い医師たちに,小児科というのは夢も希望もあって,これから伸びる学問であるということを伝えたいですね。また,定年で辞めるとき,あるいは人生を終えるときに,「やはり小児科医になってよかった」と感じられる要素を持っているのが,小児科だと思うのです。白木 本日は,これから小児科学,小児医療がどのように発展していくかということを大変コンパクトにお話しいただきました。これを読んで小児科を志望する方が出てくれば大変ありがたいですし,また小児科医の方に元気を出して頑張っていただければと思います。どうもありがとうございました。
(おわり)
