「基本的臨床技能の教育法ワークショップ 」開催
身体診察や医療面接の効果的な教育・評価法を学ぶ

昨年11月22-24日,東京の日赤武蔵野女子短大で,「基本的臨床技能の教育法ワークショップ」(主催=日本医学教育学会「基本的臨床技能教育法ワーキング・グループ」)が開催された。
このワークショップは,卒前教育において,基本的な臨床技能(医療面接や身体診察など)を学生に効果的に修得させるための教育・評価の手法を学ぶことがテーマ。各医科大学・医学部の臨床技能教育担当者(予定も含む)28名が参加し,合宿形式で行なわれた。なおスタッフは上記ワーキング・グループ主任の津田司氏(川崎医大教授)の他,畑尾正彦氏(日赤武蔵野女子短大教授),伴信太郎氏(川崎医大助教授),藤崎和彦氏(奈良医大教授),中村千賀子氏(東医歯大)の計5名が担当した。
ワークショップ参加大学
|
先進的な教育手法を ワークショップ形式で学習
ワークショップは (1)臨床技能教育の目標,(2)臨床技能教育の方略と評価,(3)臨床技能の評価表作成,(4)医療面接の臨床技能教育,(5)身体診察の臨床技能教育などの項目に沿って進行した。要所要所で津田氏らによるレクチャーもあったものの,構成の中心は小グループ(4班)でのディスカッションと全体討議。提示される課題ごとにグループでディスカッションを行ない,それぞれの結論を全体討議で報告し,議論するという形式で行なわれた。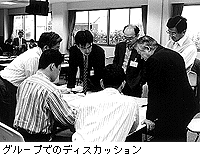 | 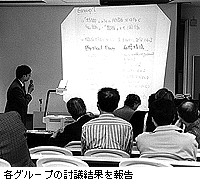 |
医療面接・身体診察の学習法として,書物,講義,見学,練習などの方法が考えられる。また,評価法にはペーパーテスト,口頭試問,そして実地試験に最適とされるOSCE(objective structured clinical examination:客観的臨床能力試験)がある。ワークショップでは,効果的な教育手法とされるロールプレイ(学生同士が患者役,医師役,評価者となって練習する)やSP(模擬患者,標準模擬患者=患者役として一定の標準的対応ができるよう訓練を受けた者)を用いた練習,またOSCEによる評価についての具体的な学習がなされた。
学生のつもりでロールプレイ
ロールプレイ,SP,OSCEについては,解説・グループ討議(導入にあたっての問題点など)の他,参加者がその実際を体験する場面も設定された。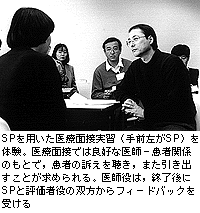 はじめに参加者が互いに医師役・患者役となって,医療面接のロールプレイを実施。グループ討議で感想を抽出した後,今度は各グループに1人ずつのSP(東京SP研究会所属)を迎え,グループの中の1人が医師役となって,初診患者を想定した医療面接実習を行なった。SPに関しては,その後の討議で「学生同士のロールプレイよりも臨場感,緊迫感がある」「SPからのフィードバックは有用」「コミュニケーション能力の教育に適している」などの意見が出された。さらに医療面接の意味や具体的な教育手順,教育上の留意点などについての解説も行なわれた。
はじめに参加者が互いに医師役・患者役となって,医療面接のロールプレイを実施。グループ討議で感想を抽出した後,今度は各グループに1人ずつのSP(東京SP研究会所属)を迎え,グループの中の1人が医師役となって,初診患者を想定した医療面接実習を行なった。SPに関しては,その後の討議で「学生同士のロールプレイよりも臨場感,緊迫感がある」「SPからのフィードバックは有用」「コミュニケーション能力の教育に適している」などの意見が出された。さらに医療面接の意味や具体的な教育手順,教育上の留意点などについての解説も行なわれた。
身体診察に関しては,各大学での現在の教育の問題点についてディスカッション。設備・人員不足,目標設定,評価,実施時期,テキスト,男女共学の場合の配慮など,克服すべき課題があげられた。またレクチャーでは,アメリカの教育用ビデオや,オランダ・リムバーグ大(本紙第2219号参照)の教育を解説したビデオ,また各種の教材も紹介された。
OSCEの実際を体験
2日目までの議論を経て,ワークショップ最終日には実際に,武蔵野日赤病院の研修医(1年目)5名を受験者役にしたOSCEが行なわれた。会場となった体育館には5つのステーション(試験場所)が置かれ,ワークショップ参加者たちはグループに分かれて,評価者として各ステーションに配置された。患者役には,医療面接ではSPが,その他のステーションでは現役の医学生が扮した。
各ステーションで出された課題はそれぞれ(1)医療面接,(2)バイタルサイン,(3)腹部診察,(4)脳神経診察(5つめのステーションでは休憩)。受験者は1ステーション5分間の実技を終えたのち,2分間のフィードバックを受け,次のステーションへと移動する。評価者は各受験者に対する評価を評価シートに記載し,交代でフィードバックも担当した。
OSCEについては文献や言葉でいくら説明されても,実際の様子を体験しないことにはその概要をつかみにくい。デモンストレーション終了後の全体討議では,課題の出し方や試験時間,国家試験への導入の可能性など,参加者から具体的な質問が出され,OSCEに対する理解の深まりをうかがわせた。
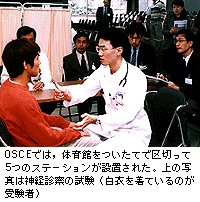 | 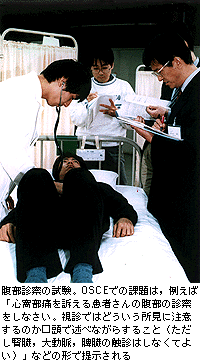 | |
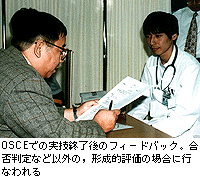 |
すぐにでも実践できる
今回のワークショップのねらいは,ここで学んだ教育手法を各大学ですぐにでも実践できるように,細かいノウハウまで修得すること。そのため,配付された資料は,医療面接・身体診察教育の基本や方法の解説,ロールプレイ用の症例(シナリオ),またOSCEの評価シートや評価マニュアルなど,そのまま教育の場で使用できる内容になっている。周到に準備された資料には参加者の評価も高かったようだ。参加大学の中にはOSCEなどを導入する計画をすでに立てているところもあり,主催者側では1年以内に参加者にアンケートを送り,各大学の状況を調査することにしている。なお同様のワークショップは今後も継続して行なわれる予定。
