クリティカル・シンキング研究会 '96 ユタ大学夏期セミナー開催
「フィジカル・アセスメントとクリティカル・シンキングの理論と実際」
野地有子(聖路加看護大学),牧本清子(金沢大学),ダーリン・メサビー(ユタ大学)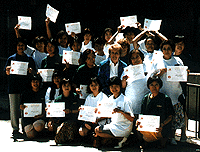 '96ユタ大学夏期セミナーは,1994年に行われたワシントン大学セミナー後のフォローアップ・ミーティングから結成された日本クリティカル・シンキング研究会の主催により実施された。ユタ大学は,全米で看護教育の長い伝統をほこり,CNSなど看護専門職のリーダーを多く育て,ナーシング・センターなどで看護の独自性を生かしたサービスを地域へ展開してきている。そこで私たちは,米国の看護教育の基盤となっているクリティカル・シンキングと,フィジカル・アセスメントの理論と実際を学ぶために,本年8月3日にソルトレイクシティーを訪ね,11日までのセミナーを実施した。参加者は,全国の看護教育者と臨床ナースおよび保健婦20名であった。
'96ユタ大学夏期セミナーは,1994年に行われたワシントン大学セミナー後のフォローアップ・ミーティングから結成された日本クリティカル・シンキング研究会の主催により実施された。ユタ大学は,全米で看護教育の長い伝統をほこり,CNSなど看護専門職のリーダーを多く育て,ナーシング・センターなどで看護の独自性を生かしたサービスを地域へ展開してきている。そこで私たちは,米国の看護教育の基盤となっているクリティカル・シンキングと,フィジカル・アセスメントの理論と実際を学ぶために,本年8月3日にソルトレイクシティーを訪ね,11日までのセミナーを実施した。参加者は,全国の看護教育者と臨床ナースおよび保健婦20名であった。
地域ボラと一緒に模擬演習
セミナーは,早朝の図書館での自己学習からスタートした。ユタ大学の図書館地下1階には,コンピュータと自己学習用のソフトが充実していた。午前中は,クリティカル・シンキングのクラスがもたれた。講師は修士論文でクリティカル・シンキングを研究,現在は看護実践コーディネーターをしているリン・ホリスターさんで,クリティカル・シンキングの定義,基礎的要素である事実,発想,結果と推論,技法の特定を重点的に考察。グループ討議などを通して,事例による推論のトレーニング,「ナースはフィジカル・アセスメントをするべきでない」をテーマにしたディベート,看護過程において必要なクリティカル・シンキング技法についての検討などのプログラムが展開された。この体験は,教室や臨床現場におけるクリティカル・シンキング奨励のための環境設定の方法を具体的に身につけるよい機会となった。フィジカル・アセスメントでは,心臓血管系,呼吸器系,耳鼻咽喉系,神経系,運動機能について講義と演習を行なった。講師はヒラリー・パーソンさん(老人・家族・在宅ケア専門)とカレン・スティリングさん(成人・小児・家族ケア専門)の2人のベテランのナースプラクティショナーで,演習用模擬患者として3名の地域住民がボランティアで協力。各自アセスメント用具を手に,ナースが組織的,系統的かつ専門職にふさわしい方法で,成人患者から関連データを引き出す上で必要な技法を修得し発展させるトレーニングをした。
アモス学部長によれば,ユタ大学においても高齢者看護は重要になってきているとのことで,特に,高齢者については1日かけて,米国と日本の事例から,推論を活用したアセスメントを学んだ。実際のベテランのパフォーマンスも参考となった。
最終日には,「Critical Thinking in Medical-Surgical Settings:A Case Study Approach」の著者のメリル・ウイニンガム氏を迎え,事例を通して看護の知識とクリティカル・シンキングの技能を習得する看護教育方法について学んだ。
本セミナーから今後の研究会活動に多くの示唆を得た(関連対談)。
・日本クリティカル・シンキング研究会 事務局:聖路加看護大学内(野地有子) TEL&FAX(03)5550-2271
