来世紀の小児科学「成育医療」を語る
国立成育医療センター(仮称)設立に向けて
 小林 登氏(東京大学名誉教授,国立小児病院名誉院長)に聞く
小林 登氏(東京大学名誉教授,国立小児病院名誉院長)に聞く
1994年11月,厚生省保健医療局の委員会は,母子を中心とする次世代の健康を考えた「成育医療」のナショナルセンターを設立する必要があるという答申を行なった。そこで国立病院の再編成の中で,国立小児病院と,同じ世田谷区にある国立大蔵病院とを合わせて「国立成育医療センター(仮称)」を設立すべく,現在基本的な設計の段階に入っている。2001年には,病棟10階建,研究所8階建,情報センターを含む事務棟3階建という大規模な病院ができることになっている。
本号では,この4月をもって国立小児病院長を退官した小林登氏に,その背景,来世紀の小児科学の姿といえる「成育医療」についてお話をうかがった。
小児難病の成人化
小児医療には大きく分けて2つあります。1つは総合病院の中の小児医療,そしてもう1つは小児病院で行なわれる小児医療で,これを小児総合医療といいます。つまり小児病院というのは,単なる小児科の病院というものではありません。外科もあるし眼科,耳鼻咽喉科,歯科もある。つまり「子どもの総合病院」ということです。国が子どもの総合病院を持っているということがあまり認識されていないようですが,いわゆる小児医療と小児の総合医療は本質的に違います。国立小児病院の眼科の医師は,子どもの眼科の問題を何十年も見てきている専門家です。外科,耳鼻咽喉科,歯科のそれぞれの医師も,小児特有な疾患,病態の専門的,総合的な知識と技術を持った専門家たちなのです。そのような小児の総合医療が現在抱えている問題の第1は,小児難病治療の進歩に伴う問題です。この進歩の結果,治療を受けた子どもたちが大人になってきている。私は「小児難病の成人化」という言葉を使っています。例えば,先天性の胆道閉鎖で手術した子どもがやがては成人して,女の子ならば妊娠するということにもなります。あるいは,4歳か5歳くらいからインスリンを打ち続けながら大人になる糖尿病の子どももいるのです。こういった治療医学の進歩のおかげで,今の国立小児病院には,200名くらいの患者さんが入院していますが,そのうち10人ほどは成人です。それは,その人は成人したのだから内科に移るようにして下さいといっても,そういった患者さんを内科の医師は診たことがないからです。産婦人科の医師でも,先天性の胆道閉鎖症の子どもが大人になって妊娠したらどうなるかという経験もない。もちろん糖尿病の子どもたちは年に1回必ず国立小児病院に入院して血糖コントロールを図りますし,先天性の胆道閉鎖を治療した子どもも調子が悪ければ入院したりしながら,教育を受け社会人になっています。ですから小児難病治療の進歩に伴って,医療は今後一層「小児難病の成人化」に対応していかなくてはなりません。
そして第2には「成人病の若年化」です。肥満のために糖尿病の発病が早くなるとか,高血圧のために若くして動脈硬化になるという問題が出てきています。
さらには第3の大きな問題として,ハイリスク妊娠があります。これは小児科の医師の立場からみると,生まれてくる新生児がハイリスクということです。今でも国立小児病院では,他の医療施設で生まれたハイリスクの新生児,未熟児の治療を引き受けています。ですがこれからは,糖尿病のお母さんが妊娠すれば,血糖のコントロールを教える,あるいは高血圧の妊婦さんならば,その治療をしながら,お産の前から病院に来てもらって,そこで出産してすぐに専門家が対応するようにすれば非常に効率よく医療が提供できるのではないかと考えています。
それから4番目が思春期医療ですね。思春期医療というのは,重要でかつ近年患者さんが増えているにもかかわらず,各科の狭間にあるのが現状です。小児科も原則として15歳以下を対象としていますので,ここから外れている世代に特有な問題を対象とした医療を充実させようということです。
ライフサイクルで捉える「拡大された」小児医療
小児科をとりまく環境としては,子どもの数はもちろん減っていますし,その上生活水準もよく,多くが順調に発育するようになっていますから,小児科の患者さんは少なくなってきていて,東京では山手線の内側にある総合病院の小児科は閉鎖してしまうといった事態になってきています。しかし,国立小児病院でも,患者さんの数は減ってきてはいるけれども難病に対する医療の需要はそれほど少なくはなっていないどころか,ますます必要になってきているのが実状です。そこで小児医療を新しく捉え直して,従来の単なる小児科ではやっていけない医療もできるようにしなければならなりません。これまで小児科では,出生,小児,成人,老人といったそれぞれのライフステージの枠組の中で小児医療を捉えてきました。しかしよく考えてみると,小児科というのは,生命の誕生から大人になって次の生命にバトンタッチするという,一連の流れに対処する医療であるべきです。人為的にライフステージで切っていくのは時代錯誤であり,これに代わってライフサイクルでみていく小児医療が必要ではないかという体系を考えて「成育医療」という新しい体系を提唱しているわけです(図1)。
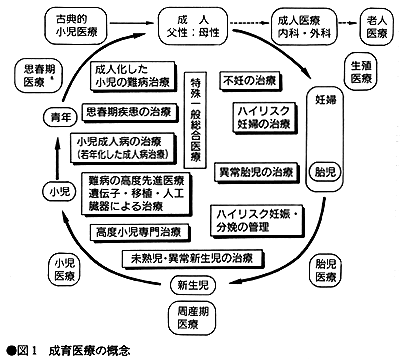
つまりこれまでライフステージという捉え方で発展してきた小児科を,ライフサイクルの中で捉え直して発展的に拡げていくのが成育医療ということになります。具体的には生殖医療(不妊治療),胎児医療,ハイリスク妊娠への対応,周産期医療,これまでの小児医療,そして思春期医療をカバーするものです。そうすると,これらの領域に対応する総合医療も不可欠です。つまり,「拡大された小児病院(Extended Type Children Hospital)」として新しい総合医療施設が必要となるのです。昔の古典的な小児科というのは,総合病院の中の小児科でした。私のこれまでの小児医療の歩みを考えてみても,医学部を卒業して間もなく新生児医療がはじまり,それから小児科の専門分化が起こって小児医学に発展していった。だからこの段階でも「拡大された小児医療」になったわけです。それによって国立小児病院ができて,さらに周産期が入ってきてこれは母子医療になった。母性小児医療センターは神奈川県や大阪府にありますが,これをとり込み乗り越えて「成育医療」という医療体系を考えているのです(図2)。
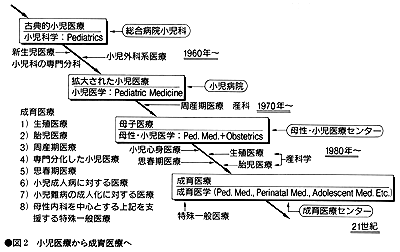
組織としては国立大蔵病院は総合病院で,助産婦学校も,産婦人科も整っている病院ですから,それと国立小児病院を一緒にして,500床規模の「国立小児医療センター」という,癌センターや循環器病センターに準じるインテリジェント化したナショナル・センターを作る予定です。また,現在の小児医療研究センターも,生殖生物学や産科学専門の研究分野も加えて1.5倍ほどの規模になります。
厚生省は,3万坪ある国立大蔵病院の敷地に大きなガーデンホスピタル,「成育ガーデン」という小公園を持った病院を作る計画で,この間もインテリアやデザイン関係の人も入った設計のグループが来て検討していました。おそらく21世紀のライフサイクルを志向した,新しい母子を中心とした総合医療の場としてふさわしい病院ができあがるのではないかと思います。
