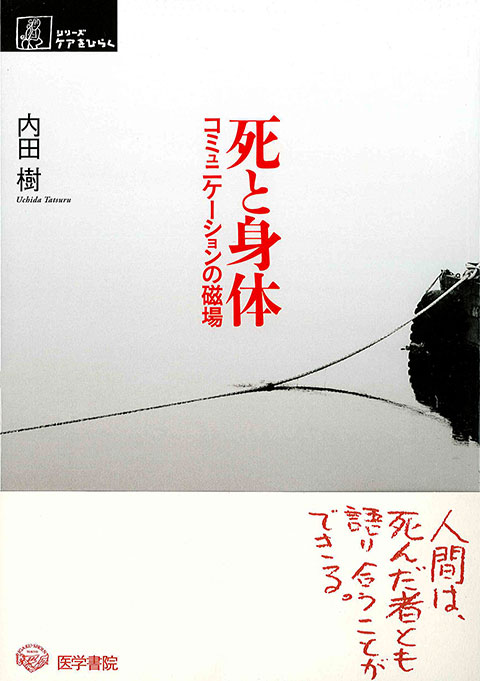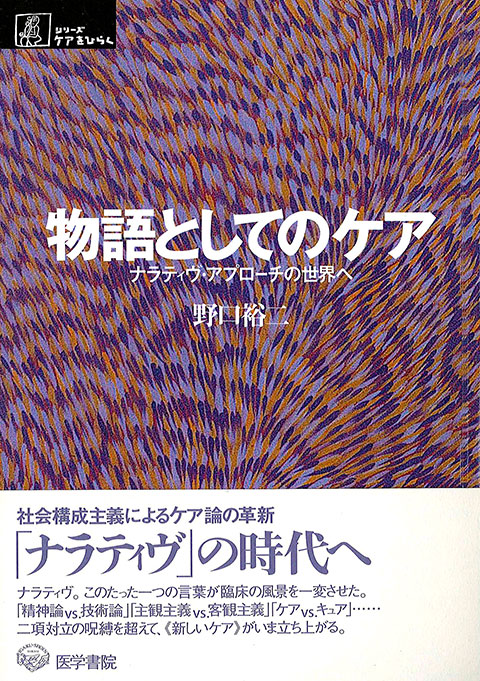驚きの介護民俗学
語りの森へ。
もっと見る
『神、人を喰う』でサントリー学芸賞を受賞した気鋭の民俗学者は、あるとき大学をやめ、老人ホームで働きはじめる。そこで出会った「忘れられた日本人」たちの語りに身を委ねていると、やがて目の前に新しい世界が開けてきた……。「事実を聞く」という行為がなぜ人を力づけるのか。聞き書きの圧倒的な可能性を活写し、高齢者ケアを革新する話題の書。
| シリーズ | シリーズ ケアをひらく |
|---|---|
| 著 | 六車 由実 |
| 発行 | 2012年03月判型:A5頁:244 |
| ISBN | 978-4-260-01549-3 |
| 定価 | 2,200円 (本体2,000円+税) |
更新情報
-
更新情報はありません。
お気に入り商品に追加すると、この商品の更新情報や関連情報などをマイページでお知らせいたします。
- TOPICS
- 序文
- 目次
- 書評
TOPICS
開く
●『シリーズ ケアをひらく』が第73回毎日出版文化賞(企画部門)受賞!
第73回毎日出版文化賞(主催:毎日新聞社)が2019年11月3日に発表となり、『シリーズ ケアをひらく』が「企画部門」に選出されました。同賞は1947年に創設され、毎年優れた著作物や出版活動を顕彰するもので、「文学・芸術部門」「人文・社会部門」「自然科学部門」「企画部門」の4部門ごとに選出されます。同賞の詳細情報はこちら(毎日新聞社ウェブサイトへ)。
●本書が日本医学ジャーナリスト協会賞大賞(書籍部門)を受賞!
第2回日本医学ジャーナリスト協会賞(日本医学ジャーナリスト協会主催)が2013年10月7日に発表となり、大賞(書籍部門)に本書が選出されました。 《認知症については、かつては脳科学的解明が優先され、コミュニケーションの重要性が指摘されても、それはあくまでも「よい支援」をするためのものでした。本書は、認知症の人を「支援する対象」とだけ見ていては到達できない事実を明らかにしました。》――受賞理由(抜粋)
●第20回旅の文化奨励賞を受賞!
●著者の六車由実氏がAERA「現代の肖像」に登場!
《自ら挫折や苦渋を味わってきた六車だからこそ、高齢者たちの人生の最終章における伴奏者としての視線には独特の柔らかさが宿る。》――横田増生(ノンフィクションライター)
●動画配信中!
日本記者クラブ主催の「著者と語る」で、著者・六車由実氏が会見し、記者の質問に答えました(YouTube 日本記者クラブチャンネルより)。
序文
開く
九月のある日、老人ホームのリビングで利用者とともに夕食のワゴン車が来るのを待っていた。そのまったりとした時間に、認知症を患っている鈴木のり子さん(仮名、以下同)が、テーブルの上に飾ってあった作り物の柿を枝からもいで、「おいしそうだねえ」と言って食べようとしていた。
口に入れる寸前に気づいた私はとっさに、「ごめんなさい。これ食べられないんです」と言って、のり子さんの右手から柿を取り上げた。するとのり子さんは、「そう、まだ渋が抜けてなかったんだね」と残念そうにうなずいた。あんまりがっかりしているので、事故を防ぐためとはいえ急に取り上げたのは申し訳なかったなと思い、のり子さんにあらためて謝ろうと思っていたら、今度は彼女は大きな声で歌い始めた。
「柿、柿な~れ、千百俵、成らぬとぶっ伐るぞ、低いとこ成ると子どもがとるぞ、高いとこ成るとカラスが食べるぞ、ちょうどいいとこかたまれ、かたまれ」
急に歌い始めたので最初は何なのかよく聞き取れなかったが、とまどう私の様子をすぐ傍で見ていた杉本雅夫さんが、「ああ、おばあさんは、ほら、正月十五日の、あれを歌っているんですよ」と教えてくれた。私は「柿」と「正月十五日のあれ」でピンときた。そう、のり子さんは成り木責めのときの歌を歌っているのだと。
成り木責めとは、小正月行事のひとつで、柿や栗など実の成る木を鉈〈なた〉などで叩きながら文句を唱えることで、その年の豊かな実りを祈ろうとする民俗儀礼である。各地で歌の文句や儀礼の細部に違いがあるため民俗学でも取り上げられることが多い。私は、歌の文句を書きとめようとすぐにメモ帳を取り出し、のり子さんにもう一度歌ってくれと頼んだ。のり子さんは私のペンの進み具合を見ながら何度も何度も繰り返し歌ってくれ、そして庭の柿の木を鉈で叩きながら歌ったことや、叩いた後に木に粥をこすりつけたことなど、子どものころの体験も話してくれた。雅夫さんもうんうんとうなずいている。
私はメモをとりながら幸せな気持ちでいっぱいになった。すると今度は、まわりで聞いていた他の利用者たちが、自分たちのところではこういう文句だったと歌ってくれたり、鉈じゃなくて、漆〈うるし〉に似たカツノキという木でつくった刀を使ったとか、成り木責めをめぐって利用者それぞれの記憶を披露してくれた。作り物の柿を認知症の利用者が食べそうになるという“ヒヤリハット”の場面であったが、その柿をきっかけに、利用者たちの子どものころの正月の記憶に思わず触れる楽しい時間へと展開していったのだった。
大学を辞めて、縁あって老人ホームで介護職員として働き始めてから三年が経とうとしている。介護の現場は想像以上に大変で、毎日のルーティンワークをこなすので精一杯だが、そうした忙しさのなかでも、利用者たちの子どものころや青年期についての記憶に思わず触れる瞬間は、私に驚きと興奮と、そしてひとときの幸せを与えてくれている。老人ホームには、今ではムラの調査では直接出会うことのできない世代である大正一桁生まれはもちろんのこと、明治生まれの利用者もいる。また地元だけではなく、利用者の出身地は全国各地に及ぶ。そして彼らの記憶の何と鮮明なことか。長いあいだ、さまざまな地域をまわってムラでお年寄りたちに聞き書きをし、地域の民俗事象について研究してきた私には、老人ホームで働き、そうした利用者に囲まれている毎日が、まるでフィールドワークをしているかのように刺激的であり、幸せの日々なのである。
民俗研究者であり介護職員でもあるという立場から、私は日々の介護の現場で出会うこのようなさまざまな利用者との関わりやそのエピソードを文章にまとめ、《驚きの「介護民俗学」》というタイトルで、医学書院の『看護学雑誌』、およびその後、看護師のためのウェブマガジン『かんかん!』に連載させてもらった。
「介護民俗学」などという分野があったわけではないし、ましてやそんな言葉だってなかった。私自身の反省でもあるが、民俗学にとって、介護の現場は関心の外だったのである。けれど実際に現場に入ってみると、先ほど述べたように介護現場は民俗学にとってとても魅力的な場所だし、また、民俗学でこれまで蓄積されてきた知識や技術が介護現場に役立つ可能性もあるのではないか、と私には思えた。そこで、「介護現場は民俗学にとってどのような意味をもつのか?」、そして「民俗学は介護の現場で何ができるのか?」という二つの方向性から問題提起をしてみようと思い、あえて「介護民俗学」を掲げてみたのである。
本書は、十五回にわたる連載を中心に、書き下ろしと合わせて再構成してまとめたものである。一年三か月にわたる連載期間中に、私の所属もデイサービスから、特別養護老人ホーム(入所)、ショートステイへと変わっていったため、本文中にはそれぞれでの経験が混在している。その点はご容赦願いたい。また、本文中に登場する利用者の名前はすべて仮名であることもここに記しておく。
民俗学を専門としている読者には介護現場の魅力を、そして、介護現場で働いたり在宅介護をしたりと何らかのかたちで高齢者介護に関わる読者には民俗学的思考の面白さを、そして、それぞれがさまざまな人生を生きてきているすべての読者に、老人ホームの利用者たちの語る世界の豊かさを感じていただけたら幸いである。
目次
開く
第一章 老人ホームは民俗学の宝庫
「テーマなき聞き書き」の喜び
老人ホームで出会った「忘れられた日本人」
女の生き方
第二章 カラダの記憶
身体に刻み込まれた記憶
トイレ介助が面白い
第三章 民俗学が認知症と出会う
とことんつきあい、とことん記録する
散りばめられた言葉を紡ぐ
同じ問いの繰り返し
幻覚と昔話
第四章 語りの森へ
「回想法ではない」と言わなければいけない訳
人生のターミナルケアとしての聞き書き
生きた証を継承する-『思い出の記』
喪失の語り-そして私も語りの樹海〈うみ〉に飲み込まれていく
終章 「驚けない」現実と「驚き続ける」ことの意味
驚き続けること
驚きは利用者と対等に向き合うための始まりだ
おわりに
書評
開く
●新聞で紹介されました
《そこに浮かび上がってきたのは、「傾聴」「共感」「受容」という観念にがんじがらめになったケア(「聴き取り」)の歪(いびつ)さであり、一方でテーマを先に設定する民俗学調査のまなざしの狭さだった。》――鷲田清一(大谷大学教授・哲学)
(『朝日新聞』2012年4月1日 書評欄・BOOK.asahi.comより)
《民俗学者がその訓練を生かしてフル勤務の介護職員となって記録をとり、骨太のストーリーを発掘してゆく。故・小澤勲対談集『ケアって何だろう』あたりから医学書院の出版物に目が離せなくなった。》――中井久夫(精神科医)
(『図書新聞』2012年7月21日より)
《介護する側と介護される側とが共に蘇生していく過程が、短編小説のような味わいで描かれる。ついのめりこんで読まずにはいられない。》――上野千鶴子(東京大学名誉教授・社会学)
(共同通信社配信、『北日本新聞』2012年4月1日 書評欄、ほか/ちづこのブログNo.23 | WAN:Women's Action Networkより)
《「聞き書きがいいのは、話す人だけでなく、聞く側も変わるということです。その人がどんなふうに生きてきたかが分かると、大抵のことは許せるという感覚になる。》
(『日本経済新聞』2012年7月7日 「こころ」欄より)
《「生き証人としての圧倒的な存在感。聞き手の視野が広がり、生きる支えになると思います。私がそうだったように」》
(共同通信社配信「種をまく」より、『静岡新聞』2012年6月12日ほか)
《介護現場では以前から、言葉を引き出し、話に耳を傾ける試みは行われてきた。だが、それは「介護の一環なので、話の内容自体より、話している心身の状態が観察対象で、記録もされません」。民俗学的アプローチでは、話の奥へと分け入っていく。》
(『北海道道新聞』2012年5月6日、『西日本新聞』2012年5月20日 「訪問」より)
《老人の聞き取りを3~5か月かけてまとめる小冊子「思い出の記」を手にして、伏し目がちに語った。積極性と控えめさ。そのバランスが年上の人に信頼される秘密とみた。》
(著者来店:本よみうり堂:読売新聞(YOMIURI ONLINE)2012年4月29日より)
《静岡県内の介護施設で働きながら入所者の人生を聞き取った「驚きの介護民俗学」(医学書院)が話題を呼んでいる。実は4年前まで私大の准教授だった正真正銘の民俗学者だ。》
(『中日新聞』2012年4月29日「この人」より)
《なれない介護の現場でそれぞれの生活史を背負った認知症の老人と接しながら、民俗学の〈聞き書き〉の力を介護に生かせるのではと実感し、入居者の様々な語りを記録し始める。従来の介護方法・技術の枠を広げる体当たりの試みと経験。》
(『東京新聞』2012年4月29日 書評欄より)
《本書は民俗学と介護の両分野に新しい可能性を開く瞠目の書である。》
((『47NEWS』新刊レビュー 2012年4月30日より)
《介護職員としての仕事の傍ら、高齢者から聞き取った話をまとめたのが本書だ。……昭和初期の会社勤めなど都市生活をの様子を語る人もおり、本書はさながら宮本常一『忘れられた日本人』の現代版とでもいえそうな趣だ。》
(『日本経済新聞』2012年4月15日 書評欄「あとがきのあと」より)
《六車さんは、日本中の寒村を歩いた民俗学者宮本常一の書名を引き合いに「まさに『忘れられた日本人』がいた」と驚いた。六車さんは「介護民俗学」という新しい発想を提唱するようになった。》
(『中日新聞』2012年4月3日より)
●雑誌で紹介されました
《お年寄りたちは錆びた門のかんぬきを外すようにしゃべり出すのである。介護される者が熱く語り出し、介護する者がうなずいて聞く。幸福な主客転倒である。》――村田嘉代子(作家)
(『明日の友』2017年春号「こんな本をひらいた」より)
《〈そこで利用者は、聞き手に知らない世界を教えてくれる師となる〉という六車の指摘は重要である。「してあげる側」と「される側」に固定化された関係が、そこでは一次的にであれ逆転するのだ。》――斎藤美奈子(評論家)
(『ちくま』2016年3月号「世の中ラボ」より)
《本書は評者にとって、そして初めて本書の内容に接する多くの読者にとっても「驚きの『驚きの介護民俗学』」である。》――波平恵美子(お茶の水女子大学名誉教授)
(『日本民俗学』第276号(2013年11月30日) 書評より)
《著者は一歩踏み込んで「聞き書き」は死の淵にいる利用者へのターミナル・ケアとしての意味も必然的に持つことになるのではないか、とまで言いきっている。ずいぶんと大胆ではあるが、著者が列挙している具体例に照らし合わせてみるなら、これも得心のいく主張であると言ってよい。》――上村忠男(東京外国語大学名誉教授)
(『みすず』2012年6月号 「ヘテロトピア通信」より)
《「介護」と「民俗学」の結びつきにまず驚くが、勤めていた大学を辞め実家のある静岡県のデイサービス施設で介護職員として働き始めたとき六車さんの中ではその二つがすんなりつながったそうだ。》――佐久間文子(ライター)
((『文藝春秋』2012年5月10日号より)
《老人ホームで働きはじめた民俗学者が、高齢者たちの聞き書きを行った体験を書いた本があると聞いて、すぐにネットで注文した。…いやあ、ほんとに面白い。そして深い。》――梯久美子(ノンフィクション作家)
(『サンデー毎日』2012年6月3日号 「読書の部屋」より)
《介護民俗学のキーワードである「驚き」は、語る相手への敬意と愛情と知的好奇心が込められている。それは介護だけではなく、よりよいコミュニケーションのための重要なキーワードでもあるように思う。》――白石公子(詩人・エッセイスト)
(『婦人公論』2012年5月22日号 「カルチャーセクションBOOK」より)
《「常民の研究といいつつ、フィールドワークではある特別な人たちの特別な話を聞いていたことに気づかされました。お年寄りの話にじっくり耳を傾けるとみなさんすごく喜びます、家族には話しづらいこともおおいですから(笑)」》
(『週刊文春』2012年4月5日号より)
《100人いれば100人の人生や暮らしがあって、聞き書きしながら泣いたり笑ったり、民俗学者であることを差し置いても、人間のすばらしさを感じて幸せな気持ちになりますね。》
(『清流』2012年7月号 「著者に聞く」より)
《「高齢者一人一人の話に、小説以上の豊かさがある」》
(『クロワッサン』2012年6月25日号 著者インタビューより)
《人の話を聞くというのは、実は難しいことであり、やり取りを通して豊かなコミュニケーションが生まれる可能性を秘めている。》
(『WEDGE』2012年6月号より)
《介護でも「話を聞く」のは、「傾聴」と言われ重要視されているが、著者は、言葉の裏にある見えない「気持ちや心の動き」を重視するあまり、実は言葉を聞けていないのはと問題提起する。》
(『月刊ケアマネジメント』2012年4月号より)
異業種の「プロ」をいかす試み
書評者:岡田 慎一郎 (理学療法士・介護福祉士)
近年,ケアの現場にはさまざまな職業を経験した方々が転職してくる。建築業,外食産業,販売業,スポーツ,芸能,美術,IT,農業,漁業,林業……,驚くほど多様な職業からやってくる。
この本の著者,六車由実さんもそういった異業種からの転職組の一人だ。大学の准教授で気鋭の民俗学者だった彼女はあるとき職を辞し,郷里の介護施設に就職する。介護職として勤務する中で,施設利用者たちからの聞き書きを行うようになる。そして民俗学者としての視点から,これまで気付かなかった利用者の人生や行動を鮮やかに浮かび上がらせていく。
民俗学者ならではの着眼点
介護職ならずとも家庭介護の場でも直面する認知症の基本症状に,「同じ問いの繰り返し」がある。日本民俗学の創始者である柳田國男も最晩年,相手に出身地を問うことをエンドレスで行っていたという。しかし著者の六車さんは,出身地にこだわることは柳田民俗学の原点であり,その原点は最後まで失われていなかったのだと言う。ならば施設の認知症高齢者たちの「同じ問いの繰り返し」にも,その人のベースとなる「生きる方法」につながる意味があるのではないか——。こう考えて利用者さんの話を聞くと,そこにはさまざまな発見があった。
またレクリエーションの時間に,苦肉の策としてジェスチャーゲームを行ってみた。そこで利用者の見せる脱穀機やもちつきの動きが,民俗学者の知識,予測をことごとく打ち砕くものになったというくだりも痛快であった。言葉ではない,身体に刻まれた記憶が一瞬にして目覚めるさまが丁寧に描かれ,著者の驚きと快感が読者の私にシンクロしてくる感覚すら覚えた。
このように,介護現場ならではのエピソードを民俗学的思考によってひも解いていくところに本書の面白さがある。著者ならではの知的好奇心とチャーミングさが同居する文章によって,読者はあっという間にその語りの中に引き込まれていくだろう。
憧れと嫉妬を超えて
しかし,現場の職員の立場から考えてみると複雑な気持ちになるかもしれない。憧れと嫉妬が渦巻くからだ。本書の中にも,著者に浴びせられた同僚の痛烈な言葉が紹介されている。
「話を聞くことが介護なの? じいちゃん,ばあちゃんはみんな話したくてたまらないのよ」
介護現場は,入浴,排せつ,食事の三大介護を中心に,その日の生活をサポートするためにフル稼働している。人員配置も,その仕事量と比べると圧倒的に余裕がないのが現状だ(六車さんも,人員の不足から介護現場の最前線を経験することになり,そのハードさに驚愕している)。実は多くの介護職員は,状況さえ許せば,心ゆくまで利用者と話をしたいのである。だからそう言いたくなる気持ちはわかる。
しかし今後は六車さんの職場のように,違う業種で積み上げてきたプロのスキルが介護・看護現場で存分に生かせる道を探るべきだと私は思う。現在の多くの職場では,異業種での経験やスキルが生かされることなく,一介護・看護職員としての取り組みを要求される。順調に職場になじめる方もいる一方で,これまではまったく違う環境でゼロからやり直すプレッシャーから実力を発揮できないまま退職する方も少なくない。そんな姿を何人も見送るたびに,その方がもっとケアの現場で生きる働き方はなかったんだろうかと考えずにはいられなかった。
そのような意味からも,六車さんが活躍する場を提供してバックアップした職場環境も,「介護民俗学」という魅力的な学問領域を生み出す大きな原動力となったのだと大いに関心を覚えた。
世に出された本はすべて誤読されると言った編集者がいた。私の読み方は六車さんが伝えたかったこととは違うかもしれない。しかし私は,本書で展開される六車さんの語りに触発され,ケア現場が持つ豊かさと,ケアに関わる仕事の可能性の広さ,自由さにあらためて気づかされた。そして,「ケアとは何か」と“同じ問い”を繰り返す中でしか,その本質は立ち上がってこないだろうと思えてならなかった。