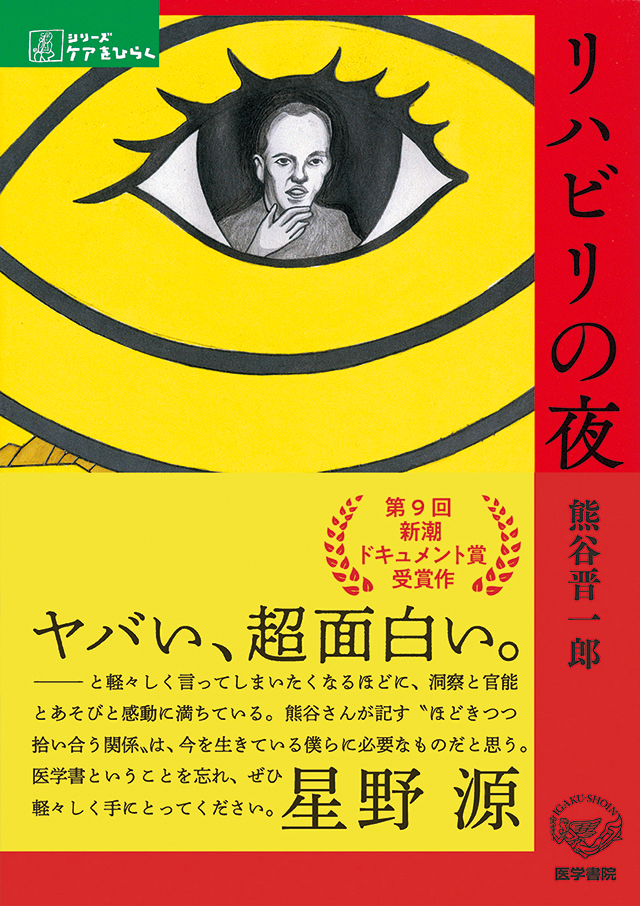食べることと出すこと
食べて出せればOKだ!(けど、それが難しい……。)
もっと見る
「人間なんてしょせん食べて出すだけ」。なるほど。ではそれができなくなったらどうする――個性的なカフカ研究者として知られる著者は、潰瘍性大腸炎という難病に襲われた。食事と排泄という「当たり前」が当たり前でなくなったとき、世界はどう変わったのか? 高カロリー輸液でも癒やせない顎や舌の飢餓感とは? ヨーグルトが口腔内で爆発するとは? 茫然と便の海に立っているときに看護師から雑巾を手渡されたときの気分は? 切実さの狭間に漂う不思議なユーモアが、何が「ケア」なのかを教えてくれる。
| シリーズ | シリーズ ケアをひらく |
|---|---|
| 著 | 頭木 弘樹 |
| 発行 | 2020年08月判型:A5頁:328 |
| ISBN | 978-4-260-04288-8 |
| 定価 | 2,200円 (本体2,000円+税) |
更新情報
-
更新情報はありません。
お気に入り商品に追加すると、この商品の更新情報や関連情報などをマイページでお知らせいたします。
- TOPICS
- 序文
- 目次
- 書評
TOPICS
開く
●『シリーズ ケアをひらく』が第73回毎日出版文化賞(企画部門)受賞!
第73回毎日出版文化賞(主催:毎日新聞社)が2019年11月3日に発表となり、『シリーズ ケアをひらく』が「企画部門」に選出されました。同賞は1947年に創設され、毎年優れた著作物や出版活動を顕彰するもので、「文学・芸術部門」「人文・社会部門」「自然科学部門」「企画部門」の4部門ごとに選出されます。同賞の詳細情報はこちら(毎日新聞社ウェブサイトへ)。
序文
開く
健康の光の衰えとともに姿をあらわす未発見の国々が
いかに驚くばかりか
ヴァージニア・ウルフ(『病むことについて』川本静子=編訳、みすず書房)
はじめに 「食べて出す」ことが、あたりまえでなくなったら?
ごはんとうんち
まだ動画を簡単に撮れる時代ではなかった。唯一残っている祖父の声だ。
「そんなんじゃなくて、もっといいことを言って」と小学生の私は文句を言っている。ごはんとかうんちとか、そんなくだらないことじゃなくて、と思ったのをおぼえている。
しかし、今となってみると、祖父の言ったことは、とても大切なことだった。
その後――祖父はもう亡くなってかなりたっていたが――私はまさに、ちゃんと食べてちゃんと出すことができなくなってしまったのだ。
今あらためて、この言葉を聞くと、まったくちがって聞こえる。
人間の製糞機
(『米朝落語全集 増補改訂版』第三巻、創元社)
くだらない奴ばかりということを、こういうふうに表現している。
人間なんかたいしたものではない、人生なんかたいしたものではないと言いたいときに、「人間なんて、しょせん、食って出すだけの存在だ」というような言い方をよくする。
あるいは逆に、「人間というのは、ただ飯を食って出すだけの存在ではないんだ」というような言い方もする。
いずれにしても、「食って出すだけ」では、つまらないということだ。
食べて出すということに対する軽蔑、軽視が、たいていの人の心の中にはある。少なくとも、それだけでは満足できないという気持ちが。
人間の活動の究極
しかし一方で、人間の生活から、必須ではないものをどんどんそぎ落としていくと、最後に残るのは「食べる・出す・寝る」だろう。
寝るは活動停止だとすると、活動に限れば、食べると出すが残ることになる。
こればっかりは、そぎ落とせない。数日でも「食べる・出す」ことができなくなれば、命にかかわる。
だからこそ、「人間なんて、しょせん、食って出すだけの存在だ」という言い方にもなるのだろう。
人間の活動の究極は、食べることと出すことにある、と言うこともできる。
サバイバル
深沢七郎(『人間滅亡的人生案内』河出書房新社)
人生にあれこれ悩んでいる人に対して、深沢七郎はこう答えている。「ヒって」というのは「排泄して」という意味。
ここにあるのは、人間なんてそれだけのものなんだという虚無感であり、人間の活動の究極はこういうことなんだという根本の提示だ。
しかし、それだけではないだろう。ここには力強さがある。苦しい状況でもなんとか生き残っていこうとする、たくましさが感じられる。
食べて出すことには、生命力、生きる意欲、死なないしぶとさのようなものがある。ひと言で言えば、サバイバルだろうか。
食べて出すことが、うまくできなくなってしまったら?
食べて出すことは、くだらないことであり、人間の活動の究極であり、サバイバルである。
では、その食べて出すことが、うまくできなくなってしまったら、いったいどういうことになるのか?
それをこれから、お話ししてみたいと思う。
目次
開く
第1章 まず何が起きたのか?
第2章 食べないとどうなるのか?
第3章 食べることは受け入れること
第4章 食コミュニケーション――共食圧力
第5章 出すこと
第6章 ひきこもること
第7章 病気はブラック企業
第8章 孤独がもれなくついてくる
第9章 ブラックボックスだから(心の問題にされる)
第10章 めったにないことが起きる/治らないことの意味
あとがき 白石さんとホワイトボード
書評
開く
●新聞で紹介されました
《その貰い事故のような生の途上で、言葉をフックとして、杖として、梃子として生き延びる処方箋が総体として浮かび上がってくるようなのだ。》――大和志保(歌人)
(『図書新聞』2020年11月21日より)
《二ページに一つ、ひょっとしたら一ページに一つ、「そうだったのか!」っと思うような記述がある。…中でも白眉は、「出すこと」、特に、潰瘍性大腸炎の症状である下痢について書かれた文章たちだ。》――斎藤真理子(翻訳家)
(『週刊読書人』2020年10月16日より)
《本書の論点の中心は、闘病そのものより、病人を取り巻く社会についてにある。……これらのエピソードから見えてくるのは、「普通」から外れた人が生きづらい社会だ。》――阿古真理(生活史評論家)
(『日本経済新聞』2020年10月10日 読書面より)
《著者は、闘病を通じ、図らずも持ち合わせることになった鋭敏な感覚をもって世の中を見渡し、物事の多様性に目を見開く。そして、人はいろんな事情を抱えて生きていることに思いを致す。〈「想像が及ばないことがあるだろう」という理解〉の大切さ。本書は、他人を思いやる行為が独りよがりなものになってはいないかと問いかけてくる。》――通崎睦美(木琴奏者・随筆家)
(『読売新聞』2020年9月13日 読書面・読売新聞オンラインより)
《病は幸福のハードルを下げ、感度を高める。久しぶりの外出で「風景が後ろに動いていく」ことに驚き、1カ月以上の絶食後のヨーグルトは「味の爆発」、シャワーを浴びては体表を伝う水の流れに感じ入る。闘病してこその深い観察。食事と排泄から見えてくる人間をかみしめた。》――黒沢大陸(朝日新聞大阪編集局長補佐)
(『朝日新聞』2020年9月5日 読書欄・BOOK.asahi.comより)
《医学書を専門に発行している出版社の本とは思えない内容に、目を見張る思いがするのだから不思議だ。哲学的な考察をすら感じられる本である。》
(『日本農業新聞』2021年1月10日「あぜ道書店」より)
《頭木さんは大学生のときに突然、潰瘍性大腸炎を発症した。激しい痛みに襲われ、食事と排泄という当たり前が、当たり前でなくなる。朝起きて痛みがなければ、もうそれだけで幸福感に包まれた日々を近著『食べることと出すこと』(医学書院)につづっている。》
(『読売新聞』編集手帳2020年8月29日より)
《難病の治療によって生じる肉体的存在としての自分の変化、世界の見え方の変容を淡々とつづる文章の行間からは、絶望文学に精通した著者ならではの冷めたユーモアが立ち上る。》
(『産経新聞』2020年8月16日 「本」より)
●雑誌で紹介されました
《なんか、そこはかとなーく、愉快なんです。ものすごく悲惨な症状を描写をしながら、ユーモアを失っていない。》――山田詠美(作家)
(『女性セブン』2021年1月21日号「日々甘露苦露」より)
《そう、病気の苦しみは、頭木さんに別の、大切なものを与えた。健康で強い人間にはわからない、弱い立場の人たちの気持ちがわかるようになっていったのである。》――高橋源一郎(作家)
(『サンデー毎日』2020年12月13 日号より)
《生きることの基本であり、当たり前だったはずの〈食べて出す〉がうまくできなくなると、人はこんなにも弱い存在になって世界の見え方が一変するのだという事実に、しみじみと驚かされる。》――川口晴美(詩人)
(『婦人公論』12月22日/1月4日合併号より)
《読後、古い眼鏡のレンズの曇りをゴシゴシ拭いた気分になった。わかり合うには「自分の知っていることはそんなに多くない」と心を開くこと、と思えたのも、この本の効用である。》――浅生ハルミン(イラストレーター)
(『母の友』2020年12月号より)
《食べる、という行為は、楽しいこと、明るいことずくめのように語られがちだ。でも、それだけじゃない。『食べることと出すこと』には、食べることのダークサイドがきっちりえがかれている。》――木村衣有子(文筆家)
(『週刊文春』2020年10月8日号より)
●ラジオで紹介されました
《とにかく口で何か噛みたくなる! 噛みたいっていうのよく分かる。私も歯が悪いんでね。部分入れ歯なんですが、なんか噛みたいのね、固いものを。あのサクサクって骨に響く音は生きている実感なんだよね。》――武田鉄矢(俳優・歌手)
(「武田鉄矢 今朝の三枚おろし」 頭木弘樹著『食べること出すこと』2021年2月15〜19日より)
読めば身体が変わる,食べること・病めることのリアル
書評者:太田 充胤(内分泌代謝内科医・批評家)
書評を見る閉じる
生活習慣病領域の診療を通じて,常々「食べること」の複雑さを実感している。
われわれは一見みな同じように食べているが,ほんとうは食べ物を選んでいるときや食べているとき,人によってぜんぜん違うことを考えたり感じたりしている。なんの病気もない人と,病気を抱えた人ではさらに違う。「食べること」が苦痛に直結するような病気ならば尚更だ。
同じヒトでも一人ひとり違う食行動の環世界をつぶさに描いた本が読んでみたいと,ずっと思っていた。そして,「ケアをひらく」シリーズの新刊『食べることと出すこと』は,まさしくそういう本なのである。
著者の頭木弘樹氏は,20歳のときに潰瘍性大腸炎を発症し,若くして入院治療を繰り返す。長期間の絶飲食を経てふたたび食べられるようになった感動もつかの間,頭木氏を待っていたのは綱渡りのような食生活だった。
何を選んで食べるかが腹痛や下痢に直結する病態,ステロイドによる易感染性とみえない病原体への恐怖……こうして頭木氏は,口に入れるもの全てを慎重に吟味し,絶えず下痢の恐怖に苛まれる人生へと足を踏み出す。
恐ろしいことに,問題は「食べること」と「出すこと」にとどまらない。これらの営みに問題を抱える者は,これらをつつがなく営むことを前提とした文化や社会になじまないからだ。
他人と一緒に同じものを食べられない。そして他人の前で「出す」わけにはいかない。公共空間で共有されるべき食の営みが共有不可能になり,私秘的空間で営まれるべき排泄が公共空間に引きずり出されてしまう絶望。
頭木氏は発症後しばらくの間,ずっと自宅で引きこもっていたという。当たり前である。こうして公私が捩じれてしまうような状況に置かれたら,誰だってそうするしかないような気がする。
頭木氏は主にカフカを専門とする文学紹介者で,『絶望名人カフカの人生論』(新潮社,2014)に始まる「絶望」シリーズで知られている。カフカといえば『変身』……とつないでもよいが,「食べられない」で思い起こされるのはやはり『断食芸人』のほうだ。
断食芸人は餓死する間際にこう言った。「私はうまいと思う食べ物を見つけることができなかった」。
もし見つけられていたら,みんなと同じようにたらふく食べることができただろうか。その孤独を,そしてカフカ自身の生きづらさを,頭木氏は身体のレベルで理解し,根の生えた言葉で語る。なんの病気もない読み手にとっては,こういう言葉に触れて初めて見えてくるカフカ文学の地平があり,病めることのリアルがある。
医療者は,基本的には診療の中でしか病人を診られないし,症状でしか病気を把握できない。しかし実際には,病人は絶え間なく「病んでいる」ことを強いられる。人生の99%は診療の外で営まれるし,症状のない時間もまた病気なのである。
医療者は読みながら耳の痛い思いをすることになるが,読めば身体が変わる。そんな一冊。
「想像する」と、その限界と
書評者:初川 久美子(東京都公立学校スクールカウンセラー/臨床心理士・公認心理師)
書評を見る閉じる
ものすごい本と出会ってしまった。この本を読んで私が最初に思ったのはこれだった。
著者の頭木弘樹さんは20歳のときに潰瘍性大腸炎という難病に襲われ、「食べることと出すこと」が普通にできなくなってしまう。しかし、できなくなったのはそれだけではなかった。病気の発症時からコロナ禍の現在に至るまで、頭木さんが経験し、感じ、考えたこと。それがさまざまな文学作品の引用や軽妙な語り口によって、とてもおもしろく、受け取りやすい形に結実している。
「経験しないとわからない」という壁
この本には、読了した人と話し合ってみたい味わい深いテーマがいくつもある。ここでは「経験しないとわからない」という壁について考えてみる。
私は臨床心理士である。クライエントの話を聴くことがすべての始まりとなる。カウンセラーはクライエントとまったく同じ経験をしたということはもちろんない。カウンセラーがクライエントの話を共感的に聴き、受容できるのは、自らが経験をしているからではなく、いわゆる専門性と呼ばれる技術の研鑽や知見の蓄積の結果、そういう営みが成立している。だから、同じ経験をしていなくても援助ができるのだ。
しかし、この本を読んで、そこが揺らいだ。
「経験しないとわからない」という壁を前に閉じてしまうと、経験していない人との間に断絶が生じる。だから頭木さんは自らの経験をきわめて丁寧に言語化して、それを経験していない人がどうにかその壁を越え、経験した人へ思いを馳せるための糸口をさまざまに語っている。
はじめはこの病気そのものについての経験から。しかしそこで留まらない。次に患者という視点から見える周りの人のあり方について。さらには、自身や周囲の人を含め、世界全体の見え方について。こうして経験によって見えてきた新たな気づきを語っている。病を抱えることで、こうも世界の見え方が変わり、気づくところ、感じるところが変わるものなのか。
圧倒され、揺らいでしまう……
このことはもちろん心理職として頭では当然理解していたことである。しかし、気持ちという次元を超え、世界の見え方までも、こんなにもこれまでとは違う文脈が生まれてくるのだということに単純に圧倒された。
私は、ここまでの奥行きをもってクライエントに思いを馳せることができていたのだろうか。そこに何か事情があるのでは、とわずかな「ためらい」があるだけでよいと頭木さんは語る。それも心理職の得意技であるが、自分の「ためらい」度合いはここまで深いものだったろうか。思わず揺らいでしまう。
想像が及ばないこともある
また、折々に引用される文学作品等の一節を読むと、この病気を発症した頭木青年が文学にのめりこみ、その中で描かれる絶望に救いを得ていたこと、そして、「困難があったけど見事に復活して勝つ」というよくある物語ではない物語を探していた姿が思い浮かぶ。これまた心理職として感じ入るところがある。
もし私が担当カウンセラーとして出会っていたら、私にいったい何ができたであろうか。
想像する、思いを馳せる。でも「想像が及ばないこともある」――
最後に頭木さんはそう語る。思いを馳せるのは心理職にとって呼吸みたいなものだが、どれだけ想像をしても「想像が及ばないこともある」。頭木さんがそう語ることの重さ・深さが、逆に私にとっては救済の意味合いを持って感じられる。精進しよう、そう思わされる。
これは単に潰瘍性大腸炎の話だけではない。対人援助に携わる方々に、ぜひお読みいただきたい。