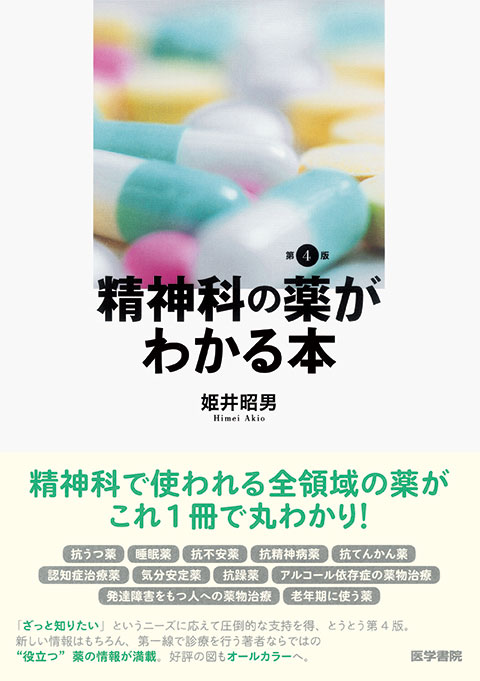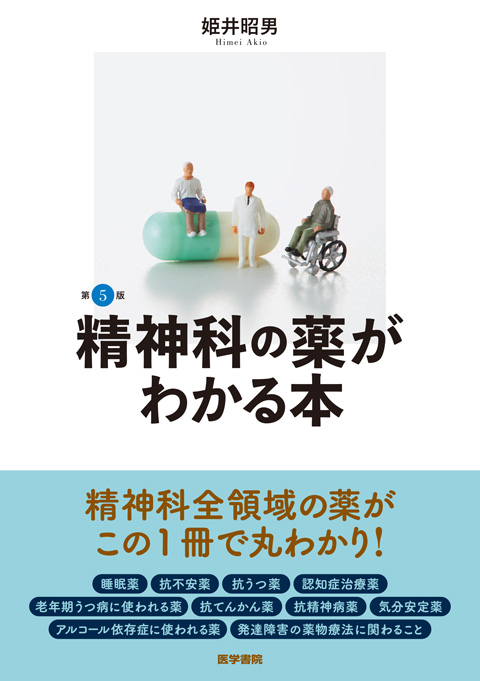精神科の薬がわかる本 第4版
精神科の薬を“ざっと”知りたいあなたへ
もっと見る
好評定番書の内容改訂&オールカラー化!「精神科の薬を取り巻く環境の変化や新薬を、著者の臨床実践を基に追加」というコンセプトはそのままに、よりわかりやすく見やすく紙面を刷新。社会背景とともに変わっていく薬の評価や役割。氾濫する情報にまどわされないためにも、医療職だけでなく精神科の薬にかかわるすべての人が手元に置いておきたい1冊。
| 著 | 姫井 昭男 |
|---|---|
| 発行 | 2019年01月判型:A5頁:228 |
| ISBN | 978-4-260-03830-0 |
| 定価 | 2,420円 (本体2,200円+税) |
- 販売終了
更新情報
-
更新情報はありません。
お気に入り商品に追加すると、この商品の更新情報や関連情報などをマイページでお知らせいたします。
- 序文
- 目次
序文
開く
第4版によせて あらゆる人にとって、必要最小限の、間違いのない知識を
「精神科」を受診するハードルは、この10年で格段に下がったと感じます。それは、精神疾患に対する差別意識が解消されてきたことの表れでもあり、ようやく精神科医療も欧米に近い環境が整い始めたという印象です。しかしながら、精神科での治療内容を相談できる第三者的な場はまだ少なく、インターネットから情報を収集することが多いために、新たな問題も生じてきています。
第3版を執筆していた頃すでに、処方薬の情報の氾濫が問題となり始めていました。多くは、新薬の改良された部分のみが誇張され、“本来の機能以上の期待を持たれる”ことで臨床現場が困惑するという問題でした。しかし最近の問題は、個人の服薬の印象がブログという形で伝えられ、中にはステルスマーケティング(消費者に宣伝と気づかれないように行う宣伝行為)とも思われるものがあること、逆に、ある製剤に事実無根の有害事象が存在するかのような情報発信がなされていることです。
薬の評価をブログで情報発信することは自由です。また、「精神科の薬」を服用した人が感じた薬剤の印象を知ることは治療学的にも有用なことだと考えています。ただ、誰もが閲覧できるインターネット上で薬の情報を得るときには、「発信者が、本当に適切な評価ができる環境にあるのか」がわからないのです。
薬理学的に正しく処方されたものを、服用指示を守って服用した上での評価なのか。あるいは、その薬の服用を本当に必要とする人が服用したものなのか(診立てを誤った医師が選択した薬剤を服用させられた結果ではないか)という点が明確でなければ、正しい評価とはいえません。そういった“背景がわからない精神科の薬の情報や評価”は、あくまで参考程度にしなければならないのですが、インターネットの世界では、“閲覧数の多い”ブログが信用されてしまう傾向にあるのです。
今日、治療を受ける側も適正で適切な医療を受けているかどうかを知るために、医学情報をある程度は身につけておくことが必要な時代になっています。しかしながら精神医学は、未だに解明されていない部分も多く、またどんな「精神科の薬」であってもメンタル疾患を根治できる薬剤ではなく、症状を改善させるためのものにすぎません。
本書の初版を作成する際、本書の役割は「医療職、とくに精神科薬物療法の初学者向けに、わかりやすく薬のことを理解してもらうこと」でした。版を重ねた現在の役割は、「あらゆる人にとって、精神科の薬の必要最小限の、間違いのない知識を伝えること」であると感じています。
今回の改訂においても、正しい情報を可能なかぎり平易に解説することに努めました。たとえ最新の医学研究論文の知見が発表されていたとしても、現時点で評価の定まっていない内容は記載していません。また一般論として定着していることであっても、著者が実際に臨床経験で確かに得られた効果(再現性も含め)、有害事象(副作用)、注意したい点に基づいて構成しました。
さらに、これまで『精神科の薬がわかる本』をお読みいただいた方々から頂いた意見や質問を参考に情報を追記し、新しい章や項目を設け、わかりやすさをさらに重視して改訂しました。
「作り手と読み手によって作られた本」と呼ばれるようになれば、望外の喜びです。
2018年12月
姫井昭男
「精神科」を受診するハードルは、この10年で格段に下がったと感じます。それは、精神疾患に対する差別意識が解消されてきたことの表れでもあり、ようやく精神科医療も欧米に近い環境が整い始めたという印象です。しかしながら、精神科での治療内容を相談できる第三者的な場はまだ少なく、インターネットから情報を収集することが多いために、新たな問題も生じてきています。
第3版を執筆していた頃すでに、処方薬の情報の氾濫が問題となり始めていました。多くは、新薬の改良された部分のみが誇張され、“本来の機能以上の期待を持たれる”ことで臨床現場が困惑するという問題でした。しかし最近の問題は、個人の服薬の印象がブログという形で伝えられ、中にはステルスマーケティング(消費者に宣伝と気づかれないように行う宣伝行為)とも思われるものがあること、逆に、ある製剤に事実無根の有害事象が存在するかのような情報発信がなされていることです。
薬の評価をブログで情報発信することは自由です。また、「精神科の薬」を服用した人が感じた薬剤の印象を知ることは治療学的にも有用なことだと考えています。ただ、誰もが閲覧できるインターネット上で薬の情報を得るときには、「発信者が、本当に適切な評価ができる環境にあるのか」がわからないのです。
薬理学的に正しく処方されたものを、服用指示を守って服用した上での評価なのか。あるいは、その薬の服用を本当に必要とする人が服用したものなのか(診立てを誤った医師が選択した薬剤を服用させられた結果ではないか)という点が明確でなければ、正しい評価とはいえません。そういった“背景がわからない精神科の薬の情報や評価”は、あくまで参考程度にしなければならないのですが、インターネットの世界では、“閲覧数の多い”ブログが信用されてしまう傾向にあるのです。
今日、治療を受ける側も適正で適切な医療を受けているかどうかを知るために、医学情報をある程度は身につけておくことが必要な時代になっています。しかしながら精神医学は、未だに解明されていない部分も多く、またどんな「精神科の薬」であってもメンタル疾患を根治できる薬剤ではなく、症状を改善させるためのものにすぎません。
本書の初版を作成する際、本書の役割は「医療職、とくに精神科薬物療法の初学者向けに、わかりやすく薬のことを理解してもらうこと」でした。版を重ねた現在の役割は、「あらゆる人にとって、精神科の薬の必要最小限の、間違いのない知識を伝えること」であると感じています。
今回の改訂においても、正しい情報を可能なかぎり平易に解説することに努めました。たとえ最新の医学研究論文の知見が発表されていたとしても、現時点で評価の定まっていない内容は記載していません。また一般論として定着していることであっても、著者が実際に臨床経験で確かに得られた効果(再現性も含め)、有害事象(副作用)、注意したい点に基づいて構成しました。
さらに、これまで『精神科の薬がわかる本』をお読みいただいた方々から頂いた意見や質問を参考に情報を追記し、新しい章や項目を設け、わかりやすさをさらに重視して改訂しました。
「作り手と読み手によって作られた本」と呼ばれるようになれば、望外の喜びです。
2018年12月
姫井昭男
目次
開く
1 「抗うつ薬」がわかる。
1 「うつ」の薬による治療
2 「抗うつ薬」の特徴と副作用
3 薬の知識を活かした助言
抗うつ薬へのQ&A
2 「睡眠薬」と「抗不安薬」がわかる。
1 マイナートランキライザーとは
2 「睡眠薬」がわかる
3 「抗不安薬」がわかる
睡眠薬へのQ&A
Lecture ベンゾジアゼピン系薬剤の安全な止め方
3 「抗精神病薬」がわかる。
1 統合失調症とは
2 定型抗精神病薬の特徴
3 非定型抗精神病薬の特徴
4 重大な副作用
5 剤形による特徴
抗精神病薬へのQ&A
Lecture 単剤化の方法
4 「抗てんかん薬」がわかる。
1 薬によるてんかんの治療
2 知っておきたい注意点
抗てんかん薬へのQ&A
5 「認知症治療薬」がわかる。
1 認知症のタイプと治療
2 認知症(アルツハイマー型認知症)の治療薬
認知症治療薬へのQ&A
6 「老年期に使う薬」がわかる。
1 薬を処方する前に気をつけておきたいこと
2 パーキンソン病の治療薬
3 うつ病・抑うつ状態の治療薬
4 頭部外傷の後遺症の治療薬
5 夜間せん妄の治療薬
6 代謝性意識障害への対処
7 「その他の精神科の薬」がわかる。
1 不眠症治療薬
2 気分安定薬
3 抗躁薬
4 アルコール依存症の薬物療法
5 悪性症候群の治療薬
6 発達障害をもつ人への薬物療法
その他の精神科の薬へのQ&A
あとがき
索引
Plus one
SSRI、SNRI、NaSSAの薬理作用
超高齢社会における抗うつ薬処方の注意点
抗うつ作用をもつその他の薬
うつ病の拡大診断の弊害
慢性疼痛と抗うつ薬
催眠薬エスゾピクロン
睡眠薬開発は副作用との闘いだった
ドーパミン“過剰”説と、グルタミン酸“低下”説
抗精神病薬の多剤併用の問題
抗てんかん薬の薬理作用
てんかん発作を誘発する負荷因子について
アセチルコリン分解酵素阻害薬の薬理作用
グルタミン酸NMDA受容体拮抗薬の薬理作用
パーキンソン病治療薬の薬理作用
双極性障害II型という診断名の増加について
炭酸リチウムの薬理作用(仮説)
アルコール摂取によるグルタミン酸神経系とGABA神経系への影響
グルタミン酸神経系とGABA神経系の力関係
1 「うつ」の薬による治療
2 「抗うつ薬」の特徴と副作用
3 薬の知識を活かした助言
抗うつ薬へのQ&A
2 「睡眠薬」と「抗不安薬」がわかる。
1 マイナートランキライザーとは
2 「睡眠薬」がわかる
3 「抗不安薬」がわかる
睡眠薬へのQ&A
Lecture ベンゾジアゼピン系薬剤の安全な止め方
3 「抗精神病薬」がわかる。
1 統合失調症とは
2 定型抗精神病薬の特徴
3 非定型抗精神病薬の特徴
4 重大な副作用
5 剤形による特徴
抗精神病薬へのQ&A
Lecture 単剤化の方法
4 「抗てんかん薬」がわかる。
1 薬によるてんかんの治療
2 知っておきたい注意点
抗てんかん薬へのQ&A
5 「認知症治療薬」がわかる。
1 認知症のタイプと治療
2 認知症(アルツハイマー型認知症)の治療薬
認知症治療薬へのQ&A
6 「老年期に使う薬」がわかる。
1 薬を処方する前に気をつけておきたいこと
2 パーキンソン病の治療薬
3 うつ病・抑うつ状態の治療薬
4 頭部外傷の後遺症の治療薬
5 夜間せん妄の治療薬
6 代謝性意識障害への対処
7 「その他の精神科の薬」がわかる。
1 不眠症治療薬
2 気分安定薬
3 抗躁薬
4 アルコール依存症の薬物療法
5 悪性症候群の治療薬
6 発達障害をもつ人への薬物療法
その他の精神科の薬へのQ&A
あとがき
索引
Plus one
SSRI、SNRI、NaSSAの薬理作用
超高齢社会における抗うつ薬処方の注意点
抗うつ作用をもつその他の薬
うつ病の拡大診断の弊害
慢性疼痛と抗うつ薬
催眠薬エスゾピクロン
睡眠薬開発は副作用との闘いだった
ドーパミン“過剰”説と、グルタミン酸“低下”説
抗精神病薬の多剤併用の問題
抗てんかん薬の薬理作用
てんかん発作を誘発する負荷因子について
アセチルコリン分解酵素阻害薬の薬理作用
グルタミン酸NMDA受容体拮抗薬の薬理作用
パーキンソン病治療薬の薬理作用
双極性障害II型という診断名の増加について
炭酸リチウムの薬理作用(仮説)
アルコール摂取によるグルタミン酸神経系とGABA神経系への影響
グルタミン酸神経系とGABA神経系の力関係
更新情報
-
更新情報はありません。
お気に入り商品に追加すると、この商品の更新情報や関連情報などをマイページでお知らせいたします。