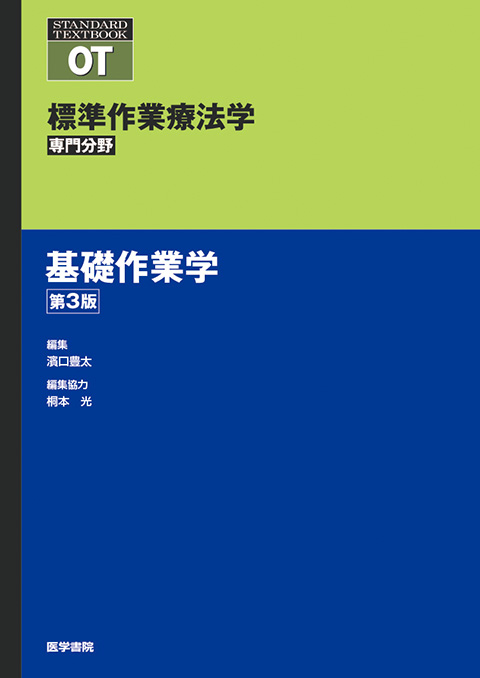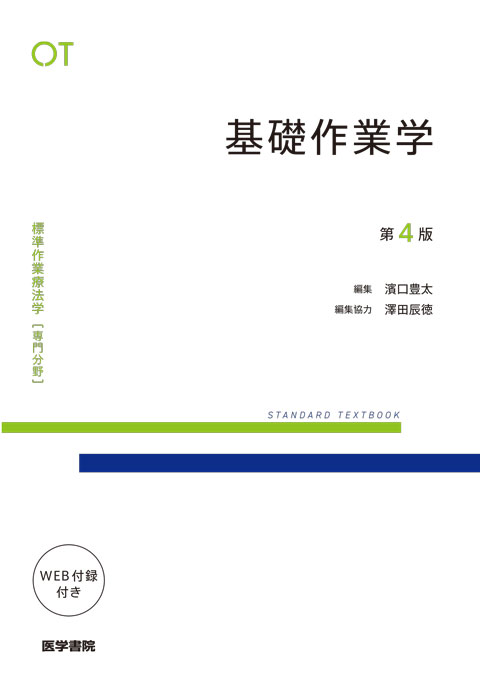基礎作業学 第3版
作業を治療として用いるために必要な作業療法の基礎を学べるテキスト、待望の改訂版!
もっと見る
作業療法士は、人間がなす「作業」を治療に用いている(=作業療法)。本巻では、まず作業療法の基礎が理解できるよう、作業療法の理論や作業の分類を紹介している。また、人間の行動を“身体”と“心理”という大きな2つの側面から捉える構成とし、そこから「作業」を治療に持ち込むための仕組みを学ぶことができる。また各章末には、作業療法で作業を用いるというのはどのようなことか体験できる各種演習課題を用意している。
*「標準作業療法学」は株式会社医学書院の登録商標です。
| シリーズ | 標準作業療法学 専門分野 |
|---|---|
| シリーズ監修 | 矢谷 令子 |
| 編集 | 濱口 豊太 |
| 編集協力 | 桐本 光 |
| 発行 | 2017年10月判型:B5頁:232 |
| ISBN | 978-4-260-03055-7 |
| 定価 | 4,400円 (本体4,000円+税) |
- 販売終了
更新情報
-
更新情報はありません。
お気に入り商品に追加すると、この商品の更新情報や関連情報などをマイページでお知らせいたします。
- 序文
- 目次
序文
開く
第3版 序
人間の生活は人間がなす「作業」の集合である.人間の所作が有形または無形の表象として「作業」となっている.人間の所作は言語や物を介して他覚できるため,継承可能なものである.人間は生存するために考え,物をつくり,生活に備えて「作業」を経済性につなげ,職業,趣味,芸術などへと意味づけしてきた.作業療法士はこの作業を治療に用いている.本書は次の5つに主眼をおいた.
1.作業療法を知るために
作業を治療として用いるには,主体として活動する人間と人間がなす作業をよく知ることが必要である.第1章では作業する人間と人間以外の部分とを分けた.作業する人間と,作業を工程や道具のような物理環境とに分けてみることにより,作業療法の基礎を考察している.
本書では作業を用いて療法となすための理論を紹介し,作業療法の役割について学ぶことができる.理論を読み終えたら,作業療法で作業を用いることとはどのようなものかを体験するための演習課題を設けているので,身近にある作業を題材にしながら学習に役立てていただきたい.
対象者に作業療法を行うとき,そのはじめに作業の選択がなされる.対象者が必要としている作業が何であるかを知るためには,対象者との対話が必要である.疾病や障害のある人たちの身体と心理にかかわる作業療法の入口で,対象者と対話する基礎的な技術も学んでおこう.
2.身体と心理とに分けて
作業を行う人間がその行動によって得られる効能には身体と心理の機序がある.デカルト(René Descartes,1596~1650年.哲学者,数学者)の心身二元論を待つまでもなく,人間の心身は分割して存在することが適わないが,本書では作業と人間とを身体と心理に分けて解説する.
第2章では,作業が人間の身体に与える影響を学ぶために,運動学と運動生理学の視座から作業と人体について解説している.解剖学で分けられた運動器が人間の生活の中でどのように作用しているのか理解するためには,運動学または神経生理学の基礎を理解する必要がある.身体が動的能力を発揮するには生体の運動エネルギーが求められる.呼吸と循環,加齢と発達など運動生理学の観点からも人間と作業との関係を学んでおこう.
また,本書では作業が人体に作用して身体活動を支援する技術であることを体験学習するために,身体機能の基礎作業学演習を設けている.運動学と運動生理学の治療的応用について,筋電図のような特殊な機材を用いて実験すること,あるいはそれらを用いなくても人間の動作を観察して推量することなどから,作業が身体機能にもたらす影響について考えてみたい.
3.作業を誘発し継続させるための心理
作業療法は対象者に対し作業を手段として用い,身体ならびに精神の治癒を促し,生活を営んでいくための支援技術でもある.作業を行う人間の身体機能の基礎を運動学と神経生理学を通して理解したならば,次は作業の心理的作用,つまり作業を開始させ継続させるための支援について考えてみよう.
第3章では,人間が作業を行うときに振る舞う心理について解説している.行動学習の理論には,パブロフの犬の実験に代表されるオペラント条件づけやレスポンデント条件づけがあり,行動制御理論は作業療法学の基礎でもある.
人間は行動を学習することで自らの生活にとって有効だと思うことを再現しようとする.行動学習の理論は,作業療法士が対象者に対峙するとき,生来の発達理論はもとより,人生のなかで課題として身につけて生活していく心理神経学的解釈をも含めて作業療法について説明ができる強力な学術基盤である.
4.生活期と作業
人間は生まれてから死ぬまでの間にいくつかの生活期(ライフステージ)を経る.生活の様式はそこで育まれた人々の文化に従いながら,身体と心理の発達過程に臨界期を感じ,個体もしくは集団としてふさわしい形態をなす.
個体が形成した習慣,集団に形成された慣習,生活する国や地域が形成した文化など,それぞれに作業が含まれている.多様な人間の生活期を解説するには紙幅が足りないが,第4章では人間の発達過程と高齢期の時間軸に課題をみつけ,その支援を行う作業療法の基本的姿勢について紹介を試みた.
5.作業療法の基礎がわかったなら
作業の概念と作業療法の理論を知り,作業をする人間に生じる体と心の振る舞いをとらえることができたなら,あなたは作業療法の対象となる人たちにその理論や心身相関がどのように作業療法に用いられているのか伝えられるだろうか.そして,作業療法の一部である基礎作業学を礎にして,自らの臨床と研究の発展に資する座標に本書がなっているかどうか,あなたたちと意見を交わしてみたい.
作業療法は他の治療法と同じように対象者の身体または精神に作用するものであり,対象者の心身に作業の効能がなくとも社会からみた効果を求めることもできる.それらの作用には機序がある.このことを理解するために解剖学,運動学,心理学,社会科学の成書を傍らに置こう.本書は人間と作業を治療法としての機構に見立て,その学ぶべき一端を著したものである.
2017年9月
濱口 豊太
人間の生活は人間がなす「作業」の集合である.人間の所作が有形または無形の表象として「作業」となっている.人間の所作は言語や物を介して他覚できるため,継承可能なものである.人間は生存するために考え,物をつくり,生活に備えて「作業」を経済性につなげ,職業,趣味,芸術などへと意味づけしてきた.作業療法士はこの作業を治療に用いている.本書は次の5つに主眼をおいた.
1.作業療法を知るために
作業を治療として用いるには,主体として活動する人間と人間がなす作業をよく知ることが必要である.第1章では作業する人間と人間以外の部分とを分けた.作業する人間と,作業を工程や道具のような物理環境とに分けてみることにより,作業療法の基礎を考察している.
本書では作業を用いて療法となすための理論を紹介し,作業療法の役割について学ぶことができる.理論を読み終えたら,作業療法で作業を用いることとはどのようなものかを体験するための演習課題を設けているので,身近にある作業を題材にしながら学習に役立てていただきたい.
対象者に作業療法を行うとき,そのはじめに作業の選択がなされる.対象者が必要としている作業が何であるかを知るためには,対象者との対話が必要である.疾病や障害のある人たちの身体と心理にかかわる作業療法の入口で,対象者と対話する基礎的な技術も学んでおこう.
2.身体と心理とに分けて
作業を行う人間がその行動によって得られる効能には身体と心理の機序がある.デカルト(René Descartes,1596~1650年.哲学者,数学者)の心身二元論を待つまでもなく,人間の心身は分割して存在することが適わないが,本書では作業と人間とを身体と心理に分けて解説する.
第2章では,作業が人間の身体に与える影響を学ぶために,運動学と運動生理学の視座から作業と人体について解説している.解剖学で分けられた運動器が人間の生活の中でどのように作用しているのか理解するためには,運動学または神経生理学の基礎を理解する必要がある.身体が動的能力を発揮するには生体の運動エネルギーが求められる.呼吸と循環,加齢と発達など運動生理学の観点からも人間と作業との関係を学んでおこう.
また,本書では作業が人体に作用して身体活動を支援する技術であることを体験学習するために,身体機能の基礎作業学演習を設けている.運動学と運動生理学の治療的応用について,筋電図のような特殊な機材を用いて実験すること,あるいはそれらを用いなくても人間の動作を観察して推量することなどから,作業が身体機能にもたらす影響について考えてみたい.
3.作業を誘発し継続させるための心理
作業療法は対象者に対し作業を手段として用い,身体ならびに精神の治癒を促し,生活を営んでいくための支援技術でもある.作業を行う人間の身体機能の基礎を運動学と神経生理学を通して理解したならば,次は作業の心理的作用,つまり作業を開始させ継続させるための支援について考えてみよう.
第3章では,人間が作業を行うときに振る舞う心理について解説している.行動学習の理論には,パブロフの犬の実験に代表されるオペラント条件づけやレスポンデント条件づけがあり,行動制御理論は作業療法学の基礎でもある.
人間は行動を学習することで自らの生活にとって有効だと思うことを再現しようとする.行動学習の理論は,作業療法士が対象者に対峙するとき,生来の発達理論はもとより,人生のなかで課題として身につけて生活していく心理神経学的解釈をも含めて作業療法について説明ができる強力な学術基盤である.
4.生活期と作業
人間は生まれてから死ぬまでの間にいくつかの生活期(ライフステージ)を経る.生活の様式はそこで育まれた人々の文化に従いながら,身体と心理の発達過程に臨界期を感じ,個体もしくは集団としてふさわしい形態をなす.
個体が形成した習慣,集団に形成された慣習,生活する国や地域が形成した文化など,それぞれに作業が含まれている.多様な人間の生活期を解説するには紙幅が足りないが,第4章では人間の発達過程と高齢期の時間軸に課題をみつけ,その支援を行う作業療法の基本的姿勢について紹介を試みた.
5.作業療法の基礎がわかったなら
作業の概念と作業療法の理論を知り,作業をする人間に生じる体と心の振る舞いをとらえることができたなら,あなたは作業療法の対象となる人たちにその理論や心身相関がどのように作業療法に用いられているのか伝えられるだろうか.そして,作業療法の一部である基礎作業学を礎にして,自らの臨床と研究の発展に資する座標に本書がなっているかどうか,あなたたちと意見を交わしてみたい.
作業療法は他の治療法と同じように対象者の身体または精神に作用するものであり,対象者の心身に作業の効能がなくとも社会からみた効果を求めることもできる.それらの作用には機序がある.このことを理解するために解剖学,運動学,心理学,社会科学の成書を傍らに置こう.本書は人間と作業を治療法としての機構に見立て,その学ぶべき一端を著したものである.
2017年9月
濱口 豊太
目次
開く
1 作業と治療を理解するために
GIO,SBO,修得チェックリスト
I 作業療法の成り立ち
A 人間と作業
1 リハビリテーションと作業療法
2 人間にある自然の力
3 作業療法の科学性
4 作業と治療の理解
5 作業療法の根拠
6 作業療法の計画と記録
B 作業の分類
1 作業の種類と分類
2 作業の意味・形態・機能
3 作業を名義的に分けてみる
4 作業と道具
5 ライフステージと社会生活の作業
C 作業療法の理論とその役割
1 作業療法理論の特徴と種類
2 人間作業モデル(MOHO)
3 カナダ作業遂行モデル(CMOP)
4 作業療法介入プロセスモデル(OTIPM)
5 作業科学
6 作業療法理論をとりまく状況
II 作業療法士に必要なコミュニケーションスキル
A 対象者の心理を知る
B 対象者が処理する障害心理
C 心理的外傷と外傷後成長
D 心理的支援
E 対象者の感情を探索して共感するスキル
F 作業療法の方針を話し合うスキル
III 作業療法の体験
A コミュニケーションスキルの演習
1 課題解説とワークシート
2 フィードバックと学習課題
B 作業,物づくりの課題解説
1 くす玉づくりの体験
2 くす玉づくりから作業療法を考える
C 作業,物づくりの演習ワークシート
本章のキーワード
2 作業と運動生理機能
GIO,SBO,修得チェックリスト
I 作業と運動学
A 作業時に働く力と作用
1 力とは
2 動作と相互に作用する力
3 日常生活活動で使う用具と力
4 支持基底面と重心
B 作業時の筋活動と関節運動
1 骨格筋の構造と筋出力のメカニズム
2 日常生活で必要な筋収縮様式と筋力
3 日常生活で生じる関節運動パターン
4 日常生活活動の解析
C 運動を作業療法に応用するには
1 姿勢を保持する方法
2 立ち上がり動作
3 リーチ動作
D 運動を作業療法に応用した事例
1 事例1
2 事例2
II 作業と神経生理学
A 作業と筋電図
1 表面筋電図とは
2 日常生活活動における表面筋電図の記録と解釈
B 作業とニューロリハビリテーション
1 ニューロリハビリテーションの理解に必要な基礎知識
2 運動イメージ+ブレイン・マシン・インターフェイス(BMI)
3 集中的作業療法による「学習された不使用」の改善
4 非侵襲的脳刺激を併用したニューロリハビリテーション
III 基礎作業学演習
A 運動・生理学的テクニックを用いた作業療法学演習
1 演習課題名:立ち上がり動作の観察
2 演習課題名:重心移動と体幹の運動の観察
3 演習課題名:リーチ動作の観察
B 神経生理学の応用
1 電気工作で実験用具を作製する
2 日常生活活動や作業時の筋活動量を知る
3 運動反応時間を計測する
本章のキーワード
3 作業と心理
GIO,SBO,修得チェックリスト
I 作業と心理学
A 作業を学習するための理論
1 人が自発的に行動するためには-オペラント条件づけ
2 人間の行動を誘発するためには-レスポンデント条件づけ
3 行動学習を利用した作業療法
B 作業を自発的に行い,継続するための理論
1 行動とは
2 行動を誘発する刺激のしかた-先行刺激
3 行動を継続させる刺激のしかた-後続刺激
C 行動学習の方法
1 分化強化-望ましい行動を増やし,望ましくない行動を減らすために
2 人間の行動のルール
3 望ましい行動のスケジュール
II 作業の分析
A 作業を分析する手続き
1 作業を測定する
2 行動を誘発する刺激とその準備
3 行動を継続させる刺激とその準備
4 作業を学習したときの効果判定
B 作業の分析と作業療法への応用
1 行動分析の方法
2 作業と精神心理効果
3 精神機能作業療法の分析例
III 行動学習の基礎作業学演習
A 身体機能作業療法への治療応用(演習)
1 演習の目的
2 対象者のプロフィール
3 演習の手順
B 精神機能作業療法への治療応用(演習)
1 演習の目的
2 対象者のプロフィール
3 演習の手順
本章のキーワード
4 ライフステージと作業療法
GIO,SBO,修得チェックリスト
I 発達期と作業
A 作業と人間発達
1 成長と発達
2 発達と感覚統合
3 感覚統合理論にある3つの感覚
4 感覚信号処理と行動発現
B 作業と運動発達
1 運動発達の理論
2 乳幼児期の運動発達
3 運動・姿勢発達の指標
C 知的発達の理論
1 知覚と認知
2 知的発達の理論
D 知的発達と作業課題
1 乳幼児期から青年期
2 前操作的表象の段階
3 具体的操作の段階
4 形式的操作の段階
E 発達過程の作業療法例
1 運動障害児の例
2 作業療法評価
3 作業療法計画と実施
4 発達過程に寄り添う作業療法士
II 青年期と作業
A 作業と人間関係の構築
1 個性の確立
2 人間関係の構築
B 作業と社会とのかかわり
1 人間関係の濃度
2 人の欲求と作業
3 集団に所属する人の作業
C 対象者の人間関係を支援する
1 感情障害の例
2 作業を介して他者への緊張感を弱める
3 作業量を調節して並行した集団に参加する能力を支援する
4 承認欲求に対して支援する
5 現実検討を促す
6 生活に役立つ情報を得る
7 集団生活のなかで自己表現を助ける
8 集団関係技能と作業
III 高齢期と作業
A 高齢期にある役割と作業
1 高齢期の身体
2 高齢期の心理
3 生きがいが保つ生活機能
4 高齢者の役割
B 高齢期の作業療法
1 蓄積された体験の活用
2 高齢期の作業療法例
本章のキーワード
基礎作業学の発展に向けて
A 基礎作業学の起点
B 作業の研究法
C 心身相関
D 社会の一員として
さらに深く学ぶために
索引
GIO,SBO,修得チェックリスト
I 作業療法の成り立ち
A 人間と作業
1 リハビリテーションと作業療法
2 人間にある自然の力
3 作業療法の科学性
4 作業と治療の理解
5 作業療法の根拠
6 作業療法の計画と記録
B 作業の分類
1 作業の種類と分類
2 作業の意味・形態・機能
3 作業を名義的に分けてみる
4 作業と道具
5 ライフステージと社会生活の作業
C 作業療法の理論とその役割
1 作業療法理論の特徴と種類
2 人間作業モデル(MOHO)
3 カナダ作業遂行モデル(CMOP)
4 作業療法介入プロセスモデル(OTIPM)
5 作業科学
6 作業療法理論をとりまく状況
II 作業療法士に必要なコミュニケーションスキル
A 対象者の心理を知る
B 対象者が処理する障害心理
C 心理的外傷と外傷後成長
D 心理的支援
E 対象者の感情を探索して共感するスキル
F 作業療法の方針を話し合うスキル
III 作業療法の体験
A コミュニケーションスキルの演習
1 課題解説とワークシート
2 フィードバックと学習課題
B 作業,物づくりの課題解説
1 くす玉づくりの体験
2 くす玉づくりから作業療法を考える
C 作業,物づくりの演習ワークシート
本章のキーワード
2 作業と運動生理機能
GIO,SBO,修得チェックリスト
I 作業と運動学
A 作業時に働く力と作用
1 力とは
2 動作と相互に作用する力
3 日常生活活動で使う用具と力
4 支持基底面と重心
B 作業時の筋活動と関節運動
1 骨格筋の構造と筋出力のメカニズム
2 日常生活で必要な筋収縮様式と筋力
3 日常生活で生じる関節運動パターン
4 日常生活活動の解析
C 運動を作業療法に応用するには
1 姿勢を保持する方法
2 立ち上がり動作
3 リーチ動作
D 運動を作業療法に応用した事例
1 事例1
2 事例2
II 作業と神経生理学
A 作業と筋電図
1 表面筋電図とは
2 日常生活活動における表面筋電図の記録と解釈
B 作業とニューロリハビリテーション
1 ニューロリハビリテーションの理解に必要な基礎知識
2 運動イメージ+ブレイン・マシン・インターフェイス(BMI)
3 集中的作業療法による「学習された不使用」の改善
4 非侵襲的脳刺激を併用したニューロリハビリテーション
III 基礎作業学演習
A 運動・生理学的テクニックを用いた作業療法学演習
1 演習課題名:立ち上がり動作の観察
2 演習課題名:重心移動と体幹の運動の観察
3 演習課題名:リーチ動作の観察
B 神経生理学の応用
1 電気工作で実験用具を作製する
2 日常生活活動や作業時の筋活動量を知る
3 運動反応時間を計測する
本章のキーワード
3 作業と心理
GIO,SBO,修得チェックリスト
I 作業と心理学
A 作業を学習するための理論
1 人が自発的に行動するためには-オペラント条件づけ
2 人間の行動を誘発するためには-レスポンデント条件づけ
3 行動学習を利用した作業療法
B 作業を自発的に行い,継続するための理論
1 行動とは
2 行動を誘発する刺激のしかた-先行刺激
3 行動を継続させる刺激のしかた-後続刺激
C 行動学習の方法
1 分化強化-望ましい行動を増やし,望ましくない行動を減らすために
2 人間の行動のルール
3 望ましい行動のスケジュール
II 作業の分析
A 作業を分析する手続き
1 作業を測定する
2 行動を誘発する刺激とその準備
3 行動を継続させる刺激とその準備
4 作業を学習したときの効果判定
B 作業の分析と作業療法への応用
1 行動分析の方法
2 作業と精神心理効果
3 精神機能作業療法の分析例
III 行動学習の基礎作業学演習
A 身体機能作業療法への治療応用(演習)
1 演習の目的
2 対象者のプロフィール
3 演習の手順
B 精神機能作業療法への治療応用(演習)
1 演習の目的
2 対象者のプロフィール
3 演習の手順
本章のキーワード
4 ライフステージと作業療法
GIO,SBO,修得チェックリスト
I 発達期と作業
A 作業と人間発達
1 成長と発達
2 発達と感覚統合
3 感覚統合理論にある3つの感覚
4 感覚信号処理と行動発現
B 作業と運動発達
1 運動発達の理論
2 乳幼児期の運動発達
3 運動・姿勢発達の指標
C 知的発達の理論
1 知覚と認知
2 知的発達の理論
D 知的発達と作業課題
1 乳幼児期から青年期
2 前操作的表象の段階
3 具体的操作の段階
4 形式的操作の段階
E 発達過程の作業療法例
1 運動障害児の例
2 作業療法評価
3 作業療法計画と実施
4 発達過程に寄り添う作業療法士
II 青年期と作業
A 作業と人間関係の構築
1 個性の確立
2 人間関係の構築
B 作業と社会とのかかわり
1 人間関係の濃度
2 人の欲求と作業
3 集団に所属する人の作業
C 対象者の人間関係を支援する
1 感情障害の例
2 作業を介して他者への緊張感を弱める
3 作業量を調節して並行した集団に参加する能力を支援する
4 承認欲求に対して支援する
5 現実検討を促す
6 生活に役立つ情報を得る
7 集団生活のなかで自己表現を助ける
8 集団関係技能と作業
III 高齢期と作業
A 高齢期にある役割と作業
1 高齢期の身体
2 高齢期の心理
3 生きがいが保つ生活機能
4 高齢者の役割
B 高齢期の作業療法
1 蓄積された体験の活用
2 高齢期の作業療法例
本章のキーワード
基礎作業学の発展に向けて
A 基礎作業学の起点
B 作業の研究法
C 心身相関
D 社会の一員として
さらに深く学ぶために
索引
更新情報
-
更新情報はありません。
お気に入り商品に追加すると、この商品の更新情報や関連情報などをマイページでお知らせいたします。