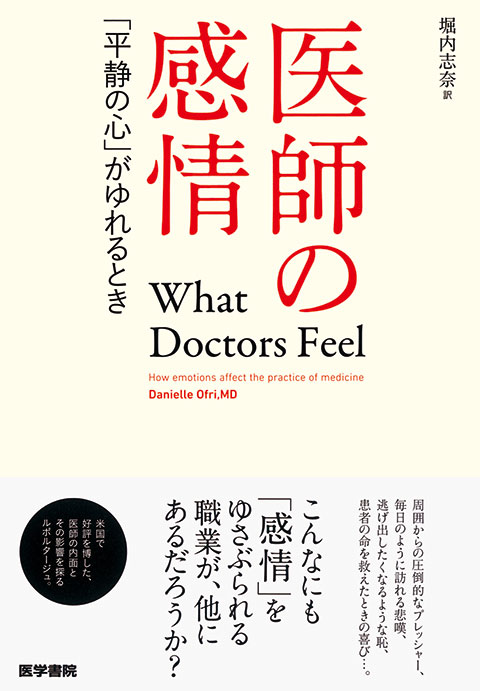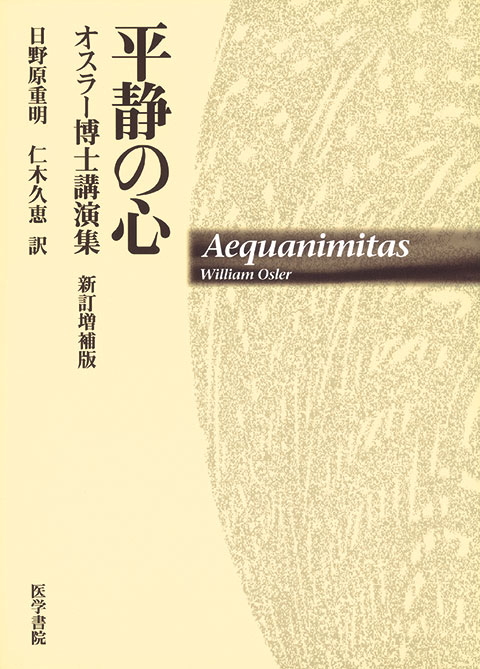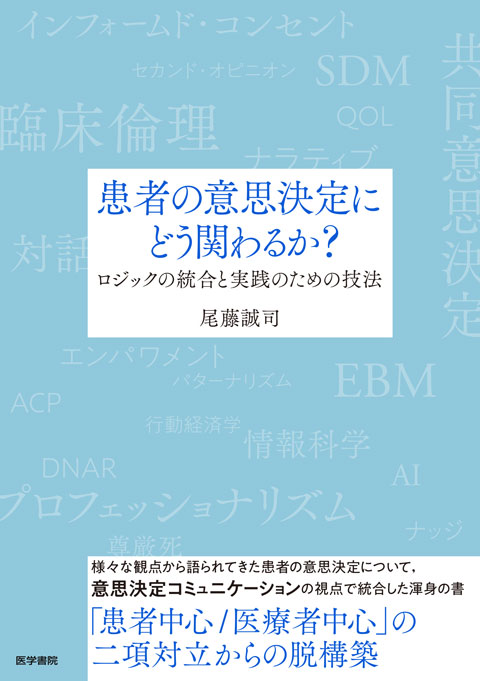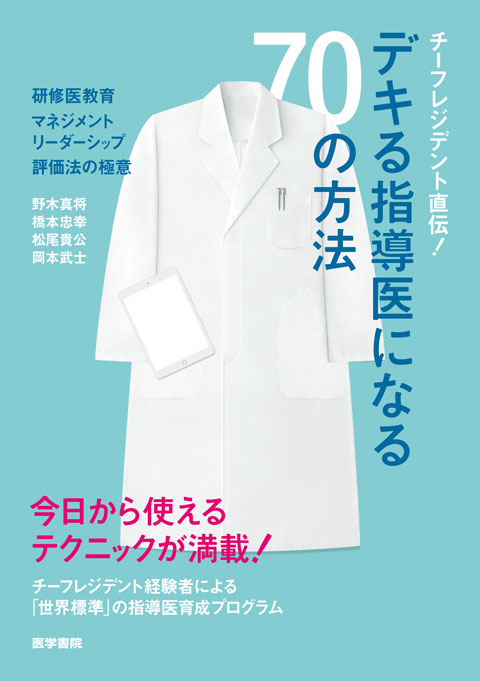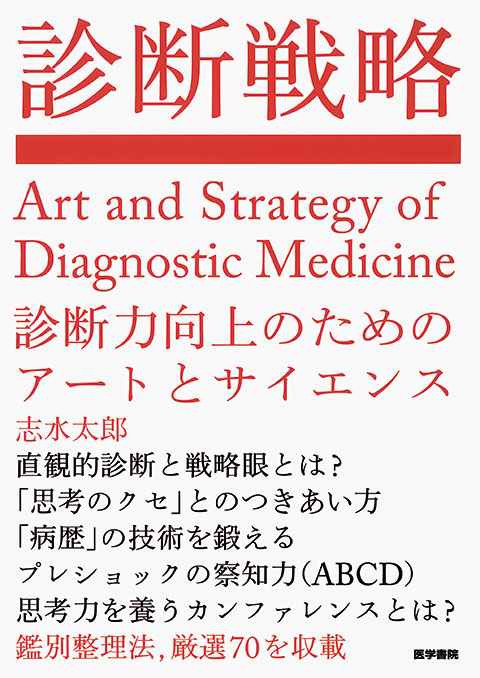医師の感情
「平静の心」がゆれるとき
医師は何を感じているのか?
もっと見る
医師の感情はコントロール可能か? 直視されることのない医師の感情——共感や悲しみ、恥やストレス、または訴訟リスクへの対応など、さまざまな問題を紹介。また、それが患者に及ぼす影響についても解説を加える。現役の医師自らがひもとく、感情のルポルタージュ。
| 原著 | Danielle Ofri |
|---|---|
| 訳 | 堀内 志奈 |
| 発行 | 2016年06月判型:四六頁:384 |
| ISBN | 978-4-260-02503-4 |
| 定価 | 3,520円 (本体3,200円+税) |
更新情報
-
更新情報はありません。
お気に入り商品に追加すると、この商品の更新情報や関連情報などをマイページでお知らせいたします。
- 序文
- 目次
- 書評
序文
開く
序章 医師の行動の裏にあるもの
医学教育や医療現場はこれまでにも本やテレビ番組、映画などで多岐にわたって描かれてきた。その中には丹念に調べ上げられた鋭い視点のものもある一方、現実に即さないまったくの娯楽作品もある。また、医師の行為やその思考プロセスについても多くが書かれてきた。しかし、医療において勝るとも劣らず重要な意味を持つにもかかわらず、「感情」の側面(必ずしも論理的には動かず、体系だった医療介入にそぐわないこともある)となると、これまで十分な検討が加えられてきたとは言い難い。
医学や医療とまったく縁のない人は存在しない。だからこそ医療は常に人々の興味の対象であり、同時に不安をかきたてるものなのだ。人が医療というものにひきつけられてやまないその裏には、現実の医療システムが理想的な形で機能していないことに対する不満の気持ちが存在する。社会的圧力、法改正、法的論争があっても、医師が人々の期待に応える働きをするとは限らない。私は医療における「知性」のさらに下にあるものを掘り返し、そこに存在する何が実際医師を動かすのか、その行動の動機を突き止められたら、と思う。
「治してさえしてくれたらいいんだ、医者がどう感じているかなんて知ったことか」と言う向きもあるかもしれない。それももっともなことだ。たしかに、単純な症例ならこうした考え方は妥当かもしれない。たとえ医師が怒りや、不安、嫉妬、燃え尽き感、恐怖、羞恥といった感情を抱えていたとしても、たいがいの場合、気管支炎や足関節の捻挫といった疾患ならきちんと治療することができるだろう。
問題なのは、状況が複雑であったり、なかなか現状打破できない時、予想されなかった合併症や医療ミス、心理的な要素が加わってきたような時だ。こうした場合、臨床能力以外のファクターがものを言い始める。
歴史上の転換期ともいえる現代、患者は(少なくとも先進国に暮らす者は)誰もが、医師が仕事に用いる医学的知識の情報源に同様にアクセスすることが可能となった。WebMDを見れば基本的な情報が手に入るし、PubMedでは最新の研究成果を読むことができる。医学書や医学雑誌もネットで買える。そうなってくると重要なことは、医師がいかにこの情報を「用いるか」であり、これによって患者は現実的に影響を受けるわけである。
医師がどのように思考するか、については現在に至るまでずっと様々な研究がなされてきた。ジェローム・グループマンは、洞察に満ちた、そのものずばりのタイトルの自著『How Doctors Think』(邦題:『医者は現場でどう考えるか』)で、医師が診断や治療を進める際にとる様々なスタイル、戦略について、それぞれの長短を指摘し、検討を加えている。彼は医師の認知プロセスについての研究を行ったが、その結果、医師の思考パターンは感情に強い影響を受けることがあり、時にはそのために患者が大きな不利益を被っていることを見いだした。「ほとんどの(医療)過誤は思考における過ちである」とグループマンは書いている「そしてこうした認知エラーをおこす原因の一つは、我々の内的感情であるが、我々はそうした感情が自分の内にあるとは容易には認めないし、自分自身その存在に気づいていないことすらしばしばである」 1) 。これを裏付ける研究がある 2) 。それによれば、ポジティブな感情を持つ時、ひとはより包括的な状況把握をし(「森を見る」状態)、柔軟な姿勢で問題解決にあたる傾向があるという。一方、ネガティブな感情を持っている時は、状況の枝葉の部分に焦点を当てて、全体像として捉えることの重要性を見失うきらいがある(「木を見る」状態)、と指摘している。また認知心理学の研究では、ネガティブな感情を抱いているひとはより係留バイアス(anchoring bias)に陥りやすいとされる。すなわち、ある一つの些末にこだわり、他の要素が目に入らなくなってしまうのだ。この係留バイアスは診断ミスの大きな原因の一つであるが、これが作用すると医師は第一印象に固執し、たとえその後矛盾するデータが出て来てもそれを無視して切り捨ててしまう。一方、ポジティブな感情を抱いているひともバイアスと無縁ではない。彼らは帰属バイアス(attribution bias)に陥りやすい。これは医療の世界で言えば、ある疾患を見たときその状況(例えば、細菌に曝露されたという事実)よりも患者がどんな人物か(例、麻薬常習者である)ということに引きずられてしまう状態をいう。
だが、これはポジティブな感情がネガティブな感情より良いとか悪いという話ではない。どちらも人間の正常な感情の振れである。しかし、医師が臨床の場でその認知力が求められる範囲は、遺伝子検査、通常のスクリーニング検査、侵襲的処置、ICUモニタリング、終末期医療における決断、など極めて広く、それを思えば最終的な帰結にいかに医師の感情が大きな影響を与えうるかがわかるだろう。
神経学者のアントニオ・ダマシオは感情を「連綿と心が奏でる旋律、途切れることのないハミング 3) 」と表現している。この通奏低音は、医師が顕在意識上で医学的決断を下している間にも、ずっと響き続けているのだ。この意識下のバスの旋律がいかに私達医師の行動に影響を与えるものか、そして患者への(私達自身がそちらの側に回るときもある!)最終的な影響はどのようなものか、というテーマが私の興味の対象である。
現在では、医療のあらゆるレベルで感情が介在するということに、どんな頭の固い保守的な医師でも異議を唱えることはないだろう。しかし、こうした様々な感情は往々にしてストレスや疲労として十把一絡げに片付けられてしまう。感情というものは十分自己修練さえ積んでいれば本来コントロールできるはずだ、という暗黙の了解もそこには存在する。
とはいえ、医療における様々な感情のひだは、私達の希望的観測よりもはるかにニュアンスに富んだもので、普遍的なものである。実際のところ、感情は医療意思決定の場において支配的なプレーヤーとなることも多く、EBMや臨床アルゴリズム、クオリティコントロール基準、そしてそれまで積んできた臨床経験をも容易に凌駕する影響力を持つことすらある。しかも、そんな力が裏で働いているとは誰の意識にも上らないこともあるのだ。
たしかに、例えば会計士や配管工、電気工事士に較べて医師の感情が特別複雑なわけはなかろう、ということももっともであるが、医師の行為はそれが論理的であれ、感情的であれ、非論理的であれ、なんであれ文字通り患者の生死を分ける影響を持ちうるのだ。そしてこれは誰にとっても他人事ではない話である。
自分自身のため、そして家族のために優れた医療を皆望み、最高のトレーニングを受けた医師、最も経験を積んだ医師、あるいはUS News & World Reportのランキングで最上位の医師にかかれば最良の医療が受けられると考えがちだ。しかしながら、底に流れる感情の様々な影響がこうした要素にかかわると話はややこしくなる。
にもかかわらず、医師はどんなときもおよそ感情的になることはない、という固定観念は今も根強く残る。こうした医師のイメージはカナダの著名な医師ウィリアム・オスラー卿にまで遡るとするひとは多い。彼は医学生たちを象牙の塔から連れ出し、実際の患者をベッドサイドで診察させて医学を実地で学ばせるという革命的なアイディアを実行した近代医学の父としばしば見なされる人物である。現在の臨床クラークシップとレジデンシートレーニングによる教育システムの大部分はオスラーに端を発し、彼のものとされる名言も数多く残る。幾多の疾患に関して今なお続く彼の影響は明白で、その証として無数の図書館、医学棟、病棟、学会、賞に彼の名を見ることができる。
一八八九年五月一日、オスラー博士はペンシルベニア大学医学部の卒業生を前に告別講演を行った。「平静の心(Aequanimitas)」 4) と題されたこのスピーチは、現在オスラーの教えの「正典」とも目されている。この中で、彼はこれから医師になろうとする若者たちに対して「感受性の鈍い方が資質としてはかえって望ましいと言える ▼ 」と強く語っている。
こうした姿勢を最初に考え出したのはオスラーではないかもしれないが、医師は概してこのようにふるまうべきである、というイメージをきちんとした形でまとめあげたのは彼である。一方で、「心を強ばらせること」、すなわち「平静」という考えから連想されるようなステレオタイプな血の通わない、冷徹な医師となることをオスラーははっきり戒めてもいる。
大衆文化にもこのステレオタイプは体現されている。ベン・ケイシーからグレゴリー・ハウスにいたるまで、テレビドラマに登場する医師は卓越した技術と診断能で人々をうならせるが、患者には超然とした態度を崩さない。無私で働く理想主義的な医師(Arrowsmith, Middlemarch, Cutting for the Stoneなどのドラマに見られる)も、極めて嫌みな医師(M*A*S*H, House of God, Scrubなど)も、どちらも患者との間に平静さを失わないだけの感情の距離は保っている。
どの病院においてもその「運営理念」の中には、「思いやり」の文言がどこかにうやうやしく盛り込まれている。どの医学部でも思いやることの素晴らしさが熱く語られる。しかし、実際の医療現場という戦場では、医師は患者に過剰に感情移入すべきでない、という暗黙の(時にはっきり言葉にされることもあるが)メッセージがしばしば存在する。感情は判断を鈍らせる、と学生は教えられる。カリキュラムの中でも、感傷的だとインターンにレッテルを貼られた科目の出席率は悲惨なものとなる。高い効率性や技術的知識といったことが今も何にもまして重んじられているのだ。
しかし、その描かれようがどうであろうが、そしてどんなにたくさんのハイテク機器が導入されようが、医師─患者間の相互関係というのはやはり基本的に人間的な営みである。そして人間関係のあるところには、必然的にその裏で感情が網細工のように織りなされている。どんなによそよそしい、冷めた医師であっても、押し寄せる強い感情の波に圧倒されることはあり、それはあけっぴろげに感情を示すタイプの医師と何ら変わらない。感情は酸素のごとく常にそこに存在するものである。しかし、私達医師がどのようにこうした感情を認識して処理するか、そのやり方は個々人で大きく異なる。そして、その違いに最も翻弄されるのは相互関係のもう一方の当事者である患者だ。
この本の目的は、医療における様々な感情に光をあて、それが医療行為のあらゆるレベルでどのような影響を及ぼすか考えてみることである。その結果、この次自分が患者の立場になったとき、治療にあたってくれる人物の心の働きが以前よりもよく理解できるようになれば幸いである。
「認知と感情は切り離せないものである」とグループマンは言う。「患者と向かい合うときは、いつも必ずこの二つは混じり合って働く」 5) 。そして、この混合具合が患者にとってとても有益な場合もあれば、惨事をもたらすこともあるのだ。
医師-患者間における感情の持つポジティブな影響とネガティブな感情を理解することは、医療の質を最大限に高めるためには不可欠である。医師はすべての患者に対してその能力の限り最善の医療を行うべきだが、そのためには下に潜む感情をはっきり認識し、それをコントロールする術を学ぶことが、検査台のどちらの側にいるひとにとっても重要なことなのだ。
文献
医学教育や医療現場はこれまでにも本やテレビ番組、映画などで多岐にわたって描かれてきた。その中には丹念に調べ上げられた鋭い視点のものもある一方、現実に即さないまったくの娯楽作品もある。また、医師の行為やその思考プロセスについても多くが書かれてきた。しかし、医療において勝るとも劣らず重要な意味を持つにもかかわらず、「感情」の側面(必ずしも論理的には動かず、体系だった医療介入にそぐわないこともある)となると、これまで十分な検討が加えられてきたとは言い難い。
医学や医療とまったく縁のない人は存在しない。だからこそ医療は常に人々の興味の対象であり、同時に不安をかきたてるものなのだ。人が医療というものにひきつけられてやまないその裏には、現実の医療システムが理想的な形で機能していないことに対する不満の気持ちが存在する。社会的圧力、法改正、法的論争があっても、医師が人々の期待に応える働きをするとは限らない。私は医療における「知性」のさらに下にあるものを掘り返し、そこに存在する何が実際医師を動かすのか、その行動の動機を突き止められたら、と思う。
「治してさえしてくれたらいいんだ、医者がどう感じているかなんて知ったことか」と言う向きもあるかもしれない。それももっともなことだ。たしかに、単純な症例ならこうした考え方は妥当かもしれない。たとえ医師が怒りや、不安、嫉妬、燃え尽き感、恐怖、羞恥といった感情を抱えていたとしても、たいがいの場合、気管支炎や足関節の捻挫といった疾患ならきちんと治療することができるだろう。
問題なのは、状況が複雑であったり、なかなか現状打破できない時、予想されなかった合併症や医療ミス、心理的な要素が加わってきたような時だ。こうした場合、臨床能力以外のファクターがものを言い始める。
歴史上の転換期ともいえる現代、患者は(少なくとも先進国に暮らす者は)誰もが、医師が仕事に用いる医学的知識の情報源に同様にアクセスすることが可能となった。WebMDを見れば基本的な情報が手に入るし、PubMedでは最新の研究成果を読むことができる。医学書や医学雑誌もネットで買える。そうなってくると重要なことは、医師がいかにこの情報を「用いるか」であり、これによって患者は現実的に影響を受けるわけである。
医師がどのように思考するか、については現在に至るまでずっと様々な研究がなされてきた。ジェローム・グループマンは、洞察に満ちた、そのものずばりのタイトルの自著『How Doctors Think』(邦題:『医者は現場でどう考えるか』)で、医師が診断や治療を進める際にとる様々なスタイル、戦略について、それぞれの長短を指摘し、検討を加えている。彼は医師の認知プロセスについての研究を行ったが、その結果、医師の思考パターンは感情に強い影響を受けることがあり、時にはそのために患者が大きな不利益を被っていることを見いだした。「ほとんどの(医療)過誤は思考における過ちである」とグループマンは書いている「そしてこうした認知エラーをおこす原因の一つは、我々の内的感情であるが、我々はそうした感情が自分の内にあるとは容易には認めないし、自分自身その存在に気づいていないことすらしばしばである」 1) 。これを裏付ける研究がある 2) 。それによれば、ポジティブな感情を持つ時、ひとはより包括的な状況把握をし(「森を見る」状態)、柔軟な姿勢で問題解決にあたる傾向があるという。一方、ネガティブな感情を持っている時は、状況の枝葉の部分に焦点を当てて、全体像として捉えることの重要性を見失うきらいがある(「木を見る」状態)、と指摘している。また認知心理学の研究では、ネガティブな感情を抱いているひとはより係留バイアス(anchoring bias)に陥りやすいとされる。すなわち、ある一つの些末にこだわり、他の要素が目に入らなくなってしまうのだ。この係留バイアスは診断ミスの大きな原因の一つであるが、これが作用すると医師は第一印象に固執し、たとえその後矛盾するデータが出て来てもそれを無視して切り捨ててしまう。一方、ポジティブな感情を抱いているひともバイアスと無縁ではない。彼らは帰属バイアス(attribution bias)に陥りやすい。これは医療の世界で言えば、ある疾患を見たときその状況(例えば、細菌に曝露されたという事実)よりも患者がどんな人物か(例、麻薬常習者である)ということに引きずられてしまう状態をいう。
だが、これはポジティブな感情がネガティブな感情より良いとか悪いという話ではない。どちらも人間の正常な感情の振れである。しかし、医師が臨床の場でその認知力が求められる範囲は、遺伝子検査、通常のスクリーニング検査、侵襲的処置、ICUモニタリング、終末期医療における決断、など極めて広く、それを思えば最終的な帰結にいかに医師の感情が大きな影響を与えうるかがわかるだろう。
神経学者のアントニオ・ダマシオは感情を「連綿と心が奏でる旋律、途切れることのないハミング 3) 」と表現している。この通奏低音は、医師が顕在意識上で医学的決断を下している間にも、ずっと響き続けているのだ。この意識下のバスの旋律がいかに私達医師の行動に影響を与えるものか、そして患者への(私達自身がそちらの側に回るときもある!)最終的な影響はどのようなものか、というテーマが私の興味の対象である。
現在では、医療のあらゆるレベルで感情が介在するということに、どんな頭の固い保守的な医師でも異議を唱えることはないだろう。しかし、こうした様々な感情は往々にしてストレスや疲労として十把一絡げに片付けられてしまう。感情というものは十分自己修練さえ積んでいれば本来コントロールできるはずだ、という暗黙の了解もそこには存在する。
とはいえ、医療における様々な感情のひだは、私達の希望的観測よりもはるかにニュアンスに富んだもので、普遍的なものである。実際のところ、感情は医療意思決定の場において支配的なプレーヤーとなることも多く、EBMや臨床アルゴリズム、クオリティコントロール基準、そしてそれまで積んできた臨床経験をも容易に凌駕する影響力を持つことすらある。しかも、そんな力が裏で働いているとは誰の意識にも上らないこともあるのだ。
たしかに、例えば会計士や配管工、電気工事士に較べて医師の感情が特別複雑なわけはなかろう、ということももっともであるが、医師の行為はそれが論理的であれ、感情的であれ、非論理的であれ、なんであれ文字通り患者の生死を分ける影響を持ちうるのだ。そしてこれは誰にとっても他人事ではない話である。
自分自身のため、そして家族のために優れた医療を皆望み、最高のトレーニングを受けた医師、最も経験を積んだ医師、あるいはUS News & World Reportのランキングで最上位の医師にかかれば最良の医療が受けられると考えがちだ。しかしながら、底に流れる感情の様々な影響がこうした要素にかかわると話はややこしくなる。
にもかかわらず、医師はどんなときもおよそ感情的になることはない、という固定観念は今も根強く残る。こうした医師のイメージはカナダの著名な医師ウィリアム・オスラー卿にまで遡るとするひとは多い。彼は医学生たちを象牙の塔から連れ出し、実際の患者をベッドサイドで診察させて医学を実地で学ばせるという革命的なアイディアを実行した近代医学の父としばしば見なされる人物である。現在の臨床クラークシップとレジデンシートレーニングによる教育システムの大部分はオスラーに端を発し、彼のものとされる名言も数多く残る。幾多の疾患に関して今なお続く彼の影響は明白で、その証として無数の図書館、医学棟、病棟、学会、賞に彼の名を見ることができる。
一八八九年五月一日、オスラー博士はペンシルベニア大学医学部の卒業生を前に告別講演を行った。「平静の心(Aequanimitas)」 4) と題されたこのスピーチは、現在オスラーの教えの「正典」とも目されている。この中で、彼はこれから医師になろうとする若者たちに対して「感受性の鈍い方が資質としてはかえって望ましいと言える ▼ 」と強く語っている。
こうした姿勢を最初に考え出したのはオスラーではないかもしれないが、医師は概してこのようにふるまうべきである、というイメージをきちんとした形でまとめあげたのは彼である。一方で、「心を強ばらせること」、すなわち「平静」という考えから連想されるようなステレオタイプな血の通わない、冷徹な医師となることをオスラーははっきり戒めてもいる。
大衆文化にもこのステレオタイプは体現されている。ベン・ケイシーからグレゴリー・ハウスにいたるまで、テレビドラマに登場する医師は卓越した技術と診断能で人々をうならせるが、患者には超然とした態度を崩さない。無私で働く理想主義的な医師(Arrowsmith, Middlemarch, Cutting for the Stoneなどのドラマに見られる)も、極めて嫌みな医師(M*A*S*H, House of God, Scrubなど)も、どちらも患者との間に平静さを失わないだけの感情の距離は保っている。
どの病院においてもその「運営理念」の中には、「思いやり」の文言がどこかにうやうやしく盛り込まれている。どの医学部でも思いやることの素晴らしさが熱く語られる。しかし、実際の医療現場という戦場では、医師は患者に過剰に感情移入すべきでない、という暗黙の(時にはっきり言葉にされることもあるが)メッセージがしばしば存在する。感情は判断を鈍らせる、と学生は教えられる。カリキュラムの中でも、感傷的だとインターンにレッテルを貼られた科目の出席率は悲惨なものとなる。高い効率性や技術的知識といったことが今も何にもまして重んじられているのだ。
しかし、その描かれようがどうであろうが、そしてどんなにたくさんのハイテク機器が導入されようが、医師─患者間の相互関係というのはやはり基本的に人間的な営みである。そして人間関係のあるところには、必然的にその裏で感情が網細工のように織りなされている。どんなによそよそしい、冷めた医師であっても、押し寄せる強い感情の波に圧倒されることはあり、それはあけっぴろげに感情を示すタイプの医師と何ら変わらない。感情は酸素のごとく常にそこに存在するものである。しかし、私達医師がどのようにこうした感情を認識して処理するか、そのやり方は個々人で大きく異なる。そして、その違いに最も翻弄されるのは相互関係のもう一方の当事者である患者だ。
この本の目的は、医療における様々な感情に光をあて、それが医療行為のあらゆるレベルでどのような影響を及ぼすか考えてみることである。その結果、この次自分が患者の立場になったとき、治療にあたってくれる人物の心の働きが以前よりもよく理解できるようになれば幸いである。
「認知と感情は切り離せないものである」とグループマンは言う。「患者と向かい合うときは、いつも必ずこの二つは混じり合って働く」 5) 。そして、この混合具合が患者にとってとても有益な場合もあれば、惨事をもたらすこともあるのだ。
医師-患者間における感情の持つポジティブな影響とネガティブな感情を理解することは、医療の質を最大限に高めるためには不可欠である。医師はすべての患者に対してその能力の限り最善の医療を行うべきだが、そのためには下に潜む感情をはっきり認識し、それをコントロールする術を学ぶことが、検査台のどちらの側にいるひとにとっても重要なことなのだ。
文献
| 1. | Jerome Groopman, How Doctors Think (Boston: Houghton Miffl in, 2007), 40. |
| 2. | M. C. McConnell and K. Eva, "The Role of Emotion in the Learning and Transfer of Clinical Skills and Knowledge," Academic Medicine 87 (2012): 1316-22. |
| 3. | Antonio Damasio, Looking for Spinoza: Joy, Sorrow, and the Feeling Brain (New York: Harcourt, 2003), 3. |
| 4. | William Osler, "Aequanimitas," speech, Celebrating the Contributions of William Osler, website, Johns Hopkins University, http://www.medicalarchives.jhmi.edu/. |
| 5. | Groopman, How Doctors Think, 39. |
| ▼ | 日野原重明、二木久恵(訳):平静の心 オスラー博士講演集 新訂増補版、p.5、医学書院、二〇〇三 |
目次
開く
序章 医師の行動の裏にあるもの
第1章 先生はいま手が離せません
——共感ができない原因は、医師にあるのか? 患者にあるのか?
ジュリアの物語1
第2章 医師の品質改善は可能か?
——研修を通して損なわれていくもの
ジュリアの物語2
第3章 怖れに支配されて
——我々を動けなくするほどの「怖れ」の意味
ジュリアの物語3
第4章 死が身近な日々
——医師にとって「悲しみ」とは悪なのだろうか?
ジュリアの物語4
第5章 灼けるような恥ずかしさ
——なぜそれほどまでに恥を怖れるのか?
ジュリアの物語5
第6章 溺死
——医療の現場に幻滅してしまったら
ジュリアの物語6
第7章 顕微鏡の下で
——訴訟をめぐる感情と、医療に対する影響
ジュリアの物語7
あとがき
謝辞
訳者あとがき
文献一覧
第1章 先生はいま手が離せません
——共感ができない原因は、医師にあるのか? 患者にあるのか?
ジュリアの物語1
第2章 医師の品質改善は可能か?
——研修を通して損なわれていくもの
ジュリアの物語2
第3章 怖れに支配されて
——我々を動けなくするほどの「怖れ」の意味
ジュリアの物語3
第4章 死が身近な日々
——医師にとって「悲しみ」とは悪なのだろうか?
ジュリアの物語4
第5章 灼けるような恥ずかしさ
——なぜそれほどまでに恥を怖れるのか?
ジュリアの物語5
第6章 溺死
——医療の現場に幻滅してしまったら
ジュリアの物語6
第7章 顕微鏡の下で
——訴訟をめぐる感情と、医療に対する影響
ジュリアの物語7
あとがき
謝辞
訳者あとがき
文献一覧
書評
開く
うごめく感情の渦の中で,あるべき医師像とは
書評者: 平島 修 (徳洲会奄美ブロック総合診療研修センター長)
「医療現場をこれほどまでに赤裸々に,リアルに書いていいものだろうか」という驚きがこの本を読んで生じた感情だった。いてもたってもいられず,本書の書評を書かせてほしいと出版担当者にお願いしてしまった。「医師はいかなる時も平静の心を持って患者と向き合うべきである」と説いた臨床医学の基礎を作ったウィリアム・オスラー先生の「平静の心」を揺るがす内容なのである。
「医師は患者に必要以上に感情移入してはいけない」
医師なら一度は耳にした言葉であると思うが,医師は感情を意識的に心に押し込んでおくことが本当に正しいのだろうか。本書はこのタブーとさえされてきたような感情の問題を,医師にはどのような感情が生まれ,どのように反応してしまうのかを,掘り下げてゆく。命を扱う医師という職業は他の職業と違い,さまざまな感情の波が患者本人や家族だけでなく押し寄せる職業である。医療の主役は患者であり,疾患を患った患者がいかなる感情を抱くかに関してはこれまで何度も議論されてきたが,医師が受ける感情に関する議論はほとんどされてこなかった。
「不安・恐怖・悲しみ・恥・怒り・困惑・幻滅」といった感情は,医師が臨床現場で日常的に感じる感情である。このような感情についてエピソードを交えて述べられているが,筆者の壮絶な経験と心の中で揺れ動く葛藤は,臨床医なら身近に感じられる内容で描かれており,どんどん引き込まれてゆく。医師がアルコール依存症患者や肥満患者に軽蔑の念を抱くことや,寝たきり患者が発熱を主訴に救急外来に運ばれると“gomer”(go out of my ER)と差別的な用語で呼ばれる現状をありのままに指摘し,医学生が持つ純粋な気持ちがどのようになくなっていくのかについても冷静に分析している。また本書は医療ミスの原因となる感情も指摘している。医師の不安や恐れといった感情はあたかもひた隠しにされ,ミスのない完璧な医術を要求される。しかしミスが大きかれ,小さかれ,なくなることはない。医療機器は発展してもそれを扱う医師が血の通う人間であるならば,システムだけを指摘するのではなく,背景となった感情にまで言及しなければ医療ミスを明らかにすることすらできない。本書で書かれているエピソードは,筆者が訴える「平静な心」ではいられないという言葉に非常に納得させられる内容である。
「医師の感情」はこれまであまり認識されてこなかった内容であるが,医師―患者関係を良好にする意味で非常に重要な基盤となる。これから医療現場に臨む医学生から指導医まで,共通した認識を持つためにもぜひ読んでいただきたい一冊である。
医師の感情の凄まじい変化
書評者: 徳田 安春 (臨床研修病院群プロジェクト群星沖縄副センター長)
この本が書店に並べられて最初にタイトルを見かけた時,ある種の衝撃を受けた。というのは,タイトルは『医師の感情』であるが,副題が“「平静の心」がゆれるとき”となっていたからだ。「平静の心」とはオスラー先生が遺した有名な言葉であり,医師にとって最も重要な資質のことであったからだ。医師にとって最も重要な資質である“「平静の心」がゆれるとき”とはどういうときなのか,これは非常に重要なテーマについて取り組んだ本であると直観的にわかった。
この本を実際に手に取ってみると訳本であった。原題は“What Doctors Feel ”である。なるほど,この本はあの良書“How Doctors Think ”(邦題『医者は現場でどう考えるか』,石風社,2011年)が扱っていた医師の思考プロセスの中で,特に感情について現役の医師が考察したものである。“How doctors think ”は誤診の起こるメカニズムについて医師の思考プロセスにおけるバイアスの影響について詳細に解説していた。一方,この本は,無意識に起きている感情的バイアスについて著者自身が体験した生々しい実例を示しながら解説したものである。リアルストーリーであり,説得力がある。
医師も人間であり感情を持つ。感情の中で,共感は医療人にとっては非常に重要なものである。このもともと人間として持っていた共感という感情が,医学生から研修医となるときにどのように失われていくのかを克明に記載している。このように,ある感情が失われていくのも医師の特徴なのだ。そして悲しみの感情もそうだ。
医師の感情の中でむしろ特徴的なものは,恐れや恥という感情である。不確定性に満ちた臨床における恐れのプレッシャーは強い。診療現場での失敗に対するネガティブなラベリングの文化が蔓延しているため,失敗したときに,みんなから非難が下されることに対する恐れの感情は大きい。ほとんどの医師が気付いていないことであるが,医師は自分の失敗を認めようとしたくないという恥の感情を強く持つということである。
医師はバーンアウトが多い。バーンアウトによる脱人格化で気難しい性格となった医師も多い。日本でも,医師をやめてビジネスに転向した人も多いようである。臨床現場の中で変貌していく自分の感情に耐えきれなくなった人もいるのであろう。
この本はアメリカの臨床医によるものであるが,日本の医師の感情にも共通部分が多い。気難しい医師,とっつきにくい医師,変な医師,などという人たちを日ごろから相手にしている人たちは本書を読むことによってかなり理解できる部分があるだろう。看護師,薬剤師,医療クラーク等の人たちにもお薦めしたい。もちろん,医学生は自分自身の感情がどのように今後変化するかを前もって知るうえで大変貴重な本となるだろう。また,病院の院長や事務長などの経営者はこれを読むことにより,従業員である医師をどう動かすかということを感情面からも把握しておくことはとても役に立つと思う。
書評者: 平島 修 (徳洲会奄美ブロック総合診療研修センター長)
「医療現場をこれほどまでに赤裸々に,リアルに書いていいものだろうか」という驚きがこの本を読んで生じた感情だった。いてもたってもいられず,本書の書評を書かせてほしいと出版担当者にお願いしてしまった。「医師はいかなる時も平静の心を持って患者と向き合うべきである」と説いた臨床医学の基礎を作ったウィリアム・オスラー先生の「平静の心」を揺るがす内容なのである。
「医師は患者に必要以上に感情移入してはいけない」
医師なら一度は耳にした言葉であると思うが,医師は感情を意識的に心に押し込んでおくことが本当に正しいのだろうか。本書はこのタブーとさえされてきたような感情の問題を,医師にはどのような感情が生まれ,どのように反応してしまうのかを,掘り下げてゆく。命を扱う医師という職業は他の職業と違い,さまざまな感情の波が患者本人や家族だけでなく押し寄せる職業である。医療の主役は患者であり,疾患を患った患者がいかなる感情を抱くかに関してはこれまで何度も議論されてきたが,医師が受ける感情に関する議論はほとんどされてこなかった。
「不安・恐怖・悲しみ・恥・怒り・困惑・幻滅」といった感情は,医師が臨床現場で日常的に感じる感情である。このような感情についてエピソードを交えて述べられているが,筆者の壮絶な経験と心の中で揺れ動く葛藤は,臨床医なら身近に感じられる内容で描かれており,どんどん引き込まれてゆく。医師がアルコール依存症患者や肥満患者に軽蔑の念を抱くことや,寝たきり患者が発熱を主訴に救急外来に運ばれると“gomer”(go out of my ER)と差別的な用語で呼ばれる現状をありのままに指摘し,医学生が持つ純粋な気持ちがどのようになくなっていくのかについても冷静に分析している。また本書は医療ミスの原因となる感情も指摘している。医師の不安や恐れといった感情はあたかもひた隠しにされ,ミスのない完璧な医術を要求される。しかしミスが大きかれ,小さかれ,なくなることはない。医療機器は発展してもそれを扱う医師が血の通う人間であるならば,システムだけを指摘するのではなく,背景となった感情にまで言及しなければ医療ミスを明らかにすることすらできない。本書で書かれているエピソードは,筆者が訴える「平静な心」ではいられないという言葉に非常に納得させられる内容である。
「医師の感情」はこれまであまり認識されてこなかった内容であるが,医師―患者関係を良好にする意味で非常に重要な基盤となる。これから医療現場に臨む医学生から指導医まで,共通した認識を持つためにもぜひ読んでいただきたい一冊である。
医師の感情の凄まじい変化
書評者: 徳田 安春 (臨床研修病院群プロジェクト群星沖縄副センター長)
この本が書店に並べられて最初にタイトルを見かけた時,ある種の衝撃を受けた。というのは,タイトルは『医師の感情』であるが,副題が“「平静の心」がゆれるとき”となっていたからだ。「平静の心」とはオスラー先生が遺した有名な言葉であり,医師にとって最も重要な資質のことであったからだ。医師にとって最も重要な資質である“「平静の心」がゆれるとき”とはどういうときなのか,これは非常に重要なテーマについて取り組んだ本であると直観的にわかった。
この本を実際に手に取ってみると訳本であった。原題は“What Doctors Feel ”である。なるほど,この本はあの良書“How Doctors Think ”(邦題『医者は現場でどう考えるか』,石風社,2011年)が扱っていた医師の思考プロセスの中で,特に感情について現役の医師が考察したものである。“How doctors think ”は誤診の起こるメカニズムについて医師の思考プロセスにおけるバイアスの影響について詳細に解説していた。一方,この本は,無意識に起きている感情的バイアスについて著者自身が体験した生々しい実例を示しながら解説したものである。リアルストーリーであり,説得力がある。
医師も人間であり感情を持つ。感情の中で,共感は医療人にとっては非常に重要なものである。このもともと人間として持っていた共感という感情が,医学生から研修医となるときにどのように失われていくのかを克明に記載している。このように,ある感情が失われていくのも医師の特徴なのだ。そして悲しみの感情もそうだ。
医師の感情の中でむしろ特徴的なものは,恐れや恥という感情である。不確定性に満ちた臨床における恐れのプレッシャーは強い。診療現場での失敗に対するネガティブなラベリングの文化が蔓延しているため,失敗したときに,みんなから非難が下されることに対する恐れの感情は大きい。ほとんどの医師が気付いていないことであるが,医師は自分の失敗を認めようとしたくないという恥の感情を強く持つということである。
医師はバーンアウトが多い。バーンアウトによる脱人格化で気難しい性格となった医師も多い。日本でも,医師をやめてビジネスに転向した人も多いようである。臨床現場の中で変貌していく自分の感情に耐えきれなくなった人もいるのであろう。
この本はアメリカの臨床医によるものであるが,日本の医師の感情にも共通部分が多い。気難しい医師,とっつきにくい医師,変な医師,などという人たちを日ごろから相手にしている人たちは本書を読むことによってかなり理解できる部分があるだろう。看護師,薬剤師,医療クラーク等の人たちにもお薦めしたい。もちろん,医学生は自分自身の感情がどのように今後変化するかを前もって知るうえで大変貴重な本となるだろう。また,病院の院長や事務長などの経営者はこれを読むことにより,従業員である医師をどう動かすかということを感情面からも把握しておくことはとても役に立つと思う。