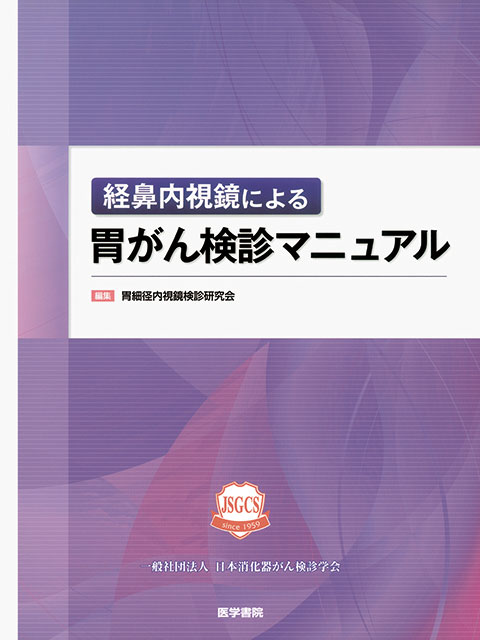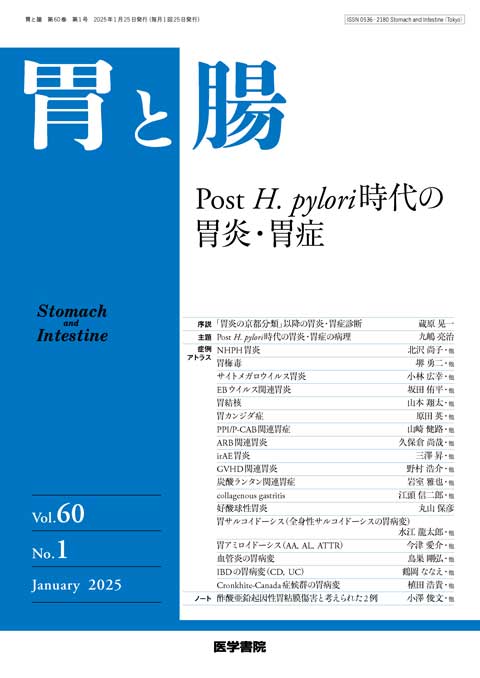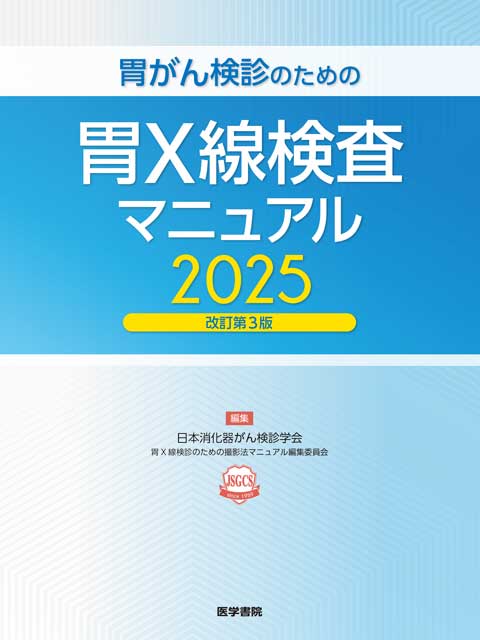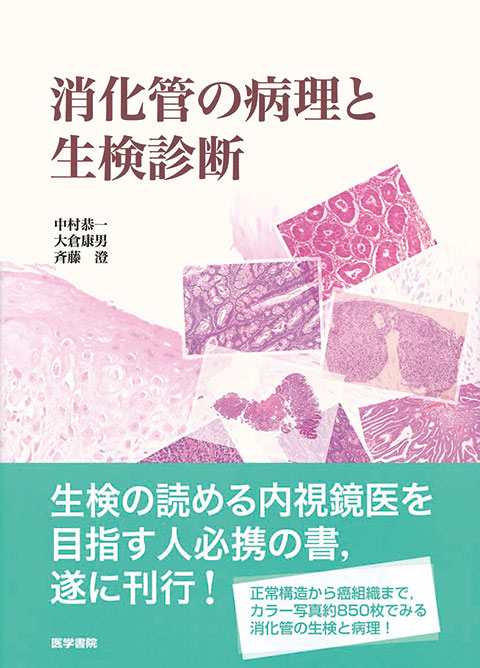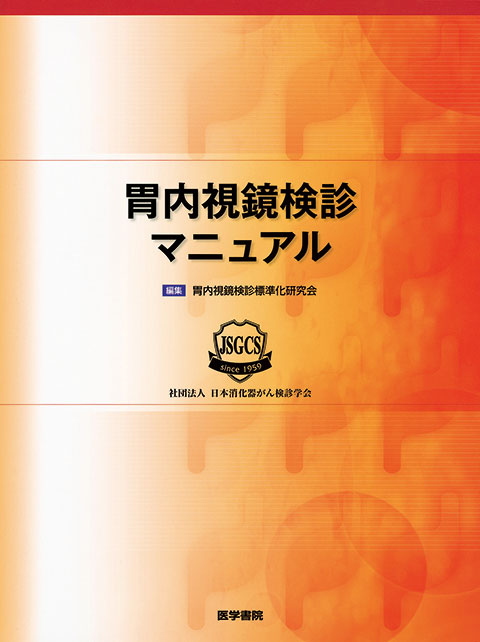経鼻内視鏡による
胃がん検診マニュアル
経鼻内視鏡による標準的検査方法の到来に先駆けて発刊
もっと見る
経鼻内視鏡による胃がん検診の件数は増加にあるものの、死亡率減少効果を判断する根拠がまだ不十分であり、現状では集団を対象としての実施は勧められていない。標準法が確立されておらず、各施行者が独自の判断で行っているのが実状だ。その混乱回避と、来たるべき内視鏡による集団検診が行われる時代に先駆けて、経鼻内視鏡による“望ましい”検診について、標準的な使用方法等を幅広く本書で解説する。
| 編集 | 日本消化器がん検診学会 胃細径内視鏡検診研究会 |
|---|---|
| 発行 | 2014年03月判型:A4変頁:112 |
| ISBN | 978-4-260-01923-1 |
| 定価 | 3,300円 (本体3,000円+税) |
更新情報
-
更新情報はありません。
お気に入り商品に追加すると、この商品の更新情報や関連情報などをマイページでお知らせいたします。
- 序文
- 目次
序文
開く
発刊にあたって
このたび,日本消化器がん検診学会の附置研究会である胃細径内視鏡検診研究会の編纂による『経鼻内視鏡による 胃がん検診マニュアル』が発刊される運びとなり,本学会理事長として一言ご挨拶を申し上げます.
本学会では,2010年,内視鏡による胃がん検診の標準化を眼目として『胃内視鏡検診マニュアル』(附置研究会 胃内視鏡検診標準化研究会)を刊行しておりますが,今回発刊されるマニュアルは,安全性や受容度に勝るとされている経鼻内視鏡による検診に焦点を当てたものになっています.内視鏡による検診は,2006年に公表された厚生労働省研究班(研究代表者 祖父江友孝)による『有効性評価に基づく胃がん検診ガイドライン』において,今のところ死亡率減少効果のエビデンスが十分でないという判断から対策型検診には推奨できないとされております.しかし,人間ドックなどの任意型検診としてはもちろん,いくつかの地域ではすでに対策型検診として導入を進めており,本学会の全国集計でも2010年には受診者が40万人を超えていることが示されております.私は,本学会のスタンスとして先のガイドラインで推奨されなかった検診を排除すべきとは毛頭考えておらず,むしろ内視鏡検診のデータを蓄積して疫学的解析により,死亡率減少効果を的確に評価してほしいと考えております.そのためには,検診の手順,精度管理(機器の管理,偽陰性対策,事後管理),研修や教育など一定の基準のもとで検診を行うことが必要となります.今回刊行されたマニュアルでは,その点に十分な配慮がなされ,それらの項目について詳細に記載されております.
私自身,平成19~21年度の3年間,厚生労働省の第3次対がん総合戦略事業「新たな胃がん検診システムに必要な検診方法の開発とその有効性評価に関する研究」の主任研究者を務め,いくつかの地域で先行的に実施されている内視鏡検診の現況を見る機会を得ましたが,その際,内視鏡検診を実施している地域の医師会の並外れたパワーには驚かされました.内視鏡検診は医師が実施することが必須であり,処理能力や効率性には問題がありますが,その効果が効率性を凌駕するものであれば,実施体制の整った地域では対策型検診に導入していけばよいと考えております.本マニュアルが,その効率性の向上にも役立つのではないかと秘かに期待しているところです.
最後になりますが,本マニュアル刊行にあたりご苦労された胃細径内視鏡検診研究会代表世話人の細川治先生をはじめ,執筆にあたられた諸先生にはあらためて感謝の意を表します.
2014年3月
一般社団法人 日本消化器がん検診学会
理事長 深尾 彰
このたび,日本消化器がん検診学会の附置研究会である胃細径内視鏡検診研究会の編纂による『経鼻内視鏡による 胃がん検診マニュアル』が発刊される運びとなり,本学会理事長として一言ご挨拶を申し上げます.
本学会では,2010年,内視鏡による胃がん検診の標準化を眼目として『胃内視鏡検診マニュアル』(附置研究会 胃内視鏡検診標準化研究会)を刊行しておりますが,今回発刊されるマニュアルは,安全性や受容度に勝るとされている経鼻内視鏡による検診に焦点を当てたものになっています.内視鏡による検診は,2006年に公表された厚生労働省研究班(研究代表者 祖父江友孝)による『有効性評価に基づく胃がん検診ガイドライン』において,今のところ死亡率減少効果のエビデンスが十分でないという判断から対策型検診には推奨できないとされております.しかし,人間ドックなどの任意型検診としてはもちろん,いくつかの地域ではすでに対策型検診として導入を進めており,本学会の全国集計でも2010年には受診者が40万人を超えていることが示されております.私は,本学会のスタンスとして先のガイドラインで推奨されなかった検診を排除すべきとは毛頭考えておらず,むしろ内視鏡検診のデータを蓄積して疫学的解析により,死亡率減少効果を的確に評価してほしいと考えております.そのためには,検診の手順,精度管理(機器の管理,偽陰性対策,事後管理),研修や教育など一定の基準のもとで検診を行うことが必要となります.今回刊行されたマニュアルでは,その点に十分な配慮がなされ,それらの項目について詳細に記載されております.
私自身,平成19~21年度の3年間,厚生労働省の第3次対がん総合戦略事業「新たな胃がん検診システムに必要な検診方法の開発とその有効性評価に関する研究」の主任研究者を務め,いくつかの地域で先行的に実施されている内視鏡検診の現況を見る機会を得ましたが,その際,内視鏡検診を実施している地域の医師会の並外れたパワーには驚かされました.内視鏡検診は医師が実施することが必須であり,処理能力や効率性には問題がありますが,その効果が効率性を凌駕するものであれば,実施体制の整った地域では対策型検診に導入していけばよいと考えております.本マニュアルが,その効率性の向上にも役立つのではないかと秘かに期待しているところです.
最後になりますが,本マニュアル刊行にあたりご苦労された胃細径内視鏡検診研究会代表世話人の細川治先生をはじめ,執筆にあたられた諸先生にはあらためて感謝の意を表します.
2014年3月
一般社団法人 日本消化器がん検診学会
理事長 深尾 彰
目次
開く
発刊にあたって
経鼻内視鏡附置研究会のこれまでの軌跡とこれから
I 胃内視鏡検診における細径内視鏡の役割と意義
1 細径内視鏡の改良
2 経鼻内視鏡検査の受容性
3 経鼻内視鏡検査の利点・欠点
4 経鼻内視鏡検査の呼吸循環動態への影響
5 経鼻内視鏡検査によるがん発見率
II 経鼻内視鏡検査機器と管理
1 各メーカーの経鼻スコープの特性
A オリンパス
B 富士フイルム
C HOYA
2 スコープ以外の処置具
A 送水装置
B 生検鉗子
C マウスピース
3 内視鏡機器の洗浄・消毒
III インフォームド・コンセントとリスク管理
1 インフォームド・コンセントの実際
2 偶発症とその対処法
A 鼻痛
B 鼻出血
C スコープの抜去困難
D その他のまれな偶発症
IV 経鼻内視鏡検査手順
1 適応と禁忌
A 一般的な胃内視鏡検診としての適応
B 内視鏡機種からみた適応
1)機種の使い分け
2)特に経鼻内視鏡が有用である場合
C 相対的禁忌
D 禁忌
E 生検の適応と禁忌
2 前処置・前投薬
A 検査前日までの注意点
1)検査前日の飲食
2)抗血栓薬の服用
B 検査当日の注意点
1)内服薬
2)禁煙
3)義歯
C 前処置の前に確認すべきこと
D 経鼻内視鏡検査の前処置
1)消化管ガス駆除薬
2)鎮痙薬,鎮静薬
3)局所血管収縮薬
4)挿入する鼻腔の決定
5)鼻腔麻酔
a.スティック法
b.スプレー法
c.スティック・スプレー併用法
d.注入法
6)咽頭麻酔
7)内視鏡挿入時の注意
8)その他の注意点
[Memo]鼻腔麻酔─注入法について─
3 咽頭観察と食道挿入法
A 受診者の体位と呼吸法
B 検査医の準備とスコープの把持
C 咽頭観察と挿入法(経鼻挿入)
1)鼻腔内通過方法
a.中鼻甲介(下端)ルート
b.下鼻甲介(下端)ルート
2)咽頭観察法
3)食道入口部挿入
4 食道・胃・十二指腸観察
A 食道
B 胃
5 記録画像と二次読影
A スクリーニングの2つの方法
B 二次読影
6 生検
A 経鼻内視鏡(細径内視鏡)専用生検鉗子
B 正確な狙撃生検を行うために
C 抗血栓療法中の生検
7 専用車を用いた検診
A 経鼻内視鏡専用検診車について
B 経鼻内視鏡検診対象者と可能症例数について
C 経鼻内視鏡専用検診車の構造
D 経鼻内視鏡検査の実際
E 経鼻内視鏡専用検診車にかかわるスタッフ
F 生検について
G 出張での内視鏡検査の特性と偶発症対策
H 検査結果について
I 経鼻内視鏡専用検診車を使用する内視鏡検診のメリット
J 検診車運用においての今後の課題と展望
V 偽陰性対策と事後管理
1 偽陰性と見逃し
2 偽陰性の定義
3 細径内視鏡検査の偽陰性の実態
4 細径内視鏡検査の偽陰性対策
5 適切な撮影順序と撮影枚数
6 ダブルチェックの意義
7 所見記載に関する工夫(鼻腔ルート詳細)
VI 細径内視鏡検査実施にあたっての研修と教育
1 検査医の資格
2 研修と教育の必要性
3 研修と教育の実際
A 検査医
B コメディカル
C 内視鏡検診実施主体
VII 症例提示
症例1 初回発見例
症例2 初回発見例
症例3 初回発見例
症例4 経鼻内視鏡発見例(経口内視鏡偽陰性)
症例5 偽陰性例
症例6 偽陰性例
症例7 偽陰性例
症例8 偽陰性例
症例9 偽陰性例
症例10 偽陰性例
索引
経鼻内視鏡附置研究会のこれまでの軌跡とこれから
I 胃内視鏡検診における細径内視鏡の役割と意義
1 細径内視鏡の改良
2 経鼻内視鏡検査の受容性
3 経鼻内視鏡検査の利点・欠点
4 経鼻内視鏡検査の呼吸循環動態への影響
5 経鼻内視鏡検査によるがん発見率
II 経鼻内視鏡検査機器と管理
1 各メーカーの経鼻スコープの特性
A オリンパス
B 富士フイルム
C HOYA
2 スコープ以外の処置具
A 送水装置
B 生検鉗子
C マウスピース
3 内視鏡機器の洗浄・消毒
III インフォームド・コンセントとリスク管理
1 インフォームド・コンセントの実際
2 偶発症とその対処法
A 鼻痛
B 鼻出血
C スコープの抜去困難
D その他のまれな偶発症
IV 経鼻内視鏡検査手順
1 適応と禁忌
A 一般的な胃内視鏡検診としての適応
B 内視鏡機種からみた適応
1)機種の使い分け
2)特に経鼻内視鏡が有用である場合
C 相対的禁忌
D 禁忌
E 生検の適応と禁忌
2 前処置・前投薬
A 検査前日までの注意点
1)検査前日の飲食
2)抗血栓薬の服用
B 検査当日の注意点
1)内服薬
2)禁煙
3)義歯
C 前処置の前に確認すべきこと
D 経鼻内視鏡検査の前処置
1)消化管ガス駆除薬
2)鎮痙薬,鎮静薬
3)局所血管収縮薬
4)挿入する鼻腔の決定
5)鼻腔麻酔
a.スティック法
b.スプレー法
c.スティック・スプレー併用法
d.注入法
6)咽頭麻酔
7)内視鏡挿入時の注意
8)その他の注意点
[Memo]鼻腔麻酔─注入法について─
3 咽頭観察と食道挿入法
A 受診者の体位と呼吸法
B 検査医の準備とスコープの把持
C 咽頭観察と挿入法(経鼻挿入)
1)鼻腔内通過方法
a.中鼻甲介(下端)ルート
b.下鼻甲介(下端)ルート
2)咽頭観察法
3)食道入口部挿入
4 食道・胃・十二指腸観察
A 食道
B 胃
5 記録画像と二次読影
A スクリーニングの2つの方法
B 二次読影
6 生検
A 経鼻内視鏡(細径内視鏡)専用生検鉗子
B 正確な狙撃生検を行うために
C 抗血栓療法中の生検
7 専用車を用いた検診
A 経鼻内視鏡専用検診車について
B 経鼻内視鏡検診対象者と可能症例数について
C 経鼻内視鏡専用検診車の構造
D 経鼻内視鏡検査の実際
E 経鼻内視鏡専用検診車にかかわるスタッフ
F 生検について
G 出張での内視鏡検査の特性と偶発症対策
H 検査結果について
I 経鼻内視鏡専用検診車を使用する内視鏡検診のメリット
J 検診車運用においての今後の課題と展望
V 偽陰性対策と事後管理
1 偽陰性と見逃し
2 偽陰性の定義
3 細径内視鏡検査の偽陰性の実態
4 細径内視鏡検査の偽陰性対策
5 適切な撮影順序と撮影枚数
6 ダブルチェックの意義
7 所見記載に関する工夫(鼻腔ルート詳細)
VI 細径内視鏡検査実施にあたっての研修と教育
1 検査医の資格
2 研修と教育の必要性
3 研修と教育の実際
A 検査医
B コメディカル
C 内視鏡検診実施主体
VII 症例提示
症例1 初回発見例
症例2 初回発見例
症例3 初回発見例
症例4 経鼻内視鏡発見例(経口内視鏡偽陰性)
症例5 偽陰性例
症例6 偽陰性例
症例7 偽陰性例
症例8 偽陰性例
症例9 偽陰性例
症例10 偽陰性例
索引
更新情報
-
更新情報はありません。
お気に入り商品に追加すると、この商品の更新情報や関連情報などをマイページでお知らせいたします。