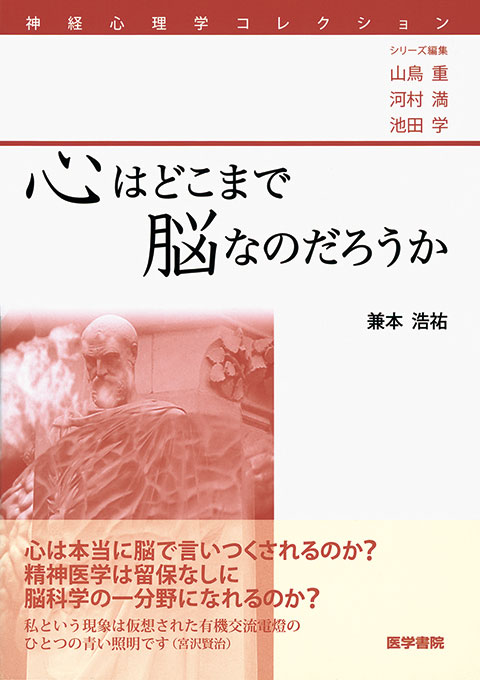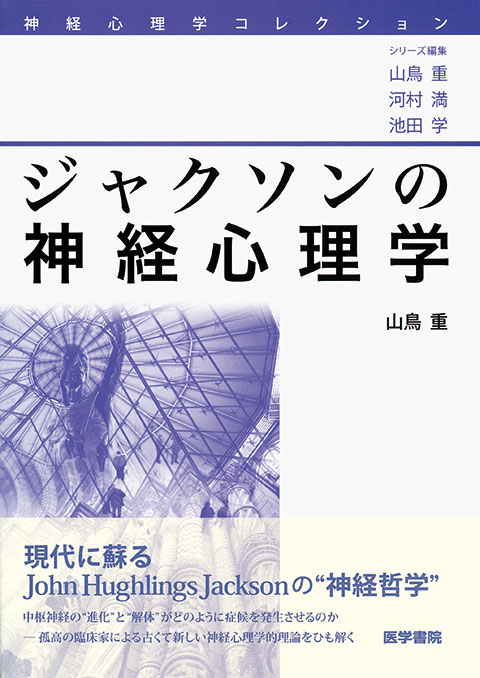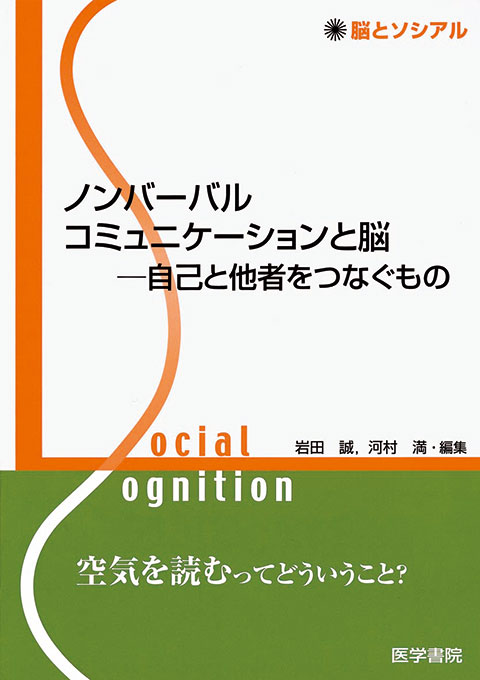心はどこまで脳なのだろうか
「私という現象」は本当に存在するのか、「心」はどこまで「脳」なのか
もっと見る
近年の脳科学の進歩や操作的診断基準の普及により、精神医学の拠って立つ地平が大きなパラダイムシフトを起こしている。患者の病的体験を直接的に「了解」しようとするアプローチは廃れ、あたかも精神医学が脳科学の一分野であるかのように語られている。しかし、本当に「心」はすべて「脳」で説明しきれるのだろうか。精神医学、脳科学の根本命題をめぐる、著者一流の考察。
*「神経心理学コレクション」は株式会社医学書院の登録商標です。
| シリーズ | 神経心理学コレクション |
|---|---|
| 著 | 兼本 浩祐 |
| シリーズ編集 | 山鳥 重 / 河村 満 / 池田 学 |
| 発行 | 2011年05月判型:A5頁:212 |
| ISBN | 978-4-260-01330-7 |
| 定価 | 3,740円 (本体3,400円+税) |
更新情報
-
更新情報はありません。
お気に入り商品に追加すると、この商品の更新情報や関連情報などをマイページでお知らせいたします。
- 序文
- 目次
- 書評
序文
開く
まえがき
少なくとも世紀の変わり目くらいまでは,多くの精神科医にとって,ヤスパースの精神病理学総論が括りだしたいくつかの鍵概念,了解可能性,発達か過程か,内因・外因・心因の区別,道具性の障害などは,診療や症例についての議論を行ううえでの基本的な原理であり続けていました。ところが今世紀に入って,驚くべき地殻変動が精神医学において地滑り的とも言える速度で起こり,多くのヤスパースの鍵概念は,批判して否定されるというよりは立ち止まって吟味されることもなく忘れられつつあります。これには操作的診断体系のグローバリゼーションを含め,複数の原因が関与していると思われますが,脳科学による精神という領域への侵入もその大きな原動力の1つとなっていることは間違いないことのように思えます。精神医学が扱う主要な領域は,「‘私’という現象」にかかわるわけですが,そもそも「‘私’という現象」の存在それ自体に対して,現在,脳科学は深刻な懐疑を差しはさんでいます。
こうしたなし崩し的な精神医学の変貌は,20世紀の精神医学的な営みの核心の1つであった「了解」という試みの価値を明らかに大きく減じてしまいました。統合失調症体験がその典型ですが,立場の違いを超えて20世紀後半の私たちは,私たちとは異なった体験の枠組みのうちにいる人たちが,どのように世界を体験しているかを可能な限り直接的に了解しようという試みに価値を見出していました。しかしこうした試みは,現在,たとえば前頭前部の障害によって社会的機能の不全が起こるといった認知科学的説明によって置き換えられ,統合失調症体験を自分のものとして了解しようという試みは,今やいささか時代錯誤的に響くようになっています。その結果,どのような異質な体験が病的体験においては生じているかということを可能な限りなぞり直そうというミンコフスキーが目指した20世紀的精神病理学の営みに対する関心は急速に失われつつあります。そしてこうした変化は,遅れていた精神医学という領域が,他の身体各科とようやく轡〈くつわ〉を並べることができるようになった精神医学の文明開化としておおむね好意的に受け取られています。確かに一部の精神分析的方向性を持った症例検討会などで以前見かけることのあったいくぶん閉鎖的な雰囲気と比べると,医師・患者関係をトレーナーとトレーニーの関係に置き換える認知行動療法はカリフォルニアの青空のようにカラッとしていて,日本の世紀末の精神療法に対する必要な修正を含んでいたことは確かなようにも思えます。しかし,他方で精神医学は本当に留保なしに脳科学の一分野となることができるのか,あるいは心は本当に脳で言いつくされるのかという問いを問い直すことには,いまなお意味があるようにも思えるのです。つまりはそれは,私たちは今や説明をするだけで,もう了解しなくてもよいのか,私たちは本当にヤスパースを乗り越えて過去のものとしたのかという問いでもあります。
この本のおおよその構成は以下のようになっています。最初に脳からの読み筋と心からの読み筋が簡単には1つに折り合えないことを,それぞれ脳の障害および心の葛藤によって引き起こされたと考えられる典型的な症例を取り上げて呈示しました(第1~3章)。次に脳からみた心は具体的にはどのようなシステムとして想定されるかを,これまで考案されてきた機械論的な説明をもとにイメージしました(第4,9,10,12,13章)。そして動物と人間の意識にもし断裂があるとしたら,その際に決定的な役割を果たす可能性のある事象として,対象を名づけるという構え,あるいは意味の生成について私見を展開しました(第6~8章,第11~13章)。さらに最終章の近くでは,脳から眺める限り,「‘私’という現象」には連続性はなく,私の連続性は,脳の外へと私が張り出していることからしか論じ得ないのではないかという問題を再考しました(第13~17章)。とはいえ,この本は各章毎にある程度独立したテーマを扱っていますから,少し難しそうな章は読み飛ばしてもらっておもしろそうな章から読んでいただいても大丈夫だと思います。
この本ができたのは一重に医学書院の樋口覚さんに忍耐強く待っていただいたお蔭であること,そして樋口さんとの友情の賜物であることをここに深謝しておきます。医局の小川ルミナさんには文献や本の取り寄せで医学書院の後藤エリカさんには校正でお世話になりました。深謝致します。
この本のいくつかの章では,「意識障害とは何か-精神医学的意識障害の再評価の試み」(精神神経学誌 106 : 1083-1109, 2004),「原罪としてのコギト-『生命のかたち/かたちの生命』を読んで」(イマーゴ 6 : 222-227, 1995),「「靴のようなもの」から「靴」へ-イデア論の再考」(イマーゴ 7 : 169-173, 1996),「意識障害とその展望」(精神医学 49 : 994-1002, 2007)の4篇の論文を手直しして再録してあります。また,「フロイト全集第一巻 解題」(岩波書店, 2009)の一部も手直しして再録しました。症例は臨床情報を除いては実際の人物からは大きく改変して掲載しています。また文献はある程度脚注に挙げてあり,残りを参考文献の欄に挙げてあります。この本は,一緒に働いている精神科医や心理の先生,研修医の先生達と休み時間や飲み会の時に雑談をしている時のミニ・カンファを念頭に置いて書きました。日頃あれこれ手助けをしてもらっている彼らと楽しく話せる話題の1つとなればとも思います。
平成23年4月 名古屋・長久手にて
兼本浩祐
少なくとも世紀の変わり目くらいまでは,多くの精神科医にとって,ヤスパースの精神病理学総論が括りだしたいくつかの鍵概念,了解可能性,発達か過程か,内因・外因・心因の区別,道具性の障害などは,診療や症例についての議論を行ううえでの基本的な原理であり続けていました。ところが今世紀に入って,驚くべき地殻変動が精神医学において地滑り的とも言える速度で起こり,多くのヤスパースの鍵概念は,批判して否定されるというよりは立ち止まって吟味されることもなく忘れられつつあります。これには操作的診断体系のグローバリゼーションを含め,複数の原因が関与していると思われますが,脳科学による精神という領域への侵入もその大きな原動力の1つとなっていることは間違いないことのように思えます。精神医学が扱う主要な領域は,「‘私’という現象」にかかわるわけですが,そもそも「‘私’という現象」の存在それ自体に対して,現在,脳科学は深刻な懐疑を差しはさんでいます。
こうしたなし崩し的な精神医学の変貌は,20世紀の精神医学的な営みの核心の1つであった「了解」という試みの価値を明らかに大きく減じてしまいました。統合失調症体験がその典型ですが,立場の違いを超えて20世紀後半の私たちは,私たちとは異なった体験の枠組みのうちにいる人たちが,どのように世界を体験しているかを可能な限り直接的に了解しようという試みに価値を見出していました。しかしこうした試みは,現在,たとえば前頭前部の障害によって社会的機能の不全が起こるといった認知科学的説明によって置き換えられ,統合失調症体験を自分のものとして了解しようという試みは,今やいささか時代錯誤的に響くようになっています。その結果,どのような異質な体験が病的体験においては生じているかということを可能な限りなぞり直そうというミンコフスキーが目指した20世紀的精神病理学の営みに対する関心は急速に失われつつあります。そしてこうした変化は,遅れていた精神医学という領域が,他の身体各科とようやく轡〈くつわ〉を並べることができるようになった精神医学の文明開化としておおむね好意的に受け取られています。確かに一部の精神分析的方向性を持った症例検討会などで以前見かけることのあったいくぶん閉鎖的な雰囲気と比べると,医師・患者関係をトレーナーとトレーニーの関係に置き換える認知行動療法はカリフォルニアの青空のようにカラッとしていて,日本の世紀末の精神療法に対する必要な修正を含んでいたことは確かなようにも思えます。しかし,他方で精神医学は本当に留保なしに脳科学の一分野となることができるのか,あるいは心は本当に脳で言いつくされるのかという問いを問い直すことには,いまなお意味があるようにも思えるのです。つまりはそれは,私たちは今や説明をするだけで,もう了解しなくてもよいのか,私たちは本当にヤスパースを乗り越えて過去のものとしたのかという問いでもあります。
この本のおおよその構成は以下のようになっています。最初に脳からの読み筋と心からの読み筋が簡単には1つに折り合えないことを,それぞれ脳の障害および心の葛藤によって引き起こされたと考えられる典型的な症例を取り上げて呈示しました(第1~3章)。次に脳からみた心は具体的にはどのようなシステムとして想定されるかを,これまで考案されてきた機械論的な説明をもとにイメージしました(第4,9,10,12,13章)。そして動物と人間の意識にもし断裂があるとしたら,その際に決定的な役割を果たす可能性のある事象として,対象を名づけるという構え,あるいは意味の生成について私見を展開しました(第6~8章,第11~13章)。さらに最終章の近くでは,脳から眺める限り,「‘私’という現象」には連続性はなく,私の連続性は,脳の外へと私が張り出していることからしか論じ得ないのではないかという問題を再考しました(第13~17章)。とはいえ,この本は各章毎にある程度独立したテーマを扱っていますから,少し難しそうな章は読み飛ばしてもらっておもしろそうな章から読んでいただいても大丈夫だと思います。
この本ができたのは一重に医学書院の樋口覚さんに忍耐強く待っていただいたお蔭であること,そして樋口さんとの友情の賜物であることをここに深謝しておきます。医局の小川ルミナさんには文献や本の取り寄せで医学書院の後藤エリカさんには校正でお世話になりました。深謝致します。
この本のいくつかの章では,「意識障害とは何か-精神医学的意識障害の再評価の試み」(精神神経学誌 106 : 1083-1109, 2004),「原罪としてのコギト-『生命のかたち/かたちの生命』を読んで」(イマーゴ 6 : 222-227, 1995),「「靴のようなもの」から「靴」へ-イデア論の再考」(イマーゴ 7 : 169-173, 1996),「意識障害とその展望」(精神医学 49 : 994-1002, 2007)の4篇の論文を手直しして再録してあります。また,「フロイト全集第一巻 解題」(岩波書店, 2009)の一部も手直しして再録しました。症例は臨床情報を除いては実際の人物からは大きく改変して掲載しています。また文献はある程度脚注に挙げてあり,残りを参考文献の欄に挙げてあります。この本は,一緒に働いている精神科医や心理の先生,研修医の先生達と休み時間や飲み会の時に雑談をしている時のミニ・カンファを念頭に置いて書きました。日頃あれこれ手助けをしてもらっている彼らと楽しく話せる話題の1つとなればとも思います。
平成23年4月 名古屋・長久手にて
兼本浩祐
目次
開く
第1章 心とは脳だろうか
第2章 あるピアニストの事例-心が体に置き換えられる
第3章 ある老画家の事例-脳が心を支配する
第4章 外因・内因・心因-神経回路網としての心と内因性精神疾患
第5章 デカルト的二元論
第6章 連合型視覚失認の事例-名づけられることの前と後
第7章 同じものが同じであることの奇跡
第8章 イデア論再考
第9章 ヤンツ教授の最終講義-てんかんとは「学習過程」“Lernprozess”である
第10章 心は計算式に置き換えられるか
第11章 犬がもし操作的に診断されたとしたら
第12章 プライミングとジョン・ヒューリングス・ジャクソン
第13章 心は開かれた形で生まれ、後に閉じることを学ばれる-並列処理の直列化
第14章 フロイトの無意識とは何か
第15章 漢方治療と官能的身体
第16章 精神分析における心的装置-それはたぶん脳の外に跨っている
エピローグ スピノザの幸福とデカルトの不幸
参考文献
索引
第2章 あるピアニストの事例-心が体に置き換えられる
第3章 ある老画家の事例-脳が心を支配する
第4章 外因・内因・心因-神経回路網としての心と内因性精神疾患
第5章 デカルト的二元論
第6章 連合型視覚失認の事例-名づけられることの前と後
第7章 同じものが同じであることの奇跡
第8章 イデア論再考
第9章 ヤンツ教授の最終講義-てんかんとは「学習過程」“Lernprozess”である
第10章 心は計算式に置き換えられるか
第11章 犬がもし操作的に診断されたとしたら
第12章 プライミングとジョン・ヒューリングス・ジャクソン
第13章 心は開かれた形で生まれ、後に閉じることを学ばれる-並列処理の直列化
第14章 フロイトの無意識とは何か
第15章 漢方治療と官能的身体
第16章 精神分析における心的装置-それはたぶん脳の外に跨っている
エピローグ スピノザの幸福とデカルトの不幸
参考文献
索引
書評
開く
知識や理論を臨床と結び付ける方法を伝える格好の書
書評者: 鈴木 國文 (名大教授・精神神経科学)
とにかく面白い本である。最初の頁から最後までワクワク感を失うことなく一気に読むことのできるまれな専門書の一つと言っていい。
なぜこの本がこれ程に面白いのか。それは,豊富な臨床例を踏まえ,その臨床場面から立ち上がる疑問を出発点に,その疑問について,単に教科書的理解でよしとするのではなく,手に入る理論のすべてを動員し,できる限り飛躍することなく疑問を埋めていく,そうした歩みを,この本は忠実に実行しているからである。難解な理論でけむに巻くようなところは一つもない。そのため,この本は,一人一人の精神科医が,さまざまな知識,さまざまな理論をどのように臨床と結び付けていけばいいのか,そのことを伝える格好の導きの書となっている。
たとえば,一足の靴について,それを靴と言い切ることができず,「靴のようなもの」としか認識できなくなった「連合型視覚失認」の症例を診たときの驚きから,著者は,「普通の人が一足の靴を見てそれを靴と呼び,何の過不足も感じないで済ますことができるのはなぜか」という問いを立てる。こうした問いを立てることは,哲学者ならともかく,普通の臨床家には,決して容易なことではない。たいていの場合,「これは連合型視覚失認である」という記述で終わってしまうのである。著者は,その症例の抱える困難から,脳の機能について,さらには脳が機能する際の言語の役割について,丁寧な推論を重ねる。そのスリリングな歩みは,精神について考える際に踏まえなければならない基本的な哲学的前提と,脳科学の最新知見の両方を,極めてわかりやすい形でわれわれに伝えてくれている。
著者,兼本浩祐という人は,どんな場面で雑談をしていても,常に相手を聞き入らせる不思議な技を持った人である。ある時,彼が「意味のない無駄話ならいくらでも続けることができるよ」と言うのを聞いたことがあるが,彼の話は,よく聞いていると,それぞれの断片がどんな遠いところからでも必ず核心へとつながっていく,そういう仕組みになっている。実は,無駄な話が一つもないのである。そう言えば,この本にも無駄なことが少しも書かれていない。理論のための理論のような無駄な論立てが,一切ないのである。
心の文法で読み解くべき事柄,脳の文法で読み解くべき事柄,その二つがどのようにつながり,どのように離れているのか,もちろんこれは,今日の科学における最大のハードプログラムの一つである。この問題に正面から向かい,これだけ平易に論述することは,てんかん学というフィールドでこの問題を考え続けてきた著者でなければ成しえない仕事と言えよう。しかも,この書で使われている日本語はきれいである。今,物事を頭に整理して入れようとするとき,どのような言葉を使えばいいのか,ここでの論述はその見事な範例と言えるだろう。
単に精神科医だけでなく,心を扱う多くの人に読んでほしい一書である。
書評者: 鈴木 國文 (名大教授・精神神経科学)
とにかく面白い本である。最初の頁から最後までワクワク感を失うことなく一気に読むことのできるまれな専門書の一つと言っていい。
なぜこの本がこれ程に面白いのか。それは,豊富な臨床例を踏まえ,その臨床場面から立ち上がる疑問を出発点に,その疑問について,単に教科書的理解でよしとするのではなく,手に入る理論のすべてを動員し,できる限り飛躍することなく疑問を埋めていく,そうした歩みを,この本は忠実に実行しているからである。難解な理論でけむに巻くようなところは一つもない。そのため,この本は,一人一人の精神科医が,さまざまな知識,さまざまな理論をどのように臨床と結び付けていけばいいのか,そのことを伝える格好の導きの書となっている。
たとえば,一足の靴について,それを靴と言い切ることができず,「靴のようなもの」としか認識できなくなった「連合型視覚失認」の症例を診たときの驚きから,著者は,「普通の人が一足の靴を見てそれを靴と呼び,何の過不足も感じないで済ますことができるのはなぜか」という問いを立てる。こうした問いを立てることは,哲学者ならともかく,普通の臨床家には,決して容易なことではない。たいていの場合,「これは連合型視覚失認である」という記述で終わってしまうのである。著者は,その症例の抱える困難から,脳の機能について,さらには脳が機能する際の言語の役割について,丁寧な推論を重ねる。そのスリリングな歩みは,精神について考える際に踏まえなければならない基本的な哲学的前提と,脳科学の最新知見の両方を,極めてわかりやすい形でわれわれに伝えてくれている。
著者,兼本浩祐という人は,どんな場面で雑談をしていても,常に相手を聞き入らせる不思議な技を持った人である。ある時,彼が「意味のない無駄話ならいくらでも続けることができるよ」と言うのを聞いたことがあるが,彼の話は,よく聞いていると,それぞれの断片がどんな遠いところからでも必ず核心へとつながっていく,そういう仕組みになっている。実は,無駄な話が一つもないのである。そう言えば,この本にも無駄なことが少しも書かれていない。理論のための理論のような無駄な論立てが,一切ないのである。
心の文法で読み解くべき事柄,脳の文法で読み解くべき事柄,その二つがどのようにつながり,どのように離れているのか,もちろんこれは,今日の科学における最大のハードプログラムの一つである。この問題に正面から向かい,これだけ平易に論述することは,てんかん学というフィールドでこの問題を考え続けてきた著者でなければ成しえない仕事と言えよう。しかも,この書で使われている日本語はきれいである。今,物事を頭に整理して入れようとするとき,どのような言葉を使えばいいのか,ここでの論述はその見事な範例と言えるだろう。
単に精神科医だけでなく,心を扱う多くの人に読んでほしい一書である。
更新情報
-
更新情報はありません。
お気に入り商品に追加すると、この商品の更新情報や関連情報などをマイページでお知らせいたします。