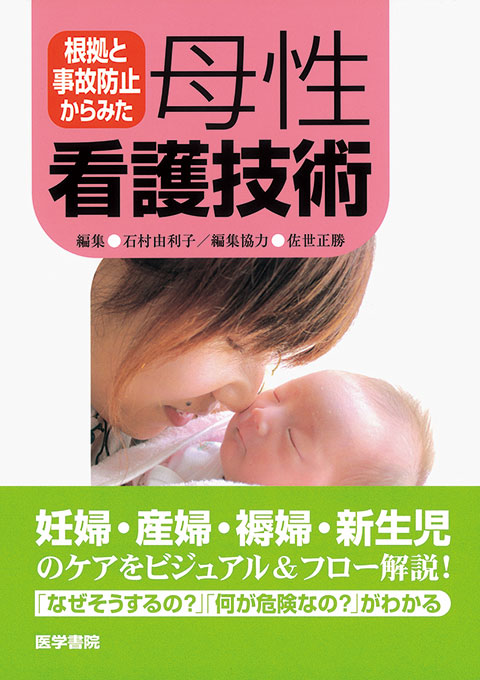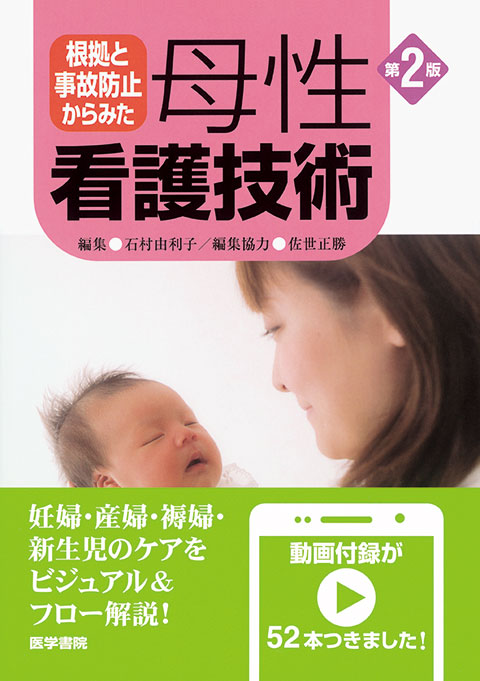根拠と事故防止からみた
母性看護技術
妊婦、産婦、褥婦、新生児それぞれに対する看護技術が写真とイラストでわかる!
もっと見る
母性看護では、健康問題を抱える対象のみでなく、順調な経過をたどる妊産褥婦・新生児を対象とすることが多い。一方で、妊娠・分娩経過では正常からの逸脱の予防、早期発見、適切なケアが欠かせない。そうした特徴を踏まえ、本書は妊婦、産婦、褥婦、新生児それぞれに対する看護技術を広く網羅し、写真とイラストを多用して解説。さらに、「根拠」「コツ」「注意」「事故防止のポイント」「緊急時対応」を豊富に記載した。
| シリーズ | からみた看護技術 |
|---|---|
| 編集 | 石村 由利子 |
| 編集協力 | 佐世 正勝 |
| 発行 | 2013年03月判型:A5頁:496 |
| ISBN | 978-4-260-01137-2 |
| 定価 | 4,180円 (本体3,800円+税) |
- 販売終了
更新情報
-
更新情報はありません。
お気に入り商品に追加すると、この商品の更新情報や関連情報などをマイページでお知らせいたします。
- 序文
- 目次
序文
開く
はじめに
「根拠と事故防止からみた」シリーズの『小児看護技術』『老年看護技術』の出版から遅れること7か月,やっと『母性看護技術』も発刊の運びとなりました.企画のお話をいただいてからの2年余の間には,初学者にわかりやすい本であることを念頭に,それぞれの看護技術を手順に沿って分解しながら,写真に収める場面の決定,記述の統一等々に多くの検討を重ねてきました.編集部の方々と様々な意見交換があったことが懐かしく思い出されます.
執筆者は単に手順を解説するにとどまらず,このシリーズが最も重視している根拠と事故防止という観点から,「なぜそうするのか」「なぜこうしたほうがいいのか」「何が危険なのか」を示しながら書き進めてきました.さらに,各執筆者がそれぞれの臨床経験のなかで培ったコツを伝えることで,技術の習得を容易にすることにも心がけました.看護技術は「絶対にこの方法以外してはならない」というものはほとんどなく,ケアの場や対象の特性に応じたアレンジが必要となります.根拠を知っていることによって応用が可能となり,対象への負担を減じて安全なケアを提供する一助になると思います.
母性看護学は,「性と生殖」をキーワードに,人の一生の様々なステージに広く関与する学問領域です.それぞれの時期に成長発達段階に応じた特有の健康問題があり,適切なケアが望まれることはいうまでもありません.決して妊娠や出産,育児に限局した領域ではありませんが,看護基礎教育のなかで,母性看護実習は主にマタニティサイクルに焦点を当てた学習の場として展開されます.
時々,学生から「母性看護学はむずかしい」という感想を耳にすることがあります.その理由の1つとして妊娠出産,子育てが病気ではない日常の営みであること,健康なレベルにある人々の健康問題を捉えることに慣れていないことがあげられます.さらに,母体の健康が次世代の健康に大きく影響し,母体を通して別の生命の健康をアセスメントするという他領域では経験しないことが重要な学習課題となっていることも考えられます.母体内現象を正しく把握するための診断技術は非日常的手法であり,可視化が困難なものは「むずかしい」という反応に結びつきやすいのだと思います.
加えて,他領域では使わない看護技術が多く,具体的なイメージが十分に形成されないまま臨地実習に臨むため,習得に困難を感じていることがあげられます.少子化の進む昨今,実習施設の確保が難しいことや地区の中核病院への実習生の集中により,かつてのように1人の学生が1組の周産期の母子を受け持つことが難しくなってきました.看護職の技術教育が高い専門性を追求する一方で,基本的なケア技術を経験する機会はより少なくなり,その少ない機会を効果的な学びの場とするために,いかにイメージを形成しておくかが大切となります.本書では写真を多用し,それに対応する記述で理解を促し,容易に自己学習を進めることができる内容になっています.実習の場でサブテキストとして活用していただけるものと思っています.
さらに付け加えるなら,臨床指導者の多くは助産師であり,ややもすると,その指導は母性看護学の教育内容の範疇を超えた課題に発展することがあります.実際,対象を目の前にしたとき,母性看護学と助産学との境界は明瞭ではなく,また,より広い視野でのアセスメントやケアを実践してほしいと望む指導者の思いも納得できるものです.
本書はタイトルを『母性看護技術』として看護学生の学習の一助となるよう企画されたものですが,助産学生,臨床の看護師・助産師の方々にも活用いただける一冊になっていると考えています.特に助産学生の学習にも役立つ内容でありたいと願い,助産の技術も収載しました.内診,分娩介助のように,法律上,看護師に許されていない技術もありますが,これらの解説を読むことで,診察の意義や行われている行為の理解を深めることができると信じています.
周産期医療・看護の場では,妊産褥婦特有の生理的変化に由来する事故や新生児の取り違えのような不幸な出来事,血液を介した感染の危険性など,細心の注意をもって防がなければならないことがたくさんあります.妊娠・分娩は正常に経過して当たり前であり,そのためのケアが求められます.看護実践に責任が問われる時代であり,根拠を説明できることはこれからますます重要なこととなるでしょう.常に根拠を考える姿勢をはぐくむことが大切であり,本書がその一端を担うことができれば幸いです.
本書の出版にあたり,多くの方々のお世話になりました.モデルになってくださった皆さま,撮影を許可して下さった施設の関係者の皆さま,その他多くのご尽力くださった皆さまのご協力に深く感謝申し上げます.とりわけ,出生間もない赤ちゃんたちの多様な表情には専門書であることを忘れ,心がなごみます.感謝とともに健やかな成長をお祈りいたします.
最後になりましたが,本書は医学書院編集者の方々の丁寧なご助言と温かいご支援によって完成しました.心よりお礼申し上げます.
2013年2月
著者を代表して 石村由利子
「根拠と事故防止からみた」シリーズの『小児看護技術』『老年看護技術』の出版から遅れること7か月,やっと『母性看護技術』も発刊の運びとなりました.企画のお話をいただいてからの2年余の間には,初学者にわかりやすい本であることを念頭に,それぞれの看護技術を手順に沿って分解しながら,写真に収める場面の決定,記述の統一等々に多くの検討を重ねてきました.編集部の方々と様々な意見交換があったことが懐かしく思い出されます.
執筆者は単に手順を解説するにとどまらず,このシリーズが最も重視している根拠と事故防止という観点から,「なぜそうするのか」「なぜこうしたほうがいいのか」「何が危険なのか」を示しながら書き進めてきました.さらに,各執筆者がそれぞれの臨床経験のなかで培ったコツを伝えることで,技術の習得を容易にすることにも心がけました.看護技術は「絶対にこの方法以外してはならない」というものはほとんどなく,ケアの場や対象の特性に応じたアレンジが必要となります.根拠を知っていることによって応用が可能となり,対象への負担を減じて安全なケアを提供する一助になると思います.
母性看護学は,「性と生殖」をキーワードに,人の一生の様々なステージに広く関与する学問領域です.それぞれの時期に成長発達段階に応じた特有の健康問題があり,適切なケアが望まれることはいうまでもありません.決して妊娠や出産,育児に限局した領域ではありませんが,看護基礎教育のなかで,母性看護実習は主にマタニティサイクルに焦点を当てた学習の場として展開されます.
時々,学生から「母性看護学はむずかしい」という感想を耳にすることがあります.その理由の1つとして妊娠出産,子育てが病気ではない日常の営みであること,健康なレベルにある人々の健康問題を捉えることに慣れていないことがあげられます.さらに,母体の健康が次世代の健康に大きく影響し,母体を通して別の生命の健康をアセスメントするという他領域では経験しないことが重要な学習課題となっていることも考えられます.母体内現象を正しく把握するための診断技術は非日常的手法であり,可視化が困難なものは「むずかしい」という反応に結びつきやすいのだと思います.
加えて,他領域では使わない看護技術が多く,具体的なイメージが十分に形成されないまま臨地実習に臨むため,習得に困難を感じていることがあげられます.少子化の進む昨今,実習施設の確保が難しいことや地区の中核病院への実習生の集中により,かつてのように1人の学生が1組の周産期の母子を受け持つことが難しくなってきました.看護職の技術教育が高い専門性を追求する一方で,基本的なケア技術を経験する機会はより少なくなり,その少ない機会を効果的な学びの場とするために,いかにイメージを形成しておくかが大切となります.本書では写真を多用し,それに対応する記述で理解を促し,容易に自己学習を進めることができる内容になっています.実習の場でサブテキストとして活用していただけるものと思っています.
さらに付け加えるなら,臨床指導者の多くは助産師であり,ややもすると,その指導は母性看護学の教育内容の範疇を超えた課題に発展することがあります.実際,対象を目の前にしたとき,母性看護学と助産学との境界は明瞭ではなく,また,より広い視野でのアセスメントやケアを実践してほしいと望む指導者の思いも納得できるものです.
本書はタイトルを『母性看護技術』として看護学生の学習の一助となるよう企画されたものですが,助産学生,臨床の看護師・助産師の方々にも活用いただける一冊になっていると考えています.特に助産学生の学習にも役立つ内容でありたいと願い,助産の技術も収載しました.内診,分娩介助のように,法律上,看護師に許されていない技術もありますが,これらの解説を読むことで,診察の意義や行われている行為の理解を深めることができると信じています.
周産期医療・看護の場では,妊産褥婦特有の生理的変化に由来する事故や新生児の取り違えのような不幸な出来事,血液を介した感染の危険性など,細心の注意をもって防がなければならないことがたくさんあります.妊娠・分娩は正常に経過して当たり前であり,そのためのケアが求められます.看護実践に責任が問われる時代であり,根拠を説明できることはこれからますます重要なこととなるでしょう.常に根拠を考える姿勢をはぐくむことが大切であり,本書がその一端を担うことができれば幸いです.
本書の出版にあたり,多くの方々のお世話になりました.モデルになってくださった皆さま,撮影を許可して下さった施設の関係者の皆さま,その他多くのご尽力くださった皆さまのご協力に深く感謝申し上げます.とりわけ,出生間もない赤ちゃんたちの多様な表情には専門書であることを忘れ,心がなごみます.感謝とともに健やかな成長をお祈りいたします.
最後になりましたが,本書は医学書院編集者の方々の丁寧なご助言と温かいご支援によって完成しました.心よりお礼申し上げます.
2013年2月
著者を代表して 石村由利子
目次
開く
はじめに
本書の構成と使い方
第1章 妊婦のケア
1.妊婦のアセスメント
1.インタビュー(問診)
2.バイタルサイン
3.視診
4.触診
(1)顔・上肢・乳房・乳頭・腹部・下肢
(2)レオポルド触診法
5.計測診
(1)身長・体重
(2)子宮底長・子宮底高・腹囲
(3)骨盤外計測
(4)ノンストレステスト(NST)
(5)バイオフィジカルプロファイルスコア(BPS)
6.聴診(胎児心音)
7.内診(介助)
2.妊婦の生活援助技術
1.食生活
2.排泄
3.清潔
4.運動
5.姿勢・日常生活動作
6.休息・睡眠
7.衣生活(更衣)
8.出産準備
第2章 産婦のケア
1.産婦のアセスメント
1.インタビュー(問診)
2.バイタルサイン
3.視診
4.触診
(1)顔・上肢・乳房・腹部・下肢
(2)ザイツ法
5.計測診
(1)超音波診断
児頭大横径の計測/羊水量の測定
(2)胎児心拍陣痛図(CTG)
6.内診(介助)
2.産婦の生活援助技術
1.食生活
2.排泄
3.清潔
4.活動・姿勢
5.休息・睡眠
3.分娩援助技術
1.出産環境の整備
2.分娩介助
分娩の準備/分娩介助の実際
3.胎盤計測
4.産痛緩和
第3章 褥婦のケア
1.褥婦のアセスメント
1.インタビュー(問診)
インタビューの準備/インタビューの実際
2.バイタルサイン
3.視診
4.触診
5.計測診
6.腟鏡診・内診(介助)
分娩直後(胎盤娩出後)/退院診察時
7.産褥復古の観察
子宮復古/悪露
8.乳汁分泌の観察
乳腺開口・射乳状態の観察/新生児の体重変化/搾乳量の観察/乳汁の観察
2.褥婦の生活援助技術
1.食生活
2.排泄
3.清潔
身体清拭・シャワー浴/外陰部の清潔ケア
4.動作・姿勢
動作(離床)への援助/姿勢への援助
5.休息・睡眠
3.産褥復古支援技術
1.産後.痛ケア
分娩損傷,脱肛・痔核の疼痛緩和の援助/後陣痛緩和の援助/
腰痛・恥骨痛緩和の援助/排尿時痛緩和の援助
2.悪露交換
3.脱肛・痔核への対処
整復/疼痛緩和の援助と指導/悪化防止の指導
4.排尿障害への対処
排尿障害の内容と程度の把握/尿閉時のケア/排尿時痛がある場合のケア
5.産褥体操
4.母乳育児支援技術
1.母乳育児支援
2.乳房トラブルのケア
乳房マッサージ(排乳介助)/乳頭痛のケア/乳房痛のケア
3.授乳
直接授乳/搾母乳の授乳/人工乳の授乳
4.搾乳
用手搾乳/搾乳器による搾乳
第4章 新生児のケア
1.新生児のアセスメント
1.バイタルサイン
(1)呼吸・心拍・体温
(2)アプガースコア
2.視診
(1)全身と便・尿の性状
(2)成熟度の診断
3.触診
4.身体計測
5.聴診
2.新生児の環境整備
1.室温・湿度・音・照明
2.事故・感染防止
3.新生児の養護技術
1.保温
2.点眼
3.臍処置
4.栄養
5.与薬(ビタミンK)
6.衣生活(更衣)
7.清潔
(1)おむつ交換
(2)沐浴
(3)ドライテクニック(全身清拭)
4.愛着行動支援技術
1.早期母子接触と母児同室
早期母子接触(出生直後~2時間)/母児同室
索引
本書の構成と使い方
第1章 妊婦のケア
1.妊婦のアセスメント
1.インタビュー(問診)
2.バイタルサイン
3.視診
4.触診
(1)顔・上肢・乳房・乳頭・腹部・下肢
(2)レオポルド触診法
5.計測診
(1)身長・体重
(2)子宮底長・子宮底高・腹囲
(3)骨盤外計測
(4)ノンストレステスト(NST)
(5)バイオフィジカルプロファイルスコア(BPS)
6.聴診(胎児心音)
7.内診(介助)
2.妊婦の生活援助技術
1.食生活
2.排泄
3.清潔
4.運動
5.姿勢・日常生活動作
6.休息・睡眠
7.衣生活(更衣)
8.出産準備
第2章 産婦のケア
1.産婦のアセスメント
1.インタビュー(問診)
2.バイタルサイン
3.視診
4.触診
(1)顔・上肢・乳房・腹部・下肢
(2)ザイツ法
5.計測診
(1)超音波診断
児頭大横径の計測/羊水量の測定
(2)胎児心拍陣痛図(CTG)
6.内診(介助)
2.産婦の生活援助技術
1.食生活
2.排泄
3.清潔
4.活動・姿勢
5.休息・睡眠
3.分娩援助技術
1.出産環境の整備
2.分娩介助
分娩の準備/分娩介助の実際
3.胎盤計測
4.産痛緩和
第3章 褥婦のケア
1.褥婦のアセスメント
1.インタビュー(問診)
インタビューの準備/インタビューの実際
2.バイタルサイン
3.視診
4.触診
5.計測診
6.腟鏡診・内診(介助)
分娩直後(胎盤娩出後)/退院診察時
7.産褥復古の観察
子宮復古/悪露
8.乳汁分泌の観察
乳腺開口・射乳状態の観察/新生児の体重変化/搾乳量の観察/乳汁の観察
2.褥婦の生活援助技術
1.食生活
2.排泄
3.清潔
身体清拭・シャワー浴/外陰部の清潔ケア
4.動作・姿勢
動作(離床)への援助/姿勢への援助
5.休息・睡眠
3.産褥復古支援技術
1.産後.痛ケア
分娩損傷,脱肛・痔核の疼痛緩和の援助/後陣痛緩和の援助/
腰痛・恥骨痛緩和の援助/排尿時痛緩和の援助
2.悪露交換
3.脱肛・痔核への対処
整復/疼痛緩和の援助と指導/悪化防止の指導
4.排尿障害への対処
排尿障害の内容と程度の把握/尿閉時のケア/排尿時痛がある場合のケア
5.産褥体操
4.母乳育児支援技術
1.母乳育児支援
2.乳房トラブルのケア
乳房マッサージ(排乳介助)/乳頭痛のケア/乳房痛のケア
3.授乳
直接授乳/搾母乳の授乳/人工乳の授乳
4.搾乳
用手搾乳/搾乳器による搾乳
第4章 新生児のケア
1.新生児のアセスメント
1.バイタルサイン
(1)呼吸・心拍・体温
(2)アプガースコア
2.視診
(1)全身と便・尿の性状
(2)成熟度の診断
3.触診
4.身体計測
5.聴診
2.新生児の環境整備
1.室温・湿度・音・照明
2.事故・感染防止
3.新生児の養護技術
1.保温
2.点眼
3.臍処置
4.栄養
5.与薬(ビタミンK)
6.衣生活(更衣)
7.清潔
(1)おむつ交換
(2)沐浴
(3)ドライテクニック(全身清拭)
4.愛着行動支援技術
1.早期母子接触と母児同室
早期母子接触(出生直後~2時間)/母児同室
索引
更新情報
-
更新情報はありません。
お気に入り商品に追加すると、この商品の更新情報や関連情報などをマイページでお知らせいたします。