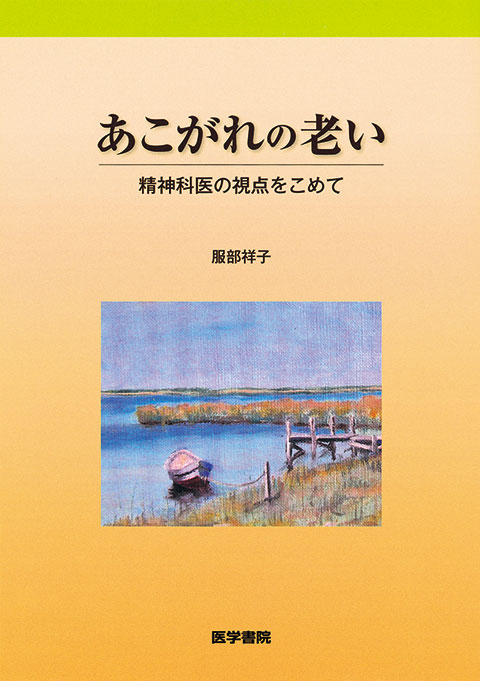あこがれの老い
精神科医の視点をこめて
老いの豊かさ、味わい深さ。老い人たちに向ける精神科医のまなざし。
もっと見る
人生の究極で問われるそれぞれの生き方。精神科医としての40年の臨床経験のなかで出会った人々のエピソードを語りながら、成熟の輝きを放つ先人たちを12章にわたって紹介し、老いの豊かさ、味わい深さ、老いの醍醐味を論じる。人は生涯にわたって成長・発達し続けるものであるとする著者の人間讃歌。高齢者ケアを専門とされる方々に、またやがて訪れる自らの「老い」に思いをめぐらす方々にもぜひ読んでいただきたい。
| 著 | 服部 祥子 |
|---|---|
| 発行 | 2008年10月判型:B6頁:280 |
| ISBN | 978-4-260-00744-3 |
| 定価 | 2,200円 (本体2,000円+税) |
更新情報
-
更新情報はありません。
お気に入り商品に追加すると、この商品の更新情報や関連情報などをマイページでお知らせいたします。
- 序文
- 目次
- 書評
序文
開く
はじめに
加齢は宿命的に心身の老化をきたし、どんな人も体力の衰えを感じ生気が失われていくことから免れ得ない。しかし生涯のそれぞれの段階がそうであるように、老いには苦しみや悩みとともに老い固有の価値や魅力があり、人間的な成熟のチャンスは十分にある。
数年前に、私自身も高齢者と公的に定められている年齢(六五歳)を迎えた。寿命が驚異的に延びている現代日本社会にあっては、まだ老いの入口に立つに過ぎないのかもしれないが、ひとつの節目を越した今、老いについて私なりに考えてみようと思い立った。その時最初に頭に浮かんだ言葉が「憧れ」である。
わが行く手の老いに思いをめぐらすとき、一番似合っている心性が憧れなのだと気づき、私はひとり苦笑した。なぜなら憧れは無限の可能性を秘めた思春期にこそふさわしい特性と一般的にいわれ、私自身もそう考えてきた。それがもはや良きも悪しきも多くの未知は既知となり、希望しても新たな能力や可能性の拓ける機会は少なく、残り時間も乏しい老年期にいたってなお憧れとは……という、半ば滑稽とさえ感じられる思いである。
しかし老年期を迎えた今こそ憧れをもちたい。自分の人格や気概や努力と無関係に、いつどんなできごとに遭遇し、脳や身体機能の壊滅が訪れるのか計り知れず、希望通りの老いを生きられるという保証はどこにもない。だからこそ、自分というものをはっきり意識している間は、先人の生き方を慕い、思いを寄せ、憧れの翼を広げてみたいのである。
思えば人は幼少期よりさまざまな経験やできごとに遭遇し、発達をしつつ老いを迎える。したがって老いはその人の人生の究極であり、総決算である。それまでの日々をどう生きたかが老いに至って問われるのである。
しかし人生最後のライフステージに至ってなお、残り少ない時間の中で、ことに絶望に足をすくわれそうになりながらも、人は思いもかけぬ新しい発想や観念や行動を生み出すことがあるのを、精神科医として何度も見てきた。わが憧れの老い人(びと)にもそれを強く感じることが多い。それこそが老いのだいご味だと思う。
とはいえ、人間は連綿と続く人生という時間の中で、唯一無二の自分というものを発達させていくという生涯人間発達論を唱える立場に私は立っているので、老いの新しい輝きもまた唐突なものではなく、その元となるものがその人の内に存在しており、それが立ち上がってきたと考える。遺伝や胎内性とともに幼少期や若き日の体験がどんなに小さくても火種のように灯されており、それが老いに至って大きく燃え上がり、その人の人間性を内側より豊かに発達させるのだと思う。
詩人のポール・エリュアールはこんな風に詩(うた)っている。
年をとる。それは己が青春を
歳月の中で 組織することだ
(大岡 信訳)
縦糸、横糸、斜め糸、ほつれ糸、迷い糸など、さまざまな糸が織りなされて味わい深い柄の一枚の布ができ上がるように、人が年をとるということは、青く若々しい青春の時から、偶然と必然のおびただしいできごとを織り込み組織しつつ、人生という布にその人固有の作品を仕立てあげていくことのような気がする。その意味から言えば、今目の前にいる思春期の若者に老いの姿を想像することと、今は老人となった人々の思春期に思いを馳(は)せることは、どこかで脈々とつながっているのかもしれない。
思春期を専門として生きてきた精神科医であるから、わが憧れの老い人(びと)を眺める時、ごく自然にその人の幼き日や青春の季節に私はまなざしを向ける。本書にとりあげた憧れの先人たちのみならず、まわりの老い人(びと)たちの一人ひとりを眺める時にも、私は今現在の老いたその人の姿のみに視野を限定せず、それまでの歩み来し道に目を向ける姿勢を忘れまいと思う。そうすることで、どんな老い人(びと)にもその存在の厚みと味わいを見出すことができると信じているからである。
服部祥子
加齢は宿命的に心身の老化をきたし、どんな人も体力の衰えを感じ生気が失われていくことから免れ得ない。しかし生涯のそれぞれの段階がそうであるように、老いには苦しみや悩みとともに老い固有の価値や魅力があり、人間的な成熟のチャンスは十分にある。
数年前に、私自身も高齢者と公的に定められている年齢(六五歳)を迎えた。寿命が驚異的に延びている現代日本社会にあっては、まだ老いの入口に立つに過ぎないのかもしれないが、ひとつの節目を越した今、老いについて私なりに考えてみようと思い立った。その時最初に頭に浮かんだ言葉が「憧れ」である。
わが行く手の老いに思いをめぐらすとき、一番似合っている心性が憧れなのだと気づき、私はひとり苦笑した。なぜなら憧れは無限の可能性を秘めた思春期にこそふさわしい特性と一般的にいわれ、私自身もそう考えてきた。それがもはや良きも悪しきも多くの未知は既知となり、希望しても新たな能力や可能性の拓ける機会は少なく、残り時間も乏しい老年期にいたってなお憧れとは……という、半ば滑稽とさえ感じられる思いである。
しかし老年期を迎えた今こそ憧れをもちたい。自分の人格や気概や努力と無関係に、いつどんなできごとに遭遇し、脳や身体機能の壊滅が訪れるのか計り知れず、希望通りの老いを生きられるという保証はどこにもない。だからこそ、自分というものをはっきり意識している間は、先人の生き方を慕い、思いを寄せ、憧れの翼を広げてみたいのである。
思えば人は幼少期よりさまざまな経験やできごとに遭遇し、発達をしつつ老いを迎える。したがって老いはその人の人生の究極であり、総決算である。それまでの日々をどう生きたかが老いに至って問われるのである。
しかし人生最後のライフステージに至ってなお、残り少ない時間の中で、ことに絶望に足をすくわれそうになりながらも、人は思いもかけぬ新しい発想や観念や行動を生み出すことがあるのを、精神科医として何度も見てきた。わが憧れの老い人(びと)にもそれを強く感じることが多い。それこそが老いのだいご味だと思う。
とはいえ、人間は連綿と続く人生という時間の中で、唯一無二の自分というものを発達させていくという生涯人間発達論を唱える立場に私は立っているので、老いの新しい輝きもまた唐突なものではなく、その元となるものがその人の内に存在しており、それが立ち上がってきたと考える。遺伝や胎内性とともに幼少期や若き日の体験がどんなに小さくても火種のように灯されており、それが老いに至って大きく燃え上がり、その人の人間性を内側より豊かに発達させるのだと思う。
詩人のポール・エリュアールはこんな風に詩(うた)っている。
年をとる。それは己が青春を
歳月の中で 組織することだ
(大岡 信訳)
縦糸、横糸、斜め糸、ほつれ糸、迷い糸など、さまざまな糸が織りなされて味わい深い柄の一枚の布ができ上がるように、人が年をとるということは、青く若々しい青春の時から、偶然と必然のおびただしいできごとを織り込み組織しつつ、人生という布にその人固有の作品を仕立てあげていくことのような気がする。その意味から言えば、今目の前にいる思春期の若者に老いの姿を想像することと、今は老人となった人々の思春期に思いを馳(は)せることは、どこかで脈々とつながっているのかもしれない。
思春期を専門として生きてきた精神科医であるから、わが憧れの老い人(びと)を眺める時、ごく自然にその人の幼き日や青春の季節に私はまなざしを向ける。本書にとりあげた憧れの先人たちのみならず、まわりの老い人(びと)たちの一人ひとりを眺める時にも、私は今現在の老いたその人の姿のみに視野を限定せず、それまでの歩み来し道に目を向ける姿勢を忘れまいと思う。そうすることで、どんな老い人(びと)にもその存在の厚みと味わいを見出すことができると信じているからである。
服部祥子
目次
開く
はじめに
第1章 わが友ハロルド
――明朗さを保ち続けた老い
第2章 西行
――途上のものであり続けた老い
第3章 小説『マディソン郡の橋』のフランチェスカ、『心のおもむくままに』のオルガ
――心の地下室を開いた老い
第4章 ヘルマン・ヘッセ
――心の葛藤を闘いぬいた老い
第5章 メイ・サートン
――最後まで孤独を手放さなかった老い
第6章 池波正太郎
――職人技を楽しんだ老い
第7章 映画『八月の鯨』のリビーとセーラ、『永遠と一日』のアレクサンドレ
――人生と和解した老い
第8章 多田富雄さん
――障害とともに生きる老い
第9章 須賀敦子
――深い沈黙を湛えた老い
第10章 モリー先生
――天職を全うした老い
第11章 新藤兼人・乙羽信子夫妻、小説『リトル・トリー』の祖父母
――カップルとして生き抜く老い
第12章 フランシス・ジャム
――信仰と愛をもち続けた老い
おわりに
第1章 わが友ハロルド
――明朗さを保ち続けた老い
第2章 西行
――途上のものであり続けた老い
第3章 小説『マディソン郡の橋』のフランチェスカ、『心のおもむくままに』のオルガ
――心の地下室を開いた老い
第4章 ヘルマン・ヘッセ
――心の葛藤を闘いぬいた老い
第5章 メイ・サートン
――最後まで孤独を手放さなかった老い
第6章 池波正太郎
――職人技を楽しんだ老い
第7章 映画『八月の鯨』のリビーとセーラ、『永遠と一日』のアレクサンドレ
――人生と和解した老い
第8章 多田富雄さん
――障害とともに生きる老い
第9章 須賀敦子
――深い沈黙を湛えた老い
第10章 モリー先生
――天職を全うした老い
第11章 新藤兼人・乙羽信子夫妻、小説『リトル・トリー』の祖父母
――カップルとして生き抜く老い
第12章 フランシス・ジャム
――信仰と愛をもち続けた老い
おわりに
書評
開く
知命の齢が近づきつつある人すべてに薦めたい一冊
書評者: 清水 將之 (前 日本児童青年精神医学会理事長)
◆老いを考えるということ
高齢者問題が,国家財政,営利福祉,人情・家庭事情など幅広く話題となる時代なので,老人や老齢を語る書物が陸続と刊行されている。老いについての書物は,若いころに触れたキケロ以外はほとんど読んだことがない。本書は例外である。
老いをあこがれる,とはどういうことか,と訝った。読んで,著者の思惑がわかった。
1年間の雑誌連載をまとめたという成立にも由るのだろう,12通りに老いが類型化されている。みな魅力的である。そのすべてに著者は強い憧憬を寄せている。ここから書名が誕生したのであろう。才女が,思いつくままに連載メモを作っていたら,望ましい老いが12か月分となったのか。須賀敦子についての語り(第9章)のみが他に比して異様に長文となっている。どうしてか。著者の生と重なり合うところがあるのだろうか。そこは,読者それぞれが揣摩臆測(しまおくそく)に興ずればよろしかろう。読書というものの楽しいところでもある。
◆青年期と老年期
著者は,評者が始めた思春期の精神科医療を,同じ土地で力強く継承・展開してくれた後輩である。そのような職種事情のため,人を測るこの著者の視点は常に,幼少期からの育ち,そして思春期における成熟への大転換を基点としている。
老い行くことに関しても然り。このところが恐らく,山積する老年本と大きく異なるのであろうと忖度する。一例のみ挙げれば,西行の生涯を追った第二章。20歳過ぎと70歳と,半世紀を分けた同一人物の詠唱を並べ,青年期にして既に西行は成熟を果しており,古希を迎えてなお若さを維持していることへの賛嘆を語っている。
◆美しく老いる準備
幼児期に愛されることが思春期の通過を一層安全にし,思春期に悩み苦しみ,そこを支えられ信頼されることが成熟を保障する。そのことのために児童思春期精神科医は存在する,著者はそう考えつつ臨床を重ねてきた。この人は「生きる力の火種」ということばを愛用している。思春期は火種を培う年ごろ,それが成立すればおとなに向けての成熟過程が安定するという。今回の書物では,火種が培われておれば満たされた老年期を歩むことが可能になると拡伸(かくしん)し,さまざまな人生事例からこのことを説伏(せっぷく)しようと企てる。
◆老いへのあこがれ
老年期に達したがゆえに見えてくるもの,味得でき腑に落ちること,遠慮なく語れることば(この書評も含め)がたくさん用意されている。そのことを評者も古希を超える前後から実感しつつ暮らしている。そのような枠組みに座して本書をひもとけば,生の多様な読みようを教えられ,来し方の意味をあらためて考えさせられる。そのような書物である。
青年期に本書を読んで感動する人がいたとすれば,不気味である。壮年期では,この域まで視線が届き難かろう。耳順(じじゅん,60歳)ではいささか遅い。いまの不惑は元気過ぎて読み流されてしまうかもしれない。知命(ちめい,50歳)の齢が近づきつつある人はすべて,本書に接することを薦める。さすれば,必ずや,充実して穏やかな老後を喫する可能性を見いだすであろう。
書評者: 清水 將之 (前 日本児童青年精神医学会理事長)
◆老いを考えるということ
高齢者問題が,国家財政,営利福祉,人情・家庭事情など幅広く話題となる時代なので,老人や老齢を語る書物が陸続と刊行されている。老いについての書物は,若いころに触れたキケロ以外はほとんど読んだことがない。本書は例外である。
老いをあこがれる,とはどういうことか,と訝った。読んで,著者の思惑がわかった。
1年間の雑誌連載をまとめたという成立にも由るのだろう,12通りに老いが類型化されている。みな魅力的である。そのすべてに著者は強い憧憬を寄せている。ここから書名が誕生したのであろう。才女が,思いつくままに連載メモを作っていたら,望ましい老いが12か月分となったのか。須賀敦子についての語り(第9章)のみが他に比して異様に長文となっている。どうしてか。著者の生と重なり合うところがあるのだろうか。そこは,読者それぞれが揣摩臆測(しまおくそく)に興ずればよろしかろう。読書というものの楽しいところでもある。
◆青年期と老年期
著者は,評者が始めた思春期の精神科医療を,同じ土地で力強く継承・展開してくれた後輩である。そのような職種事情のため,人を測るこの著者の視点は常に,幼少期からの育ち,そして思春期における成熟への大転換を基点としている。
老い行くことに関しても然り。このところが恐らく,山積する老年本と大きく異なるのであろうと忖度する。一例のみ挙げれば,西行の生涯を追った第二章。20歳過ぎと70歳と,半世紀を分けた同一人物の詠唱を並べ,青年期にして既に西行は成熟を果しており,古希を迎えてなお若さを維持していることへの賛嘆を語っている。
◆美しく老いる準備
幼児期に愛されることが思春期の通過を一層安全にし,思春期に悩み苦しみ,そこを支えられ信頼されることが成熟を保障する。そのことのために児童思春期精神科医は存在する,著者はそう考えつつ臨床を重ねてきた。この人は「生きる力の火種」ということばを愛用している。思春期は火種を培う年ごろ,それが成立すればおとなに向けての成熟過程が安定するという。今回の書物では,火種が培われておれば満たされた老年期を歩むことが可能になると拡伸(かくしん)し,さまざまな人生事例からこのことを説伏(せっぷく)しようと企てる。
◆老いへのあこがれ
老年期に達したがゆえに見えてくるもの,味得でき腑に落ちること,遠慮なく語れることば(この書評も含め)がたくさん用意されている。そのことを評者も古希を超える前後から実感しつつ暮らしている。そのような枠組みに座して本書をひもとけば,生の多様な読みようを教えられ,来し方の意味をあらためて考えさせられる。そのような書物である。
青年期に本書を読んで感動する人がいたとすれば,不気味である。壮年期では,この域まで視線が届き難かろう。耳順(じじゅん,60歳)ではいささか遅い。いまの不惑は元気過ぎて読み流されてしまうかもしれない。知命(ちめい,50歳)の齢が近づきつつある人はすべて,本書に接することを薦める。さすれば,必ずや,充実して穏やかな老後を喫する可能性を見いだすであろう。
更新情報
-
更新情報はありません。
お気に入り商品に追加すると、この商品の更新情報や関連情報などをマイページでお知らせいたします。