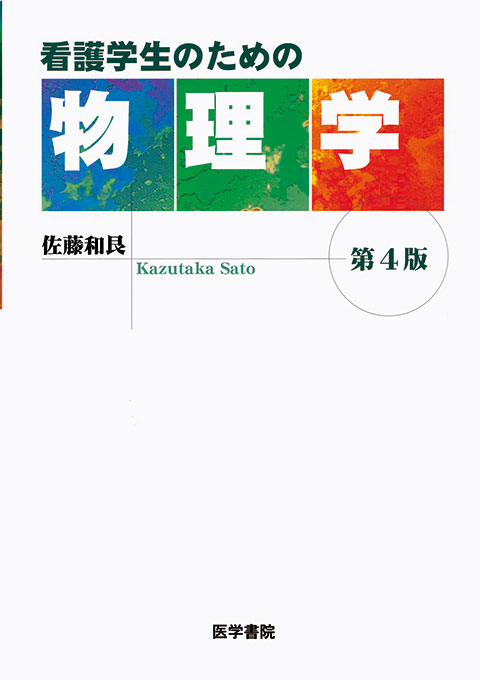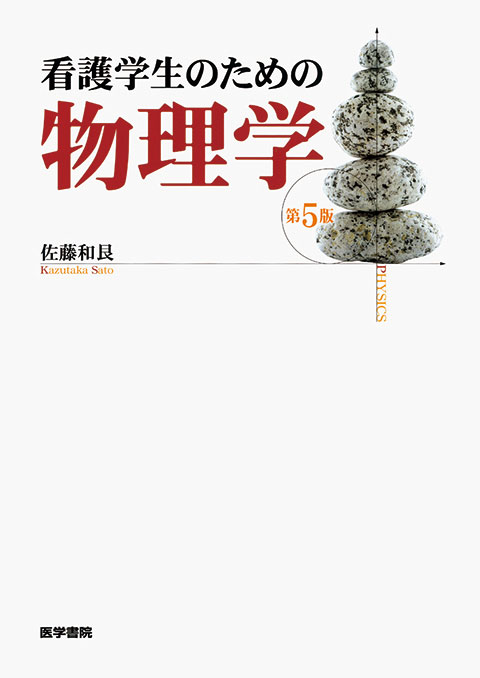看護学生のための物理学 第4版
臨床の看護行為や人体のしくみを通して、物理学的思考が自然と身につくテキスト
もっと見る
看護学生が不得手で興味をもちづらい物理学を臨床の看護行為や人体のしくみに関連させ、豊富な図を用いてわかりやすく解説したテキスト。ボディメカニクスやてこの原理、点滴静注に関連した物理や呼吸器・循環器がどう物理学と関わっているかを学ぶうちに、自然と物理学的思考が身につき、科学的な目で看護に関わる現象を理解できるようになる。
| 著 | 佐藤 和艮 |
|---|---|
| 発行 | 2008年11月判型:B5頁:200 |
| ISBN | 978-4-260-00651-4 |
| 定価 | 2,420円 (本体2,200円+税) |
- 販売終了
更新情報
-
更新情報はありません。
お気に入り商品に追加すると、この商品の更新情報や関連情報などをマイページでお知らせいたします。
- 序文
- 目次
序文
開く
第4版の序
筆者が初めて看護学生に向き合い「看護学生のための物理学」を手探りし始めてから約40年が経過し,そしてばらばらの講義プリントが,教科書『看護学生のための物理学』として形を整えてからも約20年になる。この間,医療現場も日進月歩で大きく様変わりし,患者の意識や看護師の任務も変わってきた。また看護学生の気質や意識もずいぶん変わってきた。そうした変化に対応して本書も内容を書き改め,この度,第4版を出版することになった。本書の基本的学習姿勢である「どうなっているのだろう? なぜだろう? どうしたらよいのだろう!」は踏襲した。知的好奇心に基づいて現象をみつめ,学際的なさまざまな知識を有効につなぎ合わせて真理に迫り,必要な判断を下し,最も有効な対処法を見出すことをめざした。また,本書でとくに大事にした精神は,科学の立場から見た人間讃歌である。この精神で患者に接し,同時に自分自身も大事にして有意義な人生を送ってほしい。
初版から第3版までの本書は,「物理講義編」「物理実験編」「遊び心の物理」の3部構成であった。『物理学』は,文字通り『物』の『理(ことわり)』を深める学問であり,『物』を扱うからには,まず「物をよく見て,その性質を詳しく調べる」態度が大切である。この態度は看護の精神とも共通しているので,第3版までは「物理実験編」として記述した。また,これからの看護を担う看護学生には,幅広い学問を楽しみながら学び,豊かな人間性を培ってもらうために「遊び心の物理」を提案した。従来の看護教育には,「一般教養を深めたうえで専門教科をしっかりと」というよき雰囲気があった。しかし時代の要請で課題が増加し,看護学の枠組みも変わり,カリキュラムが窮屈になってきた。教育現場では,物理学の履修を取り止めたり,あるいは時間数を半減させるなどしている。看護教育の中で,「物理実験」や「遊び心の物理」を学習する余地がほとんど失われてしまったことは,大変残念なことである。第4版ではやむなくこれらの紙面を削除し,そこで扱った内容はできるだけ第8章までの関連する章の中に統合した。とくに「遊び心の物理」の内容は,章末の[付録]に「観察と思考の物理」として記述した。本書の使用に関しては,まずこの[付録]を読み,いわゆる「物理嫌い」の気風を一掃してもらってから最初に戻り,第1章から順次学んでもらうと効果的ではないかと思われる。
物理学では数式表現が多用されるが,本書では数式を覚えたり,計算で正解を得ることなどを目的としていない。数式は各要素相互の関係を簡潔に示す表現方法の1つである。「散文」と同じ内容を,「詩」で簡潔に表現したようなものと思ってほしい。数式は,「ある要素が大きくなれば,結果としてこれが大きくなる」「相互関係は,なるほどそんなものか」と感覚的に概観する程度で十分である。後半ではかなり多くの数式が登場するが,そのすべてを確実に習熟するなどの必要は毛頭ない。「看護や人体といった複雑な現象でも,これを数式で表わし計算から結果を推察できる」といった学問的面白さをみてほしい。数式表現にも臆せず,これを乗り越えてどんどんと前へ読み進んでもらいたい。
本書で取り上げたテーマは,物理学の学問体系のうちのほんの一部であり,また看護学と物理学との関わりもこれ以外にも数多くあり,それらすべてを極めようとしたら切りがない。そうした広範な中から本書では8テーマを選んだにすぎないが,これだけの学習でも視野を広めたり,思考を深めたり,必要な知識を増やしたりと,学ぶ意義は十分にあると思われる。本書のこうした内容は,看護学生や卒業生,そして看護教員たちとの話し合いや提言によって生み出されたものである。本書はこうした多くの皆さんの支援を受けた結果であることを申し添え,感謝の意を表わしたい。
今の世の中の数多くの職業の選択肢の中から,あえて看護の道を選び,日夜努力している看護学生の皆さん,非常に立派な心掛けで貴重なことだと思います。価値のある仕事のために今後予想される苦労や困難は乗り越えて頑張ろうとしている若い学生,一度社会に出て経験を重ねる中で看護に真の価値を見出して若い学生と一緒に切磋琢磨する年輩の学生,幼い子供を預けながら学校へ実習場へと通うママさん学生,そしてまだ少数派で大多数の女子学生の中で何かと苦労し頑張っている男子学生,それぞれがいい所を出し合って一緒に勉強し,立派な看護師に成長していって下さい。世の中の人たちは,皆さんの情熱あふれる優秀な看護を期待し待っています。心よりの声援を送ります。
2008年10月
著者
筆者が初めて看護学生に向き合い「看護学生のための物理学」を手探りし始めてから約40年が経過し,そしてばらばらの講義プリントが,教科書『看護学生のための物理学』として形を整えてからも約20年になる。この間,医療現場も日進月歩で大きく様変わりし,患者の意識や看護師の任務も変わってきた。また看護学生の気質や意識もずいぶん変わってきた。そうした変化に対応して本書も内容を書き改め,この度,第4版を出版することになった。本書の基本的学習姿勢である「どうなっているのだろう? なぜだろう? どうしたらよいのだろう!」は踏襲した。知的好奇心に基づいて現象をみつめ,学際的なさまざまな知識を有効につなぎ合わせて真理に迫り,必要な判断を下し,最も有効な対処法を見出すことをめざした。また,本書でとくに大事にした精神は,科学の立場から見た人間讃歌である。この精神で患者に接し,同時に自分自身も大事にして有意義な人生を送ってほしい。
初版から第3版までの本書は,「物理講義編」「物理実験編」「遊び心の物理」の3部構成であった。『物理学』は,文字通り『物』の『理(ことわり)』を深める学問であり,『物』を扱うからには,まず「物をよく見て,その性質を詳しく調べる」態度が大切である。この態度は看護の精神とも共通しているので,第3版までは「物理実験編」として記述した。また,これからの看護を担う看護学生には,幅広い学問を楽しみながら学び,豊かな人間性を培ってもらうために「遊び心の物理」を提案した。従来の看護教育には,「一般教養を深めたうえで専門教科をしっかりと」というよき雰囲気があった。しかし時代の要請で課題が増加し,看護学の枠組みも変わり,カリキュラムが窮屈になってきた。教育現場では,物理学の履修を取り止めたり,あるいは時間数を半減させるなどしている。看護教育の中で,「物理実験」や「遊び心の物理」を学習する余地がほとんど失われてしまったことは,大変残念なことである。第4版ではやむなくこれらの紙面を削除し,そこで扱った内容はできるだけ第8章までの関連する章の中に統合した。とくに「遊び心の物理」の内容は,章末の[付録]に「観察と思考の物理」として記述した。本書の使用に関しては,まずこの[付録]を読み,いわゆる「物理嫌い」の気風を一掃してもらってから最初に戻り,第1章から順次学んでもらうと効果的ではないかと思われる。
物理学では数式表現が多用されるが,本書では数式を覚えたり,計算で正解を得ることなどを目的としていない。数式は各要素相互の関係を簡潔に示す表現方法の1つである。「散文」と同じ内容を,「詩」で簡潔に表現したようなものと思ってほしい。数式は,「ある要素が大きくなれば,結果としてこれが大きくなる」「相互関係は,なるほどそんなものか」と感覚的に概観する程度で十分である。後半ではかなり多くの数式が登場するが,そのすべてを確実に習熟するなどの必要は毛頭ない。「看護や人体といった複雑な現象でも,これを数式で表わし計算から結果を推察できる」といった学問的面白さをみてほしい。数式表現にも臆せず,これを乗り越えてどんどんと前へ読み進んでもらいたい。
本書で取り上げたテーマは,物理学の学問体系のうちのほんの一部であり,また看護学と物理学との関わりもこれ以外にも数多くあり,それらすべてを極めようとしたら切りがない。そうした広範な中から本書では8テーマを選んだにすぎないが,これだけの学習でも視野を広めたり,思考を深めたり,必要な知識を増やしたりと,学ぶ意義は十分にあると思われる。本書のこうした内容は,看護学生や卒業生,そして看護教員たちとの話し合いや提言によって生み出されたものである。本書はこうした多くの皆さんの支援を受けた結果であることを申し添え,感謝の意を表わしたい。
今の世の中の数多くの職業の選択肢の中から,あえて看護の道を選び,日夜努力している看護学生の皆さん,非常に立派な心掛けで貴重なことだと思います。価値のある仕事のために今後予想される苦労や困難は乗り越えて頑張ろうとしている若い学生,一度社会に出て経験を重ねる中で看護に真の価値を見出して若い学生と一緒に切磋琢磨する年輩の学生,幼い子供を預けながら学校へ実習場へと通うママさん学生,そしてまだ少数派で大多数の女子学生の中で何かと苦労し頑張っている男子学生,それぞれがいい所を出し合って一緒に勉強し,立派な看護師に成長していって下さい。世の中の人たちは,皆さんの情熱あふれる優秀な看護を期待し待っています。心よりの声援を送ります。
2008年10月
著者
目次
開く
1.重いものを持つにはどうしたらよいか
A.力のモーメント
B.てこの原理の人体中での応用
C.筋肉の張力と関節にはたらく力の大きさ
D.腰にかかる力
2.看護ボディメカニクスの物理
A.ベッド上の患者を起こす方法
B.小さな力でも大きな効果が
C.看護ボディメカニクスの物理的重点事項
3.身近かな圧力
A.圧力とは何か
B.もし気圧が変わったら人間はどうなるか
C.入浴とベッドの圧力効果
4.呼吸器と吸引の物理
A.肺はどのようにして呼吸をするか
B.吸引(ドレナージ)
C.サイフォン
5.点滴静脈注射の物理
A.ボトルごとの点滴セッティングの違い
B.流量の調節
C.ボトルの高さ
D.滴下装置内の物理
6.循環器の物理
A.ポンプとしての心臓
B.血液循環と血圧
C.血圧が測定できる理由
D.水銀血圧計の知識
E.いろいろなタイプの血圧計
F.血圧の重力による影響
7.感覚器の物理
A.感覚の大きさ
B.聴覚の大きさ
C.対数目盛を使った感覚範囲の拡大
D.対数目盛の感覚で聞いている音程
E.生理現象も対数関係
F.感覚は変化に敏感で,時間とともに弱まる
G.視覚の機能
8.体温制御の物理
A.身体各部の温度
B.身体の熱流モデル
C.体温調節のための機能
D.身体の熱収支の計算例
E.体温調節のための制御機能
F.体温異常のメカニズム
G.熱温存のための巧妙な仕組み
付録 観察と思考の物理
寺田寅彦全集より
参考文献
参考書
練習問題の解答
さくいん
A.力のモーメント
B.てこの原理の人体中での応用
C.筋肉の張力と関節にはたらく力の大きさ
D.腰にかかる力
2.看護ボディメカニクスの物理
A.ベッド上の患者を起こす方法
B.小さな力でも大きな効果が
C.看護ボディメカニクスの物理的重点事項
3.身近かな圧力
A.圧力とは何か
B.もし気圧が変わったら人間はどうなるか
C.入浴とベッドの圧力効果
4.呼吸器と吸引の物理
A.肺はどのようにして呼吸をするか
B.吸引(ドレナージ)
C.サイフォン
5.点滴静脈注射の物理
A.ボトルごとの点滴セッティングの違い
B.流量の調節
C.ボトルの高さ
D.滴下装置内の物理
6.循環器の物理
A.ポンプとしての心臓
B.血液循環と血圧
C.血圧が測定できる理由
D.水銀血圧計の知識
E.いろいろなタイプの血圧計
F.血圧の重力による影響
7.感覚器の物理
A.感覚の大きさ
B.聴覚の大きさ
C.対数目盛を使った感覚範囲の拡大
D.対数目盛の感覚で聞いている音程
E.生理現象も対数関係
F.感覚は変化に敏感で,時間とともに弱まる
G.視覚の機能
8.体温制御の物理
A.身体各部の温度
B.身体の熱流モデル
C.体温調節のための機能
D.身体の熱収支の計算例
E.体温調節のための制御機能
F.体温異常のメカニズム
G.熱温存のための巧妙な仕組み
付録 観察と思考の物理
寺田寅彦全集より
参考文献
参考書
練習問題の解答
さくいん
更新情報
-
更新情報はありません。
お気に入り商品に追加すると、この商品の更新情報や関連情報などをマイページでお知らせいたします。