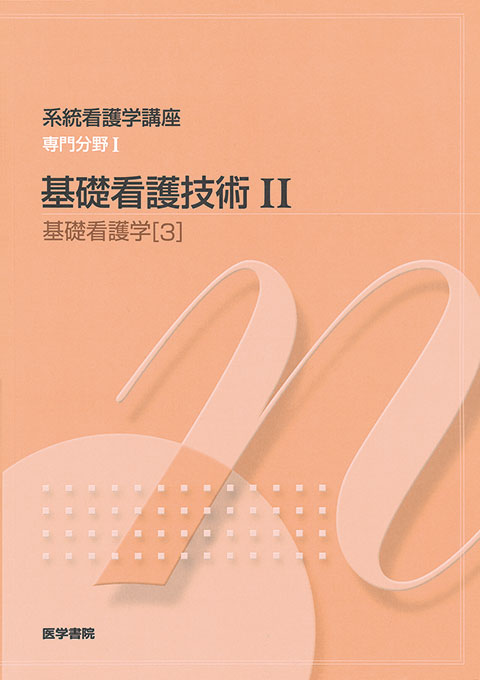基礎看護学[3]
基礎看護技術Ⅱ 第15版
本書の特長
もっと見る
●「厚生労働省 新人看護職員研修到達目標・新人看護職員研修指導指針」の「看護技術についての到達目標」に準じた目次立てとし、より臨床での実践に役だつような内容構成となっています。
●嚥下訓練、ストーマケア、排痰ケア、人工呼吸器、末梢循環促進ケア、身体計測、バイタルサインの観察、生体情報のモニタリング、薬剤・放射線曝露防止、洗浄の介助などの項目を追加しました。
●ページ数は約160ページ増、一層の内容充実をはかっています。
●豊富な図版・写真によって、より理解を深めることができます。
*2011年版より表紙が新しくなりました。
| シリーズ | 系統看護学講座 |
|---|---|
| 編集 | 藤崎 郁 / 任 和子 |
| 執筆 | 有田 清子 / 井川 順子 / 石賀 奈津子 / 岡本 啓子 / 尾﨑 章子 / 小林 優子 / 茂野 香おる / 竹林 直紀 / 只浦 寛子 / 立野 淳子 / 田中 靖代 / 田村 富美子 / 徳永 惠子 / 任 和子 / 林 静子 / 平松 八重子 / 藤崎 郁 / 三富 陽子 / 守本 とも子 / 山勢 博彰 / 𠮷村 雅世 |
| 発行 | 2009年02月判型:B5頁:520 |
| ISBN | 978-4-260-00666-8 |
| 定価 | 3,190円 (本体2,900円+税) |
- 販売終了
更新情報
-
更新情報はありません。
お気に入り商品に追加すると、この商品の更新情報や関連情報などをマイページでお知らせいたします。
- 序文
- 目次
- 正誤表
序文
開く
はしがき
今回の改訂では,本書を「第1部 看護技術概論」「第2部 16領域の看護技術」の2部構成とした。第1部では看護技術の4つの基本原則とその優先順位について説明を試み,第2部では看護技術を16の領域に分けて説明している。
この16領域の区分は,「新人看護職員の臨床実践能力の向上に関する検討会」(厚生労働省)が発表した「新人看護職員研修到達目標」の「看護技術についての到達目標」,および「看護基礎教育の充実に関する検討会」(厚生労働省)により発表された「看護基礎教育の充実に関する検討会報告書」の「看護師教育の技術項目と卒業時の到達度(案)」で示されている,13領域の看護技術に準拠したものである。
本書では,上記の13領域をそれぞれ13の章とし,さらに,そこには含まれないものの看護師が行う技術として「死の看取りの技術」,「侵襲的処置の介助の技術」について,それぞれ章を加えた。また「看護基礎教育の充実に関する検討会報告書」のなかに,基礎看護学における学習の留意点として,「コミュニケーション,フィジカルアセスメントを強化する内容とする」という一文が含まれていることをふまえ,あらたに「患者・家族とのコミュニケーション」の章をたてた。
このことに代表されるように,本書を「学内の実習室で行われている基礎看護技術」と「臨床で実践されている基礎看護技術」とのかけ橋とすることを,目次の企画の段階から最終校正までのすべての段階においてつねに頭におきながら,精一杯のくふうを重ねてきたつもりである。改訂にあたっては,それぞれの技術についてできるだけ最新の方法を紹介し,その根拠を示すように心がけた。
とはいうものの,限られた紙面でもあり,まだ実際の臨床現場での看護実践をほとんど知らない初学者向けの教科書としての本書の特徴も加味しなければならず,実際の臨床現場で行われている技術上のくふうや,看護の対象となる一人ひとりの患者や家族に合わせたくふうについてまでは,十分にふれることができているとはいいがたい。また,看護の対象は個人や家族だけではなく,地域やグループといったコミュニティにも及ぶということは,われわれ著者も十分に理解はしているが,その実際の介入技術の基本に関しては,本書本版では全く言及できていない。
しかしながら,ここではっきりと述べておきたいことは,なにも看護技術に限らず,「技術」と名のつくもののすべてが,社会や時代の要請をはじめ,関連する技術や道具の発展,あるいは信頼性や妥当性のあるきっちりとした研究の成果によって得られた最新のエビデンスの確立といったものを要因として,日ごとにどんどんと変化していくという特性をもつものだということである。学生諸子には,そのことを自分のなかでつねに肝に銘じつつ,本書を入り口として,問題意識をもった積極的な学びをぜひ行ってほしい。
本書を通じて,みずから問題意識を発見し,そのことを看護の対象となる人々のために探求し続ける姿勢をこそもっともたいせつにする学生たちを育てたいと願っている。
そのことを誰も知らなかったり評価してくれないような状況にあったとしても,決して手を抜かずに,自分のケアする対象者に必要な技術に関して問題意識をもち続け,そのことに関する最新の情報をあらゆる手段をもって収集し,その成果を自分の実践のくふうのなかにいかしていく姿勢がとてもたいせつである。このような姿勢や能力のことを,「self-directed learning(セルフ・ディレクティッド・ラーニング)」とよぶが,本書では,そのことを総論のなかでも,また16章ある各論のすべてのなかでも,くり返し言葉や伝えかたをかえて,強調して述べた。
学生諸子には,このような「看護技術に対する姿勢」こそが,看護師,助産師,その他あらゆる臨床現場における援助者としての将来の自分の成長を助けるということを覚えていてほしい。
そのために,この「基礎看護技術II」という教科書が少しでも役に立つことができるとすれば,今回の改訂にかかわった著者として,また責任編集者として,幸せのきわみである。
とはいえ,本書がまだまだ改善の余地のあることは,責任編集者や編集部はもちろんのこと,各著者も十分に承知している。今後も本書の内容についてお気づきの点があれば,ご指導,ご教示いただければ幸いである。
2008年11月
著者を代表して
藤崎 郁
今回の改訂では,本書を「第1部 看護技術概論」「第2部 16領域の看護技術」の2部構成とした。第1部では看護技術の4つの基本原則とその優先順位について説明を試み,第2部では看護技術を16の領域に分けて説明している。
この16領域の区分は,「新人看護職員の臨床実践能力の向上に関する検討会」(厚生労働省)が発表した「新人看護職員研修到達目標」の「看護技術についての到達目標」,および「看護基礎教育の充実に関する検討会」(厚生労働省)により発表された「看護基礎教育の充実に関する検討会報告書」の「看護師教育の技術項目と卒業時の到達度(案)」で示されている,13領域の看護技術に準拠したものである。
本書では,上記の13領域をそれぞれ13の章とし,さらに,そこには含まれないものの看護師が行う技術として「死の看取りの技術」,「侵襲的処置の介助の技術」について,それぞれ章を加えた。また「看護基礎教育の充実に関する検討会報告書」のなかに,基礎看護学における学習の留意点として,「コミュニケーション,フィジカルアセスメントを強化する内容とする」という一文が含まれていることをふまえ,あらたに「患者・家族とのコミュニケーション」の章をたてた。
このことに代表されるように,本書を「学内の実習室で行われている基礎看護技術」と「臨床で実践されている基礎看護技術」とのかけ橋とすることを,目次の企画の段階から最終校正までのすべての段階においてつねに頭におきながら,精一杯のくふうを重ねてきたつもりである。改訂にあたっては,それぞれの技術についてできるだけ最新の方法を紹介し,その根拠を示すように心がけた。
とはいうものの,限られた紙面でもあり,まだ実際の臨床現場での看護実践をほとんど知らない初学者向けの教科書としての本書の特徴も加味しなければならず,実際の臨床現場で行われている技術上のくふうや,看護の対象となる一人ひとりの患者や家族に合わせたくふうについてまでは,十分にふれることができているとはいいがたい。また,看護の対象は個人や家族だけではなく,地域やグループといったコミュニティにも及ぶということは,われわれ著者も十分に理解はしているが,その実際の介入技術の基本に関しては,本書本版では全く言及できていない。
しかしながら,ここではっきりと述べておきたいことは,なにも看護技術に限らず,「技術」と名のつくもののすべてが,社会や時代の要請をはじめ,関連する技術や道具の発展,あるいは信頼性や妥当性のあるきっちりとした研究の成果によって得られた最新のエビデンスの確立といったものを要因として,日ごとにどんどんと変化していくという特性をもつものだということである。学生諸子には,そのことを自分のなかでつねに肝に銘じつつ,本書を入り口として,問題意識をもった積極的な学びをぜひ行ってほしい。
本書を通じて,みずから問題意識を発見し,そのことを看護の対象となる人々のために探求し続ける姿勢をこそもっともたいせつにする学生たちを育てたいと願っている。
そのことを誰も知らなかったり評価してくれないような状況にあったとしても,決して手を抜かずに,自分のケアする対象者に必要な技術に関して問題意識をもち続け,そのことに関する最新の情報をあらゆる手段をもって収集し,その成果を自分の実践のくふうのなかにいかしていく姿勢がとてもたいせつである。このような姿勢や能力のことを,「self-directed learning(セルフ・ディレクティッド・ラーニング)」とよぶが,本書では,そのことを総論のなかでも,また16章ある各論のすべてのなかでも,くり返し言葉や伝えかたをかえて,強調して述べた。
学生諸子には,このような「看護技術に対する姿勢」こそが,看護師,助産師,その他あらゆる臨床現場における援助者としての将来の自分の成長を助けるということを覚えていてほしい。
そのために,この「基礎看護技術II」という教科書が少しでも役に立つことができるとすれば,今回の改訂にかかわった著者として,また責任編集者として,幸せのきわみである。
とはいえ,本書がまだまだ改善の余地のあることは,責任編集者や編集部はもちろんのこと,各著者も十分に承知している。今後も本書の内容についてお気づきの点があれば,ご指導,ご教示いただければ幸いである。
2008年11月
著者を代表して
藤崎 郁
目次
開く
第1部 看護技術総論 (藤崎郁)
第1章 本書で学ぶべきことがらとその特徴
A 看護介入技術の学習にあたっての心がまえ
B 本書の構成と本書で学んでほしいこと
第2章 看護技術の基本原則
A 基本原則の優先順位
B 看護介入技術の基盤としての「安全・安楽」
第2部 16領域の看護技術
第1章 環境調整技術 (藤崎郁・守本とも子・吉村雅世・岡本啓子)
A 本章の概要と目的
B 病床環境の調整
第2章 食事援助技術 (藤崎郁・茂野香おる・田中靖代)
A 本章の概要と目的
B 食事援助の基礎知識
C 食事介助
D 摂食・嚥下訓練
E 非経口的栄養摂取の援助
第3章 排泄援助技術 (藤崎郁・茂野香おる・三富陽子)
A 本章の概要と目的
B 自然排尿および自然排便の介助
C 導尿
D 排便を促す援助
E ストーマケア
第4章 活動・休息援助技術 (藤崎郁・林静子・徳永惠子・只浦寛子・尾崎章子)
A 本章の概要と目的
B 基本的活動の援助
C 睡眠・覚醒の援助
第5章 清潔・衣生活援助技術 (藤崎郁・茂野香おる・有田清子・守本とも子・吉村雅世・岡本啓子)
A 本章の概要と目的
B 清潔の援助
C 病床での衣生活の援助
第6章 呼吸・循環を整える技術 (藤崎郁・小林優子・田村富美子・立野淳子・山勢博彰)
A 本章の概要と目的
B 酸素吸入療法
C 吸引
D 排たんケア
E 吸入
F 人工呼吸療法
G 末梢循環促進ケア
第7章 創傷管理技術 (藤崎郁・三富陽子・茂野香おる)
A 本章の概要と目的
B 創傷管理の基礎知識
C 創傷処置
D 褥瘡予防
第8章 与薬の技術 (藤崎郁・小林優子・任和子)
A 本章の概要と目的
B 与薬の基礎知識
C 経口与薬
D 吸入
E 点眼
F 点鼻
G 経皮的与薬
H 直腸内与薬
I 注射
J 輸血管理
第9章 救命救急処置技術 (藤崎郁・山勢博彰・立野淳子)
A 本章の概要と目的
B 救命救急処置の基礎知識
C 心肺蘇生法
D 止血法
E 院内急変時の対応
第10章 症状・生体機能管理技術 (藤崎郁・小林優子・平松八重子)
A 本章の概要と目的
B 身体計測
C バイタルサインの観察
D 身体診察
E 検体検査
F 生体検査
G 生体情報のモニタリング
第11章 苦痛の緩和・安楽確保の技術 (藤崎郁・林静子・小林優子・竹林直紀)
A 本章の概要と目的
B 薬剤調整
C 体位保持(ポジショニング)
D 罨法
第12章 感染防止の技術 (藤崎郁・井川順子)
A 本章の概要と目的
B 感染防止の基礎知識
C 標準予防策(スタンダード-プリコーション)
D 感染経路別予防策
E 洗浄・消毒・滅菌
F 無菌操作
G 感染性廃棄物の取り扱い
H カテーテル関連血流感染対策
I 針刺し防止策
第13章 安全確保の技術 (藤崎郁・任和子)
A 本章の概要と目的
B 誤薬防止
C チューブ類の予定外抜去防止
D 患者誤認防止
E 転倒転落防止
F 薬剤・放射線曝露の防止
第14章 侵襲的処置の介助技術 (藤崎郁・小林優子・平松八重子)
A 本章の概要と目的
B 穿刺の介助
C 洗浄の介助
第15章 死の看取りの技術 (藤崎郁・石賀奈津子)
A 本章の概要と目的
B 死の看取りの基礎知識
C 施設内での臨終の見まもりと死後のケア
D 在宅における臨終の見まもりと死後のケア
第16章 患者や家族とのコミュニケーションの技術 (藤崎郁)
A 本章の概要と目的
B 患者や家族とのコミュニケーションの基礎知識
C 「話したいという気持ちをもっている患者」に対する援助
D 「話したくないと思っている患者」に対する援助
索引
第1章 本書で学ぶべきことがらとその特徴
A 看護介入技術の学習にあたっての心がまえ
B 本書の構成と本書で学んでほしいこと
第2章 看護技術の基本原則
A 基本原則の優先順位
B 看護介入技術の基盤としての「安全・安楽」
第2部 16領域の看護技術
第1章 環境調整技術 (藤崎郁・守本とも子・吉村雅世・岡本啓子)
A 本章の概要と目的
B 病床環境の調整
第2章 食事援助技術 (藤崎郁・茂野香おる・田中靖代)
A 本章の概要と目的
B 食事援助の基礎知識
C 食事介助
D 摂食・嚥下訓練
E 非経口的栄養摂取の援助
第3章 排泄援助技術 (藤崎郁・茂野香おる・三富陽子)
A 本章の概要と目的
B 自然排尿および自然排便の介助
C 導尿
D 排便を促す援助
E ストーマケア
第4章 活動・休息援助技術 (藤崎郁・林静子・徳永惠子・只浦寛子・尾崎章子)
A 本章の概要と目的
B 基本的活動の援助
C 睡眠・覚醒の援助
第5章 清潔・衣生活援助技術 (藤崎郁・茂野香おる・有田清子・守本とも子・吉村雅世・岡本啓子)
A 本章の概要と目的
B 清潔の援助
C 病床での衣生活の援助
第6章 呼吸・循環を整える技術 (藤崎郁・小林優子・田村富美子・立野淳子・山勢博彰)
A 本章の概要と目的
B 酸素吸入療法
C 吸引
D 排たんケア
E 吸入
F 人工呼吸療法
G 末梢循環促進ケア
第7章 創傷管理技術 (藤崎郁・三富陽子・茂野香おる)
A 本章の概要と目的
B 創傷管理の基礎知識
C 創傷処置
D 褥瘡予防
第8章 与薬の技術 (藤崎郁・小林優子・任和子)
A 本章の概要と目的
B 与薬の基礎知識
C 経口与薬
D 吸入
E 点眼
F 点鼻
G 経皮的与薬
H 直腸内与薬
I 注射
J 輸血管理
第9章 救命救急処置技術 (藤崎郁・山勢博彰・立野淳子)
A 本章の概要と目的
B 救命救急処置の基礎知識
C 心肺蘇生法
D 止血法
E 院内急変時の対応
第10章 症状・生体機能管理技術 (藤崎郁・小林優子・平松八重子)
A 本章の概要と目的
B 身体計測
C バイタルサインの観察
D 身体診察
E 検体検査
F 生体検査
G 生体情報のモニタリング
第11章 苦痛の緩和・安楽確保の技術 (藤崎郁・林静子・小林優子・竹林直紀)
A 本章の概要と目的
B 薬剤調整
C 体位保持(ポジショニング)
D 罨法
第12章 感染防止の技術 (藤崎郁・井川順子)
A 本章の概要と目的
B 感染防止の基礎知識
C 標準予防策(スタンダード-プリコーション)
D 感染経路別予防策
E 洗浄・消毒・滅菌
F 無菌操作
G 感染性廃棄物の取り扱い
H カテーテル関連血流感染対策
I 針刺し防止策
第13章 安全確保の技術 (藤崎郁・任和子)
A 本章の概要と目的
B 誤薬防止
C チューブ類の予定外抜去防止
D 患者誤認防止
E 転倒転落防止
F 薬剤・放射線曝露の防止
第14章 侵襲的処置の介助技術 (藤崎郁・小林優子・平松八重子)
A 本章の概要と目的
B 穿刺の介助
C 洗浄の介助
第15章 死の看取りの技術 (藤崎郁・石賀奈津子)
A 本章の概要と目的
B 死の看取りの基礎知識
C 施設内での臨終の見まもりと死後のケア
D 在宅における臨終の見まもりと死後のケア
第16章 患者や家族とのコミュニケーションの技術 (藤崎郁)
A 本章の概要と目的
B 患者や家族とのコミュニケーションの基礎知識
C 「話したいという気持ちをもっている患者」に対する援助
D 「話したくないと思っている患者」に対する援助
索引
正誤表
開く
本書の記述の正確性につきましては最善の努力を払っておりますが、この度弊社の責任におきまして、下記のような誤りがございました。お詫び申し上げますとともに訂正させていただきます。
更新情報
-
更新情報はありません。
お気に入り商品に追加すると、この商品の更新情報や関連情報などをマイページでお知らせいたします。