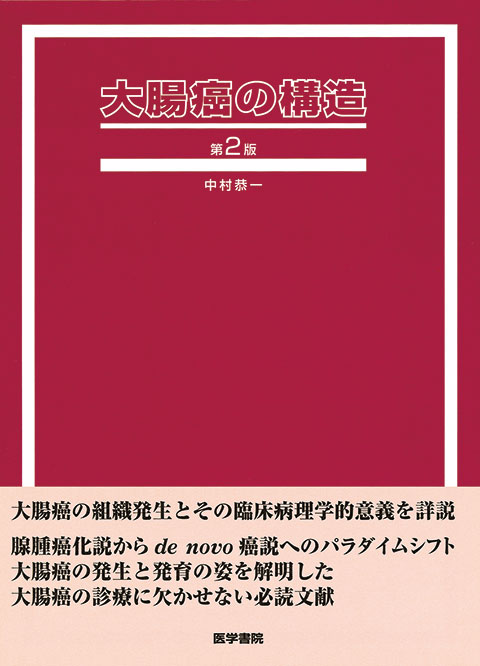胃癌の構造 第3版
著者渾身の全面改訂版をすべての臨床家・病理医に贈る
もっと見る
胃癌はどのように発生し、どのように発育していくのか? 分化型癌と未分化型癌の違いおよび組織型分類の意味は? 胃癌の組織発生とX線・内視鏡診断の関連は? 厖大なデータをもとに精緻な論理を構築していく著者の筆致は他の追随を許さず、既に古典的名著の誉れ高い本書であるが、古典は常に新しい。胃癌の発育・進展の実相を理解せずして正しい診断・治療は望めない。胃癌の診療に携わるすべての臨床家・病理医に贈る著者渾身の全面改訂版である。
| 著 | 中村 恭一 |
|---|---|
| 発行 | 2005年10月判型:B5頁:452 |
| ISBN | 978-4-260-00138-0 |
| 定価 | 22,000円 (本体20,000円+税) |
更新情報
-
更新情報はありません。
お気に入り商品に追加すると、この商品の更新情報や関連情報などをマイページでお知らせいたします。
- 目次
- 書評
目次
開く
I. プロローグ
II. 早期胃癌,胃癌の発生母地病変および胃癌組織発生研究の歴史的考察
III. 胃の潰瘍と癌の因果関係:潰瘍癌について
IV. 胃のポリープと癌
V. 胃癌発生の場
VI. 胃癌の組織発生
VII. 微小胃癌から導かれた胃癌組織発生の検討-一般的な大きさの癌で
VIII. 胃癌の細胞発生とその初期における癌細胞の生体生着様式
IX. 胃癌発生のまとめ
X. 胃癌の組織発生からみた胃癌の組織型
XI. 未分化型癌と分化型癌の臨床病理学的差異
XII. 胃癌組織発生の観点からの胃癌診断:
胃底腺粘膜から発生した癌のX線・内視鏡診断
XIII. 胃癌の組織発生から導かれる胃癌の発育速度
XIV. linitis plastica型癌,その癌発生から完成までの発育進展過程:
-linitis plastica への小径(Caminito a la linitis plastica)
XV. 胃癌組織発生からみた胃癌診断の考え方:“胃癌の三角”
XVI. 胃癌あれこれ
XVII. エピローグ
索引
II. 早期胃癌,胃癌の発生母地病変および胃癌組織発生研究の歴史的考察
III. 胃の潰瘍と癌の因果関係:潰瘍癌について
IV. 胃のポリープと癌
V. 胃癌発生の場
VI. 胃癌の組織発生
VII. 微小胃癌から導かれた胃癌組織発生の検討-一般的な大きさの癌で
VIII. 胃癌の細胞発生とその初期における癌細胞の生体生着様式
IX. 胃癌発生のまとめ
X. 胃癌の組織発生からみた胃癌の組織型
XI. 未分化型癌と分化型癌の臨床病理学的差異
XII. 胃癌組織発生の観点からの胃癌診断:
胃底腺粘膜から発生した癌のX線・内視鏡診断
XIII. 胃癌の組織発生から導かれる胃癌の発育速度
XIV. linitis plastica型癌,その癌発生から完成までの発育進展過程:
-linitis plastica への小径(Caminito a la linitis plastica)
XV. 胃癌組織発生からみた胃癌診断の考え方:“胃癌の三角”
XVI. 胃癌あれこれ
XVII. エピローグ
索引
書評
開く
「胃癌の構造」を解き明かす胃癌理解の必読書
書評者: 柳澤 昭夫 (京府医大教授・計量診断病理学)
本書は1982年に出版された『胃癌の構造』の全面改訂版である。“初版出版によせて”において中村先生の恩師で,当時,癌研究所所長であった菅野晴夫先生が“本書はヒト胃癌に関する最も重要な成書として長く歴史に残ることになるであろうことは疑いない”と述べておられる。『胃癌の構造』はまさに菅野先生が予想されたように,20年以上にわたって「初版印刷時の鉛板がすり減って印刷に耐えない状態」まで出版され続け現在にいたった。この事実は,この本がいかに多くの読者にとって重要な書であったかを裏付けるものである。さらに,今回の改訂は本書が胃癌に関する重要な成書として今後とも歴史に長く残ることを確信させるものである。
今回の改訂版は,初版の総頁数が252頁であったのに対して,424頁と倍に近い。この頁数からわかるように,中村先生がいかに今回の改訂に力を注いだか,また今回の改訂が単なる改訂にとどまらないかが理解できる。このことは,先生自身が序文の「“胃癌の構造”事始め」で,この本の改訂には4年を費やしたと述べておられることからも裏付けられる。
中村先生は胃癌の組織発生に関する本を1972年,金芳堂書店より『胃癌の病理―微小癌と組織発生』として最初に出版されている。この本は表紙,裏表紙,背表紙と全面黒で装丁されていたことにより“黒本”と呼ばれて愛読され,胃癌を研究する研究者に限らず病理医,臨床医にとってもバイブル的役割を果たしていた。“黒本”出版10年後に刊行されたのが『胃癌の構造』である。この本は“黒本”で述べられていた理論をさらに体系的に著したものであり,特に胃癌の組織発生の章は過去の胃癌発生の学説の誤りを中村先生独特(中村流)の論調で理論的に説いており,読んでいて痛快さをも感じさせるものであった。
今回の改訂は,初版の『胃癌の構造』をさらに体系化したものである。前半は胃癌の発生に関して,先生が研究してきた「胃癌の構造」の幹としている胃癌の細胞・組織発生から導かれた過程が,早期胃癌,胃癌の発生母地病変および胃癌組織発生研究の歴史的考察から始まり,潰瘍と胃癌の因果関係,ポリープと胃癌,胃癌発生の場,組織発生,微小癌から導かれる組織発生,細胞発生とその初期における癌細胞の生体生着様式の順で明快に述べられている。さらに,“胃癌発生のまとめ”として,胃癌発生の全体像が読者によりわかりやすく理解できるように1つの章にまとめられている。先生が,今回の改訂でいかに「胃癌の構造」全体を理解しやすくするかに腐心されたかが伝わってくる配置である。
次に述べられている項目は,胃癌の組織発生の分析結果から発生した胃癌が,どのように成長し,どのような組織像,肉眼像を現し,臨床所見を呈するか,また,胃癌の発育速度はどうであるか,すなわち,発生した胃癌が成長するとどのように展開していくかの研究結果から得られた結論が述べられているが,これらの項目は実際に胃癌を病理組織診断する場合や,臨床の場で診断する場合,そこで観察される所見を理解するうえで大きな手助けを与えてくれるものであり,研究を離れた実際の診断においても有益なものである。
臨床的問題が多く予後の悪いLinitis plastica型癌においては,“臨床的頻度は低く,その道は「小道caminito」である”としながらも,大きく頁を割いている。先生が何故この癌に対してこのように頁を割いたか興味があるところであり,この癌に対する取り組み方が,先生の癌に対する基本姿勢であると推測される。すなわち,たとえ臨床的に見つけられた時点でどんなに予後が悪い癌であっても,その初期像,構造を明らかにすることによって早期発見は可能となる。いいかえれば,どんな難治性癌も絶対早期発見できる(どんな癌も治す)とする姿勢でもある。
最後に先生はエピローグにおいて,“「胃癌の構造」のフィルターを通してその癌の胃癌全体のなかにおける位置づけが,そして,その癌の生物学的振る舞いから,以後に起こる可能性のあることをある程度予測できます”と述べている。これは,前述したことと通じるものであり,「胃癌の構造」を知ることは臨床の場で胃癌を診断するうえでも重要であることを意味するものである。本書を読むことにより,この言葉の真意が容易に納得できる。
今回私が改訂された本書を手にした時,20数年前に出版された『胃癌の構造』初版を読んで,胃癌発生に対する疑問をたとえ人体材料であっても理論的に矛盾のない結論へと導く論法に感銘したと同時に,人体材料を基にした癌研究のおもしろさを知ったことや,中村先生と知り合った当時のことを懐かしく思い出した。それ以来,常に物事を理論的に矛盾のない結論へ導く姿勢(たとえお酒がはいっていても変わらない)に感服している。この20年の間に遺伝子をはじめとする分子生物学研究の進歩は目覚ましいものがあったにもかかわらず,初版で得られた結論は揺るぎないものであり,まったく変わることなく現在もなお支持されている。さらに今回,初版を幹に全面改訂されたことは,常日頃,物事を論理的にとらえる姿勢の賜物であることに改めて感心させられた次第である。
先生の書は常に研究者に限らず臨床家にとっても必読書となっている。これは書かれている結論がすべて人体材料を基にしたものであり,常日頃臨床をよく知り多くの臨床家と議論している結果といえる。本書は胃癌に関心を持つ多くの研究者に限らず,胃癌診断を行っている病理医,臨床医にとっても“胃癌”を理解するための必読書であること,また,癌を研究している多くの研究者に有益な示唆を与えることを確信し,一読を推奨する次第である。
胃癌の病理学における“中村学”の集大成
書評者: 丸山 雅一 ((財)早期胃癌検診協会・理事長)
筆者は中村恭一先生の教えを受けた者の中では最も不出来な者の1人であると自らに言い聞かせている。先生と初めて対面したのは,1967年もすでに押し迫った頃である。先輩の熊倉を通じての入門であった。以後,私は先生が癌研究所病理部を去られるまでの期間,折りにふれて中村研究室へ通ってはいたものの,最後まで「お前は何も解っていない」,と叱責されてばかりいた。
ましてや,今や私は一度はこの道一筋と心に決めた消化管の診断学からも距離を置く立場になってしまった。いくら先生の指示があったとはいえ,先生のライフワークの集大成とも言うべき『胃癌の構造』(第3版)の書評を書くのは傲岸不遜であるとの大方の誹りを免れないかもしれない。
そんな状況を認識しつつも,敢えてこの一文を認めようと思いたった理由がいくつかある。それらをここに吐露するつもりはないが,ある種の情念にそれらを置き換えて私なりの書評を書く決断をした。
本書を目の前にして,私はまず中村先生との出会いから現在までに起きた消化管の診断学の変遷と発展について回顧し,先生がその歴史のなかで果たされた数々の業績を思い起こすことにかなりの時間をかけた。私の記憶が誤りでなければ,先生の仕事の大部分は癌研時代になされたものである。したがって,私は当時先生が世に問おうとしていた諸論文の内容については,半ば素人として聞き役を演じた。「どうだ,解ったか」と念をおされても咄嗟には返答に窮するような場面もしばしばあった。
先生は,「改訂3版の出版にあたって」という序文のなかで,「『胃癌の構造』樹の枝葉は繁茂しています」と表現している。言うまでもないことだが,この樹を根底で支えているのは「微小胃癌」と“極微小胃癌”である。これらは先生の仕事の最初から最後まで通奏低音の役割を演じている。「胃の潰瘍と癌の因果律」,「胃のポリープと癌」,「胃癌の組織発生」,「胃癌の組織型」,そして「linitis plastica型癌」など,胃癌の病理学の歴史に名をとどめる先生の数々の業績については,改めて紹介する必要はないであろう。そして,いわば悟りの境地のように感じられる「胃癌の三角」は,先生が到達した胃癌の組織発生論のminimalismである。
どのような学問の分野においても,確固不動の定説が正しいとは限らない。熟読含味すればその定説の根拠には弱点があるはずである。そして,それは何かと執拗に追究することによって,その定説は脆くも崩れてしまうことがある。これは先人の説く箴言であるが,まさにそのことが先生の仕事にはしばしば起きている。
そして,私は先生が「歴史的考察」の次に「胃の潰瘍と癌の因果律」の章をもってきたことにこの方の執念を感じる。言うまでもないことだが,先生は師匠である太田邦夫先生の定説(胃癌の発生,日病会誌53:36, 1965)を完全に否定することによって以後の研究に邁進することができた。師の仕事を否定することは極めて危険な行為である。この章では,先生が師を超えて研究者として生き残るためにはいかなる偏見や迫害にも耐えるという究極の決断をしたことをその行間から感じ取るべきであろう。
すでに,その内容の大部分は人口に膾炙されている本書の内容については逐一概説する必要はあるまい。むしろ,本書は,わが国における早期胃癌の診断(臨床・病理)の歴史を踏まえて熟読含味すべきものである。私は前段で敢えて執念と書いたが,中村学が評価されるまでの道程を考慮すれば,それは,むしろ,ある種のルサンチマンとも言うべきものかもしれない。トーマス・クーンの引用はこれを薄める効果を果たしているものの,「エピローグ」の内容には胸に迫るものがある。
先生は,本書の内容に過不足のあることを十分に承知している。だが,意図的に短くとどめてはいるものの,強烈な問題提起をしている。例えば,「腺管を形成している癌の一部には組織発生の点で胃固有粘膜から発生した未分化型癌に属する癌が存在していることを指摘し,そのような癌の形態認識についても記載しているにもかかわらず,あたかも腺管形成の有無が未分化型癌と分化型癌の区別の絶対的尺度であると主張しているかのように取り扱われている。すなわち,腺管を形成している癌のなかには粘液形質が胃型である癌が存在し,それを胃型分化型癌としている報告がみられる。ここにおいて,胃固有粘膜から発生した腺管形成の癌,つまり腺管を形成していても,癌組織発生の観点からは未分化型癌に属する癌(胃型分化型癌)の形態的な認識が問題となる(216―217ページ)」という記載に対して同時代の専門家たちはどのように反応するのであろうか。
ちなみに,雑誌『胃と腸』(胃型の分化型胃癌―病理診断とその特徴:34巻4号,胃型早期胃癌の病理学的特徴と臨床像:38巻5号)では歴史認識に断層があるように感じられてならない。執筆者たちは,論理で反論せず,「握り潰す」ことができる権威であると錯覚しているのであろうか。あるいは,単に,不勉強であるという理由のためであろうか。中村先生の系列に繋がる松田・西俣らが,『胃と腸』(38巻5号,673ページ)で,熊倉・丸山ほかの1972年の『胃と腸』(7号)論文を引用し,類似IIbに言及しているのがせめてもの救いであるが,境界の不明な分化型の早期癌は30年以上も前から存在したのである。『胃と腸』の来し方行く末には一抹の不安を抱かずにはいられない。
最後に,強調したいことがある。それは,中村先生の膨大な数の論文には英文で書かれたものも多数あるが,それらのほとんどはわが国で発行された英文誌に掲載されたものであるということである。その理由を推し量るに,欧米の英文誌の編集者たちは中村学を理解できなかったか,あるいは,中村学は不要であると結論したのか,のいずれかの可能性を私は考えている。しかし,今や,南米諸国の病理医たちは中村学を完全に自家薬籠中のものとしている。本書のエピローグのなかで先生は,Todo avance se inicia al momento de derrumbar el muro del presente.という響きのよいスペイン語の文章を挿入した。敢えて南米を視野に入れスペイン語で,既存のパラダイムを破壊すべしと主張する。これは頑迷な白人文化への大いなる皮肉ではないのか。
中村先生が最後の最後に書き記すように,「おかしな所見,即,生検」でも胃癌の確定診断は可能である。そして,同じ論理で,本書を読まずとも胃癌の臨床病理を語ることはできる。だが,「やはり,病変が呈する所見の依った所以を知らずして,診断能の向上はありえ」ないし,「医師たることを放棄していることにも通じる」。その意味において,本書は,長く座右におき,折りにふれて読み返す度に味わいの深くなる本である。それはさながら,ヘロドトス「歴史」のごとくに。
書評者: 柳澤 昭夫 (京府医大教授・計量診断病理学)
本書は1982年に出版された『胃癌の構造』の全面改訂版である。“初版出版によせて”において中村先生の恩師で,当時,癌研究所所長であった菅野晴夫先生が“本書はヒト胃癌に関する最も重要な成書として長く歴史に残ることになるであろうことは疑いない”と述べておられる。『胃癌の構造』はまさに菅野先生が予想されたように,20年以上にわたって「初版印刷時の鉛板がすり減って印刷に耐えない状態」まで出版され続け現在にいたった。この事実は,この本がいかに多くの読者にとって重要な書であったかを裏付けるものである。さらに,今回の改訂は本書が胃癌に関する重要な成書として今後とも歴史に長く残ることを確信させるものである。
今回の改訂版は,初版の総頁数が252頁であったのに対して,424頁と倍に近い。この頁数からわかるように,中村先生がいかに今回の改訂に力を注いだか,また今回の改訂が単なる改訂にとどまらないかが理解できる。このことは,先生自身が序文の「“胃癌の構造”事始め」で,この本の改訂には4年を費やしたと述べておられることからも裏付けられる。
中村先生は胃癌の組織発生に関する本を1972年,金芳堂書店より『胃癌の病理―微小癌と組織発生』として最初に出版されている。この本は表紙,裏表紙,背表紙と全面黒で装丁されていたことにより“黒本”と呼ばれて愛読され,胃癌を研究する研究者に限らず病理医,臨床医にとってもバイブル的役割を果たしていた。“黒本”出版10年後に刊行されたのが『胃癌の構造』である。この本は“黒本”で述べられていた理論をさらに体系的に著したものであり,特に胃癌の組織発生の章は過去の胃癌発生の学説の誤りを中村先生独特(中村流)の論調で理論的に説いており,読んでいて痛快さをも感じさせるものであった。
今回の改訂は,初版の『胃癌の構造』をさらに体系化したものである。前半は胃癌の発生に関して,先生が研究してきた「胃癌の構造」の幹としている胃癌の細胞・組織発生から導かれた過程が,早期胃癌,胃癌の発生母地病変および胃癌組織発生研究の歴史的考察から始まり,潰瘍と胃癌の因果関係,ポリープと胃癌,胃癌発生の場,組織発生,微小癌から導かれる組織発生,細胞発生とその初期における癌細胞の生体生着様式の順で明快に述べられている。さらに,“胃癌発生のまとめ”として,胃癌発生の全体像が読者によりわかりやすく理解できるように1つの章にまとめられている。先生が,今回の改訂でいかに「胃癌の構造」全体を理解しやすくするかに腐心されたかが伝わってくる配置である。
次に述べられている項目は,胃癌の組織発生の分析結果から発生した胃癌が,どのように成長し,どのような組織像,肉眼像を現し,臨床所見を呈するか,また,胃癌の発育速度はどうであるか,すなわち,発生した胃癌が成長するとどのように展開していくかの研究結果から得られた結論が述べられているが,これらの項目は実際に胃癌を病理組織診断する場合や,臨床の場で診断する場合,そこで観察される所見を理解するうえで大きな手助けを与えてくれるものであり,研究を離れた実際の診断においても有益なものである。
臨床的問題が多く予後の悪いLinitis plastica型癌においては,“臨床的頻度は低く,その道は「小道caminito」である”としながらも,大きく頁を割いている。先生が何故この癌に対してこのように頁を割いたか興味があるところであり,この癌に対する取り組み方が,先生の癌に対する基本姿勢であると推測される。すなわち,たとえ臨床的に見つけられた時点でどんなに予後が悪い癌であっても,その初期像,構造を明らかにすることによって早期発見は可能となる。いいかえれば,どんな難治性癌も絶対早期発見できる(どんな癌も治す)とする姿勢でもある。
最後に先生はエピローグにおいて,“「胃癌の構造」のフィルターを通してその癌の胃癌全体のなかにおける位置づけが,そして,その癌の生物学的振る舞いから,以後に起こる可能性のあることをある程度予測できます”と述べている。これは,前述したことと通じるものであり,「胃癌の構造」を知ることは臨床の場で胃癌を診断するうえでも重要であることを意味するものである。本書を読むことにより,この言葉の真意が容易に納得できる。
今回私が改訂された本書を手にした時,20数年前に出版された『胃癌の構造』初版を読んで,胃癌発生に対する疑問をたとえ人体材料であっても理論的に矛盾のない結論へと導く論法に感銘したと同時に,人体材料を基にした癌研究のおもしろさを知ったことや,中村先生と知り合った当時のことを懐かしく思い出した。それ以来,常に物事を理論的に矛盾のない結論へ導く姿勢(たとえお酒がはいっていても変わらない)に感服している。この20年の間に遺伝子をはじめとする分子生物学研究の進歩は目覚ましいものがあったにもかかわらず,初版で得られた結論は揺るぎないものであり,まったく変わることなく現在もなお支持されている。さらに今回,初版を幹に全面改訂されたことは,常日頃,物事を論理的にとらえる姿勢の賜物であることに改めて感心させられた次第である。
先生の書は常に研究者に限らず臨床家にとっても必読書となっている。これは書かれている結論がすべて人体材料を基にしたものであり,常日頃臨床をよく知り多くの臨床家と議論している結果といえる。本書は胃癌に関心を持つ多くの研究者に限らず,胃癌診断を行っている病理医,臨床医にとっても“胃癌”を理解するための必読書であること,また,癌を研究している多くの研究者に有益な示唆を与えることを確信し,一読を推奨する次第である。
胃癌の病理学における“中村学”の集大成
書評者: 丸山 雅一 ((財)早期胃癌検診協会・理事長)
筆者は中村恭一先生の教えを受けた者の中では最も不出来な者の1人であると自らに言い聞かせている。先生と初めて対面したのは,1967年もすでに押し迫った頃である。先輩の熊倉を通じての入門であった。以後,私は先生が癌研究所病理部を去られるまでの期間,折りにふれて中村研究室へ通ってはいたものの,最後まで「お前は何も解っていない」,と叱責されてばかりいた。
ましてや,今や私は一度はこの道一筋と心に決めた消化管の診断学からも距離を置く立場になってしまった。いくら先生の指示があったとはいえ,先生のライフワークの集大成とも言うべき『胃癌の構造』(第3版)の書評を書くのは傲岸不遜であるとの大方の誹りを免れないかもしれない。
そんな状況を認識しつつも,敢えてこの一文を認めようと思いたった理由がいくつかある。それらをここに吐露するつもりはないが,ある種の情念にそれらを置き換えて私なりの書評を書く決断をした。
本書を目の前にして,私はまず中村先生との出会いから現在までに起きた消化管の診断学の変遷と発展について回顧し,先生がその歴史のなかで果たされた数々の業績を思い起こすことにかなりの時間をかけた。私の記憶が誤りでなければ,先生の仕事の大部分は癌研時代になされたものである。したがって,私は当時先生が世に問おうとしていた諸論文の内容については,半ば素人として聞き役を演じた。「どうだ,解ったか」と念をおされても咄嗟には返答に窮するような場面もしばしばあった。
先生は,「改訂3版の出版にあたって」という序文のなかで,「『胃癌の構造』樹の枝葉は繁茂しています」と表現している。言うまでもないことだが,この樹を根底で支えているのは「微小胃癌」と“極微小胃癌”である。これらは先生の仕事の最初から最後まで通奏低音の役割を演じている。「胃の潰瘍と癌の因果律」,「胃のポリープと癌」,「胃癌の組織発生」,「胃癌の組織型」,そして「linitis plastica型癌」など,胃癌の病理学の歴史に名をとどめる先生の数々の業績については,改めて紹介する必要はないであろう。そして,いわば悟りの境地のように感じられる「胃癌の三角」は,先生が到達した胃癌の組織発生論のminimalismである。
どのような学問の分野においても,確固不動の定説が正しいとは限らない。熟読含味すればその定説の根拠には弱点があるはずである。そして,それは何かと執拗に追究することによって,その定説は脆くも崩れてしまうことがある。これは先人の説く箴言であるが,まさにそのことが先生の仕事にはしばしば起きている。
そして,私は先生が「歴史的考察」の次に「胃の潰瘍と癌の因果律」の章をもってきたことにこの方の執念を感じる。言うまでもないことだが,先生は師匠である太田邦夫先生の定説(胃癌の発生,日病会誌53:36, 1965)を完全に否定することによって以後の研究に邁進することができた。師の仕事を否定することは極めて危険な行為である。この章では,先生が師を超えて研究者として生き残るためにはいかなる偏見や迫害にも耐えるという究極の決断をしたことをその行間から感じ取るべきであろう。
すでに,その内容の大部分は人口に膾炙されている本書の内容については逐一概説する必要はあるまい。むしろ,本書は,わが国における早期胃癌の診断(臨床・病理)の歴史を踏まえて熟読含味すべきものである。私は前段で敢えて執念と書いたが,中村学が評価されるまでの道程を考慮すれば,それは,むしろ,ある種のルサンチマンとも言うべきものかもしれない。トーマス・クーンの引用はこれを薄める効果を果たしているものの,「エピローグ」の内容には胸に迫るものがある。
先生は,本書の内容に過不足のあることを十分に承知している。だが,意図的に短くとどめてはいるものの,強烈な問題提起をしている。例えば,「腺管を形成している癌の一部には組織発生の点で胃固有粘膜から発生した未分化型癌に属する癌が存在していることを指摘し,そのような癌の形態認識についても記載しているにもかかわらず,あたかも腺管形成の有無が未分化型癌と分化型癌の区別の絶対的尺度であると主張しているかのように取り扱われている。すなわち,腺管を形成している癌のなかには粘液形質が胃型である癌が存在し,それを胃型分化型癌としている報告がみられる。ここにおいて,胃固有粘膜から発生した腺管形成の癌,つまり腺管を形成していても,癌組織発生の観点からは未分化型癌に属する癌(胃型分化型癌)の形態的な認識が問題となる(216―217ページ)」という記載に対して同時代の専門家たちはどのように反応するのであろうか。
ちなみに,雑誌『胃と腸』(胃型の分化型胃癌―病理診断とその特徴:34巻4号,胃型早期胃癌の病理学的特徴と臨床像:38巻5号)では歴史認識に断層があるように感じられてならない。執筆者たちは,論理で反論せず,「握り潰す」ことができる権威であると錯覚しているのであろうか。あるいは,単に,不勉強であるという理由のためであろうか。中村先生の系列に繋がる松田・西俣らが,『胃と腸』(38巻5号,673ページ)で,熊倉・丸山ほかの1972年の『胃と腸』(7号)論文を引用し,類似IIbに言及しているのがせめてもの救いであるが,境界の不明な分化型の早期癌は30年以上も前から存在したのである。『胃と腸』の来し方行く末には一抹の不安を抱かずにはいられない。
最後に,強調したいことがある。それは,中村先生の膨大な数の論文には英文で書かれたものも多数あるが,それらのほとんどはわが国で発行された英文誌に掲載されたものであるということである。その理由を推し量るに,欧米の英文誌の編集者たちは中村学を理解できなかったか,あるいは,中村学は不要であると結論したのか,のいずれかの可能性を私は考えている。しかし,今や,南米諸国の病理医たちは中村学を完全に自家薬籠中のものとしている。本書のエピローグのなかで先生は,Todo avance se inicia al momento de derrumbar el muro del presente.という響きのよいスペイン語の文章を挿入した。敢えて南米を視野に入れスペイン語で,既存のパラダイムを破壊すべしと主張する。これは頑迷な白人文化への大いなる皮肉ではないのか。
中村先生が最後の最後に書き記すように,「おかしな所見,即,生検」でも胃癌の確定診断は可能である。そして,同じ論理で,本書を読まずとも胃癌の臨床病理を語ることはできる。だが,「やはり,病変が呈する所見の依った所以を知らずして,診断能の向上はありえ」ないし,「医師たることを放棄していることにも通じる」。その意味において,本書は,長く座右におき,折りにふれて読み返す度に味わいの深くなる本である。それはさながら,ヘロドトス「歴史」のごとくに。
更新情報
-
更新情報はありません。
お気に入り商品に追加すると、この商品の更新情報や関連情報などをマイページでお知らせいたします。