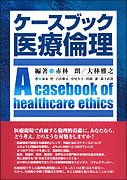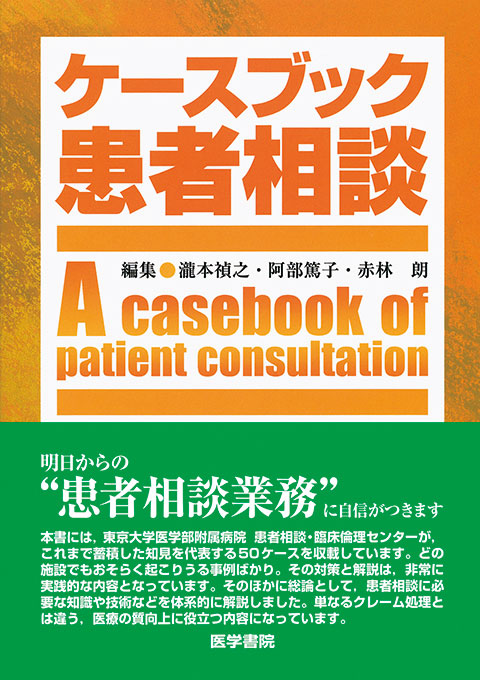ケースブック医療倫理
医療現場で直面する倫理的な問題を各領域の専門家たちが多角的に論じる
もっと見る
医療倫理はケースで学ぶ! 医療現場で直面する倫理的な葛藤,判断に悩む27ケースについて2通りのアプローチでどのように問題整理し,よりよい判断へとつなげていくのか,医学・看護学・哲学・倫理学・法学等の専門家が多角的な視点から論じた。日々新たに生じる倫理的課題は豊富なトピックスとコラムで紹介。
更新情報
-
更新情報はありません。
お気に入り商品に追加すると、この商品の更新情報や関連情報などをマイページでお知らせいたします。
- 目次
- 書評
目次
開く
はじめに--本書を使われる皆さんへ
Approach 1
■成人期の課題
Case 1 医療者の指示に従わない患者
Case 2 がんの告知
■終末期の課題
Case 3 安楽死・尊厳死
Case 4 セデーション(鎮静)
■脳死と臓器移植
Case 5 脳死
■老年期の課題
Case 6 在宅患者への医療・介護
Case 7 痴呆高齢者のリハビリテーション
■青年・成人期の課題
Case 8 HIV/AIDS
Case 9 人工妊娠中絶
■小児期の課題
Case10 子どもへの病気説明
Case11 子ども虐待
■出生時の課題
Case12 体外受精
Case13 出生前診断
■現場の人間関係
Case14 同僚のミス
Case15 対応の難しい患者
■研究倫理
Case16 研究の倫理
Approach 2
Case 1 医師,看護師,家族それぞれの思い
Case 2 患者への内服治療の説明
Case 3 痴呆高齢者の転倒・転落事故
Case 4 職場における感染症への対応
Case 5 信仰上の理由による治療拒否
Case 6 重度の障害をもつ新生児の治療
Case 7 義父の精子を使用したAID
Case 8 悪い病名や予後をどのように伝えるか(1)
Case 9 悪い病名や予後をどのように伝えるか(2)
Case10 悪い病名や予後をどのように伝えるか(3)
Case11 誰が研究論文の著者になるのか
あとがき
Approach 1
■成人期の課題
Case 1 医療者の指示に従わない患者
Case 2 がんの告知
■終末期の課題
Case 3 安楽死・尊厳死
Case 4 セデーション(鎮静)
■脳死と臓器移植
Case 5 脳死
■老年期の課題
Case 6 在宅患者への医療・介護
Case 7 痴呆高齢者のリハビリテーション
■青年・成人期の課題
Case 8 HIV/AIDS
Case 9 人工妊娠中絶
■小児期の課題
Case10 子どもへの病気説明
Case11 子ども虐待
■出生時の課題
Case12 体外受精
Case13 出生前診断
■現場の人間関係
Case14 同僚のミス
Case15 対応の難しい患者
■研究倫理
Case16 研究の倫理
Approach 2
Case 1 医師,看護師,家族それぞれの思い
Case 2 患者への内服治療の説明
Case 3 痴呆高齢者の転倒・転落事故
Case 4 職場における感染症への対応
Case 5 信仰上の理由による治療拒否
Case 6 重度の障害をもつ新生児の治療
Case 7 義父の精子を使用したAID
Case 8 悪い病名や予後をどのように伝えるか(1)
Case 9 悪い病名や予後をどのように伝えるか(2)
Case10 悪い病名や予後をどのように伝えるか(3)
Case11 誰が研究論文の著者になるのか
あとがき
書評
開く
キーワードは“Approach”――読み解くほどに内容がリッチになる
書評者: 中西 睦子 (国際医療福祉大学保健学部教授・看護学科長)
◆倫理問題取り組みのエクササイズ
これは実用の書を装いながら,じつは読者の思索を深めるよう巧みに仕組まれた書である。キーワードは“Approach”。あとから思うと,なんとも含蓄深い。
本書はApproach1とApproach2の2部構成である。前者は著者らによれば,比較的「短いケース」の提示があって,そのあとに考えるべき課題が提示される。これはいうなれば実践編,少ない情報をたよりにその場の状況をつかみ,判断と行動を導いていく。といっても,解答はもっぱら読者の胸中にある。
本書の紙面づくりがあまりにすっきりしているので,初心者は,なーンだ,倫理問題への対応ってカンタンなんだ,と思うかもしれない。しかし,あなどってはいけない。ここに掲載される情報は思いきりスリム化されている。たとえば,ケース13の「出生前診断」の項をみる。ほんとに短いケースの紹介があって,そのあとに「当事者が望んでいること」「当事者が大切にしているもの」という見出しがくる。この見出しにそって妻(患者),夫,医師,看護師それぞれの見解が1―2行で簡潔に述べられる。だが現実がこんなに簡潔に描けることは少ない。やれ,姑がこう言った,なのに舅の意見は違う,等々,外野席の主張も激しい。そのおかげで,夫は迷って自分の意見を言わない,等々,迷路に入りがちだ。つまり本書では,現実のもつれにもつれた糸をときほぐす部分は,すべて著者らがやってくれている。そのうえで,こういう道筋に沿って考えていくと,ひとまず倫理的に正当化される一定の結論が導けますよ,というエクササイズを用意してくれているのだ。
とくに親切だと思うのは,ケース提示のあと,「このケースを考えるために」という課題をめぐる専門的な解説があり,さらに“Topics”という課題に関連した最近の動向を紹介するコラムもあること。実務家にとっては,たいへん助かるにちがいない。ことほどさように,構成がじつによく考えられていて,著者らがしっかりと議論をした成果だろうなと思う。
◆主要な倫理問題をカバーした優れた教材
さて,後者のApproach2では,「比較的長いケース」の提示に続いて,3人の執筆者がそれぞれの視点からコメントしている。言えば,学際的紙上討論といったところだろうか(双方通行ではないけれども)。まったく同じ状況でも,切り口(approach)が違えば,見解も違うことを,読者に理解させる意図があったのだろう。
ただし,ここはふしぎなことに,論点の鮮やかな相違が見出せるものは,案外少ない。もしかしたら,著者らの議論のしすぎかな,もう少し演出があってもいいな,とも思ったりする。そして,Approach1からApproach2にどう切り結ぶのかなとも,1読者として思案している。
とはいっても,ケースの選択は,主要な倫理問題をカバーしており,難しい理論的知識はいったん消化され,コメントその他のコラム上にさりげなく示される。内容は,読み解くほどにリッチになるという仕掛けが心憎い。優れた教材である。
倫理教育の方針にピッタリはまった1冊
書評者: 下村 朋子 (鹿児島医療福祉専門学校・教務主任)
今日,遺伝子治療や臓器移植に代表される高度に発達した医療が日常的になり,患者の高齢化・重症化,平均在院日数の短縮などによって看護業務も多様化・複雑化し,密度が高くなってきている。
このような状況のもと,臨床看護の現場では,「患者を守る」とか「患者のために」といった看護の基本的な信念や行動の規範を定めた職業倫理綱領があるにもかかわらず,その倫理綱領と照らし合わせても答えの出にくい医療上の問題が多数発生しており,医療を複雑にしている。
医療上の問題の中には,正しいか間違っているか,よいか悪いか,よく考えるべき倫理的な要素が含まれるものもある。特に看護職の場合は,その特有の役割と責任から,倫理的問題のジレンマにしばしば陥って,立ち往生する場面があると聞く。
◆具体的事例をもとに考える訓練が必要
日本語の「倫理」の「倫」は人と人の関係を,「理」は人間というものの中で発展した共生を意味していることから,日本語の倫理は,伝統的には,人間関係を表しているそうだ。そうであれば,看護基礎教育の中で,看護の対象を包括的にみる学習を臨地実習で体験する学習途上の学生であっても,臨地で出会うすべての人間とのかかわりにおいて,このような倫理的な問題に直面する可能性は大きいともいえる。
そこで,倫理的諸問題に対処できる看護職を育成する教育では,何ができるのか考えてみた。看護学校に入学し,看護の旅を歩き始めた学生には,将来生死と向きあう医療現場で医療チームの一員として「倫理上の問題」を発見できる看護者になってほしいと望んでいる。そのためには,何が倫理的に正しいのか,何を根拠にそれを判断するのか,自分で考えることができればよいと思う。
今後はヒトゲノム解析や遺伝子診断・遺伝子治療など,ますます倫理的な判断が要求される問題が増えてくるだろう。そこで具体的な事例をもとに,論理的な問題を据え考える訓練をすることが,専門職につく学生の自覚としては必要である。
よいテキストはないかと思案していた折,『ケースブック医療倫理』に出会った。
◆倫理学担当講師が太鼓判
このテキストは,医療現場で生じる事例に,当事者の価値観や希望,関連した情報が整理して提示されており,事例を読んだ学生は最終的によく考え自分で判断するような構成になっている。とはいえ,臨床経験のない学生はこの事例を理解できるだろうかと危惧したのは事実である。しかし,事例の内容が現代社会情勢をとらえた内容であり,学生はすぐに興味を持った。
また,医療職ではない倫理学の講師はこのテキストを手にされた時,「とても難しい」という印象を持たれていた。そのため,講義は事例をゆっくり読んで説明し事実確認をしながら,問題点を明確にしてディスカッションをする方法をとられていた。その結果講義終了時には,「非常によくできた内容であり,看護学校ではやるべきテキストである」と太鼓判を押してくださった。
まさに,私の医療倫理の考えにピッタリはまった1冊である。
書評者: 中西 睦子 (国際医療福祉大学保健学部教授・看護学科長)
◆倫理問題取り組みのエクササイズ
これは実用の書を装いながら,じつは読者の思索を深めるよう巧みに仕組まれた書である。キーワードは“Approach”。あとから思うと,なんとも含蓄深い。
本書はApproach1とApproach2の2部構成である。前者は著者らによれば,比較的「短いケース」の提示があって,そのあとに考えるべき課題が提示される。これはいうなれば実践編,少ない情報をたよりにその場の状況をつかみ,判断と行動を導いていく。といっても,解答はもっぱら読者の胸中にある。
本書の紙面づくりがあまりにすっきりしているので,初心者は,なーンだ,倫理問題への対応ってカンタンなんだ,と思うかもしれない。しかし,あなどってはいけない。ここに掲載される情報は思いきりスリム化されている。たとえば,ケース13の「出生前診断」の項をみる。ほんとに短いケースの紹介があって,そのあとに「当事者が望んでいること」「当事者が大切にしているもの」という見出しがくる。この見出しにそって妻(患者),夫,医師,看護師それぞれの見解が1―2行で簡潔に述べられる。だが現実がこんなに簡潔に描けることは少ない。やれ,姑がこう言った,なのに舅の意見は違う,等々,外野席の主張も激しい。そのおかげで,夫は迷って自分の意見を言わない,等々,迷路に入りがちだ。つまり本書では,現実のもつれにもつれた糸をときほぐす部分は,すべて著者らがやってくれている。そのうえで,こういう道筋に沿って考えていくと,ひとまず倫理的に正当化される一定の結論が導けますよ,というエクササイズを用意してくれているのだ。
とくに親切だと思うのは,ケース提示のあと,「このケースを考えるために」という課題をめぐる専門的な解説があり,さらに“Topics”という課題に関連した最近の動向を紹介するコラムもあること。実務家にとっては,たいへん助かるにちがいない。ことほどさように,構成がじつによく考えられていて,著者らがしっかりと議論をした成果だろうなと思う。
◆主要な倫理問題をカバーした優れた教材
さて,後者のApproach2では,「比較的長いケース」の提示に続いて,3人の執筆者がそれぞれの視点からコメントしている。言えば,学際的紙上討論といったところだろうか(双方通行ではないけれども)。まったく同じ状況でも,切り口(approach)が違えば,見解も違うことを,読者に理解させる意図があったのだろう。
ただし,ここはふしぎなことに,論点の鮮やかな相違が見出せるものは,案外少ない。もしかしたら,著者らの議論のしすぎかな,もう少し演出があってもいいな,とも思ったりする。そして,Approach1からApproach2にどう切り結ぶのかなとも,1読者として思案している。
とはいっても,ケースの選択は,主要な倫理問題をカバーしており,難しい理論的知識はいったん消化され,コメントその他のコラム上にさりげなく示される。内容は,読み解くほどにリッチになるという仕掛けが心憎い。優れた教材である。
倫理教育の方針にピッタリはまった1冊
書評者: 下村 朋子 (鹿児島医療福祉専門学校・教務主任)
今日,遺伝子治療や臓器移植に代表される高度に発達した医療が日常的になり,患者の高齢化・重症化,平均在院日数の短縮などによって看護業務も多様化・複雑化し,密度が高くなってきている。
このような状況のもと,臨床看護の現場では,「患者を守る」とか「患者のために」といった看護の基本的な信念や行動の規範を定めた職業倫理綱領があるにもかかわらず,その倫理綱領と照らし合わせても答えの出にくい医療上の問題が多数発生しており,医療を複雑にしている。
医療上の問題の中には,正しいか間違っているか,よいか悪いか,よく考えるべき倫理的な要素が含まれるものもある。特に看護職の場合は,その特有の役割と責任から,倫理的問題のジレンマにしばしば陥って,立ち往生する場面があると聞く。
◆具体的事例をもとに考える訓練が必要
日本語の「倫理」の「倫」は人と人の関係を,「理」は人間というものの中で発展した共生を意味していることから,日本語の倫理は,伝統的には,人間関係を表しているそうだ。そうであれば,看護基礎教育の中で,看護の対象を包括的にみる学習を臨地実習で体験する学習途上の学生であっても,臨地で出会うすべての人間とのかかわりにおいて,このような倫理的な問題に直面する可能性は大きいともいえる。
そこで,倫理的諸問題に対処できる看護職を育成する教育では,何ができるのか考えてみた。看護学校に入学し,看護の旅を歩き始めた学生には,将来生死と向きあう医療現場で医療チームの一員として「倫理上の問題」を発見できる看護者になってほしいと望んでいる。そのためには,何が倫理的に正しいのか,何を根拠にそれを判断するのか,自分で考えることができればよいと思う。
今後はヒトゲノム解析や遺伝子診断・遺伝子治療など,ますます倫理的な判断が要求される問題が増えてくるだろう。そこで具体的な事例をもとに,論理的な問題を据え考える訓練をすることが,専門職につく学生の自覚としては必要である。
よいテキストはないかと思案していた折,『ケースブック医療倫理』に出会った。
◆倫理学担当講師が太鼓判
このテキストは,医療現場で生じる事例に,当事者の価値観や希望,関連した情報が整理して提示されており,事例を読んだ学生は最終的によく考え自分で判断するような構成になっている。とはいえ,臨床経験のない学生はこの事例を理解できるだろうかと危惧したのは事実である。しかし,事例の内容が現代社会情勢をとらえた内容であり,学生はすぐに興味を持った。
また,医療職ではない倫理学の講師はこのテキストを手にされた時,「とても難しい」という印象を持たれていた。そのため,講義は事例をゆっくり読んで説明し事実確認をしながら,問題点を明確にしてディスカッションをする方法をとられていた。その結果講義終了時には,「非常によくできた内容であり,看護学校ではやるべきテキストである」と太鼓判を押してくださった。
まさに,私の医療倫理の考えにピッタリはまった1冊である。