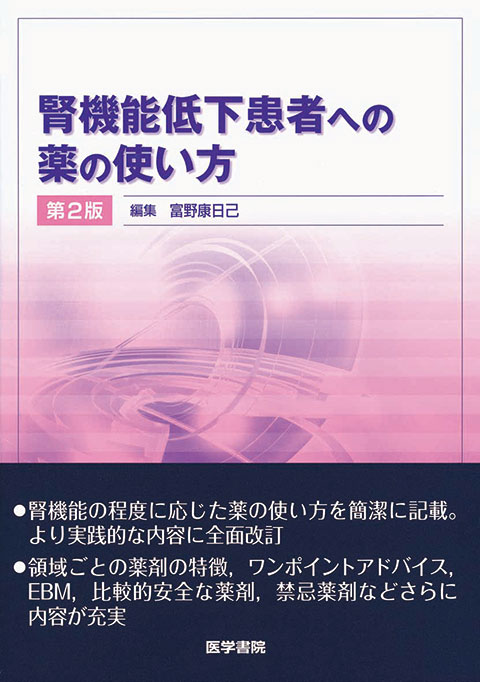腎機能低下患者への薬の使い方
薬剤にかかわるすべての医療関係者必携書
もっと見る
腎機能が低下した患者への薬物療法について,薬理の基礎から具体的な処方例までをコンパクトにまとめた。臨床薬理学的な立場から腎と薬物動態の基礎を平易に解説した後に,一般的によく使用され,腎機能低下時の処方に注意が必要な薬剤について,腎機能低下の程度別に処方例を提示。腎障害時に注意が必要な副作用,相互作用,投薬時のポイントも薬剤ごとに解説。
| 編集 | 富野 康日己 |
|---|---|
| 発行 | 2002年05月判型:B6頁:292 |
| ISBN | 978-4-260-10259-9 |
| 定価 | 4,180円 (本体3,800円+税) |
- 販売終了
更新情報
-
更新情報はありません。
お気に入り商品に追加すると、この商品の更新情報や関連情報などをマイページでお知らせいたします。
- 目次
- 書評
目次
開く
総論
第1章 はじめに-腎と薬物療法
第2章 腎と薬物動態の基礎知識
各論
第3章 感染症治療薬(抗菌薬,抗真菌薬,抗ウイルス薬などを含む)および呼吸器疾患治療薬
第4章 循環器疾患治療薬
第5章 消化器疾患治療薬
第6章 精神・神経疾患治療薬
第7章 血液疾患,内分泌・代謝疾患治療薬
第8章 抗炎症薬,抗リウマチ薬,鎮痛薬
第9章 造影剤,診断用薬
第10章 その他
第1章 はじめに-腎と薬物療法
第2章 腎と薬物動態の基礎知識
各論
第3章 感染症治療薬(抗菌薬,抗真菌薬,抗ウイルス薬などを含む)および呼吸器疾患治療薬
第4章 循環器疾患治療薬
第5章 消化器疾患治療薬
第6章 精神・神経疾患治療薬
第7章 血液疾患,内分泌・代謝疾患治療薬
第8章 抗炎症薬,抗リウマチ薬,鎮痛薬
第9章 造影剤,診断用薬
第10章 その他
書評
開く
難解な腎不全患者への薬剤投与がズバリわかる
書評者: 斎藤 明 (東海大総合医学研教授)
最近,順天堂大学医学部腎臓内科の富野康日己教授編集による『腎機能低下患者への薬の使い方』が医学書院から刊行された。腎機能低下患者への薬剤投与は,臨床医にとり日常臨床の中でしばしば遭遇し,薬剤の特徴に応じ,また腎機能低下の段階に応じて投与量と投与方法を変えることを必要とされる,難解な領域の1つと考えられる。
まず,薬剤の排泄部位が腎臓か肝臓かにより薬剤投与量が異なることになる。肝排泄性薬剤では通常投与量でよいが,腎排泄性の比率が高い場合には,腎機能の低下レベルに応じた投与量の減量が必要となる。蓄積により腎障害を引き起こす薬剤やその他の副作用を引き起こす薬剤があり,その薬剤ごとの有効血中濃度と蓄積による副作用の種類や発現との関連性を知る必要がある。一般に,腎機能低下レベルが大きくなるにしたがい,腎排泄性薬剤の蓄積が著しくなり,投与量,投与間隔を大きく変える必要がある。
末期腎不全にいたると,血液透析,腹膜透析などの治療を受けることになる。その際,薬剤の分布領域,分子量や蛋白結合性が,透析による除去率に大きく影響する。蛋白結合率の高い薬剤は,透析による体内からの除去が少なく,蛋白結合率の低く,分子量の高くない薬剤は透析により6―7割を喪失することになる。適正な投与にはそれらの基礎知識が不可欠である。
◆わかりやすくコンパクトにまとめられた腎機能低下患者の診療
本書では,「総論」として,中毒性腎障害,造影剤による腎障害,腎機能の程度にしたがった薬物療法,腎臓の構造・機能と薬物排泄,腎機能低下時の薬剤投与設計などの基礎がわかりやすく解説されている。
また,「各論」において感染症治療薬(抗菌薬,抗真菌薬,抗ウイルス薬など)および呼吸器疾患治療薬,循環器疾患治療薬,消化器疾患治療薬,精神・神経疾患治療薬,血液疾患,内分泌・代謝疾患治療薬,抗炎症薬,抗リウマチ薬,鎮痛薬,造影剤,診断用薬,その他の薬剤について,具体的に100種類以上の薬剤をあげて,代表的商品名,剤形,適応,常用量,腎排泄率,主な類似薬,腎機能低下時の処方例,腎機能低下時の副作用・相互作用などにつき,わかりやすく,コンパクトにまとめられている。さらに,薬剤ごとに腎機能低下患者への投与時のワンポイントアドバイスを示し,注意点を喚起している点が魅力である。
本書は,臨床家が日常診察室のかたわらに置いて,または白衣のポケットに入れて,治療の合間に参考にするにふさわしい治療マニュアルである。多くの臨床家の腎機能低下患者診察に大いに役立つものと確信する。
“かゆいところに手が届く”きわめて実践的編集
書評者: 小池 隆夫 (北大大学院教授・免疫病態内科学)
超高齢化社会の到来が現実になり,加えて糖尿病患者の急増などにより,腎機能が低下している患者に遭遇する機会も増えてきた。また,腎機能は正常でありながらも,現在投与している薬がどの程度腎機能に障害を与えるのか悩むことは,日常臨床ではしばしば経験する。
◆投薬に際しての疑問や注意点がたちどころにわかる内容
このたび富野康日己教授が編集され,ご自身と順天堂大学医学部腎臓内科のスタッフによって執筆された『腎機能低下患者への薬の使い方』という実に実践的でかつ有用な本が上梓された。私から申すまでもないが,富野教授は,IgA腎症の世界的な権威であられる。数年前『IgA Nephropathy; from molecules to men』と題する研究の集大成を〈Contributions to Nephrology〉(Karger)に,ご自身の単著で上梓され,その内容の豊かさに圧倒されたことが記憶に新しい。今回のテキストは,それとはがらりと趣が変わり,まさに“かゆいところに手が届く”編集で,きわめて実践的であり,われわれがしばしば遭遇する,腎機能低下患者への投薬に際してのさまざまな疑問や注意点が,たちどころにわかる内容になっている。
◆大変役立つ「ワンポイントアドバイス」
「腎と薬物療法」,「腎と薬物動態の基礎知識」の2章からなる総論と続く8章に及ぶ各論から構成されている本書の最大の特徴の1つは,腎機能低下時における各種薬剤の使い方を,見開き2頁にコンパクトにまとめてある点である。薬剤名と常用量ならびにその薬剤の腎排泄率が簡潔に記述されており,続いて腎機能低下時の処方例や副作用ならびに相互作用の要点が書かれている。特記すべきは,「ワンポイントアドバイス」が全薬剤につき述べられていることであり,これが大変に役立つ。まず最初にこの部分に目をとおし,投与する薬剤の基本的知識を再確認するとよい。
本書の約半分が,抗生物質と降圧剤を主体とした循環器薬で占められていることも,日常臨床でこのような薬剤が使用されることが多い現実に即している。アミノグリコシドはもとより第三世代セフェム系,キノロンさらにはニューキノロンにも記述が及んでいる。また腎機能障害時に使われることの多い各種ACE阻害薬や,最近のアンジオテンシンII受容体拮抗薬も記載されている。
腎臓病一般に使用する治療薬が,副腎皮質ホルモン,免疫抑制剤,利尿薬程度しか存在しないにもかかわらず,日常臨床で遭遇する腎機能低下患者はきわめて多く,さまざまな注意が必要であることは皮肉な現実ではあるが,本書は大きさも手ごろで,日常臨床にきわめて有用であり,研修医や一般医家に広くお勧めしたい。
腎不全患者を扱う医療関係者に必携の1冊
書評者: 斉藤 喬雄 (福岡大教授・腎臓内科学)
一般に薬剤の代謝過程において,腎臓は肝臓とともに重要な排泄経路である。特に腎臓では,糸球体濾過の他に尿細管における再吸収・分泌というメカニズムが排泄を複雑にしており,薬剤によって排泄の実態が異なっていると考えられる。したがって,専門医といえる私たちでも,十分理解していない点が少なくない。
◆常に念頭に置く必要がある腎機能と薬剤情報
腎で排泄される薬剤については,腎機能低下とともに血中濃度が異常に上昇し,副作用を引き起こす危険があることや,排泄の過程で主に尿細管・間質系に障害を及ぼす恐れについて考慮しなければならない。最近,このような問題が重視されており,実際の診療において薬剤の投与量を定める場合,常に念頭に置く必要が出てきた。このため,各薬剤ごとに,腎機能と投与量の関係を示した成書もいくつか出版されている。しかし,これらでは詳細な内容は示されずに,単に投与量を羅列するに終わっていることも多い。また,新しい薬剤についての記載が少なく,使用したい薬剤の情報がしばしば得られない。
今回,富野教授の編集により刊行された『腎機能低下患者への薬の使い方』では,このような問題点を十分に考慮し,保存期および透析期腎不全の治療を行なうにあたって,実際的な薬剤の使い方を述べている。使用頻度が高い薬剤を中心に,副作用や相互作用などとともに処方例がのせられており,医療現場において,迷うことなく処方用量を定められるという利点を持つ。特に,現場で遭遇する状況を想定してその対処法を説明したワンポイントアドバイスは,きわめて有用であろう。使用される場を考慮して小型化してサイズも好ましい。
一方,なぜこのような投与量にしなければならないのか,腎機能低下時における薬物動態や薬物投与設計について,薬理学の植松俊彦岐阜大学名誉教授により詳しく解説がなされている。したがって,本書に記載されていない薬剤を投与する必要がある場合に,投与量を決定する参考となるし,腎機能低下時の薬剤投与法をよく理解し知識をまとめる際に役に立つ。現場を離れて十分な時間がある時など,腎臓の役割を認識する上からも好著である。以上のような点から,本書は腎や透析の専門医だけでなく,腎不全患者を扱う医師に広く勧めたい。
書評者: 斎藤 明 (東海大総合医学研教授)
最近,順天堂大学医学部腎臓内科の富野康日己教授編集による『腎機能低下患者への薬の使い方』が医学書院から刊行された。腎機能低下患者への薬剤投与は,臨床医にとり日常臨床の中でしばしば遭遇し,薬剤の特徴に応じ,また腎機能低下の段階に応じて投与量と投与方法を変えることを必要とされる,難解な領域の1つと考えられる。
まず,薬剤の排泄部位が腎臓か肝臓かにより薬剤投与量が異なることになる。肝排泄性薬剤では通常投与量でよいが,腎排泄性の比率が高い場合には,腎機能の低下レベルに応じた投与量の減量が必要となる。蓄積により腎障害を引き起こす薬剤やその他の副作用を引き起こす薬剤があり,その薬剤ごとの有効血中濃度と蓄積による副作用の種類や発現との関連性を知る必要がある。一般に,腎機能低下レベルが大きくなるにしたがい,腎排泄性薬剤の蓄積が著しくなり,投与量,投与間隔を大きく変える必要がある。
末期腎不全にいたると,血液透析,腹膜透析などの治療を受けることになる。その際,薬剤の分布領域,分子量や蛋白結合性が,透析による除去率に大きく影響する。蛋白結合率の高い薬剤は,透析による体内からの除去が少なく,蛋白結合率の低く,分子量の高くない薬剤は透析により6―7割を喪失することになる。適正な投与にはそれらの基礎知識が不可欠である。
◆わかりやすくコンパクトにまとめられた腎機能低下患者の診療
本書では,「総論」として,中毒性腎障害,造影剤による腎障害,腎機能の程度にしたがった薬物療法,腎臓の構造・機能と薬物排泄,腎機能低下時の薬剤投与設計などの基礎がわかりやすく解説されている。
また,「各論」において感染症治療薬(抗菌薬,抗真菌薬,抗ウイルス薬など)および呼吸器疾患治療薬,循環器疾患治療薬,消化器疾患治療薬,精神・神経疾患治療薬,血液疾患,内分泌・代謝疾患治療薬,抗炎症薬,抗リウマチ薬,鎮痛薬,造影剤,診断用薬,その他の薬剤について,具体的に100種類以上の薬剤をあげて,代表的商品名,剤形,適応,常用量,腎排泄率,主な類似薬,腎機能低下時の処方例,腎機能低下時の副作用・相互作用などにつき,わかりやすく,コンパクトにまとめられている。さらに,薬剤ごとに腎機能低下患者への投与時のワンポイントアドバイスを示し,注意点を喚起している点が魅力である。
本書は,臨床家が日常診察室のかたわらに置いて,または白衣のポケットに入れて,治療の合間に参考にするにふさわしい治療マニュアルである。多くの臨床家の腎機能低下患者診察に大いに役立つものと確信する。
“かゆいところに手が届く”きわめて実践的編集
書評者: 小池 隆夫 (北大大学院教授・免疫病態内科学)
超高齢化社会の到来が現実になり,加えて糖尿病患者の急増などにより,腎機能が低下している患者に遭遇する機会も増えてきた。また,腎機能は正常でありながらも,現在投与している薬がどの程度腎機能に障害を与えるのか悩むことは,日常臨床ではしばしば経験する。
◆投薬に際しての疑問や注意点がたちどころにわかる内容
このたび富野康日己教授が編集され,ご自身と順天堂大学医学部腎臓内科のスタッフによって執筆された『腎機能低下患者への薬の使い方』という実に実践的でかつ有用な本が上梓された。私から申すまでもないが,富野教授は,IgA腎症の世界的な権威であられる。数年前『IgA Nephropathy; from molecules to men』と題する研究の集大成を〈Contributions to Nephrology〉(Karger)に,ご自身の単著で上梓され,その内容の豊かさに圧倒されたことが記憶に新しい。今回のテキストは,それとはがらりと趣が変わり,まさに“かゆいところに手が届く”編集で,きわめて実践的であり,われわれがしばしば遭遇する,腎機能低下患者への投薬に際してのさまざまな疑問や注意点が,たちどころにわかる内容になっている。
◆大変役立つ「ワンポイントアドバイス」
「腎と薬物療法」,「腎と薬物動態の基礎知識」の2章からなる総論と続く8章に及ぶ各論から構成されている本書の最大の特徴の1つは,腎機能低下時における各種薬剤の使い方を,見開き2頁にコンパクトにまとめてある点である。薬剤名と常用量ならびにその薬剤の腎排泄率が簡潔に記述されており,続いて腎機能低下時の処方例や副作用ならびに相互作用の要点が書かれている。特記すべきは,「ワンポイントアドバイス」が全薬剤につき述べられていることであり,これが大変に役立つ。まず最初にこの部分に目をとおし,投与する薬剤の基本的知識を再確認するとよい。
本書の約半分が,抗生物質と降圧剤を主体とした循環器薬で占められていることも,日常臨床でこのような薬剤が使用されることが多い現実に即している。アミノグリコシドはもとより第三世代セフェム系,キノロンさらにはニューキノロンにも記述が及んでいる。また腎機能障害時に使われることの多い各種ACE阻害薬や,最近のアンジオテンシンII受容体拮抗薬も記載されている。
腎臓病一般に使用する治療薬が,副腎皮質ホルモン,免疫抑制剤,利尿薬程度しか存在しないにもかかわらず,日常臨床で遭遇する腎機能低下患者はきわめて多く,さまざまな注意が必要であることは皮肉な現実ではあるが,本書は大きさも手ごろで,日常臨床にきわめて有用であり,研修医や一般医家に広くお勧めしたい。
腎不全患者を扱う医療関係者に必携の1冊
書評者: 斉藤 喬雄 (福岡大教授・腎臓内科学)
一般に薬剤の代謝過程において,腎臓は肝臓とともに重要な排泄経路である。特に腎臓では,糸球体濾過の他に尿細管における再吸収・分泌というメカニズムが排泄を複雑にしており,薬剤によって排泄の実態が異なっていると考えられる。したがって,専門医といえる私たちでも,十分理解していない点が少なくない。
◆常に念頭に置く必要がある腎機能と薬剤情報
腎で排泄される薬剤については,腎機能低下とともに血中濃度が異常に上昇し,副作用を引き起こす危険があることや,排泄の過程で主に尿細管・間質系に障害を及ぼす恐れについて考慮しなければならない。最近,このような問題が重視されており,実際の診療において薬剤の投与量を定める場合,常に念頭に置く必要が出てきた。このため,各薬剤ごとに,腎機能と投与量の関係を示した成書もいくつか出版されている。しかし,これらでは詳細な内容は示されずに,単に投与量を羅列するに終わっていることも多い。また,新しい薬剤についての記載が少なく,使用したい薬剤の情報がしばしば得られない。
今回,富野教授の編集により刊行された『腎機能低下患者への薬の使い方』では,このような問題点を十分に考慮し,保存期および透析期腎不全の治療を行なうにあたって,実際的な薬剤の使い方を述べている。使用頻度が高い薬剤を中心に,副作用や相互作用などとともに処方例がのせられており,医療現場において,迷うことなく処方用量を定められるという利点を持つ。特に,現場で遭遇する状況を想定してその対処法を説明したワンポイントアドバイスは,きわめて有用であろう。使用される場を考慮して小型化してサイズも好ましい。
一方,なぜこのような投与量にしなければならないのか,腎機能低下時における薬物動態や薬物投与設計について,薬理学の植松俊彦岐阜大学名誉教授により詳しく解説がなされている。したがって,本書に記載されていない薬剤を投与する必要がある場合に,投与量を決定する参考となるし,腎機能低下時の薬剤投与法をよく理解し知識をまとめる際に役に立つ。現場を離れて十分な時間がある時など,腎臓の役割を認識する上からも好著である。以上のような点から,本書は腎や透析の専門医だけでなく,腎不全患者を扱う医師に広く勧めたい。
更新情報
-
更新情報はありません。
お気に入り商品に追加すると、この商品の更新情報や関連情報などをマイページでお知らせいたします。