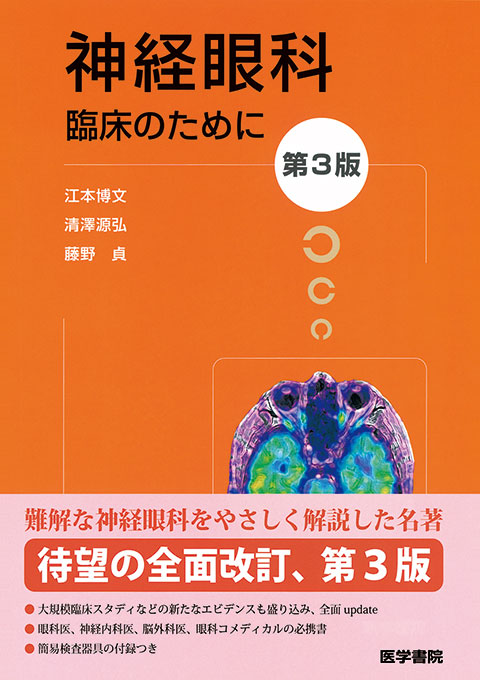神経眼科 第2版
臨床のために
「難しい」神経眼科をわかりやすく実践的に解説
もっと見る
「ポケットに入るほどの器具を用いる神経眼科」のキャッチフレーズで登場した本書は,とかく難しいと言われる神経眼科において,多くの臨床家の福音となった。改訂第2版は,わかりやすく実践的というコンセプトはそのままに,さらに研鑚を重ねた著者が内容を大幅に追加した。眼科医はもとより,神経内科医,脳神経外科医も必携の書。
| 著 | 藤野 貞 |
|---|---|
| 発行 | 2001年10月判型:B5頁:328 |
| ISBN | 978-4-260-13774-4 |
| 定価 | 10,450円 (本体9,500円+税) |
- 販売終了
更新情報
-
更新情報はありません。
お気に入り商品に追加すると、この商品の更新情報や関連情報などをマイページでお知らせいたします。
- 目次
- 書評
目次
開く
神経眼科臨床の解剖・生理(図譜)
症状・徴候より診断へ(decision tree)
1 視神経の病変
2 乳頭の腫脹・隆起,乳頭の異常
3 神経と関連の深い眼病変,頭蓋内病変
4 視交叉,頭蓋内視路および後頭葉視領の病変
5 瞳孔,自律神経系の異常
6 眼球運動の障害
7 眼振
8 眼瞼の異常,顔面神経の障害
9 眼窩
10 片頭痛,頭蓋内循環障害,その他の頭痛
11 ポケットに入る神経眼科用検査器具とその使用法
症状・徴候より診断へ(decision tree)
1 視神経の病変
2 乳頭の腫脹・隆起,乳頭の異常
3 神経と関連の深い眼病変,頭蓋内病変
4 視交叉,頭蓋内視路および後頭葉視領の病変
5 瞳孔,自律神経系の異常
6 眼球運動の障害
7 眼振
8 眼瞼の異常,顔面神経の障害
9 眼窩
10 片頭痛,頭蓋内循環障害,その他の頭痛
11 ポケットに入る神経眼科用検査器具とその使用法
書評
開く
著者の気力に溢れる神経眼科の好書
書評者: 本田 孔士 (京大大学院教授・視覚病態学)
CTやMRIがなくても,上手な問診や簡単な(著者は「ポケットに入るほどの」と形容している)小道具で,神経眼科はここまでわかるということを示した好著(1991年)の改訂版である。
◆小気味いい割り切った記述と診断フローチャート
文章は要点箇条書きのサブノート形式をとり,余計なことは一切書かれていない。したがって,全巻328頁ではあるが内容が非常に濃い。この厄介な分野で箇条書きに言い切るには,著者の頭の中で物事がよほど明解に理解されていなければならないわけで,割り切った記述と診断フローチャート(decision tree)が実に小気味いい。いろいろな例外を記して大枚の頁を費やすより,よほど大変な作業だったと思い,著者の努力に頭が下がる思いである。
挿入図も写真でなく,著者が1つひとつを確認して手描きしており,心がこもっている。だから文中に示された解剖図や神経路は,決して美しくはないが,とてもわかりやすい。今回の改訂ではカラー版も含め,数も内容もさらに充実した。
ここで著者が唱えている「患者にできるだけ負担をかけない」という視点は,現在,われわれが高度な検査にあまりにも安易に依存しがちな傾向に竿さし,とても輝いて,かえって新鮮にみえるから不思議である。臨床症状から病巣決定まで,診察は頭でするものだ,ということを改めて思い起こさせる。文献として,本邦で手に入りやすいものをあえて選んでいるところも親切である。大学の図書館にいかねばみられないような外国文献を羅列しても,多くの読者にとって実用的でない,という著者の判断によるのだろう。その数も,厳選されたものばかりで過不足がない。
◆感嘆する著者の神経眼科臨床の力
著者は第11章で,自分の白衣のポケットの中味を披露して,小道具の使い方を述べているが,この簡単な道具が手品のように診断に役立つからおもしろい。実際,その小道具が巻末に付録としてついているのも親切である。入門書として読まれた方は,こんなに明解にパズルが解けるのかと,著者の神経眼科臨床の力に感嘆するだろうし,きっとこの分野が好きになると思う。その意味で類をみない好著と言える。一方,著者が最初に述べているように,このような診察で手に負えない症例に出くわした時は,それなりの病院へ紹介し高度な検査に委ねるべきことは当然で,手作り診察の分限を弁えるべきことも諭している。この本に述べられた神経眼科は,神経内科,脳外科医にも格好のボリュームであり,眼科の診療装置を持たない方にとっても,きわめて有用であろう。
初版には,「亡き父母に,そして妻寿に」との献辞があったが,今回の改訂では,「亡き妻,寿(Toshi)に」とされており,先日他界した寿氏(MD)への著者の深い思いやりを感じる。藤野氏は,最近,若手臨床家を育てるために,寿さんの名を付した多額の基金を日本神経眼科学会に寄贈しており,氏の神経眼科への思い入れがいかに深いかがわかる。藤野氏こそ,疑いもなくこの分野の日本の代表的Founderである。私は,氏の気力に溢れるこの好著書を,視覚の神経異常を扱うすべての臨床医の座右の書として強く推薦したい。
時間とともにますます深まっていく優れた臨床家の知恵
書評者: 岩田 誠 (東女医大脳神経センター所長)
藤野先生の本が改訂されたので書評を頼みたいという依頼を,私は2つ返事で引き受けてしまった。しかしその後になって,私はこれまで同じ本の書評を2度も書いたことはないことに気がついた。私は,すでに藤野先生の書かれたこの教科書の初版の書評を書き,そのすばらしい内容に対して賞賛の意を表したのである。その私が,同じ書物の改訂第2版に対する書評を書くとすれば,それは当然,初版との比較にならざるを得ない。またその改訂版は,初版よりも格段に優れたものであってくれねばならない。書評というものは,その対象となった書物が,買うべき本かどうかということを,買おうか買うまいか迷っている人に示して,その判断を助けるためのものだからである。ちょうど10年前に出版された藤野先生の本が,その時点ですでにすばらしく完成された内容のものであっただけに,その改訂が一体どのようになされるのか,そして初版本を持っている人に対しても,改訂版を買うことを勧め得るかどうか,その点についていささかの不安をおぼえたのである。
◆数段読みやすくなった第2版
そんな気持ちで第2版を手にした私は,今度の版が,藤野先生の巧みな工夫により,初版本より数段読みやすくなっていることに気づき,大変驚いた。赤・青の入った3色刷りになったせいか,冒頭の図譜の部分からして,初版とは随分変わった感じであり,格段と見やすい図に変わっている。また,本文中の説明図も随分増えていて,記述だけではやや難解なところも容易に理解できるようになっているのがありがたい。それに加えての傑作は,藤野先生がところどころに挿入されている,ユーモアあふれる漫画風のイラストである。これらの絵を見ていると,かつて東大病院でさまざまな患者を診ていただき,1つひとつの所見についてていねいに教えていただいた頃を思い出す。難しい問題をも私たちにわかりやすく,そして楽しく教えてくださったあの頃の藤野先生のお姿そのままが,この書物に見えてくる。本書の初版の書評の中で,私は,「優れた臨床家の知恵というものを読み取ってほしい」と書いた。そしてこの第2版を読んだ私は,優れた臨床家の知恵は時間とともにますます深まっていくことを知った。その故をもって,この書物は,これから神経眼科学を学ぼうとされる方々にお勧めできるだけでなく,すでに初版本によって神経眼科学を学ばれた方々にも,私は自信を持って改訂版に買い替えることをお勧めしたいと思うのである。
よく見ると,初版本では「妻に」とあった中扉の献辞が,「亡き妻に」と変わっていた。藤野先生の臨床家としての知恵を支えられた奥様のご冥福をお祈りしたい。
神経眼科一筋30年,著者研鑽の結実
書評者: 大庭 紀雄 (鹿児島大教授・眼科学)
◆学際的研究進む神経眼科
「神経眼科」という学際的な診療研究領域があるのをご存じだろうか。視覚系には,網膜から視覚皮質までの入力系,瞳孔運動や眼球運動系などの出力系がある。精緻かつ複雑な神経回路網のどこかに機能的あるいは構造的な異常が発生すれば,視覚生活に支障をきたすであろう。物を「見る」といった原初感覚の異常から,「認知し解釈し記憶する」といった高次感覚の異常まで,さまざまなタイプの疾病や病態が診療現場に持ち込まれてくる。視覚系の異常を専門とする眼科の診療は,眼光学(ophthalmic optics)・内科的眼科学(medical ophthalmology)・外科的眼科学(surgical ophthalmology)を中核とするが,そこに隣接するのが神経眼科学(neuro-ophthalmology)である。眼科の固有領域と異なって,神経内科,脳神経外科,精神神経科,耳鼻科などと連携して問題の解決に立ち向かう必要がある。こうした観点に立って,先進諸国,ことに米国では,高度医療施設にサブスペシャリストneuro-ophthalmologistが配置されて,講座や診療科を横断して診療のみならず教育と研究に活動している。専門医の多くは眼科を基盤として,神経学関連領域の研修を受けて活躍している。わが国では,さまざまな理由から独立した診療部門の設置にはいたっていないが,学会活動は活発に行なわれており,25年の歴史を持つ日本神経眼科学会は,1000名を超える会員でもって国際レベルを維持している。
◆神経眼科を身近にさせてくれる心憎い工夫の数々
神経眼科の対象疾患は多岐にわたるが,白内障や眼底病のようには手にとるように見えにくいのに加えて,治療が困難な事例が多いといったことから,眼科の中でも敬遠されがちである。だが,対象となる患者は決して少なくないから,その知識は日常診療では欠かすことができない。本書は,30年にわたって神経眼科一筋に研鑽を積んでこられた藤野博士によるものである。
本書の初版から10年,診断技術,病態理解が進んだ。筆者には初版でも書評を書く機会があったが,本書刊行の意図と目標は,初版の書き出しに明解である。「神経眼科は難しいという。本当でしょうか。『山登り』と聞き,ロッククライミングを連想すると,その技術の高度さに,自分とは無縁のものと思うでしょう……」。第2版の序はこうである。「神経系病変には,しばしば眼の異変が現れる。問診と,眼の所見,患者の状態の注意深い観察で,主病変が何処にあるか,何の異変か,見当をつけられることが少なくない……しかし,傍ら患者さんの望む,治療,対策,予防,カウンセリングなどに,素早く対応できるように心掛けたい」。まず地図(解剖図)をそろえ,簡単な検査から診断へのディシジョン・ツリーを作成し,対象となる疾病をくまなく取り上げて要点を記載し,ポケットに入るほどの診察器具を付録とする,といった神経眼科を身近にさせてくれる工夫は心憎いほどである。眼科の研修医のみならず,神経疾患に接する多くの方々が診察机をそなえておけば,大いに役立つにちがいない。
書評者: 本田 孔士 (京大大学院教授・視覚病態学)
CTやMRIがなくても,上手な問診や簡単な(著者は「ポケットに入るほどの」と形容している)小道具で,神経眼科はここまでわかるということを示した好著(1991年)の改訂版である。
◆小気味いい割り切った記述と診断フローチャート
文章は要点箇条書きのサブノート形式をとり,余計なことは一切書かれていない。したがって,全巻328頁ではあるが内容が非常に濃い。この厄介な分野で箇条書きに言い切るには,著者の頭の中で物事がよほど明解に理解されていなければならないわけで,割り切った記述と診断フローチャート(decision tree)が実に小気味いい。いろいろな例外を記して大枚の頁を費やすより,よほど大変な作業だったと思い,著者の努力に頭が下がる思いである。
挿入図も写真でなく,著者が1つひとつを確認して手描きしており,心がこもっている。だから文中に示された解剖図や神経路は,決して美しくはないが,とてもわかりやすい。今回の改訂ではカラー版も含め,数も内容もさらに充実した。
ここで著者が唱えている「患者にできるだけ負担をかけない」という視点は,現在,われわれが高度な検査にあまりにも安易に依存しがちな傾向に竿さし,とても輝いて,かえって新鮮にみえるから不思議である。臨床症状から病巣決定まで,診察は頭でするものだ,ということを改めて思い起こさせる。文献として,本邦で手に入りやすいものをあえて選んでいるところも親切である。大学の図書館にいかねばみられないような外国文献を羅列しても,多くの読者にとって実用的でない,という著者の判断によるのだろう。その数も,厳選されたものばかりで過不足がない。
◆感嘆する著者の神経眼科臨床の力
著者は第11章で,自分の白衣のポケットの中味を披露して,小道具の使い方を述べているが,この簡単な道具が手品のように診断に役立つからおもしろい。実際,その小道具が巻末に付録としてついているのも親切である。入門書として読まれた方は,こんなに明解にパズルが解けるのかと,著者の神経眼科臨床の力に感嘆するだろうし,きっとこの分野が好きになると思う。その意味で類をみない好著と言える。一方,著者が最初に述べているように,このような診察で手に負えない症例に出くわした時は,それなりの病院へ紹介し高度な検査に委ねるべきことは当然で,手作り診察の分限を弁えるべきことも諭している。この本に述べられた神経眼科は,神経内科,脳外科医にも格好のボリュームであり,眼科の診療装置を持たない方にとっても,きわめて有用であろう。
初版には,「亡き父母に,そして妻寿に」との献辞があったが,今回の改訂では,「亡き妻,寿(Toshi)に」とされており,先日他界した寿氏(MD)への著者の深い思いやりを感じる。藤野氏は,最近,若手臨床家を育てるために,寿さんの名を付した多額の基金を日本神経眼科学会に寄贈しており,氏の神経眼科への思い入れがいかに深いかがわかる。藤野氏こそ,疑いもなくこの分野の日本の代表的Founderである。私は,氏の気力に溢れるこの好著書を,視覚の神経異常を扱うすべての臨床医の座右の書として強く推薦したい。
時間とともにますます深まっていく優れた臨床家の知恵
書評者: 岩田 誠 (東女医大脳神経センター所長)
藤野先生の本が改訂されたので書評を頼みたいという依頼を,私は2つ返事で引き受けてしまった。しかしその後になって,私はこれまで同じ本の書評を2度も書いたことはないことに気がついた。私は,すでに藤野先生の書かれたこの教科書の初版の書評を書き,そのすばらしい内容に対して賞賛の意を表したのである。その私が,同じ書物の改訂第2版に対する書評を書くとすれば,それは当然,初版との比較にならざるを得ない。またその改訂版は,初版よりも格段に優れたものであってくれねばならない。書評というものは,その対象となった書物が,買うべき本かどうかということを,買おうか買うまいか迷っている人に示して,その判断を助けるためのものだからである。ちょうど10年前に出版された藤野先生の本が,その時点ですでにすばらしく完成された内容のものであっただけに,その改訂が一体どのようになされるのか,そして初版本を持っている人に対しても,改訂版を買うことを勧め得るかどうか,その点についていささかの不安をおぼえたのである。
◆数段読みやすくなった第2版
そんな気持ちで第2版を手にした私は,今度の版が,藤野先生の巧みな工夫により,初版本より数段読みやすくなっていることに気づき,大変驚いた。赤・青の入った3色刷りになったせいか,冒頭の図譜の部分からして,初版とは随分変わった感じであり,格段と見やすい図に変わっている。また,本文中の説明図も随分増えていて,記述だけではやや難解なところも容易に理解できるようになっているのがありがたい。それに加えての傑作は,藤野先生がところどころに挿入されている,ユーモアあふれる漫画風のイラストである。これらの絵を見ていると,かつて東大病院でさまざまな患者を診ていただき,1つひとつの所見についてていねいに教えていただいた頃を思い出す。難しい問題をも私たちにわかりやすく,そして楽しく教えてくださったあの頃の藤野先生のお姿そのままが,この書物に見えてくる。本書の初版の書評の中で,私は,「優れた臨床家の知恵というものを読み取ってほしい」と書いた。そしてこの第2版を読んだ私は,優れた臨床家の知恵は時間とともにますます深まっていくことを知った。その故をもって,この書物は,これから神経眼科学を学ぼうとされる方々にお勧めできるだけでなく,すでに初版本によって神経眼科学を学ばれた方々にも,私は自信を持って改訂版に買い替えることをお勧めしたいと思うのである。
よく見ると,初版本では「妻に」とあった中扉の献辞が,「亡き妻に」と変わっていた。藤野先生の臨床家としての知恵を支えられた奥様のご冥福をお祈りしたい。
神経眼科一筋30年,著者研鑽の結実
書評者: 大庭 紀雄 (鹿児島大教授・眼科学)
◆学際的研究進む神経眼科
「神経眼科」という学際的な診療研究領域があるのをご存じだろうか。視覚系には,網膜から視覚皮質までの入力系,瞳孔運動や眼球運動系などの出力系がある。精緻かつ複雑な神経回路網のどこかに機能的あるいは構造的な異常が発生すれば,視覚生活に支障をきたすであろう。物を「見る」といった原初感覚の異常から,「認知し解釈し記憶する」といった高次感覚の異常まで,さまざまなタイプの疾病や病態が診療現場に持ち込まれてくる。視覚系の異常を専門とする眼科の診療は,眼光学(ophthalmic optics)・内科的眼科学(medical ophthalmology)・外科的眼科学(surgical ophthalmology)を中核とするが,そこに隣接するのが神経眼科学(neuro-ophthalmology)である。眼科の固有領域と異なって,神経内科,脳神経外科,精神神経科,耳鼻科などと連携して問題の解決に立ち向かう必要がある。こうした観点に立って,先進諸国,ことに米国では,高度医療施設にサブスペシャリストneuro-ophthalmologistが配置されて,講座や診療科を横断して診療のみならず教育と研究に活動している。専門医の多くは眼科を基盤として,神経学関連領域の研修を受けて活躍している。わが国では,さまざまな理由から独立した診療部門の設置にはいたっていないが,学会活動は活発に行なわれており,25年の歴史を持つ日本神経眼科学会は,1000名を超える会員でもって国際レベルを維持している。
◆神経眼科を身近にさせてくれる心憎い工夫の数々
神経眼科の対象疾患は多岐にわたるが,白内障や眼底病のようには手にとるように見えにくいのに加えて,治療が困難な事例が多いといったことから,眼科の中でも敬遠されがちである。だが,対象となる患者は決して少なくないから,その知識は日常診療では欠かすことができない。本書は,30年にわたって神経眼科一筋に研鑽を積んでこられた藤野博士によるものである。
本書の初版から10年,診断技術,病態理解が進んだ。筆者には初版でも書評を書く機会があったが,本書刊行の意図と目標は,初版の書き出しに明解である。「神経眼科は難しいという。本当でしょうか。『山登り』と聞き,ロッククライミングを連想すると,その技術の高度さに,自分とは無縁のものと思うでしょう……」。第2版の序はこうである。「神経系病変には,しばしば眼の異変が現れる。問診と,眼の所見,患者の状態の注意深い観察で,主病変が何処にあるか,何の異変か,見当をつけられることが少なくない……しかし,傍ら患者さんの望む,治療,対策,予防,カウンセリングなどに,素早く対応できるように心掛けたい」。まず地図(解剖図)をそろえ,簡単な検査から診断へのディシジョン・ツリーを作成し,対象となる疾病をくまなく取り上げて要点を記載し,ポケットに入るほどの診察器具を付録とする,といった神経眼科を身近にさせてくれる工夫は心憎いほどである。眼科の研修医のみならず,神経疾患に接する多くの方々が診察机をそなえておけば,大いに役立つにちがいない。
更新情報
-
更新情報はありません。
お気に入り商品に追加すると、この商品の更新情報や関連情報などをマイページでお知らせいたします。