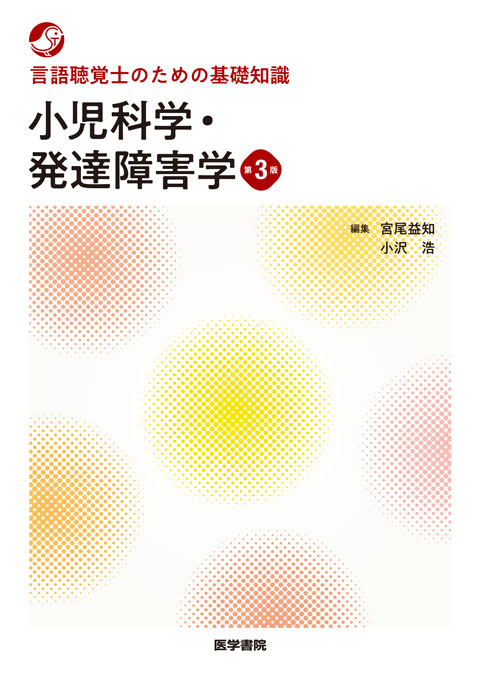発達期言語コミュニケーション障害の新しい視点と介入理論
『言語コミュニケーション障害の新しい視点と介入理論』の姉妹編登場
もっと見る
ここ数年、発達障害としてのコミュニケーション障害(本書の第1章~第5章)の本質に迫る脳科学的、認知・行動科学的究明が急速に進展しつつある。本書ではこれら5障害と共に、発達障害の特性を部分的に持つコミュニケーション障害(第6章~第8章)をも取り上げ、内外の文献reviewによる最新の知見・展望を読者に示し、臨床的・教育的対応への示唆・提言を行う。コミュニケーション障害のある子どもたちにかかわる専門職、特別支援教育担当教員などの必読の書。
| 編集 | 笹沼 澄子 |
|---|---|
| 発行 | 2007年06月判型:B5頁:328 |
| ISBN | 978-4-260-00366-7 |
| 定価 | 6,600円 (本体6,000円+税) |
- 販売終了
更新情報
-
更新情報はありません。
お気に入り商品に追加すると、この商品の更新情報や関連情報などをマイページでお知らせいたします。
- 序文
- 目次
- 書評
序文
開く
序
笹沼澄子
ここ数年来の精神・神経科学,分子遺伝学などを含む脳科学領域の目覚しい進展と相俟って,子どもたちのなかに少なからず発現する発達障害(developmental disorder)としての言語コミュニケーション障害が新たな注目を浴びています.こうした障害の発現メカニズムや障害像の特性をめぐる“発達認知神経心理学的”ともいえる研究・論議が,このところ内外の関連誌上をにぎわしているのです.これら言語コミュニケーション障害は,言語発達の“単なる遅れ”とは異質な障害であり,生得的な要因に由来する脳機能の非定型的な発達過程と環境要因とのダイナミックな相互作用によって形成される可能性が明らかにされつつあります.本書は,このような発達障害としての言語コミュニケーション障害に関する最新の知見・理論を整理・統合し,子どもたち一人ひとりの言語臨床に反映させるとともに,仮説検証的な介入活動を通して障害の発現・変容過程のメカニズム解明への限りない接近にも貢献することを願って企画されました.
全体の構成は11章からなり,そのうちの8章が,いわば典型的な発達障害(第1~5章)および発達障害的要因を大なり小なり併せ持つ言語コミュニケーション障害(第6~8章)に当てられています.前者,典型的発達障害に含まれるのは,自閉症スペクトラム,発達性読み書き障害(発達性dyslexia),特異的言語発達障害,Down症候群,およびWilliams症候群の5分野であり,それぞれの歴史的背景,障害の実態に関する実証的研究の蓄積・深化の度合い,臨床的評価・診断・介入法の確立度,などの点でさまざまな段階にあることがうかがわれます.後者,発達障害的要因を併せ持つ言語コミュニケーシ障害としては,後天性小児失語症の障害像と改善過程,人工内耳装用児の言語発達にみる脳機能の可塑性,吃音の脳科学的・音声言語学的・遺伝学的知見,などを取り上げました.残る3章中の2章(第9,10章)は,健常乳児の音声知覚および幼児の言語発達過程についてそれぞれ最新の知見を織り込んだ解説編であり,最後を締めくくる第11章には,発達障害に関する最近の神経学的・行動学的知見の飛躍的進歩を支えている脳機能画像の方法論について,fMRIに的を絞った小児・乳幼児の脳機能イメージングの現況と展望が述べられています.
執筆の労をとられた先生方は,児童精神医学・小児神経学・耳鼻咽喉科学領域でそれぞれ研鑽を積まれた医師,および心理学・認知神経心理学・言語学,心理言語学・言語聴覚障害学などの第一線で活躍されている専門職の方々であり,文字通り学際的な陣容を構成しています.執筆方針として,各担当領域にかかわる内外の研究論文のreviewを通して最新のperspectivesを読者に示し,今後の課題・展望に加えて,言語臨床を中心とする療育/教育支援のあり方についての示唆・提言にもふれていただくようにお願いしました.
なお,本書の編集を最初に思い立ち,上記執筆陣の参加了承も含めて大まかな構想ができあがったのは,成人・高齢者の言語コミュニケーション障害に焦点を当てた既出書『言語コミュニケーション障害の新しい視点と介入理論』(2005年)の構想が具体化し始めた3年前の早春に遡ります.この書の姉妹編として,発達期の子どもたちに現れる言語コミュニケーション障害にさまざまな立場から関与しておられる方々に,上述のような発達障害に関する新しい視点を伝え,可及的早期の評価・診断手続きによって障害児一人ひとりの特性を明らかにし,一人ひとりの潜在能力を最大限に引き出し育成しうるような介入・支援方略を企画・実施していただく必要性を強く感じたからにほかなりません.しかし,諸般の事情により計画の達成が大幅に遅れ,今日に至りました.
この間にわが国では国連による障害者の「完全参加と平等」の理念に基づき策定された「障害者基本計画」(2003~2012年度)のなかで,障害児者の個別的ニーズを重視し,乳幼児から学校卒業後までのライフステージに沿った一貫した個別支援計画の一環として「特別支援教育制度の在り方」が検討されてきました.教育現場では,この4月から「一人ひとりの教育的ニーズを把握」し,「適切な指導および必要な支援を行う」特別支援教育制度が全国的な規模で実際に動き出すと聞いています.この特別支援教育では,従来の特殊教育の対象となってきた知的障害・聴覚障害・言語障害などに加え,通常の学級に在籍することの多い高機能自閉症(本書第1章),学習障害/LD(本書コラムC)の80%を占めるとされる発達性dyslexia(第2章),これら2 つの障害と併存または独立して出現する注意欠陥/多動性障害(AD/HD)(コラムA,コラムD)などがある子どもが対象として含まれることになりました.また,言語障害〔特異的言語発達障害(第3章),後天性小児失語症(第4章),吃音(第8章)など〕,聴覚障害〔人工内耳装用適応の聴覚障害(第7章)など〕,知的障害〔Down症候群(第4章),Williams症候群(第5章)など〕のために従来の特殊教育の対象となってきた子どもたちも,それぞれ個を重視する特別支援教育の理念を具現した施策に浴することが期待されます.
特別支援教育の実を真に挙げるための必須条件の第一は,個々の対象児がもつ問題/障害特性の専門的評価・診断に基づいた介入・教育的ニーズの正確な把握にあります.しかも,発達・成長に伴う障害特性,したがって本人が必要とする介入・支援内容の変容に柔軟に対応しうる縦断的視点が不可欠であり,そのためにも多分野間の密接な連携を基盤とする一貫した支援システムの構築が最重要課題の1つでありましょう.こうした支援教育システムにかかわる教職員・関連専門職すべての方々にとって,本書の各章に盛り込まれている基本的かつ最前線の知見・情報がさまざまなかたちでお役に立てることを切に願うしだいです.
最後に,予想を超えて長期にわたった本書の編集作業に,終始一貫行き届いたお世話をいただきました医学書院の坂口順一氏に深謝いたします.
2007年4月
笹沼澄子
ここ数年来の精神・神経科学,分子遺伝学などを含む脳科学領域の目覚しい進展と相俟って,子どもたちのなかに少なからず発現する発達障害(developmental disorder)としての言語コミュニケーション障害が新たな注目を浴びています.こうした障害の発現メカニズムや障害像の特性をめぐる“発達認知神経心理学的”ともいえる研究・論議が,このところ内外の関連誌上をにぎわしているのです.これら言語コミュニケーション障害は,言語発達の“単なる遅れ”とは異質な障害であり,生得的な要因に由来する脳機能の非定型的な発達過程と環境要因とのダイナミックな相互作用によって形成される可能性が明らかにされつつあります.本書は,このような発達障害としての言語コミュニケーション障害に関する最新の知見・理論を整理・統合し,子どもたち一人ひとりの言語臨床に反映させるとともに,仮説検証的な介入活動を通して障害の発現・変容過程のメカニズム解明への限りない接近にも貢献することを願って企画されました.
全体の構成は11章からなり,そのうちの8章が,いわば典型的な発達障害(第1~5章)および発達障害的要因を大なり小なり併せ持つ言語コミュニケーション障害(第6~8章)に当てられています.前者,典型的発達障害に含まれるのは,自閉症スペクトラム,発達性読み書き障害(発達性dyslexia),特異的言語発達障害,Down症候群,およびWilliams症候群の5分野であり,それぞれの歴史的背景,障害の実態に関する実証的研究の蓄積・深化の度合い,臨床的評価・診断・介入法の確立度,などの点でさまざまな段階にあることがうかがわれます.後者,発達障害的要因を併せ持つ言語コミュニケーシ障害としては,後天性小児失語症の障害像と改善過程,人工内耳装用児の言語発達にみる脳機能の可塑性,吃音の脳科学的・音声言語学的・遺伝学的知見,などを取り上げました.残る3章中の2章(第9,10章)は,健常乳児の音声知覚および幼児の言語発達過程についてそれぞれ最新の知見を織り込んだ解説編であり,最後を締めくくる第11章には,発達障害に関する最近の神経学的・行動学的知見の飛躍的進歩を支えている脳機能画像の方法論について,fMRIに的を絞った小児・乳幼児の脳機能イメージングの現況と展望が述べられています.
執筆の労をとられた先生方は,児童精神医学・小児神経学・耳鼻咽喉科学領域でそれぞれ研鑽を積まれた医師,および心理学・認知神経心理学・言語学,心理言語学・言語聴覚障害学などの第一線で活躍されている専門職の方々であり,文字通り学際的な陣容を構成しています.執筆方針として,各担当領域にかかわる内外の研究論文のreviewを通して最新のperspectivesを読者に示し,今後の課題・展望に加えて,言語臨床を中心とする療育/教育支援のあり方についての示唆・提言にもふれていただくようにお願いしました.
なお,本書の編集を最初に思い立ち,上記執筆陣の参加了承も含めて大まかな構想ができあがったのは,成人・高齢者の言語コミュニケーション障害に焦点を当てた既出書『言語コミュニケーション障害の新しい視点と介入理論』(2005年)の構想が具体化し始めた3年前の早春に遡ります.この書の姉妹編として,発達期の子どもたちに現れる言語コミュニケーション障害にさまざまな立場から関与しておられる方々に,上述のような発達障害に関する新しい視点を伝え,可及的早期の評価・診断手続きによって障害児一人ひとりの特性を明らかにし,一人ひとりの潜在能力を最大限に引き出し育成しうるような介入・支援方略を企画・実施していただく必要性を強く感じたからにほかなりません.しかし,諸般の事情により計画の達成が大幅に遅れ,今日に至りました.
この間にわが国では国連による障害者の「完全参加と平等」の理念に基づき策定された「障害者基本計画」(2003~2012年度)のなかで,障害児者の個別的ニーズを重視し,乳幼児から学校卒業後までのライフステージに沿った一貫した個別支援計画の一環として「特別支援教育制度の在り方」が検討されてきました.教育現場では,この4月から「一人ひとりの教育的ニーズを把握」し,「適切な指導および必要な支援を行う」特別支援教育制度が全国的な規模で実際に動き出すと聞いています.この特別支援教育では,従来の特殊教育の対象となってきた知的障害・聴覚障害・言語障害などに加え,通常の学級に在籍することの多い高機能自閉症(本書第1章),学習障害/LD(本書コラムC)の80%を占めるとされる発達性dyslexia(第2章),これら2 つの障害と併存または独立して出現する注意欠陥/多動性障害(AD/HD)(コラムA,コラムD)などがある子どもが対象として含まれることになりました.また,言語障害〔特異的言語発達障害(第3章),後天性小児失語症(第4章),吃音(第8章)など〕,聴覚障害〔人工内耳装用適応の聴覚障害(第7章)など〕,知的障害〔Down症候群(第4章),Williams症候群(第5章)など〕のために従来の特殊教育の対象となってきた子どもたちも,それぞれ個を重視する特別支援教育の理念を具現した施策に浴することが期待されます.
特別支援教育の実を真に挙げるための必須条件の第一は,個々の対象児がもつ問題/障害特性の専門的評価・診断に基づいた介入・教育的ニーズの正確な把握にあります.しかも,発達・成長に伴う障害特性,したがって本人が必要とする介入・支援内容の変容に柔軟に対応しうる縦断的視点が不可欠であり,そのためにも多分野間の密接な連携を基盤とする一貫した支援システムの構築が最重要課題の1つでありましょう.こうした支援教育システムにかかわる教職員・関連専門職すべての方々にとって,本書の各章に盛り込まれている基本的かつ最前線の知見・情報がさまざまなかたちでお役に立てることを切に願うしだいです.
最後に,予想を超えて長期にわたった本書の編集作業に,終始一貫行き届いたお世話をいただきました医学書院の坂口順一氏に深謝いたします.
2007年4月
目次
開く
第1章 自閉症スペクトラムの理解
第2章 発達性読み書き障害
第3章 特異的言語発達障害とその周辺
第4章 Down症候群の言語・コミュニケーション能力
第5章 Williams症候群の発達認知神経心理学
第6章 後天性小児失語症をめぐる諸問題
第7章 脳機能からみた人工内耳装用児の言語発達
第8章 吃音研究の現状と展望
第9章 健常乳児の音声知覚と言語発達
第10章 幼児期の話しことばの発達
第11章 小児・乳幼児の脳機能イメージング
索引
第2章 発達性読み書き障害
第3章 特異的言語発達障害とその周辺
第4章 Down症候群の言語・コミュニケーション能力
第5章 Williams症候群の発達認知神経心理学
第6章 後天性小児失語症をめぐる諸問題
第7章 脳機能からみた人工内耳装用児の言語発達
第8章 吃音研究の現状と展望
第9章 健常乳児の音声知覚と言語発達
第10章 幼児期の話しことばの発達
第11章 小児・乳幼児の脳機能イメージング
索引
書評
開く
「なるほど」と共感してしまう臨床の経験も盛り込まれた良書
書評者: 小枝 達也 (鳥取大学地域学部教授・小児神経科医)
本書は,成人の言語障害を対象とした『言語コミュニケーション障害の新しい視点と介入理論』の姉妹本として企画されたものであると,編集者の笹沼氏が序で述べておられるが,単なる小児に見られるさまざまな言語障害の解説にとどまっておらず,小児の認知神経心理学を網羅するかのような幅広い視点で執筆されている。
最近では,発達障害に焦点をあてたマニュアル的な書籍が氾濫する中で,本書は研究者の視点から多くの文献をていねいに解説しながら,最新の仮説を詳述してあり,実に読み応えのあるものに仕上がっている。
各分担執筆者が丹念に文献を調べ上げて,それをわかりやすく紹介しているだけでなく,各執筆者の研究成果の紹介や臨床家としての経験も盛り込まれているために,単なる理論の展開にとどまっておらず,同じ臨床家として「なるほど」と,つい共感してしまうような記述が多いのも本書の長所と思われる。
特に自閉症スペクトラムとDevelopmental Dyslexiaについては,複数の分担執筆者がこれまでの諸仮説を余すことなく,しかもじつに詳細に紹介してある。これまでいろいろな書籍や文献で得ていた知識が,一挙にまとめて示してあるので,同じ分野を研究しているものの一人として,整理ができて大いに助かる。ふと確認したいと思ったときに,いろいろな書籍や文献を探し回るのではなく,本書に帰れば済むという印象を持った。
小児の言語障害だけでなく,小児の言語発達に関する脳科学的視点と最新の研究成果が盛り込まれているため,本書をじっくりと読みこなすことにより新しい研究の方向性が見えてくるし,具体的なアイデアも浮かんでくる。実にありがたいことである。出版が遅れたと序にあるが,これだけ充実した内容の本が一朝一夕にできあがるとは思えず,遅れたのも無理からぬことであろう。本書の企画編集に精力的に取り組まれた笹沼氏とそれぞれの章を緻密かつていねいに書き上げた各分担執筆者に敬意を表したいと思う。
エビデンスに基づく実践に役立つ「介入理論」
書評者: 藤野 博 (東京学芸大学総合教育科学系特別支援科学講座支援方法学分野准教授)
本書は発達期に生じることばとコミュニケーションの障害について最新の研究知見をまとめたものである。編者はわが国の言語障害学の草分けでありこの分野の研究をリードしてきた笹沼澄子氏で,いずれの章も今日の日本を代表する第一線の研究者・臨床家の手になる。
ここ10年あまりで飛躍的に発展した認知神経心理学と発達神経心理学を背景として進化した近年の発達障害研究の成果が言語・コミュニケーション領域を中心に余すところなくレビューされている。自閉症スペクトラム,発達性読み書き障害,特異的言語発達障害,Down症候群,Williams症候群,後天性小児失語,人工内耳装用児,吃音,健常幼児の音声知覚,幼児期の話しことばの発達,小児・乳幼児の脳機能イメージングの全11章から構成されており,特別支援教育の領域で取り上げられることの多い自閉症スペクトラムと発達性読み書き障害に関する記述は厚く,この2つの章で全体の半分近くのページが使われている。特に自閉症スペクトラムについて詳しく,心の理論,中枢性統合理論,実行機能,言語特性などに関する先端研究が網羅されていて読み応えがある。
編者の笹沼氏は序で,言語コミュニケーション障害は「言語発達の“単なる遅れ”とは異質な障害であり,生得的な要因に由来する脳機能の非定型的な発達過程と環境要因とのダイナミックな相互作用によって形成される」ことを述べている。「非定型発達」や「神経学的に非定型的(neurologically atypical)」などの表現をこのところよく見かけるようになった。発達障害は近年,単純な発達の遅れでも脳の局所的な故障の直接の現れでもなく脳システム全体の非定型的な発達の問題として捉えられている。“症状”の分析にはヒトの認知・行動システムと発達過程,その神経学的基盤が理解される必要があるが,本書はそのためのたいへん質の高い手引となるものである。
そしてWHOの提唱するICF(国際生活機能分類)の概念にもみられるように,今日では障害の発生や様相は個体因子と環境因子との相互作用の中で説明がなされる。そのような考え方の変化は支援のあり方にも影響し,個に対する訓練的な働きかけだけでなく,コミュニケーション上のバリアの除去や二次障害の予防のために環境をどう最適化するかといった生態学的な視点も重視されるようになった。本書で「治療理論」「訓練理論」などでなく「介入理論」と表現されているのはそのような含みがあるからであろう。
認知的・分析的視点と発達的・生成的視点がミックスされた本書は「発達認知神経心理学」に関する現在のところわが国で唯一の成書といえよう。内容は高度で深く入門書というより専門家向きだが,研究者だけでなく小児を対象とする臨床家や特別支援教育の教師は座右に備える価値があると思う。エビデンスに基づく実践に役立つだろう。
高次脳機能障害と異なる発達性障害を理解するために
書評者: 岩田 誠 (東女医大教授・神経内科学)
本書の書評の依頼を受けていささか困惑した。私にとっては専門外の領域の物事を扱った書物であり,しかもタイトルから察するに,大変難解な内容であるような感じがしたからである。しかし,いざ本を手にして中を読み出すと,各章や,それを構成している各項の概要がそれぞれの冒頭に示されており,これを頼りにして読み進むと,意外に読みやすいことに気づいて,まずは安心した。
私自身は,これまで成人における失語,失読,失書といったような,一旦獲得した機能が脳病変によって失われたことに基づくさまざまな障害に接し,それらの障害をヒトの大脳における機能局在の原則に従って理解しようと試みる研究に従事してきた。そのような方法論を扱いなれた視点から眺めていると,本書で扱われているような発達性障害の病態を理解することはきわめて困難である。このことを自分自身で強く感じたのは,今からもう十数年前になろうか,本書でも取り上げられているWilliams症候群の患者に初めて出会った時であった。この特異な症候群の患者に図形の模写をしてもらった時,私はそれまで幾度となく経験してきた成人における視覚構成障害とは,根本的に違う何かを感じたのである。自分がそれまで金科玉条として信じていた大脳機能局在論では理解しがたい,何か不可思議なことが起こっているということに気づいたのである。その時が,私にとっての発達性高次脳機能障害への開眼元年であった。
それまでも,本書で取り上げられているさまざまな病態,特に自閉症スペクトラムや発達性読み書き障害の神経心理学的研究に接する機会がなかったわけではないが,そんな時私にとってはいつも消化不良の感じで終わるのが常であった。それは,いつも成人における神経心理学的手法がうまく適合できなかった例として,それらの研究を見てきたからだと思う。それは,私自身の誤りであったと同時に,この分野の研究者の方々の誤解に基づくものであったことも否定できないであろう。大脳の発達過程で生じてくるさまざまな病態と,それによって生じる障害,それらのことを,できあがった機能の喪失と同列に扱い,同じような理論で理解しようとすることが,そもそも適切ではないということが,どちらの側の研究者にも十分理解されてはいなかったのであろう。しかし,それから20年余の月日を経て,発達性コミュニケーション障害の研究は大きな展開を遂げていた。発達性障害というものは,成人における出来上がった機能の障害,というものとは切り離して考えられねばならないということ,そしてそのような発達性高次脳機能障害の研究こそが,高次脳機能の発達そのものの機構を明らかにする研究領域であるということ,本書を読めば,それらのことが如実に感じられるのである。ヒトの高次脳機能,特にその形成過程に関心のある方々には,ぜひ一読されることを薦めたい。
書評者: 小枝 達也 (鳥取大学地域学部教授・小児神経科医)
本書は,成人の言語障害を対象とした『言語コミュニケーション障害の新しい視点と介入理論』の姉妹本として企画されたものであると,編集者の笹沼氏が序で述べておられるが,単なる小児に見られるさまざまな言語障害の解説にとどまっておらず,小児の認知神経心理学を網羅するかのような幅広い視点で執筆されている。
最近では,発達障害に焦点をあてたマニュアル的な書籍が氾濫する中で,本書は研究者の視点から多くの文献をていねいに解説しながら,最新の仮説を詳述してあり,実に読み応えのあるものに仕上がっている。
各分担執筆者が丹念に文献を調べ上げて,それをわかりやすく紹介しているだけでなく,各執筆者の研究成果の紹介や臨床家としての経験も盛り込まれているために,単なる理論の展開にとどまっておらず,同じ臨床家として「なるほど」と,つい共感してしまうような記述が多いのも本書の長所と思われる。
特に自閉症スペクトラムとDevelopmental Dyslexiaについては,複数の分担執筆者がこれまでの諸仮説を余すことなく,しかもじつに詳細に紹介してある。これまでいろいろな書籍や文献で得ていた知識が,一挙にまとめて示してあるので,同じ分野を研究しているものの一人として,整理ができて大いに助かる。ふと確認したいと思ったときに,いろいろな書籍や文献を探し回るのではなく,本書に帰れば済むという印象を持った。
小児の言語障害だけでなく,小児の言語発達に関する脳科学的視点と最新の研究成果が盛り込まれているため,本書をじっくりと読みこなすことにより新しい研究の方向性が見えてくるし,具体的なアイデアも浮かんでくる。実にありがたいことである。出版が遅れたと序にあるが,これだけ充実した内容の本が一朝一夕にできあがるとは思えず,遅れたのも無理からぬことであろう。本書の企画編集に精力的に取り組まれた笹沼氏とそれぞれの章を緻密かつていねいに書き上げた各分担執筆者に敬意を表したいと思う。
エビデンスに基づく実践に役立つ「介入理論」
書評者: 藤野 博 (東京学芸大学総合教育科学系特別支援科学講座支援方法学分野准教授)
本書は発達期に生じることばとコミュニケーションの障害について最新の研究知見をまとめたものである。編者はわが国の言語障害学の草分けでありこの分野の研究をリードしてきた笹沼澄子氏で,いずれの章も今日の日本を代表する第一線の研究者・臨床家の手になる。
ここ10年あまりで飛躍的に発展した認知神経心理学と発達神経心理学を背景として進化した近年の発達障害研究の成果が言語・コミュニケーション領域を中心に余すところなくレビューされている。自閉症スペクトラム,発達性読み書き障害,特異的言語発達障害,Down症候群,Williams症候群,後天性小児失語,人工内耳装用児,吃音,健常幼児の音声知覚,幼児期の話しことばの発達,小児・乳幼児の脳機能イメージングの全11章から構成されており,特別支援教育の領域で取り上げられることの多い自閉症スペクトラムと発達性読み書き障害に関する記述は厚く,この2つの章で全体の半分近くのページが使われている。特に自閉症スペクトラムについて詳しく,心の理論,中枢性統合理論,実行機能,言語特性などに関する先端研究が網羅されていて読み応えがある。
編者の笹沼氏は序で,言語コミュニケーション障害は「言語発達の“単なる遅れ”とは異質な障害であり,生得的な要因に由来する脳機能の非定型的な発達過程と環境要因とのダイナミックな相互作用によって形成される」ことを述べている。「非定型発達」や「神経学的に非定型的(neurologically atypical)」などの表現をこのところよく見かけるようになった。発達障害は近年,単純な発達の遅れでも脳の局所的な故障の直接の現れでもなく脳システム全体の非定型的な発達の問題として捉えられている。“症状”の分析にはヒトの認知・行動システムと発達過程,その神経学的基盤が理解される必要があるが,本書はそのためのたいへん質の高い手引となるものである。
そしてWHOの提唱するICF(国際生活機能分類)の概念にもみられるように,今日では障害の発生や様相は個体因子と環境因子との相互作用の中で説明がなされる。そのような考え方の変化は支援のあり方にも影響し,個に対する訓練的な働きかけだけでなく,コミュニケーション上のバリアの除去や二次障害の予防のために環境をどう最適化するかといった生態学的な視点も重視されるようになった。本書で「治療理論」「訓練理論」などでなく「介入理論」と表現されているのはそのような含みがあるからであろう。
認知的・分析的視点と発達的・生成的視点がミックスされた本書は「発達認知神経心理学」に関する現在のところわが国で唯一の成書といえよう。内容は高度で深く入門書というより専門家向きだが,研究者だけでなく小児を対象とする臨床家や特別支援教育の教師は座右に備える価値があると思う。エビデンスに基づく実践に役立つだろう。
高次脳機能障害と異なる発達性障害を理解するために
書評者: 岩田 誠 (東女医大教授・神経内科学)
本書の書評の依頼を受けていささか困惑した。私にとっては専門外の領域の物事を扱った書物であり,しかもタイトルから察するに,大変難解な内容であるような感じがしたからである。しかし,いざ本を手にして中を読み出すと,各章や,それを構成している各項の概要がそれぞれの冒頭に示されており,これを頼りにして読み進むと,意外に読みやすいことに気づいて,まずは安心した。
私自身は,これまで成人における失語,失読,失書といったような,一旦獲得した機能が脳病変によって失われたことに基づくさまざまな障害に接し,それらの障害をヒトの大脳における機能局在の原則に従って理解しようと試みる研究に従事してきた。そのような方法論を扱いなれた視点から眺めていると,本書で扱われているような発達性障害の病態を理解することはきわめて困難である。このことを自分自身で強く感じたのは,今からもう十数年前になろうか,本書でも取り上げられているWilliams症候群の患者に初めて出会った時であった。この特異な症候群の患者に図形の模写をしてもらった時,私はそれまで幾度となく経験してきた成人における視覚構成障害とは,根本的に違う何かを感じたのである。自分がそれまで金科玉条として信じていた大脳機能局在論では理解しがたい,何か不可思議なことが起こっているということに気づいたのである。その時が,私にとっての発達性高次脳機能障害への開眼元年であった。
それまでも,本書で取り上げられているさまざまな病態,特に自閉症スペクトラムや発達性読み書き障害の神経心理学的研究に接する機会がなかったわけではないが,そんな時私にとってはいつも消化不良の感じで終わるのが常であった。それは,いつも成人における神経心理学的手法がうまく適合できなかった例として,それらの研究を見てきたからだと思う。それは,私自身の誤りであったと同時に,この分野の研究者の方々の誤解に基づくものであったことも否定できないであろう。大脳の発達過程で生じてくるさまざまな病態と,それによって生じる障害,それらのことを,できあがった機能の喪失と同列に扱い,同じような理論で理解しようとすることが,そもそも適切ではないということが,どちらの側の研究者にも十分理解されてはいなかったのであろう。しかし,それから20年余の月日を経て,発達性コミュニケーション障害の研究は大きな展開を遂げていた。発達性障害というものは,成人における出来上がった機能の障害,というものとは切り離して考えられねばならないということ,そしてそのような発達性高次脳機能障害の研究こそが,高次脳機能の発達そのものの機構を明らかにする研究領域であるということ,本書を読めば,それらのことが如実に感じられるのである。ヒトの高次脳機能,特にその形成過程に関心のある方々には,ぜひ一読されることを薦めたい。