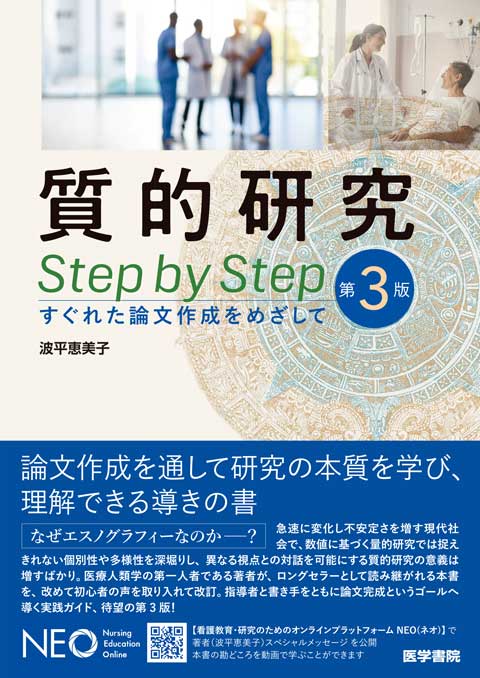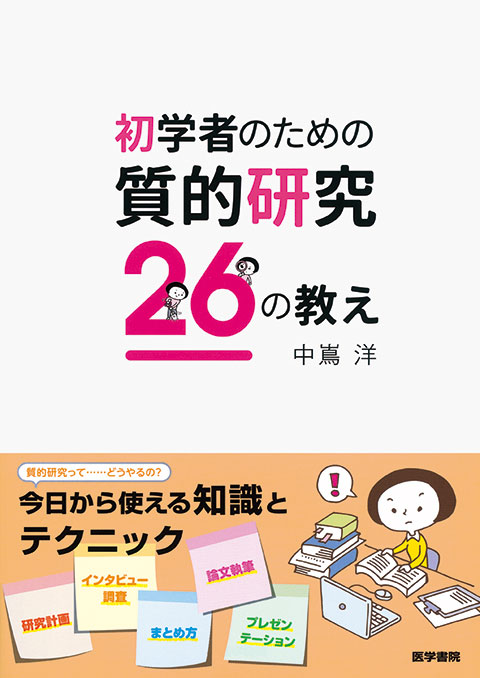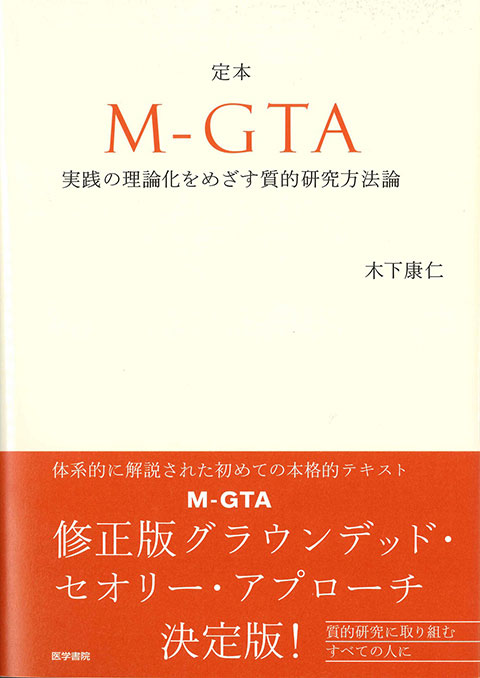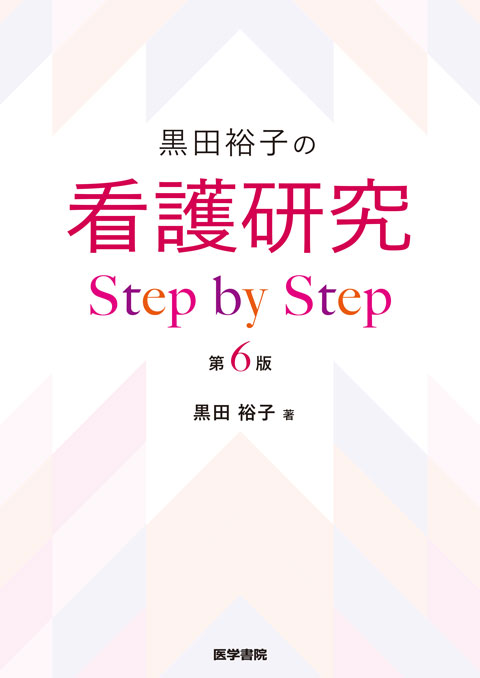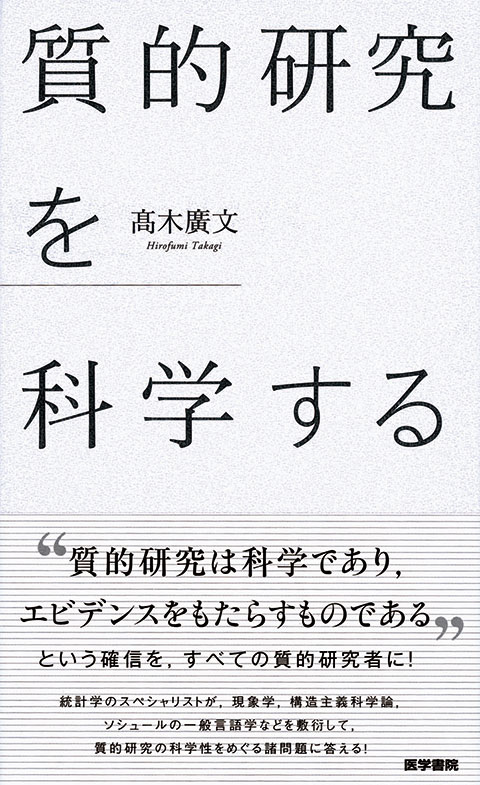質的研究 Step by Step 第3版
すぐれた論文作成をめざして
なぜエスノグラフィーが有効なのか 論文作成を通して研究の本質を学び、理解する
もっと見る
なぜエスノグラフィーなのか? 急速に変化し不安定さを増す現代社会で、数値に基づく量的研究では捉えきれない個別性や多様性を明らかにし、異なる視点との対話を可能にする質的研究の意義は増すばかり。ロングセラーとして世代を超え、読み継がれてきた本書を、医療人類学の第一人者である著者が、初心者のために各Stepごとの解説を補強。指導者と書き手をともに論文完成というゴールへ導く実践ガイド、待望の第3版である。
| 著 | 波平 恵美子 |
|---|---|
| 発行 | 2025年12月判型:B5頁:144 |
| ISBN | 978-4-260-06271-8 |
| 定価 | 3,080円 (本体2,800円+税) |
更新情報
-
更新情報はありません。
お気に入り商品に追加すると、この商品の更新情報や関連情報などをマイページでお知らせいたします。
- ご案内
- 序文
- 目次
- 書評
ご案内
開く
看護教育・研究のためのオンラインプラットフォームNEO(Nursing Education Online)にて、
著者のスペシャルメッセージを公開しています。本書の勘どころを動画にてご覧いただけます。
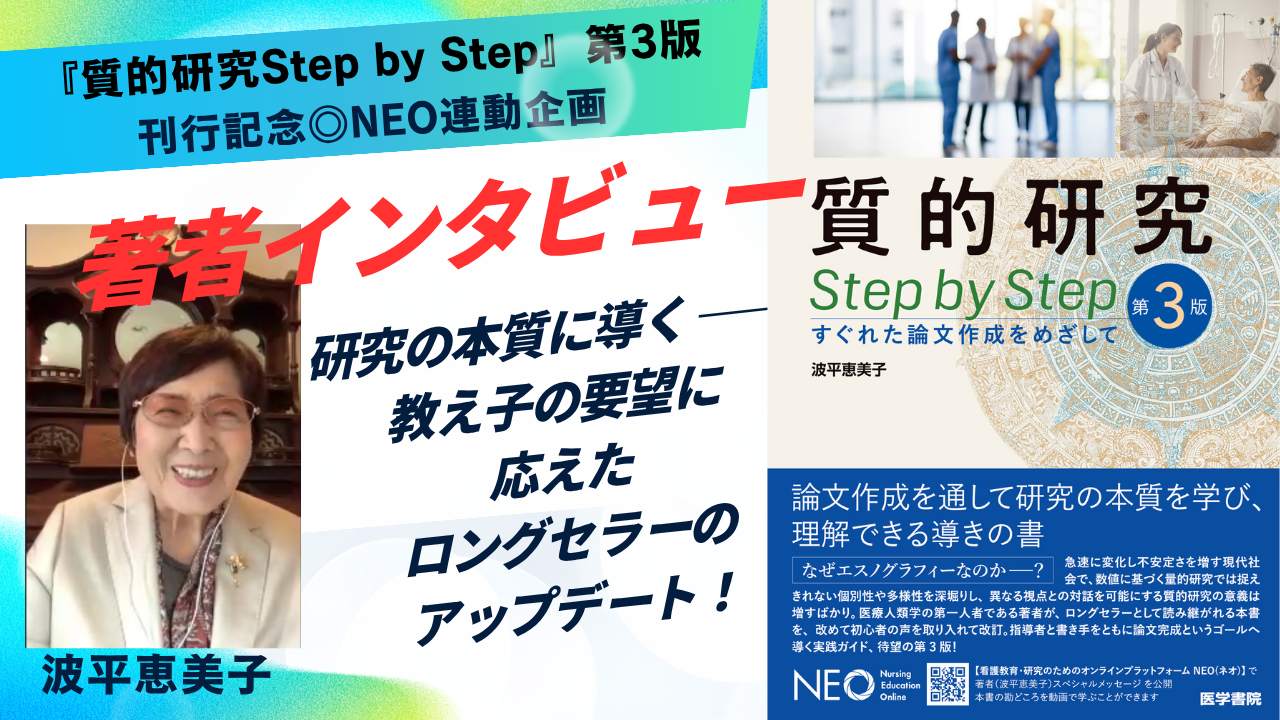
『質的研究Step by Step』第3版連動企画
【刊行インタビュー】研究の本質に導く――教え子の要望に応えたロングセラーのアップデート!
序文
開く
はじめに
本書は,2005年に著した『質的研究 Step by Step』の第3版である。第1版から20年,第2版発刊から9年経ったが,その間,質的研究の重要性は広く認められるようになり,いくつもの分野で質的研究による研究成果が多く発表された。また,質的研究のための優れたテキストが刊行されている。第3版は,こうした動向を考慮し,また,第2版を使用した学生や指導のためにテキストとした教員からのコメントを参考にしながら,本書の内容をより理解しやすいように加筆し,また文章を修正した。
大きな変更点は,第4章と第5章の研究テーマとその研究の手順と方法である。
本書の内容は,次のような特徴をもつ。
- 本書の基本的理論と方法は,文化人類学に拠っている。
- 質的研究とはどのような知的営為であり,質的研究によって何を明らかにすることができるかを述べている。また,質的研究と現象学的思考との間には深い関係があり,それについて第1章において述べているが,他の章でも表現と事例を変えながら繰り返し説明している。
- 質的研究の重要性は現在では認められつつあるが,それでも「客観性に欠ける」などの批判や疑問が向けられことがある。本書ではなぜこうした批判や疑問が生じるかを検討し,文化人類学の研究方法を参照しながら,その対処法について述べる。
- 大学院生レベルの学生が,質的研究を進めるうえで出会うことの多いさまざまな問題や疑問を段階(STEP)ごとに示したうえで,その対応策を示している。
- 研究の取り掛かりから,論文審査まで,学生が各段階で出会い,そして越えなければならない問題を具体的に,また,さまざまな側面から述べている。特に,第4章と第5章では,指導を受ける学生の研究の成熟度を見極めつつ,教員が指導のレベルを上げていく方法も示している。
- 多様な方法を含む質的研究の中で,本書ではエスノグラフィーを中心的に示す。それは,エスノグラフィーが参与観察,インタビュー,文書調査,資料整理など多様な方法を含むからである。
- 巻末には,テーマ別に「文献解題──質的研究者のためのブックガイド」を付している。重要な参考文献ではあるが,本文で取り上げ論じると,テキストという本書の性格上本筋が見えにくくなると考え,「解題」として掲載した。
- 健康科学分野での質的研究で主流であるグラウンデッド・セオリー(GT)について述べていないが,それは,すでに多くの優れたテキストが刊行されているからである。
質的研究への関心の高まりの背景には次のことが考えられる。
1つには,自分が生きている世界が急速に変化し複雑に分化・分断していくのを見ながらも,その全体像をとらえることはできず理解できない状況に抗して,自分が大きな関心を抱く対象を,主体的に,具体的また詳細に知り理解する適切な方法として質的研究が認識されるようになってきたこと。
2つには,世界におけるさまざまな現象が数によって均一的に把握され提示される傾向に抗して,対象の多様性,個別・独自性を明らかにする要請に質的研究は対応できること。
3つには,同じ社会のメンバーの間でも,立場の違いだけではなく世界を見る視点の違いが大きくなり,それが和解や理解や共感の機会を失わせる状況が顕著になっている現在,自らの視点さえも相対化しつつ,対象を分析する視点・立場に常に意識的であろうとする質的研究の特徴が評価されるようになったこと。
社会の複雑さと変化の速さが著しくなるなか,自分の周囲で起きている現象を確実に知り理解しようとする欲求が人々の間に強くなっている。しかしながら,グローバル化の全体像は見えないまま,食料や日用品,インターネット環境をはじめ,確実にグローバル化の影響を受けて生きているという実感を人は抱くものの,全体像や関係性を把握できていない。こうした状況は,PCを十分に使いこなしながらもハードウエア,ソフトウエアについてその原理やシステム全体を知らないし,仮に,知ろうとしても容易ではないのと同じである。
このような状況に人はどこかで不安や欲求不満を感じ,そこにある現象を,たとえ部分であっても確実に把握したいと思うようになる。質的研究は,そうした要請に応えようとする知的な営為である。
質的研究は,研究分野は何であれ,質的研究をはじめる前と後では研究対象はもちろん自分の生活世界を見る目に変化が生じていることに気づくことになる。研究を進めるなかでそれは大きな楽しみともなる。本書がその入り口となることを,著者として願う。
2025年10月
波平恵美子
目次
開く
はじめに
第1章 質的研究をはじめるにあたって
STEP 1 質的研究の概要を知ろう
1 展望──質的研究の多様性と超えるべき問題
2 質的研究と「哲学」との関係
3 現象学的立場と質的研究
4 一般的世界と研究的世界との乖離──質的研究のおかれる立場
5 評価における問題点──妥当性・一般化可能性・信頼性
6 思想としての質的研究
7 問題意識の十分な検討の必要性
8 文化人類学と質的研究との関係
[LECTURE] 「エスノグラフィー的体験」とエスノグラフィーの作成
STEP 2 質的研究の方法と研究手順
1 質的研究の方法の多様性
2 研究方法の組み合わせ──トライアンギュレーション
3 研究方法の選択とその習得
4 研究手順
STEP 3 今後の質的研究と量的研究との関係
1 互いの研究成果を参照しあう
2 研究グループどうしで協働する
第2章 質的研究とエスノグラフィー
STEP 1 エスノグラフィーの概要を知ろう
1 エスノグラフィーの誕生と発展の歴史
2 文化人類学におけるエスノグラフィー
3 エスノグラフィーと「文化人類学」
4 未知のことを広く伝える方法としてのエスノグラフィー
5 フィールドワークの始まりとその重要性
6 多くの分野に展開するエスノグラフィー
7 文化人類学における伝統的なエスノグラフィーと現代的なエスノグラフィー
8 現代的なエスノグラフィーの目的と質的研究との関係
[LECTURE] ビジネス・エスノグラフィー
STEP 2 エスノグラフィーとその方法
1 ヘルス・エスノグラフィー
2 エスノグラフィーの研究目的とその方法との関係
3 エスノグラフィーと伝統的な「参与観察」
4 観察と観察者(研究者)の立場
5 研究者の「位置取り」(positioning)
6 実際の研究と位置取りとの関係
7 研究者も研究協力者も避けられない「位置取り」
STEP 3 観察結果の記録と整理
1 観察の方法と記録
2 データの整理
3 データ整理におけるITの活用とその効果
4 インタビューとそのデータ整理
5 文書調査
STEP 4 テーマ設定・分析・議論
1 研究テーマ
2 研究設問
3 分析と議論
[LECTURE] 究極のエスノグラフィー:自分自身をエスノグラフィーの対象とする
第3章 質的研究における口頭資料の収集と分析
STEP 1 口頭資料の種類
1 口頭資料の種類とその資料整理
2 半構造化インタビューの資料とその整理
3 ナラティブ分析
STEP 2 口頭資料の研究上での位置づけと評価
1 研究上の位置づけと資料整理
2 口頭資料の内容評価
3 口頭資料を分析するうえでの問題点と対策
第4章 慢性腎臓病の質的研究──看護学研究分野での学位論文作成の例
STEP 1 慢性腎臓病治療における看護師の役割の重要性
STEP 2 問題意識から研究テーマに至るまでの経緯
1 鈴木さんの臨床経験と問題意識
2 問題意識を特に喚起したエピソード例
3 それぞれの事例についての気づき
4 医療人類学からの発想──「体験としての病気」
5 研究テーマの設定
6 研究方法
STEP 3 論文作成までの研究手順
1 研究協力機関への申請と承認・許可の取得
2 大学院研究科への研究計画の提出
3 研究協力者の選定と協力依頼
STEP 4 研究のプロセス(I)
1 文献調査
2 半構造化インタビューの質問項目を作成する
STEP 5 研究のプロセス(II)
1 半構造化インタビューの実施
2 質問回答の整理
3 データの分析
4 必要に応じて文献調査の分析内容も参考にしながら論文を書く
5 論文の完成
6 論文提出後の備え
第5章 地域包括ケアの質的研究──文化人類学研究分野での学位論文作成の例
STEP 1 地域包括ケアシステムの時代
STEP 2 研究の目的と研究テーマの設定
1 上田さんの研究経歴と問題意識
2 研究テーマの設定
3 研究テーマに沿った研究計画の検討──指導教員との対話
STEP 3 研究計画実施内容の検討
1 自助・共助・公助の関係を明らかにするための基本的調査の検討
2 インタビュー調査の検討──指導教員との対話
3 アンケート調査の検討──指導教員との対話
STEP 4 研究計画の提出と審査委員会による承認
1 研究計画の提出
2 研究計画段階での委員会審査
3 研究テーマおよび計画についての審査会での承認
STEP 5 調査データの整理と分析
1 第1段階の調査(予備調査)の資料整理と分析
2 第2段階の調査(インタビュー調査)の資料整理と分析
3 第3段階の調査(アンケート調査)の資料整理と分析
STEP 6 資料全体の分析と論文作成
第6章 質的研究の問題点とその対策
STEP 1 質的研究への批判的評価の検討
1 質的研究の評価において呈される疑問や方法論上の「問題」の背景
2 質的研究へ向けられる批判的評価とそれへの対応
[LECTURE] 質的研究の論文が「エッセイ」とみなされないために
3 質的研究におけるデータとしての「事例研究」の検討
STEP 2 質的研究の評価基準項目の検討と対応策
1 メンバーチェッキング
2 データの信用性の確保
3 研究協力者(研究参加者)の選択基準の適切さ
4 データの真正性
5 サンプルの代表性と研究協力者の数ないしは事例の数の適正さ
STEP 3 質的研究を進めるための対応と対策
1 自分がもっている「問い」を徹底して検討する
2 研究テーマとなる「問い」の内容の精査
3 「問い」に対する解答をどのように示すか,その道筋の確認
STEP 4 データ収集とその整理および分析
1 データの整理
2 分析の方法と分析内容の説得性
文献解題──質的研究者のためのブックガイド
質的研究に関する文献解題
質的研究と現象学との関わりに関する文献解題
文化人類学に関する文献解題
エスノグラフィーに関する文献解題
事例研究に関する文献解題
口頭資料に関する文献解題
索引
書評
開く
意義ある質的研究の本質を学ぶための先導書
書評者:坂下 玲子(兵庫県立大学副学長/教授・看護学)
多くの質的研究の成果物が公表されているが,看護に新たな知をもたらしたと思える研究に出合うことは多くない。質的研究に取り組む者は,自分が引かれた現象の固有性に肉薄し,それを言語化しようと試みるが,事例の多様性と複雑さの前で輪郭はぼやけ,「どの事例にも外れない(その実,どの事例にも当てはまらない)汎用例」に着地しがちである。そうならないためには,質的研究の本質と具体的な手法を学ぶことが必要だ。
本書は,エスノグラフィー(文化人類学)の手法により「ハレ・ケ・ケガレ」の概念を構築し,わが国の医療人類学を切り開いてきた波平恵美子氏による実践的な手引き書の第3版である。そのタイトルが示すように,優れた論文作成に向けた道筋とコツが,段階をおって丁寧に示されている。新たに改訂された今版は,さらに読者に寄り添い,最初の問題意識が,どのように研究テーマとなり,研究が計画され,実施されていくかが丁寧に描かれている。また,本書は博士課程の学生や質的研究の初心者が論文を作成することを念頭に置き書かれていると思うが,学生指導を行う教員や自身の研究に納得していない研究者にもお薦めしたい。
私が本書を優れていると思うのは次の四点に集約される。
まず,第一章に質的研究の歴史的背景と哲学的な位置付けが平易な言葉で示され,読者は質的研究の意義と特徴を理解し研究に取り組むための準備が整う。思想としての質的研究を理解しない限り,それを有効に使いこなすのは難しいだろう。
第二に,著者が長年取り組み輝かしい業績を上げてきたエスノグラフィーの手法をベースとし,どの質的研究にも必要な要素が具体的に紹介されている。コンパクトな誌面に,研究者の「位置取り」から,参加観察およびインタビューなどのデータ収集方法,データの整理,分析に至るまでそのエキスが濃縮されている。エスノグラフィーは長い歴史により培われてきた質的研究法であり,その特徴と方法を学ぶことは,あらゆる質的研究に通じる基礎となる。
第三は,具体的な研究のプロセスが,その出発点から細かく示されている点である。第4章と第5章は,今版で全面改訂され,看護学と文化人類学の博士論文の作成過程を学生の視点から描く点は前版と共通するが,問題意識から研究テーマ設定,計画立案に至るまでの経過がより丁寧に記されている。指導教員との対話を通して研究計画が編み上げられていく過程は,研究指導に悩む教員には大変参考になるであろう。
第四は,本書が質的研究の入門実践書として書かれ,144ページという凝縮された分量にもかかわらず,随所にちりばめられた適切な引用文献によって,読者が質的研究の深部へ踏み込めることである。
圧巻は巻末の「文献解題」で,著者の解説付きによる質的研究の名著リストが示される。質的研究をさらに深めたい人にとっては,格好の先導となる。
意義ある質的研究をめざす人は,この一冊から始めてほしい。