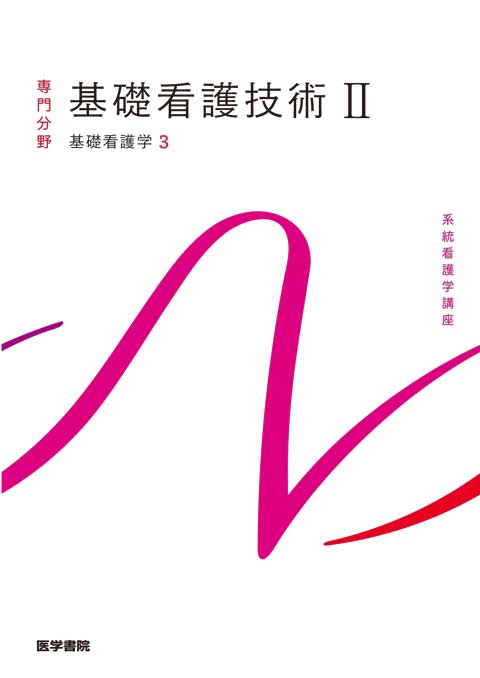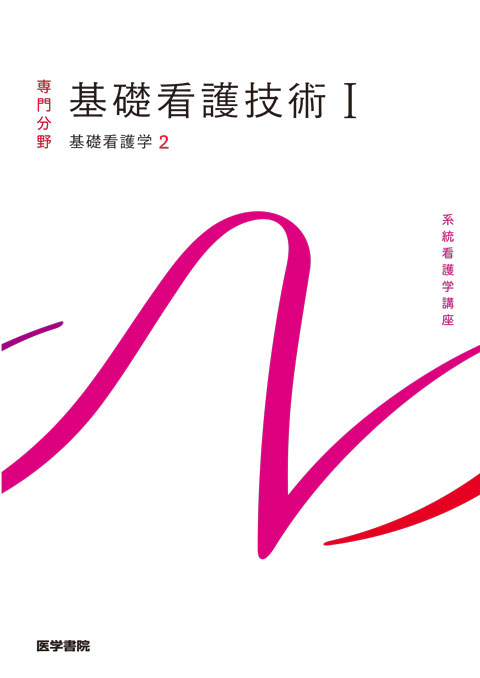基礎看護学[3]
基礎看護技術Ⅱ 第19版
もっと見る
- 「看護師教育の技術項目と卒業時到達度」「看護師国家試験出題基準 令和5年版」を網羅することに加え、「厚生労働省 新人看護職員研修ガイドライン」の「看護技術についての到達目標」も加味し、臨床での実践に役立つような構成としました。
- 手技のポイントや注意点、根拠がわかりやすくなるようアイコンを設けています。
- 図版・写真をより充実させ、1つひとつの手技を視覚的に理解しやすくなっています。また、QRコードから、おもな看護技術の動画を視聴できます。
- 動画には、ナレーションがついており、またシーンセレクトで手順ごとに視聴することも可能です。
- 「系統看護学講座/系看」は株式会社医学書院の登録商標です。
| シリーズ | 系統看護学講座-専門分野 |
|---|---|
| 執筆 | 有田 清子 / 今井 宏美 / 内海 桃絵 / 尾﨑 章子 / 小林 優子 / 坂下 貴子 / 茂野 香おる / 立野 淳子 / 田戸 朝美 / 辻 守栄 / 内藤 知佐子 / 長坂 育代 / 任 和子 / 林 静子 / 比田井 理恵 / 平松 八重子 / 三富 陽子 / 森下 智美 |
| 発行 | 2025年02月判型:B5頁:504 |
| ISBN | 978-4-260-05688-5 |
| 定価 | 3,520円 (本体3,200円+税) |
- 増刷中
- 改訂情報
更新情報
-
正誤表を更新しました
2025.04.07
-
正誤表を掲載しました
2025.03.19
- 序文
- 目次
- 正誤表
序文
開く
はしがき
このテキストは,看護師を志す看護学生の皆さんが,最初に手にする看護専門書の一冊であろう。本書は初学者の皆さんのために書かれた,看護技術の基本のテキストであるが,看護学生としてだけでなく,看護師として臨床現場で働くようになってからも役立つように編集されている。
本書の使い方の基本は,本文を繰り返し読み,“なぜそのようにするのか?”という根拠とともに方法を理解していくことである。動画でみたそのままをまねるだけでなく,本文を繰り返し読み,正しい方法を身につけてほしい。さらに,理解したことは,反復して練習してほしい。看護技術は受け身の講義で身につくものではなく,主体的に技術を獲得しようという意欲を持ち,繰り返し練習してこそ身につくものである。なお,本書中の図や動画においては,日常生活の中では見ることのない身体の部位や,侵襲を伴う看護技術も扱っている。効果的な技術習得のためにリアルに描いているが,表現の目的をつねに念頭に置いて利用してほしい。
さて,看護ケアを行う際に対象者の個別性が重視されるが,これについて考えてほしい。看護ケアの実践にあたっては,ただ記述された手順通りに看護技術を適用するだけでは看護専門職の行為とは言えない。看護師の専門職たるゆえんは,看護判断を行い,それに基づいてケアを提供することにある。つまり,対象者の状況をアセスメントし,ケアの内容と方法を決定することが,看護師の重要な役割なのである。本書では,看護技術項目の1つひとつについて,「実施前の評価」「適応・禁忌」「根拠」「実施後の評価」など,看護技術提供の前後の基本的な観察・判断事項を記載している。これらの記載事項を参考に,看護技術を提供するためのアセスメントを行い,対象者1人ひとりの状況に応じた看護ケアが行えるようになってほしい。
実践の場で実際にケアを行うとき,1回目にはうまくいったケアが,その次には満足のいくようにできないかもしれない。そのようなときには,基本であるこのテキストに戻り,「なぜうまくいかなかったのか」を考えてほしい。根本的に実施方法が間違っていたのか,患者の状況が変化しているのに以前と同じ方法で行ったのか(実施前の判断ミスによる方法選択の誤り)など,さまざまな視点からケアを振り返るために本書が役立つだろう。看護師資格を手にしてからも,臨床実践の多くの場面で,皆さんは基本に立ち返ることを求められるはずである。あるいは,学生時代の授業では十分にふれられなかった技術を臨床現場で行わなければならないこともあるだろう。本書をつねに手元に置き,必要なときにひもといて確認することが,必ず皆さんの役に立つものと考えている。
ところで,このテキストを手にしている皆さんが,看護師という職業に興味を持ち,本格的に学びたい,生涯の職業としたいと思ったきっかけはなんであろうか。幼少のころに出会った優しい笑顔の看護師への憧れだろうか。あるいは,中学・高校生時代に体験した「一日看護体験」で,看護師がケアによって“心地よさ”を提供していたのを目の当たりにして感動した経験だろうか。いずれにしても,なんらかのかたちで看護師の直接的な看護実践にふれて,看護師を志した人が多いだろう。しかし,憧れの看護師が,そのときに体とともに頭をはたらかせていたこと,すなわちさまざまなことを同時に考え,確かな理由に基づいてそのケアを行っていたことに気づいていただろうか。さりげなくケアを行っていた看護師,終始笑顔で患者や家族や周囲の人にまで気配りをしながら処置をしていた看護師……皆さんの心に思い浮かぶその先輩看護師は,実は目に見える看護技術を提供していただけではない。さまざまな情報を得て,適切な判断をし,個別の状況に即した方法を選択し,実施中も配慮の言葉かけをしながら患者や家族の様子を観察するという,目には見えないいくつものことを,同時に,かつ組み合わせて行っていたのだ。皆さんは,まだ,「自分は人のために役立つ存在になれるのだろうか」「後輩の憧れの存在になれるのだろうか」などという思いが先行し,なかなか自信が持てないかもしれない。しかし,理想の看護師に近づくはじめの一歩は確実な看護技術を身につけることである。本書と動画が存分に活用され,そして,皆さんの技術レベルが向上することを願っている。
本書では最も基本となる看護の方法について,多くの写真やイラストによって手順をわかりやすく示すだけでなく,おもな看護技術の手順については動画で確認できるようにしている。今回の改訂では動画コンテンツをさらに充実させ,「ストレッチャーでの移送(活動援助)」「端座位から立位への援助(活動援助)」「手浴(清潔援助)」などを追加し,臨地実習の場面でそのまま使えるようにしている。このほか,「シーツ交換(環境調整)」と「寝衣交換(衣生活援助)」では,使用済みのものと新しいものの区別が明確になるようにし,さらに撮影アングルを増やすことで皆さんの理解が容易になるように工夫している。動画は全体の流れの把握,文章だけではイメージしにくい部分のイメージ化の助けとなり,内容の理解を促進するものとなる。動画コンテンツをおおいに活用してほしい。
本書が,皆さんの学習,何より直接看護を行う際の手引きとして役立てるよう願っている。皆さんが,このテキストをボロボロになるまで,繰り返し使いこんでいくことを切に望みたい。
2024年11月
著者を代表して
茂野香おる
目次
開く
序章 看護技術の根底をなすもの──適切な技術習得のために (茂野香おる)
A 本書の構成
B 看護技術の基盤
1 医療安全の確保
2 患者および家族への説明と助言
3 的確な看護判断と適切な看護技術の提供
C 本書を活用した看護技術習得方法
第1章 環境調整技術 (長坂育代)
A 環境調整の援助の基礎知識
1 環境と看護
2 病床の環境
B 環境調整の援助の実際
1 病床の環境整備
2 ベッドメーキング
3 臥床患者のシーツ交換
第2章 食事援助技術 (茂野香おる)
A 食事援助の基礎知識
1 栄養状態および摂食能力,食欲や食に対する認識のアセスメント
2 医療施設で提供される食事の種類と形態
B 食事摂取の介助
1 援助の基礎知識
2 援助の実際
C 非経口的栄養摂取の援助
1 経管栄養法
2 中心静脈栄養法
第3章 排泄援助技術 (茂野香おる・三富陽子)
A 自然排尿および自然排便の介助
1 自然排尿および自然排便の基礎知識
2 自然排尿および自然排便の介助の実際
B 導尿
1 一時的導尿
2 持続的導尿
C 排便を促す援助
1 排便を促す援助の基礎知識
2 浣腸(グリセリン浣腸〔GE〕)
3 摘便
D ストーマケア
1 援助の基礎知識
2 援助の実際
第4章 活動・休息援助技術 (林静子・尾﨑章子)
A 基本的活動の援助
1 基本的活動の基礎知識
2 基本的活動の援助の実際
B 睡眠・休息の援助
1 援助の基礎知識
2 援助の実際
第5章 苦痛の緩和・安楽確保の技術 (林静子・小林優子・茂野香おる)
A 体位保持(ポジショニング)
1 援助の基礎知識
2 援助の実際
B 罨法
1 援助の基礎知識
2 援助の実際
C 安楽をもたらす身体ケア
1 援助の基礎知識
2 援助の実際
第6章 清潔・衣生活援助技術 (茂野香おる・有田清子・森下智美)
A 清潔の援助
1 清潔の援助の基礎知識
2 清潔の援助の実際
B 病床での衣生活の援助
1 援助の基礎知識
2 援助の実際
第7章 呼吸・循環を整える技術 (今井宏美・茂野香おる・比田井理恵・田戸朝美)
A 気道管理
1 気道管理の基礎知識
2 気道管理の援助の実際
B 酸素療法(酸素吸入療法)
1 援助の基礎知識
2 援助の実際
C 人工呼吸療法
1 援助の基礎知識
2 援助の実際
D 体温管理の技術
1 援助の基礎知識
2 援助の実際
E 循環促進ケア
1 援助の基礎知識
2 援助の実際
第8章 創傷管理技術 (三富陽子・茂野香おる)
A 創傷管理の基礎知識
1 創傷
2 創傷治癒のための環境づくり
B 創傷処置
1 術後一次縫合創とドレーン創の処置
2 創洗浄と創保護
3 テープによる皮膚障害
4 包帯法
C 褥瘡予防
1 援助の基礎知識
2 援助の実際(体圧分散ケア)
第9章 与薬の技術 (小林優子・茂野香おる・坂下貴子・有田清子・内海桃絵・内藤知佐子・任和子・辻守栄)
A 与薬の基礎知識
1 薬物の基本的性質
2 看護師の役割
B 経口与薬・口腔内与薬
1 援助の基礎知識
2 援助の実際
C 吸入
1 援助の基礎知識
2 援助の実際
D 点眼・点入
1 援助の基礎知識
2 援助の実際
E 点鼻
1 援助の基礎知識
2 援助の実際
F 経皮的与薬
1 援助の基礎知識
2 援助の実際
G 直腸内与薬
1 援助の基礎知識
2 援助の実際
H 注射
1 注射の基礎知識
2 注射の実施法
a 皮下注射
b 皮内注射
c 筋肉内注射
d 静脈内注射
I 輸血管理
1 援助の基礎知識
2 援助の実際
第10章 救命救急処置技術 (立野淳子)
A 救命救急処置の基礎知識
1 救急対応の考え方
2 救急・急変時における初期対応の流れ
3 トリアージ
B 一次救命処置(BLS)
1 心肺蘇生法の基礎知識
2 一次救命処置の実際
3 小児,乳児の心肺蘇生法
4 二次救命処置
C 止血法
1 援助の基礎知識
2 援助の実際
D 院内急変時の対応
1 援助の基礎知識
2 援助の実際
第11章 症状・生体機能管理技術 (任和子・小林優子・平松八重子)
A 症状・生体機能管理技術の基礎知識
B 検体検査
1 血液検査(静脈血採血,動脈血採血,血糖測定)
2 尿検査
3 便検査
4 喀痰検査
C 生体情報のモニタリング
1 心電図モニター
2 Spo2モニター(パルスオキシメーター)
3 血管内留置カテーテルモニターを使用したモニタリング
第12章 診察・検査・処置における技術 (任和子・小林優子)
A 診察の介助
B 検査・処置の介助
1 X線検査
2 コンピュータ断層撮影(CT)
3 磁気共鳴画像(MRI)
4 内視鏡検査
5 超音波検査(エコー検査)
6 心電図検査
7 肺機能検査
8 核医学検査
9 穿刺
第13章 死の看取りの援助 (茂野香おる・長坂育代)
A 死にゆく人と周囲の人々へのケア
1 死にいたるまでの多様な過程
2 死を予告されたり予期したりした人の反応の理解
3 死にゆく人の家族の心理とケアの必要性
4 死にゆく人のもつ苦痛とその対処
5 家族を含めた死の看取り
6 死者への敬意
7 残された人の悲嘆へのケア(グリーフケア)
B 死後のケア
1 死後のケアの基礎知識
2 死後のケアの援助の実際
動画一覧
索引
正誤表
開く
本書の記述の正確性につきましては最善の努力を払っておりますが、この度弊社の責任におきまして、下記のような誤りがございました。お詫び申し上げますとともに訂正させていただきます。
更新情報
-
正誤表を更新しました
2025.04.07
-
正誤表を掲載しました
2025.03.19