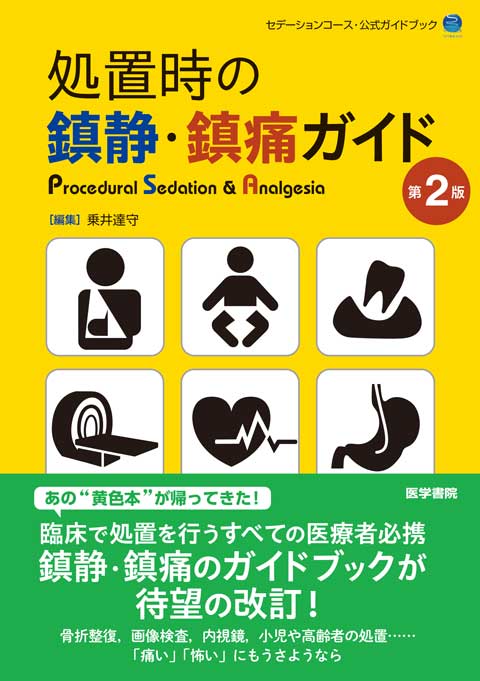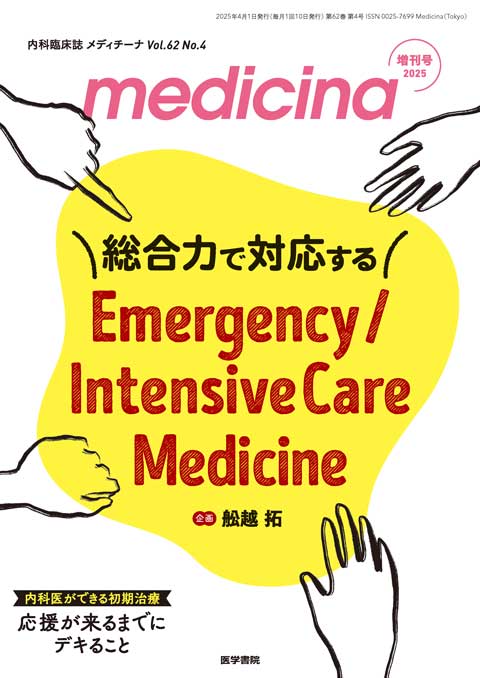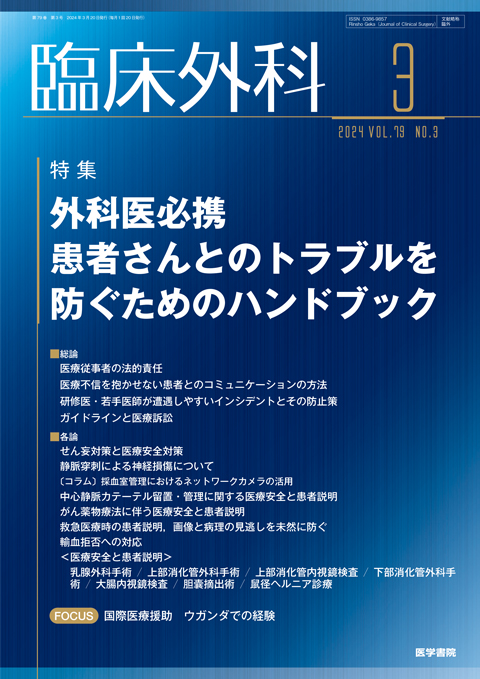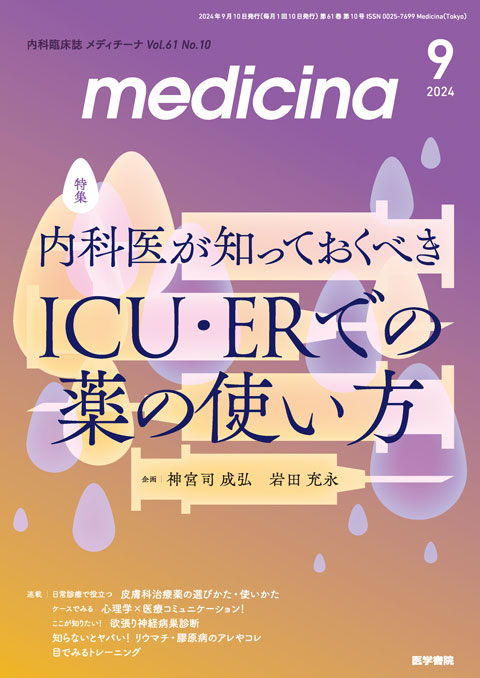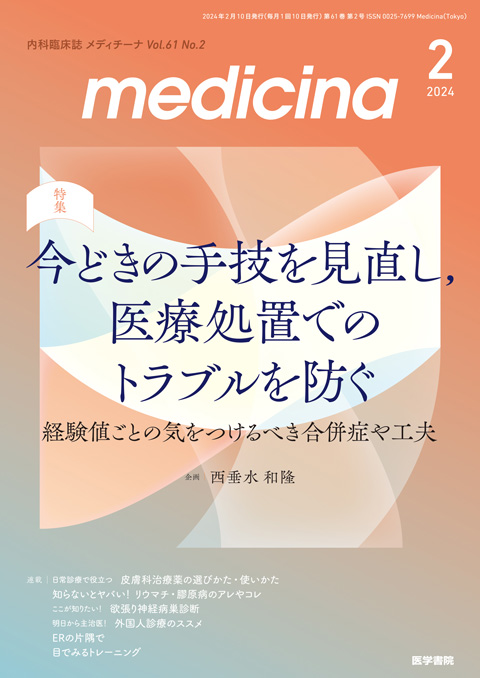処置時の鎮静・鎮痛ガイド 第2版
患者も術者もラクになる! 処置時の鎮静・鎮痛のガイドブックが待望の改訂!
もっと見る
非麻酔科医でも安全にできる「鎮静」や「鎮痛」の理論と手法について、国際的スタンダードを解説したガイドブックの改訂版。縫合・除細動・内視鏡の挿入などの処置時に患者の痛みや不安をいかに軽減するか、基本的な考え方から具体的な薬剤の使い分け、ケーススタディまで収録。新章としてチーム医療、安全対策なども追加。鎮静・鎮痛施行時の各種チェックリスト、同意書のひな形、院内ガイドラインなどの付録はダウンロード可能。
| 編集 | 乗井 達守 |
|---|---|
| 発行 | 2025年09月判型:A5頁:328 |
| ISBN | 978-4-260-05770-7 |
| 定価 | 4,950円 (本体4,500円+税) |
更新情報
-
更新情報はありません。
お気に入り商品に追加すると、この商品の更新情報や関連情報などをマイページでお知らせいたします。
- 序文
- 目次
- 付録・特典
序文
開く
第2版 まえがき
「鎮静深度が深くなったら,手錠を外してもらおうか」
胸腔ドレナージチューブを入れるための鎮静をしている間に,大暴れしていた患者さんの呼吸は落ち着いてきました.胸を刺されて救急搬送されてきた患者さんは,到着するなり私に銃を向けたので,居合わせた保安官に逮捕されて手錠がついたままです.でも,そろそろ外して処置が実施できるかもしれません.興奮に対する鎮静から,処置のための鎮静に移行するタイミングです.
上記はつい先日経験したやや極端な例ですが,処置時の鎮静・鎮痛(procedural sedation and analgesia:PSA)はさまざまな場面で用いられ,奥が深い手技です.患者さんは快適に処置を受けられるようになり,医療者側も処置が実施しやすくなります.ただ,PSAには大きなメリットがある一方,呼吸停止や喉頭痙攣などの合併症も起こりうる諸刃の剣でもあります.
私たちのグループは2012年からPSAを体系的に学べるコースを開催してきました.その教科書がこの書籍です.初版が発行されたのが約10年前.2016年といえば,オバマ米大統領(当時)が現職の米大統領として初めて被爆地・広島を訪れたという年でした.広島平和記念資料館にはオバマ大統領が折った鶴が今でも展示されています.初版が発行された当時は,処置時の鎮静・鎮痛という言葉を知っている人は少なく,日本での情報もほとんどありませんでした.この10年で大きく日本における事情も変わり,ガイドラインも充実してきました.
例えば「呼吸器内視鏡診療における鎮静に関する安全指針」(2023年)や「婦人科癌小線源治療における鎮静鎮痛ガイドライン」(2020年)など,ここ数年だけでも新たなガイドラインが相次いで発表されています.包括的な指針である「安全な鎮静のためのプラクティカルガイド」も,日本麻酔科学会によって2021年に作成されました.本書は,これらのガイドラインの内容を参考にしながら,臨床・教育・研究の各分野で長年にわたりPSAに携わってきたメンバーがエビデンスと豊かな臨床経験をもとに執筆したものです.
PSAに使用できる薬剤の種類もこの10年で増えてきました.ベンゾジアゼピン系の新しい薬剤で,ミダゾラムよりも超短時間作用型であるレミマゾラムの発売が開始されたのをはじめ,いくつかの新たな薬剤が使用可能となりました.今回の改訂では,そうした新しい薬剤についても取り上げています.
また,初版が刊行された当時には国内でほとんど知られていなかった「ケトフォール」(ケタミンとプロポフォールを併用する方法)についても,近年エビデンスが蓄積され,一定の評価と普及が進んできました.そのような,既存の薬剤の新しい知見も本改訂では積極的に紹介しています.なお,冒頭の症例も,ケトフォールを用いたPSAで無事に処置が終了しました.
PSAといえば,チームワーク.先ほどの症例でも,患者が銃を取り出して私に向けたときにすぐ患者の腕を抑えて発砲を防いでくれたのは救急看護師でした.その同じ看護師はPSAのモニタリングでも大いに助けてくれました.チームワークなくして,安全なPSAなし.今回の改訂では,Part11において1章を丸々使ってPSAにおけるチーム医療について詳しく取り上げています.
この10年であった大きな出来事の1つはCOVID-19のパンデミックです.忘れたくても忘れられません.PSAでは飛沫予防策やエアロゾル対策などの観点から感染対策が重要になりました.そのような経験をふまえ,今回の改訂ではPart12で感染対策について解説しています.この新設されたPart12では,ほかにも医療安全,院内ガイドラインの作り方などを紹介しており必読です.
今回の改訂では,読みやすさは変わらずに,原理原則をおさえつつ,最新のエビデンスやトピックを学べる書籍になっています.編集部の井上様,藤島様,そして富岡様のおかげで,表や図なども理解しやすさが大幅にアップしています.
安全で効果的なPSAが実施できるように学んでみませんか? 患者さんも医療者も両方が楽になるように,安全なPSAが広がることを執筆者一同願っています.
2025年6月
著者を代表して 乗井達守
目次
開く
Part1 序論
① 処置時の鎮静および鎮痛とは
誰でも不快なのは嫌だ/処置時の鎮静および鎮痛(PSA)とは/珍しいが怖い,重篤な合併症/時には鎮静をしないという選択肢も/インフォームドコンセント(説明と同意)
② ガイドライン
諸外国のガイドライン/日本のガイドラインの現状
③ PSAをめぐる歴史と研究
進化し続けるPSA/AI(人工知能)とPSA/やはり気になるのは安全性/鎮痛は本当に必要なのか?/忘れるということ/洞窟に閉じ込められた少年たちを救ったケタミン/これも,PSAといっていいの?/日本発のPSA研究と隣国の現状
Part2 処置前の評価と準備
① 体系だった問診・身体診察
AMPLEで問診を行う
② 気道の評価
LEMONで挿管困難を予測する!/MOANSで換気困難を予測する!/HOPで病態困難を予測する!/気道トラブル,換気困難が起こったときは
③ ASA分類
ASA分類とは/ASA分類によるPSAのリスク評価
④ 準備するもの
必要な物品はSOAPIERでチェック/実は大切な,経過観察のための人員と場所/ACLSは必修科目!
⑤ 前酸素化のメリット/デメリット
前酸素化の方法/前酸素化をめぐるエビデンス/前酸素化のデメリット/高齢者の前酸素化
Part3 モニタリング
① モニタリングの必要性と注意点
全身麻酔とPSA/モニタリングの原則/各臓器機能とモニター機器/モニタリングとガイドライン
② モニタリング各論
パルスオキシメーター/灌流指数(PI)/心電図/非観血的血圧測定/カプノグラフィ/BISモニター/深部体温
③ モニタリングのtips
複数の生体情報を測定可能なモニター機器/モニター機器の配置/アラームの設定/最も重要なモニター機器とは/[Q&A] 人手が少ないときはどうしたらよいでしょうか?
Part4 薬剤の特徴と使い分け
① PSAに使う薬剤:総論
中枢神経系での濃度上昇が大事!/過量投与を防ぐためには/胎児にも薬は届きます
② 鎮静薬
PSAでよく使用する鎮静薬/[Q&A] プロポフォールとミダゾラムの使い分けはありますか?/その他の鎮静薬/PSAで推奨されない薬剤/小児領域ではいまだに現役の抱水クロラール/今後に期待したい! 鎮静薬
③ 鎮痛薬
PSAでよく使用する鎮痛薬/その他の鎮痛薬
④ ケタミン
古くて新しい薬ケタミン
⑤ 拮抗薬,補助薬,薬剤以外
拮抗薬の作用は一時的/補助薬/薬剤以外による鎮静・鎮痛
Part5 処置後のケア
① 処置後の経過観察
「処置の終わり=鎮静の終わり」ではない/処置後モニタリングの目安は30分
② 帰宅基準
帰宅OKの基準は意識とバイタルサインの回復(+α)
③ 帰宅時の指導
帰宅後にも鎮静薬の影響は残りうる/車の運転には特に注意/帰宅後の注意事項説明用紙をつくっておくと便利/[Q&A] 処置後の評価をするのは,医師でないとダメでしょうか?/[Q&A] 患者を早く帰宅させたいので,拮抗薬を使ってもよいでしょうか?
Part6 合併症対策
① 主な合併症の種類と頻度
航空機事故による死亡事故なみに珍しい,重篤な合併症/処置前評価とモニタリングで合併症を防ぐ/緊急着陸はしたくない,でも必要なときにはうまくやる/早期の対応が,重篤な合併症を防ぐ
② 基本は常にABCD
Airway:気道の問題は,一刻を争う/Breathing:合併症で多いのは呼吸器系/Circulation:ハイリスク患者は,静脈ルートを2ルート確保/Disability:事前に行う家族への説明が重要
③ 合併症から何を学ぶのか
合併症対策は,国際的には最も重要視される医療評価である/[Q&A] 合併症発生時の蘇生に自信がありません.どうすればよいでしょうか?/[Q&A] 合併症に関するデータは,海外のものばかりです.日本にも,そのようなデータが当てはまるのでしょうか?
④ 局所麻酔薬中毒
頻度は低いが,危険な合併症/LAST発生時の対処法/何よりも予防が重要!
Part7 状況別の鎮静・鎮痛
① 救急外来
救急外来におけるPSAとは/救急外来と一般外来の違いを認識する/鎮静・鎮痛の処置前評価・準備をし,処置の緊急度を把握する/処置の種類や患者背景により,PSAを最適化する/鎮静の前に準備すべきモノ・ヒトをそろえる/起こりうる合併症とその頻度/帰宅時の注意点/[Q&A] 処置時の鎮静と画像検査時の鎮静にはどのような違いがありますか?
② CT/MRI検査時
CT/MRI検査時の鎮静/MRI室の特殊性を理解する/モニタリング/[Q&A] CTやMRI検査時の鎮静に使用される代表的な薬剤について,具体的な投与量と投与方法を教えてください.
③ 消化管内視鏡時
内視鏡時に目標とする鎮静の深さ/状況別の鎮静薬・鎮痛薬の使い分け/麻酔科へコンサルトをしたほうがよいケース/内視鏡における拮抗薬/飲酒と鎮静薬の関係
④ 画像下治療(IVR)時
画像下治療とは/IVRの特徴を分類する/モニタリング/非薬理学的介入/具体的な鎮静・鎮痛の戦略/今後に向けて
⑤ 気管支鏡時
局所麻酔/気管支鏡検査時の目標深度/経静脈麻酔/抗コリン薬/気管支鏡検査中の呼吸モニタリングと気道確保/気管挿管
⑥ 歯科・口腔外科
なぜ歯科治療において鎮静が必要なのか/歯科における鎮静の特徴/歯科における鎮静の種類/救急外来における歯科・口腔外科領域の麻酔
Part8 小児と高齢者の鎮静・鎮痛
① 小児における注意点
小児の解剖・生理学的特徴を把握する/事前準備:絶食時間,気道困難のリスク評価/それぞれの患児にあわせた鎮静・鎮痛方法の選択/患児,保護者への説明/[Q&A] 慣れていない小児の患者に鎮静をかけることが不安です./[Q&A] 保護者は鎮静時,処置時には同席させるべきですか?/[Q&A] LET液のレシピを教えてください./[Q&A] 鎮静後はいつまでモニタリングしたらよいですか? いつ帰宅させてもよいですか?
② 高齢者における注意点
科を問わず,高齢者への処置の機会は多い/生理機能の低下+個人差の大きさ/高齢者では鎮静薬・鎮痛薬の感受性が高い/高齢者では薬剤の濃度が下がりにくい/高齢者ではpolypharmacy(多剤多量処方)の患者が多い/高齢者はバッグバルブマスクによる陽圧換気が難しい/[Q&A] 高齢者の処置時の鎮静には注意する点が多く,不安になってきました./[Q&A] 少量投与とは,具体的にどれくらいの量を投与すればよいのでしょうか?
Part9 ケーススタディ
① 骨折整復の症例
② 除細動の症例
③ 縫合を必要とする小児の症例
④ MRI検査を受ける小児の症例
⑤ 内視鏡検査を受ける症例
⑥ 歯科・口腔外科の症例
⑦ 合併症:モニタリング・蘇生の失敗
⑧ 合併症:拮抗薬の不適切な使用
Part10 トレーニング
有害事象は必ず発生する/なぜシミュレーションコースが必要なのか/米国におけるトレーニングコース/日本の現状/シミュレーションにおける工夫/[Q&A] 看護師や技師など(医師以外)が受けられるコースはないのでしょうか?/[Q&A] オンラインでのコースはないのでしょうか?
Part11 チーム医療
PSAにおけるチームワーク/日本におけるコミュニケーション様式/チーム医療を促進する技術/患者・患者家族もチーム医療の一員であるということ/[Q&A] チームワークやコミュニケーションをトレーニングできるコースはありますか?
Part12 その他のtips
① 感染対策
鎮静時の感染対策の重要性/標準予防策の概要と重要性/手指衛生の重要性と実践/個人防護具の適切な使用/今後に向けて
② 医療安全
医療安全に関わる制度・公的組織/鎮静・鎮痛に使用する麻薬の取り扱い
③ 院内ガイドラインの作り方
処置時の鎮静・鎮痛の実施状況の確認およびインシデント事例分析/ワーキンググループの結成/エビデンスの収集/ガイドラインの原案作成/フィードバックと修正/完成版の承認/実施と教育/モニタリングと再評価
④ 診療報酬・添付文書上の問題点
添付文書と適応外使用という難しさ/ケタミンは入院が必要!?
付録
1.鎮静時のチェックリスト
2.セデーションタイムアウト時のチェックリスト
3.直前チェックのための参考資料
4.鎮静薬(・鎮痛薬)使用同意書
5.小児のMRI検査のための鎮静前チェックリスト
6.小児の鎮静後に家族への説明・指導に用いる文書の例
7.「MRI検査時の鎮静に関する共同提言」の早見表
8.〇〇市民病院検査・処置時の鎮静・鎮痛ガイドライン(抜粋版)
索引
付録・特典
開く
付録PDF版のご案内
本書に収載されております付録のうち、「付録1~4」、「付録8の完全版」のPDFをご利用いただけます。下記のボタンよりダウンロードしてください。