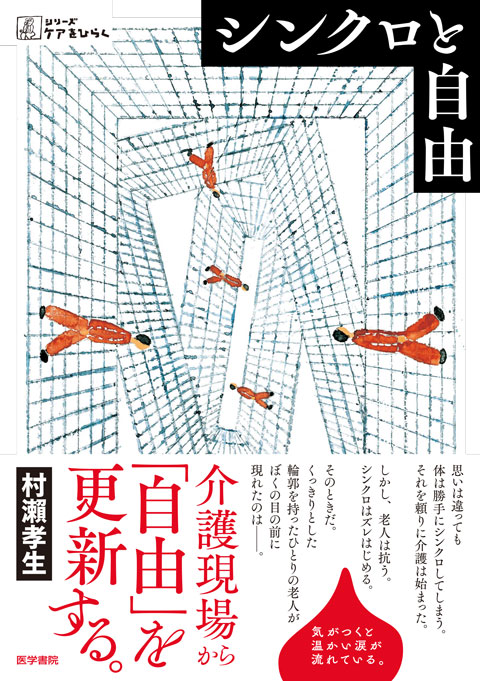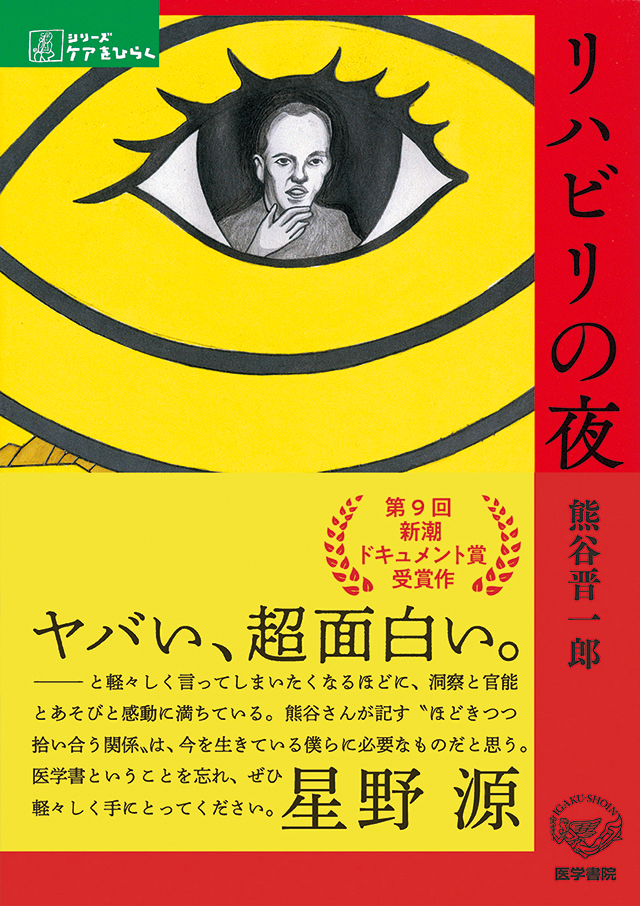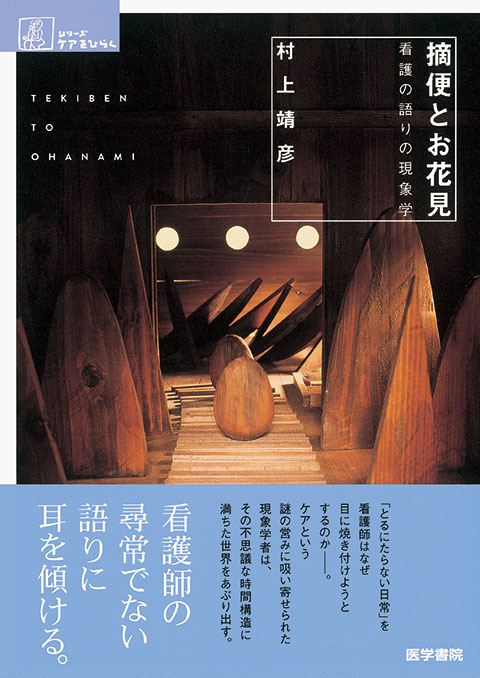シンクロと自由
介護現場から「自由」を更新する!
もっと見る
「こんな老人ホームなら入りたい!」と熱い反響を呼んだNHK番組「よりあいの森 老いに沿う」。その施設長が綴る、自由と不自由の織りなす不思議な物語。万策尽きて、途方に暮れているのに、希望が勝手にやってくる。誰も介護はされたくないし、誰も介護はしたくないのに、笑いがにじみ出てくる。しなやかなエピソードに浸っているだけなのに、気づくと温かい涙が流れている。
*「ケアをひらく」は株式会社医学書院の登録商標です。
| シリーズ | シリーズ ケアをひらく |
|---|---|
| 著 | 村瀨 孝生 |
| 発行 | 2022年07月判型:A5頁:296 |
| ISBN | 978-4-260-05051-7 |
| 定価 | 2,200円 (本体2,000円+税) |
更新情報
-
更新情報はありません。
お気に入り商品に追加すると、この商品の更新情報や関連情報などをマイページでお知らせいたします。
- TOPICS
- 序文
- 目次
- 書評
TOPICS
開く
●詩人の谷川俊太郎さんからコメントが届きました!
本書を刊行してからひと月ほど経ったころ、谷川俊太郎さんより著者の村瀨孝生さん宛に、本書『シンクロと自由』を読んだ感想が記された手紙が届きました。谷川さんにご許可をいただき、ここに転載いたします。
《僕は視力が衰えてきて手元に拡大鏡が手放せない有様ですが、280ページ余を休み休み読み、「北極と岡山にある郵便局」で爽快なカタルシスを味わいました。これは何と言うか、人を具体から抽象へ誘う哲学書でもありますね。
この本には言葉より先に「現場」がある。それに比べると僕が書いているような「詩」には言葉しか(日本語しか)現場がない、それがいつも僕を苛立たせ、詩という書きものに疑問を感じさせているのです。その不満がまた僕の詩を書くエネルギー源になってもいるのですが。
この本を読んでいると、以前だったら書いている村瀨さんの側に立っていたと思うのですが、今や書かれているお年寄りの側に立っている自分に気付きます。鶴見俊輔さんは言葉を人間語、生き物語、存在語というふうに分けていましたが、老いてくるとおいそれと言葉にならない存在語の方に気持ちが寄っていきます。お年寄りが発する存在語に詩で近づきたいというのが目下の見果てぬ夢です。》――谷川俊太郎
●『シリーズ ケアをひらく』が第73回毎日出版文化賞(企画部門)受賞!
第73回毎日出版文化賞(主催:毎日新聞社)が2019年11月3日に発表となり、『シリーズ ケアをひらく』が「企画部門」に選出されました。同賞は1947年に創設され、毎年優れた著作物や出版活動を顕彰するもので、「文学・芸術部門」「人文・社会部門」「自然科学部門」「企画部門」の4部門ごとに選出されます。同賞の詳細情報はこちら(毎日新聞社ウェブサイトへ)。
序文
開く
はじめに
時の流れが速すぎてついていけません。街の風景も忙しく変わるので落ち着かないのです。時と場の目まぐるしい変化を寄る辺なく感じています。
そんなぼくが、これまで生きてこられたのは、老人介護のおかげです。決して大げさではなく本当にそう思います。
年を重ねた老人たちはゆっくりと動きます。排泄も滞ります。眠る時間も増えていきます。衰える時間に付き合うことは徒労の連続に思えました。けれども右肩上がりの経済成長に執着し続ける社会とは真逆の世界が老いにありました。
お年寄り一人ひとりの時と場にチューニングしてみると、ケアしているぼくがケアされていることに気がつきます。
半身麻痺のハナさんは座位を保つことすらできないのに、ぼくの体を洗おうとします。
キミエさんは、自分の食べこぼしを拾ってぼくに食べさせようとしました。
徘徊するヨシオさんは付き添うぼくに「君はどこに行きたいのかね?」と心配します。
そのような気遣いにぼくたちの社会は気がついていません。時と場の移り変わりがあまりに速すぎて「見えない」のだと思います。そのことが常態化して「見ようとしなくなった」のではないでしょうか。認知症の症状ばかりがよく見えて、その人が見えなくなったようです。
そのように考えると、人としての時と場を失ってしまったのは、認知症のお年寄りではなく我々であるように思えてきます。我々が積極的に「見ている」のは言葉や数値で可視化された「分かりやすくてコントロールしやすいモノ」ばかりです。そして今、社会はもっと効率をあげて介護せよと求めます。
客観視することで正しさの精度が上がり続ける世界に「わたし」の主観など無用です。データによる裏付けのある方法論に「わたし」の実感など不要です。ましてや考えなど邪魔でしょう。そうやって「わたし」は消えていくのです。
ところが、お年寄りの世界は実感に満ちあふれていました。主観がぶつかり合っていました。けっして右向け右にはならない「わたし」がいっぱい居たのです。
お年寄り一人ひとりの実感に、ぼくの実感をシンクロさせることが面白く感じられました。ふたりの「わたし」の実感が絡み合って生活はつくられていきます。お年寄りたちも生きた実感を交わすことでぼくをひとりの人間として受け止めていたと思います。
こうしてぼくは、ひとつの行為をふたりで成すために、シンクロする努力に勤(いそ)しんできました。しかしその一方で、意図的にシンクロすることを目指すほど、お年寄りを支配しようとしているのではないか、という疑念が生じはじめてきました。シンクロすることで生活行為における不自由は免れるのですが、何かに拘束されてしまい、自由を失っていくようにも感じられたのです。
むしろ、お年寄りとうまくシンクロできなかったとき、万策が尽きて手段を失ったときにこそ、解放される。そんな感覚を得るようになりました。お年寄りとぼく、両者の「思い」が成就しなかったその先に、「する、される」を超えてお互いにケアしあう状況が生まれるのかもしれません。
シンクロがずれるたびに、お互いが顔を洗って出直すことになります。ぼくたちは感覚を合わせ、実感を交換しあい、合意することを諦めません。一人ひとりの実感を言葉にし、伝えあうことを諦めません。生きることに直結する行為は歩みを止めることができないので、シンクロを重ね、合意し直していくよりないからです。
この終わることのない繰り返しのプロセスのなかで、「わたし」は「ふたりのわたし」となり、「わたしたち」が現れる。私の居場所はそうやってつくられていくように思います。
本書は個人の実感と主観に満ちており、そこから生じた考えで成り立っています。よって、明日からの介護にすぐ役立つことはありません。エビデンス重視の時代と逆行する本だと思います。けれど、よく分からないことに、分からぬまま付き合い続ける実践があってもよいと思うのです。
目次
開く
はじめに
partI 不自由な体同士がシンクロする
1章 思いどおりにならない
1 論と肉声
2 通用しない感じ
3 生身の限界
4 食べない宣言
5 「イヤ」に導かれて
2章 わたし
1 不自由になりつつ自由になる
2 ぼくの体
3 「実感」という事実
4 記憶フォルダーのふしぎ
3章 ふたりのわたし
1 人の体は簡単にさわれない
2 快楽と暴力
3 シンクロは気持ちいい
4 シンクロか、乗っ取りか
4章 時間と場所と、わたしたち
1 変容する見当識
2 タイムスリップ
3 時と場が得られない
4 取り付く島としての「混乱」
5 交感する体たち
6 巻き込まれる力
partII シンクロがずれて自由になる
5章 家が血肉となったお婆さん
おしっこスイッチ
街の記憶とリンクする体
行方知れず
知ったことか
赦し
ミツコさんだけの中継基地
痛み分け
寝たきりがよか
どういたしまして
壊れたおもちゃ
家を守るお爺さん
孤軍奮闘するお爺さん
反転する体
6章 「お婆」を探すお婆さん
危険な声色
声にある波動
新人さん、迫真の現場報告
私の知らない「わたし」
ぼくの場合
再現できない出来事
タブーにふれる
タブーからの解放
7章 人を殺したお婆さん
創られる「おはなし」
殺されそうになった花子さん
離婚係争中と乳首とオランダ人
生き返る母
躍動する知性
8章 たそがれるお爺さん
たそがれる自由人
正常と異常のはざまで生きられないか
契約か信頼か
ステルス介護
顔と通帳
自殺願望
北極と岡山にある郵便局
水浸しと熱中症
有縁と無縁のはざまで
おわりに
書評
開く
老い「あるべき自分」からの解放
書評者:中島岳志(東京工業大学教授・政治学)
毎日新聞 2022年9月10日「今週の本棚」より全文転載
書評を見る閉じる
著者は特別養護老人ホーム「よりあいの森」「在宅所よりあい」などの統括所長。長年にわたって、お年寄りのケアに携わってきた。
村瀨が大切にしているのは、チューニングすることやピントが合うことである。お年寄りは時に家にたどり着くことができず、住み慣れたはずの町を徘徊(はいかい)する。なぜ道が分からなくなるかというと、新しい建物や道ができることで、体の記憶と風景のピントが合わなくなるからだ。逆に、昔から見慣れた看板などが目に入ると、体感によって家までの道が開示され、帰ることができる。大切なのは、実感とのチューニングなのだ。
これは介護の現場の人間関係にも言える。排せつや入浴などは、介助者とお年寄りが体を委ねあうことで成立する。互いが互いの体を通じて、一つの行為を成立させていく。その繰り返しによって二人の体が慣れ始め、同調する。この時、「ふたりで“今ここ”をとらえる」というシンクロが起きる。
私は私から解放され、他者に開かれた自由を生きる。ケアは、自己を自由へと導く行為でもあるのだ。
しかし、意図的にシンクロしようとすると、今度はお年寄りを支配することになる。他者をコントロールしようとすると、乗っ取りという現象が生じ、自由が失われる。
シンクロしないことを恐れてはいけない。うまくシンクロできないときにこそ、その人の輪郭が現れ、別の自由がやってくる。「思い」が成就しなかったときにこそ、「する、される」を超えた状態が生まれ、相互のケアが成立する。村瀨は言う。「この終わることのない繰り返しのプロセスのなかで、『わたし』は『ふたりのわたし』となり、『わたしたち』が現れる」
私たちは老いによって機能不全が起きることを「不自由」と捉えがちである。しかし、村瀨は、そこに新たな自由を見出(みいだ)す。時間が分からなくなることで時間から解放され、子どもの顔が分からなくなることで親であることから解放される。覚えていることが出来なくなるので、毎日が新鮮。規範的な自己像が崩れることで、自分を縛っていた「あるべき自分」から解放される。
筋肉はどんどん衰える。しかし、内臓は動き続ける。内臓は意思によってコントロールされない。勝手に動き続ける。村瀨の見るところ、人は老いによって、内臓に回帰していく。意思がどんどんと不明確なものになり、「食べる」「排泄(はいせつ)する」「眠る」といったオートマティックな繰り返しを生きる。ここには目論見(もくろみ)がない。意思から解放された自由が存在する。
お年寄りは、「今」からも自由になる。過去の感情が今の私とシンクロすると、昔の「わたし」がよみがえる。昔の「わたし」が今の「わたし」に現れる。「わたし」の膜が溶け出し、タイムスリップが起きる。私は今に限定されない。「『わたし』とは、体という場に蓄積した時間」である。
本書は、何よりも読者を「あるべき規範」から自由にしてくれる。近代は人間に「意思」や「合理性」、「責任」といった観念を強いることで、そこからズレた存在を疎外してきた。この硬直化した人間像から解放された時、私たちは老いによる自由に、慈しみと敬愛の念を持つことになるだろう。名著だ。
老いと介護にある「救い」とは
書評者:頭木弘樹(文学紹介者)
日本経済新聞 2022年8月20日 書評欄より全文転載
書評を見る閉じる
「衰える時間に付き合うことは徒労の連続に思えました」と著者は「はじめに」で書いている。まさにそこが私も気になっていた。子育ても大変だが、子どもはできなかったことができるようになっていく。看護も病人が治っていくことがある。しかし老いでは、できていたことができなくなっていく。成長しないものの面倒をみることは難しい。花だって、育っていくから、みんな水をあげるのだ。介護に情熱を傾けている人たちは、そこをどう考えているのか?
「お年寄りたちは喜んで介護されてはいなかった。介護するぼくも喜んでしているわけでもなかった。それは仕方なく始まっていくものだった」と著者。なるほどと納得がいく。しかし、続く文が意外だ。「けれども、この仕方なく始まることに救いがあると思うようになった」。救いとはどういうことなのか、気になって読み進めた。
著者は特別養護老人ホーム「よりあいの森」「宅老所よりあい」「第2宅老所よりあい」の統括所長。施設の高齢者とのさまざまなエピソードが語られているが、読んでいるうちに、人間とは? という話に感じられてきて、さらに自分自身のことに思えてくる。たとえば、100歳の女性が、夜中になると幼児に戻って「おかあさ~ん」と泣きそうな声を上げる。夜勤の女性が「どうしたの」と声をかけると「ああ、お母さん来てくれた!」と大喜びで抱きつき、「お母さん、入れ歯がないの」。
2歳であり100歳なのだ。著者は自分を振り返る。「57歳のぼくの体には0歳も、13歳も、22歳も、45歳も存在している。ぼくは多世代人格によって成っている」
言われてみれば、私もそうだ。
介護する側とされる側の体や心がシンクロする。しかし、すぐにズレ始める。ズレは解放であり自由でもある。またシンクロしようと努力する。その繰り返し。思うようにならない他人や自分と、どう付き合えばいいのか。介護だけの問題ではないだろう。箇条書きになるような方法があるわけではない。しかし、たくさんのヒントで、頭の中が星空のようになる。
読み終えて、老いへの不安が、好奇心に変わり、「おわりに」の冒頭に書いてある「長生きしたいと思うようになりました」という著者の言葉に、素直にうなずけた。
介護の現場から考える“自由”
書評者:中村佑子(映像作家・立教大学講師)
(VOGUE BOOK CLUB 2022年11月9日より)
「老いて衰える」こともおもしろそう
書評者:中野亜海(編集者)
(HONZ 2022年11月13日より)
●コメントが届きました。
《僕は視力が衰えてきて手元に拡大鏡が手放せない有様ですが、280ページ余を休み休み読み、「北極と岡山にある郵便局」で爽快なカタルシスを味わいました。これは何と言うか、人を具体から抽象へ誘う哲学書でもありますね。》――谷川俊太郎(詩人)
「TOPICS」欄へ
●新聞で紹介されました。
《著者は自らの見た光景や実践を通して、社会では〈混乱〉や〈バグ〉とされるものを丁寧に解し、言語化していく。その様子に繰り返し触れるうちに胸に届き始めたのは、人間の老いというものの力強さだった。》──稲泉連(ノンフィクション作家)
(『朝日新聞』2022年9月10日 書評欄・BOOK.asahi.comより)
《著者は「シンクロ」を、限られた時間と場所でぴたりと合わせる現象から解放する。著者の「シンクロ」は、時間も場所も超え、今ここにある自身の体に、相手に起こっていること、あるいはかつて起こっていたことを立ち上げる。この本の不思議な物語の数々を読めば、読者も、その「シンクロ」の力に触れることができる。》──細馬宏通(早稲田大学教授・人間行動学)
(共同通信配信、『神戸新聞』2022年9月17日ほか)
《本書は、介護者が「ケアする側」と「ケアされる側」という立ち場をこえて人間の根源的なあり方を問い直そうとする画期的な本である。……評者は本書を読むまでは、ままならない体を持つのはお年寄りであって、介護する人は健康であるがゆえにその体をコントロールできていると思っていた。だが、直立人も様々な衝動に絡めとられながら、横臥者の衝動とシンクロさせ折り合いをつけているのかもしれない。》──小川公代(上智大学教授・英文学)
(『週刊読書人』2022年10月7日)
●雑誌で紹介されました。
《老人ひとりひとりの「わたし」の動きや思考に、介護をする「わたし」が幾度ものずれを経てシンクロしたとき、お互い合意する介護ができると著者は繰り返す。》──東えりか(書評家)
(『婦人公論』2022年12月)
●webで紹介されました。
《村瀬さんは「老人性アルツハイマー病」というお婆さんが受けている診断の医学的な見方に対し、お婆さんのタイムスリップを生活者としての視点から「『老人性アメイジング』と呼んでみたい」と記す。》──猪熊律子(読売新聞・編集委員)
(読賣新聞オンライン「安心コンパス」2023年2月23日)