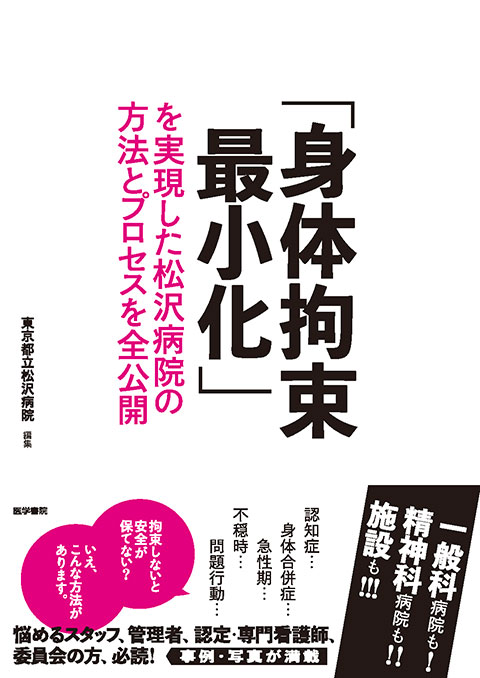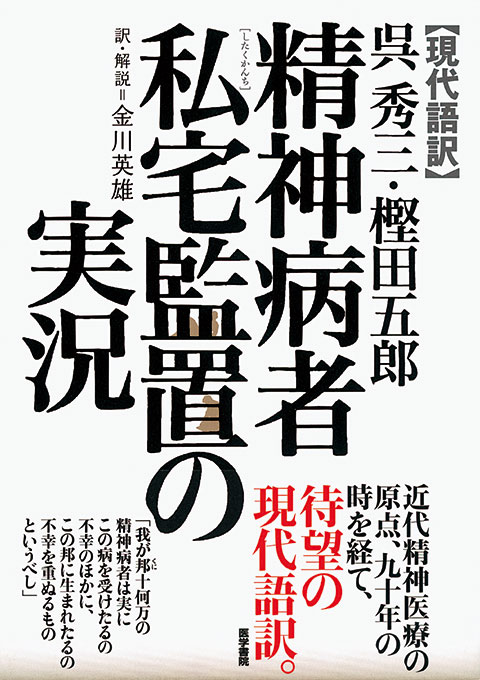「身体拘束最小化」を実現した松沢病院の方法とプロセスを全公開
あの松沢病院のテクニック・考え方を、次はあなたの組織でも!
もっと見る
| 編集 | 東京都立松沢病院 |
|---|---|
| 発行 | 2020年11月判型:B5頁:192 |
| ISBN | 978-4-260-04355-7 |
| 定価 | 2,420円 (本体2,200円+税) |
更新情報
-
更新情報はありません。
お気に入り商品に追加すると、この商品の更新情報や関連情報などをマイページでお知らせいたします。
- 序文
- 目次
- 書評
序文
開く
松沢病院の変遷を、世に公開することの意義
2012年以降、松沢病院は身体拘束削減、隔離室使用の短縮に努めてきた。現場におけるそのプロセスは、本書の中に詳しく述べられている。私は、病院の管理者として考えたこと、行ったことについて述べることにする。
麻痺していた倫理観を覚醒させる
精神科病棟における患者の意思に反した隔離・拘束は、患者自身を守るため、患者の暴力から職員の身を守るため、あるいは離院等の事故を防ぐために行われる。したがって、行動制限の大部分は「治療者側の論理」で正当化される。しかしこれを患者の側から見たらどうだろう。あらゆる行動制限は、その意味を理解しない患者にとって、極めて不合理な心的外傷に他ならない。
精神保健福祉法による行動制限の手続きは、患者の人権を守るための規定と考えられている。しかし一方で、正しい手続きを踏んでいるということ、定時の観察記録を診療録に残しているということが、行動制限をする側が本来感じるべきためらいを薄め、私たちの倫理観を麻痺させている。
松沢病院の行動制限最小化は、麻痺していた私たちの倫理観を覚醒させ、1人の人として患者を遇するという精神医療の基本中の基本を思い出させるもの、そして患者を傷つけない精神医療の実践を目指すものであった。
患者中心の精神科医療へ
2012年、広い敷地に点在していた20あまりの病棟のほとんどを新しいビルに集約し、松沢病院は現代的な病院に生まれ変わった。そしてこの年に開始した行動制限最小化の動きは、2013年度の目標《民間病院の依頼を断らない》と、2014年度の目標《患者に選ばれる病院になる》と一体となって、患者中心の精神医療を推進することとなった。
《民間病院の依頼を断らない》という目標は、入院患者を増やして病院の収支を改善しようというものではない。松沢病院は極めて高コストな病院であり、その赤字はすべて公費で補填されている。この状況を正当化するためには、一般納税者を含むすべてのステークホルダー(利害関係者)を納得させるだけの精神医療を展開しなければならない。収支に合わない手間のかかる患者は松沢が引き受ける、という方針を徹底すれば、税金を使う大義にもなるし、民間病院の負担軽減を通じて精神医療全般の治療の質の向上にも資する。
《患者に選ばれる病院をつくる》という目標は、患者自らが治療を受けようと思う病院になるということである。過去には強制的な治療により入院治療が患者のトラウマ体験となり、そのために具合が悪くなってもそれを隠し、病院に行かないようにし、最悪の状態になってから入院するという現象が起きていた。行動制限の最小化により入院治療が患者のトラウマにならなければ、具合が悪くなった時、患者が自ら治療を求めて来院するようになり、予後改善にもつながる。そして強制的な治療を強いる必要性は劇的に小さくなる。
病院経営者としてコミットしたこと
行動制限最小化の推進と並行して、私は次の3点について環境整備を進めた。
①事故のリスクを管理する
行動制限をする動機の1つが事故防止である。
事故を過度に恐れては前に進めないが、いったん大きな事故が起これば、長年積み重ねた努力が一朝にして水泡に帰す。事故は必ず起こるという前提で、その被害を最小にする努力をしなければならない。
最初に手をつけたのは、「インシデントアクシデント報告(以下IAレポート)の実効性の向上」である。2012年度以前、松沢病院のIAレポートのインシデントの数は不自然に少なかった。アクシデントについては隠しようがないからほぼ正確だと言ってよい。ところが軽度のインシデントは報告されなければ確認のしようがない。幸い同じ時期に電子カルテが導入され、IAレポートの報告がたやすくなった。小さなインシデントであればごくごく簡単な報告でよい、法令違反や重大な怠慢がない限り報告者の責任を問わない、という方針を徹底することによって、軽微なインシデントの報告数が増えていった。
この作業と並行して行われたのが、看護部を中心とした「リスクマネジメント機能の強化」である。専従リスクマネジャーに求められる役目は、事故が起こった時に張り切って調査に入り、責任を追及することではない。何もない時にIAレポートを集め、分析し、大きな事故の兆しを察知し、それを避けることである。事故は必ず起こる。事故の責任は、当事者だけでなくそれを防げなかったリスクマネジャーのものである。そうして最後は、看護部長、病院長が責任を負う覚悟を示すことが、職場の安心を高める。
②自分たちの仕事を評価される機会を積極的につくる
精神科病院の病棟は閉鎖的な空間である。社会的な常識が通用しないこともある。働く私たちは、しばしばその特殊性を忘れてしまう。厳しい評価は耳に届きにくい。自分たちの仕事に対する評価は、私たち自身が積極的に求めなければならない。
この時手をつけたのは、都立病院全体で行われていた「退院患者・家族アンケートの分析」である。毎月松沢病院で行われるアンケートの回収率は30%前後で、しかも患者が自分で記入したものと、家族が記入したものとが区別なく集計されていた。非自発的な入院を強いられた患者と、処遇に困って病院に助けを求めた家族とでは、入院に対する評価が正反対になることもある。異質なデータを平均してしまっては、全く無意味である。
そこで患者と家族のアンケートを区別し、退院時に看護師から記入を促して回収率を高めた。さらに患者のアンケートに隔離・拘束の有無を尋ねる設問を追加し、ありと答えた患者には自由記載で感想を求めた。拘束された患者の自由記載コメントは、拘束削減を推進する際に大きな力になった。
同時に、都庁により隔年実施されていた、全入院患者に対するone day調査と、外来患者全員に対する1週間にわたるアンケートを毎年行うことにした(まもなく、他の都立病院も隔年実施を毎年実施に変更した)。
続いて、「面会に来られた家族を可能な限り病棟内に導く」、また「院外からの研修、見学等を積極的に受け入れる」という方針を立てた。これによって、職員の日常の仕事ぶりが他人の目に触れるようになり、私たちの仕事の緊張が増すと同時に批判を受けることが容易になる。そして家族や第三者の目が入れば、看護労力の絶対的な不足という日本の精神医療の実情を知ってもらうこともできる。こうした相互理解は、事故の際の訴訟リスクを下げる。
2013 年度からは、「第三者評価制度を導入」した。看護、精神医療、その他(弁護士、ジャーナリスト、その他の学識経験者等)からなるチームが病棟に入り、レポートを作成する。レポートは当該病棟に回され、病棟で対応を考える。年度末に第三者評価委員、病院幹部、当該病棟スタッフが集まってディスカッションを行う。弁護士、ジャーナリストなどの意見は、しばしば臨床現場の常識とはかけ離れていることもあるが、専門家が忘れていた視点を提示されて目を開かれることも稀ではない。
この他、学会発表、論文、講演、ホームページ、その他のメディアを通じて「病院が情報を発信する」ことにも努めてきた。これによって臨床の質が向上し、同時に閉鎖的な精神科病棟の日常が明らかになる。過大な期待、精神医療に対する根拠のない蔑視、偏見は、いずれも事故後の訴訟リスクを拡大する。
③患者の声を聴く工夫
退院患者、在院患者アンケートの自由記載欄を読むことは、隔離・拘束の削減に大きな力があった。
例えば薬物の急性中毒で入院した青年は、身体拘束について、「目が覚めたらベッドに拘束されて身動きできなかった。おしっこをしたいと言ったら、オムツをつけてあるからそこでしても大丈夫だと看護師が言って相手にしてくれなかった。オムツをつけられたことも縛られたことも覚えていなかったが、興奮している間に裸にされて縛られたのだろう思うと身が震えた。こんな屈辱感は味わったことがない」と記した。隔離や拘束に関与する医師、看護師がこうした記載を通じて患者の声を直接聞くことは重要である。
この他、患者とのコミュニケーションを深めるため、「診察室やナースステーションから出よ」「拘束した患者のそばに座って患者の罵声を聴け」という目標を掲げた。些細なことでも、患者からの問いかけには、看護ステーションを出て向き合って話そうという意味である。ナースステーションのモニターを通じて隔離室で拘束されている患者を観察し、マイクで患者に話しかけていては、患者の痛みがわからない。
拘束された患者のそばにいて、罵声を浴び、つばを吐きかけられなければ拘束された人の気持ちはわからない。興奮する患者を多人数で押さえ込み、拘束して薬で鎮静するというプロセスに、ふと、これでよかったのだろうかと心によぎる不安や揺らぎが、私たちの臨床を強いものにする。
呉秀三と松沢の100年
今からちょうど100年前、第5代の松沢病院長だった呉秀三は、精神障害者への医療の必要性とその人道的処遇を説いた。拘束具の全廃を命じ、さらに隔離室の使用を制限すると同時に、看護職員の資質向上に努めた。
100年が経った今、どうなったか。精神障害者の隔離拘束という医療課題は、向精神薬もmECTもなかった当時と少しも変わっていない。それは、精神障害者を客観的に観察・評価しない、その心の中の主観的苦しみに十分な配慮をしないという精神医療の本質が変わっていないからではないか。
私たちは、松沢病院の行動制限最小化の試みが、少しずつ精神科病院の治療構造に地殻変動を起こしつつあることを実感している。100年後の精神医療従事者が、2019年の松沢病院の努力を振り返り、「あれが今日につながっている」と思ってくれるような努力を続けなければならない。
東京都立松沢病院長 齋藤正彦
目次
開く
1章 日本の身体拘束の現状と、松沢病院の改革
1 そもそも身体拘束の定義にグレーゾーンがあるために生じている問題があります
2 何が「身体拘束」? 自分の施設の基準を決めよう
3 松沢病院では身体拘束をこのように定義しました
4 過酷な条件下でも身体拘束最小化はできることを示していく。
それが松沢の使命
5 はじめの一歩。認知症病棟では何をしたのか
6 乗り越えるべき3つの壁がありました
取り組み裏話① 管理者の立場で語る、認知症病棟で
拘束ゼロに取り組み始めた当初のこと
2章 松沢病院が身体拘束最小化を実現した25の方法
はじまりのはじまり
それは新院長・新看護部長の方針表明から始まった
ここから25の方法を紹介します
方法01 行動制限のデータを数値化し、公表し、可視化する
方法02 身体拘束を明確に定義し、グレーゾーンを作らないようにする
方法03 “支えるリスクマネジメント”に切り替え、医療安全委員会と連携する
方法04 いざという時は管理者が「責任を負う」ことを明言する
方法05 データ集計の単位を変更。変化がわかりやすいようにする
方法06 身体拘束を「する」ことの弊害に意識が向くように情報を伝える
方法07 家族に「当院はできる限り身体拘束を行いません。
それによる転倒のリスクがあります」と説明し、
納得を得てから入院してもらう
方法08 職員教育で、患者さんの目線に立った研修を開催する
方法09 指示を出す医師との意識のギャップをなくし、協働する
方法10 行動制限最小化委員会が、現場で解除を推進する
方法11 代替手段を提案、導入し、ケアの引き出しを増やす
方法12 身体拘束を解除する目的で多職種カンファレンスを毎日開く
方法13 記録に無駄な時間をかけず、患者さんのそばに行く時間を増やす
方法14 救急・急性期病棟 入院時に鎮静・身体拘束ではなく、会話をする
方法15 慢性期病棟 重症化の前に自らの意思で「休息入院」を選択してもらう
方法16 慢性期病棟 問題行動ではなく「困っているサイン」と捉える
方法17 認知症病棟 QOLから考え、身体拘束せずにできる治療へと、工夫を極める
方法18 身体合併症病棟 身体治療においても精神科医が早期に介入する
方法19 終末期医療 死は負けではない。治療は、本人・家族・医療者の考えを
すり合わせてから
不安や気持ちの壁をどう乗り越えるか
方法20 まずは1人からやってみて小さな成功体験を積み重ねる
方法21 最小化できない理由を探さない
方法22 「手間暇はかかるもの」と腹をくくる
方法23 患者さんに対して抱いている「不安」「恐怖」「偏見」を自覚する
方法24 「最小化」を目標にするのではなく、あくまで
「患者さんのQOLの向上」を目指す
方法25 悩み続ける姿勢、あきらめない姿勢でいく
一緒に進んでいきましょう
3章 こんな工夫と考え方で身体拘束を外せた15の事例
事例01 長期入院中の統合失調症の男性。
問題行動、興奮、転倒の心配から、長期間拘束が外せなかった事例
事例02 統合失調症、ステロイド性精神障害の50代女性。
ベッドから転落しようとする衝動行為が止まらず、
拘束が長期化していた事例
事例03 長期入院中の統合失調症の60代女性。
危険行為、迷惑行為、転倒リスクから、
長期間拘束が外せなかった事例
事例04 パーソナリティ障害を持つ長期入院中の50代女性。
「自傷➡拘束」の繰り返しでスタッフが疲弊しきっていた事例
取り組み裏話② 認知症病棟が本当の意味で「身体拘束なし」を
実現するまでの経緯
事例05 認知症の70代女性。
他の患者さんの経鼻チューブを抜く危険な行動があるが、
それでも行動制限せず歩いてもらった事例
事例06 BPSDの改善目的で転院してきた認知症の70代男性。
前院で拘束や制限の多い環境に置かれ、暴力的になっていた事例
事例07 BPSDの改善目的で入院してきた80代の認知症男性。
転倒リスクが高いが、被害妄想が強いため
近づくことを許さない事例
認知症の患者さんの周辺環境を、安全に心地良く整えるためにできる工夫
取り組み裏話③ ルート類が入っていることが多い身体合併症病棟で
身体拘束を早く外すために
事例08 アルコール依存症の50代男性。
中心静脈栄養(CV)が挿入されたが、
状態の改善に伴い自己抜去のリスクが高まった事例
事例09 がん末期で転院してきた40代男性。
ルート自己抜去、せん妄など、リスクが重なっていた事例
事例10 認知症が進行した70代女性。
ミトンを外す時間を長くしたいが、
経鼻チューブを自己抜去されるジレンマがあった事例
事例11 認知症の80代男性。
前院で食事摂取は困難と判断され、経管栄養に。
自己抜去防止のために拘束され、衰弱した状態で転院してきた事例
事例12 緊急措置入院のアルツハイマー型認知症の60代男性。
拘束具により2日目に圧迫創傷が生じた事例
取り組み裏話④ 救急外来・急性期病棟で身体拘束なしに大転換できた理由
事例13 警察依頼で搬送されてきた、統合失調症の40代女性。
意思疎通が困難で、落ち着きがなかった事例
事例14 統合失調症の50代女性。
緊急措置入院で、点滴が入ったまま保護室へ。
目覚めた時に点滴台でケガをするリスクがあった事例
事例15 双極性感情障害の40代女性。
躁状態で暴言・暴力があり、保護室に隔離。
激しく拒薬している事例
おわりに
身体拘束最小化がもたらしたもの
column 一覧
[1]医療観察法病棟には身体拘束具を置かなかった
[2]当初の混乱を経て、「いかに身体拘束を回避するか」に焦点が移るまで
[3]一律から個別へ。とにかく会話を始めた
[4]措置入院でも身体拘束が減り、「やわらかな治療」へ
[5]方針が出た時には想像もつかなかった景色が目の前にあった
[6]認知症病棟にならい、精神科救急病棟でも
「身体拘束をしない同意書」を導入
[7]内科医が考える身体合併症治療と身体拘束
[8]精神科医が考える身体合併症治療と身体拘束
[9]一度医療を始めてしまったら後戻りはできない。だから入口が大事なのだ
書評
開く
書評者:小貫 洋子(医療法人社団全生会江戸川病院看護部長)
本書を目にした時,「実現した方法とプロセスを全公開」というタイトルに惹きこまれた。
講演や学会などで,東京都立松沢病院が行動制限最小化の取り組みに成果を上げていることは幾度となく聞いてきた。今回その取り組みの全てを知ることができる本書を手にし,胸が躍りワクワクした。本書には「身体拘束最小化を実現した25の方法」と「身体拘束を外せた15の事例」が書かれている。内容を読み進めていくとワクワクが確信へと変わる。なぜなら私たち精神科看護師は誰もが一度は,なぜ拘束が外せないのかと悩んだことがあるからだ。しかし,適切なアドバイスや方法が見つけられず,安全と人権の倫理に悩みながらも身体拘束を続けてしまっているのではないだろうか。本書はその悩みを解決する糸口を見つけ出せる1冊だからである。
その身体拘束は誰のため?何のため?
「精神保健福祉資料・630調査」によると2018年に身体拘束は全国で1万人以上に実施され,10年前の約2倍に増加している。そして日本は2025年に75歳以上の後期高齢者が2000万人を突破。この超高齢社会においてさまざまな疾患が増えたこと,そして認知症が増加したことが身体拘束増加の要因の1つなのだろう。しかし,果たして原因はそれだけだろうか。
身体拘束実施について厚生労働省は,三要件「切迫性」「非代替性」「一時性」を全て満たしているケースに限るとしている。ただ,自身の経験では,身体拘束開始の時には確かに三要件に基づき開始したものの,いつの日かその理由がすり替わってしまい,長期間の拘束実施になってしまったケースがある。
なぜ理由がすり替わるのか? そこには医療安全の壁がある。当初は「患者の身を守るために拘束する」であったはずが,拘束を続けることで「身体機能が衰える」「身体機能の衰えから転倒する」「転倒すればインシデントレポートを書かなくてはならない」「レポートを書くことが苦痛(懲罰)である」「書きたくないから転ばせたくない」「転ばせたくないから拘束をする」という悪循環に陥り,患者さんの身の安全よりも自分たち医療者の安全のために漫然と拘束を続ける。
「ふらふらしていて転倒リスクが高いから」と言えばいかにも患者側の理由に聞こえるが,その裏には「転ばれたら困る」という医療者側の実情があるのだ。
この本を手に成功体験を
この医療安全の壁を乗り越えたのが,東京都立松沢病院である。始まりは,新院長・新看護部長による方針表明だったとある。
職員1人ひとり,誰しもが医療や看護に対して悩んだり,不安だったり,変化を起こしたい,改善したいと思っている。しかし自分1人ではできることも限られる。何よりも自分が行動を起こして患者さんに何かあったらどうしようと思うと,行動する手が止まってしまう。その職員のチャレンジを活かす原動力になったのが方針表明である。
トップの思いや考えが職員に伝わり,自分たちが支え守られていると感じられると,1人,2人と「やってみましょうか」と声が上がり,活動の輪が広がっていった。身体拘束最小化を行うことで得られる患者さんの笑顔のために,そして私たち医療者の笑顔のために,「まずは1人から,少しずつ」を合言葉に,この1冊を手に成功体験を積み重ねていこう。私は今,看護部長としてそう考えている。
身体拘束最小化という願いを叶えるための歩みを示す(雑誌『看護管理』より)
評者:小藤 幹恵(石川県看護協会 会長)
身体拘束をしないことが医療の中で普通になっていくことを願う人々にとって,今,既にそれを実現している医療の場は,強い関心を抱く対象となる。
本書を編んだ松沢病院が取り組んだ医療の先にあるものは何か。本書は,患者さんと医療従事者との関係性を,病院の目指すところに向けて発展させた,具体的な実践である。「私たちはこのように生きたい」「このような社会で暮らしたい」という,医療の根底にある願いを見つめて行動した,医療チーム,患者さん,家族の物語である。ここに描かれている実践には真に迫る凄みがある。
本書に示された,人への畏敬の念とその実践
今日この進歩した社会をもってしてもいまだ「身体拘束」にはさまざまな状況があり,取り組みの産声を上げることさえはばかられるときもある。本書には,松沢病院のように多数の専門職によって構成される大規模な病院がこれに取り組むことについての,不安,恐怖,苦難とその先にある諸事への対応など,立ちはだかる壁の姿も具体的に示されている。壁の明確化は身体拘束低減への扉を開く。そして,社会にとって大切なものを伝える。
例えば,「先生(病院長)の怒りは,患者さんの気持ちを代弁した態度」と受け止める域にある看護師長と,その思いを着任当初からの日々の中で醸し出す病院長という,リーダーの姿があったことに心打たれる。
身体拘束最小化に取り組んだ歳月に一貫して流れているのは,人々が共感し合う様子と,目指す医療に向かうパッションだ。本書に示されている,人への畏敬の念とその実践は,医療に携わるという点で土俵を一にする私たち読者に,願いを叶えるための歩みを示し,勇気と慎重な準備に基づく行動を喚起するものと言える。
中でも,専門領域の違う医師たちが,目の覚めるような発想の転換に基づき,患者を中心に連携した様子は,身体拘束最小化を含めた新たな医療モデルと言え,その内容が記されているのは本書ならではと思われる。
貴重なケアの実例がアイデアのリソースに
本書では,多くの素晴らしい言葉に出会う。「自分の意思,選択に加え,自分の足で入院する」「動かないでいてもらうことは援助ではない」「入院時は身体拘束ではなく,会話を」など,読者自身も知っている何気ない状況が,捉え方によって意味と輝きを増すという発見がある。また貴重なケアの数々が写真も用いて示され,参考となりアイデアのリソースにできよう。
筆者も身体拘束をしないことの効果・成果を問われることがある。本書の中でも,「患者さんにとっては拘束されないことが普通で当たり前である」ということについて,医療従事者間で認識にズレがあるかもしれないと述べられている。病院長の方針と院内の取り組みが,このようなことに気づいていける環境を作り上げていっている。
そして,“身体拘束をしないこと”が継続できている理由として,心に沁みる医療や看護の姿が描かれている。身体拘束をしないことによって“神業”とも言えるようなことが起こっている様子,医療が希求する情景が,映し出されている。本書を手にし,読み進めることで,困難が多いものと受け止められがちな“身体拘束をしないこと”が一歩進めば日常の幸せがひとつ増えることを,ぜひ実感していただければと願う。
(『看護管理』2021年4月号掲載)
「身体拘束最小化」――この言葉に心がうずく人こそ読んでほしい(雑誌『精神看護』より)
書評者:安藤 由紀(医療法人社団協友会笛吹中央病院勤務・看護師)
私が寝たきりになっても
私は右向きで、顔の下に右手があり左手が顔の前になければ落ち着いて眠れない。極私的なことであり、共に暮らす家族がいないので、こんな癖を知っている人はいない。もしも長生きし、どなたかが寝かしつけてくれるような状況になった時には右向きにしてほしい。
「あの患者さん、褥瘡ができないように向きを変えても右ばっかり向いて。枕があるのに腕を曲げるから固まっちゃうし。でも、あれが落ち着くんだろうね」と言ってぜひ放置しておいてもらいたい。今から、いざという時のお願いリストに書いておこうと思っている。間違っても、褥瘡ができないように逆向きにされて拘束などはしないでいただきたい。
取ってあげたい vs 保身
新人の頃に、両手にミトンを着けた100歳に近い認知症のAさんに「神様、仏様、看護婦様ー。これを取ってください。私が何か悪いことをしましたか? 助けてくださーい、お願いしまーす」と言われたことがある。治療のため経鼻胃管を挿入し、自己抜去予防のためにミトンを使用していた。息子さんが面会している間は外していたが、帰り際に「やっぱりミトンを外せませんか? なんだかかわいそうで……。でももし抜いたらまた鼻から管を入れ直すのも大変ですよね。私も、ずっとは居られないし……」と言われるたびに「すみません」としか言えず、その時はやるせない気持ちになった。だが抜かれた時のことを考えると(医師への報告、家族への連絡、インシデントレポート、再挿入など)、患者さんや家族の気持ちよりも保身が上回った。
せめてベッドサイドにいる時間だけでもとAさんのミトンを外すと、「あー幸せ幸せ」と言いながら自由になった手で私の頬を撫でてくれた。ちょっとウルっとしていたら、離れた病室の認知症患者の離床センサーが作動した。ここでAさんにミトンを着け直していたら、あっちの患者さんが転んでしまう。でもミトンを着けないと抜かれちゃう、と、「どっちだー!!」と焦りながら、目の前のAさんに「お願いだから抜かないで! すぐに戻るから。頼んだよ、ほんとお願い」と叫びながら走り出した。
離床センサーの紐が抜けベッド柵にもたれ掛かっていた患者さんの元に着くと、点滴の針は抜けオムツも外れていた。転ばなくてよかったとホッとし、他の看護師が来たので「Aさんがミトンを外したままなので戻ります。こっちお願いします」と胃管が抜かれていないことを祈りながら走って戻った。「お願い抜かないで!!」の祈りが通じたのか、Aさんは自由になった手を胸の上で組んで静かに待っていた。抜かないようにと自分で気をつけて手を組んでくれていたのかもしれない。「抜かないでくれてありがとう。助かりました」とAさんに言ったのを覚えている。
しばらくしてAさんは療養病棟に移り、手を鼻の近くまで動かすことができなくなったためミトンは外され、たまに会いに行くと目を閉じて胸の上で手を組んでいた。
「転ばないで」はいつしか「動かないで」に
私は一般病棟で働いており、“転ばないように”“抜かれないように”とミトンや車椅子ベルトなど使用して身体拘束を行っているが、それでも患者さんは転んでしまうし、チューブ類を抜いてしまう。先に書いたように「ミトンか!?センサーか!?」と迷うこともあるし、センサーが同時に2人、3人と鳴ることもあり、綱渡り。いつ転倒に遭遇してもおかしくない状況だ。
そのような中で、「お願い、転ばないで」が、いつしか「お願い、動かないで」に変わってしまい、患者さんの動こうとした理由や動ける力を知るために患者さんの傍にいるよりも、センサーから体幹ベルトへと、より患者の動きを狭めてしまう拘束を行っていることも多い。患者さんの動こうとした理由がわかっても、毎回それに付き添えず拘束に至ることもある。
体幹ベルトよりは体を動かせるクリップ式のセンサーを、と考えて使用していた認知症の患者に「こんなの着けて。俺は犬っころじゃない!!」と怒鳴られたこともある。よほど屈辱的だったんだろうなと思いながらも「転んでケガをしないためです。我慢してください」と使い続けた。もっと看護師がいたら……と毎日思うが、看護師がいても状況はもしかして変わらないのかもしれない。やっぱり危険だ、転んでしまう、と理由をつけて同じことをするのだろう。
「ゼロ」ではなく「最小化」と言っている理由
本書『「身体拘束最小化」を実現した松沢病院の方法とプロセスを全公開』は、身体拘束ゼロとは謳っていない。私は「最小化」という言葉によって、この本に興味を持った。身体拘束ゼロと言われてしまったら一気にハードルが高くなり、「看護師が十分いる病院だからできるんじゃないの? うちは無理、無理」と読む気が失せてしまっていただろう。
読んでみると精神科病棟の看護師の少なさに驚き、そんな中でこんなことができたのかとさらに驚いた。看護師の数じゃない、それを言い訳にしないでできることを探さなければ、ということなのだ。そして読みながら、「そんなの無理、無理」って思うことはそれほど書かれていない、と思った。本にはこう書かれてある。
「身体拘束ゼロ」を目指していく気持ちは大切です。しかし、「ゼロ」が目的となってはいけないと考えています。本当の「目的」は「患者さんの幸福」です。私たち医療者は、患者さん1人1人の人生に寄り添いながら「身体拘束」について考えていく必要があります。(第1章p24)
たぶん誰もが心がざわめくだろうけれど
なお、正直に言うと拘束について書くのは大変苦しかった。上述したように、今でもさんざん拘束をしていて、インシデントレポートやアクシデントレポートも書いているのに、と、自らの矛盾や、保身やあきらめや、勉強不足や理想が頭の中でざわめき、そんな自分が何を書くのかと、自己ツッコミがやめられなくなるからである。だからもしかしたら読者の皆さんも、この本を読むと心がざわめくかもしれない。この本は私たちをいっさい責めていないし、できる方法を具体的に提示してくれているのだが、やっぱり身体拘束が外せない状況にある自分たちを鏡で見せられているように感じてしまうからだ。
だが、本書をめくりながら、1枚の素敵な写真が目に留まった。認知症の患者さんが椅子に座り1人で外の緑を眺めている写真だ。背中からなので患者さんの表情はわからないが、その佇まいからは意思が感じられる。気力を失った諦めの背中ではない。こんな風景が松沢病院の認知症病棟では当たり前に見られるのだろう。
そこに至るまでのプロセスは、この本に「25の方法」や「15の事例」として解説されており、当初どのような葛藤があり乗り越えたのかというスタッフの生の声も「裏話」として載っているのでここで詳しくは述べないが、私にはこの写真がすべてを物語っているように思えた。「手間暇はかかるもの」(p101)と腹をくくった結果、このような風景に出会えるというのか。私もできることなら自分の病院でこんな患者さんの姿を見てみたい。その思いで、いまも本書をめくり続けている。
(『精神看護』2021年1月号掲載)
更新情報
-
更新情報はありません。
お気に入り商品に追加すると、この商品の更新情報や関連情報などをマイページでお知らせいたします。