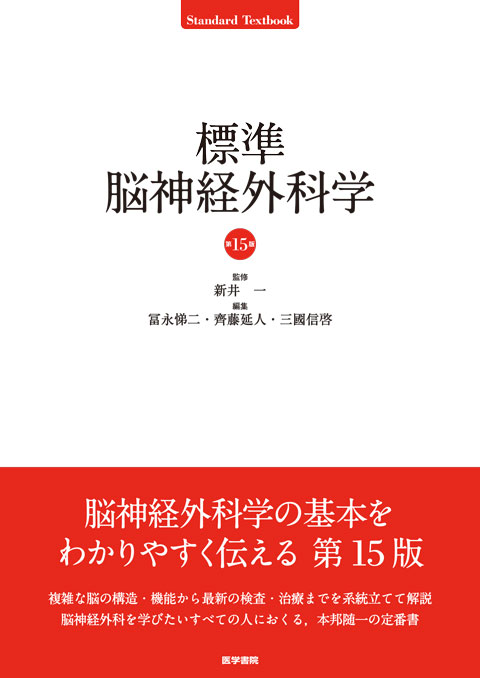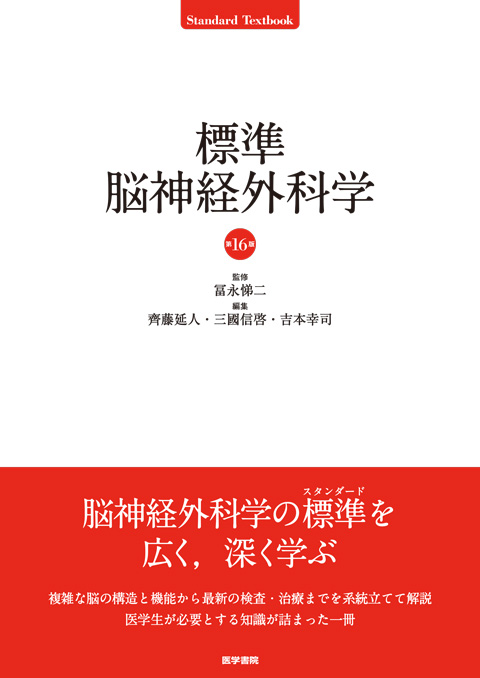標準脳神経外科学 第15版
更新情報
-
正誤表を追加しました。
2022.04.12
- 序文
- 目次
- 正誤表
序文
開く
第15版 序
このたび,『標準脳神経外科学』第15版を出版する運びとなった.編集ならびに執筆に関わっていただいた諸先生に深く感謝申し上げる.
本書の初版は1979(昭和54)年に竹内一夫先生監修のもと刊行されたが,それから40年を超える年月が過ぎたことになる.この間の医療・医学の進歩は目覚ましく,それに関連する情報量も膨大なものになったが,そのなかで医学生が必要とする基本的な知識と日進月歩の最先端の知識のバランスをとり,本書を「標準」的な内容にすることが歴代編集者の腐心したところである.
脳神経外科が医学の1分野として確立してから未だ100年に達しておらず,ほかの分野に比較して歴史は浅いといえるが,一方でその発展はさまざまな技術の進歩と相まって極めて急速に進んだのも事実である.特に,CT(computed tomography)やMRI(magnetic resonance imaging)などをもたらした技術革新は,脳神経外科の有り様を大きく変えたといっても過言ではない.
例えば1975(昭和50)年にわが国に初めて第1号器が設置されたCTは,頭部外傷の診断に威力を発揮し1980年代初頭には全国の病院に広く普及することになったが,さらにその後の機器の機能進化を経て,現在では脳神経外科診療において欠かせない診断法となった.
すなわち,本書の初版が刊行された1979年の時点ではCTは最先端の技術であったが,いまやそれは学生にとっても修得すべき極めて重要な画像診断の基本となっている.このように,基本的な知識と最先端の知識は時代とともに変遷するため,今回の第15版においてはまず現時点で医学生にとって必須の「標準」的な知識をしっかりと述べ,最先端の知識についてはそのエッセンスを紹介するという手法をとった.
現在,わが国における医学教育は大きく変わろうとしている.2001(平成13)年,膨大となった医学の知識と技術の量を整理するとともに,医学・医療に対する社会のニーズの変化に対応し,すべての医学生が履修すべき必要不可欠な教育内容を提示することを目的として,文部科学省主導で医学教育モデル・コア・カリキュラムが制定された.2017(平成29)年には,この医学教育モデル・コア・カリキュラムの3回目の改訂が約6年ぶりに実施された(平成28年度改訂版).そのなかでは「多様なニーズに対応できる医師の養成」がキャッチフレーズとして掲げられ,「社会の変遷への対応」「卒前・卒後の一貫性」が基本理念として盛り込まれた.同時に,「診療参加型臨床実習」の重要性が改めて指摘され,これを充実させ国際的水準を確保することの必要性が喚起された.
卒業時に医師としての基礎的な臨床実践力を身につけるためには,2年間の診療参加型臨床実習に腰を据えて取り組むことが極めて重要になる.現在,臨床実習の内容あるいはその期間について,全国のすべての医学部において一定の水準を確保すべくPost-CC OSCE(post-clinical clerkship objective structured clinical examination)の導入も含めさまざまな取り組みがなされている.このような医学教育の変革期において,医学生に求められているのはpassiveではなくactiveに勉学に励むことであり,教科書はその水先案内の役割を果たさなくてはならないと考える.本書が,医学生諸氏のactive learningの一助となることを強く期待するところである.
最後に,本書の改訂版出版にあたり,並々ならぬ情熱と真摯な態度を積み重ねてこられた医学書院の関係者に深甚なる謝意を表する.
2020年12月
監修・編集を代表して 新井 一
目次
開く
総論
第1章 緒論
A 脳神経外科学の歴史
B 脳神経外科学とは
C 脳の臓器特殊性
D 脳神経外科学の将来
第2章 臨床解剖
A 頭蓋と頭蓋内腔構造
B 髄膜
C 大脳
D 脳幹・小脳
E 脳動脈
F 脳静脈
G 脳室およびくも膜下腔
H 脊柱
I 脊髄
第3章 神経学的検査法
A 患者の診察にあたって
B 神経所見のとりかた
C 脳神経の診かた
D 大脳の局在機能の診かた
E 脳幹の局在機能の診かた
F 小脳の局在機能の診かた
G 脊髄の局在機能の診かた
第4章 補助診断法
A 頭部単純X線撮影
B コンピュータ断層撮影
C 磁気共鳴画像法
D 脳血管撮影・デジタル血管撮影
E 核医学検査
F 脊椎・脊髄の検査
G 神経超音波検査
H 脳波
I 誘発電位
J 腰椎穿刺
第5章 脳に特異な症候と病態
A 頭痛
B 精神症状と認知症
C けいれん(痙攣)
D 意識障害
E 運動麻痺
F 頭蓋内圧亢進
G 脳ヘルニア
H 血液脳関門と脳浮腫
I 脳循環代謝異常
第6章 脳腫瘍
A 脳腫瘍とは
B 脳腫瘍の診断
C 脳腫瘍の鑑別診断
D 脳腫瘍の治療
E 神経上皮性腫瘍
F 髄膜腫
G 下垂体腺腫
H 神経鞘腫
I 頭蓋咽頭腫
J 胚細胞腫瘍
K 脊索腫
L 血管系腫瘍
M 原発性中枢神経系悪性リンパ腫
N 転移性脳腫瘍
O 頭蓋腫瘍と鑑別を要する疾患
第7章 脳血管障害
A 脳血管障害とは
B くも膜下出血
C 脳動脈瘤
D 脳動静脈奇形・その他の血管奇形
E 硬膜動静脈瘻
F 脳内出血
G 虚血性脳疾患(脳梗塞・一過性脳虚血発作)
H もやもや病
I 血管性認知症
J 脳卒中の医療連携およびリハビリテーション
第8章 頭部外傷
A 頭部外傷の臨床
B 重症頭部外傷の治療
C 頭皮の損傷
D 頭蓋骨の損傷
E 脳の損傷
F 急性頭蓋内血腫(急性硬膜外血腫・急性硬膜下血腫)
G 慢性硬膜下血腫
H 脳神経の損傷
I 頭部外傷後の感染症
J 小児頭部外傷
K 頭部外傷による脳血管障害
第9章 先天奇形
A 先天奇形とは
B 神経管閉鎖障害による奇形(1):二分脊椎
C 神経管閉鎖障害による奇形(2):二分頭蓋
D 大脳の奇形
E 後頭蓋窩の脳奇形
F くも膜囊胞
G 頭蓋骨[縫合早期]癒合[症]・狭頭症
H 頭蓋頚椎移行部の奇形
I 神経皮膚症候群
第10章 水頭症
A 水頭症とは
B 小児の水頭症
C 胎児水頭症
D 正常圧水頭症(成人)
E 硬膜下液体貯留
第11章 機能的脳神経外科
A 機能的脳神経外科とは
B 頑痛
C 不随意運動症
D てんかん
E 片側顔面けいれん
F 三叉神経痛
各論
第12章 脊髄・脊椎疾患
A 頚椎変性疾患(変形性頚椎症・頚椎椎間板ヘルニア)
B 脊柱靱帯骨化[症]
C 腰椎椎間板ヘルニア
D 腰部脊柱管狭窄[症]
E 脊髄腫瘍
F 脊髄硬膜外膿瘍
G 脊髄動静脈奇形
H 脊髄空洞症
I 脊椎・脊髄の外傷
第13章 末梢神経の外科
A 末梢神経障害の診断
B 末梢神経の外傷
C 絞扼性末梢神経障害
D 末梢神経の腫瘍
第14章 炎症性疾患
A 中枢神経系感染症とは
B 細菌性髄膜炎
C その他の髄膜炎
D ウイルス性脳炎
E その他のウイルス性脳炎・脳症
F 脳膿瘍
G 硬膜下膿瘍
H 脳寄生虫症
第15章 臨床医学の実習・研修の手引き
A はじめに
B 脳神経外科における実習・研修の心構え
C 医療技術の習得について
D おさえておきたい知識
E まとめ
和文索引
欧文索引
正誤表
開く
本書の記述の正確性につきましては最善の努力を払っておりますが、この度弊社の責任におきまして、下記のような誤りがございました。お詫び申し上げますとともに訂正させていただきます。