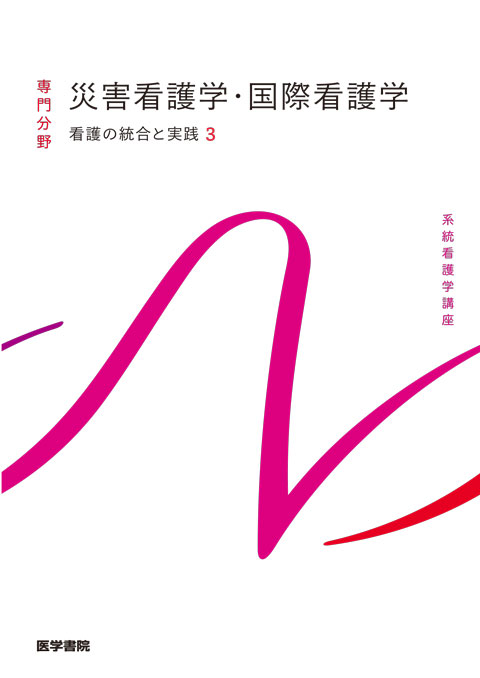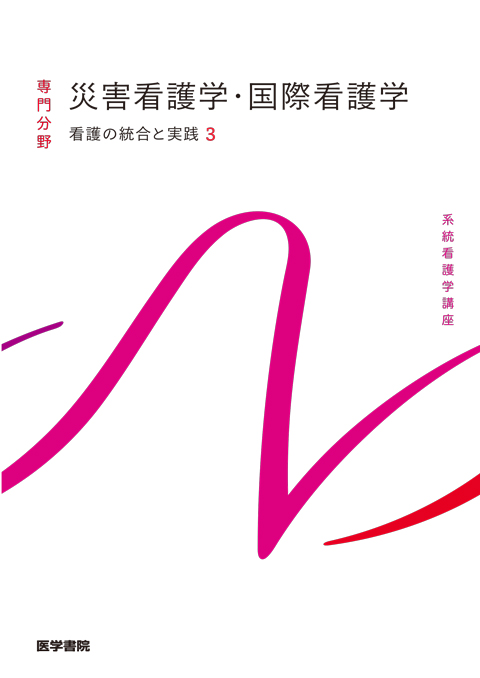看護の統合と実践[3]
災害看護学・国際看護学 第4版
もっと見る
- 今回の改訂では、近年の災害における支援活動の特徴・課題や、国際的な防災・減災の動向など、最新の情報をわかりやすく解説し内容の充実をはかりました。基礎から実践までを網羅し、学生の理解を促す内容となっています。
- 第1章では、看護とグローバリゼーションとの関係に触れたうえで、現代社会における災害看護と国際看護の必要性と関連性について述べています。
- 第2章では、災害医療・災害看護の基礎知識から、災害サイクル別・被災者別に具体的な災害看護の内容を取り上げています。災害時に特有の健康障害やアセスメントの解説を充実させ、また、こころのケアについても述べています。
- 第3章では、地震災害に関する発災直後・急性期・亜急性期・慢性期・復興期、それぞれの看護展開を模擬事例によって紙上演習的に学ぶことができます。
- 第4章の国際看護学は、前版より内容構成や著者陣を一新し、事例を追加してより充実した内容となりました。国際看護学に関する基礎知識から、文化を考慮した看護、開発協力・国際救援における具体的な国際看護の展開までを学べる内容となっています。
- 第5章では、災害看護学・国際看護学における教育・研究に関して留意すべきことについて述べています。
- 「系統看護学講座/系看」は株式会社医学書院の登録商標です。
| シリーズ | 系統看護学講座-専門分野 |
|---|---|
| 編集 | 竹下 喜久子 |
| 執筆 | 竹下 喜久子 / 池田 由美子 / 井 清司 / 宮田 昭 / 奥本 克己 / 白土 直樹 / 小原 真理子 / 内木 美恵 / 亀井 縁 / 東 智子 / 西村 佳奈美 / 金 愛子 / 高橋 清美 / 後藤 智子 / 姫野 稔子 / 小林 裕美 / 中村 光江 / 織方 愛 / 村上 典子 / 東浦 洋 / 菅原 直子 / 髙原 美貴 / 田中 康夫 / 佐藤 展章 / 伊藤 明子 / 関塚 美穂 / 池田 載子 / 堀 乙彦 / 阿部 妙子 |
| 発行 | 2019年01月判型:B5頁:392 |
| ISBN | 978-4-260-03570-5 |
| 定価 | 2,640円 (本体2,400円+税) |
- 2024年春改訂
- 改訂情報
更新情報
-
更新情報はありません。
お気に入り商品に追加すると、この商品の更新情報や関連情報などをマイページでお知らせいたします。
- 序文
- 目次
- 正誤表
序文
開く
はしがき
わが国は,地震や風水害などの自然災害が多発し,被災地の人々は命や健康をそこない,財産を奪われるなど,多くの被害を受けてきた。近代までは,地域の人々のたすけ合いにより,このような災害をしのいできたが,明治期になると,被災地外からの医療従事者や日本赤十字社などの救護団体の救護活動が行われるようになった。
第二次世界大戦後は,災害救助法(1947年)や災害対策基本法(1961年)を制定するなど,国や地方公共団体をはじめとした公共機関の責務を明確にし,防災対策を進めてきた。しかし,本格的・総合的に災害対策が講じられてきたのは,1995年に発生した阪神・淡路大震災を経験したのちからである。災害拠点病院の設置や災害救護チームの育成,医療職者以外の職種やボランティアとの協働などの総合的な対策が講じられてきた。
2011年に発生した東日本大震災では,超急性期・急性期における救護のみならず,慢性期・復興期の支援および静穏期の防災・減災対応の充実が課題となった。また,二次災害となった原子力発電所の事故による放射線被害は,原子力発電所を有する諸外国をはじめ,世界的にも大きな課題をもたらした。
また2016年の熊本地震では,前震・本震という連続する震度7の大きな揺れにおそわれた。屋内での避難生活に不安をいだき車中泊を選択した人も多く,深部静脈血栓症(エコノミー症候群)を発症して死亡した例もみられ,あらためて災害関連死という課題が浮きぼりとなった。
近年,地球温暖化に伴う気候変動などの影響もあり,洪水や土砂災害などの災害の頻度や規模が拡大し,被害も増大している。このような状況の中で,被災傷病者の医療・看護への期待は大きく,看護職者は人々の健康にかかわる看護の専門職として,役割を発揮していくことが求められている。
本書は,看護基礎教育課程において,災害看護を実践できる基礎的能力を身につけるとともに,国際看護における具体的な活動内容を考察することができるように構成した。
グローバリゼーションがますます進展している現在,各国のできごとは,相互に影響を及ぼし合い,けっして1つの国のできごととしてはおさまらない状況にある。まず第1章では,基礎的な理解としてグローバリゼーションと看護の関係を概括するともに災害看護と国際看護の知識が,それぞれの活動において不可分なものであることにふれた。持続可能な開発目標(SDGs)や世界防災会議など,世界的な防災・減災の取り組みについても記述し,また,それぞれの活動の土台となる人道支援の原則についても取り上げている。
第2章は,近年の災害から得られた知見も含めた災害看護学の基礎的な知識を学べるものとした。さらに,看護を実践するために必要なアセスメントについて追記した。
災害時の救護活動は,看護職者だけで行えるものではなく,救護チームとして活動し,国や地域の災害対策にのっとり実施される。したがって,災害活動の法的根拠や,さまざまな職種の人々と協働し,災害時の看護活動を円滑に行うために必要となる災害医療の基礎知識を解説し,今日の課題となっている受援体制についても述べた。
また,災害現場の状況をイメージできるように,災害サイクル別に,活動現場に応じた看護活動を具体的に提示した。とくに,被災者特性に応じた看護の展開を述べるとともに,救援者も含めたこころのケアを具体的に解説した。
第3章では,さらに災害現場を具体的にイメージしながら,看護師がどのように活動していくのかが理解できるように,地震災害を設定した事例を設け,災害看護活動のペーパーシミュレーションを試みた。看護過程の展開の理解のための演習や災害活動演習に活用していただきたい。
第4章では,国際救援ならびに開発協力における看護師の活動を具体的に学べるよう内容をより充実させた。グローバルヘルスや国際協力のしくみ,文化を考慮した看護といった国際看護の基礎知識を学んだうえで,国際看護の展開過程や開発協力・国際救援における具体的な看護活動を紹介し,諸外国との協力をはじめとした国際看護活動を具体的に考察できる内容とした。先進国であるわが国には,保健医療の側面に対しても,国際的に活動することが大いに期待されている。本書での学びを通じて国外へも目を向け,活躍されることを期待している。
最後に第5章では,今後の災害看護学・国際看護学を支え・発展させていくために必要な「教育・研究」に関して概説している。
なお,付録では応急処置や搬送法を動画とともに学べるように工夫した。
本書の執筆にあたっては,より実践的な知識を学べるよう実際の災害状況や国際協力における看護の実際のイメージ化に努め,具体的に解説することを心がけた。看護学生の皆さんにはテキストとして,さらに看護教育施設の教員の方々には救護演習などの場面においても,さまざまな工夫をして活用いただければ幸いである。
また,救護活動の要請が増加している現状において,臨床で勤務しておられる看護師の方々にもご活用いただき,今後想定される大災害に対して,「備え」としていただければ幸甚である。
2018年11月
著者らを代表して
浦田喜久子
わが国は,地震や風水害などの自然災害が多発し,被災地の人々は命や健康をそこない,財産を奪われるなど,多くの被害を受けてきた。近代までは,地域の人々のたすけ合いにより,このような災害をしのいできたが,明治期になると,被災地外からの医療従事者や日本赤十字社などの救護団体の救護活動が行われるようになった。
第二次世界大戦後は,災害救助法(1947年)や災害対策基本法(1961年)を制定するなど,国や地方公共団体をはじめとした公共機関の責務を明確にし,防災対策を進めてきた。しかし,本格的・総合的に災害対策が講じられてきたのは,1995年に発生した阪神・淡路大震災を経験したのちからである。災害拠点病院の設置や災害救護チームの育成,医療職者以外の職種やボランティアとの協働などの総合的な対策が講じられてきた。
2011年に発生した東日本大震災では,超急性期・急性期における救護のみならず,慢性期・復興期の支援および静穏期の防災・減災対応の充実が課題となった。また,二次災害となった原子力発電所の事故による放射線被害は,原子力発電所を有する諸外国をはじめ,世界的にも大きな課題をもたらした。
また2016年の熊本地震では,前震・本震という連続する震度7の大きな揺れにおそわれた。屋内での避難生活に不安をいだき車中泊を選択した人も多く,深部静脈血栓症(エコノミー症候群)を発症して死亡した例もみられ,あらためて災害関連死という課題が浮きぼりとなった。
近年,地球温暖化に伴う気候変動などの影響もあり,洪水や土砂災害などの災害の頻度や規模が拡大し,被害も増大している。このような状況の中で,被災傷病者の医療・看護への期待は大きく,看護職者は人々の健康にかかわる看護の専門職として,役割を発揮していくことが求められている。
本書は,看護基礎教育課程において,災害看護を実践できる基礎的能力を身につけるとともに,国際看護における具体的な活動内容を考察することができるように構成した。
グローバリゼーションがますます進展している現在,各国のできごとは,相互に影響を及ぼし合い,けっして1つの国のできごととしてはおさまらない状況にある。まず第1章では,基礎的な理解としてグローバリゼーションと看護の関係を概括するともに災害看護と国際看護の知識が,それぞれの活動において不可分なものであることにふれた。持続可能な開発目標(SDGs)や世界防災会議など,世界的な防災・減災の取り組みについても記述し,また,それぞれの活動の土台となる人道支援の原則についても取り上げている。
第2章は,近年の災害から得られた知見も含めた災害看護学の基礎的な知識を学べるものとした。さらに,看護を実践するために必要なアセスメントについて追記した。
災害時の救護活動は,看護職者だけで行えるものではなく,救護チームとして活動し,国や地域の災害対策にのっとり実施される。したがって,災害活動の法的根拠や,さまざまな職種の人々と協働し,災害時の看護活動を円滑に行うために必要となる災害医療の基礎知識を解説し,今日の課題となっている受援体制についても述べた。
また,災害現場の状況をイメージできるように,災害サイクル別に,活動現場に応じた看護活動を具体的に提示した。とくに,被災者特性に応じた看護の展開を述べるとともに,救援者も含めたこころのケアを具体的に解説した。
第3章では,さらに災害現場を具体的にイメージしながら,看護師がどのように活動していくのかが理解できるように,地震災害を設定した事例を設け,災害看護活動のペーパーシミュレーションを試みた。看護過程の展開の理解のための演習や災害活動演習に活用していただきたい。
第4章では,国際救援ならびに開発協力における看護師の活動を具体的に学べるよう内容をより充実させた。グローバルヘルスや国際協力のしくみ,文化を考慮した看護といった国際看護の基礎知識を学んだうえで,国際看護の展開過程や開発協力・国際救援における具体的な看護活動を紹介し,諸外国との協力をはじめとした国際看護活動を具体的に考察できる内容とした。先進国であるわが国には,保健医療の側面に対しても,国際的に活動することが大いに期待されている。本書での学びを通じて国外へも目を向け,活躍されることを期待している。
最後に第5章では,今後の災害看護学・国際看護学を支え・発展させていくために必要な「教育・研究」に関して概説している。
なお,付録では応急処置や搬送法を動画とともに学べるように工夫した。
本書の執筆にあたっては,より実践的な知識を学べるよう実際の災害状況や国際協力における看護の実際のイメージ化に努め,具体的に解説することを心がけた。看護学生の皆さんにはテキストとして,さらに看護教育施設の教員の方々には救護演習などの場面においても,さまざまな工夫をして活用いただければ幸いである。
また,救護活動の要請が増加している現状において,臨床で勤務しておられる看護師の方々にもご活用いただき,今後想定される大災害に対して,「備え」としていただければ幸甚である。
2018年11月
著者らを代表して
浦田喜久子
目次
開く
第1章 災害看護学・国際看護学を学ぶにあたって(浦田喜久子・池田由美子)
A 看護とグローバル化した社会
1 グローバル化の影響
2 看護職者に求められるグローバルな視点
B 求められる災害看護学と国際看護学
1 災害看護学と国際看護学を学ぶ意義
2 災害看護・国際看護の原則
第2章 災害看護学(浦田喜久子ほか)
A 災害看護の歩み
1 救護活動としての災害看護のはじまり
2 災害の体験から求められる看護の役割の拡大
B 災害医療の基礎知識
1 災害の定義
2 災害の種類と健康被害
3 災害医療の特徴
4 マスギャザリングとNBC災害への対応
5 災害と情報
6 災害対応にかかわる職種間・組織間連携
7 災害看護と法律
8 近年の災害における課題と対策
C 災害看護の基礎知識
1 災害看護の定義と役割
2 災害看護の対象
3 災害看護の特徴と看護活動
4 災害看護活動に必要な情報
5 災害看護活動におけるアセスメント
6 災害看護場面におけるジレンマ
D 災害サイクルに応じた活動現場別の災害看護
1 急性期・亜急性期
2 慢性期・復興期
3 静穏期
E 被災者特性に応じた災害看護の展開
1 子どもに対する災害看護
2 妊産婦に対する災害看護
3 高齢者に対する災害看護
4 障害者に対する災害看護
5 精神障害者に対する災害看護
6 慢性疾患患者に対する災害看護
7 原子力災害による被災者への看護
8 在留外国人に対する災害看護
F 災害とこころのケア
1 災害がもたらす精神的影響
2 こころのケアとは
3 被災者のこころのケア
4 遺族のこころのケア(グリーフケア)
5 被災救援者のこころのケア
6 救援者のストレスとこころのケア
第3章 地震災害看護の展開(池田由美子)
A 発災直後から出動までの看護
1 災害発生直後の情報
2 出動までの対応
B 急性期の看護
1 出動
2 救護活動の実際
3 はじめての災害救護活動を終えてのまとめ
C 亜急性期の看護
1 災害発生から2週間後の状況
2 出動までの情報
3 救護活動の実際
D 慢性期・復興期の看護
1 災害発生から2か月後の状況
2 出動までの情報
3 救護活動の実際
第4章 国際看護学(東浦 洋ほか)
A 国際看護学とは
1 世界の健康問題の現状
2 国際看護学の定義
3 国際看護学の対象
4 国際看護学に関連する基礎知識
B グローバルヘルス
1 インターナショナルヘルスからグローバルヘルスへ
2 プライマリヘルスケア(PHC)とヘルスプロモーション(HP)
3 人間の安全保障
4 ミレニアム開発目標(MDGs)
5 持続可能な開発目標(SDGs)
6 ユニバーサルヘルスカバレッジ(UHC)
C 国際協力のしくみ
1 国際救援・保健医療協力分野で活躍する国際機関
2 国際救援の調整
3 開発協力
D 文化を考慮した看護
1 文化を考慮した看護理論
2 日本における文化や制度を考慮した在留外国人への看護の実践
E 国際看護活動の展開過程
1 情報収集とアセスメントおよび問題の明確化
2 計画
3 実施
4 評価
F 開発協力と看護
1 開発途上国と看護
2 開発途上国における国際看護の展開
G 国際救援と看護
1 近年の世界における災害と難民・国内避難民の現状
2 国際救援活動の基本理念
3 国際的な災害救援および復興支援にかかるガイドライン
4 近年の特徴的な災害・紛争救援活動の概要
5 国際救援における看護の展開
6 紛争地における看護
7 事例における看護の展開
H 21世紀の国際協力の課題
1 人道危機に対応する新たなしくみの構築
2 これからの国際協力
第5章 災害看護学・国際看護学における教育・研究(内木美恵)
A 災害看護学・国際看護学における教育
1 わが国の災害看護教育の発展と展望
2 国際看護を実践する人材像
B 災害看護学・国際看護学と研究
付録
資料1 応急処置・搬送法(阿部妙子)
資料2 救護装備と診療・蘇生・外科・薬品セット(西村佳奈美)
索引
A 看護とグローバル化した社会
1 グローバル化の影響
2 看護職者に求められるグローバルな視点
B 求められる災害看護学と国際看護学
1 災害看護学と国際看護学を学ぶ意義
2 災害看護・国際看護の原則
第2章 災害看護学(浦田喜久子ほか)
A 災害看護の歩み
1 救護活動としての災害看護のはじまり
2 災害の体験から求められる看護の役割の拡大
B 災害医療の基礎知識
1 災害の定義
2 災害の種類と健康被害
3 災害医療の特徴
4 マスギャザリングとNBC災害への対応
5 災害と情報
6 災害対応にかかわる職種間・組織間連携
7 災害看護と法律
8 近年の災害における課題と対策
C 災害看護の基礎知識
1 災害看護の定義と役割
2 災害看護の対象
3 災害看護の特徴と看護活動
4 災害看護活動に必要な情報
5 災害看護活動におけるアセスメント
6 災害看護場面におけるジレンマ
D 災害サイクルに応じた活動現場別の災害看護
1 急性期・亜急性期
2 慢性期・復興期
3 静穏期
E 被災者特性に応じた災害看護の展開
1 子どもに対する災害看護
2 妊産婦に対する災害看護
3 高齢者に対する災害看護
4 障害者に対する災害看護
5 精神障害者に対する災害看護
6 慢性疾患患者に対する災害看護
7 原子力災害による被災者への看護
8 在留外国人に対する災害看護
F 災害とこころのケア
1 災害がもたらす精神的影響
2 こころのケアとは
3 被災者のこころのケア
4 遺族のこころのケア(グリーフケア)
5 被災救援者のこころのケア
6 救援者のストレスとこころのケア
第3章 地震災害看護の展開(池田由美子)
A 発災直後から出動までの看護
1 災害発生直後の情報
2 出動までの対応
B 急性期の看護
1 出動
2 救護活動の実際
3 はじめての災害救護活動を終えてのまとめ
C 亜急性期の看護
1 災害発生から2週間後の状況
2 出動までの情報
3 救護活動の実際
D 慢性期・復興期の看護
1 災害発生から2か月後の状況
2 出動までの情報
3 救護活動の実際
第4章 国際看護学(東浦 洋ほか)
A 国際看護学とは
1 世界の健康問題の現状
2 国際看護学の定義
3 国際看護学の対象
4 国際看護学に関連する基礎知識
B グローバルヘルス
1 インターナショナルヘルスからグローバルヘルスへ
2 プライマリヘルスケア(PHC)とヘルスプロモーション(HP)
3 人間の安全保障
4 ミレニアム開発目標(MDGs)
5 持続可能な開発目標(SDGs)
6 ユニバーサルヘルスカバレッジ(UHC)
C 国際協力のしくみ
1 国際救援・保健医療協力分野で活躍する国際機関
2 国際救援の調整
3 開発協力
D 文化を考慮した看護
1 文化を考慮した看護理論
2 日本における文化や制度を考慮した在留外国人への看護の実践
E 国際看護活動の展開過程
1 情報収集とアセスメントおよび問題の明確化
2 計画
3 実施
4 評価
F 開発協力と看護
1 開発途上国と看護
2 開発途上国における国際看護の展開
G 国際救援と看護
1 近年の世界における災害と難民・国内避難民の現状
2 国際救援活動の基本理念
3 国際的な災害救援および復興支援にかかるガイドライン
4 近年の特徴的な災害・紛争救援活動の概要
5 国際救援における看護の展開
6 紛争地における看護
7 事例における看護の展開
H 21世紀の国際協力の課題
1 人道危機に対応する新たなしくみの構築
2 これからの国際協力
第5章 災害看護学・国際看護学における教育・研究(内木美恵)
A 災害看護学・国際看護学における教育
1 わが国の災害看護教育の発展と展望
2 国際看護を実践する人材像
B 災害看護学・国際看護学と研究
付録
資料1 応急処置・搬送法(阿部妙子)
資料2 救護装備と診療・蘇生・外科・薬品セット(西村佳奈美)
索引
正誤表
開く
本書の記述の正確性につきましては最善の努力を払っておりますが、この度弊社の責任におきまして、下記のような誤りがございました。お詫び申し上げますとともに訂正させていただきます。
更新情報
-
更新情報はありません。
お気に入り商品に追加すると、この商品の更新情報や関連情報などをマイページでお知らせいたします。