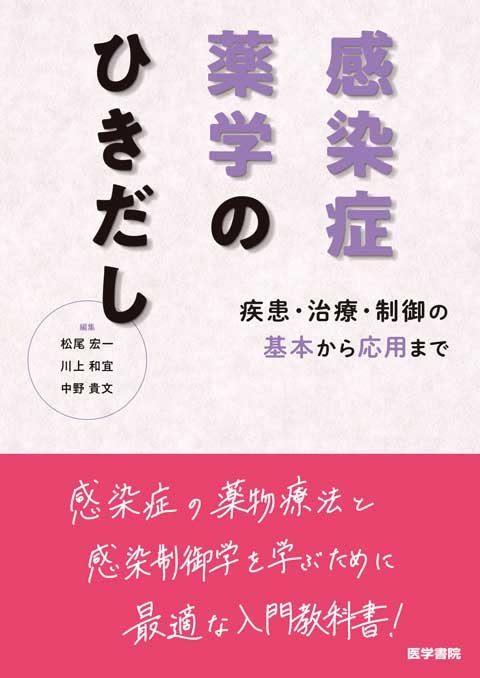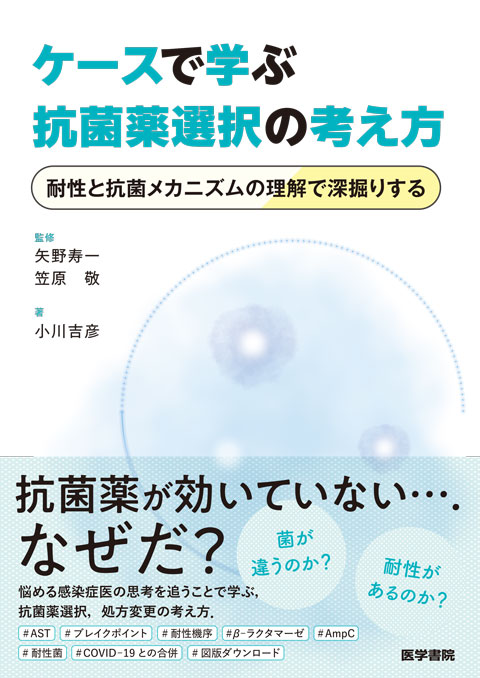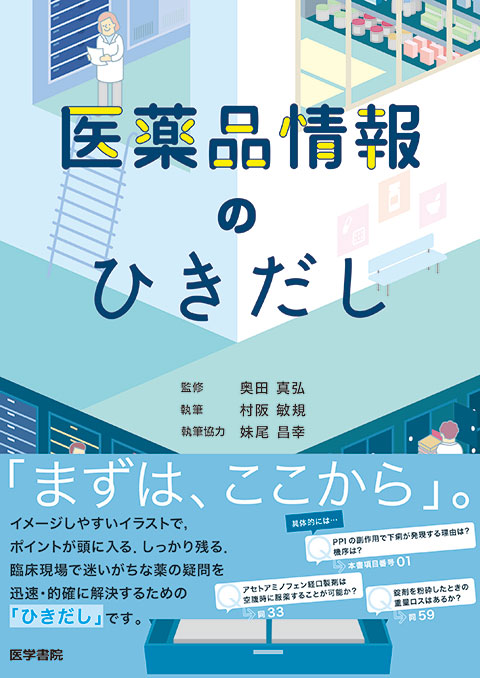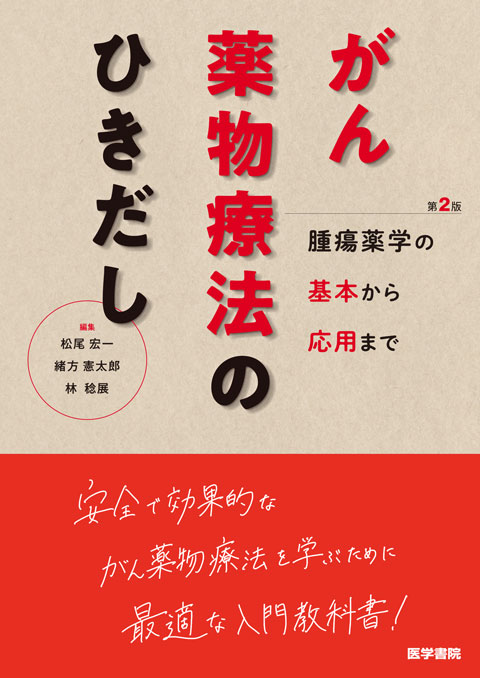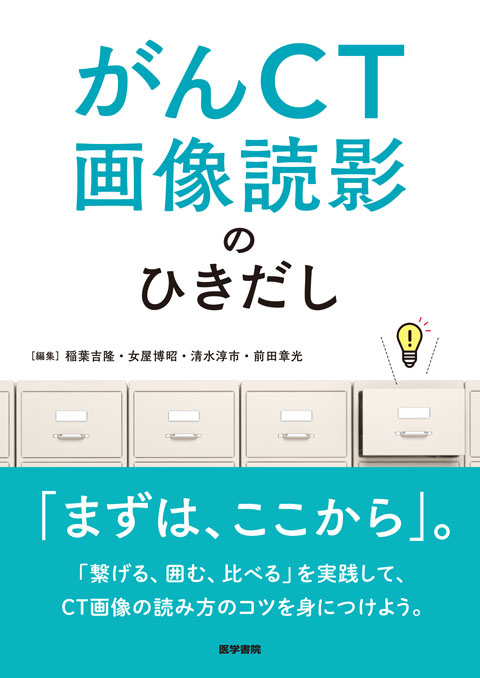感染症薬学のひきだし
疾患・治療・制御の基本から応用まで
「まずはここから」。感染症の薬物療法と感染制御学の入門教科書
もっと見る
若手薬剤師や薬学生に向けて、感染症の薬物療法と感染制御学に必須の知識を解説した教科書。目次は「1.総論」「2.感染臓器・原因微生物からみた感染症」「3.感染症の治療薬」「4.感染制御学」の4つから構成。代謝や病態による薬の使い分けなどの実践的な知識が満載で、各項目の解説が相互につながって理解が深まる。AST(抗菌薬適正使用支援チーム)やICT(感染制御チーム)のメンバーの薬剤師にもぜひ!
更新情報
-
更新情報はありません。
お気に入り商品に追加すると、この商品の更新情報や関連情報などをマイページでお知らせいたします。
- 序文
- 目次
- 書評
序文
開く
序
抗菌薬の不適切な使用によって既存の抗菌薬に耐性菌が生じて大きな問題になっていることは,読者の皆さんもご存じのことでしょう。薬剤耐性菌の感染による死亡者数は,2019年に世界で年間約127万人にのぼります。今後も何も対策を講じなければ2050年には世界で約1000万人が死亡すると推定されています。このような深刻な状況は以前から続いており,2015年にはWHO総会で薬剤耐性に関する国際行動計画が採択され,日本でもこの問題に取り組むため2016年に薬剤耐性(AMR)対策アクションプランが策定されました。また2023年にはさらなる薬剤耐性対策を推進する新たなアクションプランが策定されています。
さて医療現場の感染症対策において,薬剤師は感染制御に関する高度な知識・技術・実践を通じて,その役割を確実に果たしていくことが求められています。薬剤師の感染症対策への関与が,患者にとって安心・安全で適切な治療を受けるために必要な環境をもたらし,さらに感染症治療に関する薬物療法の適切かつ安全な遂行に寄与すると期待されているのです。
本書は薬剤師にとって感染症分野で必要となる知識・技術・実践を基礎からわかりやすく解説し,また抗菌薬や感染症の各種認定制度試験を受験するためのテキストとしても使えるように編纂しました。その特徴は感染症の「疾患」「治療」「制御」の基本から応用まで多岐にわたる内容を1冊で学べることです。
本書を手に取った皆さんが,感染症に関する日常業務の課題や疑問を解決するため,そして自身のステップアップのため,本書『感染症薬学のひきだし』を開いて大いに活用してくださったら編者として望外の喜びです。
2025年3月
編者を代表して 松尾宏一
目次
開く
1段目 総論
1 感染症の基本
2 抗菌薬の選択と適正使用
3 抗菌薬のPK/PD
4 抗菌薬のTDM
5 感染症診断の進め方と検査
2段目 感染臓器・原因微生物からみた感染症
6 呼吸器感染症
A 気道感染症
B 肺炎
C 肺結核
D インフルエンザ
E 新型コロナウイルス
7 消化器感染症
A 急性下痢症
B 腹膜炎
C 胆囊・胆管感染症
D ウイルス性肝炎
8 耳鼻咽喉感染症
A 中耳炎
B 鼻副鼻腔炎
C 耳下腺炎
D 急性咽頭炎・扁桃炎
9 尿路・泌尿器感染症
A 尿路感染症
B 前立腺炎
10 中枢神経系感染症
A 髄膜炎
B 脳炎
C 脳膿瘍
11 皮膚・軟部組織感染症
A 蜂窩織炎,丹毒
B 壊死性筋膜炎
C 動物咬傷による感染症
D 糖尿病性足感染症
12 骨・関節感染症
A 骨髄炎
B 感染性関節炎
13 眼感染症
A 眼瞼感染症
B 涙器感染症
C 結膜炎
D 角膜感染症
14 性感染症
A 性器クラミジア感染症
B 淋菌感染症
C 性器ヘルペス感染症
D 尖圭コンジローマ
E 腟トリコモナス症
F 梅毒
G マイコプラズマ感染症
15 HIV感染症
A HIV感染症
B サイトメガロウイルス感染症
C トキソプラズマ感染症
16 心血管系感染症
A 感染性心内膜炎
B カテーテル関連感染症
17 敗血症
A 敗血症
18 真菌感染症
A カンジダ感染症
B アスペルギルス感染症
C クリプトコックス症(肺クリプトコックス症)
D ニューモシスチス感染症(ニューモシスチス肺炎)
3段目 感染症の治療薬
19 ペニシリン系薬
20 セフェム系薬
21 カルバペネム系薬,モノバクタム系薬
22 マクロライド系薬
23 キノロン系薬
24 アミノグリコシド系薬
25 テトラサイクリン系薬
26 その他の抗菌薬
27 抗MRSA薬
28 抗結核薬
29 抗真菌薬
30 抗ウイルス薬
31 消毒薬
32 ワクチン
4段目 感染制御学
33 感染制御に関する法律,診療報酬,ガイドライン
34 感染制御の院内体制と取り組み
35 感染予防対策
36 院内感染対策
37 洗浄と滅菌
38 医療廃棄物
39 針刺しと曝露対策
付録
A 筋肉注射(ワクチン接種)の方法と注意点
B 感染症と原因菌,対応する抗菌薬
C 予防接種の種類
D 感染症治療薬の略名一覧
E 菌名一覧
索引
書評
開く
感染症治療と感染制御学を実践的・体系的に学べる教科書
書評者:池末 裕明(名大病院薬剤部教授・薬剤部長)
近年,薬剤耐性の問題を考慮した適切な薬物療法や感染制御における薬剤師の役割はますます重要になっており,一層積極的な関与が求められています。本書はそうした時代の要請に応える形で編集され,感染症分野で必要とされる理論と実践を体系的に学ぶことができます。ぜひ多くの薬剤師の方や,感染症治療や感染制御学を学ぶ薬学生に本書を手に取っていただきたく,ご紹介します。
本書は「総論」「感染臓器・原因微生物からみた感染症」「感染症の治療薬」「感染制御学」と大きく4つのまとまり(「ひきだし」のタイトルになぞらえて「段目」)から成り立っています。
・1段目「総論」では,感染症の基本や抗菌薬の選択と適正使用,PK/PDなどの基礎的な内容が網羅されています。
・2段目「感染臓器・原因微生物からみた感染症」では各臓器や原因微生物に焦点を当てた感染症の解説が続き,実際の臨床現場で遭遇する症例に即した知識が盛り込まれています。
・3段目「感染症の治療薬」では,各薬剤の特徴を理解し,代謝や病態による薬の使い分けなどの実践的な知識が満載です。各項目の解説が相互につながっているため,薬剤師としての実践力を重層的に養うことができます。
・感染制御活動を担当する場合は,AST(抗菌薬適正使用支援チーム),ICT(感染制御チーム)の一員として,感染症を専門としていない医療従事者に適切な助言をしたり院内の運用を定めて説明したりするなど,指導的役割が求められます。4段目「感染制御学」の段では,これらの理論的背景もまとめられており,業務を進めていく支えになってくれるでしょう。
さらに各章の構成も工夫されています。最初に要点がまとめられ,その後に解説を読むことで体系的に知識を得ることができます。加えて随所に示された「ステップアップのひきだし」には,専門性をより深めていくためのさまざまな気付きが用意されており,実践力を養うことができます。
ところで臨床現場では救急や悪性腫瘍,循環器領域など,各疾患の薬物療法と感染症治療の両面を十分理解して対応する必要があります。本書では各領域にそれぞれ精通したエキスパートの著者陣がそろい,多様な視点と豊富な経験に基づく実践的知識がまとめられている点も魅力です。
以上,『感染症薬学のひきだし』は感染症薬学の基礎から応用までを網羅した,実践的かつ体系的な教科書であり,薬学生や,感染制御活動を担当している,あるいは認定資格をめざす薬剤師の方など幅広い読者に役立つ一冊と言えます。感染症の薬物療法と感染制御学を学ぶ基礎として,本書を手に取っていただくことを強くお勧めします。
感染対策チーム(ICT)の全職種が共有できるテキスト
書評者:青木 洋介(なゆたの森病院長/前・佐賀大医学部教授)
「学習成果を実社会で発揮するためには,継続的な脳への情報のinputに加え,脳内に蓄えられた知識を適時・適格にoutputすることのできるスキルも同様に不可欠である」(Benedict Carey註):How We Learn――Throw out the rule and unlock your brain’s potential, Random House, 2014)。
この「Input」と「Output」の双方を司るために必要なのが脳の中の“ひきだし”に相当するのではないか。専門家になっていく過程で多くの情報(知識)を修得し,その時点まで培った知識体系の中で意味付けをし,自分の知として咀嚼・収得としたものを系統的に管理するスペースが“ひきだし”である。普段は意識上になくとも,目前の課題に対応するひきだしを開けることで,その場面で必要とされるセオリーや問題解決の糸口を自ら取り出すことができる。優れた専門家は,ひきだしの中身のみでなく,ひきだしの組み方自体も必要に応じて更新し,体系だった思考回路をupdateし,常に実践的であろうと心掛ける。
本書『感染症薬学のひきだし』は,“ひきだし”と名のつくとおり,学習者が知識体系を整理し,機動性を持たせることを支援してくれるテキストである。感染症の総論および疾患各論,抗微生物薬の各論,そして感染制御と,大きな4段のひきだしからなり,感染対策チーム(ICT:infection control team)機能の全体をカバーする構成になっている。全ての各論(1~39)においてサブテーマが記載されており―例えば「26.その他の抗菌薬」の副題は,“使いこなせば便利な名脇役たち”である―,これらが新作映画のキャッチコピーのように,早く中身を見たくなる気持ちにさせてくれる。
いずれの各論も冒頭の「はじめのひきだし」は非常に重要で,後に続く詳細なfactsの学習内容を俯瞰する道標的役割を果たしている。さらに「ステップアップのひきだし」は,最新のトピックスや専門的に特化した知見が紹介されている。これは執筆担当者が重視する事項が何であるかを示しており,同分野にいそしむ自分以外の専門家がひきだしに格納している智恵を知ることにもなり,興味深い。同時に,読者のひきだしの中身も細部にわたり充実することが期待される。
『感染症薬学』と題された本書であるが,感染症の治療薬(3段目)は当然ながら,感染症各論(2段目)の内容も過不足なく記載されている。4段目の感染制御学は図説や写真も多く,施設内感染対策の保守点検に活用することができる。さらに巻末の付録では,予防接種が類別化されており,各ワクチンの接種時期,接種法について丁寧に表記されている。このように,全体を通して本書はとても実用的なものとなっている。
『感染症薬学のひきだし』はICTの全職種が共有できるテキストである。時間をかけてでも皆で読み上げることができれば,チーム力が向上し,個々の患者さんの診療の質向上に十分に貢献できることが期待される。各自の知的“ひきだし”を構築しながら,ぜひ読み進めていただきたい一冊である。編集・編集協力の先生方の手腕に敬意を表したい。
註)ベネディクト・ケアリー(1960年~)はニューヨーク・タイムズの医療・科学担当記者。
現場で実践するために必要な知識や想いが詰まったひきだし
書評者:村木 優一(京都薬科大教授・臨床薬剤疫学)
感染症にかかわる薬剤師の仕事は年々その幅が広がっています。抗菌薬の選択や投与設計にとどまらず,感染制御チーム(ICT)や抗菌薬適正使用支援チーム(AST)の一員として,チーム医療の中で積極的な関与が求められるようになってきました。そんな中で登場したのが,医学書院の『感染症薬学のひきだし』。この本はまさに“現場で使える知識と考え方”をわかりやすくまとめた一冊で,感染症を担当する薬剤師や認定資格をめざす薬剤師,これから現場に出て活躍をめざす薬学生に強くお薦めしたい内容です。
タイトルの通り,「ひきだし」という言葉がしっくりくる構成になっていて,現場でふと迷ったときにパッと開けて使えるツール集のような感覚があります。総論,感染症,治療薬,感染制御というひきだしがあり,例えば,「この抗菌薬の注意点は何だろうか,投与中はどのような点をモニタリングすればよいのだろうか?」など臨床的な疑問が生じた際にすぐに答えにたどり着きやすいよう構成されています。
また,本書の中には,「ステップアップのひきだし」といったトピックス(コラム)が用意されており,初学者だけでなく一歩進んだ知識を身につけたい薬剤師にとっても有益な情報が含まれているのも大きな魅力です。執筆陣には感染症薬学に精通した現場の薬剤師や研究者がそろっており,どの章も読み手のことを考えて熱いメッセージが込められているのを感じます。また,付録には筋肉注射の方法や注意点にも触れられており,文章ではわかりにくい感染症治療薬やワクチン,菌名が表としてまとめられているのも他書とは差別化できている点だと思います。
幅広く感染症治療や感染制御をカバーしているため,ボリュームとしては初学者や薬学生がいきなり全部を理解するのは少し大変かもしれません。でも医療現場で感染症の患者さんや,感染制御が必要な機会に何度も調べながら読み進めることで,確実に一歩先の実践力が身につき,読者が感染症に強い薬剤師として成長するのを後押ししてくれるでしょう。『感染症薬学のひきだし』は,感染症領域で働く薬剤師や学びたい初学者にとって心強い相棒になってくれる本です。デスクの上に置いておきたくなる,そして何度も“ひきだし”を開けて読みたくなる,そんな一冊です。ぜひ手に取ってみてほしいと思います。