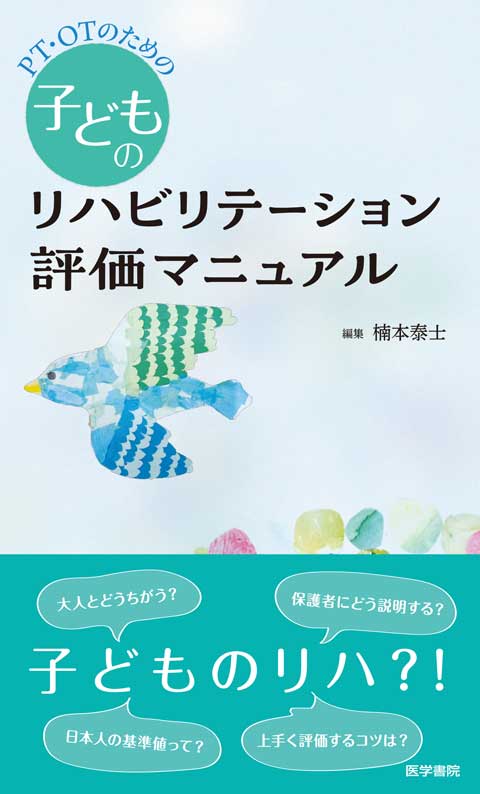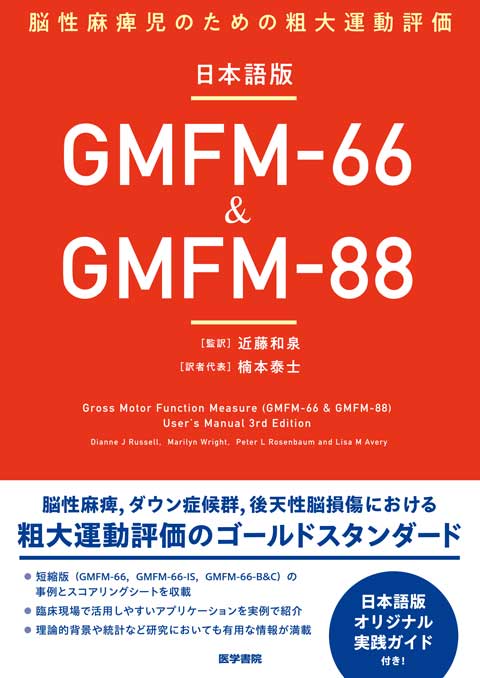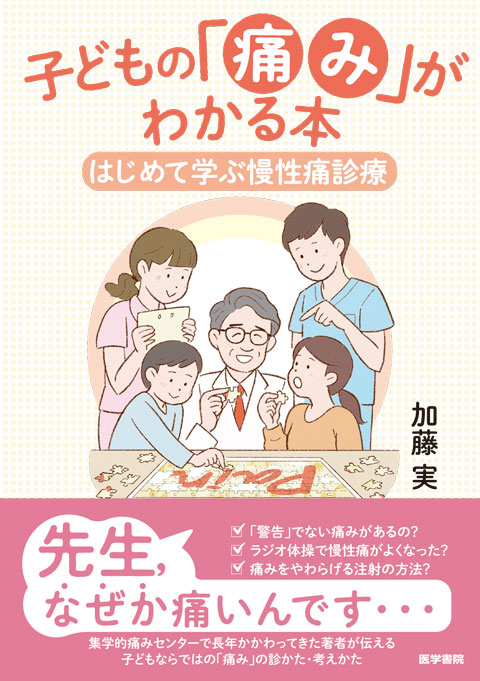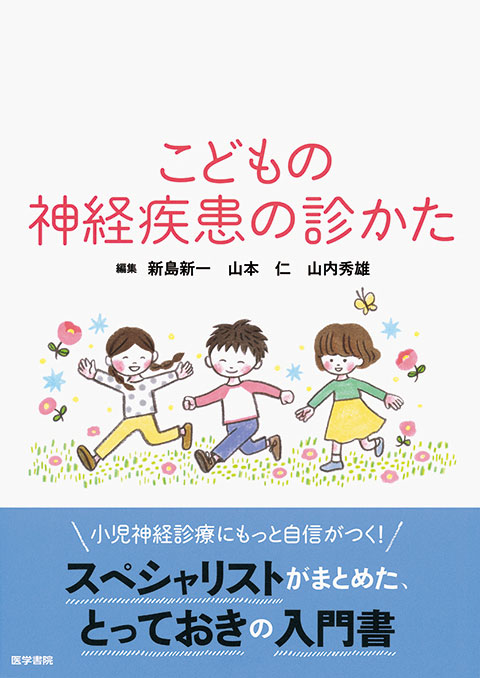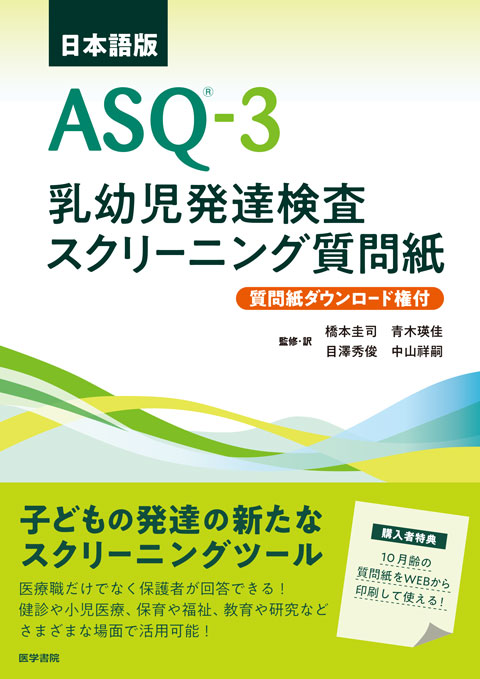PT・OTのための子どものリハビリテーション評価マニュアル
子どもにかかわるPT・OT必携の書
もっと見る
理学療法士、作業療法士が子どもとかかわる際に必要な知識や数値をギュッと1冊に凝縮。機能別と疾患別の2つの視点で、目の前の対象児にどんな評価が必要かが一目瞭然。巻末には、就学支援・就労支援のフローチャートや各種平均値など、保護者や他職種へ説明する際に活用できる資料を付録。さらに、病院、訪問、児童発達支援、学校など、多様な施設間での連携をとりやすくするため、働く場所に応じたポイントも解説。
| 編集 | 楠本 泰士 |
|---|---|
| 発行 | 2025年04月判型:B6変頁:344 |
| ISBN | 978-4-260-05775-2 |
| 定価 | 3,960円 (本体3,600円+税) |
更新情報
-
正誤表を掲載しました
2025.04.11
- 序文
- 目次
- 書評
- 付録・特典
- 正誤表
序文
開く
序
「自分の臨床に自信が持てない」「根拠のある説明をしたい」「説明の際に役立つ資料が欲しい」──これらの悩みは,子どもの医療・療育に携わる専門職の多くが経験するものではないでしょうか.医療やリハビリテーションの情報は日々更新されており,経験だけで臨床を成し遂げるには限界があります.そのため,保護者や保育士,看護師,そして,リハビリテーション専門職が,子どもの成長や発達を支援するために,最新の情報を手軽に確認できる環境が求められています.そのような経緯から,本書は企画されました.
子どものリハビリテーションは,かつては療育センターがその中心的役割を担っていましたが,現在では一般病院,訪問リハビリテーション事業所,児童発達支援事業所,放課後等デイサービス事業所など,専門職が活躍する場が広がっています.成人分野で働いていた療法士が小児リハビリテーションにかかわる機会も増え,セカンドキャリアとしてこの分野を選択する人も少なくありません.リハビリテーションにおいて,さまざまな検査値や評価結果の平均値・基準値は重要な指標です.しかし,多くの基準値は海外のデータであり,日本国内のデータであっても,古いものが使われ続けていることが多く,医療・療育に携わる専門職の間で,情報の統一が十分に図られていないのが現状です.
健常児の基準値は,治療や発達支援の目標設定に活用されます.疾患を有する子どもの値は,発達を促す際の目標や予後予測,介入計画の立案に役立ちます.世の中に流通している情報に対して,「このデータは正しいのか?」「この基準値は最新なのか?」と問い続けることは,すべての医療職や療育スタッフにとって,必要な姿勢だと考えています.常に最新の知識をもとに,子どもの成長や発達を支援できる環境を整えることが,より良い医療や療育の提供につながるのです.
本書では,さまざまな臨床場面の課題を解決するために,子どものリハビリテーションに特化した評価指標や測定値を整理し,実践的な活用方法を提案します.一般家庭でもわかりやすい体格や足のサイズに関する情報,学校で実施される新体力テストなどのデータ,医療機関で使用される生化学データなどを体系的にまとめました.
あらゆる現場で,家族中心的な医療(family centered service)を提供するために,また,複数の不確定な情報を提示する際の意思決定の進め方である共同意思決定(shared decision making)を実施するために,ぜひevidence based medicineをもとにした情報の活用を心掛けていきましょう.
2025年3月
楠本泰士
目次
開く
第1章 子どものリハビリテーションの基礎知識
1 子どもを読み解くヒント
2 子どもの成長と発達
3 子どもの障害のとらえ方
4 測定値の読み方と活用
5 治療に向けて,子どもの将来を見える化,予測するために
6 痙性治療の考え方
7 一般の子ども(いわゆる障害児でない)のリハビリテーションで大切なこと
8 社会福祉制度
第2章 場面別に重要な評価の視点とそのみかた
1 病院
a NICU・PICU
b 観血的な治療前後,外来リハビリテーション
2 訪問事業所
3 児童発達支援事業所
4 療育センター
5 就学支援
6 学校
7 就労支援
第3章 子どもの心身の評価と測定値──基本編
1 身長,体重,BMI(カウプ指数,ローレル指数)
2 足,アーチ,母趾角
3 基礎的なバランス
4 筋緊張と関節弛緩性
5 原始反射
6 血圧,脈拍(心拍)
7 睡眠
8 食事,栄養
9 摂食嚥下機能
10 注意機能
11 視機能
12 視覚情報処理機能
13 知能検査
14 発達検査
第4章 子どもの心身の評価と測定値──臨床編
1 General Movements(GMs)
2 ブラゼルトン新生児行動評価(NBAS)
3 早産児行動評価(APIB)
4 ハマースミス乳児神経学的検査(HINE)
5 血液検査データ
6 生化学検査データ
7 免疫学的検査データ
8 内分泌学的検査データ
9 呼吸
10 血液ガス
11 X線検査
12 脳画像
13 筋力
14 運動耐容能
15 姿勢の評価
16 複合的なバランス
17 協調性
18 随意性
19 上肢の器用さ,運動の質
20 感覚プロファイル(SP)
21 感覚統合機能
22 意志・動機(PVQ)
23 不安
24 抑うつ
第5章 子どもの活動の評価と測定値
1 幼児の運動能力調査
2 新体力テスト
3 一般的な歩行,歩容の一般値
4 医療分野の歩行測定
5 医療分野の移動能力測定(FMS)
6 GMFM
7 総合的な上肢機能(ABILHAND-Kids)
8 ADLの評価(FIM,WeeFIM)
9 ADLの評価(AMPS,School AMPS)
10 総合的な評価
第6章 子どもの参加,背景因子の評価と測定値
1 心理社会的な適応/不適応状態,問題行動
2 家族を中心としたかかわり(MPOC)
3 地域参加(PEM-CY)
4 生活の質(QOL)
5 適応行動
6 社会生活能力
7 得意/不得意(SDQ)
8 作業の評価
9 目標設定
10 読み書きスクリーニング
11 座位保持装置の作製
12 車椅子
13 下肢装具,体幹装具
14 上肢装具
15 福祉用具
16 支援機器
17 就労支援(BWAP2)
第7章 疾患別評価
1 脳性麻痺(CP)
2 神経発達症
3 ダウン症候群
4 筋ジストロフィー
5 二分脊椎
6 脊髄性筋萎縮症(SMA)
7 てんかん
8 先天性心疾患
9 不整脈
10 スポーツ障害
11 脊柱側弯症
12 頸髄症
13 腰痛・腰部脊柱管狭窄症
14 ペルテス病(Legg-Calvé-Perthes病)
15 肥満症
16 1型糖尿病
17 がん
18 小児の高次脳機能障害
巻末資料
1 社会福祉制度
2 就学支援のフローチャート(就学先決定の流れ)
3 就労に関する支援メニューと相談窓口
4 年代別の身長,体重,頭位の基準
5 筋力
6 幼児の運動能力調査
7 新体力テスト
8 代表的な知能検査
9 代表的な発達検査
略語一覧
索引
書評
開く
子どものリハビリテーションに携わるセラピストのポケットに入れておきたい一冊
書評者:加藤 寿宏(関西医大大学院教授・生涯健康科学)
本書は,子どものリハビリテーションに必要な評価がB6変型判のポケットサイズに盛り込まれている(盛り込まれているという表現が適している)。私自身,数多くの子どものリハビリテーション評価を知っていたつもりであったが,本書で初めて知った評価が数多くある。
評価は,対象児を理解するための道具であり,数値を出すこと自体が目的ではない。「はかる」のではなく「わかる」ことが重要である。そのため,多くの評価を並べ,それらの評価を説明するだけの書籍では,実践書としての役割を果たせない。
しかし,本書は,最初に子どものリハビリテーションの基礎知識として,(1)子どもの成長と発達,(2)障害のとらえ方,(3)評価の信頼性・妥当性,(4)評価で算出される数値の意味,など,子どもを評価する上で忘れてはならないことがまとめられている。また,疾患別・場面別の2つの切り口で「評価の特徴やポイント」「使用する代表的な評価方法」もまとめられているため,自身が勤務する病院・施設の役割や対象児の疾患を踏まえた評価の選択に役立つ。
加えて,本書に掲載されている評価には,他書にない特徴がある。姿勢や運動・知能・感覚統合機能などの心身機能やADLを主とした活動の評価だけでなく,「血液,生化学,免疫,内分泌,X線」といったカルテ情報を読み取る上で重要な値,あるいは,「身長・体重,新体力テストの得点」といった臨床で気になったときに知りたい情報が表で示されており,その場ですぐに確認することができる。さらに,地域生活やQOL,適応行動といった子どもの参加・背景因子に関する評価も含まれている。
このように,膨大な量の評価が掲載されているにもかかわらず,これらのほとんどは見開き2ページで簡潔にまとめられている。じっくりと読んで理解するというよりも,対象児を理解するために必要となる評価はどのようなものがあるのかを検索すること(例:協調運動を評価するための検査は何か)や,曖昧な内容を確認するといった使用の仕方に適した書である。常に携帯ができるポケットサイズであることや,表紙がすべりにくいよう加工されていることも,このような使用に適している。より詳しく評価内容が知りたい場合には,原本や文献を探す必要があるが,本書では二次元コードから文献リストを見ることができる。本文を読みながらスマホで文献にアクセスできるため,非常に効率よく臨床に活用できる。
地域へ発展する新時代を見据えた子どものリハビリテーション評価マニュアル
書評者:新田 收(アール医療専門職大リハビリテーション学部学部長)
書籍『PT・OTのための子どものリハビリテーション評価マニュアル』を拝読しました。コンパクトな書籍でありながら,内容は充実したものでした。発達理論をベースとしながら,子どもをどのようにとらえたら良いのかについての解説から始まっています。この点は人間発達学の領域であり,臨床を続けているとふと忘れてしまいそうな,基礎科目ともいえるものです。臨床家を対象とした書籍でありながら,こうした基礎領域をしっかり押さえていることが素晴らしい点です。さまざまな評価は,こうした基礎領域の理解があって,初めて有用な結果を見せてくれます。
続いて,病院,訪問,学校,就労支援といった臨床現場ごとに役割の解説があります。現在,PT・OTの職域は拡大しています。地域や学校で働くPT・OTも増加傾向にあります。しかし,PT・OT養成校の講義で取り上げられる臨床現場は,病院がほとんどであり,地域や学校については,自らの経験を基に講義をすることができる教員が決定的に不足しています。本書は,こうした教育課程における知識を補っています。そして,臨床現場で働くための実践的な視点を提供しています。
本書を編集した楠本泰士先生は,病院で長年勤務した後,大学教員をしながら,地域で子どもとのかかわりを継続しておられます。臨床の大ベテランであり,地域における活動の先駆者です。そして,教育者です。楠本先生が,自らの経験に基づき編集されているので,非常にわかりやすく,現場に即したものとなっています。
書籍の本体は実に幅広い評価法,評価データの解析となっていました。扱う評価データは,バイタル,睡眠,栄養といった基本データを含んでいます。PT・OTがつい見過ごしてしまうようなデータですが,臨床では理解しておかなくてはならない点です。ここまで網羅した解説書は少なく,楠本先生の編集の意図がうかがわれます。
さらに,子どもの心身,活動,参加にかかわる評価が解説されています。項目としては,姿勢,感覚などから,体力,ADL,地域参加といったように,非常に幅広く,それぞれの評価尺度は最新のものが含まれており,しっかりとエビデンスにも触れています。
子どもに関するPT・OTの職場は変化しています。地域に展開する訪問リハ,放課後デイサービスといった,臨床現場に対するニーズは増加しています。短い経験年数,あるいは新卒で,こうした現場に配属されるPT・OTも少なくありません。本書はこうした新人に,またベテランのPT・OTに対しても,知識を確認するための大きな助けになると信じます。ぜひ手に取っていただくことをお勧めします。
付録・特典
開く
本書に関連する表を下記ボタンからご覧いただけます。
p.242 第7章 2. 神経発達症 評価法の一覧
p.282 第7章 18. 小児の高次脳機能障害 表1. 神経心理学的検査
正誤表
開く
本書の記述の正確性につきましては最善の努力を払っておりますが、この度弊社の責任におきまして、下記のような誤りがございました。お詫び申し上げますとともに訂正させていただきます。