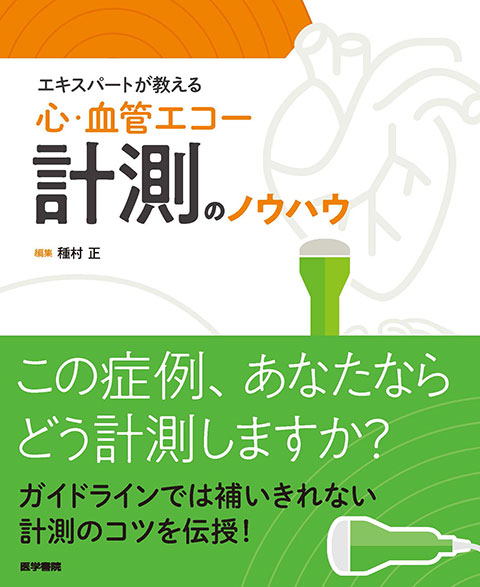心臓疾患のCTとMRI 第2版
更新情報
-
更新情報はありません。
お気に入り商品に追加すると、この商品の更新情報や関連情報などをマイページでお知らせいたします。
- 序文
- 目次
序文
開く
第2版の序
『心臓血管疾患のMDCTとMRI』が2005年に刊行されてからすでに19年が経過した.2005年はちょうど64列CTという革新的な技術が登場し,冠動脈内腔の狭窄や冠動脈壁のプラークの評価という,心臓の非侵襲的画像診断の夢が実現した時期であり,その後日本では欧米と比較しても急速に心臓CTが普及した.また,心臓MRIの分野では,シネMRIやblack blood T2強調画像などは2000年以前から利用可能であったが,遅延造影MRI,負荷心筋パーフュージョンMRI,whole heart coronary MRAなどはこの時期に臨床利用が可能となった撮影法である.振り返ってみると,2005年には冠動脈CTが今とほぼ同じように行われていたし,現在三重大学で実施されている心臓MRI検査プロトコールは,T1マッピングを除いて2005年当時と実はあまり変わっていないことに気づく.
もちろん,その後も心臓の非侵襲的画像診断法は著しく進歩し,心臓CTではarea detector CTや2管球CTが開発され,撮影速度や画質が大きく向上し放射線被曝も低減した.また,心筋遅延造影CTや心筋パーフュージョンCT,FFR-CTなどの技術開発によって,虚血を含む機能や組織性状の評価が可能になった.また,MRIについてはT1,T2マッピングによる定量的評価や4D-flowなどの新しい撮影が可能になり,compressed sensingやdeep learningによる撮影高速化と高画質化が進んだ.
こうした心臓の非侵襲的画像診断法の技術的進歩は大きな臨床的インパクトを与えたわけであるが,それよりも過去19年間の変化として最も注目すべきは,数多くの多施設研究やメタ解析によって心臓CTやMRI検査の有効性に関するエビデンスの蓄積が進み,さまざまな心疾患のガイドラインにおいて,心臓CTやMRIの役割が飛躍的に高まったことである.慢性冠動脈疾患の冠動脈CTは,検査前確率が5~85%と非常に幅広い患者において第一選択の検査法となった.また,T1,T2マッピングを含む心臓MRI検査は,心アミロイドーシスや心筋炎など,数多くの心疾患の診断に不可欠の診断法となっている.このように,心臓CTやMRIは,大学病院やハートセンターなどで必要となるやや特殊な画像診断検査から,一般病院であればどこでも必要に応じて実施すべき画像診断検査へと,その役割が大きく変化している.しかし,多くの医療機関において,特に心臓MRIは必要に応じて気軽に放射線科に検査依頼できる画像診断検査とはなっておらず,循環器医療のニーズに応えられていないのが現状である.
本書では,心臓血管領域におけるCTとMRIの検査に必要な解剖と撮影断面,撮影法の基礎と実践,画像解析と表示法,画像診断の適応となる疾患の基礎と読影のポイント,ガイドラインにおける役割等について,放射線科と循環器診療科のエキスパートに詳細に解説していただいた.本書が循環器医,放射線科医,放射線技師をはじめとする皆さんに活用され,日本における心臓CTとMRIの利用の拡大と診療の質の向上につながればと願っている.
2024年8月
佐久間 肇
目次
開く
心臓の解剖
1 心臓のcross sectional anatomy
A 横断像
1 肺動脈弁レベル
2 左冠動脈起始部レベル
3 右冠動脈入口部レベル
4 大動脈弁レベル
5 左室流出路レベル
6 房室弁(三尖弁,僧帽弁)レベル
7 冠状静脈洞レベル
8 左心室下壁レベル
9 後室間溝レベル
B 冠状断像(coronal像)
C 矢状断像(sagittal像)
D 左室短軸断面
E 左室長軸断面
F 四腔断面
G 三腔断面
2 冠動脈・心筋のセグメント分類
A 冠動脈
1 冠動脈のセグメント分類(AHA分類)
B 心筋
1 心筋のセグメント分類
C 冠動脈の心筋への支配領域
3 心臓弁
A 房室弁(三尖弁,僧帽弁)
1 三尖弁
2 僧帽弁
B 動脈弁(大動脈弁,肺動脈弁)
1 大動脈弁
2 肺動脈弁
撮影編
1 CT
A 撮影法と画像再構成法
1 冠動脈CT
2 検査法の最近の進歩
3 心筋パーフュージョンCT
4 遅延造影CT
[コラム]dual-energy CTによる心筋評価
B ポストプロセッシング
1 冠動脈評価
2 FFR-CT
3 心筋評価(心筋パーフュージョンCT,遅延造影CT)
4 心機能と局所壁運動異常の評価
2 MRI
A 撮影法とポストプロセッシング
1 ベーシックパルスシーケンス
2 シネMRI
3 T2強調画像
4 心筋パーフュージョンMRI
5 遅延造影MRI
6 マッピング(T1,ECV,T2,T2*)
7 血流計測(2D位相コントラストMRIを中心に)
8 冠動脈MRA
9 心筋ストレインイメージング
B 撮影法の最近の進歩
1 心臓領域の高速イメージング
2 4D flow MRI
3 検査の安全性
A 検査に用いられる薬剤
1 CT造影剤
2 MRI造影剤
3 その他
B 心臓CTにおける放射線被曝
1 CTにおける放射線量の評価法
2 心臓CTにおけるCTDIおよびDLP
3 心臓CTの被曝による人体影響
4 心臓CTにおける被曝対策
C MRIの安全性
1 MRIの安全性に関する考え方
2 MRI検査における適応の判断
3 体内金属やデバイスに関する留意点
4 条件付きMR対応CIEDs植込み患者への対応
疾患編
1 慢性虚血性心疾患
A 概念と治療法の変遷
1 治療の目標
2 生命予後改善のための最適な診断・治療
3 症状改善のための最適な診断・治療
[コラム]ACSとCCS
B CT,MRIの適応とプロトコール
C 冠動脈
1 狭窄評価
①CT
[コラム]ブリッジ
②MRI
2 冠動脈プラークの評価
①CT
[コラム]dual-energy CTによるplaque characterization
[コラム]advancement in perivascular fat attenuation
②MRI
3 PCI後の評価
4 冠動脈バイパスグラフト後の評価
5 石灰化スコアの意義
D 虚血と心筋バイアビリティの評価
1 虚血評価の意義,予後予測
[コラム]ISCHEMIA試験をどうとらえるか
①CT
②FFR-CT
[コラム]HeartFlow® Planner
[コラム]workstation based computational fluid dynamics
③MRI
[コラム]STICHトライアルと心筋バイアビリティ
④局所壁運動
E グローバルMPRと心筋血流定量計測の重要性
1 心筋血流予備能と冠血流予備能
2 グローバルMPRを評価する意義
3 位相コントラストシネMRIによるグローバルCFRの計測
4 心筋血流定量計測の重要性
[コラム]INOCA
2 急性虚血性心疾患
A 概念と治療法の変遷
B 適応とプロトコール
C PCI後評価としてのMRI
1 心臓MRIによる急性心筋梗塞の評価
2 心筋浮腫,“area at risk”,心筋salvageの評価
3 梗塞サイズと心筋バイアビリティの評価
4 microvascular obstructionと心筋内出血
5 T1/T2マッピングによる組織性状評価
D MINOCAの評価
3 心筋疾患
A 概念と治療法の変遷
B 適応とプロトコール
C 拡張型心筋症
[コラム]LVNCは疾患か?
D 肥大型心筋症
E たこつぼ心筋症
F 不整脈原性右室心筋症〔ARVC(ARVD)〕
[コラム]NDLVC
G 心筋炎
[コラム]COVID-19と心筋炎
H 心臓サルコイドーシス
I 心アミロイドーシス
1 疾患概念
2 画像診断
J Fabry病
K 筋ジストロフィー
1 概念
2 各論
L 全身疾患の心臓involvement
1 全身疾患と心臓障害
2 心臓障害が生じ得る代表的な全身疾患
M onco-cardiology
4 心膜疾患
A 適応とプロトコール
B 心膜疾患
5 構造的心疾患
A 概念と治療法の変遷
B 経カテーテル大動脈弁留置術(TAVI)
C 経カテーテル僧帽弁置換術(TMVR)
D 経皮的左心耳閉鎖術(LAAO)
6 心不全
A 概念と治療法の変遷
B MRIの役割(HFrEF,HFpEF)
C CTの役割
7 右心系・肺循環
A 概念と治療法の変遷
B 右室負荷と右室不全の評価
C 慢性血栓塞栓性肺高血圧症(CTEPH)
D 右心系の血流動態評価
8 先天性心疾患
A 概念と治療法の変遷
B 適応とプロトコール
C 小児先天性心疾患
D 成人先天性心疾患
E 冠動脈奇形
9 川崎病冠動脈病変
A 概念と治療法の変遷
B 適応とプロトコール
C 川崎病
[コラム]冠動脈周囲炎
10 心臓腫瘍
A 頻度と分類
B 適応とプロトコール
C 心臓腫瘍
1 心腔内血栓
2 心膜囊腫
3 悪性リンパ腫
4 未分化肉腫
5 粘液腫
6 脂肪腫
7 線維腫
8 乳頭状線維弾性腫
9 血管腫
10 血管肉腫
11 転移性腫瘍
11 心外病変
A 心臓CT,MRIで遭遇する偶発所見
1 大動脈疾患
2 肺病変
3 縦隔病変
4 乳腺疾患
5 胃・食道病変
6 肝臓・胆囊・膵臓病変
7 心外病変評価のための費用対効果
索引


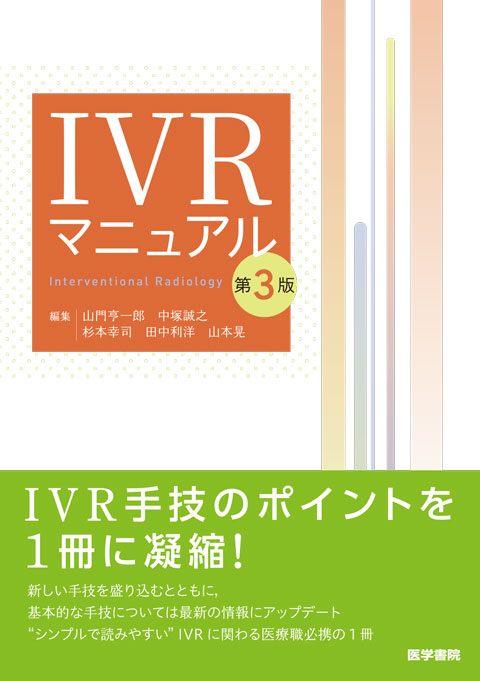
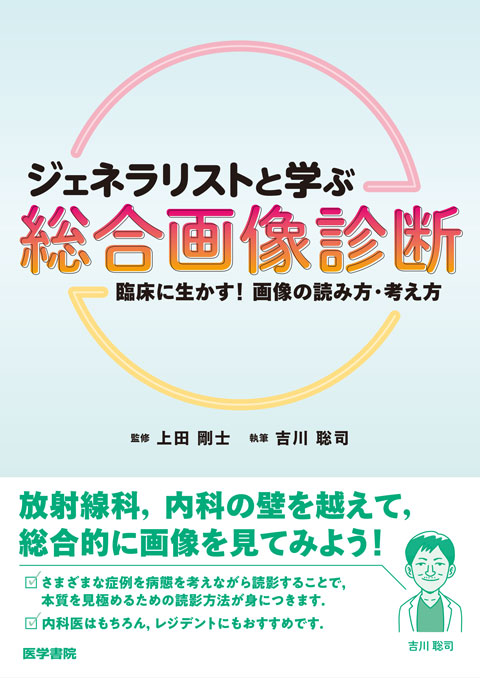
![救急超音波診療ガイド[Web動画付]](https://www.igaku-shoin.co.jp/application/files/1017/0063/3188/113479.jpg)