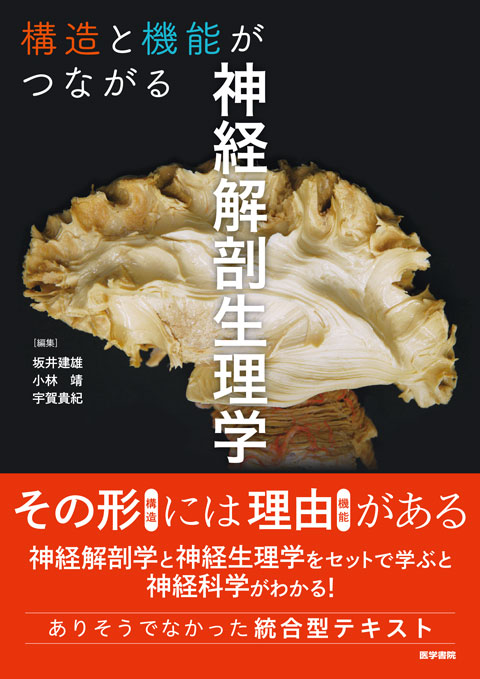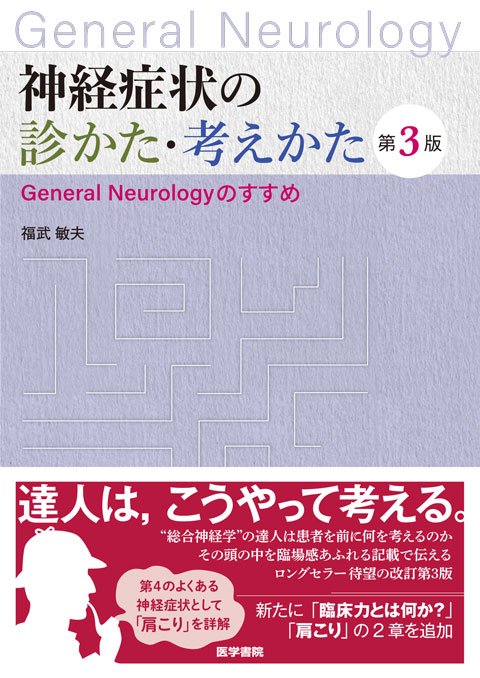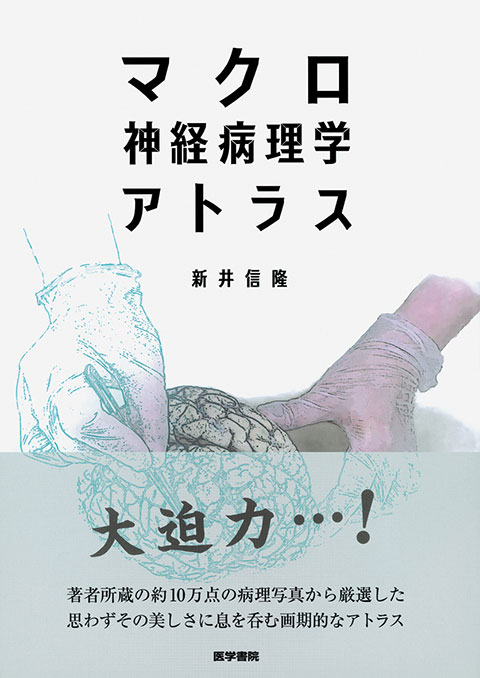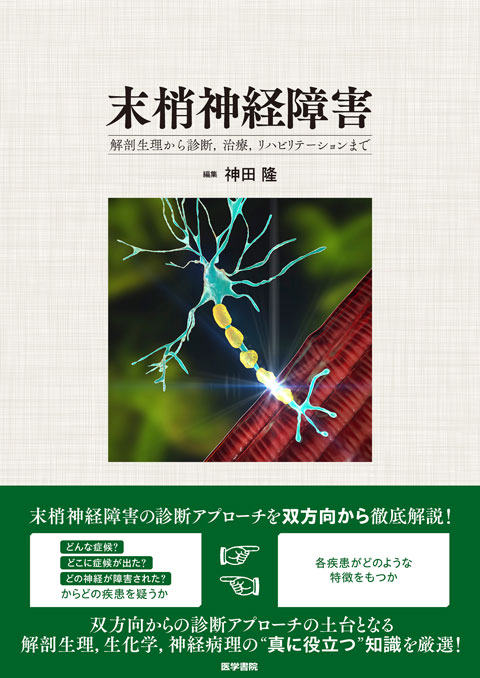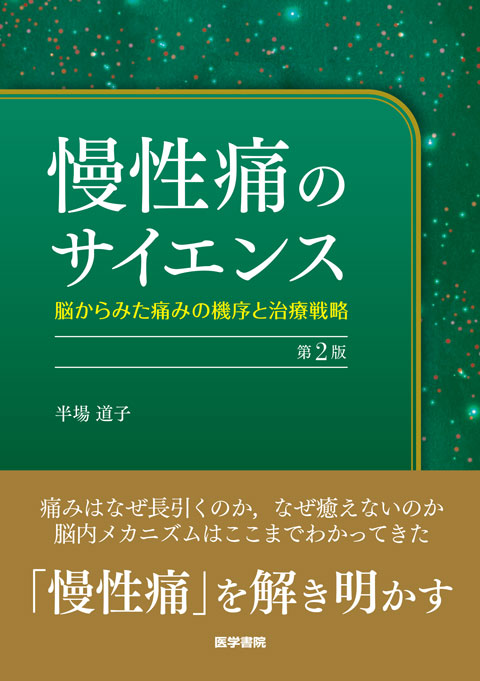構造と機能がつながる神経解剖生理学
その形(構造)には理由(機能)がある。ありそうでなかった統合型テキスト
もっと見る
神経解剖学と神経生理学をセットで学ぶと、神経科学がわかる! 神経の構造(解剖学)と機能(生理学)を1項目見開き2ページで解説。解剖学、神経解剖学、神経生理学のスペシャリストによる解説が有機的に連携し、知識が重層的に統合されていくダイナミズムを体感できる。さらに、運動機能や高次脳機能の障害については、臨床のスペシャリストがそのメカニズムを解き明かす。学ぶ楽しさを実感できる1冊。
更新情報
-
正誤表を更新しました
2025.12.18
-
正誤表を掲載しました
2025.04.21
- 序文
- 目次
- 書評
- 正誤表
序文
開く
序
神経科学 neuroscienceは,現代の医学・生物学の中で最も活発な研究領域である.さらに人間の心理・認知・行動を通して現代社会のあり方や政治・経済などにも関わり,医学・生物学の枠を越えた学際的な広がりをもつ.しかし,そのような現代の神経科学を,医療系学生が初歩から学ぶための適切なカリキュラム,あるいは教科書というものがどうにも見当たらない.脳の構造を教える「神経解剖学 neuroanatomy」の教科書はいくつもあるが,脳の機能を探究する「神経生理学 neurophysiology」と必ずしもうまく結びついていない.脳の構造と機能を有機的に結びつけて学ぶこと,これこそが現代の神経科学を医療系学生が学ぶための王道ではないだろうか.
神経解剖学は,神経系の臨床医学(脳神経内科学,脳神経外科学)を学ぶための基礎という一面ももっている.かつて,脳の病変部位は神経症状から推理するしかなく,伝導路や神経核に関する詳細な解剖学の知識が求められていた.脳内での脳血管の詳細な走行を理解しておくことは,脳血管障害の診断・治療に必須である.しかし,1990年代以降の医用画像(CT,MRI)の飛躍的な発展により,脳病変や脳血管の走行が生体において可視化されるようになってきた.神経解剖学のミッションは,もはや脳の構造や脳血管の走行の詳細を学ぶことだけではなく,それを脳の機能といかに結びつけるかに変わらなければならない.近年,欧米の神経解剖学の教科書には,機能との結びつきを重視したものもいくつか出版されており,一部は日本語にも訳されているが,脳の構造を扱う神経解剖学と,脳の機能を扱う神経生理学を有機的に結びつけた教科書は,まだ目にしたことがない.
解剖学,生理学,生化学といった学問分野の垣根は次第に消えつつあり,現代の医学・生物学研究はあらゆる研究手法を総動員して行われる.医学教育モデル・コア・カリキュラムでは,科目別の授業ではなく,臓器別の統合型授業が推奨されている.しかし,大学の組織においても,また医学系の学会においても,学問分野が確実に生き残っている.そもそも学問分野とは,それぞれの教師・研究者が得意とする教育・研究のアプローチであり,人体と病気を探究するための基盤である.その基盤の上に,学問分野の枠を超えた連携を通して,総合的な理解がはじめて可能になる.私はこれまで多分野の執筆者を集めて統合型の教科書をいくつか編集・執筆してきたが,その経験からも学問分野を超えた共通の理解や協力をすることが,並大抵ではない難事であることを実感してきた.神経解剖学の専門家と神経生理学の専門家が協力して統合的な神経解剖生理学という教科書を実現することは,容易なことではないのである.
本書『構造と機能がつながる神経解剖生理学』は,神経解剖学と神経生理学の卓越した研究者である小林靖氏と宇賀貴紀氏を,私が個人的にもよく知っていたことで実現可能となった.私が本書のグランドデザインを描き,3人の間の緊密な協力を土台に,得意分野を分担して執筆することで,この良質の神経解剖生理学の教科書がはじめて誕生した.全頁をフルカラーの見開き構成にしたこと,最後の第8章では臨床の専門家も加えて精神医学領域を含む脳の高次機能障害を扱ったことは,現代の神経科学を視野に入れた本書の価値を大いに高めてくれたと思う.専門家としてのこだわりのある著者たちの間を巧みに調整し,本書を完成に導いてくれた医学書院の金井真由子氏の献身的な努力に深く感謝したい.
2024年8月
編者を代表して 坂井建雄
目次
開く
第1章 神経系の概観──マクロ解剖学
1.神経系の構成
1.神経系は,中枢神経系と末梢神経系からなる
2.末梢神経は,中枢神経からの情報を全身に伝える
2.脊髄神経
3.脊髄神経は脊柱管から椎間孔を通って出ていく
4.脊髄神経の前枝は身体の大部分に,後枝は背部のみに分布する
5.頸神経叢の枝は,頸部の皮膚・筋と横隔膜に分布する
6.腕神経叢の枝は上肢に分布する
7.腕神経叢の前方の枝は屈筋に,後方の枝は伸筋に分布する
8.腰神経叢の枝は,下腹部から大腿前面に分布する
9.仙骨神経叢の枝は,殿部~大腿後面と下腿~足に分布する
3.脳神経
10.脳神経は,支配領域の発生学的起源から3つに分けられる
11.嗅覚・視覚・聴覚は,特殊感覚である
12.眼球と舌を動かすのは,体性運動神経である
13.第1鰓弓から,三叉神経ができる
14.第2・3鰓弓から,顔面神経と舌咽神経ができる
15.第4~6鰓弓から,迷走神経と副神経ができる
4.自律神経
16.内臓と血管は交感神経と副交感神経により二重に支配される
17.交感神経は内臓・血管と体壁の両方を支配する
18.自律神経は伝達物質によって作用する
第2章 神経系の細胞生物学──ミクロ解剖学
1.神経系の細胞
1.神経系の細胞には,ニューロンと支持細胞がある
2.グリア細胞はニューロンの活動環境を整える
3.髄鞘が神経線維を取り巻く
2.細胞膜の興奮性
4.ニューロンは電気を帯びている
5.興奮は,Na+による活動電位によって運ばれる
3.興奮の伝達
6.シナプスでは,化学信号を伝える
7.シナプスの強さは,学習によって変わる
8.伝達物質は,受容体に働いてさまざまな反応を起こす
第3章 中枢神経
1.中枢神経の発生と区分
1.神経管から脳と脊髄が形成される
2.末梢神経は神経堤からも作られる
3.脳は,大脳・間脳・小脳・脳幹に分けられる
2.脊髄
4.脊髄は,脊柱管の中に位置する
5.脊髄の後根から感覚性入力,前根から運動性出力がある
6.脊髄には単純な反射回路や歩行プログラムがある
7.脊髄損傷の症状は損傷部位によって異なる
3.脳幹:延髄,橋,中脳
8.脳幹は中脳・橋・延髄からなる
9.脳幹の脳神経核は支配器官の性質によって分かれている
10.伝導路には上行性と下行性があり,その多くが脳幹か脊髄で対側に交叉する
11.脳幹は生命維持と脳活動レベルの調節に関与する
4.視床と視床上部
12.間脳は松果体,視床,視床下部などからなる
13.視床は大脳皮質へ入る情報の中継点である
14.視床が障害されると感覚障害や疼痛が生じる
5.視床下部と下垂体
15.視床下部には多数の小さな神経核があり,個体と種の維持に関わる多様な機能を営む
16.下垂体は前葉と後葉でホルモンの種類と分泌機構が異なる
17.視床下部ホルモンは内分泌系の最上位に位置する
18.下垂体前葉ホルモンは他の内分泌腺の機能を調節する
6.辺縁葉と辺縁系
19.嗅脳を含む辺縁葉は視床下部と深く関わる皮質である
20.海馬はエピソード記憶の形成に重要である
21.扁桃体は情動反応とその記憶に重要である
7.小脳
22.小脳には皮質と小脳核があり,機能的に3つに区分される
23.小脳皮質には精密な神経回路が存在する
24.小脳は脳幹の神経核や視床を介して他の領域に影響を及ぼす
8.大脳基底核
25.大脳の深部に大脳基底核がある
26.大脳皮質と大脳基底核のループは適切な運動の選択を行う
9.大脳の皮質と髄質
27.大脳の表面には新皮質が広がり,6つの葉に分かれる
28.大脳皮質の層構造は部位によって異なり,その領域の機能を反映する
29.大脳皮質の各領野は異なる機能を担う
30.連合野はさまざま情報を統合し,高次機能を営む
31.大脳髄質は3種類の線維で大脳皮質を各部につなぐ
10.頭蓋腔と脳
32.脳と脊髄は3重の髄膜で包まれる
33.髄液は中枢神経系を保護している
34.脳脊髄液の過剰や減少によって,脳の機能が障害される
35.脳の血液は内頸動脈と椎骨動脈によって供給される
36.頭蓋腔の容積と脳の血流量は一定に保たれている
37.脳の循環障害は,突然発症する
第4章 感覚機能
1.感覚機能の概観
1.頭部で特殊感覚を,全身の体壁で体性感覚を感知する
2.感覚は受容細胞で感知され,求心性神経を通って脊髄,脳幹に伝えられる
2.体性感覚
3.体性感覚は,皮膚と運動器の受容器によって生じる
4.体性感覚の受容器は,種類によって特性が異なる
5.体性感覚は,対側の大脳皮質の感覚野に伝えられる
3.視覚
6.眼球壁は3層構造であり,光は5つの透明構造物を通って網膜に達する
7.網膜には,2種類の視細胞と4種類の神経細胞が3層に配置されている
8.色と明暗を感知する2種類の視細胞の配置により,視覚の特性が決まる
9.眼球は水晶体の厚さを変えてピントを調節し,調節機能の障害などにより疾患を生じる
10.視覚情報は,視覚伝導路を経て大脳皮質の一次視覚野に伝えられる
11.大脳皮質の一次視覚野は,6層のカラム構造で情報処理を行う
12.視覚の情報処理は一次視覚野の単純型・複雑型細胞へと引き継がれる
4.聴覚と平衡感覚
13.耳は外耳,中耳,内耳から構成され,内耳では聴覚と平衡感覚を感知する
14.基底板の部位によって,音の高さが識別される
15.音波は,有毛細胞の感覚毛の揺れによって電気信号に変換される
16.有毛細胞からの信号は,大脳皮質の聴覚野に伝えられる
17.ヒトの聴力は,会話に使用する周波数で高い
18.前庭(耳石器)の平衡斑では直線加速度を,半規管では回転加速度を感知する
19.平衡感覚は,身体の姿勢と眼球の向きを制御する
5.嗅覚と味覚
20.嗅細胞は,感覚ニューロンでもある
21.味細胞は,5つの基本味を感知する
第5章 運動機能
1.運動機能の概観
1.脊髄前角にある運動ニューロンの神経終末が,骨格筋細胞とシナプスを形成する
2.身体部分の位置や力についての固有感覚は,姿勢・運動の制御に関わる
3.運動機能は,複数の中枢により階層的に制御される
2.下位脳による運動制御
4.脊髄は下位運動中枢で,脊髄反射の中枢である
5.姿勢や歩行運動は,下位運動中枢が制御する
6.よく見えるように眼球を動かすのは脳幹である
3.大脳皮質からの運動指令
7.大脳皮質からの運動指令は錐体路を通って脊髄に伝えられる
8.随意運動の指令は大脳皮質の一次運動野から送られる
9.環境と身体の感覚情報を用いて,適切な随意運動が実現される
10.小脳は,感覚情報と運動指令を統合し,的確な運動を実現する
11.大脳基底核は,必要な運動と不必要な運動を選別する
4.運動機能の障害
12.錐体路を損傷すると,随意運動ができなくなる
13.小脳の損傷によって運動失調が起こる
14.大脳基底核の損傷によって不随意運動や筋緊張の異常が起こる
15.神経可塑性によって運動麻痺を回復することができる
第6章 生命維持に関わる中枢機能
1.生命の維持と意識水準
1.視床下部による内臓機能の調節は生命維持に不可欠である
2.睡眠と覚醒の切り替えには脳幹と視床下部が関与する
2.本能と意欲
3.視床下部は自律神経と本能行動の中枢である
4.辺縁系は感情と情動の中枢だけではない
5.報酬系は行動の結果を判定し,ドパミン神経は,報酬予測誤差情報を伝える
第7章 脳の高次機能
1.認知機能
1.視覚情報は,背側と腹側の連合野に至る
2.概日リズムは視床下部で作られ,時間の感覚は大脳皮質・小脳・大脳基底核で形成される
3.意思決定とは,複数の選択肢を1つに絞るプロセスである
4.前頭前野は,柔軟な判断に必要である
2.言語機能
5.左脳のウェルニッケ野の損傷により,感覚性失語が起こる
6.左脳のブローカ野の損傷により,運動性失語が起こる
3.学習と記憶
7.意識にのぼる長期記憶には,エピソード記憶と意味記憶がある
8.海馬は,陳述記憶の形成に不可欠である
9.手続き記憶には,大脳基底核と小脳のループ構造が関わる
4.中枢機能の差異
10.性ホルモンは脳を分化させ,固有の性行動を引き起こす
第8章 脳の高次機能障害
1.高次脳機能障害は,脳の損傷によって生じる認知障害である
2.認知症では最近の記憶が障害される
3.統合失調症では,対人・自我機能と認知と意欲に症状が現れる
4.双極症とうつ病は,気分の障害である
5.自閉スペクトラム症には,独特の認知特性がある
6.依存性の薬物は,脳の報酬回路を駆動する
索引
コラム目次
皮膚分節
筋枝と皮枝
神経筋特異性
舌の運動
側頭骨骨折による顔面神経障害
胸鎖乳突筋と僧帽筋の由来
鰓弓器官とは?
脳死
頸動脈洞と頸動脈小体
老廃物を搬出するグリンパティック系
てんかん:過剰な興奮の原因は?
素材をどのように視覚で認知するのか?
飛行機で,耳が痛くなるのはなぜ?
周波数,振動,神経応答の関係
臨床における外眼筋の検査
書評
開く
統合型神経科学教育の新たなスタンダードとなる一冊
書評者:北澤 茂(阪大教授・生理学)
神経解剖学と神経生理学,さらに臨床医学のエッセンスを融合させた『構造と機能がつながる神経解剖生理学』は,神経科学を学ぶ医学や関連分野の学生にとって「画期的」な教科書です。
伝統的な医学教育では,解剖学で神経系の構造を,その後に生理学で機能を,さらに臨床医学でその障害と治療法を,段階的に教えてきました。この「王道」スタイルは,一部の学生には有効です。しかし,多くの学生(私もその一人でしたが)は,神経系の複雑な構造を「覚える」ところで挫折しがちでした。大脳基底核の複雑な構造は典型的な難所ですが,「行動選択装置」という機能に着目して,アクセルの役割を果たす直接路とブレーキの役割を担う間接路に分けて学ぶと,難なくクリアできます。さらには,直接路や間接路の障害としてパーキンソン病やハンチントン病の病態をとらえると,一気に理解が進みます。解剖・生理・臨床の統合は,学習効果を飛躍的に高めるのです。
米国で始まった統合型カリキュラムには50年の歴史があり,日本でもその取り組みは進んでいます。しかし,教科書は依然として解剖学,生理学,臨床医学に分かれたままで,統合的な視点を反映したものがないという課題が残っていました。本書は,編者の坂井建雄氏の指揮のもと,解剖学の小林靖氏,生理学の宇賀貴紀氏,さらには臨床医学の専門家が緊密に協力して執筆を進めることで,この課題を解決しました。全編フルカラーの見開き2ページ構成を採用して,視覚的にも楽しめる,わかりやすい作りとなっています。
本書は,神経系の基礎から運動,感覚,生命維持機能,高次機能,さらにはその障害までを全8章で網羅しています。ただ平板に網羅するだけでなく,先端的で尖った内容が含まれている点も画期的です。例えば,第8章にある,認知症をデフォルトモードネットワークの障害としてとらえた解説などは,現代的で秀逸であると感じました。
神経系の構造・機能・障害を基礎から最新の情報まで一気に効率よく学びたい方全てに,本書を強く推薦します。医学や心理学の学生にとどまらず,AIや大規模言語モデルの専門家など情報科学領域の専門家にもお薦めしたい,まさに「ありそうでなかった」テキストです。
今後の統合型神経科学教育の新たなスタンダードになる一冊といえるでしょう。
解剖と生理が交差する学び――リハビリテーションの実践に役立つ神経科学
書評者:森岡 周(畿央大教授・理学療法学)
私たちが日常的に行っている「見る」「動かす」「感じる」といった営みは,脳と神経の複雑なネットワークによって支えられている。その神秘に触れる手がかりとして,本書『構造と機能がつながる神経解剖生理学』は,リハビリテーション専門職やその学生にとって心強い存在となる。神経解剖学と神経生理学を統合的に学べる本書は,「脳の地図」と「脳の動き」を並行して理解できる独自の構成を有する。見開き2ページで解剖と生理を対比して解説しており,知識が積み重なる感覚を味わえる。
目次が「である」調で記されている点も特徴的である。各項目が明確に示されており,学習の指針として有効である。リハビリテーション専門職にとって,神経障害のみならず解剖学や生理学といった幅広い基礎知識を習得し,統合的に理解することは不可欠である。複雑な情報が簡潔にまとめられている本書は,現場での実践にも直結し,学びの効率も高まるであろう。
本書を読み進める際には,神経生理学と神経症候学を区別しつつも,統合的に理解することが求められる。神経生理学は「神経系の標準的な機能」を解き明かす学問であり,神経症候学は「損傷や病変による神経機能の変化や症状」を扱う。リハビリテーションでは,神経系がどのように機能し,適応するのかを理解することが重要である。それにより,損傷や機能低下が生じた際の対応力が養われる。本書は,神経系の標準機能と病態を並行して学べるように設計されており,両者の関連性が自然に理解できる点が大きな魅力である。
運動機能障害や運動回復のメカニズムについても詳述されている。リハビリテーションに携わる専門職にとって,こうした知識は臨床で不可欠である。神経症状の理解に加え,回復に向けた介入のヒントが得られるのは,解剖学と生理学が一体化された「統合型テキスト」である本書の強みである。
また,本書の価値は運動機能にとどまらない。高次脳機能の章では,認知,言語,情動といった領域にも踏み込んでいる。リハビリテーションでは多職種連携が不可欠であり,脳の多様な働きについての理解が進めば,患者をより多角的に支援できる。視覚情報の処理や情動の制御といった高度なテーマも,フルカラーの図版やイラストによってわかりやすく解説されている。脳の仕組みが立体的に理解でき,断片的な知識がつながっていく感覚を得られる点も特筆すべきである。
本書は,神経系のマクロな構造から脊髄,脳幹,感覚・運動機能,高次機能障害まで幅広くカバーしている。実践的な内容が多く,学生だけでなく,現場で活躍する専門職にとっても知識をアップデートするための良き指針となる。今後は,神経ネットワークの視点がさらに強化されることを期待したい。
本書はリハビリテーション専門家や医療系学生が神経科学を深く学び,臨床で生かしていくための強力な道しるべとなるであろう。基礎知識と臨床応用を橋渡しする“統合型テキスト”として,学ぶ楽しさを実感させてくれる一冊である。
神経科学の新たな地平を拓く,待望の統合教科書
書評者:池谷 裕二(東大大学院教授・薬品作用学)
本書は,神経解剖学と神経生理学という2つの柱を融合させた,まさに「ありそうでなかった」一冊である。高等教育において,神経解剖学と神経生理学は(そして私の専門分野である神経薬理学も),しばしば独立した講義として提供される。しかし,本書は,これらの学問分野が本来一つの「身体」という存在を異なる側面から照らし出したものであるという原点に立ち返り,統合的な視点から神経科学を学ぶことを重視している。分断された知識体系では決して得られない深い理解へと読者を誘う本書は,まさに神経科学教育におけるパラダイムシフトを実証する。
見開き1ページを1単元とする構成であり,各単元で扱われる内容が相互に有機的に結び付くことで,「構造」と「機能」の関連性を直感的かつ深く理解できるようになっている。フルカラーで印刷された美しい図版の数々も,視覚的な学習効果を高めてくれる。
本書の特長は,単なる知識の羅列に終わらず,具体的な事例を通して「構造」と「機能」の関連性を深く掘り下げている点にある。序文で「解剖学,生理学,生化学といった学問分野の垣根は次第に消えつつあり」と述べられているが,本書はまさにその言葉を体現している。各分野の知識が有機的に結び付き,複雑な神経系の構造と機能が,まるで万華鏡のように鮮やかに浮かび上がる。例えば,第4章「感覚機能」では,嗅覚,視覚,聴覚といった特殊感覚が,どのように脳に伝達されるのかが詳細に解説されている。嗅覚のメカニズムを例にとると,嗅神経が鼻腔内の嗅粘膜から脳底部の嗅球へ,そして嗅脳へと情報を伝達する過程が,解剖学的な構造とともに,生理学的な特性を踏まえて丁寧に説明されている。嗅細胞の構造や再生能力といった微視的なレベルの記述から,嗅覚が人間の生活においていかに重要な役割を果たすかという巨視的なレベルの考察まで,一貫して「構造」と「機能」の関連性を軸に展開される論述は,読者の知的好奇心を刺激し,深い理解へと導く。
驚くべきは,第7章「脳の高次機能」や第8章「脳の高次機能障害」といった,従来の解剖学の教科書ではほとんど扱われることのなかった領域にまで踏み込んでいる点である。統合失調症や認知症といった疾患において,神経系の構造的な異常が精神機能に及ぼす影響を具体的に解説するなど,神経科学の臨床応用への架け橋となる役割も果たしている。
このような幅広いトピックを高いレベルで一貫して扱うことができたのは,編者である坂井建雄氏をはじめとする,卓越した知識と経験を持つ執筆陣の貢献によるものだろう。医療系の学生や専門家が,神経科学の全体像を把握するための「決定版」と呼ぶにふさわしい,圧倒的な情報量と質の高さを誇っている。読者は,本書を通じて神経科学の奥深さと面白さを再認識し,知的な興奮を覚えるに違いない。それは単なる知識の習得にとどまらず,生命の神秘に対する畏敬の念を呼び覚ます体験となるだろう。
やっと画期的な本が出版された
書評者:宇川 義一(福島医大名誉教授・脳神経内科学)
私が学生の時には,解剖学・組織学(ミクロ解剖)・生理学・生化学・薬理学などの講義を受けた後に,それらの知識を自分なりに統合して,神経系に関する基礎知識を整理した。それぞれの学問を修得するのにかなりの時間を要し,医学部の4年生くらいになってからでないと総合的に理解することができなかった。
本書では,それらの知識が話題ごとに見開き2ページで整理されている。神経系を全体的に理解するのに最適なテキストであり,多くの医学生の助けとなるであろう。また,最新の研究成果の一部も紹介されているので,知識のアップデートにもなる。さらに,理解を助けるきれいなイラストがふんだんにあり,わかりやすさを際立たせている。
臨床現場で遭遇する疾患の病態生理に関しても簡潔に記載されている点が,本書のもう1つの特色である。この部分は,臨床医が患者を診たときにすぐに参考にできる側面もある。また,「第8章 脳の高次機能障害」を除く大部分が3人の編集者自身による執筆であり,本書全体の統一性と読みやすさにつながっている。これらのことを踏まえて,以下の2つの使い方が考えられる。
◆学生が神経系の授業を受けていくときの指南書
学生が解剖学や生理学といった科目を学ぶとき,本書があればその科目の神経機能的側面を理解しながら,その詳細を学び進める助けになる。ターゲットの話題が全て理解できなくても,その位置付けを理解しつつ勉強を進めることができる。したがって,解剖学・生理学・生化学などの講義のたびに,同じ箇所を何度も読むことになるだろう。これは,学問の修得は同時並行かつ繰り返し行うべきで,一度聞いたことは一度で全て理解できるわけではなく,何度も聞くことによって自分のものとなるという理論と合致している。そして,学年が進むに従って,本書で述べられている内容を十分に理解できるようになるだろう。
また,本書の序にもあるが,神経に関する臓器別統合型授業において,特に最適な教科書となるであろう。
◆臨床で忙しい医師がそれぞれ話題となる知識の確認
臨床現場にいる神経系の医師は,本来は本書に書かれた内容を周知しているはずである。しかし,忘れていることもあれば,曖昧になっている点もある。それらの知識をコンパクトに復習でき,臨床現場で助けとなる。話題ごとにまとまっているため,素早く読みたい箇所を確認できるし,最新の知識に触れることで,専門書で調べるきっかけになることもあるだろう。
ただし,本書を読めば,全てのことが理解できるわけではない。いずれの話題も2ページでコンパクトにまとめられているので,全体像を効率よく理解できるが,さらに詳細に理解を深めたいときは,それぞれの分野の成書や論文に当たる必要がある。そのきっかけとなる書籍である。
基礎から臨床,さらに研究の最前線までを見通す統合学習を具現化した一冊
書評者:佐々木 哲也(筑波大准教授・解剖学・神経科学)
神経科学の教育における長年の課題に真正面から取り組んだ画期的な教科書が誕生した。従来の教科書では,神経解剖学と神経生理学が別個の学問として扱われ,その間の有機的な連携の欠如が,医学教育における大きな問題であった。本書『構造と機能がつながる神経解剖生理学』は,この課題を解決し,現代の神経科学教育に新たな指針を示している。
本書の最大の特徴は,単なる知識の寄せ集めではなく,現代の医療現場で求められる実践的な理解を促す構成にある。これは,現代の臨床現場で求められる実践的な知識体系の構築に大きく貢献するものである。神経解剖学は,CTやMRIなどの医用画像技術の発展により,従来の詳細な解剖学的知識の暗記に重点を置いた教育から,画像所見と機能的理解を結び付ける新しいアプローチへと転換している。この文脈において,VogelとWainwrightが1969年に述べた「機能なき構造は死体,構造なき機能は幽霊」という言葉は,本書の本質を端的に表現している。生命科学において構造と機能は不可分の関係にあり,その統合的理解なくして真の医学教育は成立し得ない。本書は,この根本的な認識に基づき,神経科学教育に新たなパラダイムを提示している。
全ページフルカラーの見開き構成は,この理念を視覚的に具現化している。例えば,神経伝導路の解説では,解剖学的構造と生理学的機能が同一ページ上で有機的に結び付けられ,学習者は両者の関係性を直感的に把握できる。各章の冒頭では構造と機能の関連性について概観が示され,学習者が常に両者の関係性を意識しながら学習を進められるように工夫されている。また,豊富な図表と写真は,複雑な神経系の構造と機能を理解する上で極めて効果的な学習ツールとなっている。
構成上の特徴として特筆すべきは,各章が明確な主題を持つ節によって体系的に組み立てられている点である。例えば「シナプスの強さは,学習によって変わる」「海馬はエピソード記憶の形成に重要である」「扁桃体は情動反応とその記憶に重要である」といった節タイトルが示すように,構造と機能の関係性が端的かつ明確に示されている。これにより,学習者は神経系の構造が持つ機能的意義を,より直接的に理解することができる。
近年,神経科学は医学・生物学の枠を超えて,心理学,認知科学,さらには人工知能研究にまで影響を及ぼす学際的な領域となっている。本書は,このような現代的な文脈も適切に取り入れている。特に,神経回路の機能的な結合様式や情報処理メカニズムの解説は,現代の脳科学研究の知見を反映した最新のものとなっている。本書は,基礎的な内容から発展的な話題まで,体系的かつ段階的に学習を進められるよう緻密に構成されている。「末梢神経系」「中枢神経系」「感覚機能」「運動機能」「高次機能」という基本的な構成に加え,各章内での配列も学習者の理解を助ける工夫が随所にみられる。例えば,感覚系の解説では,受容器から中枢への情報伝達経路,そして情報処理メカニズムへと,論理的な流れで説明が展開される。
これらの特徴に加えて,最新の研究成果や臨床知見を適切に取り入れながらも,基礎的な概念の説明をおろそかにしていないため,初学者から専門家まで,幅広い読者層に対応することに成功している。随所に配置されたコラムや臨床的・発展的な話題は,学習者の興味を喚起し,学習した知識の実践的な応用を促す動機付けとなっている。このような統合的アプローチは,現代の医療者に求められる本質的な能力の育成を効果的に支援する。構造と機能を有機的に結び付けて理解することは,臨床現場における的確な判断と治療方針の決定に直結する重要なスキルである。本書は,この理想を実現するための優れた指針を提供している。
坂井建雄氏を中心に,神経解剖学の専門家である小林靖氏,神経生理学の専門家である宇賀貴紀氏が編集を担当し,臨床の専門家も執筆に参加し,基礎から臨床まで一貫した視座で神経科学を理解できる構成となっている。特に,精神医学や高次脳機能障害に関する記述は,現代の臨床ニーズに即した実践的な内容となっている。
本書は,構造と機能の有機的統合という,現代の神経科学教育における待望の教科書である。VogelとWainwrightの言葉が示唆する構造と機能の不可分性を具現化した本書は,神経科学の領域にとどまらず,解剖学,生理学,生化学といった基礎医学教育全般に新たな方向性を示すものである。
正誤表
開く
本書の記述の正確性につきましては最善の努力を払っておりますが、この度弊社の責任におきまして、下記のような誤りがございました。お詫び申し上げますとともに訂正させていただきます。