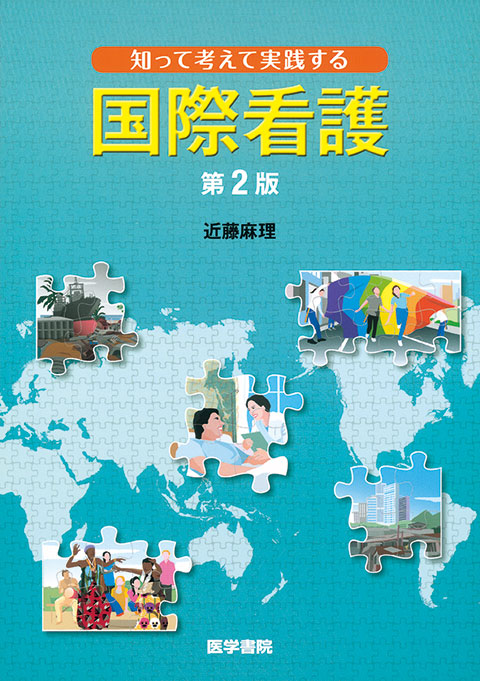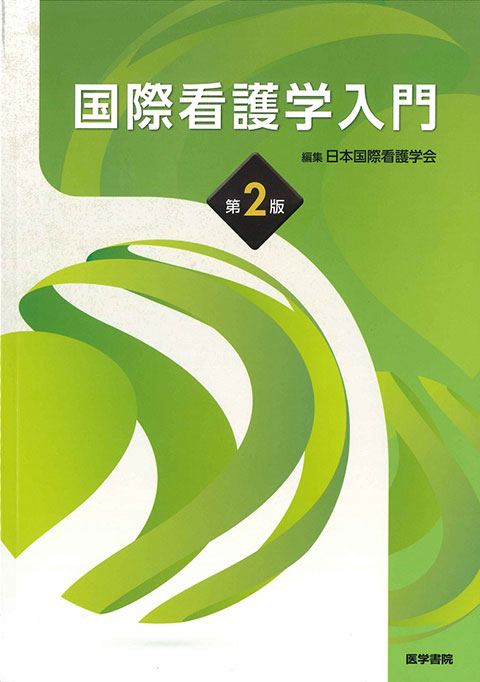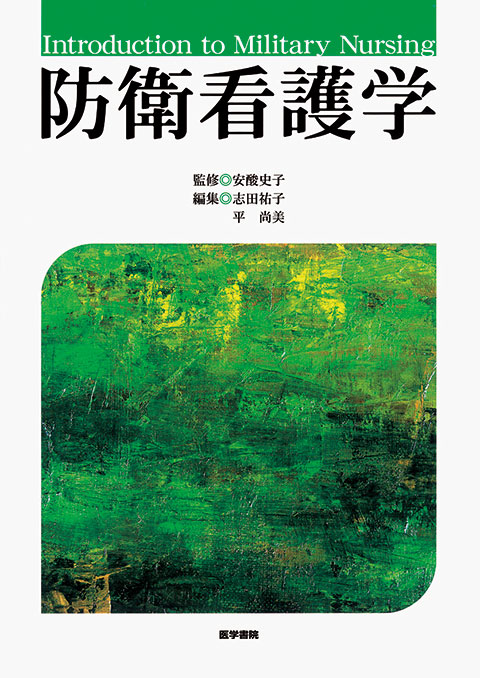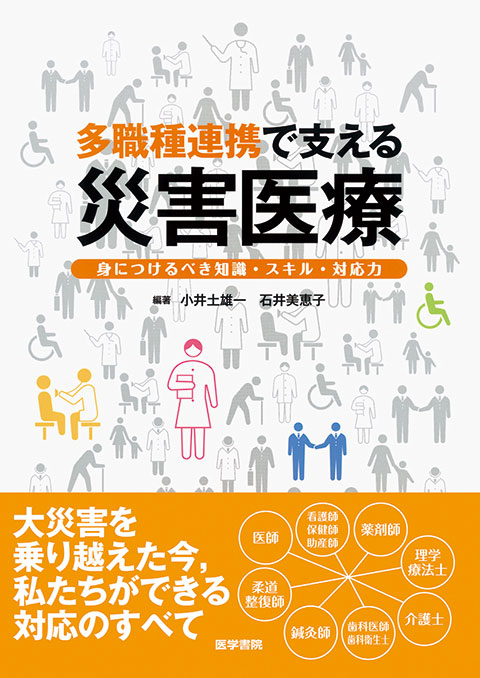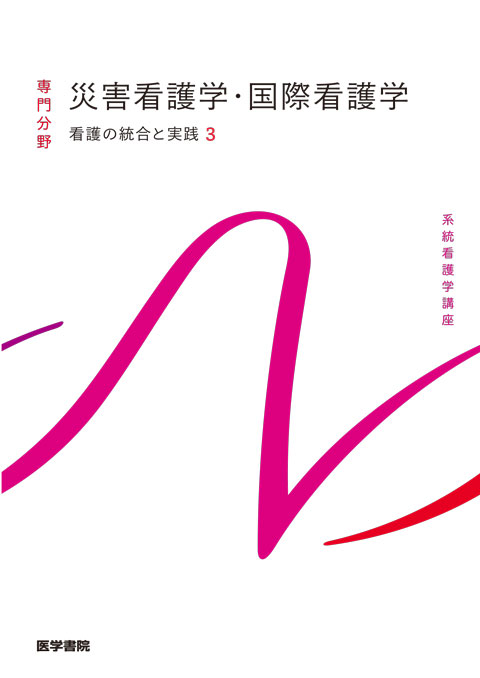知って考えて実践する 国際看護 第2版
授業で使いやすくつくられた国際看護のテキスト、待望の第2版
もっと見る
国際協力を学ぶことが国際看護学ではありません。すべての看護師が日常的に国際的視野をもち、日本国内も含め、世界のどこででも通用する看護を身につけることが重要です。第2版では、学校(大学)の講義あるいは研修で使いやすい工夫をすることと、日本や世界で看護を実践するうえで異文化への理解が求められていることを強調しました。ぜひ身近な話題として「国際」をとらえてください。
| 著 | 近藤 麻理 |
|---|---|
| 発行 | 2018年02月判型:A5頁:144 |
| ISBN | 978-4-260-03536-1 |
| 定価 | 1,980円 (本体1,800円+税) |
- 販売終了
更新情報
-
更新情報はありません。
お気に入り商品に追加すると、この商品の更新情報や関連情報などをマイページでお知らせいたします。
- 著者による本書の紹介
- 序文
- 目次
- 書評
著者による本書の紹介
開く
序文
開く
はじめに――国際看護について考えてみませんか
この本の初版は何年もの構想の末に,ようやく一冊の本になり,2011年に出版されました.そしてこのたび,改訂版が出版されることになりました.初版からの7年間に,日本の看護職の意識は国際化に向けて変化したでしょうか.この本を手に取られた皆さんは,21世紀になってからの世界の変化を察知して,看護のグローバル化の重要性にすでに気づいていることと思います.
看護の対象は「人間」です.「日本人」だけではないのです.看護は,民族,国境,宗教を超えていると考えたほうがより自然です.ですから,“国際”とわざわざ標榜しなくても,看護そのものが国際的な意味をもっているのです.21世紀は,国際的な視点からグローバルな看護活動をも包括した看護学を,私たちの手でつくりあげる必要があります.
日本の施設や病院でも,多くの外国人が外来受診したり入院したりしています.それを特別なことではなく,日本人と同じように多様な看護の対象者の1人であると感じることが,あたりまえになるのを期待しています.そう考えると日常の看護の場面でも,多くの国際化の実践はされているのです.
国際看護と聞いて,「私は国際協力なんてしませんし,外国にも行きたくないから関係ないです」と国際的視野をもつ必要に対して疑問を投げかける方もいます.しかし国際看護と国際協力が同義語ではないように,国際看護が目指すものは,けっして世界の国際協力の現場で活躍する看護職を養成することだけではないのです.ですから,「国際看護=外国の地で看護職が“活躍する”」という考えかたには賛成できません.
看護職の皆さんは,国際的視野をもち「世界のなかのかけがえのない1人の看護職である」という誇りのもとで仕事に携わっているでしょうか.学生や若い看護職が,「将来は,外国で看護の仕事や国際協力をしてみたい」と恥ずかしそうに話しかけてきたとき,教員やベテランの看護職の皆さんは,どのように応えてきたでしょうか.
看護職であれば誰でも,人生のどこかでプロフェッショナルとして国際協力にかかわる可能性はあるのです.看護の対象は「人間」ですから,看護という概念には,もともと国境も,人種も,文化も超えた国際看護という考えかたが備わっています.だからこそ,すべての看護職に国際看護の知識が必要であると強く思うのです.
ここで,この本について説明しましょう.
関心のあるテーマからどうぞ読み始めてみてください.この本は,看護を学ぶ学生さんはもちろん,これからの看護を考える多くの方に楽しく学習してもらえるように,私自身が体験した事例やコラムを取り入れ,話しかけるようなつもりで執筆しました.参考となるウェブサイトや文献,そして映画も紹介しています.
2020年に東京オリンピック開催を控え,ますますの国際化が予想されることから,病院や施設の現場では,看護職の継続教育の参考資料としてご活用ください.また,教育現場では学生への看護教育でシラバスを作成する際には,概要と具体的な目標,そして1,2章のキーワードを参考にし,8~15コマの国際看護学の科目として組むことが可能です.この本は,『看護教育』(医学書院)2009年1~12月号(Vol. 50 No. 1~12)の連載「誌上講義:国際看護学」とリンクしています.教育にかかわる皆様には,連載に掲載された国際看護教育の授業方法や資料を合わせてご覧いただけることを期待しています.
この本を手に取られた方に,私の想いが届きますように,そして,皆さんの知と技に磨きがかかり,国際看護と看護の発展にますます寄与されますように,願っています.
2018年1月吉日
近藤麻理
この本の初版は何年もの構想の末に,ようやく一冊の本になり,2011年に出版されました.そしてこのたび,改訂版が出版されることになりました.初版からの7年間に,日本の看護職の意識は国際化に向けて変化したでしょうか.この本を手に取られた皆さんは,21世紀になってからの世界の変化を察知して,看護のグローバル化の重要性にすでに気づいていることと思います.
看護の対象は「人間」です.「日本人」だけではないのです.看護は,民族,国境,宗教を超えていると考えたほうがより自然です.ですから,“国際”とわざわざ標榜しなくても,看護そのものが国際的な意味をもっているのです.21世紀は,国際的な視点からグローバルな看護活動をも包括した看護学を,私たちの手でつくりあげる必要があります.
日本の施設や病院でも,多くの外国人が外来受診したり入院したりしています.それを特別なことではなく,日本人と同じように多様な看護の対象者の1人であると感じることが,あたりまえになるのを期待しています.そう考えると日常の看護の場面でも,多くの国際化の実践はされているのです.
国際看護と聞いて,「私は国際協力なんてしませんし,外国にも行きたくないから関係ないです」と国際的視野をもつ必要に対して疑問を投げかける方もいます.しかし国際看護と国際協力が同義語ではないように,国際看護が目指すものは,けっして世界の国際協力の現場で活躍する看護職を養成することだけではないのです.ですから,「国際看護=外国の地で看護職が“活躍する”」という考えかたには賛成できません.
看護職の皆さんは,国際的視野をもち「世界のなかのかけがえのない1人の看護職である」という誇りのもとで仕事に携わっているでしょうか.学生や若い看護職が,「将来は,外国で看護の仕事や国際協力をしてみたい」と恥ずかしそうに話しかけてきたとき,教員やベテランの看護職の皆さんは,どのように応えてきたでしょうか.
看護職であれば誰でも,人生のどこかでプロフェッショナルとして国際協力にかかわる可能性はあるのです.看護の対象は「人間」ですから,看護という概念には,もともと国境も,人種も,文化も超えた国際看護という考えかたが備わっています.だからこそ,すべての看護職に国際看護の知識が必要であると強く思うのです.
ここで,この本について説明しましょう.
関心のあるテーマからどうぞ読み始めてみてください.この本は,看護を学ぶ学生さんはもちろん,これからの看護を考える多くの方に楽しく学習してもらえるように,私自身が体験した事例やコラムを取り入れ,話しかけるようなつもりで執筆しました.参考となるウェブサイトや文献,そして映画も紹介しています.
2020年に東京オリンピック開催を控え,ますますの国際化が予想されることから,病院や施設の現場では,看護職の継続教育の参考資料としてご活用ください.また,教育現場では学生への看護教育でシラバスを作成する際には,概要と具体的な目標,そして1,2章のキーワードを参考にし,8~15コマの国際看護学の科目として組むことが可能です.この本は,『看護教育』(医学書院)2009年1~12月号(Vol. 50 No. 1~12)の連載「誌上講義:国際看護学」とリンクしています.教育にかかわる皆様には,連載に掲載された国際看護教育の授業方法や資料を合わせてご覧いただけることを期待しています.
この本を手に取られた方に,私の想いが届きますように,そして,皆さんの知と技に磨きがかかり,国際看護と看護の発展にますます寄与されますように,願っています.
2018年1月吉日
近藤麻理
目次
開く
はじめに――国際看護について考えてみませんか
第1章 日本から世界に目を開く――国際的視野を広げる
1.国際看護のすすめ――看護の対象は「人間」である
2.異文化への理解――基本的人権の尊重のために
3.日本の国際協力――私たちは世界とつながっている
4.「人間の安全保障」と国際機関――MDGsからSDGsへ
5.プライマリヘルスケア――自分の命と健康を自分で守ること
第2章 現場で何が起きているのか――多様性のなかで生きる私たち
1.国際移動する看護師――職場の同僚は日本人だけですか?
2.性の多様性――LGBTへの理解
3.紛争と難民――日本とは無関係なことでしょうか?
4.感染症とスティグマ――存在が見えなくなる人々へのまなざし
5.災害と看護――援助する側・される側というステレオタイプ
6.健康格差と世界の貧困――貧しい人たちとは,誰か
第3章 見て!聞いて!体験する!――国際協力への理解を深める
1.どこで何を学ぶか――情報収集の重要性
2.国際的に活動するための多様な道――夢と現実
3.国際的な仕事への挑戦――海外で,日本で
4.海外研修の実際と課題――知的好奇心を刺激する
第4章 これからの私たちの選択――看護の力を信じて
1.メディア・リテラシー――情報をどう判断するか
2.進化する国際看護とともに――10年後の看護の姿は?
おわりに
考えてみましょう
2050年の世界は? そして私たちの生活は?
世界に大きな影響を与える人たち
「いくら払えるのか?」
開発か,それともエコロジーか
国連の予算配分
ラクの物語
きつい仕事を担う外国人看護師
予防接種を食料引換の条件に
1人を助けるのか,それとも大勢を助けるのか
看護師の苦悩
災害時には,病院に駆けつけないと怒られますか!?
住民自身が命を守る救命救急研修
COLUMN
「専門家」としての意見は?
「時間を守る」のはあたりまえではない?
フィールド調査は過酷なのです
緒方さんに憧れて
予防接種は,炎天下を村まで歩いて
市民が紛争地に行くことの意味
売買春を通して考える「自分事」「他人事」
身だしなみの気持ちも大切に
意地悪すぎる質問
第1章 日本から世界に目を開く――国際的視野を広げる
1.国際看護のすすめ――看護の対象は「人間」である
2.異文化への理解――基本的人権の尊重のために
3.日本の国際協力――私たちは世界とつながっている
4.「人間の安全保障」と国際機関――MDGsからSDGsへ
5.プライマリヘルスケア――自分の命と健康を自分で守ること
第2章 現場で何が起きているのか――多様性のなかで生きる私たち
1.国際移動する看護師――職場の同僚は日本人だけですか?
2.性の多様性――LGBTへの理解
3.紛争と難民――日本とは無関係なことでしょうか?
4.感染症とスティグマ――存在が見えなくなる人々へのまなざし
5.災害と看護――援助する側・される側というステレオタイプ
6.健康格差と世界の貧困――貧しい人たちとは,誰か
第3章 見て!聞いて!体験する!――国際協力への理解を深める
1.どこで何を学ぶか――情報収集の重要性
2.国際的に活動するための多様な道――夢と現実
3.国際的な仕事への挑戦――海外で,日本で
4.海外研修の実際と課題――知的好奇心を刺激する
第4章 これからの私たちの選択――看護の力を信じて
1.メディア・リテラシー――情報をどう判断するか
2.進化する国際看護とともに――10年後の看護の姿は?
おわりに
考えてみましょう
2050年の世界は? そして私たちの生活は?
世界に大きな影響を与える人たち
「いくら払えるのか?」
開発か,それともエコロジーか
国連の予算配分
ラクの物語
きつい仕事を担う外国人看護師
予防接種を食料引換の条件に
1人を助けるのか,それとも大勢を助けるのか
看護師の苦悩
災害時には,病院に駆けつけないと怒られますか!?
住民自身が命を守る救命救急研修
COLUMN
「専門家」としての意見は?
「時間を守る」のはあたりまえではない?
フィールド調査は過酷なのです
緒方さんに憧れて
予防接種は,炎天下を村まで歩いて
市民が紛争地に行くことの意味
売買春を通して考える「自分事」「他人事」
身だしなみの気持ちも大切に
意地悪すぎる質問
書評
開く
海外で,日本で,国際的な仕事への挑戦に踏み出すきっかけとできる書(雑誌『看護教育』より)
書評者: 野地 有子 (千葉大学大学院看護学研究科教授)
私たちの社会のグローバル化は一段と進み,国際看護についての関心が高まってきています。2020年東京オリンピック・パラリンピック開催まで2年となり,外国人旅行者や在留者などの増加への施策が推進されている状況です。そんななか,国際看護の舞台は,海外だけでなく身近な日常の看護場面でも展開されてきています。国家戦略として外国人診療を推進する病院の認証や医療通訳士の配置が進められていますが,看護実践に関する検討は十分になされているでしょうか? 外国人患者と看護職や医療者の間で,文化的な生活習慣,価値観,社会背景,医療制度などの違いによる戸惑いや負担が多くみられ,トラブルや医療安全も危惧されます。今こそ,国際看護を“知って考えて実践する”ことが必要なときです。
本書は,本誌での連載「誌上講義:国際看護学」をまとめた初版(2011年)の内容に,さらに文化の多様性についてグローバルな視点を強化した改訂版です。コソボの紛争地,タイ東北部の農村地,緒方貞子さんのこと,感染症,災害,健康格差と貧困,看護と人権など,内容は幅広く,著者の豊富な国際看護の体験を,わかりやすく共有することができます。
国際看護を学ぶ魅力の1つに異文化と出合い,多様性について気づくことがあげられます。自分の知らなかった世界が広がり,驚きと時に衝撃が走ることもあります。違いに対する尊重(リスペクト)と,違いを理解したいという気持ちが求められます。文化の多様性(ダイバーシティ)を理解する道のりは,継続した努力が必要ですが,本書は,そのためによいスタートを切る入門書として助けになります。参考となるウェブサイトや文献,そして映画も豊富に紹介されていますので,たとえば映画を見ながら自然に引き込まれていきます。
また,看護学モデル・コア・カリキュラムを展開するうえですぐに役立てることができます。看護学モデル・コア・カリキュラムの国際看護に関するものは,「国際社会・多様な文化における看護職の役割」「国際社会と看護」「多様な場の特性に応じた看護を学ぶ」があげられています。本書の各章の概要,目標,キーワードを活用して,8~15コマの国際看護のシラバス作成に役立てることができます。
本書は,看護教員,看護学生,さらに看護実践家が,看護職として,国際的視野をもち「世界のなかのかけがえのない1人の看護職である」という誇りのもと仕事に携わり,海外で,日本で,国際的な仕事への挑戦に一歩を踏み出す,そんな成長のきっかけとなる1冊となるでしょう。
(『看護教育』2018年10月号掲載)
自身の看護観や看護管理実践を振り返る機会に(雑誌『看護管理』より)
書評者: 市村 尚子 (名古屋大学医学部附属病院 看護部長)
2009年に看護基礎教育カリキュラム改正で「国際看護学」がクローズアップされてから10年近く経ち,著者の近藤麻理氏をはじめ「国際看護学の教員」に出会うことも珍しくなくなった。言うまでもなく,私の学生時代には「国際看護学」の講義はなかったが,看護職に国際的視点は欠かせないと思う。
うん? 本当にそう「思う」? 「将来は海外で保健医療活動をしたい」という看護学生や若い看護師に「頼もしいね」とほほ笑みつつ,「海外に行かなくても,当院には多くの外国人患者さんがいらっしゃる。そこに積極的に取り組んでくれるといいなあ」と調子のよいことを考えながら,自らはそこに積極的に取り組めていない看護部長である。私の「看護職にとって国際的視点は欠かせない」ことへの理解は怪しい。そんなことを考えながら,本書を読み始めた。
本書は,はじめに「看護の対象は『人間』です。『日本人』だけではないのです。看護は,民族,国境,宗教を超えていると考えたほうがより自然です。ですから,“国際”とわざわざ標榜しなくても,看護そのものが国際的な意味をもっているのです」と始まる。
私たちは,ICN(国際看護師協会)の倫理綱領の前文に「(前略)看護ケアは,年齢,皮膚の色,信条,文化,障害や疾病,ジェンダー,性的指向,国籍,政治,人種,社会的地位を尊重するものであり,これらを理由に制約されるものではない(後略)」と書かれていることを知っている。また,日本看護協会の「看護者の倫理綱領」に「看護者は,人間の生命,人間としての尊厳及び権利を尊重する」と書かれていることも知っている。しかし,日常的に多く場面で「看護の対象は日本人」なので,いつしか「看護の対象は日本人」が刷り込まれてきたのかもしれない。
「第1章 日本から世界に目を開く―国際的視野を広げる」で,国際看護の根底にあるのは,全ての人の尊厳および権利を尊重・擁護するという医療職としての基本的な姿勢であることが分かった。そして,国際看護の知識が増えると,異文化への違和感が,外国人患者さんのニードとケアへの関心に変わっていくと実感した。
「第2章 現場で何が起きているか―多様性のなかで生きる私たち」では,性の多様性とLGBTへの理解についても触れられている。「さまざまな書類に『性別』という項目がありますが,男性,女性のどちらの性にもチェックしたくない人たちがいることを想像したことがありますか。自分たちで全く気づかずに,その人たちを傷つけているかもしれないことを看護の専門職として私たちは意識しなければなりません」と書かれているのを読み,ドキッとした。そうだ,それは看護の対象者とは限らない。私たちの仲間の誰かであるかもしれないのだ。
「第3章 見て!聞いて!体験する!―国際協力への理解を深める」では,国際的な人道支援活動に必要とされる資質が7点挙げられている。「国際社会の動向に関心を寄せて学ぶ姿勢」や「冷静に行動するための深い洞察力」等であるが,それらは海外に出なくても,看護に携わる際に必要とされる資質である。著者は「私たちが学び続けている看護学という学問は,ほかの学問と同様に国際的な視点を包括しています」と言う。
改めて,今,当院で提供している看護・医療について「国際看護」という視点で考えてみる,さらに,自身の看護観や看護管理実践を振り返る―そんな機会になった1冊であった。
(『看護管理』2018年5月号掲載)
書評者: 野地 有子 (千葉大学大学院看護学研究科教授)
私たちの社会のグローバル化は一段と進み,国際看護についての関心が高まってきています。2020年東京オリンピック・パラリンピック開催まで2年となり,外国人旅行者や在留者などの増加への施策が推進されている状況です。そんななか,国際看護の舞台は,海外だけでなく身近な日常の看護場面でも展開されてきています。国家戦略として外国人診療を推進する病院の認証や医療通訳士の配置が進められていますが,看護実践に関する検討は十分になされているでしょうか? 外国人患者と看護職や医療者の間で,文化的な生活習慣,価値観,社会背景,医療制度などの違いによる戸惑いや負担が多くみられ,トラブルや医療安全も危惧されます。今こそ,国際看護を“知って考えて実践する”ことが必要なときです。
本書は,本誌での連載「誌上講義:国際看護学」をまとめた初版(2011年)の内容に,さらに文化の多様性についてグローバルな視点を強化した改訂版です。コソボの紛争地,タイ東北部の農村地,緒方貞子さんのこと,感染症,災害,健康格差と貧困,看護と人権など,内容は幅広く,著者の豊富な国際看護の体験を,わかりやすく共有することができます。
国際看護を学ぶ魅力の1つに異文化と出合い,多様性について気づくことがあげられます。自分の知らなかった世界が広がり,驚きと時に衝撃が走ることもあります。違いに対する尊重(リスペクト)と,違いを理解したいという気持ちが求められます。文化の多様性(ダイバーシティ)を理解する道のりは,継続した努力が必要ですが,本書は,そのためによいスタートを切る入門書として助けになります。参考となるウェブサイトや文献,そして映画も豊富に紹介されていますので,たとえば映画を見ながら自然に引き込まれていきます。
また,看護学モデル・コア・カリキュラムを展開するうえですぐに役立てることができます。看護学モデル・コア・カリキュラムの国際看護に関するものは,「国際社会・多様な文化における看護職の役割」「国際社会と看護」「多様な場の特性に応じた看護を学ぶ」があげられています。本書の各章の概要,目標,キーワードを活用して,8~15コマの国際看護のシラバス作成に役立てることができます。
本書は,看護教員,看護学生,さらに看護実践家が,看護職として,国際的視野をもち「世界のなかのかけがえのない1人の看護職である」という誇りのもと仕事に携わり,海外で,日本で,国際的な仕事への挑戦に一歩を踏み出す,そんな成長のきっかけとなる1冊となるでしょう。
(『看護教育』2018年10月号掲載)
自身の看護観や看護管理実践を振り返る機会に(雑誌『看護管理』より)
書評者: 市村 尚子 (名古屋大学医学部附属病院 看護部長)
2009年に看護基礎教育カリキュラム改正で「国際看護学」がクローズアップされてから10年近く経ち,著者の近藤麻理氏をはじめ「国際看護学の教員」に出会うことも珍しくなくなった。言うまでもなく,私の学生時代には「国際看護学」の講義はなかったが,看護職に国際的視点は欠かせないと思う。
うん? 本当にそう「思う」? 「将来は海外で保健医療活動をしたい」という看護学生や若い看護師に「頼もしいね」とほほ笑みつつ,「海外に行かなくても,当院には多くの外国人患者さんがいらっしゃる。そこに積極的に取り組んでくれるといいなあ」と調子のよいことを考えながら,自らはそこに積極的に取り組めていない看護部長である。私の「看護職にとって国際的視点は欠かせない」ことへの理解は怪しい。そんなことを考えながら,本書を読み始めた。
本書は,はじめに「看護の対象は『人間』です。『日本人』だけではないのです。看護は,民族,国境,宗教を超えていると考えたほうがより自然です。ですから,“国際”とわざわざ標榜しなくても,看護そのものが国際的な意味をもっているのです」と始まる。
私たちは,ICN(国際看護師協会)の倫理綱領の前文に「(前略)看護ケアは,年齢,皮膚の色,信条,文化,障害や疾病,ジェンダー,性的指向,国籍,政治,人種,社会的地位を尊重するものであり,これらを理由に制約されるものではない(後略)」と書かれていることを知っている。また,日本看護協会の「看護者の倫理綱領」に「看護者は,人間の生命,人間としての尊厳及び権利を尊重する」と書かれていることも知っている。しかし,日常的に多く場面で「看護の対象は日本人」なので,いつしか「看護の対象は日本人」が刷り込まれてきたのかもしれない。
「第1章 日本から世界に目を開く―国際的視野を広げる」で,国際看護の根底にあるのは,全ての人の尊厳および権利を尊重・擁護するという医療職としての基本的な姿勢であることが分かった。そして,国際看護の知識が増えると,異文化への違和感が,外国人患者さんのニードとケアへの関心に変わっていくと実感した。
「第2章 現場で何が起きているか―多様性のなかで生きる私たち」では,性の多様性とLGBTへの理解についても触れられている。「さまざまな書類に『性別』という項目がありますが,男性,女性のどちらの性にもチェックしたくない人たちがいることを想像したことがありますか。自分たちで全く気づかずに,その人たちを傷つけているかもしれないことを看護の専門職として私たちは意識しなければなりません」と書かれているのを読み,ドキッとした。そうだ,それは看護の対象者とは限らない。私たちの仲間の誰かであるかもしれないのだ。
「第3章 見て!聞いて!体験する!―国際協力への理解を深める」では,国際的な人道支援活動に必要とされる資質が7点挙げられている。「国際社会の動向に関心を寄せて学ぶ姿勢」や「冷静に行動するための深い洞察力」等であるが,それらは海外に出なくても,看護に携わる際に必要とされる資質である。著者は「私たちが学び続けている看護学という学問は,ほかの学問と同様に国際的な視点を包括しています」と言う。
改めて,今,当院で提供している看護・医療について「国際看護」という視点で考えてみる,さらに,自身の看護観や看護管理実践を振り返る―そんな機会になった1冊であった。
(『看護管理』2018年5月号掲載)