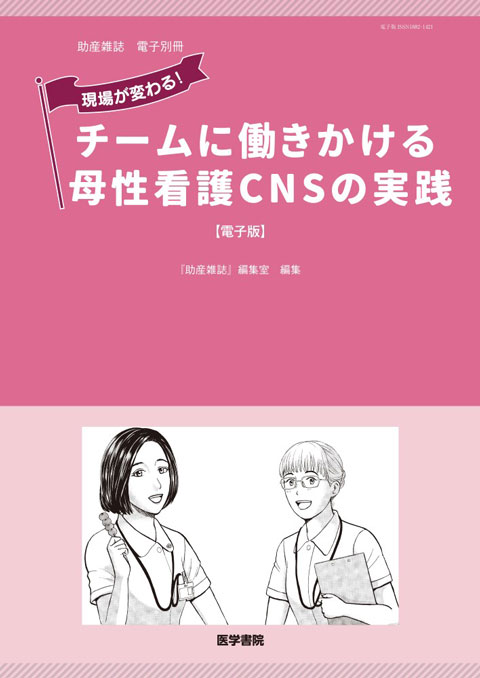助産雑誌 電子別冊 「現場が変わる! チームに働きかける母性看護CNSの実践」【電子版】
これが母性看護CNSの高度実践です
もっと見る
母性看護専門看護師(CNS)には、直接ケアの他に、6つの機能(実践、相談、調整、倫理調整、教育、研究)を使って現場を円滑に回しチームへ貢献する役割がある。その役割を正しく認識してもらうために、月刊誌『助産雑誌』連載では事例を深く掘り下げ、漫画と共に実践の「見える化」を図った。本電子別冊は、連載12回を1つにまとめたもの。日夜奮闘している母性看護CNSの高度実践を、明確にお伝えするものに仕上がった。
| 編集 | 『助産雑誌』編集室 |
|---|---|
| 発行 | 2021年12月 |
| 価格 | 2,200円 (本体2,000円+税) |
更新情報
-
更新情報はありません。
お気に入り商品に追加すると、この商品の更新情報や関連情報などをマイページでお知らせいたします。
- 本書の紹介
- 目次
本書の紹介
開く
連載「現場が変わる! チームに働きかける母性看護CNSの実践」が電子書籍になりました
松原まなみ(関西国際大学保健医療学部)
2019年,『助産雑誌』の連載「現場が変わる! チームに働きかける母性看護CNSの実践」を1年間にわたって掲載し,9事例を紹介していただく機会を得ました。このたび,医学書院初の企画である看護系雑誌連載の電子書籍化の第1号として発刊の運びとなったことは,うれしい限りです。
高度実践(ダイレクトケア),調整,相談(コンサルテーション),倫理調整などの実践について,9名の母性看護専門看護師(CNS)の方々に事例を通してご執筆いただき,それぞれの実践には,数々の看護・医療漫画を手掛けていらっしゃる,こしのりょうさんに臨場感あふれる実践場面を描いていただきました。
患者や家族,スタッフ,組織(看護チーム,医療チーム)の潜在する問題が顕在化する前に発見して対処したり,その後に問題が起きないようチームや組織を整えたりするのがCNSの役割です。CNSの存在がなければ,その事例はどんな転機をたどることになったであろう……母性看護CNSの素晴らしい実践を見聞きするたびに,卓越した実践を可視化し,その価値,存在意義を世に知らしめることが急務と感じています。
本電子書籍が刊行されるに当たり,母性看護CNS第1号であり,編集・執筆を担当した三田村七福子氏は,巻末にこう記しています。
*
[あなたたちには,CNS実践を記述して報告するミッションがある]
恩師のひとりであるPatricia Underwood先生の言葉です。reflectionを重ね,CNSである自分の質保証に注力せよという意味,そして複雑で解決困難な問題へのCNS実践経験を提示し,看護学の発展に寄与せよという意味,この2つのメッセージを含んでいると私は思っています。(中略)
それぞれの実践報告には,現象がイキイキと語られ,苦慮された判断,対象のためにチームを機能させようとする母性看護CNSの懸命な姿勢が見えます。
CNSとして対象とチームに貢献しよう,その質を少しでも上げようと,おのおのが自分と組織の状況に沿って挑んでおられることが伝わってきます。
*
『助産雑誌』読者をはじめ,多くの皆さまにこの電子書籍を手に取っていただくことで,母性看護CNSが現場にどれだけ必要な存在かを感じてもらえることと思います。
周産期の医療現場における解決困難な課題に対する卓越した看護や,チーム・組織の力を高め,看護の質を向上させていく母性看護CNSの実践を垣間見ることで,周産期の現場,ウイメンズヘルスケアに彼女たちの力が必要であることを実感していただけるはずです。
(「助産雑誌」76巻3号掲載)
目次
開く
電子版 はじめに
第1回 周産期領域における解決困難な事例にどう向き合うか?――母性看護専門看護師に期待される役割・機能
第2回 [事例編①]チームメンバーがケアの成果を実感し,看護への自信を深める――母体炎症性腸疾患(IBD)・胎児心疾患を合併した妊婦の事例を通して
第3回 [事例編②]チームで実践,ウィメンズヘルスを支える継続支援――選択性緘黙のある妊婦への関わりを通して
第4回 母性看護専門看護師の活用と現状の課題――実態調査の結果から
第5回 [事例編③]地域連携体制の構築とケアの標準化へのスタッフ育成――チームの設立と地域保健師との連絡協議会の開催
第6回 [事例編④]グリーフケアに不慣れなスタッフとチームを支えるためのCNSの介入――出生前診断で致死性疾患を指摘された事例
第7回 [事例編⑤]妊娠継続に迷う精神疾患合併妊婦のケアに戸惑う助産師に対するコンサルテーション――被虐待歴によるPTSDのある妊婦への妊娠初期から育児期までの支援
第8回 [事例編⑥]チェンジ・エージェンシーを発揮――コンフリクトケースをチームで支援するシステム作り,専門看護外来の立ち上げ
第9回 [事例編⑦]点滴治療中止を訴えてきた切迫早産妊婦に関わる倫理調整
第10回 [事例編⑧]患者の思いとスタッフの思いの溝を埋めるためのCNSの関わり――強い疼痛を体験している妊婦の事例を通して
第11回 [事例編⑨]特定妊婦の継続支援――育児習得に時間を要し,家族のサポート力が弱い褥婦に対する養育環境の調整
第12回 実践の語りから母性看護CNSの役割を可視化する――母性看護CNSの実践の語り 語り手:八巻和子,聞き手:村上靖彦
電子版のおわりに寄せて