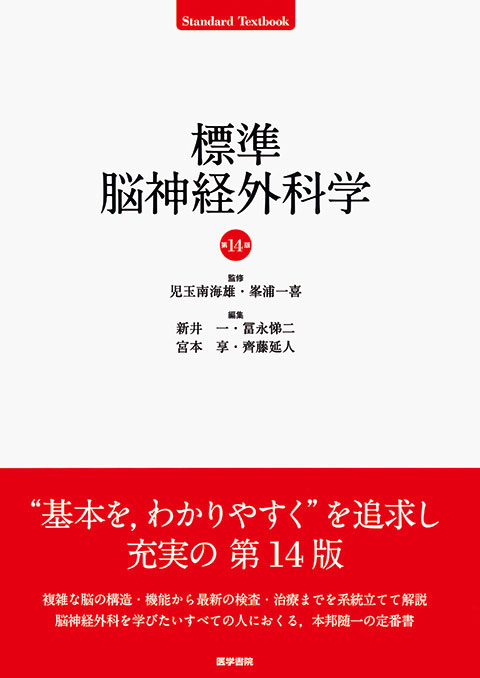標準脳神経外科学 第14版
脳神経外科学のスタンダードテキスト、堂々の改訂
もっと見る
構造的にも機能的にも複雑で奥深い、脳神経外科学領域の決定版テキスト。今版でも医学生に必要なトピックを精選・強化。重要事項がひと目で分かるアンダーラインと縦横無尽のクロスリファレンスで、“基本をわかりやすく伝える”ことを徹底した。医師国家試験出題基準・コアカリキュラム対照表、巻末演習問題も好評収載。フルカラーのシェーマが美しい、堂々の第14版!


| ● | 『標準医学シリーズ 医学書院eテキスト版』は「基礎セット」「臨床セット」「基礎+臨床セット」のいずれかをお選びいただくセット商品です。 |
| ● | 各セットは、該当する領域のタイトルをセットにしたもので、すべての標準シリーズがセットになっているわけではございません。 |
| シリーズ | 標準医学 |
|---|---|
| 監修 | 児玉 南海雄 / 峯浦 一喜 |
| 編集 | 新井 一 / 冨永 悌二 / 宮本 享 / 齊藤 延人 |
| 発行 | 2017年03月判型:B5頁:498 |
| ISBN | 978-4-260-02827-1 |
| 定価 | 7,700円 (本体7,000円+税) |
- 販売終了
更新情報
-
更新情報はありません。
お気に入り商品に追加すると、この商品の更新情報や関連情報などをマイページでお知らせいたします。
- 序文
- 目次
- 正誤表
序文
開く
第14版 序
追悼の辞
本書の脳腫瘍部門の執筆者であられた川原信隆先生(横浜市立大学大学院教授)が急逝された.無念な気持は筆舌に尽くし難く,心からのご冥福を祈るとともに,慎んで本書を川原信隆先生のご霊前に奉げる.
合掌
執筆者一同
世界中の人々が「M」「O」「N」「E」「Y」の5文字に狂奔している.医療施設が経理をおろそかにできないことは当然であるが,度を越した利益追求に走り過ぎているきらいも見え隠れする.
本書の読者である医学生や研修医の方々は,上記の5文字が絡む病院の経営などには,幸いにも今のところ大きな関わり合いはないであろう.
ところで,本書の第15章に,医学部の学生教育が授業料だけでは賄いきれず,周囲の見ず知らずの多くの方々の税金から捻出される補助金のお陰もあり卒業できることを記述した(384頁参照).医師になったら基本的な心構えとして,患者さんとして訪れる方々,この見知らぬ方々から学生時代に受けた見えにくく気付き難かった恩恵に対し,「恩返しの気持ち」を忘れることなく発揮していただきたい.
もう1つ,医師には「自己犠牲を厭わぬ気概」が不可欠である.臨床の第一線にいる医師には,日常の私生活はあっても無きが如く忙殺されることが多い.患者さんは時間を選んで発病するわけではなく,休日であろうが深夜であろうが,時を選ばずに運び込まれてくる.八方塞がりという状況も確かにあるが,それでもなお他医との連携を図るなどの工夫をし,必ず対応していく「自己犠牲を厭わぬ気概」,そして前述した「恩返しの気持ち」とを兼ね備えた医師であって欲しい.
本書は竹内一夫先生による発刊(1979年)以来,脳神経外科学の基本となる原理・原則を中心に記述してきた.これらを皆さんの若い脳に,論理的に理屈を考えながら繰り返し徹底的に叩き込んでいただきたい.ひとつの領域の基本的な理解が深まれば深まるほど,身体他部の疾患についての把握もおのずと進むものである.
今後の医学・医療は予測を遥かに超えた進歩・発展を遂げ,大きく変貌していくであろう.しかし患者さんや人間社会に対する医師としての基本的姿勢や医学・医療の原理・原則は変わらないはずである.それらを保持しつつ,最初に挙げた5文字などに決して惑うことなく,「寒青(かんせい)」のごとく青々と,全身に気高い信念を漲らせ,往く道に日毎立ちはだかる難題に対し,蓄積した情報をもとに,常に自分の頭で考えて乗り切る工夫を重ねていく医師になることを願っている.
最後に,今回の改訂で主眼とした記述内容の大幅なスリム化へのご協力を賜った執筆者の先生方に心からの感謝を申し上げ,また本書の上梓に向けて,真摯に不断の努力を積み重ねてこられた医学書院の関係諸氏にも深甚なる謝意を表する.
2017年3月
監修者 児玉南海雄
追悼の辞
本書の脳腫瘍部門の執筆者であられた川原信隆先生(横浜市立大学大学院教授)が急逝された.無念な気持は筆舌に尽くし難く,心からのご冥福を祈るとともに,慎んで本書を川原信隆先生のご霊前に奉げる.
合掌
執筆者一同
世界中の人々が「M」「O」「N」「E」「Y」の5文字に狂奔している.医療施設が経理をおろそかにできないことは当然であるが,度を越した利益追求に走り過ぎているきらいも見え隠れする.
本書の読者である医学生や研修医の方々は,上記の5文字が絡む病院の経営などには,幸いにも今のところ大きな関わり合いはないであろう.
ところで,本書の第15章に,医学部の学生教育が授業料だけでは賄いきれず,周囲の見ず知らずの多くの方々の税金から捻出される補助金のお陰もあり卒業できることを記述した(384頁参照).医師になったら基本的な心構えとして,患者さんとして訪れる方々,この見知らぬ方々から学生時代に受けた見えにくく気付き難かった恩恵に対し,「恩返しの気持ち」を忘れることなく発揮していただきたい.
もう1つ,医師には「自己犠牲を厭わぬ気概」が不可欠である.臨床の第一線にいる医師には,日常の私生活はあっても無きが如く忙殺されることが多い.患者さんは時間を選んで発病するわけではなく,休日であろうが深夜であろうが,時を選ばずに運び込まれてくる.八方塞がりという状況も確かにあるが,それでもなお他医との連携を図るなどの工夫をし,必ず対応していく「自己犠牲を厭わぬ気概」,そして前述した「恩返しの気持ち」とを兼ね備えた医師であって欲しい.
本書は竹内一夫先生による発刊(1979年)以来,脳神経外科学の基本となる原理・原則を中心に記述してきた.これらを皆さんの若い脳に,論理的に理屈を考えながら繰り返し徹底的に叩き込んでいただきたい.ひとつの領域の基本的な理解が深まれば深まるほど,身体他部の疾患についての把握もおのずと進むものである.
今後の医学・医療は予測を遥かに超えた進歩・発展を遂げ,大きく変貌していくであろう.しかし患者さんや人間社会に対する医師としての基本的姿勢や医学・医療の原理・原則は変わらないはずである.それらを保持しつつ,最初に挙げた5文字などに決して惑うことなく,「寒青(かんせい)」のごとく青々と,全身に気高い信念を漲らせ,往く道に日毎立ちはだかる難題に対し,蓄積した情報をもとに,常に自分の頭で考えて乗り切る工夫を重ねていく医師になることを願っている.
最後に,今回の改訂で主眼とした記述内容の大幅なスリム化へのご協力を賜った執筆者の先生方に心からの感謝を申し上げ,また本書の上梓に向けて,真摯に不断の努力を積み重ねてこられた医学書院の関係諸氏にも深甚なる謝意を表する.
2017年3月
監修者 児玉南海雄
目次
開く
総論
第1章 緒論
A 脳神経外科学
B 医の倫理
第2章 臨床解剖
A 頭蓋と頭蓋内腔構造
B 髄膜
C 大脳
D 脳幹・小脳
E 脳動脈
F 脳静脈
G 脳室およびくも膜下腔
H 脊柱
I 脊髄
第3章 神経学的検査法
A 患者さんの診察にあたって
B 神経所見のとりかた
C 脳神経の診かた
D 大脳の局在機能の診かた
E 脳幹の局在機能の診かた
F 小脳の局在機能の診かた
G 脊髄の局在機能の診かた
第4章 補助診断法
A 頭部単純X線撮影
B CT(コンピュータ断層撮影)
C MRI(磁気共鳴画像)
D 脳血管撮影・デジタル血管撮影
E 核医学検査
F 脊椎・脊髄の検査
G 神経超音波検査
H 脳波
I 誘発電位
J 腰椎穿刺
第5章 脳に特異な症候と病態
A 頭痛
B 精神症状と認知症
C けいれん(痙攣)
D 意識障害
E 運動麻痺
F 頭蓋内圧亢進
G 脳ヘルニア
H 血液脳関門と脳浮腫
I 脳循環代謝異常
各論
第6章 脳腫瘍
A 脳腫瘍とは
B 脳腫瘍の診断
C 脳腫瘍の鑑別診断
D 脳腫瘍の治療
E 神経上皮性腫瘍(神経膠腫)
F 髄膜腫
G 下垂体腺腫
H 神経鞘腫
I 頭蓋咽頭腫
J 胚細胞腫瘍
K 脊索腫
L 血管系腫瘍
M 原発性悪性リンパ腫
N 転移性脳腫瘍
O 頭蓋骨腫瘍と鑑別を要する疾患
第7章 脳血管障害
A 脳血管障害
B くも膜下出血
C 脳動脈瘤
D 脳動静脈奇形・その他の血管奇形
E 硬膜動静脈瘻
F 脳卒中の医療連携およびリハビリテーション
G 脳内出血
H 虚血性脳疾患(脳梗塞・一過性脳虚血発作)
I もやもや病
J 血管性認知症
K 脳血管内治療
第8章 頭部外傷
A 頭部外傷の臨床
B 重症頭部外傷の治療
C 頭皮の損傷
D 頭蓋骨損傷
E 脳の損傷
F 急性頭蓋内血腫(1):急性硬膜外血腫
G 急性頭蓋内血腫(2):急性硬膜下血腫
H 慢性硬膜下血腫
I 脳神経の損傷
J 頭部外傷後の感染症
K 小児頭部外傷
L 頭部外傷による脳血管障害
第9章 先天奇形
A 先天奇形とは
B 神経管閉鎖障害による奇形(1):二分脊椎
C 神経管閉鎖障害による奇形(2):二分頭蓋
D 大脳の奇形
E 後頭蓋窩の脳奇形
F くも膜嚢胞
G 頭蓋縫合早期癒合症・狭頭症
H 頭蓋頚椎移行部の奇形
I 神経皮膚症候群
第10章 水頭症
A 水頭症とは
B 小児の水頭症
C 胎児水頭症
D 正常圧水頭症(成人)
E 硬膜下液体貯留
第11章 機能的脳神経外科
A 機能的脳神経外科
B 頑痛
C 不随意運動症
D てんかん
E 定位脳手術
F 神経血管減圧(減荷)術
第12章 脊髄・脊椎疾患
A 頚椎変性疾患(変形性頸椎症・頚椎椎間板ヘルニア)
B 脊柱靱帯骨化症
C 腰椎椎間板ヘルニア
D 腰椎管狭窄症
E 脊髄腫瘍
F 脊髄硬膜外膿瘍
G 脊髄動静脈奇形
H 脊髄空洞症
I 脊椎・脊髄の外傷
第13章 末梢神経の外科
A 末梢神経障害の診断
B 末梢神経の外傷
C 絞扼性末梢神経障害
D 末梢神経の腫瘍
第14章 炎症性疾患
A 中枢神経系感染症とは
B 細菌性髄膜炎
C その他の髄膜炎
D ウイルス性脳炎
E その他のウイルス性脳炎・脳症
F 脳膿瘍
G 硬膜下膿瘍
H 脳寄生虫症
第15章 臨床医学の実習・研修の手引き
A 医師(良医)をめざして
B 脳神経外科実習の手引き
演習問題
演習問題・解答と解説
医師国家試験出題基準対照表
医学教育モデル・コア・カリキュラム対照表
索引
第1章 緒論
A 脳神経外科学
B 医の倫理
第2章 臨床解剖
A 頭蓋と頭蓋内腔構造
B 髄膜
C 大脳
D 脳幹・小脳
E 脳動脈
F 脳静脈
G 脳室およびくも膜下腔
H 脊柱
I 脊髄
第3章 神経学的検査法
A 患者さんの診察にあたって
B 神経所見のとりかた
C 脳神経の診かた
D 大脳の局在機能の診かた
E 脳幹の局在機能の診かた
F 小脳の局在機能の診かた
G 脊髄の局在機能の診かた
第4章 補助診断法
A 頭部単純X線撮影
B CT(コンピュータ断層撮影)
C MRI(磁気共鳴画像)
D 脳血管撮影・デジタル血管撮影
E 核医学検査
F 脊椎・脊髄の検査
G 神経超音波検査
H 脳波
I 誘発電位
J 腰椎穿刺
第5章 脳に特異な症候と病態
A 頭痛
B 精神症状と認知症
C けいれん(痙攣)
D 意識障害
E 運動麻痺
F 頭蓋内圧亢進
G 脳ヘルニア
H 血液脳関門と脳浮腫
I 脳循環代謝異常
各論
第6章 脳腫瘍
A 脳腫瘍とは
B 脳腫瘍の診断
C 脳腫瘍の鑑別診断
D 脳腫瘍の治療
E 神経上皮性腫瘍(神経膠腫)
F 髄膜腫
G 下垂体腺腫
H 神経鞘腫
I 頭蓋咽頭腫
J 胚細胞腫瘍
K 脊索腫
L 血管系腫瘍
M 原発性悪性リンパ腫
N 転移性脳腫瘍
O 頭蓋骨腫瘍と鑑別を要する疾患
第7章 脳血管障害
A 脳血管障害
B くも膜下出血
C 脳動脈瘤
D 脳動静脈奇形・その他の血管奇形
E 硬膜動静脈瘻
F 脳卒中の医療連携およびリハビリテーション
G 脳内出血
H 虚血性脳疾患(脳梗塞・一過性脳虚血発作)
I もやもや病
J 血管性認知症
K 脳血管内治療
第8章 頭部外傷
A 頭部外傷の臨床
B 重症頭部外傷の治療
C 頭皮の損傷
D 頭蓋骨損傷
E 脳の損傷
F 急性頭蓋内血腫(1):急性硬膜外血腫
G 急性頭蓋内血腫(2):急性硬膜下血腫
H 慢性硬膜下血腫
I 脳神経の損傷
J 頭部外傷後の感染症
K 小児頭部外傷
L 頭部外傷による脳血管障害
第9章 先天奇形
A 先天奇形とは
B 神経管閉鎖障害による奇形(1):二分脊椎
C 神経管閉鎖障害による奇形(2):二分頭蓋
D 大脳の奇形
E 後頭蓋窩の脳奇形
F くも膜嚢胞
G 頭蓋縫合早期癒合症・狭頭症
H 頭蓋頚椎移行部の奇形
I 神経皮膚症候群
第10章 水頭症
A 水頭症とは
B 小児の水頭症
C 胎児水頭症
D 正常圧水頭症(成人)
E 硬膜下液体貯留
第11章 機能的脳神経外科
A 機能的脳神経外科
B 頑痛
C 不随意運動症
D てんかん
E 定位脳手術
F 神経血管減圧(減荷)術
第12章 脊髄・脊椎疾患
A 頚椎変性疾患(変形性頸椎症・頚椎椎間板ヘルニア)
B 脊柱靱帯骨化症
C 腰椎椎間板ヘルニア
D 腰椎管狭窄症
E 脊髄腫瘍
F 脊髄硬膜外膿瘍
G 脊髄動静脈奇形
H 脊髄空洞症
I 脊椎・脊髄の外傷
第13章 末梢神経の外科
A 末梢神経障害の診断
B 末梢神経の外傷
C 絞扼性末梢神経障害
D 末梢神経の腫瘍
第14章 炎症性疾患
A 中枢神経系感染症とは
B 細菌性髄膜炎
C その他の髄膜炎
D ウイルス性脳炎
E その他のウイルス性脳炎・脳症
F 脳膿瘍
G 硬膜下膿瘍
H 脳寄生虫症
第15章 臨床医学の実習・研修の手引き
A 医師(良医)をめざして
B 脳神経外科実習の手引き
演習問題
演習問題・解答と解説
医師国家試験出題基準対照表
医学教育モデル・コア・カリキュラム対照表
索引
正誤表
開く
本書の記述の正確性につきましては最善の努力を払っておりますが、この度弊社の責任におきまして、下記のような誤りがございました。お詫び申し上げますとともに訂正させていただきます。