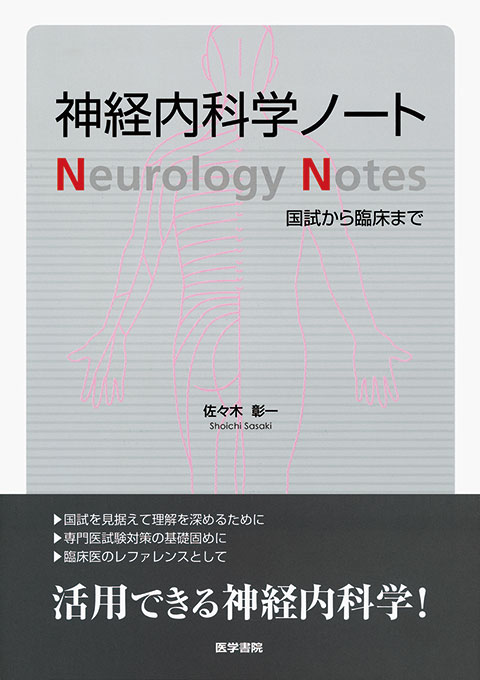神経内科学ノート
国試から臨床まで
神経内科学のツボをおさえた、ずっと使えるノート
もっと見る
医師国家試験から神経内科専門医試験にまで対応した、神経内科学のテキスト。知識のまとめをしやすくするため、本文は箇条書きとし、読みやすく調べやすい工夫をこらした。鑑別表や重要な疾患の検査画像を多数収載した上で、電子顕微鏡での珍しい組織写真も掲載。
| 著 | 佐々木 彰一 |
|---|---|
| 発行 | 2013年02月判型:B5頁:216 |
| ISBN | 978-4-260-01506-6 |
| 定価 | 4,180円 (本体3,800円+税) |
更新情報
-
更新情報はありません。
お気に入り商品に追加すると、この商品の更新情報や関連情報などをマイページでお知らせいたします。
- 序文
- 目次
- 書評
- 正誤表
序文
開く
序
筆者は30年以上にわたり、主に大学で神経内科の臨床と研究に携わってきた。その間、多くの学生や医師に、神経内科の最新の知見をわかりやすく伝え、また興味をもって学べるよう、心を砕いてきた。ひとつの神経学的事項を調べるために、あちこちから種々の参考書を取り出すのは億劫なものである。軽量で持ち運びが容易な1冊の本で、神経学の基礎から臨床までをカバーできるような書籍があれば便利であろうと思い、本書の執筆を思い立った。短時間で合理的に学べるように、写真、図および表などの視覚的な教材を多用して、簡潔な記述を補完した。国試や神経専門医試験の参考書として、また神経内科や関連各科の臨床医が座右において基礎的事項の見直しや確認をする際の便覧として、気軽に活用して頂くことを想定している。
本書は3章から成る。第I章「総論」では神経学の基礎を、第II章「神経学的診察」では実地臨床に必要な神経学的診察のポイントを、第III章「疾患各論」では主な神経疾患についての最新の知見を、それぞれコンパクトにまとめた。また、知っておいてほしい関連事項やトピックスを、 で記載した。
で記載した。
ハンディでコンパクトな書籍をめざしたために、記述が網羅的でなく、物足りなく感じる読者もいるかもしれないが、所期の目的に照らし、ご容赦願いたい。また、本書は単著のため、各章を相互に有機的に関連性をもたせて記述することができたと自負する反面、単著であるが故に、見過ごされた思い込みや記述の偏向があるかもしれない。今後諸兄のご指摘、あるいはご助言を賜れば幸甚である。
今から30年ほど前に、神経病理学を学ぶためにニューヨークに留学した。そのとき、モンテフィオーレ・メディカルセンターの平野朝雄教授から、「先生はALSの電顕をしなさい」と言われ、今日まで臨床のかたわらALSの電顕的検索を中心に研究を続けてきた。その間、平野先生ご夫妻にはいつも温かい心で接して頂き、また励まされ、公私にわたって大変お世話になった。今回も、本書を作成するにあたり、多大なご支援を賜ったことに、この場を借りて改めてお礼を申し上げたい。また、東京女子医科大学名誉教授岩田 誠先生には、数年間医局でご指導を仰ぎ、神経症候学を含む臨床神経学についての造詣の深さはもとより、自然科学の枠を越えて広く文化・芸術に通ずる該博な知識に圧倒された。今回、浅学非才の筆者が本書を書き上げることができたのは、ひとえに岩田先生が背中を押してくださったおかげであり、深謝申し上げる。
藤島英之氏に代表される医学書院のスタッフには、1年数か月に及ぶ長期間、気の遠くなりそうな訂正・加筆の依頼をその都度快く引き受けて頂き、本当に頭が下がる。プロ意識に心から敬意を表したい。
最後に、貴重な写真をご提供下さるなど、さまざまな面でご協力頂いた多くの先生方のご厚情に謝意を述べたい。
本書が神経内科学を学ぶ人達にとって少しでもお役に立てれば、筆者の望外の喜びで
ある。
2013年1月
佐々木彰一
筆者は30年以上にわたり、主に大学で神経内科の臨床と研究に携わってきた。その間、多くの学生や医師に、神経内科の最新の知見をわかりやすく伝え、また興味をもって学べるよう、心を砕いてきた。ひとつの神経学的事項を調べるために、あちこちから種々の参考書を取り出すのは億劫なものである。軽量で持ち運びが容易な1冊の本で、神経学の基礎から臨床までをカバーできるような書籍があれば便利であろうと思い、本書の執筆を思い立った。短時間で合理的に学べるように、写真、図および表などの視覚的な教材を多用して、簡潔な記述を補完した。国試や神経専門医試験の参考書として、また神経内科や関連各科の臨床医が座右において基礎的事項の見直しや確認をする際の便覧として、気軽に活用して頂くことを想定している。
本書は3章から成る。第I章「総論」では神経学の基礎を、第II章「神経学的診察」では実地臨床に必要な神経学的診察のポイントを、第III章「疾患各論」では主な神経疾患についての最新の知見を、それぞれコンパクトにまとめた。また、知っておいてほしい関連事項やトピックスを、
 で記載した。
で記載した。ハンディでコンパクトな書籍をめざしたために、記述が網羅的でなく、物足りなく感じる読者もいるかもしれないが、所期の目的に照らし、ご容赦願いたい。また、本書は単著のため、各章を相互に有機的に関連性をもたせて記述することができたと自負する反面、単著であるが故に、見過ごされた思い込みや記述の偏向があるかもしれない。今後諸兄のご指摘、あるいはご助言を賜れば幸甚である。
今から30年ほど前に、神経病理学を学ぶためにニューヨークに留学した。そのとき、モンテフィオーレ・メディカルセンターの平野朝雄教授から、「先生はALSの電顕をしなさい」と言われ、今日まで臨床のかたわらALSの電顕的検索を中心に研究を続けてきた。その間、平野先生ご夫妻にはいつも温かい心で接して頂き、また励まされ、公私にわたって大変お世話になった。今回も、本書を作成するにあたり、多大なご支援を賜ったことに、この場を借りて改めてお礼を申し上げたい。また、東京女子医科大学名誉教授岩田 誠先生には、数年間医局でご指導を仰ぎ、神経症候学を含む臨床神経学についての造詣の深さはもとより、自然科学の枠を越えて広く文化・芸術に通ずる該博な知識に圧倒された。今回、浅学非才の筆者が本書を書き上げることができたのは、ひとえに岩田先生が背中を押してくださったおかげであり、深謝申し上げる。
藤島英之氏に代表される医学書院のスタッフには、1年数か月に及ぶ長期間、気の遠くなりそうな訂正・加筆の依頼をその都度快く引き受けて頂き、本当に頭が下がる。プロ意識に心から敬意を表したい。
最後に、貴重な写真をご提供下さるなど、さまざまな面でご協力頂いた多くの先生方のご厚情に謝意を述べたい。
本書が神経内科学を学ぶ人達にとって少しでもお役に立てれば、筆者の望外の喜びで
ある。
2013年1月
佐々木彰一
目次
開く
口絵
I 総論
A 神経学の基礎知識
1 脳の画像(MRI, MRA, MRV)、頸椎・腰椎・筋のMRI
2 脳の解剖
3 頭蓋骨底の解剖(内側面)
4 硬膜と髄膜
5 脳の血管
6 神経組織の概略
7 神経細胞の形態と機能
8 二次的な遠隔効果
9 血液脳関門
10 血液神経関門
11 脳脊髄液
12 頭蓋内圧亢進所見
B 脳の機能解剖
1 大脳
2 脳幹
3 小脳
4 脳神経
5 脊髄
6 末梢神経
7 自律神経
8 筋
II 神経学的診察
A 神経障害の主要症状
1 意識障害
2 意識障害と鑑別を要する状態
3 脳死の判定基準
4 高次脳機能検査
5 遺伝性疾患の基礎的事項
6 脳神経
7 反射
8 病的反射(錐体路病変)
B 運動系の異常
1 錐体路徴候(上位運動ニューロン徴候)
2 不随意運動
3 歩行障害
4 筋萎縮
5 姿勢異常
6 錐体外路系の異常
C 感覚系の異常
1 感覚鈍麻、感覚消失
2 末梢神経性感覚障害
3 脊髄性感覚障害
4 脳幹性感覚障害
5 視床性感覚障害
6 大脳皮質性感覚障害
7 神経痛
D 小脳系の異常
E 自律神経系の異常
1 循環器系の自律神経機能検査
2 発汗障害
3 膀胱直腸障害
4 性機能障害
5 その他の自律神経障害
III 疾患各論
A 脳血管障害
1 脳梗塞
2 一過性脳虚血発作
3 可逆性脳血管れん縮症候群
4 脳出血
5 Binswanger病
6 抗リン脂質抗体症候群
7 CADASIL
8 CARASIL
9 アミロイドアンギオパチー
10 高血圧性脳症
11 くも膜下出血
12 脳動脈解離
13 脳動静脈奇形
14 内頸動脈海綿静脈洞瘻
15 慢性硬膜下血腫
16 海綿状奇形
17 もやもや病
18 線維筋性形成異常症
19 静脈洞血栓症
20 Fabry病
21 脊髄動静脈瘻
22 前脊髄動脈症候群
23 鎖骨下動脈盗血症候群
B 感染症
1 髄膜炎
2 スピロヘータ感染症
3 脳炎
4 辺縁系脳炎
5 遅発性ウイルス感染症
6 脳膿瘍
7 肥厚性硬膜炎
8 嚢虫症
9 脊髄炎
10 プリオン病
C 神経変性疾患
1 筋萎縮性側索硬化症、運動ニューロン疾患
2 大脳基底核変性疾患
3 脊髄小脳変性症
D 認知症
1 Alzheimer病
2 Lewy小体型認知症
3 前頭側頭型認知症、前頭側頭葉変性症
4 嗜銀顆粒性認知症
5 第17番染色体に連鎖する前頭側頭型認知症パーキンソニズム
6 正常圧水頭症
7 那須-ハコラ病
E 機能性疾患
1 頭痛
2 ナルコレプシー
F てんかん
1 てんかん発作の分類
2 検査
3 治療
G 脱髄性疾患、白質ジストロフィー(白質脳症)
1 多発性硬化症
2 視神経脊髄炎
3 Balo病(Balo同心円硬化症)
4 急性散在性脳脊髄炎
5 橋中心髄鞘崩壊
6 異染性白質ジストロフィー
7 副腎白質ジストロフィー
8 Krabbe病
9 Alexander病
H 筋疾患
1 炎症性ミオパチー
2 筋ジストロフィー
3 ミオトニア症候群
4 ミトコンドリア病
5 後天性代謝性ミオパチー
I 神経・筋接合部疾患
1 重症筋無力症
2 筋無力症性急性増悪(クリーゼ)
3 Lambert-Eaton症候群
4 小児型重症筋無力症
J 末梢神経障害
1 Guillain-Barré症候群
2 慢性炎症性脱髄性多発ニューロパチー
3 多巣性運動ニューロパチー
4 遺伝性運動感覚性ニューロパチー
5 代謝性ニューロパチー
6 癌性ニューロパチー
7 Crow-Fukase症候群(POEMS症候群、高月病)
8 小径線維ニューロパチー
9 Churg-Strauss症候群
10 亜急性脊髄視神経ニューロパチー
11 単神経障害
12 神経痛
13 絞扼性ニューロパチー
K 全身性疾患に伴う脳脊髄病変
1 可逆性後頭葉白質脳症
2 低酸素脳症
3 低血糖
4 基底核のマンガン沈着
5 サルコイドーシス
6 全身性エリテマトーデス
7 神経Behçet病
8 Sjögren症候群
9 橋本脳症
10 リウマチ性多発筋痛症
11 血管炎症候群
12 ポルフィリン症
L 中毒性障害
1 重金属中毒
2 有機物質による中毒
3 薬物中毒
4 その他の中毒
M 神経内科における禁忌事項
索引
I 総論
A 神経学の基礎知識
1 脳の画像(MRI, MRA, MRV)、頸椎・腰椎・筋のMRI
2 脳の解剖
3 頭蓋骨底の解剖(内側面)
4 硬膜と髄膜
5 脳の血管
6 神経組織の概略
7 神経細胞の形態と機能
8 二次的な遠隔効果
9 血液脳関門
10 血液神経関門
11 脳脊髄液
12 頭蓋内圧亢進所見
B 脳の機能解剖
1 大脳
2 脳幹
3 小脳
4 脳神経
5 脊髄
6 末梢神経
7 自律神経
8 筋
II 神経学的診察
A 神経障害の主要症状
1 意識障害
2 意識障害と鑑別を要する状態
3 脳死の判定基準
4 高次脳機能検査
5 遺伝性疾患の基礎的事項
6 脳神経
7 反射
8 病的反射(錐体路病変)
B 運動系の異常
1 錐体路徴候(上位運動ニューロン徴候)
2 不随意運動
3 歩行障害
4 筋萎縮
5 姿勢異常
6 錐体外路系の異常
C 感覚系の異常
1 感覚鈍麻、感覚消失
2 末梢神経性感覚障害
3 脊髄性感覚障害
4 脳幹性感覚障害
5 視床性感覚障害
6 大脳皮質性感覚障害
7 神経痛
D 小脳系の異常
E 自律神経系の異常
1 循環器系の自律神経機能検査
2 発汗障害
3 膀胱直腸障害
4 性機能障害
5 その他の自律神経障害
III 疾患各論
A 脳血管障害
1 脳梗塞
2 一過性脳虚血発作
3 可逆性脳血管れん縮症候群
4 脳出血
5 Binswanger病
6 抗リン脂質抗体症候群
7 CADASIL
8 CARASIL
9 アミロイドアンギオパチー
10 高血圧性脳症
11 くも膜下出血
12 脳動脈解離
13 脳動静脈奇形
14 内頸動脈海綿静脈洞瘻
15 慢性硬膜下血腫
16 海綿状奇形
17 もやもや病
18 線維筋性形成異常症
19 静脈洞血栓症
20 Fabry病
21 脊髄動静脈瘻
22 前脊髄動脈症候群
23 鎖骨下動脈盗血症候群
B 感染症
1 髄膜炎
2 スピロヘータ感染症
3 脳炎
4 辺縁系脳炎
5 遅発性ウイルス感染症
6 脳膿瘍
7 肥厚性硬膜炎
8 嚢虫症
9 脊髄炎
10 プリオン病
C 神経変性疾患
1 筋萎縮性側索硬化症、運動ニューロン疾患
2 大脳基底核変性疾患
3 脊髄小脳変性症
D 認知症
1 Alzheimer病
2 Lewy小体型認知症
3 前頭側頭型認知症、前頭側頭葉変性症
4 嗜銀顆粒性認知症
5 第17番染色体に連鎖する前頭側頭型認知症パーキンソニズム
6 正常圧水頭症
7 那須-ハコラ病
E 機能性疾患
1 頭痛
2 ナルコレプシー
F てんかん
1 てんかん発作の分類
2 検査
3 治療
G 脱髄性疾患、白質ジストロフィー(白質脳症)
1 多発性硬化症
2 視神経脊髄炎
3 Balo病(Balo同心円硬化症)
4 急性散在性脳脊髄炎
5 橋中心髄鞘崩壊
6 異染性白質ジストロフィー
7 副腎白質ジストロフィー
8 Krabbe病
9 Alexander病
H 筋疾患
1 炎症性ミオパチー
2 筋ジストロフィー
3 ミオトニア症候群
4 ミトコンドリア病
5 後天性代謝性ミオパチー
I 神経・筋接合部疾患
1 重症筋無力症
2 筋無力症性急性増悪(クリーゼ)
3 Lambert-Eaton症候群
4 小児型重症筋無力症
J 末梢神経障害
1 Guillain-Barré症候群
2 慢性炎症性脱髄性多発ニューロパチー
3 多巣性運動ニューロパチー
4 遺伝性運動感覚性ニューロパチー
5 代謝性ニューロパチー
6 癌性ニューロパチー
7 Crow-Fukase症候群(POEMS症候群、高月病)
8 小径線維ニューロパチー
9 Churg-Strauss症候群
10 亜急性脊髄視神経ニューロパチー
11 単神経障害
12 神経痛
13 絞扼性ニューロパチー
K 全身性疾患に伴う脳脊髄病変
1 可逆性後頭葉白質脳症
2 低酸素脳症
3 低血糖
4 基底核のマンガン沈着
5 サルコイドーシス
6 全身性エリテマトーデス
7 神経Behçet病
8 Sjögren症候群
9 橋本脳症
10 リウマチ性多発筋痛症
11 血管炎症候群
12 ポルフィリン症
L 中毒性障害
1 重金属中毒
2 有機物質による中毒
3 薬物中毒
4 その他の中毒
M 神経内科における禁忌事項
索引
書評
開く
170ページで神経内科学の全てを読む
書評者: 岩田 誠 (東京女子医科大学名誉教授/メディカルクリニック柿の木坂院長)
数年前に私の親しい友人で,長年の同僚である佐々木彰一先生から,学生向けの教科書を執筆中であると聞いた私は,これはきっと役に立つ素晴らしい教科書ができるに違いないと思った。私たちが共に働いてきた東京女子医科大学では,国家試験の受験を迎える最終学年の学生に対し,各領域の復習として補講を行ってきたが,それに際しては,学生たちにどの教師の講義を聴きたいかのアンケートをとり,その結果に従って補講カリキュラムを組んできたのだが,神経内科領域では毎年佐々木先生の希望が最多であり,いつも彼に講義をお願いしていた。佐々木先生から教科書執筆のことを聞いた途端に,このことを思い出し,その教科書の刊行を心待ちにしていたのである。
数日前,その教科書を佐々木先生自身から手渡されたとき,私はまず,グレイの落ち着いた表紙からなるスマートな外見に感心した。そしてページを繰ると,目に飛び込んでくるのは,実に美しいカラー図版の口絵である。佐々木先生は,大変に経験豊富,かつ優れた判断能力を持つ神経内科の臨床医であると同時に,ニューヨークのモンテフィオーレ・メディカルセンターにおいて平野朝雄先生の下で神経病理学を学ばれ,形態学の蘊奥を究めた研究者でもある。本書冒頭の口絵は,形態学者としての彼の面目躍如たるものであり,それを見ているだけでも,ほれぼれとする思いである。
本書における佐々木先生らしいもう一つの特徴は,神経解剖学を主体とした総論の章である。ここには,神経画像法によるマクロな形態から,彼の得意とする電子顕微鏡下の微細構造に至るまでの形態学が,明快な模式図とともに示されていて,極めてわかりやすい。それに続く神経学的診察の章も,常に解剖学的な理解の上に成立した症候学を展開している。私は,神経内科学における臨床活動の基礎は神経解剖学であり,形態学的な基礎のない臨床神経内科学は,机上の空論にすぎないと思っている。佐々木先生はそのような私の信念を最もよく知る仲間であるが,これら二つの章を,私たち二人の共通の信念に従って書かれたことに,私は大いに満足している。
さて,本書の後半は,各論としてさまざまな神経内科疾患について記載されているが,その膨大な領域に及ぶさまざまな疾患について,疾患概念,病理・病態,症候,検査所見,鑑別診断,治療,予後が実にコンパクトにまとめられている。このまとめ方は,かつて私がまだ若い神経内科医であったころに何度も繰り返し読んだ,Houston Merrittの『A Textbook of Neurology』を彷彿とさせる。私が読んだころの同書は,Merritt単著であり,神経内科疾患のみが簡潔な文章でわかりやすく記述されていた。考えてみると,Merrittはモンテフィオーレ・メディカルセンター神経内科主任を長く務めた方であり,それを考えると,佐々木先生のこの教科書にMerrittの教科書の面影が垣間見られたとしても不思議ではない。
本書を執筆していると私に語ってくれたとき,彼は学生向けの教科書を書いていますと言っていた。確かに,この教科書のわかりやすい記載と明快な図は,学生向けの教科書として書かれたことを物語っている。所々に挿入されている[Point]に示されたまとめや,指示記号で示された囲み記事のメモなどは,学生の勉強に大いに役立つに違いない。しかし,本書に記載されたさまざまな知識は,既に医師になった者にとっても大いに役立つ。神経内科専門医の認定試験に含まれる範囲のことは全て書かれているし,実際の臨床の現場での心覚えとしても常に座右に備えておきたい書物である。
わずか170ページ程度の書物の中で,神経内科学の全てをもれなく展開してくれた本書に,私は脱帽する。
書評者: 岩田 誠 (東京女子医科大学名誉教授/メディカルクリニック柿の木坂院長)
数年前に私の親しい友人で,長年の同僚である佐々木彰一先生から,学生向けの教科書を執筆中であると聞いた私は,これはきっと役に立つ素晴らしい教科書ができるに違いないと思った。私たちが共に働いてきた東京女子医科大学では,国家試験の受験を迎える最終学年の学生に対し,各領域の復習として補講を行ってきたが,それに際しては,学生たちにどの教師の講義を聴きたいかのアンケートをとり,その結果に従って補講カリキュラムを組んできたのだが,神経内科領域では毎年佐々木先生の希望が最多であり,いつも彼に講義をお願いしていた。佐々木先生から教科書執筆のことを聞いた途端に,このことを思い出し,その教科書の刊行を心待ちにしていたのである。
数日前,その教科書を佐々木先生自身から手渡されたとき,私はまず,グレイの落ち着いた表紙からなるスマートな外見に感心した。そしてページを繰ると,目に飛び込んでくるのは,実に美しいカラー図版の口絵である。佐々木先生は,大変に経験豊富,かつ優れた判断能力を持つ神経内科の臨床医であると同時に,ニューヨークのモンテフィオーレ・メディカルセンターにおいて平野朝雄先生の下で神経病理学を学ばれ,形態学の蘊奥を究めた研究者でもある。本書冒頭の口絵は,形態学者としての彼の面目躍如たるものであり,それを見ているだけでも,ほれぼれとする思いである。
本書における佐々木先生らしいもう一つの特徴は,神経解剖学を主体とした総論の章である。ここには,神経画像法によるマクロな形態から,彼の得意とする電子顕微鏡下の微細構造に至るまでの形態学が,明快な模式図とともに示されていて,極めてわかりやすい。それに続く神経学的診察の章も,常に解剖学的な理解の上に成立した症候学を展開している。私は,神経内科学における臨床活動の基礎は神経解剖学であり,形態学的な基礎のない臨床神経内科学は,机上の空論にすぎないと思っている。佐々木先生はそのような私の信念を最もよく知る仲間であるが,これら二つの章を,私たち二人の共通の信念に従って書かれたことに,私は大いに満足している。
さて,本書の後半は,各論としてさまざまな神経内科疾患について記載されているが,その膨大な領域に及ぶさまざまな疾患について,疾患概念,病理・病態,症候,検査所見,鑑別診断,治療,予後が実にコンパクトにまとめられている。このまとめ方は,かつて私がまだ若い神経内科医であったころに何度も繰り返し読んだ,Houston Merrittの『A Textbook of Neurology』を彷彿とさせる。私が読んだころの同書は,Merritt単著であり,神経内科疾患のみが簡潔な文章でわかりやすく記述されていた。考えてみると,Merrittはモンテフィオーレ・メディカルセンター神経内科主任を長く務めた方であり,それを考えると,佐々木先生のこの教科書にMerrittの教科書の面影が垣間見られたとしても不思議ではない。
本書を執筆していると私に語ってくれたとき,彼は学生向けの教科書を書いていますと言っていた。確かに,この教科書のわかりやすい記載と明快な図は,学生向けの教科書として書かれたことを物語っている。所々に挿入されている[Point]に示されたまとめや,指示記号で示された囲み記事のメモなどは,学生の勉強に大いに役立つに違いない。しかし,本書に記載されたさまざまな知識は,既に医師になった者にとっても大いに役立つ。神経内科専門医の認定試験に含まれる範囲のことは全て書かれているし,実際の臨床の現場での心覚えとしても常に座右に備えておきたい書物である。
わずか170ページ程度の書物の中で,神経内科学の全てをもれなく展開してくれた本書に,私は脱帽する。
正誤表
開く
本書の記述の正確性につきましては最善の努力を払っておりますが、この度弊社の責任におきまして、下記のような誤りがございました。お詫び申し上げますとともに訂正させていただきます。