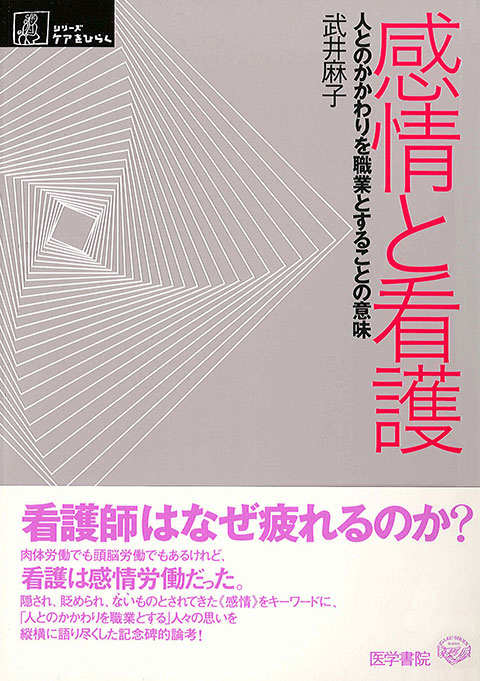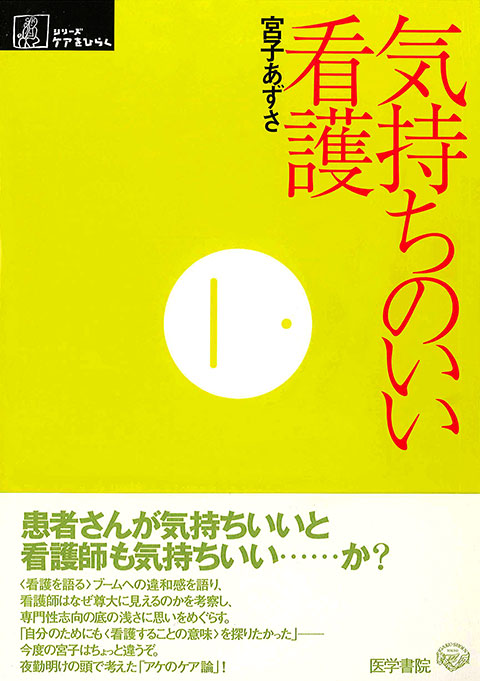ケアってなんだろう
「技術としてのやさしさ」を探る対話。
もっと見る
「ケアの境界」にいる専門家、作家、若手研究者らが、精神科医・小澤勲氏に「ケアってなんだ?」と迫り聴く。「ほんのいっときでも憩える椅子を差し出す」のがケアだと言い切れる人の《強さとやさしさ》はどこから来るのか――。感情労働が知的労働に変換されるスリリングな一瞬! 〔対話者〕田口ランディ(作家)、向谷地生良(べてるの家)、滝川一廣(精神科医)、瀬戸内寂聴(作家)、西川勝(看護/臨床哲学)、出口泰靖(社会学)、天田城介(社会学)。
| シリーズ | シリーズ ケアをひらく |
|---|---|
| 編著 | 小澤 勲 |
| 発行 | 2006年05月判型:A5頁:304 |
| ISBN | 978-4-260-00266-0 |
| 定価 | 2,200円 (本体2,000円+税) |
更新情報
-
更新情報はありません。
お気に入り商品に追加すると、この商品の更新情報や関連情報などをマイページでお知らせいたします。
- TOPICS
- 目次
- 書評
TOPICS
開く
●『シリーズ ケアをひらく』が第73回毎日出版文化賞(企画部門)受賞!
第73回毎日出版文化賞(主催:毎日新聞社)が2019年11月3日に発表となり、『シリーズ ケアをひらく』が「企画部門」に選出されました。同賞は1947年に創設され、毎年優れた著作物や出版活動を顕彰するもので、「文学・芸術部門」「人文・社会部門」「自然科学部門」「企画部門」の4部門ごとに選出されます。同賞の詳細情報はこちら(毎日新聞社ウェブサイトへ)。
目次
開く
I部 向かいあって考える■対談
ケアと異界(×田口ランディ)
「当事者の時代」に専門家はどこに立つのか(×向谷地生良)
情動・ことば・関係性(×滝川一廣)
病いを得るということ(×瀬戸内寂聴)
II部 若手研究者が考える■インタビュー+論文
「私」はどこにいるのか(×西川勝)
小澤勲はカッコいい
なんてわかりやすい人たち(×出口泰靖)
具体の人、小澤勲
治らないところから始める(×天田城介)
小澤勲の生きてきた時代の社会学的診断
III部 認知症を生きるということ■公開講座より
IV部 「ぼけ」を読む■認知症高齢者をかかえる家族への手紙
少し長いあとがきと「遺言」、そして感謝
書評
開く
書評(雑誌『看護教育』より)
書評者:桑田 美代子(青梅慶友病院看護介護開発室長,老人看護専門看護師)
書評を見る閉じる
高齢者ケアの現場のみならず,「ケア」という言葉は,それを耳にしない日がないほど頻繁に使われている。しかし,この言葉を聞いて,誰もが同じことをイメージし,具体的に説明できるのか疑問に感じるときがある。それはスタッフはじめ,実習生の場合も同様であり,じつは筆者自身も“ケアってなんだろう”と自問自答するときが少なくない。本書が発行されたとき,編著者である小澤勲氏の考える「ケア」とは何かを知りたい,そして自分なりのケアを説明するヒントを得たいと思った。
本書は小澤氏による「少し長いまえがき―この本のなりたち」からはじまる。続くI部は,田口ランディ氏,向谷地生良氏,滝川一廣氏,瀬戸内寂静聴氏ら4名との対談「向かいあって考える」,II部は,西川勝氏,出口泰靖氏,天田城介氏ら3名の若手研究者が小澤氏にインタビューし,それを受けての彼らの論文が記された「若手研究者が考える」,III部は,小澤氏自身が講演をした種智院大学での公開講座「認知症を生きるということ」,IV部は,認知症高齢者をかかえる家族への手紙「『ぼけ』を読む」,最後に「少し長いあとがきと『遺言』,そして感謝」という構成になっている。
これらのどの頁にも,“ケアってなんだろう”と自問自答する筆者にとって“珠玉の言葉”が散りばめられていた。小澤氏の言葉だけでなく,対談者によって話される内容にも新たな発見や刺激を受けた。特に若手研究者がインタビュー後に小澤氏を語る「論文」には,筆者に欠けていた視点や分析,ケアとは何かを考えるエッセンスが凝縮されていたのである。
小澤氏はこれまで認知症関連の執筆をし,注目を浴びてきた。今回も主に認知症を通して語られてはいるが,本質は認知症ケアにとどまらず,より広い視野からケアについて語られている。看護大学で非常勤の臨床教授を務める筆者は,本書を看護教育の場においても大いに活用できると考えている。看護基礎教育のなかで語られるケア,認定看護師教育のなかで語られるケア,そして,専門看護師教育のなかで語られるケアなど,ケアの本質は同じであるが,その質は異なるからだ。筆者自身は,高齢者ケアのスペシャリストとして,ケアの質をさらに追求しなければならないと強く感じている。
看護界全体を見渡してみると,産業界と同じように効率性・標準化を求めるあまりに,大切な何かを忘れているように思う。本書は,その置き忘れた大切なものが何かを思い出させてくれる。それらは本来,看護基礎教育の段階から教育される「看護の基盤」になり得るものである。もう一度,自分なりにケアを考え直し,自分の言葉で具体的に伝えケアを実践してみる。また,それらを皆で共有し,より豊かなケアにする努力が必要である。そうすることで〈技術としてのやさしさ〉を教育する第一歩になると思う。
最後の「少し長いあとがきと『遺言』,そして感謝」は,小澤氏が自らの経験を通し,今後の認知症ケアに対する示唆と願いを込めて書かれた。そして,『ケアってなんだろう』というタイトルどおり,もう一度,自分なりのケアとは何かを考える機会を与えてくれている。
(『看護教育』2006年10月号掲載)
「プロとしてのやさしさ」を再考したい人へ (雑誌『看護学雑誌』より)
書評者:水戸 美津子(自治医科大学看護学部老年看護学教授・看護学部長)
書評を見る閉じる
この本の構成はユニークだ.《少し長いまえがき》と《少し長いあとがきと「遺言」,そして感謝》の間に,4つのセクションがはさまれている.
第I部は田口ランディ(作家),向谷地 生良(ソーシャルワーカー),滝川 一廣(精神科医),瀬戸内 寂聴(作家,僧侶)という異色の4人と小澤氏との対談である.第II部は西川 勝(看護師,臨床哲学),出口 泰靖(社会学),天田 城介(社会学)という3人の若手研究者によるインタビューと,彼らから小澤氏への果敢なる挑戦あるいは畏れともとれる論文が続く.第III部は小澤氏自身の公開講座の記録,第IV部には「ぼけ」をテーマにした文学作品を紹介した随筆風文章が並んでいる.
読後,心地よく深い哲学的思考にとらわれた.「失われたケア」とでも表現したくなるほどの高齢者ケアの場――なかでも認知症高齢者のケアの場――のさびしい現状と,それとは反対に地味に黙々とさりげなく「やさしい」ケアを実践している数少ない人たちに思いを馳せた.まさに「ケアってなんだろう」と冷静に自問自答し,自分に課せられた職業人生の課題をも見出すことができるパワーのある本である.
小澤氏は,バランスのとれたケアを実践するには「感性を求めるのではなく,技術としてのやさしさを求めたほうがよい」として,次のように言う.
《いまは「感情労働」がひじょうに強く求められていますよね.それをひとことで言うと「やさしくあれ」ということだと思います.ただスタッフは,仕事がうまくいかないと,自分はやさしくない,ケアには向いていないというように思ってしまう人がいるんですよね.熱心であればあるほど》(p.147)
《どうすればやさしくなれるかという技術を伝えたつもりです.その人のかかえている不自由さをきちんと伝えて「そこでどうするかあなた考えてみて」と言いました.つまり感情労働としてではなく知的な労働としてやさしさをとらえていました.やさしさをやさしさとして求めるのではなく》(p.148)
つまり「介護・被介護という固い関係が一時でも解けて,直接的で暖かな人と人との関係が現出するケア」は,「技術としてのやさしさ」が成立したときに実現するのだろう.プロとしてのやさしさ,専門職としてのやさしさについて再考させられた.
ケアを再考する大きな道筋を提示された気がして,久方ぶりに元気の出る書物に出会った.それは,内容のみならず本の装丁からも受けるもので,表紙の寺子屋の写真は読者に大きな余韻を残す.
対談・インタビューの部分は特に含蓄のある言葉が多く,意味を解釈するのにしんどい部分もあるが,プロとしてのケアを再考したい人にはぜひ読んでいただき,そしてじっくりと眺めてほしい一冊である.
「かけがえのなさ」という軸からぶれない,かっこよさ
書評者:釈 徹宗(如来寺住職/龍谷大学講師(宗教思想)/グループホーム「むつみ庵」代表※1)
書評を見る閉じる
「よっ,スガレてるねぇ!」
落語でよく「スガレている」という表現が出てくる。「よっ,いいねぇ。スガレてて」などと使う。粋でナチュラルで様子がよいサマのことを言う。どうやら「素枯れている」と書くらしい。この本の第III部では,小澤氏の公開講座での講演録が記載されている。小澤氏の視点を理解するのによいテクストである。良寛さんの歌を引用しながら老いを語るあたりがとてもいい雰囲気だ。素枯れている。
本書は,四部構成になっていて,第I部では小澤勲氏が田口ランディ氏,向谷地生良氏,滝川一廣氏,瀬戸内寂聴氏という多彩な4氏と対談。第II部は若手研究者3氏との対談で,彼らの小澤論も添付されている。
「ケアプランはあまり意味がない」「統合失調症の人には,健常者になることへ恐怖がある」「認知症の人はきわめてわかりやすい人」「痴呆予防論はうさんくさい」などなど,一般的なケア理論の枠組みを揺さぶる言葉が飛び交う。
刺激的でありながら,楽である
この本を読んで,『言葉がもつ力』をあらためて実感した。自分の概念を揺さぶられる言葉に出会うと,(現実には何ひとつ問題は解決していないのに)なんだか楽になるのである。
小澤氏は,何度か「周辺症状は,まあなんとかなる」と語っている。おいおい,ほんとかよ,という感じである。なにしろ認知症高齢者介護の現場では,まさにその「周辺症状」2の対応に追い回されているのである。
しかし,小澤ケア論の視点は問題行動ではなく,《問題行動を生み出すメカニズム》にある。常に,なぜその行動が生じるのか,という仕組みを読み解こうとする。
本書で語られている小澤氏のメカニズム解析が本当に正解なのかどうかわからないけど,「周辺症状って……,なんとかなるかも……」という気になってくる。オルタナティブな(別方向の)アプローチが提示されるからである。新たなストーリーが切り開かれるということは,漠然と形成してしまっている図式を解体することでもある。それが介護の現場で,どれほど重要なことであるかは言を待たない。
寄り添いながらも,プラグマティックである
対談では,すごくラディカルな視点が次々と提示されるのに,なぜか奇をてらった感じがしない。違和感がない。なぜだろうと考えてみて,ここに登場している人たちがみんな「かけがえのなさ」というところから軸がブレていないからじゃないかと思い至った。
たとえば,『認知症高齢者という無名の存在へとひとくくりにされてしまうこと』に抵抗し,『その人その人の物語』に寄り添おうとする姿勢を随所に確認することができる。寄り添いながら,それでいてプラグマティックだ。そこがしびれる。素敵だ。本物の言葉はやっぱりかっこいい。
その人に寄り添うということは,その人の物語にシンクロすることである。小澤氏は,「島から来た人が入所したら,ぼくはその島を知らなかったので,船でその島に行ってきました。ああ,こういう島なんやなと。あるいは,金光教の信者が入ってきたから,どんなやろうなと三原から近かったので金光教の本部まで行ってきたりして」(頁157)と語っている。
これである。症状や行動に眼を奪われることなく,その裏に広がる物語を読み解こうとする態度だ。自分の来歴を知っている人がどんどん少なくなっていくことの寂しさや苦しさをよく知っている者の発想だ。
私たちはみんな,何らかの物語の中に生きている。でもその物語に耳を傾けようとする者がいなければ,生を持続することは困難だ。逆にいえば,耳を傾けてもらえる者がいれば,そこは生きていける場なのである。ケアとは生きることと正しく向き合うスキルなのかもしれない。
※1 評者の釈 徹宗氏は,グループホーム「むつみ庵」代表として認知症高齢者のケアにも当たっている。また昨年発行された内田樹氏との共著『インターネット持仏堂〈1〉〈2〉』(本願寺出版社)が話題を呼んだ。
※2 認知症の症状は,「記憶障害」「見当識障害」「判断力の低下」などの中心となる症状(中核症状)と,「妄想」「異食」「徘徊」などの中核症状に伴って起こる問題行動(周辺症状)に大別される。
現場で頭と心を悩ませる者の胸に届いてくる言葉(雑誌『訪問看護と介護』より)
書評者:藤井 博之(柳原リハビリテーション病院院長)
書評を見る閉じる
どうすればよいケアができるか,が本書のテーマ。『痴呆を生きるということ』『認知症とは何か』(ともに岩波新書)の著者による「ケアする人のケア」の本です。
「すべてのスタッフが,すべての場面でやさしくなれるわけではない。そこをどうするかが問題なのだ」,「感性を求めるのではなく〈技術としてのやさしさ〉を求めたほうがよい」。医療とケアの現場で著者がこだわってこられた考え方,臨床の方法がつぎつぎと語られ,現場で頭と心を悩ませる者の胸に言葉が届いてくる。そういう本です。
「障害」の回復をめざす人々のリハビリテーション施設で働く私にとっても,刺激的な本でした。それは,脳卒中等による「認知障害」をもつ方をどう援助するか,に関係します。
身体がきかないだけでなく,言葉が話せない・理解できない,あるいは見えている空間の一部や自身の半身を自分の世界として捉えられない,でも記憶力や理解力は確かな場合も多い。こうした症状には失語・失行・失認などの神経心理学的な名前があり,それらが「認知障害」と総称されます。
この「認知障害」は,じつはなかなか手ごわいのです。治りにくいことがある,機能訓練がしにくいなど,理由はいくつもあります。
なかでも,スタッフが利用者を理解すること,これはケアの出発点となるはずですが,それが簡単でないのです。利用者が何をしたいか,何ができて何をできないか,何がわかって何がわからないか,心の中でそれがどんな意味をもつか,共感して理解するのに援助者は苦労します。
動作能力の再獲得に本人は苦労することもあって,ありきたりの「リハビリ訓練」では歯が立たないことも多いのです。利用者のかかえる「障害」を神経心理学的用語で正確に捉えることも必要ですが,それだけでは十分ではありません。
どう理解するかには,当事者の言葉が参考になります。リハビリテーションに取り組んでいる時を振り返って,ある知人は「トンネルの中を行くようだった」,「この自分で生きていくしかない。そう思うのに3年かかった」と語ってくれました。体験者のこうした言葉を聴くことが「障害」をもつ人に共感するヒントになるかもしれない。そう考えていた時,「物語としての痴呆ケア」という著者の言葉に出会いました。
ああそうだ,「認知症」(痴呆症)のケアと「認知障害」のリハビリテーションは,やっぱりつながっている。そう思ったのです。
いわゆる「認知症」と「認知障害」は違います。でも「認知障害」の方のリハビリテーションと「認知症」の方のケアに共通の課題があるのは,お察しの通りです。
著者は,「自閉症」,不登校,ひきこもり,「統合失調症」,「感情病」,「認知症」という広い分野に亘って「臨床の中心的対象を,人生の段階を順に踏んで」こられた精神神経科の医師です。本書のあとがきで,「認知症」を構成する症状について失語・失行・失認など神経心理学的な概念を使って考察されているのは,実は興味深いことです。
さて私がすっかりいい気になって「物語としてのリハビリテーション」のことを考えながら本書を読んでいたら,次のような警句?が用意されていて,どきっとしました。
「自分の物語を語ることで生き生きとした表情になる方も多いのですが,その一方で,物語を読むという行為が相手を傷つける可能性も高いということを,やはりどこかで考えておかないと。人が人の物語を読むということは傲慢な行為です。」
「ケアってなんだろう」と考え込むことのある人なら,きっとこんなふうに,どきどきわくわくしながら読み通してしまう,お薦めの一冊です。
(『訪問看護と介護』2006年8月号掲載)
【特別寄稿】こまやかなまなざしと「棒の如き」思索― 『ケアってなんだろう』を読む (『週刊医学界新聞』より)
書評者:鷲田 清一(大阪大学副学長/臨床哲学)
書評を見る閉じる
「精神科の松田道雄」。小澤勲という医師に対してわたしが抱いてきたイメージはそのようなものである。
それぞれ小児科,精神科の医療のあり方について根本的な疑問をもち,医療の裾野にいる子ども・患者のいちばん近くで,ということはずっと在野で,医療の専門家でありながら医学の外の知にたっぷりと触れ,独りで時代の医療体制に対して思想闘争を仕掛け,後年は「老い」の生きがたさに身を挺して,一方は安楽死の是非について,一方は認知症への取り組みについて,ひとびとの眠りを覚ますような本質論を展開する。
それを問題としているわれわれ,という論点
長らく「痴呆」とよばれ,いまは「認知症」とよばれる症状と,それにともなうさまざまの「問題行動」には,まずは当事者自身がもがき苦しみ,介護者のほうはその堂々めぐりの介護に翻弄されて疲れきり,ほんのときたまその憔悴のなかでそれこそ僥倖のようにかぼそい一条の光にふれるといった経験を,果てしなくくりかえしてきた。
もちろんその光についにふれえなかった経験こそ無数にある。が,ごく身近なひとが「崩れてゆく」あるいは「消えてゆく」ことの衝撃のなかで,「問題行動」を「問題」としているわれわれの側の事情に眼を研ぎすませていったひとも少なくない。
どうしても納得できない,腑に落ちないという思いをひとびとが重く抱え込むなかに,小澤勲氏の認知症論の連作が世に出た。『痴呆を生きるということ』『認知症とは何か』(いずれも岩波新書)である。
これらの著述のなかで小澤氏は,認知症を病むひとたちはいったいどのような「不自由」(生きがたさ)と抗い,その抗いに挫けるなかでみずからどのような解決を図っているのかを説き,ではそのような状態のなかにある人にどのように向きあえばよいのか,その向きあいをとおしてわたしたちに迫られているものはなにかといった(問題というより)課題について,細部にきめこまやかなまなざしを届けながらもきわめて骨太な,著者の言葉を借りれば「棒の如き」思索を提示した。
「緊急対談」といった面もちも
だからこれらの書物は,認知症をどのようにとらえたらいいのか思い悩んできた家族や介護スタッフ,介護をどのような「文化」として育て,組み立てていかねばならないかを現場で呻吟しつつ模索してきたひとびとの関心を,ぐいと引き寄せた。
その引き寄せられた関心を,小澤氏にじかにぶつけ,そこから「認知症」への取り組みを「文化」として広げ,深める,そんな「緊急対談」のような面もちが,このたび編まれた対話録『ケアってなんだろう』(医学書院)には立ちこめる。
この本は,主に四つの対談と三つのインタビューと二つの講演記録からなる。対話の相手にいわゆる「認知症の専門家」はいない。が,そのことで逆に認知症という主題の,〈文化〉の,あるいは〈社会〉の問題としての,広がりや深みがおのずと浮かび上がってくる。
対談の相手は,田口ランディ(作家),向谷地生良(浦河べてるの家),滝川一廣(精神科医),そして瀬戸内寂聴の各氏。小澤氏にインタビューし,それぞれに気合いの入った小澤論を展開するのが,西川勝(看護師),それに出口泰靖,天田城介という気鋭の「ケアの社会学」者である。
「美しい物語」に昇華することを拒む
認知症というものにふれる地点が,角度が,それぞれの履歴の違いからさまざまであるので,ときに正面衝突になったり,微妙なすれちがいになったりもするが,言葉に緩みはない。遠く隔たった場所で,言葉の肌理は異なるが深い共感がこだまするといった気配が濃い。
これらの対論はどれも,認知症の切なさ,しんどさへの深い思いやりを湛えながらも,認知症の苦しみというものをまとまりよく解釈し,回収することを拒んでいる。辛抱強い対論のなかから浮かび上がってくるのは,たとえばつぎのような論点であり,提言である。
「そもそも人は理解が届かなければ人と関係を結び,人を慈しむことができないわけではない」。だから「やさしくあれ」「受容せよ」というふうにケアの〈感性〉を求めるのでなく,〈技術としてのやさしさ〉を求めたほうがよい。
「すばらしい介護」を賞賛しすぎることはときに別の当事者・介護者を傷つけたり,介護の困難を「美しい物語」へと昇華したりする危うさを孕む。だからむしろ,ケアの技術を「財産」としてどのように蓄積していくかの工夫が必要となるのだが,ただしそこに(たとえば「できる/できない」でひとを分ける地平をどのように超えてゆくのかといった)「思想」がなければ,きっとどこかで潰れてしまう。
認知症を病む人は,まわりの世界とのギャップに直面して取り繕いにしがみつかざるをえないのにその取り繕いができないでついに「異常行動」を訴えることになるが,そのギャップははたしてつねに小さくしなければならないものなのか,むしろ人としてそれを守り育てなければならないこともあるのではないか。
認知症においては,認知能力は落ちても感情は崩れない(「人の名前がわからなくなったりしても,『とても親しい人だ』ということはどこかでわかっています」)。そして情動は共同性のなかで育まれる。じっさい,彼らを取り囲む地域が「脆弱」であることがときにプラスに作用することもあるわけで,「在宅で何かをしようというとき,完璧を目指すと絶対に駄目です」。
負け試合に,エールを送りつづけるひと
これらの問題をめぐる応酬のなかから見えてくるのは,介護の現場の切なさであり,しんどさであり,危うさである。切なさに寄り添うなかでけれどもけっして「美しい物語」に昇華しない。しんどさに向きあうなかでそれがほんとうは介護者みずからのしんどさでもあることに気づき,制度の不具合をしっかり把握する。介護者の無意識の欲望がうごめきだすその危うさをしっかり見届けるために,見たくないものも逸らさずに見る……。
小澤氏と語りあった面々に共通しているのは,「異常な状況に異常な反応をするのは正常である」(V・E・フランクル)という信念であり,彼らがこぞって求めているのは,(認知症を病む人たちの「問題行動」ではなく)その「状況」のほうの異様さをどう解決するかという課題である。そうわたしは受けとめた。
最後に,インタビュアーの一人が活写している小澤勲氏のある姿を。
小澤氏が若いころ応援団員だったというのは意外だが,以前,『物語としての痴呆ケア』の出版記念パーティで,出席者への返礼として最後に壇上からエールを送った。
「小澤さんの病状を知るものには信じがたいものだった。前ボタンをはずした背広は,左右に跳ぶ体に羽のような動きをつける。拳を突き出し,足を踏みしめ,腕は大きく円弧を描く。……医師として精神科医としての小澤さんは,多くの患者たちが人生の負け試合に出会ったときにも,あの凛とした眼差しでエールを送りつづけたのだろう」
認知症とその介護の,重さと限界,そのなかでときに全身から力が抜けるほどほっとし,また笑い転げるかりそめの時をはさみながら,果てしのない時間をそれでも前へとくぐってゆく,その人たちすべてに向けたエールだったにちがいない。
(『週刊医学界新聞』第2692号に【特別寄稿】として掲載)