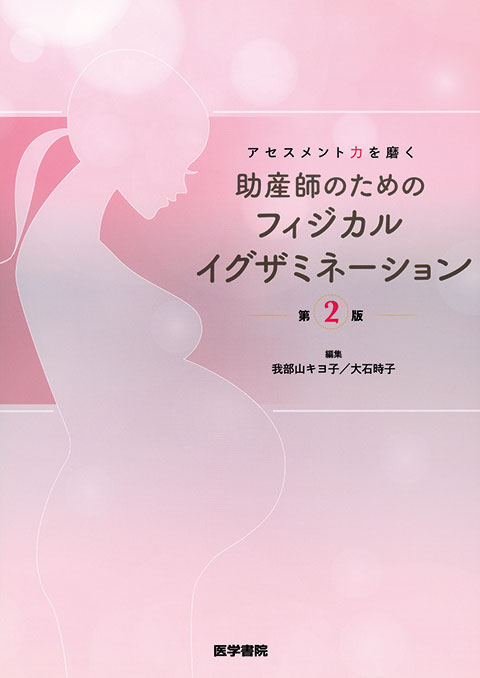アセスメント力を磨く
助産師のためのフィジカルイグザミネーション 第2版
助産師に必要なフィジカルイグザミネーションを網羅した待望の改訂版!
もっと見る
助産師に必要なフィジカルイグザミネーションについて、技術と基礎知識を網羅して好評を博した書籍の改訂版。オールカラーでさらに図版が見やすくなったほか、CLoCMiP(助産実践能力習熟段階レベルIII認証制度)を踏まえ、呼吸・循環器系、脳神経系、代謝系の異常に関する章を新設。さらに各章でハイリスクについて言及し、正常・異常の判断に関わるアセスメントの解説も充実させた。
更新情報
-
更新情報はありません。
お気に入り商品に追加すると、この商品の更新情報や関連情報などをマイページでお知らせいたします。
- 序文
- 目次
- 書評
- 正誤表
序文
開く
第2版 まえがき/本書の目的と構成
第2版 まえがき
本書初版の発行から10年が経過した。出産難民が社会現象化していた当時からすると,周産期医療の危機的状況はやや落ち着きを取り戻したかにみえるが,課題はいまだ山積している。すなわち,晩婚化・晩産化はますます進行し,30歳以上の出産は64.3%(35歳以上の出産は28.1%,いずれも2015年)となり,体外受精児は19人に1人(2015年),麻酔分娩や帝王切開分娩の増加,低出生体重児の出生割合の高止まり,児童虐待相談件数の激増など,母児ともにハイリスクな傾向は加速している。
一方,2000年代初頭,少子化に端を発した分娩取扱施設の廃止の動きが顕著となり,産婦人科・産科を標榜する施設数および産科医は,現在でも年次ごとに減少傾向が続いている。このような社会背景から,2015年日本産科婦人科学会は深刻化する産科医不足への対応策として,地域の基幹病院に産科医を集約化し,医師一人ひとりの負担を減らすとともに,24時間安心して出産できる場所を確保することを柱とした行動計画をまとめた。この計画には,高い能力をもつ助産師の育成も盛り込まれている。また,同時期に日本助産実践能力推進協議会は,助産実践能力が一定水準に達していることを客観的に評価する仕組みとして,助産実践能力習熟段階(CLoCMiP)レベルIII認証制度を創設し,運用を開始した。
このような周産期医療の背景を踏まえて,助産師に求められる実践能力も変化してきている。すなわち,従来はローリスク妊産褥婦・新生児を主な対象としていた助産師であるが,それに加えて,ハイリスク妊産褥婦・新生児の増加に伴い,正常からの逸脱の診断を適時にかつ正確に行い,早い段階で医師の診察を促し,協働して母子の安全・安心を守ることがより一層求められるようになってきた。そこには,従来にもまして高いフィジカルイグザミネーション能力とアセスメント能力が求められている。
それは単に診察(フィジカルイグザミネーション)をして身体情報を集め,正常・異常のアセスメントをするだけでなく,鑑別診断に向かってさらにどのような診察や検査が必要であるかも思考し,実施し,臨床推論をできるだけ進めていく能力である。そのことによって必要な情報を必要な専門職に,迅速かつ的確に提供し,チーム医療の力を発揮することができる。
第2版ではこれらを踏まえて,新しい知見や基準を加筆するとともに,妊娠期・分娩期・産褥期の異常,ハイリスク妊産褥婦についての解説を充実させ,「助産師が知っておきたい異常(呼吸器・循環器系,脳神経系,代謝系)」,早産児・低出生体重児等「新生児のフィジカルイグザミネーション」を新設した。
加えて「周産期のウィメンズヘルス」として,子宮頸がん,性感染症,乳腺疾患・乳がん,配偶者からの暴力(DV)などもフィジカルイグザミネーションとアセスメントの視点から取り上げ,詳述している。検査法についても新国家試験出題基準を反映して,腟鏡診,顕微鏡診等を取り入れた。
また,豊富な写真とイラストを使用した解説は初版と同様であるが,全頁をカラー化することにより,一層の見やすさ,わかりやすさに配慮した。
本書は,助産師を志す学生からベテランの助産師まで幅広く活用できる,十分手応えのある内容になったと考えている。学習テキストとして,また多くの助産師諸姉の臨床技術や診断能力の向上に,ご活用頂ければと願っている。
2018年1月
我部山キヨ子・大石時子
本書の目的と構成
本書の目的は,「高い専門知識・技術に裏付けられた助産師となるために必要な,診断能力の基礎となるフィジカルイグザミネーションを行い,またそこから得られた知見を正しくアセスメントするための基本的知識・技術から高次の知識・技術までを正確に,そして詳細に提供すること」にある。
そのために,初学者でも明確にわかるようにフィジカルイグザミネーションの実際について,カラー写真や図を多く使用している。また,正確で緻密なアセスメントができるように,診断基準(数値など)を随所に記載した。さらに,普通の妊婦診察では助産師は行わないが,より高次のフィジカルイグザミネーションとアセスメントができるように,「Another Step Advanced」として,より専門的な診断技術法を織り込んでいる。
内容に関しては,助産師業務のコアである周産期領域のフィジカルイグザミネーションとアセスメントを中心に構成したが,近年,普遍的に行われるようになってきた超音波診断などの臨床機器の使用法や診断も,図や写真を用いてわかりやすく解説している。
妊娠・分娩・産褥の各期に共通する項目については,各期でそれぞれに説明するのではなく,代表的な章にまとめている。たとえば,レオポルド触診法は妊娠期で詳細に解説し,分娩期での説明は要点のみとしている。また,乳房については,妊娠期から観察すべきであるが,その内容は産褥期の章で扱っている。
また,周産期のウィメンズヘルスとして,性感染症,子宮頸がん,乳がん,ドメスティックバイオレンス(DV)といった項目を取り上げている。これらは,妊娠期,分娩期,産褥期の診察や検査に関わる項目であり,各期の診察項目に入れてもよいものであるが,周産期以外の女性にとっても重要な診察・検査内容であるため,包括的にウィメンズヘルスとして別章とし,内容を充実させた。
第2版 まえがき
本書初版の発行から10年が経過した。出産難民が社会現象化していた当時からすると,周産期医療の危機的状況はやや落ち着きを取り戻したかにみえるが,課題はいまだ山積している。すなわち,晩婚化・晩産化はますます進行し,30歳以上の出産は64.3%(35歳以上の出産は28.1%,いずれも2015年)となり,体外受精児は19人に1人(2015年),麻酔分娩や帝王切開分娩の増加,低出生体重児の出生割合の高止まり,児童虐待相談件数の激増など,母児ともにハイリスクな傾向は加速している。
一方,2000年代初頭,少子化に端を発した分娩取扱施設の廃止の動きが顕著となり,産婦人科・産科を標榜する施設数および産科医は,現在でも年次ごとに減少傾向が続いている。このような社会背景から,2015年日本産科婦人科学会は深刻化する産科医不足への対応策として,地域の基幹病院に産科医を集約化し,医師一人ひとりの負担を減らすとともに,24時間安心して出産できる場所を確保することを柱とした行動計画をまとめた。この計画には,高い能力をもつ助産師の育成も盛り込まれている。また,同時期に日本助産実践能力推進協議会は,助産実践能力が一定水準に達していることを客観的に評価する仕組みとして,助産実践能力習熟段階(CLoCMiP)レベルIII認証制度を創設し,運用を開始した。
このような周産期医療の背景を踏まえて,助産師に求められる実践能力も変化してきている。すなわち,従来はローリスク妊産褥婦・新生児を主な対象としていた助産師であるが,それに加えて,ハイリスク妊産褥婦・新生児の増加に伴い,正常からの逸脱の診断を適時にかつ正確に行い,早い段階で医師の診察を促し,協働して母子の安全・安心を守ることがより一層求められるようになってきた。そこには,従来にもまして高いフィジカルイグザミネーション能力とアセスメント能力が求められている。
それは単に診察(フィジカルイグザミネーション)をして身体情報を集め,正常・異常のアセスメントをするだけでなく,鑑別診断に向かってさらにどのような診察や検査が必要であるかも思考し,実施し,臨床推論をできるだけ進めていく能力である。そのことによって必要な情報を必要な専門職に,迅速かつ的確に提供し,チーム医療の力を発揮することができる。
第2版ではこれらを踏まえて,新しい知見や基準を加筆するとともに,妊娠期・分娩期・産褥期の異常,ハイリスク妊産褥婦についての解説を充実させ,「助産師が知っておきたい異常(呼吸器・循環器系,脳神経系,代謝系)」,早産児・低出生体重児等「新生児のフィジカルイグザミネーション」を新設した。
加えて「周産期のウィメンズヘルス」として,子宮頸がん,性感染症,乳腺疾患・乳がん,配偶者からの暴力(DV)などもフィジカルイグザミネーションとアセスメントの視点から取り上げ,詳述している。検査法についても新国家試験出題基準を反映して,腟鏡診,顕微鏡診等を取り入れた。
また,豊富な写真とイラストを使用した解説は初版と同様であるが,全頁をカラー化することにより,一層の見やすさ,わかりやすさに配慮した。
本書は,助産師を志す学生からベテランの助産師まで幅広く活用できる,十分手応えのある内容になったと考えている。学習テキストとして,また多くの助産師諸姉の臨床技術や診断能力の向上に,ご活用頂ければと願っている。
2018年1月
我部山キヨ子・大石時子
本書の目的と構成
本書の目的は,「高い専門知識・技術に裏付けられた助産師となるために必要な,診断能力の基礎となるフィジカルイグザミネーションを行い,またそこから得られた知見を正しくアセスメントするための基本的知識・技術から高次の知識・技術までを正確に,そして詳細に提供すること」にある。
そのために,初学者でも明確にわかるようにフィジカルイグザミネーションの実際について,カラー写真や図を多く使用している。また,正確で緻密なアセスメントができるように,診断基準(数値など)を随所に記載した。さらに,普通の妊婦診察では助産師は行わないが,より高次のフィジカルイグザミネーションとアセスメントができるように,「Another Step Advanced」として,より専門的な診断技術法を織り込んでいる。
内容に関しては,助産師業務のコアである周産期領域のフィジカルイグザミネーションとアセスメントを中心に構成したが,近年,普遍的に行われるようになってきた超音波診断などの臨床機器の使用法や診断も,図や写真を用いてわかりやすく解説している。
妊娠・分娩・産褥の各期に共通する項目については,各期でそれぞれに説明するのではなく,代表的な章にまとめている。たとえば,レオポルド触診法は妊娠期で詳細に解説し,分娩期での説明は要点のみとしている。また,乳房については,妊娠期から観察すべきであるが,その内容は産褥期の章で扱っている。
また,周産期のウィメンズヘルスとして,性感染症,子宮頸がん,乳がん,ドメスティックバイオレンス(DV)といった項目を取り上げている。これらは,妊娠期,分娩期,産褥期の診察や検査に関わる項目であり,各期の診察項目に入れてもよいものであるが,周産期以外の女性にとっても重要な診察・検査内容であるため,包括的にウィメンズヘルスとして別章とし,内容を充実させた。
目次
開く
まえがき
初版まえがき
本書の目的と構成
検査法・検査項目一覧
序章 フィジカルイグザミネーションの基本
1 フィジカルイグザミネーションにおける助産師の基本的姿勢
2 フィジカルイグザミネーションの基本的技術
第I章 妊娠期のフィジカルイグザミネーション
1 問診:すべての診察の基礎
2 身体計測・骨盤計測
3 頭部,頸部,胸部,四肢
4 腹部
5 生殖器のフィジカルイグザミネーション
6 妊娠期のトラブルと胎児の診察・アドバンスト編
第II章 超音波診断装置によるフィジカルイグザミネーション
1 超音波診断装置の使用法
2 妊娠初期(4~13週)の超音波検査
3 妊娠中期(18~20週)の超音波検査
4 妊娠後期(28週以降)の超音波検査
5 分娩中の評価
6 産褥期の超音波検査
7 助産師による超音波検査
第III章 分娩期のフィジカルイグザミネーション
1 産婦のフィジカルイグザミネーション
2 胎児のフィジカルイグザミネーション
3 分娩時および分娩後に遭遇する異常出血のフィジカルイグザミネーション
第IV章 産褥期のフィジカルイグザミネーション
1 分娩後2時間(分娩第4期)の子宮の変化とフィジカルイグザミネーション
2 産褥期の全身の変化とフィジカルイグザミネーション
3 帝王切開後の診察とフィジカルイグザミネーション
4 産褥期の心理・精神の変化とフィジカルイグザミネーション
5 乳房のフィジカルイグザミネーション
第V章 助産師が知っておきたい異常
1 呼吸器・循環器系
2 脳神経系
3 代謝系
第VI章 新生児のフィジカルイグザミネーション
1 出生直後のフィジカルイグザミネーション
2 身体計測のフィジカルイグザミネーション
3 運動・神経機能のフィジカルイグザミネーション
4 バイタルサインのチェック
5 新生児に特徴的な所見
6 子ども虐待発見のフィジカルイグザミネーション
第VII章 周産期のウィメンズヘルス
1 子宮頸がん
2 性感染症(STI)
3 乳腺疾患,乳がん
4 妊娠期における配偶者からの暴力(DV)
索引
Another Step Advanced
臨床的骨盤計測法
胎向と児頭嵌入の診断
マニングのスコア
妊娠中の超音波使用の安全性
分娩監視装置による継続モニタリングの効果の検討
早産児におけるフィジカルイグザミネーション
初版まえがき
本書の目的と構成
検査法・検査項目一覧
序章 フィジカルイグザミネーションの基本
1 フィジカルイグザミネーションにおける助産師の基本的姿勢
2 フィジカルイグザミネーションの基本的技術
第I章 妊娠期のフィジカルイグザミネーション
1 問診:すべての診察の基礎
2 身体計測・骨盤計測
3 頭部,頸部,胸部,四肢
4 腹部
5 生殖器のフィジカルイグザミネーション
6 妊娠期のトラブルと胎児の診察・アドバンスト編
第II章 超音波診断装置によるフィジカルイグザミネーション
1 超音波診断装置の使用法
2 妊娠初期(4~13週)の超音波検査
3 妊娠中期(18~20週)の超音波検査
4 妊娠後期(28週以降)の超音波検査
5 分娩中の評価
6 産褥期の超音波検査
7 助産師による超音波検査
第III章 分娩期のフィジカルイグザミネーション
1 産婦のフィジカルイグザミネーション
2 胎児のフィジカルイグザミネーション
3 分娩時および分娩後に遭遇する異常出血のフィジカルイグザミネーション
第IV章 産褥期のフィジカルイグザミネーション
1 分娩後2時間(分娩第4期)の子宮の変化とフィジカルイグザミネーション
2 産褥期の全身の変化とフィジカルイグザミネーション
3 帝王切開後の診察とフィジカルイグザミネーション
4 産褥期の心理・精神の変化とフィジカルイグザミネーション
5 乳房のフィジカルイグザミネーション
第V章 助産師が知っておきたい異常
1 呼吸器・循環器系
2 脳神経系
3 代謝系
第VI章 新生児のフィジカルイグザミネーション
1 出生直後のフィジカルイグザミネーション
2 身体計測のフィジカルイグザミネーション
3 運動・神経機能のフィジカルイグザミネーション
4 バイタルサインのチェック
5 新生児に特徴的な所見
6 子ども虐待発見のフィジカルイグザミネーション
第VII章 周産期のウィメンズヘルス
1 子宮頸がん
2 性感染症(STI)
3 乳腺疾患,乳がん
4 妊娠期における配偶者からの暴力(DV)
索引
Another Step Advanced
臨床的骨盤計測法
胎向と児頭嵌入の診断
マニングのスコア
妊娠中の超音波使用の安全性
分娩監視装置による継続モニタリングの効果の検討
早産児におけるフィジカルイグザミネーション
書評
開く
標準的なフィジカルアセスメントの重要性(雑誌『助産雑誌』より)
書評者: 海野 信也 (北里大学医学部産科学教授)
身体所見を正確に,我流でなく標準的方法で取り,それを記載することは患者の状態評価の基本であり,臨床医学の基盤である。本書は,助産師を対象とし,フィジカルイグザミネーションに特化して,標準的方法を網羅的に記載した成書として希有なものである。編集にあたられた先生方の着眼のすばらしさに敬意を表したい。
現代の医学教育においては,診察法に関する教育がOSCE(客観的臨床能力試験)として系統的に行なわれており,その重要性は十分認識されていることになっている。しかし実際の診療分野の現場では,ともすると身体診察よりも結果を評価しやすい臨床検査が重視される傾向があることは否定できない事実である。
しかし,産科の領域は状況が大きく異なっている。妊娠・分娩の経過中,母体はダイナミックに変化する。正常経過であっても,当初は月単位,週単位で,妊娠末期には日単位と次第に加速し,分娩開始後は時間・分・秒単位と急激に加速した結果,児の娩出に至る。このような経過を適時,適切に把握し対応するためには,ある時間の断面を切り取るだけの臨床検査では不十分であり,われわれの技術では,即時に,そしてくり返して評価することのできる内診所見と胎児心拍数モニタリング所見が,妊娠の進行と児の状態評価のための標準的検査にならざるを得ないのである。
産科における内診は,この領域で必要とされるフィジカルイグザミネーションの中でもっとも重要と考えられ,事実上産婦人科医と助産師のみが実施する診察法である。この領域の専門職としての両者が共通の言語・用語を用いて,評価し記載することによって,はじめて専門家の知識と経験を最大限に生かした,個々の産婦にとっての最善のケアが可能になると考えられる。
しかし,実際にはこれまでこの課題について職種を超えた検討が十分なされてきたとは言い難い。本書はこの領域の初学者にとって系統的な知識を提供するだけでなく,経験ある助産師および産婦人科医にとって,自身の専門職としての知識,考え方を再確認する機会となることが期待できる。ぜひご一読をおすすめしたい。
(『助産雑誌』2018年10月号掲載)
学生からアドバンスまで助産師必携のガイドが再登場(雑誌『助産雑誌』より)
書評者: 高橋 弘枝 (大阪府看護協会会長)
第1回と第2回の助産実践能力習熟段階(CLoCMiP®)レベルIII認証制度の認証結果では,就業助産師の3割以上を占める1万1002人の「アドバンス助産師」が誕生している。このアドバンス助産師に求められる役割の1つが院内助産・助産師外来の開設,運営である。
院内助産については,2008年に「院内助産ガイドライン―医師と助産師の役割と協働」が公表され10年が経過した。この間の周産期医療を取り巻く環境や医療機関の機能は大きく変化している。また,助産師外来の数は増えているが,院内助産の数は横ばいである。増えない要因に,関係者間での合意形成と助産師の実践能力の不足があるとも言われている。
それらをふまえ,妊産褥婦とその家族の多様なニーズに応えるために,2018年3月に日本看護協会により「院内助産・助産師外来ガイドライン2018」が策定された。また,このガイドラインを活用し,日本のすべての妊産婦が安全・安心に出産できる体制が整備されるために,すべての分娩取り扱い医療機関への設置を目指すとも表明された。このガイドラインの中で特筆すべき点が,対象者の選定基準や,担当・指導する助産師の基準,産科医師・新生児科医師への相談・報告基準を設定しているところである。また,これらの基準は,設置される施設の状況をふまえ,産科医師等と協議し合意のうえで基準を定めることが,今回新たに強く推奨されている。
そのような中,このたび,書籍『アセスメント力を磨く―助産師のためのフィジカルイグザミネーション 第2版』が発行された。初版と違いオールカラーで,図や写真,イラストが見やすくなっている。CLoCMiP®レベルIII認証制度に合わせ,さらに内容が充実された。
本書は助産師を目指す学生にはもちろん,臨床の助産師にとってもさまざまな臨床判断の場での貴重な教科書,ガイドとなる。前述のガイドラインには,院内助産・助産師外来を担当・指導する助産師に求められる能力として,情報収集能力,アセスメント能力,スクリーニング能力,計画立案と変更への対応能力,急変対応と報告できる行動力,他部門との調整能力等が挙げられている。また,医師と協議し合意形成を行なう場,医師と同じ土俵に上るためには,日ごろからの根拠に基づいた実践が必要となる。本書はまさに,その能力と実践の基礎をつくるためにも,スタッフの指導時にも,自身の知識を再確認し日々の実践を強化するためにも,アドバンス助産師必携の書籍である。
(『助産雑誌』2018年9月号掲載)
書評者: 海野 信也 (北里大学医学部産科学教授)
身体所見を正確に,我流でなく標準的方法で取り,それを記載することは患者の状態評価の基本であり,臨床医学の基盤である。本書は,助産師を対象とし,フィジカルイグザミネーションに特化して,標準的方法を網羅的に記載した成書として希有なものである。編集にあたられた先生方の着眼のすばらしさに敬意を表したい。
現代の医学教育においては,診察法に関する教育がOSCE(客観的臨床能力試験)として系統的に行なわれており,その重要性は十分認識されていることになっている。しかし実際の診療分野の現場では,ともすると身体診察よりも結果を評価しやすい臨床検査が重視される傾向があることは否定できない事実である。
しかし,産科の領域は状況が大きく異なっている。妊娠・分娩の経過中,母体はダイナミックに変化する。正常経過であっても,当初は月単位,週単位で,妊娠末期には日単位と次第に加速し,分娩開始後は時間・分・秒単位と急激に加速した結果,児の娩出に至る。このような経過を適時,適切に把握し対応するためには,ある時間の断面を切り取るだけの臨床検査では不十分であり,われわれの技術では,即時に,そしてくり返して評価することのできる内診所見と胎児心拍数モニタリング所見が,妊娠の進行と児の状態評価のための標準的検査にならざるを得ないのである。
産科における内診は,この領域で必要とされるフィジカルイグザミネーションの中でもっとも重要と考えられ,事実上産婦人科医と助産師のみが実施する診察法である。この領域の専門職としての両者が共通の言語・用語を用いて,評価し記載することによって,はじめて専門家の知識と経験を最大限に生かした,個々の産婦にとっての最善のケアが可能になると考えられる。
しかし,実際にはこれまでこの課題について職種を超えた検討が十分なされてきたとは言い難い。本書はこの領域の初学者にとって系統的な知識を提供するだけでなく,経験ある助産師および産婦人科医にとって,自身の専門職としての知識,考え方を再確認する機会となることが期待できる。ぜひご一読をおすすめしたい。
(『助産雑誌』2018年10月号掲載)
学生からアドバンスまで助産師必携のガイドが再登場(雑誌『助産雑誌』より)
書評者: 高橋 弘枝 (大阪府看護協会会長)
第1回と第2回の助産実践能力習熟段階(CLoCMiP®)レベルIII認証制度の認証結果では,就業助産師の3割以上を占める1万1002人の「アドバンス助産師」が誕生している。このアドバンス助産師に求められる役割の1つが院内助産・助産師外来の開設,運営である。
院内助産については,2008年に「院内助産ガイドライン―医師と助産師の役割と協働」が公表され10年が経過した。この間の周産期医療を取り巻く環境や医療機関の機能は大きく変化している。また,助産師外来の数は増えているが,院内助産の数は横ばいである。増えない要因に,関係者間での合意形成と助産師の実践能力の不足があるとも言われている。
それらをふまえ,妊産褥婦とその家族の多様なニーズに応えるために,2018年3月に日本看護協会により「院内助産・助産師外来ガイドライン2018」が策定された。また,このガイドラインを活用し,日本のすべての妊産婦が安全・安心に出産できる体制が整備されるために,すべての分娩取り扱い医療機関への設置を目指すとも表明された。このガイドラインの中で特筆すべき点が,対象者の選定基準や,担当・指導する助産師の基準,産科医師・新生児科医師への相談・報告基準を設定しているところである。また,これらの基準は,設置される施設の状況をふまえ,産科医師等と協議し合意のうえで基準を定めることが,今回新たに強く推奨されている。
そのような中,このたび,書籍『アセスメント力を磨く―助産師のためのフィジカルイグザミネーション 第2版』が発行された。初版と違いオールカラーで,図や写真,イラストが見やすくなっている。CLoCMiP®レベルIII認証制度に合わせ,さらに内容が充実された。
本書は助産師を目指す学生にはもちろん,臨床の助産師にとってもさまざまな臨床判断の場での貴重な教科書,ガイドとなる。前述のガイドラインには,院内助産・助産師外来を担当・指導する助産師に求められる能力として,情報収集能力,アセスメント能力,スクリーニング能力,計画立案と変更への対応能力,急変対応と報告できる行動力,他部門との調整能力等が挙げられている。また,医師と協議し合意形成を行なう場,医師と同じ土俵に上るためには,日ごろからの根拠に基づいた実践が必要となる。本書はまさに,その能力と実践の基礎をつくるためにも,スタッフの指導時にも,自身の知識を再確認し日々の実践を強化するためにも,アドバンス助産師必携の書籍である。
(『助産雑誌』2018年9月号掲載)
正誤表
開く
本書の記述の正確性につきましては最善の努力を払っておりますが、この度弊社の責任におきまして、下記のような誤りがございました。お詫び申し上げますとともに訂正させていただきます。