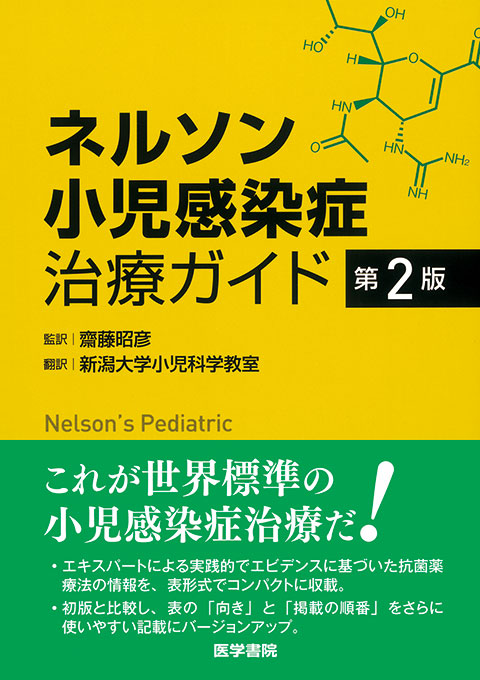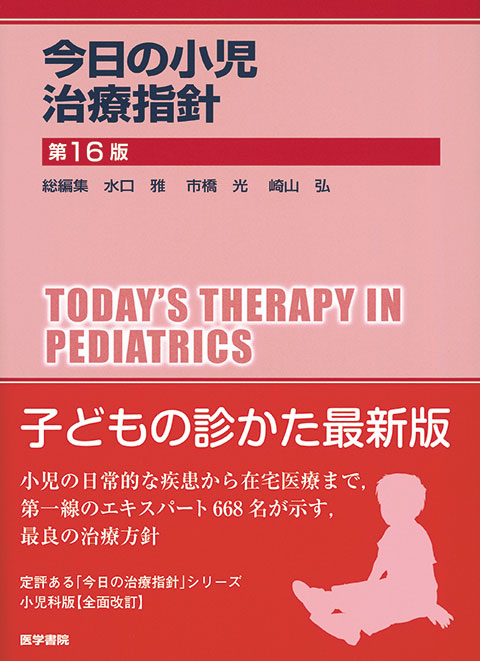ネルソン小児感染症治療ガイド 第2版
小児感染症治療のスタンダードを示す、信頼のマニュアル
もっと見る
これが世界標準の小児感染症治療だ! 抗菌薬療法のエキスパートによる実践的でエビデンスに基づいた情報を、表形式でコンパクトにまとめたマニュアル。これを読めば、信頼できる最新の推奨療法にすぐにたどり着き、多くの抗菌薬の中からベストな選択ができる! 初版と比較し、表の「向き」と「掲載の順番」をユーザーにとってさらに使いやすい記載方式にバージョンアップ。待望の第2版。
| 監訳 | 齋藤 昭彦 |
|---|---|
| 翻訳 | 新潟大学小児科学教室 |
| 発行 | 2017年01月判型:B6変頁:314 |
| ISBN | 978-4-260-02824-0 |
| 定価 | 3,960円 (本体3,600円+税) |
- 販売終了
更新情報
-
更新情報はありません。
お気に入り商品に追加すると、この商品の更新情報や関連情報などをマイページでお知らせいたします。
- 序文
- 目次
- 書評
序文
開く
第2版 監訳の序(齋藤昭彦)/はじめに(John S. Bradley, John D. Nelson)
第2版 監訳の序
本書は,小児感染症領域の抗微生物薬のポケットブックであり,米国の小児科研修医や小児科医には,俗称“Yellow Book”として広く知られている.そして,小児科医,特に多くの研修医のポケットに入っており,実際の臨床の現場で頻用されている本である.
本書は小児の抗微生物薬の草分け的な本であり,John Bradley(私のカリフォルニア大学サンディエゴ校とサンディエゴ小児病院での臨床面のメンター)とJohn Nelsonにより,1975年から発刊されている.
2011-2012年版からは,米国小児科学会の出版物となり,その信頼度をさらに高め,現在に至っている.そこには,実際の臨床現場で働く米国の小児感染症専門医の経験と知識が集約されている.
2013年に新潟大学医学部小児科の教室の有志で,原書19版を翻訳してから,はや3年の月日が経過した.原書は,2013年以前は,2年おきの改訂であったが,2014年の20版から毎年の改訂となり,今回は22版である.翻訳するにあたり,可能な限り最新版を訳さないと最新の情報が提供できないことから,今回は22版が出版されてすぐにその翻訳に取りかかった.今回も教室の有志に翻訳を依頼し,3名の新しいメンバー(大塚岳人先生,幾瀬樹先生,小嶋智子先生)に加わってもらった.
この本は,米国の実際の臨床の現場で使われているものであり,国内では使えない薬剤や,投与量や適応が異なる薬剤が記載されている.したがって,この本に記載されていることをそのまま日本の臨床の現場にあてはめることはできない.しかしながら,前版と同様,国内で使用できない薬剤を区別するためその薬剤は英語で記載し,また,投与量や適応が異なる場合などは,可能な限り訳注を付けて解説を加えた.これらの訳注を読むことで,米国と国内での抗微生物薬の使用に関するギャップがあることをおわかりいただけるかと思う.国内の小児感染症診療をどのように世界標準の診療に近づけることができるかは,これからの課題である.
最近,国内,海外における薬剤耐性微生物の脅威は,大きな話題となっている.抗微生物薬をいかに大切に使用し,耐性微生物をこれ以上作らず,抗微生物薬を将来の子どもたちに価値ある医療資源として存続させることは,抗微生物薬を処方するわれわれの重い責務である.
最後に,本書が皆さんの小児感染症の診療に役立ち,最終的に子どもたちの健康につながることを祈って.
2016年11月吉日
新潟大学大学院教授・小児科学
齋藤昭彦
はじめに
ネルソン小児感染症治療ガイド第22版の世界へようこそ! この本は1975年の初版から現在に至るまで,小児感染症における最適の治療を選択するための一助となってきた.この本は,米国小児科学会(AAP)との協同作業により,どのように小児感染症をとらえ,抗微生物薬で治療できるのか,また小児医療を行う臨床医がいかに正確で妥当性のある情報を得ることができるか,これらを追求し,非常に有益な本へと成長してきた.また,われわれがある特定の薬剤,特定の用量を推奨する理由について,臨床医から好意的な意見をもらってきた.推奨した治療に関するすべての事実・データに,臨床医がアクセスできるように引用文献を挙げたことも好評を得ている.臨床医がこれら引用文献の重要性・有用性を理解してくれたことに深く感謝する.
John Leakeは国際保健学の専門家であり,数年にわたって「寄生虫感染症」の章を執筆してきた.彼が現在取り組んでいるのは検査診断学で,エボラ感染症のような重要な新興感染症に対する検査法の開発である.彼の代わりにわれわれはElizabeth Barnettを新しい執筆者として迎えた.彼女はボストン大学医学部に所属する国際保健学/旅行医学の専門家で,旅行者,移民,難民に関する国際保健問題に焦点を当てた章を今後執筆してもらう予定である.Elizabeth Barnettは国際旅行医学会とCDCが設立したGeoSentinelサーベイランスネットワーク(訳者註:旅行者感染症のサーベイランスネットワーク)の施設長であり,先ごろ米国小児科学会感染症部門のRed Book編集委員にも任命された.
Jason Sauberanは,抗微生物薬リスト(ABC順)(第11章),肥満児に対する抗菌薬療法(第12章),新生児への抗微生物薬療法(第5章),の各章を最新の情報をもとに丹念に更新してくれた.3人の新生児科医JB Cantey,Pablo Sanchez,John van den Ankerも共著者として名を連ねている.John van den AnkerはChildren's National Medical Center所属の新生児科医/薬理学者で,今回も第5章の監修を快く引き受けてくれた.近年,新生児の薬理学は盛んに研究される分野となっている.
すべての編集者は現役で臨床医として働いている.これが,特に治療困難な感染症に対する抗菌薬推奨において鋭い視点となって表れている.彼らは小児感染症分野で最も優れた臨床医で,新旧多くの抗菌薬の中で最も効果のあるものを探求する学問的興味を持ち合わせている.また,米国小児科学会とのパートナーシップを築き,各専門領域の知識や経験に裏打ちされた素晴らしいアドバイスを行っている.
データから得られた知見はそれぞれに推奨度が決められている.われわれが強く推奨できるかどうか,それに関する強いエビデンスがあるかどうか,推奨度を表にまとめた.
毎年,明記しているが,ある特定の状況で推奨された治療は,対照を置く前方視的な比較臨床試験のような体系的試験を行っていないので,多くの推奨は論文データに基づくものである.しかしそれらのデータは米国食品医薬品局(FDA)の認可を受けていない場合もあり,その場合は投与する適応がない.小児科医の多くはこのような経験があるだろう.われわれの多くはFDAに働きかけ,成人と小児の抗菌薬治療のギャップを埋めようと努力しているし,FDAは小児の安全かつ有効な抗菌薬使用量の検討に尽力している.
われわれは米国小児科学会商品開発編集長Alain Parkの貢献に心から感謝する.彼は米国小児科学会の重要資料や,小児の健康にかかわるすべての人々の窓口となってくれた.米国小児科学会は,われわれが臨床医と情報を共有する新たな方法を提供するために出版部門を再編成した.われわれには米国小児科学会の出版部門,販売促進部門,営業部門に素晴らしい仲間がいる.Jeff Mahony,Mark Grimes,Linda Smessaert,Peter Lynch,そしてすべてのスタッフが力を結集し,臨床医ができるだけ効率よく簡単に使えるようにこの本を作り上げてくれたのである.
John S. Bradley, MD
John D. Nelson, MD
第2版 監訳の序
本書は,小児感染症領域の抗微生物薬のポケットブックであり,米国の小児科研修医や小児科医には,俗称“Yellow Book”として広く知られている.そして,小児科医,特に多くの研修医のポケットに入っており,実際の臨床の現場で頻用されている本である.
本書は小児の抗微生物薬の草分け的な本であり,John Bradley(私のカリフォルニア大学サンディエゴ校とサンディエゴ小児病院での臨床面のメンター)とJohn Nelsonにより,1975年から発刊されている.
2011-2012年版からは,米国小児科学会の出版物となり,その信頼度をさらに高め,現在に至っている.そこには,実際の臨床現場で働く米国の小児感染症専門医の経験と知識が集約されている.
2013年に新潟大学医学部小児科の教室の有志で,原書19版を翻訳してから,はや3年の月日が経過した.原書は,2013年以前は,2年おきの改訂であったが,2014年の20版から毎年の改訂となり,今回は22版である.翻訳するにあたり,可能な限り最新版を訳さないと最新の情報が提供できないことから,今回は22版が出版されてすぐにその翻訳に取りかかった.今回も教室の有志に翻訳を依頼し,3名の新しいメンバー(大塚岳人先生,幾瀬樹先生,小嶋智子先生)に加わってもらった.
この本は,米国の実際の臨床の現場で使われているものであり,国内では使えない薬剤や,投与量や適応が異なる薬剤が記載されている.したがって,この本に記載されていることをそのまま日本の臨床の現場にあてはめることはできない.しかしながら,前版と同様,国内で使用できない薬剤を区別するためその薬剤は英語で記載し,また,投与量や適応が異なる場合などは,可能な限り訳注を付けて解説を加えた.これらの訳注を読むことで,米国と国内での抗微生物薬の使用に関するギャップがあることをおわかりいただけるかと思う.国内の小児感染症診療をどのように世界標準の診療に近づけることができるかは,これからの課題である.
最近,国内,海外における薬剤耐性微生物の脅威は,大きな話題となっている.抗微生物薬をいかに大切に使用し,耐性微生物をこれ以上作らず,抗微生物薬を将来の子どもたちに価値ある医療資源として存続させることは,抗微生物薬を処方するわれわれの重い責務である.
最後に,本書が皆さんの小児感染症の診療に役立ち,最終的に子どもたちの健康につながることを祈って.
2016年11月吉日
新潟大学大学院教授・小児科学
齋藤昭彦
はじめに
ネルソン小児感染症治療ガイド第22版の世界へようこそ! この本は1975年の初版から現在に至るまで,小児感染症における最適の治療を選択するための一助となってきた.この本は,米国小児科学会(AAP)との協同作業により,どのように小児感染症をとらえ,抗微生物薬で治療できるのか,また小児医療を行う臨床医がいかに正確で妥当性のある情報を得ることができるか,これらを追求し,非常に有益な本へと成長してきた.また,われわれがある特定の薬剤,特定の用量を推奨する理由について,臨床医から好意的な意見をもらってきた.推奨した治療に関するすべての事実・データに,臨床医がアクセスできるように引用文献を挙げたことも好評を得ている.臨床医がこれら引用文献の重要性・有用性を理解してくれたことに深く感謝する.
John Leakeは国際保健学の専門家であり,数年にわたって「寄生虫感染症」の章を執筆してきた.彼が現在取り組んでいるのは検査診断学で,エボラ感染症のような重要な新興感染症に対する検査法の開発である.彼の代わりにわれわれはElizabeth Barnettを新しい執筆者として迎えた.彼女はボストン大学医学部に所属する国際保健学/旅行医学の専門家で,旅行者,移民,難民に関する国際保健問題に焦点を当てた章を今後執筆してもらう予定である.Elizabeth Barnettは国際旅行医学会とCDCが設立したGeoSentinelサーベイランスネットワーク(訳者註:旅行者感染症のサーベイランスネットワーク)の施設長であり,先ごろ米国小児科学会感染症部門のRed Book編集委員にも任命された.
Jason Sauberanは,抗微生物薬リスト(ABC順)(第11章),肥満児に対する抗菌薬療法(第12章),新生児への抗微生物薬療法(第5章),の各章を最新の情報をもとに丹念に更新してくれた.3人の新生児科医JB Cantey,Pablo Sanchez,John van den Ankerも共著者として名を連ねている.John van den AnkerはChildren's National Medical Center所属の新生児科医/薬理学者で,今回も第5章の監修を快く引き受けてくれた.近年,新生児の薬理学は盛んに研究される分野となっている.
すべての編集者は現役で臨床医として働いている.これが,特に治療困難な感染症に対する抗菌薬推奨において鋭い視点となって表れている.彼らは小児感染症分野で最も優れた臨床医で,新旧多くの抗菌薬の中で最も効果のあるものを探求する学問的興味を持ち合わせている.また,米国小児科学会とのパートナーシップを築き,各専門領域の知識や経験に裏打ちされた素晴らしいアドバイスを行っている.
データから得られた知見はそれぞれに推奨度が決められている.われわれが強く推奨できるかどうか,それに関する強いエビデンスがあるかどうか,推奨度を表にまとめた.
| 推奨の強さ | 説明 |
| A | 強く推奨する |
| B | よい選択として推奨する |
| C | 多くの他の治療のなかで,適切な治療としての選択肢の1つになりうる |
| 根拠のレベル | 説明 |
| Ⅰ | 適切な小児の症例数でよく計画され,前方視的で,ランダム比較試験に基づいている |
| Ⅱ | 前方視的であるが,少数の比較試験,あるいは信頼できる,後方視的な小児の臨床試験,あるいは成人など小児以外の対象からのデータに基づいている |
| Ⅲ | 適切なデータが存在しておらず,症例報告,合意声明,専門家の意見に基づいている |
毎年,明記しているが,ある特定の状況で推奨された治療は,対照を置く前方視的な比較臨床試験のような体系的試験を行っていないので,多くの推奨は論文データに基づくものである.しかしそれらのデータは米国食品医薬品局(FDA)の認可を受けていない場合もあり,その場合は投与する適応がない.小児科医の多くはこのような経験があるだろう.われわれの多くはFDAに働きかけ,成人と小児の抗菌薬治療のギャップを埋めようと努力しているし,FDAは小児の安全かつ有効な抗菌薬使用量の検討に尽力している.
われわれは米国小児科学会商品開発編集長Alain Parkの貢献に心から感謝する.彼は米国小児科学会の重要資料や,小児の健康にかかわるすべての人々の窓口となってくれた.米国小児科学会は,われわれが臨床医と情報を共有する新たな方法を提供するために出版部門を再編成した.われわれには米国小児科学会の出版部門,販売促進部門,営業部門に素晴らしい仲間がいる.Jeff Mahony,Mark Grimes,Linda Smessaert,Peter Lynch,そしてすべてのスタッフが力を結集し,臨床医ができるだけ効率よく簡単に使えるようにこの本を作り上げてくれたのである.
John S. Bradley, MD
John D. Nelson, MD
目次
開く
第2版 監訳の序
初版 監訳の序
はじめに
1 抗菌薬の選択
(β-ラクタム系,マクロライド系,アミノグリコシド系,フルオロキノロン系)
2 抗真菌薬の選択
(ポリエン系,アゾール系,エキノキャンディン系)
3 感受性データと薬力学と治療成績に基づく抗菌薬の投与量
4 市中MRSA
5 新生児への抗微生物薬療法
A.新生児の疾患別推奨療法
B.新生児に対する抗微生物薬の投与量
C.アミノグリコシド
D.バンコマイシン
E.妊娠および授乳中における抗微生物薬の使用
6 臨床症状による抗微生物薬療法
A.皮膚・軟部組織感染症
B.骨・関節感染症
C.眼感染症
D.耳,副鼻腔感染症
E.口腔咽頭感染症
F.下気道感染症
G.心血管系感染症
H.消化管感染症
I.性器と性感染症
J.中枢神経系感染症
K.尿路感染症
L.その他の全身感染症
7 特定の病原性微生物に対する推奨療法
A.一般的な病原性微生物と通常の抗菌薬感受性パターン(グラム陽性菌)
B.一般的な病原性微生物と通常の抗菌薬感受性パターン(グラム陰性菌)
C.一般的な病原性微生物と通常の抗菌薬感受性パターン(嫌気性菌)
D.特記すべき細菌とマイコバクテリアに対する推奨療法
8 特定の真菌に対する推奨療法
A.真菌の概要と通常の抗真菌薬感受性パターン
B.全身感染症
C.皮膚粘膜の限局性感染症
9 特定のウイルスに対する推奨療法
A.HIV以外のウイルスに対する通常の抗ウイルス薬感受性パターン
B.特定のウイルスに対する推奨療法
10 特定の寄生虫に対する推奨療法
11 抗微生物薬リスト(ABC順)
A.全身投与用抗微生物薬の剤形と投与法
B.局所に投与する抗微生物薬(皮膚,眼,耳)
12 肥満児に対する抗菌薬療法
13 重症感染症に対する静注-経口抗菌薬療法(経口ステップダウン療法)
14 症候性感染症に対する抗微生物薬の予防投与/予防
A.曝露後の短期的な抗微生物薬予防投与
B.症候性感染症の長期的抗微生物薬予防投与
C.先行治療/潜在性感染症の治療
(無症候性感染症のある小児における症候性感染症に対する予防投与)
D.手術や処置時の予防投与
15 抗微生物薬の副作用
16 薬物相互作用
付録:体表面積決定のためのノモグラム
文献
索引
初版 監訳の序
はじめに
1 抗菌薬の選択
(β-ラクタム系,マクロライド系,アミノグリコシド系,フルオロキノロン系)
2 抗真菌薬の選択
(ポリエン系,アゾール系,エキノキャンディン系)
3 感受性データと薬力学と治療成績に基づく抗菌薬の投与量
4 市中MRSA
5 新生児への抗微生物薬療法
A.新生児の疾患別推奨療法
B.新生児に対する抗微生物薬の投与量
C.アミノグリコシド
D.バンコマイシン
E.妊娠および授乳中における抗微生物薬の使用
6 臨床症状による抗微生物薬療法
A.皮膚・軟部組織感染症
B.骨・関節感染症
C.眼感染症
D.耳,副鼻腔感染症
E.口腔咽頭感染症
F.下気道感染症
G.心血管系感染症
H.消化管感染症
I.性器と性感染症
J.中枢神経系感染症
K.尿路感染症
L.その他の全身感染症
7 特定の病原性微生物に対する推奨療法
A.一般的な病原性微生物と通常の抗菌薬感受性パターン(グラム陽性菌)
B.一般的な病原性微生物と通常の抗菌薬感受性パターン(グラム陰性菌)
C.一般的な病原性微生物と通常の抗菌薬感受性パターン(嫌気性菌)
D.特記すべき細菌とマイコバクテリアに対する推奨療法
8 特定の真菌に対する推奨療法
A.真菌の概要と通常の抗真菌薬感受性パターン
B.全身感染症
C.皮膚粘膜の限局性感染症
9 特定のウイルスに対する推奨療法
A.HIV以外のウイルスに対する通常の抗ウイルス薬感受性パターン
B.特定のウイルスに対する推奨療法
10 特定の寄生虫に対する推奨療法
11 抗微生物薬リスト(ABC順)
A.全身投与用抗微生物薬の剤形と投与法
B.局所に投与する抗微生物薬(皮膚,眼,耳)
12 肥満児に対する抗菌薬療法
13 重症感染症に対する静注-経口抗菌薬療法(経口ステップダウン療法)
14 症候性感染症に対する抗微生物薬の予防投与/予防
A.曝露後の短期的な抗微生物薬予防投与
B.症候性感染症の長期的抗微生物薬予防投与
C.先行治療/潜在性感染症の治療
(無症候性感染症のある小児における症候性感染症に対する予防投与)
D.手術や処置時の予防投与
15 抗微生物薬の副作用
16 薬物相互作用
付録:体表面積決定のためのノモグラム
文献
索引
書評
開く
小児の抗菌薬の使い方を学びたい方にもイチオシ
書評者: 宮入 烈 (国立成育医療研究センター感染症科医長)
小児の抗菌薬マニュアルと言えば,評者はこの本が真っ先に思い浮かびます。John D. NelsonやJohn Bradleyといった小児科の重鎮の名を冠するこの黄色い本は米国の小児科診療の現場で長年愛用されてきた名著です。15年前,米国で小児感染症フェローとして働いていた評者も本書を “Red book” (American Academy of Pediatrics)とともにカバンに忍ばせ,コンサルトのたびに引っ張り出して抗菌薬の投与量を参照していました。今は,当院の感染症科フェローのポケットに収まり,他科からの診療相談のたびに活躍しています。
本書は,抗微生物薬の適応・用量・用法の詳細が記されたいわゆるマニュアル本です。しかし,40年以上にわたる実践の中で精度を高め,2年に1回(2014年以降は毎年)新たな知見を基に改訂され進化してきた実績があり,これに比肩するものはありません。特に治療薬選択の根拠となるエビデンスや注意事項が参考文献と共に記載されているのは本書の特徴です。例えば中耳炎の治療など議論の的となる事項については,ガイドラインの推奨やシステマチックレビューをまとめた「メモ」があります。また,壊死性筋膜炎や慢性骨髄炎に対する外科的介入の推奨など,最善の感染症治療について薬以外の治療にも言及されています。さらに,新生児,肥満児,市中MRSA感染症,小児特有の病態における予防投与などについても具体的な処方が記載されていて,包括的な内容になっています。もちろん米国のマニュアルを日本に導入するには,疫学や人種の違い,保険診療との齟齬がないかなどの検討が必要となります。そこは日米両国をまたぐ小児感染症のエキスパートである齋藤昭彦先生を中心に翻訳者陣が注釈を加えられており,大変助かります。
小児の抗菌薬の使い方を学びたい方にもイチオシの本です。冒頭には抗菌薬と抗真菌薬を選択するために鍵となる各薬剤の特徴が書かれています。一文一文に凝縮された情報を自分のものにすることができれば,自ら考えて抗菌薬を選ぶための強力な知識になります。他にも薬力学・薬物動態,静注抗菌薬から経口抗菌薬への切り替え方,副作用や相互作用などが学べる構成となっています。まずはこの本を通読し,実例に遭遇するたびに該当箇所を丁寧に読み直すことをお薦めします。読み返すたびに新たな気づきがあり,小児感染症診療に必要な抗菌薬の知識と考え方が身に付くはずです。
経験豊かな指導医による回診時の小講義を思い出す
書評者: 大曲 貴夫 (国立国際医療研究センター病院国際感染症センター長/国際診療部長)
評者自身は成人の感染症を専門としているが,修練の過程で,そして感染症医となってからも3~4歳以上の小児の感染症診療にはコンサルテーションを通じて時折かかわってきた。しかし評者は小児感染症の全体像を学んでいるわけではなく,本物の小児感染症医の先生方とは知識も経験も比較しようもない。本来この書籍はポケットに入れて日常診療の中で日々役立てるものだが,このような評者の背景もあるため,評者自身は本書を「小児感染症を知るための手引き」として読ませていただいた。
本書全体に一貫しているのは,現在わかっているエビデンスと,エビデンスのない領域を徹底して意識し,それを指針にきちんと反映している点である。特に参考となるエビデンスのない事項に関しては,それを明確にコメントとして示している。例えばマイコプラズマによる下気道感染の項目では「小児における前向きのよくコントロールされたマイコプラズマ肺炎の治療のデータには限りがある」との記載がある(p.83)。マイコプラズマ肺炎の治療薬を丸暗記することは誰でもできるが,このような記載に,編集された先生方の臨床医としての良心的な姿勢を感じる。また多くの感染症の治療期間は慣習的に定まってきたものでエビデンスに欠けるが,これもきちんと書いてある。治療期間の設定についてのマニュアルの書きぶりがあまりに断定的であれば,教条的になってしまう。読者がその記載に盲目的に従ってしまえば診療に悪影響を及ぼす。「定まっていない」ことが明確に書かれていれば,最終的にはやはり全体像を踏まえての医師の判断が必要であることを意識できる。
また本書では,疾患の自然経過についても各所に示してある。診断と経過観察を行う上で自然経過を知っておくことは大前提と言えるが,それを学べるテキストやマニュアルは少ない。
また患者の管理上,さまざまな判断が必要となる場合は,いわゆるコツが必要となる場合もある。それがコメントとして随所に記載されているのも本マニュアルの特徴である。読んでいると,経験豊かな指導医と共に回診を行っていたときの,歩きながらの小講義を思い出す。本書はマニュアルだが,その記載内容は何度も読んでかみしめてそして考えるべきものであると感じた。中にはそれを契機に自ら研究して答えを求めにいく人もいるのではなかろうか。
本書を監訳された齋藤昭彦先生には,評者の研修先である聖路加国際病院での先輩であり,評者が感染症医をめざしはじめた頃からずっとお世話になっている。初版の監訳の序からは先生の小児感染症医としての修練と,そこで培われた矜持が伝わり,一感染症医として評者も背筋が伸びる思いである。
小児感染症の専門家ばかりでなく非専門医にも薦めたい情報源
書評者: 尾内 一信 (川崎医科大教授・小児科学)
本書を手に取ってまず感じたことは,日本で長く要望されていた小児感染症の治療を簡潔に網羅したポケットに入るハンドブックのバイブルを手にすることができる喜びである。本書は,J. D. Nelson教授(テキサス州立大学ダラス校)とそのお弟子さんのJ. S. Bradley教授(カリフォルニア州立大学サンディエゴ校)による共著,“2016 Nelson's Pediatric Antimicrobial Therapy” 第22版の翻訳本である。日進月歩の医学分野においては翻訳本をいかにタイムリーに出版するかということが非常に重要なテーマであり,監訳者の齋藤昭彦博士と医学書院の編集の方々のご努力は実に賞賛に値すると思う。また,本書は小児感染症の治療をする上で必要不可欠な情報が日本語で整然とまとめられている。実に素晴らしい出来栄えであるが,編集されたのが齋藤昭彦博士なので納得できた。
“Nelson's Pediatric Antimicrobial Therapy” は,1975年から出版されているが,発行当初から現在と同じ外観でよく目立つ黄色い表紙であった。評者が米国に留学した1986年当時はまだ薄い冊子であったが,年を経て徐々に内容も充実して分厚くなってきた。当時 “The Sanford Guide to Antimicrobial Therapy” と “Nelson's Pediatric Antimicrobial Therapy” は共にとても薄い冊子だったので,レジデントやフェローはこれらをポケットに入れて日常診療(Duty)をしたりラウンドに参加したりしたものだったが,現在ではそれぞれポケットが窮屈になるぐらいに内容が充実している。当時と比べると特に解説が充実しているので,小児感染症の専門家ばかりでなく若手の小児科医や感染症に不慣れな医師でもわかりやすく役立つ情報源に仕上がっている。特に小児科以外の先生で小児を診療される先生は,ぜひとも手元において診療されることをお薦めしたい。
さて,小児感染症の原因微生物の薬剤感受性は日々変化している。それに伴って小児感染症への対応も必要に応じて変える必要がある。本書は第2版が出版されたばかりであるが,今後 “Nelson's Pediatric Antimicrobial Therapy” の改訂に伴いタイムリーに改訂されることを一読者として期待する。
書評者: 宮入 烈 (国立成育医療研究センター感染症科医長)
小児の抗菌薬マニュアルと言えば,評者はこの本が真っ先に思い浮かびます。John D. NelsonやJohn Bradleyといった小児科の重鎮の名を冠するこの黄色い本は米国の小児科診療の現場で長年愛用されてきた名著です。15年前,米国で小児感染症フェローとして働いていた評者も本書を “Red book” (American Academy of Pediatrics)とともにカバンに忍ばせ,コンサルトのたびに引っ張り出して抗菌薬の投与量を参照していました。今は,当院の感染症科フェローのポケットに収まり,他科からの診療相談のたびに活躍しています。
本書は,抗微生物薬の適応・用量・用法の詳細が記されたいわゆるマニュアル本です。しかし,40年以上にわたる実践の中で精度を高め,2年に1回(2014年以降は毎年)新たな知見を基に改訂され進化してきた実績があり,これに比肩するものはありません。特に治療薬選択の根拠となるエビデンスや注意事項が参考文献と共に記載されているのは本書の特徴です。例えば中耳炎の治療など議論の的となる事項については,ガイドラインの推奨やシステマチックレビューをまとめた「メモ」があります。また,壊死性筋膜炎や慢性骨髄炎に対する外科的介入の推奨など,最善の感染症治療について薬以外の治療にも言及されています。さらに,新生児,肥満児,市中MRSA感染症,小児特有の病態における予防投与などについても具体的な処方が記載されていて,包括的な内容になっています。もちろん米国のマニュアルを日本に導入するには,疫学や人種の違い,保険診療との齟齬がないかなどの検討が必要となります。そこは日米両国をまたぐ小児感染症のエキスパートである齋藤昭彦先生を中心に翻訳者陣が注釈を加えられており,大変助かります。
小児の抗菌薬の使い方を学びたい方にもイチオシの本です。冒頭には抗菌薬と抗真菌薬を選択するために鍵となる各薬剤の特徴が書かれています。一文一文に凝縮された情報を自分のものにすることができれば,自ら考えて抗菌薬を選ぶための強力な知識になります。他にも薬力学・薬物動態,静注抗菌薬から経口抗菌薬への切り替え方,副作用や相互作用などが学べる構成となっています。まずはこの本を通読し,実例に遭遇するたびに該当箇所を丁寧に読み直すことをお薦めします。読み返すたびに新たな気づきがあり,小児感染症診療に必要な抗菌薬の知識と考え方が身に付くはずです。
経験豊かな指導医による回診時の小講義を思い出す
書評者: 大曲 貴夫 (国立国際医療研究センター病院国際感染症センター長/国際診療部長)
評者自身は成人の感染症を専門としているが,修練の過程で,そして感染症医となってからも3~4歳以上の小児の感染症診療にはコンサルテーションを通じて時折かかわってきた。しかし評者は小児感染症の全体像を学んでいるわけではなく,本物の小児感染症医の先生方とは知識も経験も比較しようもない。本来この書籍はポケットに入れて日常診療の中で日々役立てるものだが,このような評者の背景もあるため,評者自身は本書を「小児感染症を知るための手引き」として読ませていただいた。
本書全体に一貫しているのは,現在わかっているエビデンスと,エビデンスのない領域を徹底して意識し,それを指針にきちんと反映している点である。特に参考となるエビデンスのない事項に関しては,それを明確にコメントとして示している。例えばマイコプラズマによる下気道感染の項目では「小児における前向きのよくコントロールされたマイコプラズマ肺炎の治療のデータには限りがある」との記載がある(p.83)。マイコプラズマ肺炎の治療薬を丸暗記することは誰でもできるが,このような記載に,編集された先生方の臨床医としての良心的な姿勢を感じる。また多くの感染症の治療期間は慣習的に定まってきたものでエビデンスに欠けるが,これもきちんと書いてある。治療期間の設定についてのマニュアルの書きぶりがあまりに断定的であれば,教条的になってしまう。読者がその記載に盲目的に従ってしまえば診療に悪影響を及ぼす。「定まっていない」ことが明確に書かれていれば,最終的にはやはり全体像を踏まえての医師の判断が必要であることを意識できる。
また本書では,疾患の自然経過についても各所に示してある。診断と経過観察を行う上で自然経過を知っておくことは大前提と言えるが,それを学べるテキストやマニュアルは少ない。
また患者の管理上,さまざまな判断が必要となる場合は,いわゆるコツが必要となる場合もある。それがコメントとして随所に記載されているのも本マニュアルの特徴である。読んでいると,経験豊かな指導医と共に回診を行っていたときの,歩きながらの小講義を思い出す。本書はマニュアルだが,その記載内容は何度も読んでかみしめてそして考えるべきものであると感じた。中にはそれを契機に自ら研究して答えを求めにいく人もいるのではなかろうか。
本書を監訳された齋藤昭彦先生には,評者の研修先である聖路加国際病院での先輩であり,評者が感染症医をめざしはじめた頃からずっとお世話になっている。初版の監訳の序からは先生の小児感染症医としての修練と,そこで培われた矜持が伝わり,一感染症医として評者も背筋が伸びる思いである。
小児感染症の専門家ばかりでなく非専門医にも薦めたい情報源
書評者: 尾内 一信 (川崎医科大教授・小児科学)
本書を手に取ってまず感じたことは,日本で長く要望されていた小児感染症の治療を簡潔に網羅したポケットに入るハンドブックのバイブルを手にすることができる喜びである。本書は,J. D. Nelson教授(テキサス州立大学ダラス校)とそのお弟子さんのJ. S. Bradley教授(カリフォルニア州立大学サンディエゴ校)による共著,“2016 Nelson's Pediatric Antimicrobial Therapy” 第22版の翻訳本である。日進月歩の医学分野においては翻訳本をいかにタイムリーに出版するかということが非常に重要なテーマであり,監訳者の齋藤昭彦博士と医学書院の編集の方々のご努力は実に賞賛に値すると思う。また,本書は小児感染症の治療をする上で必要不可欠な情報が日本語で整然とまとめられている。実に素晴らしい出来栄えであるが,編集されたのが齋藤昭彦博士なので納得できた。
“Nelson's Pediatric Antimicrobial Therapy” は,1975年から出版されているが,発行当初から現在と同じ外観でよく目立つ黄色い表紙であった。評者が米国に留学した1986年当時はまだ薄い冊子であったが,年を経て徐々に内容も充実して分厚くなってきた。当時 “The Sanford Guide to Antimicrobial Therapy” と “Nelson's Pediatric Antimicrobial Therapy” は共にとても薄い冊子だったので,レジデントやフェローはこれらをポケットに入れて日常診療(Duty)をしたりラウンドに参加したりしたものだったが,現在ではそれぞれポケットが窮屈になるぐらいに内容が充実している。当時と比べると特に解説が充実しているので,小児感染症の専門家ばかりでなく若手の小児科医や感染症に不慣れな医師でもわかりやすく役立つ情報源に仕上がっている。特に小児科以外の先生で小児を診療される先生は,ぜひとも手元において診療されることをお薦めしたい。
さて,小児感染症の原因微生物の薬剤感受性は日々変化している。それに伴って小児感染症への対応も必要に応じて変える必要がある。本書は第2版が出版されたばかりであるが,今後 “Nelson's Pediatric Antimicrobial Therapy” の改訂に伴いタイムリーに改訂されることを一読者として期待する。
更新情報
-
更新情報はありません。
お気に入り商品に追加すると、この商品の更新情報や関連情報などをマイページでお知らせいたします。