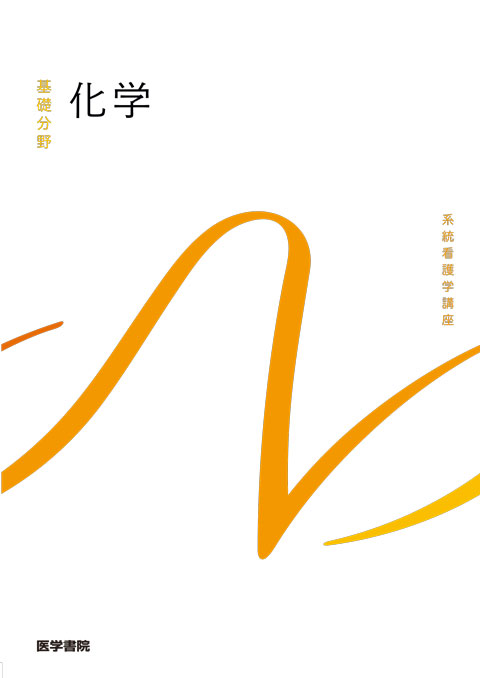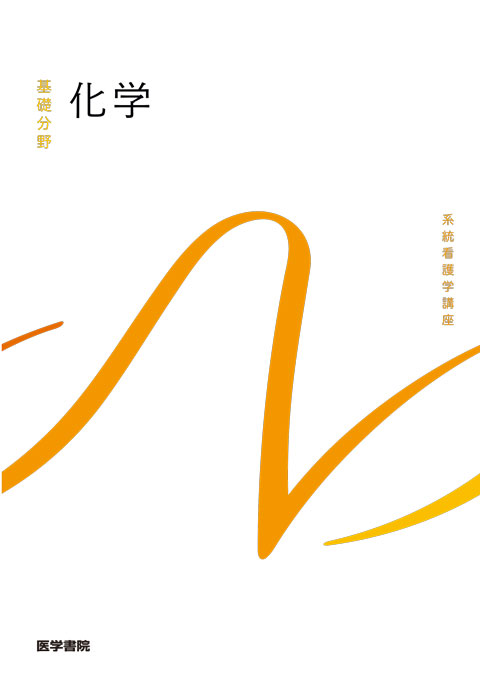化学 第7版
もっと見る
- 第1部は、中学校・高等学校で学んだ基礎的な化学用語を網羅的に復習できる構成としました。「コップ1杯の水」をテーマにやさしい解説とし、元素記号・原子・分子の書きあらわし方と読み方、pH、温度、%濃度の計算といった基本がおさらいできます。章末の穴埋め問題で知識の確認ができます。
- 単位は、SI単位のほか、TorrやmEqなどの臨床で用いられる単位について、コラムなどで補足してあります。
- 第2部では化学反応、酸化還元、反応速度、酸塩基平衡などについて学びますが、できるだけ身のまわりの反応や生理学・生化学・臨床検査で扱われる反応も取り上げ、実感をもって学べるようになっています。パルスオキシメータやMRI、血糖測定、透析など、医療機器の話題も多く取り上げています。
- 第3部の無機化学では、生体元素や環境汚染、中毒、医薬品、生活用品に関係する物質を中心に取り上げ、興味をもって読み進められるようになっています。有機化学・高分子化学は、薬理学や栄養学、生化学で扱われる物質を積極的に取り上げ、専門基礎科目や専門科目につながる内容構成としました。
- 全体の構成として、高等学校の化学で学ぶ内容(理論化学・無機化学・有機化学)はすべて網羅的に扱い、さらに原子・分子の軌道、スペクトルなどについても簡単に触れています。
- 「系統看護学講座/系看」は株式会社医学書院の登録商標です。
| シリーズ | 系統看護学講座-基礎分野 |
|---|---|
| 執筆 | 奈良 雅之 |
| 発行 | 2018年01月判型:B5頁:256 |
| ISBN | 978-4-260-03181-3 |
| 定価 | 2,640円 (本体2,400円+税) |
- 2026年春改訂
- 改訂情報
更新情報
-
正誤表を掲載しました
2022.03.23
- 序文
- 目次
- 正誤表
序文
開く
はしがき
看護師を目指すみなさんにとって,化学は生物学・物理学と並んで自然科学のなかで重要な科目に位置づけられます。これから学んでいく生理学や薬理学,生化学,栄養学,公衆衛生といった専門基礎科目を理解するためには,化学の知識が欠かせません。そして,医療の現場で働くようになると,薬液を希釈したり,医薬品を投与したり,検査値を読み取ったり,医療機器を操作したりする様々な場面において,化学の知識に基づく技術が必要となります。
たとえば,10%と1%は,数字の見かけ上は,「0」がついているかどうかの違いですが,濃度は10倍も異なります。物質は,濃度が異なることで,化学反応の方向や速度といった性質が異なってきます。医薬品の場合は,ゼロを1つ間違えることで,生体において目的とする効果が現れないばかりか,ときには致死的な作用をもたらすこともあります。溶液の濃度の調製は,理屈の上では理解していても,実際の物質を扱うとなると案外難しいものです。例えば定性実験において,「15mol/Lアンモニア水から6mol/Lアンモニア水100mLの溶液を作りなさい」と言われたとき,躊躇なくメスシリンダーでアンモニア40mLと蒸留水60mLをはかりとることができる学生は少ないものです。化学の学習を通して様々な物質の様々な濃度に触れることで,物質について十分に理解し,実際の医療現場において適切な対応ができる力を養っていく必要があります。
本書の構成
小学生や中学生の頃は好きだった理科が,高等学校に入学してから苦手になったという経験は,程度の差こそあれ多くの学生が経験してきたことかもしれません。高等学校で化学を選択せずに,大学や専門学校へ進んだ学生もいることでしょう。
本書では,まず,「序」において,中学校・高等学校の化学の基本用語を復習しながら,化学との上手な付き合い方を伝授します。ここでは「水」をテーマに取り上げていますが,ほかにも身のまわりにあるものすべてが化学に関係しますので,そういう意識をもって周囲を眺めてみましょう。「水」のテーマは,筆者が新入生を対象として行うセミナー「水の科学」をベースにしています。このセミナーでは,看護学専攻の学生に限らず,医学科・歯学科・口腔保健学科の学生も一緒にグループを作って「水」について議論します。もともと化学が好きな学生だけではなく,「化学は好きではないが,“水”には興味がある」という学生も集まってきます。化学は,私たちの生活や医学・看護から切っても切り離せないものですから,まずは関心のあるものを手掛かりとして,化学に興味をもっていくことが大切です。また,周期表は,化学を勉強するためのいわば「地図」のようなものですので,身のまわりのものと関連付けて親しんでほしいと思います。
「序」のあとは,「第1部 物質の状態」「第2部 物質の変化」「第3部 物質の構成」の3部に分けて展開していますが,その順番は必ずしも絶対的なものではありません。理解しやすいところ,必要なところから学習しましょう。第1部と第2部は,高等学校の化学のカリキュラムをベースにして理論化学を展開し,医療で必要となる項目や話題,たとえば規定度や血液ガス値,体液の緩衝系についても適宜補足してあります。
第3部の「第9章 原子の構造と化学結合」は化学の専門家が最も教えたくなるところではありますが,実際の医療の現場では,原子・分子という目に見えないミクロの化学よりも,物質の性質や取り扱いといったマクロの化学の優先度が高いと考えられますので,「第10章 無機化学」「第11章 有機化学」「第12章 高分子化学」の各論を先に学習しても全く問題ありません。各論では,実験的・工業的な知識は省き,生体物質や医薬品,中毒をおこす物質,環境汚染物質など,医療や生活・環境に関わりの深い物質を取り上げながら厳選してまとめてあります。
本書の学び方
高等学校で化学を選択していなかった学生や,化学を苦手と感じている学生は,まずは第1章をじっくり読んで,化学の基本用語をおさえてから授業に臨むとよいでしょう。一方で,化学についてもっと詳しく学びたいと感じている学生は,「第9章 原子の構造と化学結合」で扱うミクロの化学や,MRIやパルスオキシメータなどの医療機器のしくみについてのコラムなどにもチャレンジしてみて下さい。
本書は,看護職を目指す学生のみならず,医学や歯学をはじめとする医療職を志す学生のための化学の入門書としても活用できるよう,化学の基本的な学問体系に則って執筆しました。本書を活用して,よりたくさんの学生が物質についての理解を深め,その知識を医療の現場で生かしていってくれることを願っています。
2017年11月
奈良 雅之
看護師を目指すみなさんにとって,化学は生物学・物理学と並んで自然科学のなかで重要な科目に位置づけられます。これから学んでいく生理学や薬理学,生化学,栄養学,公衆衛生といった専門基礎科目を理解するためには,化学の知識が欠かせません。そして,医療の現場で働くようになると,薬液を希釈したり,医薬品を投与したり,検査値を読み取ったり,医療機器を操作したりする様々な場面において,化学の知識に基づく技術が必要となります。
たとえば,10%と1%は,数字の見かけ上は,「0」がついているかどうかの違いですが,濃度は10倍も異なります。物質は,濃度が異なることで,化学反応の方向や速度といった性質が異なってきます。医薬品の場合は,ゼロを1つ間違えることで,生体において目的とする効果が現れないばかりか,ときには致死的な作用をもたらすこともあります。溶液の濃度の調製は,理屈の上では理解していても,実際の物質を扱うとなると案外難しいものです。例えば定性実験において,「15mol/Lアンモニア水から6mol/Lアンモニア水100mLの溶液を作りなさい」と言われたとき,躊躇なくメスシリンダーでアンモニア40mLと蒸留水60mLをはかりとることができる学生は少ないものです。化学の学習を通して様々な物質の様々な濃度に触れることで,物質について十分に理解し,実際の医療現場において適切な対応ができる力を養っていく必要があります。
本書の構成
小学生や中学生の頃は好きだった理科が,高等学校に入学してから苦手になったという経験は,程度の差こそあれ多くの学生が経験してきたことかもしれません。高等学校で化学を選択せずに,大学や専門学校へ進んだ学生もいることでしょう。
本書では,まず,「序」において,中学校・高等学校の化学の基本用語を復習しながら,化学との上手な付き合い方を伝授します。ここでは「水」をテーマに取り上げていますが,ほかにも身のまわりにあるものすべてが化学に関係しますので,そういう意識をもって周囲を眺めてみましょう。「水」のテーマは,筆者が新入生を対象として行うセミナー「水の科学」をベースにしています。このセミナーでは,看護学専攻の学生に限らず,医学科・歯学科・口腔保健学科の学生も一緒にグループを作って「水」について議論します。もともと化学が好きな学生だけではなく,「化学は好きではないが,“水”には興味がある」という学生も集まってきます。化学は,私たちの生活や医学・看護から切っても切り離せないものですから,まずは関心のあるものを手掛かりとして,化学に興味をもっていくことが大切です。また,周期表は,化学を勉強するためのいわば「地図」のようなものですので,身のまわりのものと関連付けて親しんでほしいと思います。
「序」のあとは,「第1部 物質の状態」「第2部 物質の変化」「第3部 物質の構成」の3部に分けて展開していますが,その順番は必ずしも絶対的なものではありません。理解しやすいところ,必要なところから学習しましょう。第1部と第2部は,高等学校の化学のカリキュラムをベースにして理論化学を展開し,医療で必要となる項目や話題,たとえば規定度や血液ガス値,体液の緩衝系についても適宜補足してあります。
第3部の「第9章 原子の構造と化学結合」は化学の専門家が最も教えたくなるところではありますが,実際の医療の現場では,原子・分子という目に見えないミクロの化学よりも,物質の性質や取り扱いといったマクロの化学の優先度が高いと考えられますので,「第10章 無機化学」「第11章 有機化学」「第12章 高分子化学」の各論を先に学習しても全く問題ありません。各論では,実験的・工業的な知識は省き,生体物質や医薬品,中毒をおこす物質,環境汚染物質など,医療や生活・環境に関わりの深い物質を取り上げながら厳選してまとめてあります。
本書の学び方
高等学校で化学を選択していなかった学生や,化学を苦手と感じている学生は,まずは第1章をじっくり読んで,化学の基本用語をおさえてから授業に臨むとよいでしょう。一方で,化学についてもっと詳しく学びたいと感じている学生は,「第9章 原子の構造と化学結合」で扱うミクロの化学や,MRIやパルスオキシメータなどの医療機器のしくみについてのコラムなどにもチャレンジしてみて下さい。
本書は,看護職を目指す学生のみならず,医学や歯学をはじめとする医療職を志す学生のための化学の入門書としても活用できるよう,化学の基本的な学問体系に則って執筆しました。本書を活用して,よりたくさんの学生が物質についての理解を深め,その知識を医療の現場で生かしていってくれることを願っています。
2017年11月
奈良 雅之
目次
開く
序 化学の基礎知識─化学とのじょうずなつき合い方
第1章 身のまわりの化学
第2章 化学の単位と元素の周期表
A 量と単位
B 元素の周期表
第1部 物質の状態
第3章 物質の三態
A 物質の三態
B 状態の変化
C 分子間力と融点・沸点
D 圧力と大気圧
E 状態図
第4章 気体の性質
A 気体の状態方程式―理想気体
B 混合気体と分圧の法則
C 気体の液体への溶解
D 実在気体の状態方程式
第5章 液体・溶液の性質
A 溶液の濃度
B 溶液の性質
C 表面張力と界面活性剤
D コロイド
第2部 物質の変化
第6章 化学反応
A 化学反応の基本法則と種類
B 熱化学反応
C 光化学反応
D 酸化還元反応
第7章 反応速度
A 反応速度のあらわし方
B 反応次数
C 活性化エネルギーと触媒
D 反応機構
第8章 化学平衡
I 化学平衡
A 化学平衡と平衡定数
B ルシャトリエの原理
II 酸塩基平衡
A 酸と塩基
B 中和反応と塩の生成
C 電離平衡と電離定数
D 塩の水への溶解
E 中和滴定と滴定曲線
F 難溶性塩の溶解平衡
第3部 物質の構成
第9章 原子の構造と化学結合
A 原子の構造
B 化学結合
C 原子・分子の結合と分子の形
D 吸収スペクトル
第10章 無機化学
A 無機物質
B 非金属元素
C 典型金属元素
D 遷移元素
E 放射性元素
第11章 有機化学
A 有機化合物の基礎
B 脂肪族炭化水素
C 芳香族炭化水素
D 官能基と有機化合物
第12章 高分子化学
A 高分子化合物とは
B 糖質(炭水化物)
C アミノ酸,ペプチド,タンパク質
D 脂質
E 核酸
ゼミナールの解答例
索引
例題
例題1 1杯の水に含まれる水分子の数
例題2 グルコースの分子量
例題3 生理食塩液に含まれる塩の量
例題4 血液ガスの圧力の換算
例題5 ボイル・シャルルの法則
例題6 空気の重さ
例題7 単位の換算
例題8 0.90w/w%と0.90w/v%の誤差
例題9 血中のグルコース
例題10 グルコースの燃焼エンタルピーとカロリー
例題11 ヘスの法則
例題12 酢酸水溶液の水素イオン濃度とpH
例題13 アンモニア水溶液の水酸化物イオン濃度とpH
例題14 塩の水溶液のpH
例題15 酢酸+酢酸ナトリウムのpH
例題16 アンモニア+塩化アンモニウムのpH
例題17 共有結合をもつ場合の酸化数の数え方
Column・NOTE
元素記号と原子・分子,イオンの書き方と読み方
指数と指数の変換
キログラムの再定義
血液ガス分析
状態量
混合気体─呼気と吸気
水素の溶解度と水素水
当量,グラム当量,規定度
半透膜─なぜ薄い溶液から濃い溶液へ溶媒が移動するのか?
血液透析のしくみ
化学反応式のつくり方
ルミノール反応とケミカルライト
対数
体液の酸塩基平衡
パルスオキシメータ
吸収スペクトル,質量スペクトル,核磁気共鳴スペクトル
活性酸素種(活性酸素)
共役二重結合
光学異性体の旋光性(d-,l-),幾何異性体(Z-,E-,)のあらわし方
ヨウ素デンプン反応
第1章 身のまわりの化学
第2章 化学の単位と元素の周期表
A 量と単位
B 元素の周期表
第1部 物質の状態
第3章 物質の三態
A 物質の三態
B 状態の変化
C 分子間力と融点・沸点
D 圧力と大気圧
E 状態図
第4章 気体の性質
A 気体の状態方程式―理想気体
B 混合気体と分圧の法則
C 気体の液体への溶解
D 実在気体の状態方程式
第5章 液体・溶液の性質
A 溶液の濃度
B 溶液の性質
C 表面張力と界面活性剤
D コロイド
第2部 物質の変化
第6章 化学反応
A 化学反応の基本法則と種類
B 熱化学反応
C 光化学反応
D 酸化還元反応
第7章 反応速度
A 反応速度のあらわし方
B 反応次数
C 活性化エネルギーと触媒
D 反応機構
第8章 化学平衡
I 化学平衡
A 化学平衡と平衡定数
B ルシャトリエの原理
II 酸塩基平衡
A 酸と塩基
B 中和反応と塩の生成
C 電離平衡と電離定数
D 塩の水への溶解
E 中和滴定と滴定曲線
F 難溶性塩の溶解平衡
第3部 物質の構成
第9章 原子の構造と化学結合
A 原子の構造
B 化学結合
C 原子・分子の結合と分子の形
D 吸収スペクトル
第10章 無機化学
A 無機物質
B 非金属元素
C 典型金属元素
D 遷移元素
E 放射性元素
第11章 有機化学
A 有機化合物の基礎
B 脂肪族炭化水素
C 芳香族炭化水素
D 官能基と有機化合物
第12章 高分子化学
A 高分子化合物とは
B 糖質(炭水化物)
C アミノ酸,ペプチド,タンパク質
D 脂質
E 核酸
ゼミナールの解答例
索引
例題
例題1 1杯の水に含まれる水分子の数
例題2 グルコースの分子量
例題3 生理食塩液に含まれる塩の量
例題4 血液ガスの圧力の換算
例題5 ボイル・シャルルの法則
例題6 空気の重さ
例題7 単位の換算
例題8 0.90w/w%と0.90w/v%の誤差
例題9 血中のグルコース
例題10 グルコースの燃焼エンタルピーとカロリー
例題11 ヘスの法則
例題12 酢酸水溶液の水素イオン濃度とpH
例題13 アンモニア水溶液の水酸化物イオン濃度とpH
例題14 塩の水溶液のpH
例題15 酢酸+酢酸ナトリウムのpH
例題16 アンモニア+塩化アンモニウムのpH
例題17 共有結合をもつ場合の酸化数の数え方
Column・NOTE
元素記号と原子・分子,イオンの書き方と読み方
指数と指数の変換
キログラムの再定義
血液ガス分析
状態量
混合気体─呼気と吸気
水素の溶解度と水素水
当量,グラム当量,規定度
半透膜─なぜ薄い溶液から濃い溶液へ溶媒が移動するのか?
血液透析のしくみ
化学反応式のつくり方
ルミノール反応とケミカルライト
対数
体液の酸塩基平衡
パルスオキシメータ
吸収スペクトル,質量スペクトル,核磁気共鳴スペクトル
活性酸素種(活性酸素)
共役二重結合
光学異性体の旋光性(d-,l-),幾何異性体(Z-,E-,)のあらわし方
ヨウ素デンプン反応
正誤表
開く
本書の記述の正確性につきましては最善の努力を払っておりますが、この度弊社の責任におきまして、下記のような誤りがございました。お詫び申し上げますとともに訂正させていただきます。
更新情報
-
正誤表を掲載しました
2022.03.23