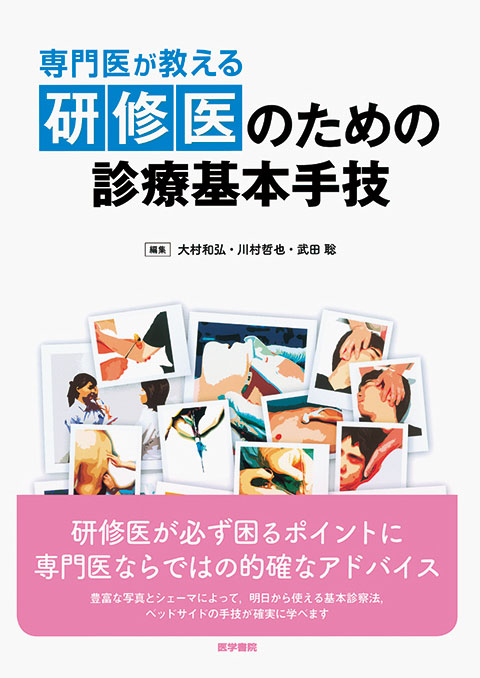専門医が教える
研修医のための診療基本手技
これからの臨床医に求められる診療基本手技を確かなものに!
もっと見る
ジェネラリストの養成に注目が集まっている現在、これからの臨床医には一定水準の診察、基本検査、救急を含めた手技の習得が欠かせない。本書は各領域のより確実な診察、基本検査、手技について、研修医が躓きやすいポイントを踏まえつつ、専門医ならではのコツを解説したもの。豊富な写真とシェーマにより、明日から使える基本診察法、ベッドサイドの手技が確実に学べる。
更新情報
-
更新情報はありません。
お気に入り商品に追加すると、この商品の更新情報や関連情報などをマイページでお知らせいたします。
- 序文
- 目次
- 書評
序文
開く
序
「各科の専門医が,研修医にとって特に必要な診察手技を書いた本です」
的確な問診と身体診察で患者さんを診断まで導く.これは医師である皆さんにとって憧れの像だと思います.そのような願いをもって,いざ身体診察の成書を開くと,山のような診察法があり,その量と奥の深さに圧倒された,そのような経験がある方も少なくないのではないでしょうか.
この本を開くと,項目別にその分野の専門家が,研修医に必要な手技を専門家の視点で教えてくれるものになっております.一冊丸々読み込めば,病棟で必要とする診察手技はたいてい網羅することができるでしょう.
私は平成16年に東京慈恵会医科大学を卒業し,当時から患者さんを総合的に診ることを重要視していた総合病院国保旭中央病院で2年間初期研修を行いました.その後同病院の救急救命科で後期研修を行い,その1年後には日本での臨床を離れ,NPO法人 JAPAN HEARTを通じてミャンマー,カンボジア,ネパールでの国際医療協力を2年間行いました.簡単に様々な検査を施行できる日本の医療と打って変わり,東南アジア諸国での限られたもののなかで行う医療活動に身を投じたことは私にとって衝撃的な経験で,身体診察の面白さや重要性に特に気づかされました.平成21年に帰国し,東京慈恵会医科大学の耳鼻咽喉科に入局,それ以降は頭頸部の領域をより詳細に診察する技術を現在まで学んでおります.
専門家になってから,頭頸部の診察のしかたや手技の方法は,それまでの5年間とは全く違ったものでした.徹底的に細部にまでこだわって診察や手技を行っている一方で,大胆に検査や手順を省略するメリハリのある診察や手技は,まさに職人技だと大変感銘を受けたことを覚えております.
このような経験を経てしだいに,
「技を持っている専門家が集まり,研修医が必要とする身体診察法や手技を,書き合う教科書を作りたい!!」という気持ちが大きくなっていきました.この企画を4年前に医学書院の七尾清氏にお話ししたところ,ご快諾いただいた当時の喜びは今でも忘れません.早速,私の尊敬する師や,ぜひ原稿を書いていただきたいと思う,信頼できる先生方お一人おひとりに電話をし,直接この本のコンセプトを説明してご協力いただくということを始めました.全員がそれぞれの勤務先の病院で主戦力となっている大変お忙しい先生方でしたが,すべての方々が心から賛同してくださり,総勢48名の先生にご協力いただきました.
そして,各分野の専門家が,ぜひこれは研修医の皆さんに知っておいてほしいという情報を厳選した本が,ここに完成いたしました.
本書を企画・編集するにあたって,医学書院とのご縁をいただきましたYMS代表市川剛先生,力強く背中を押してくださった東京慈恵会医科大学学長 松藤千弥先生,ならびにこの本のコンセプトに賛同してくださり,ご多忙中も何度も校正にお付き合いいただいた執筆者の諸先生方,編集の先生方のご尽力は感謝してもしきれません.
最後になりますが,七尾清氏,長い編集会議にもじっくりと付き合ってくださった医学書院の大橋尚彦氏,有賀大氏をはじめ関係者の皆様方に心より御礼を申し上げます.
このような機会をいただくことができた幸運に感謝し,本書が皆様の,そして患者さんの毎日をより輝かせるものとなることを心より祈っております.
2018年2月
大村和弘
的確な問診と身体診察で患者さんを診断まで導く.これは医師である皆さんにとって憧れの像だと思います.そのような願いをもって,いざ身体診察の成書を開くと,山のような診察法があり,その量と奥の深さに圧倒された,そのような経験がある方も少なくないのではないでしょうか.
この本を開くと,項目別にその分野の専門家が,研修医に必要な手技を専門家の視点で教えてくれるものになっております.一冊丸々読み込めば,病棟で必要とする診察手技はたいてい網羅することができるでしょう.
私は平成16年に東京慈恵会医科大学を卒業し,当時から患者さんを総合的に診ることを重要視していた総合病院国保旭中央病院で2年間初期研修を行いました.その後同病院の救急救命科で後期研修を行い,その1年後には日本での臨床を離れ,NPO法人 JAPAN HEARTを通じてミャンマー,カンボジア,ネパールでの国際医療協力を2年間行いました.簡単に様々な検査を施行できる日本の医療と打って変わり,東南アジア諸国での限られたもののなかで行う医療活動に身を投じたことは私にとって衝撃的な経験で,身体診察の面白さや重要性に特に気づかされました.平成21年に帰国し,東京慈恵会医科大学の耳鼻咽喉科に入局,それ以降は頭頸部の領域をより詳細に診察する技術を現在まで学んでおります.
専門家になってから,頭頸部の診察のしかたや手技の方法は,それまでの5年間とは全く違ったものでした.徹底的に細部にまでこだわって診察や手技を行っている一方で,大胆に検査や手順を省略するメリハリのある診察や手技は,まさに職人技だと大変感銘を受けたことを覚えております.
このような経験を経てしだいに,
「技を持っている専門家が集まり,研修医が必要とする身体診察法や手技を,書き合う教科書を作りたい!!」という気持ちが大きくなっていきました.この企画を4年前に医学書院の七尾清氏にお話ししたところ,ご快諾いただいた当時の喜びは今でも忘れません.早速,私の尊敬する師や,ぜひ原稿を書いていただきたいと思う,信頼できる先生方お一人おひとりに電話をし,直接この本のコンセプトを説明してご協力いただくということを始めました.全員がそれぞれの勤務先の病院で主戦力となっている大変お忙しい先生方でしたが,すべての方々が心から賛同してくださり,総勢48名の先生にご協力いただきました.
そして,各分野の専門家が,ぜひこれは研修医の皆さんに知っておいてほしいという情報を厳選した本が,ここに完成いたしました.
本書を企画・編集するにあたって,医学書院とのご縁をいただきましたYMS代表市川剛先生,力強く背中を押してくださった東京慈恵会医科大学学長 松藤千弥先生,ならびにこの本のコンセプトに賛同してくださり,ご多忙中も何度も校正にお付き合いいただいた執筆者の諸先生方,編集の先生方のご尽力は感謝してもしきれません.
最後になりますが,七尾清氏,長い編集会議にもじっくりと付き合ってくださった医学書院の大橋尚彦氏,有賀大氏をはじめ関係者の皆様方に心より御礼を申し上げます.
このような機会をいただくことができた幸運に感謝し,本書が皆様の,そして患者さんの毎日をより輝かせるものとなることを心より祈っております.
2018年2月
大村和弘
目次
開く
I 医療面接
1 医師のプロフェッショナリズム
[COLUMN]臨床倫理コンサルテーション
[COLUMN]事前指示(Advance Directive),
アドバンス・ケア・プランニングと意思決定支援
2 Medical Interview
[COLUMN]ストレスコーピング
3 診療録記載
[COLUMN]SOAPを書こう
4 温度表
5 リスクマネジメント
[COLUMN]研修医のためのリスクマネジメント川柳
6 小児の診察のしかた
7 臨終の立会いかた
8 フィードバック
II 基本診察法
1 頭頸部:頸部診察
2 頭頸部:口腔内
3 眼科
4 歯科
5 胸部:心臓
6 胸部:肺
7 乳房診察
8 腹部
9 四肢:関節・腰痛
10 四肢:むくみ・浮腫
11 神経
12 皮膚
13 小児
14 産婦人科
15 精神科
III 基本的な臨床検査
1 血液型判定・交差適合試験
2 心電図・負荷心電図
3 超音波検査
4 ベッドサイドの画像診断─ポータブル胸部単純写真の意義と読影アプローチ
IV 基本的手技
1 末梢静脈路の確保
[COLUMN]点滴の挿入のコツ
2 動脈血採血・ライン
3 血液培養
[COLUMN]新しい敗血症の定義
4 グラム染色
5 中心静脈穿刺のコツ
6 腰椎穿刺
7 胃管挿入
8 導尿・尿道カテーテル挿入
9 直腸診
10 胸腔ドレーン挿入のコツ
11 腹腔穿刺
V 外科・救急手技・ベッドサイド手技
1 酸素投与法
2 挿管
3 緊急気道確保:非侵襲的
4 緊急気道確保:侵襲的
5 気管カニューレの入れ替えのしかた
6 心肺蘇生法
7 カテコラミンの使いかた
8 局所麻酔のしかた
9 針・糸の選びかた
10 道具の持ちかた・使いかた
11 皮膚縫合
12 創部の消毒とガーゼ交換
13 術後の診察のポイント
14 外傷・熱傷の処置
15 包帯法と捻挫の基礎
索引
1 医師のプロフェッショナリズム
[COLUMN]臨床倫理コンサルテーション
[COLUMN]事前指示(Advance Directive),
アドバンス・ケア・プランニングと意思決定支援
2 Medical Interview
[COLUMN]ストレスコーピング
3 診療録記載
[COLUMN]SOAPを書こう
4 温度表
5 リスクマネジメント
[COLUMN]研修医のためのリスクマネジメント川柳
6 小児の診察のしかた
7 臨終の立会いかた
8 フィードバック
II 基本診察法
1 頭頸部:頸部診察
2 頭頸部:口腔内
3 眼科
4 歯科
5 胸部:心臓
6 胸部:肺
7 乳房診察
8 腹部
9 四肢:関節・腰痛
10 四肢:むくみ・浮腫
11 神経
12 皮膚
13 小児
14 産婦人科
15 精神科
III 基本的な臨床検査
1 血液型判定・交差適合試験
2 心電図・負荷心電図
3 超音波検査
4 ベッドサイドの画像診断─ポータブル胸部単純写真の意義と読影アプローチ
IV 基本的手技
1 末梢静脈路の確保
[COLUMN]点滴の挿入のコツ
2 動脈血採血・ライン
3 血液培養
[COLUMN]新しい敗血症の定義
4 グラム染色
5 中心静脈穿刺のコツ
6 腰椎穿刺
7 胃管挿入
8 導尿・尿道カテーテル挿入
9 直腸診
10 胸腔ドレーン挿入のコツ
11 腹腔穿刺
V 外科・救急手技・ベッドサイド手技
1 酸素投与法
2 挿管
3 緊急気道確保:非侵襲的
4 緊急気道確保:侵襲的
5 気管カニューレの入れ替えのしかた
6 心肺蘇生法
7 カテコラミンの使いかた
8 局所麻酔のしかた
9 針・糸の選びかた
10 道具の持ちかた・使いかた
11 皮膚縫合
12 創部の消毒とガーゼ交換
13 術後の診察のポイント
14 外傷・熱傷の処置
15 包帯法と捻挫の基礎
索引
書評
開く
初期研修医に必要な手技を効率よく学習できる
書評者: 徳田 安春 (群星沖縄臨床研修センター長)
総勢49名の各科専門医が研修医にとって特に必要な診察手技を書いた,という本です。病棟や救急室で必要とする診察手技は網羅していることが特徴です。冒頭の「医療面接」のチャプターは,病歴聴取や診療録の記載の仕方の基本,温度表,小児の診察などが網羅されているだけでなく,これからプロフェッショナルとして成長していく研修医にとって重要な事項もカバーしています。プロフェッショナリズムやフィードバック,臨終の立ち会いかたなどの項目です。
さらにはコラムとして,臨床倫理コンサルテーションや事前指示,アドバンス・ケア・プランニングなどの具体的なやりかたについて学習することができます。超高齢社会に直面している日本では,全ての医師が,事前指示やアドバンス・ケア・プランニングについての理解と実践方法を身につけることが求められています。2年間もの激しい心理的および肉体的ストレスにさらされる研修医には,ストレスコーピングについての項目は大きな助けになるに違いないと思います。
次のチャプターは「基本診察法」。豊富な写真やイラストとわかりやすい解説で,基本的な診察方法を身につけるベースを研修医に与えてくれます。診察部位によっては高度な手技の解説も含まれています。特に,頭頸部,眼科,歯科の領域における診察手技については,これまでに出版された類書には含まれていなかった技が披露されています。頭頸部の項目では,編集者の一人であり本書の企画を考えられたエキスパート耳鼻咽喉科医の教育への情熱に触れることができます。
続いて,「基本的な臨床検査」のチャプターがあります。研修医が現場で実施すべき心電図や超音波検査,ベッドサイドの画像診断に加えて,血液型判定と交差適合試験の基本と実施方法について学ぶことができます。評者の研修医時代,深夜の当直時間帯で遭遇した重症多発外傷患者における生血輸血診療を行ったころには良い教科書がなく,検査技師さんから徒弟的に教わり,やっとの思いでマスターしたことを思い出します。今では本書があるおかげで効率的に学ぶことができると思います。
さて,後半の2つのチャプターの「基本的手技」と「外科・救急手技・ベッドサイド手技」が,本書のコア部分であると思います。ここでも写真とイラスト,簡潔明瞭な解説文によって,それぞれの手技の全体像と重要ポイントを短時間でマスターすることができます。基本的手技を学習していく方略として最近ではビデオやシミュレーショントレーニングなどが導入されていますが,学習者の脳内シミュレーションをロジカルに構築するためにも,本書をよく読んでその図表をビジュアルに記憶しておくと学習効率が高くなると思います。ビデオやマネキンと異なり,プリントされた書物での学習にはグラフィック記憶を促す効果があると思います。
以上,初期研修医が最も必要とするコンテンツが効率よく学習できる書物です。クリニカルクラークシップを始める前の医学生の時からこの本を持ち歩いて何度も読み返すことにより,初期研修へのスムーズな移行がよりよくできることにつながると思います。
単なる知識や技術を越えた優しさや矜持に溢れた書
書評者: 青木 眞 (感染症コンサルタント)
編者のお一人である大村和弘先生とは,当時大村先生がご所属だった総合病院国保旭中央病院にカンファレンスなどで評者が定期的に伺っていたことでお会いして以来14年の付き合いとなる。初期研修の後,NPO法人JAPAN HEARTで吉岡秀人先生と出会い,アジアを中心とした国際医療協力に一時期身をていしたことは,明るく奔放なようでいて繊細な神経を持つ彼を知るものとして好ましく,ずっと好感を抱き続けてきた。プライマリケア,総合診療といった世界から一見最も距離のある,巨大な機械力に取り囲まれた大学病院という環境に身を置きながら,臨床医として誰もが身につけておきたい「一定水準の診察,基本検査,救急を含めた手技の習得」をめざした本書を生み出した大村先生ならではの歴史である。本書の,特に大村先生自身が執筆された章には,大学病院で週6日の診療を受け持ちながら,年に一度は自費でアジアの国を訪ね,国際協力活動に取り組む一人の医師としての,単なる知識や技術を越えた優しさや矜恃が溢れている。
一部を紹介すると,
I-6「小児の診察のしかた(p32)」
基本的に小児の診察(耳鼻科領域)は抑えずに行えますし(中略)この診察の根底に流れる原則というのは,子どもの自主性,自立性を重んじて,診察を理解してもらうことです。(中略)扉から一番離れた場所(机がある位置よりもさらに遠方)に椅子を置き,(中略)これは,子どもが嫌だと思ったときに逃げることができる場所で,私のことをまず認識してもらうということを大切にしています。ここまで本文。
この章の「挨拶」「スキンシップ」「約束」などの説明や写真が大村先生の診療姿勢を示しており好ましい。
II-2「頭頸部:口腔内(p49)」
反射を起こさないで診察をするということ(評者はわざと反射を起こして喉の奥を見ていました)(中略)では,どうすれば反射を起こさないのか? (1)患者との呼吸を合わせる,(2)舌圧子の使いかた,および診察の順番,(3)最初は優しく,刺激を少なく,(4)評価するポイントをしっかりと決める(中略)実はほとんどの患者で舌圧子は必要ありません。ここまで本文。
この他にも,III-1「血液型判定・交差適合試験(p132~5)」(順大練馬病院・小松孝行先生),IV-1「末梢静脈路の確保(p156~63)」(慈恵医大血管外科・宿澤孝太先生),IV-4「グラム染色(p178~81)」(東京ベイ・浦安市川医療センター感染症内科・織田錬太郎先生,関東労災病院感染症内科・本郷偉元先生)などをはじめとするわかりやすいセクションが多い。
通読するのは骨が折れると思われる方は,その都度今日行わなければならない手技の予習として関係のセクションを勉強するのでもよいと思う。「技を持っている専門家が集まり,研修医が必要とする身体診察法や手技を,書き合う教科書を作りたい!!」という意図をもって作られた本書が,多くの研修医や彼らの指導医の眼に留まることを期待している。
書評者: 徳田 安春 (群星沖縄臨床研修センター長)
総勢49名の各科専門医が研修医にとって特に必要な診察手技を書いた,という本です。病棟や救急室で必要とする診察手技は網羅していることが特徴です。冒頭の「医療面接」のチャプターは,病歴聴取や診療録の記載の仕方の基本,温度表,小児の診察などが網羅されているだけでなく,これからプロフェッショナルとして成長していく研修医にとって重要な事項もカバーしています。プロフェッショナリズムやフィードバック,臨終の立ち会いかたなどの項目です。
さらにはコラムとして,臨床倫理コンサルテーションや事前指示,アドバンス・ケア・プランニングなどの具体的なやりかたについて学習することができます。超高齢社会に直面している日本では,全ての医師が,事前指示やアドバンス・ケア・プランニングについての理解と実践方法を身につけることが求められています。2年間もの激しい心理的および肉体的ストレスにさらされる研修医には,ストレスコーピングについての項目は大きな助けになるに違いないと思います。
次のチャプターは「基本診察法」。豊富な写真やイラストとわかりやすい解説で,基本的な診察方法を身につけるベースを研修医に与えてくれます。診察部位によっては高度な手技の解説も含まれています。特に,頭頸部,眼科,歯科の領域における診察手技については,これまでに出版された類書には含まれていなかった技が披露されています。頭頸部の項目では,編集者の一人であり本書の企画を考えられたエキスパート耳鼻咽喉科医の教育への情熱に触れることができます。
続いて,「基本的な臨床検査」のチャプターがあります。研修医が現場で実施すべき心電図や超音波検査,ベッドサイドの画像診断に加えて,血液型判定と交差適合試験の基本と実施方法について学ぶことができます。評者の研修医時代,深夜の当直時間帯で遭遇した重症多発外傷患者における生血輸血診療を行ったころには良い教科書がなく,検査技師さんから徒弟的に教わり,やっとの思いでマスターしたことを思い出します。今では本書があるおかげで効率的に学ぶことができると思います。
さて,後半の2つのチャプターの「基本的手技」と「外科・救急手技・ベッドサイド手技」が,本書のコア部分であると思います。ここでも写真とイラスト,簡潔明瞭な解説文によって,それぞれの手技の全体像と重要ポイントを短時間でマスターすることができます。基本的手技を学習していく方略として最近ではビデオやシミュレーショントレーニングなどが導入されていますが,学習者の脳内シミュレーションをロジカルに構築するためにも,本書をよく読んでその図表をビジュアルに記憶しておくと学習効率が高くなると思います。ビデオやマネキンと異なり,プリントされた書物での学習にはグラフィック記憶を促す効果があると思います。
以上,初期研修医が最も必要とするコンテンツが効率よく学習できる書物です。クリニカルクラークシップを始める前の医学生の時からこの本を持ち歩いて何度も読み返すことにより,初期研修へのスムーズな移行がよりよくできることにつながると思います。
単なる知識や技術を越えた優しさや矜持に溢れた書
書評者: 青木 眞 (感染症コンサルタント)
編者のお一人である大村和弘先生とは,当時大村先生がご所属だった総合病院国保旭中央病院にカンファレンスなどで評者が定期的に伺っていたことでお会いして以来14年の付き合いとなる。初期研修の後,NPO法人JAPAN HEARTで吉岡秀人先生と出会い,アジアを中心とした国際医療協力に一時期身をていしたことは,明るく奔放なようでいて繊細な神経を持つ彼を知るものとして好ましく,ずっと好感を抱き続けてきた。プライマリケア,総合診療といった世界から一見最も距離のある,巨大な機械力に取り囲まれた大学病院という環境に身を置きながら,臨床医として誰もが身につけておきたい「一定水準の診察,基本検査,救急を含めた手技の習得」をめざした本書を生み出した大村先生ならではの歴史である。本書の,特に大村先生自身が執筆された章には,大学病院で週6日の診療を受け持ちながら,年に一度は自費でアジアの国を訪ね,国際協力活動に取り組む一人の医師としての,単なる知識や技術を越えた優しさや矜恃が溢れている。
一部を紹介すると,
I-6「小児の診察のしかた(p32)」
基本的に小児の診察(耳鼻科領域)は抑えずに行えますし(中略)この診察の根底に流れる原則というのは,子どもの自主性,自立性を重んじて,診察を理解してもらうことです。(中略)扉から一番離れた場所(机がある位置よりもさらに遠方)に椅子を置き,(中略)これは,子どもが嫌だと思ったときに逃げることができる場所で,私のことをまず認識してもらうということを大切にしています。ここまで本文。
この章の「挨拶」「スキンシップ」「約束」などの説明や写真が大村先生の診療姿勢を示しており好ましい。
II-2「頭頸部:口腔内(p49)」
反射を起こさないで診察をするということ(評者はわざと反射を起こして喉の奥を見ていました)(中略)では,どうすれば反射を起こさないのか? (1)患者との呼吸を合わせる,(2)舌圧子の使いかた,および診察の順番,(3)最初は優しく,刺激を少なく,(4)評価するポイントをしっかりと決める(中略)実はほとんどの患者で舌圧子は必要ありません。ここまで本文。
この他にも,III-1「血液型判定・交差適合試験(p132~5)」(順大練馬病院・小松孝行先生),IV-1「末梢静脈路の確保(p156~63)」(慈恵医大血管外科・宿澤孝太先生),IV-4「グラム染色(p178~81)」(東京ベイ・浦安市川医療センター感染症内科・織田錬太郎先生,関東労災病院感染症内科・本郷偉元先生)などをはじめとするわかりやすいセクションが多い。
通読するのは骨が折れると思われる方は,その都度今日行わなければならない手技の予習として関係のセクションを勉強するのでもよいと思う。「技を持っている専門家が集まり,研修医が必要とする身体診察法や手技を,書き合う教科書を作りたい!!」という意図をもって作られた本書が,多くの研修医や彼らの指導医の眼に留まることを期待している。
更新情報
-
更新情報はありません。
お気に入り商品に追加すると、この商品の更新情報や関連情報などをマイページでお知らせいたします。