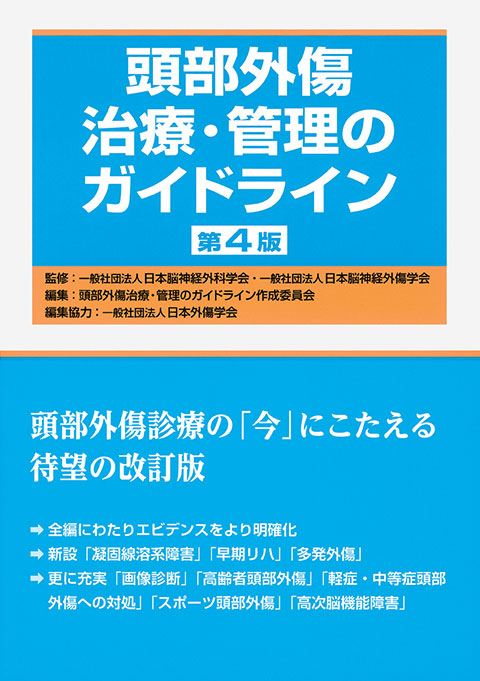頭部外傷治療・管理のガイドライン 第4版
初期診療から専門診療への連携、治療後の社会復帰支援との連携にも着目した充実の改訂版
もっと見る
頭部外傷診療を取り巻く環境変化、蓄積されたエビデンスを反映した待望の改訂版。専門診療後の後療法や社会復帰支援との連携に着目し「早期リハ」、初期診療から頭部外傷専門診療への連携を重視し「凝固線溶系障害」「多発外傷」を新設。「画像診断」「高次脳機能障害」「高齢者頭部外傷」「スポーツ頭部外傷」等の各項では更なる充実を図った。※第3版までの『重症頭部外傷治療・管理のガイドライン』からタイトルを変更した。
| 監修 | 一般社団法人 日本脳神経外科学会 / 一般社団法人 日本脳神経外傷学会 |
|---|---|
| 編集 | 頭部外傷治療・管理のガイドライン 作成委員会 |
| 編集協力 | 一般社団法人 日本外傷学会 |
| 発行 | 2019年10月判型:A5頁:272 |
| ISBN | 978-4-260-03960-4 |
| 定価 | 3,300円 (本体3,000円+税) |
更新情報
-
正誤表を掲載しました。
2024.07.30
- 序文
- 目次
- 正誤表
序文
開く
序 「頭部外傷治療・管理のガイドライン」の改訂(第4版)にあたって
「重症頭部外傷治療・管理のガイドライン」は2000年に初版を上梓し,以来2007年に第2版,2013年に第3版と版を重ね,このたび第4版が作成されるに至った.前版の序文にもあるように,ガイドラインの基本理念は医療の質を一定の水準に保ち診療に資することである.一方,診療システムや診療体制,社会情勢や診療対象,エビデンスの蓄積等,頭部外傷診療を取り巻く環境は刻々と変化しており,本版では,これらの変化に対応すべく改訂を行った.
まず,本邦における頭部外傷診療は,救急および外傷初期診療の標準化が広く浸透し,初期診療における救急医・研修医の比重が増加していることを鑑み,初期診療から頭部外傷専門診療への連携を重視した.すなわち,画像診断の項目の充実を図り,凝固線溶障害および多発外傷の項目をあらたに追加した.また,専門診療後の後療法や社会復帰支援との連携にも着目し,早期リハビリテーションの項目を新設し,高次脳機能障害の項目の充実を図った.
近年では頭部外傷重症例が減少し中等症・軽症例が増加していることから,本書のタイトルを前版までの「重症頭部外傷治療・管理のガイドライン」から「頭部外傷治療・管理のガイドライン」へと改め,軽症・中等症への対処の項目の充実を図った.中等症・軽症例の増加は,診療対象の高齢化,あるいは受傷機転の変化によるところも大きく,高齢者頭部外傷,スポーツ頭部外傷などの項目も充実を図ることとなった.
エビデンスに関しては,前版発刊(2013年)後,2018年3月までに発表された頭部外傷関連の論文をPubMedおよび医学中央雑誌の各データベースを使って検索し,PubMed約5,300件,医学中央雑誌約7,300件の該当文献を得た.これらの文献に批判的吟味がなされた後,引用文献を絞り込み,前版および各項目執筆担当者による引用文献を合わせた計約700文献を引用文献とした.同時に今版ではエビデンスの明確化も基本方針として掲げ,推奨グレードの論拠となった引用文献のエビデンスレベルについても全項目で記載した.
今版の作成にあたっては,前版の客観的評価として日本医療機能評価機構による外部評価(AGREE II)を導入した.その結果,「重要なテーマを扱っており,非専門医にとっても利用しやすい内容」との評価を得る一方,推奨とそれを支えるエビデンスの対応関係,採用されたエビデンスの検索・採択・評価方法,推奨の呈示に向けたコンセンサスの形成方法,本ガイドラインの作成に要した資金源,ガイドライン作成委員の所属・専門分野,利益相反等に関する記載が求められた.これらの指摘に対しては後述する「本書の見方」で詳細に記載した.
以上のような頭部外傷診療をとりまく環境変化と診療連携へのアップデ―トを中心に据え,ガイドラインの改訂を行った結果,前版を大きく上回る分量となったが,より充実した内容となったように思う.本ガイドラインが広く活用され,本邦の頭部外傷診療の向上に寄与することを期待してやまない.
2019年4月
ガイドライン作成委員長 冨永悌二
同 事務局 刈部 博
「重症頭部外傷治療・管理のガイドライン」は2000年に初版を上梓し,以来2007年に第2版,2013年に第3版と版を重ね,このたび第4版が作成されるに至った.前版の序文にもあるように,ガイドラインの基本理念は医療の質を一定の水準に保ち診療に資することである.一方,診療システムや診療体制,社会情勢や診療対象,エビデンスの蓄積等,頭部外傷診療を取り巻く環境は刻々と変化しており,本版では,これらの変化に対応すべく改訂を行った.
まず,本邦における頭部外傷診療は,救急および外傷初期診療の標準化が広く浸透し,初期診療における救急医・研修医の比重が増加していることを鑑み,初期診療から頭部外傷専門診療への連携を重視した.すなわち,画像診断の項目の充実を図り,凝固線溶障害および多発外傷の項目をあらたに追加した.また,専門診療後の後療法や社会復帰支援との連携にも着目し,早期リハビリテーションの項目を新設し,高次脳機能障害の項目の充実を図った.
近年では頭部外傷重症例が減少し中等症・軽症例が増加していることから,本書のタイトルを前版までの「重症頭部外傷治療・管理のガイドライン」から「頭部外傷治療・管理のガイドライン」へと改め,軽症・中等症への対処の項目の充実を図った.中等症・軽症例の増加は,診療対象の高齢化,あるいは受傷機転の変化によるところも大きく,高齢者頭部外傷,スポーツ頭部外傷などの項目も充実を図ることとなった.
エビデンスに関しては,前版発刊(2013年)後,2018年3月までに発表された頭部外傷関連の論文をPubMedおよび医学中央雑誌の各データベースを使って検索し,PubMed約5,300件,医学中央雑誌約7,300件の該当文献を得た.これらの文献に批判的吟味がなされた後,引用文献を絞り込み,前版および各項目執筆担当者による引用文献を合わせた計約700文献を引用文献とした.同時に今版ではエビデンスの明確化も基本方針として掲げ,推奨グレードの論拠となった引用文献のエビデンスレベルについても全項目で記載した.
今版の作成にあたっては,前版の客観的評価として日本医療機能評価機構による外部評価(AGREE II)を導入した.その結果,「重要なテーマを扱っており,非専門医にとっても利用しやすい内容」との評価を得る一方,推奨とそれを支えるエビデンスの対応関係,採用されたエビデンスの検索・採択・評価方法,推奨の呈示に向けたコンセンサスの形成方法,本ガイドラインの作成に要した資金源,ガイドライン作成委員の所属・専門分野,利益相反等に関する記載が求められた.これらの指摘に対しては後述する「本書の見方」で詳細に記載した.
以上のような頭部外傷診療をとりまく環境変化と診療連携へのアップデ―トを中心に据え,ガイドラインの改訂を行った結果,前版を大きく上回る分量となったが,より充実した内容となったように思う.本ガイドラインが広く活用され,本邦の頭部外傷診療の向上に寄与することを期待してやまない.
2019年4月
ガイドライン作成委員長 冨永悌二
同 事務局 刈部 博
目次
開く
序
第3版の序
第2版の序
初版の序
第4版のガイドライン改訂の経緯
第3版のガイドライン改訂の経緯
第2版のガイドライン改訂の経緯
初版のガイドライン作成の経緯
執筆者・Reviewer一覧
本書の見方
1 救急医療体制と脳神経外科医
1-1 病院前救護(プレホスピタル・ケア)
1-2 専門施設への搬送基準,搬送方法,情報伝達システム
1-3 専門施設でのチーム医療における脳神経外科医の役割
2 初期治療
2-1 外傷初期診療
2-2 気道の確保と呼吸管理
2-3 循環管理
2-4 切迫脳ヘルニアの認識と対処
3 画像診断
4 ICU管理
4-1 モニタリング
4-2 頭蓋内圧(ICP)測定の適応と方法
4-3 頭蓋内圧(ICP)と脳灌流圧(CPP)の治療閾値
4-3-1 頭蓋内圧(ICP)の治療閾値
4-3-2 脳灌流圧(CPP)の治療閾値
4-4 外科的処置(外減圧,内減圧,髄液ドレナージ)
4-4-1 外減圧
4-4-2 内減圧
4-4-3 髄液ドレナージ
4-5 鎮静,鎮痛,不動化
4-6 頭位挙上
4-7 過換気療法
4-8 マンニトール,グリセオール®,高張食塩水
4-9 バルビツレート療法
4-10 ステロイド剤
4-11 低体温療法(脳低温療法)
4-12 頭蓋内圧亢進の治療手順
4-13 外傷性けいれん発作・てんかんとその管理
4-14 栄養管理
4-15 抗菌薬
5 手術適応と手術方法
5-1 閉鎖性頭蓋骨陥没骨折
5-2 開放性頭蓋骨陥没骨折
5-3 穿通外傷
5-4 急性硬膜外血腫
5-5 急性硬膜下血腫
5-6 脳内血腫,脳挫傷
5-7 びまん性脳損傷
5-8 外傷性頭頚部血管損傷
5-8-1 診断のための検査
5-8-2 治療
5-9 外傷性髄液漏
5-10 視神経管骨折,視神経損傷
5-10-1 発生機序
5-10-2 診断
5-10-3 治療
5-11 頭部外傷急性期の麻酔
6 頭蓋顔面損傷への対処
6-1 眼窩底破裂(吹き抜け)骨折(blow-out fracture)
6-2 顎顔面外傷
6-2-1 初期対応
6-2-2 診断
6-2-3 治療
7 小児頭部外傷
7-1 病院前救護
7-2 専門施設への搬送基準
7-3 来院後の初期治療
7-4 ICUでの管理
7-4-1 頭蓋内圧(ICP)の測定の適応と方法
7-4-2 頭蓋内圧(ICP)の治療閾値
7-4-3 脳灌流圧(CPP)の治療閾値
7-4-4 鎮静剤,鎮痛剤,筋弛緩剤の治療的使用に関して
7-4-5 脳室ドレナージによる頭蓋内圧(ICP)管理
7-4-6 高張剤による治療
7-4-7 過換気療法
7-4-8 バルビツレート療法
7-4-9 体温管理療法
7-4-10 減圧開頭法
7-4-11 ステロイドの使用について
7-4-12 栄養管理
7-4-13 抗てんかん薬
7-4-14 頭位挙上
7-5 虐待による頭部外傷(abusive head trauma : AHT)
8 高齢者頭部外傷
8-1 病院前救護
8-2 初期診療
8-3 管理
8-4 手術適応と手術方法
8-4-1 Talk and deteriorate
8-4-2 急性硬膜下血腫
8-4-3 減圧開頭術
8-5 抗凝固薬・抗血小板薬の影響
9 軽症・中等症頭部外傷への対処
9-1 基本的な治療指針
9-1-1 軽症・中等症頭部外傷の診断
9-1-2 脳振盪後症候群
9-1-3 画像診断
9-1-4 治療指針
9-1-5 職場(または学校)復帰の推奨基準
9-2 重症化の危険因子
10 スポーツ頭部外傷
10-1 脳振盪に有効な診断方法
10-2 脳振盪後の診療
10-3 脳振盪の予防
10-4 慢性外傷性脳症(chronic traumatic encephalopathy : CTE)
11 外傷に伴う高次脳機能障害
11-1 外傷後高次脳機能障害の発症
11-2 急性期画像診断
11-3 高次脳機能障害の評価
11-4 慢性期画像診断
11-5 軽症脳外傷後高次脳機能障害における画像診断
11-6 認知リハビリテーション
11-7 薬物療法
11-8 包括的プログラム
11-9 自動車運転再開
12 外傷に伴う低髄液圧症候群
13 補遺
13-1 頭部外傷に伴う凝固線溶系障害
13-2 早期リハビリテーション
13-3 外傷急性期の精神障害
13-4 多発外傷
索引
第3版の序
第2版の序
初版の序
第4版のガイドライン改訂の経緯
第3版のガイドライン改訂の経緯
第2版のガイドライン改訂の経緯
初版のガイドライン作成の経緯
執筆者・Reviewer一覧
本書の見方
1 救急医療体制と脳神経外科医
1-1 病院前救護(プレホスピタル・ケア)
1-2 専門施設への搬送基準,搬送方法,情報伝達システム
1-3 専門施設でのチーム医療における脳神経外科医の役割
2 初期治療
2-1 外傷初期診療
2-2 気道の確保と呼吸管理
2-3 循環管理
2-4 切迫脳ヘルニアの認識と対処
3 画像診断
4 ICU管理
4-1 モニタリング
4-2 頭蓋内圧(ICP)測定の適応と方法
4-3 頭蓋内圧(ICP)と脳灌流圧(CPP)の治療閾値
4-3-1 頭蓋内圧(ICP)の治療閾値
4-3-2 脳灌流圧(CPP)の治療閾値
4-4 外科的処置(外減圧,内減圧,髄液ドレナージ)
4-4-1 外減圧
4-4-2 内減圧
4-4-3 髄液ドレナージ
4-5 鎮静,鎮痛,不動化
4-6 頭位挙上
4-7 過換気療法
4-8 マンニトール,グリセオール®,高張食塩水
4-9 バルビツレート療法
4-10 ステロイド剤
4-11 低体温療法(脳低温療法)
4-12 頭蓋内圧亢進の治療手順
4-13 外傷性けいれん発作・てんかんとその管理
4-14 栄養管理
4-15 抗菌薬
5 手術適応と手術方法
5-1 閉鎖性頭蓋骨陥没骨折
5-2 開放性頭蓋骨陥没骨折
5-3 穿通外傷
5-4 急性硬膜外血腫
5-5 急性硬膜下血腫
5-6 脳内血腫,脳挫傷
5-7 びまん性脳損傷
5-8 外傷性頭頚部血管損傷
5-8-1 診断のための検査
5-8-2 治療
5-9 外傷性髄液漏
5-10 視神経管骨折,視神経損傷
5-10-1 発生機序
5-10-2 診断
5-10-3 治療
5-11 頭部外傷急性期の麻酔
6 頭蓋顔面損傷への対処
6-1 眼窩底破裂(吹き抜け)骨折(blow-out fracture)
6-2 顎顔面外傷
6-2-1 初期対応
6-2-2 診断
6-2-3 治療
7 小児頭部外傷
7-1 病院前救護
7-2 専門施設への搬送基準
7-3 来院後の初期治療
7-4 ICUでの管理
7-4-1 頭蓋内圧(ICP)の測定の適応と方法
7-4-2 頭蓋内圧(ICP)の治療閾値
7-4-3 脳灌流圧(CPP)の治療閾値
7-4-4 鎮静剤,鎮痛剤,筋弛緩剤の治療的使用に関して
7-4-5 脳室ドレナージによる頭蓋内圧(ICP)管理
7-4-6 高張剤による治療
7-4-7 過換気療法
7-4-8 バルビツレート療法
7-4-9 体温管理療法
7-4-10 減圧開頭法
7-4-11 ステロイドの使用について
7-4-12 栄養管理
7-4-13 抗てんかん薬
7-4-14 頭位挙上
7-5 虐待による頭部外傷(abusive head trauma : AHT)
8 高齢者頭部外傷
8-1 病院前救護
8-2 初期診療
8-3 管理
8-4 手術適応と手術方法
8-4-1 Talk and deteriorate
8-4-2 急性硬膜下血腫
8-4-3 減圧開頭術
8-5 抗凝固薬・抗血小板薬の影響
9 軽症・中等症頭部外傷への対処
9-1 基本的な治療指針
9-1-1 軽症・中等症頭部外傷の診断
9-1-2 脳振盪後症候群
9-1-3 画像診断
9-1-4 治療指針
9-1-5 職場(または学校)復帰の推奨基準
9-2 重症化の危険因子
10 スポーツ頭部外傷
10-1 脳振盪に有効な診断方法
10-2 脳振盪後の診療
10-3 脳振盪の予防
10-4 慢性外傷性脳症(chronic traumatic encephalopathy : CTE)
11 外傷に伴う高次脳機能障害
11-1 外傷後高次脳機能障害の発症
11-2 急性期画像診断
11-3 高次脳機能障害の評価
11-4 慢性期画像診断
11-5 軽症脳外傷後高次脳機能障害における画像診断
11-6 認知リハビリテーション
11-7 薬物療法
11-8 包括的プログラム
11-9 自動車運転再開
12 外傷に伴う低髄液圧症候群
13 補遺
13-1 頭部外傷に伴う凝固線溶系障害
13-2 早期リハビリテーション
13-3 外傷急性期の精神障害
13-4 多発外傷
索引
正誤表
開く
本書の記述の正確性につきましては最善の努力を払っておりますが、この度弊社の責任におきまして、下記のような誤りがございました。お詫び申し上げますとともに訂正させていただきます。