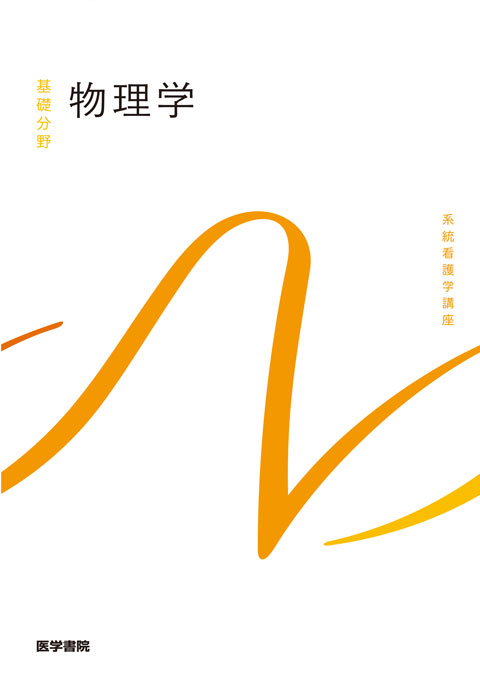物理学 第7版
もっと見る
- 本書では、「物理学をはじめて学ぶ学生」が「物理学とはなにか」をイメージできるようになることを最大の目的として構成しています。
- 公式や数式ばかりの中身ではなく、日常生活において経験するさまざまな現象を通じて、物理学の基礎的な知識を身につけていくことを目ざしています。
- 単位とはなにか、グラフはどのように読めばいいか、有効数字とはなにか、といったように、物理学に限らず、科学的な知識や思考の基本となる知識についてもわかりやすく解説しています。
- 重要な公式や概念を学ぶ際には、①例題をもとに計算してみる・考えてみる、②学習した内容を確認するために練習問題をとく、③章末の問題で再度の確認をする、といったように、複数段階で理解を深める構成としています。
- 巻末資料では、物理学を学ぶために必要となる計算方法について、基礎の基礎から解説します。
- 「系統看護学講座/系看」は株式会社医学書院の登録商標です。
| シリーズ | 系統看護学講座-基礎分野 |
|---|---|
| 執筆 | 豊岡 了 / 内山 豊美 / 大鷲 雄飛 |
| 発行 | 2015年02月判型:B5頁:168 |
| ISBN | 978-4-260-01995-8 |
| 定価 | 2,420円 (本体2,200円+税) |
更新情報
-
更新情報はありません。
お気に入り商品に追加すると、この商品の更新情報や関連情報などをマイページでお知らせいたします。
- 序文
- 目次
序文
開く
はしがき
最近では,病院に入ると受付から診察室,検査室とどこにでもコンピューターの端末が置かれているのが目につく。診察や看護においても,デジタル体温計,デジタル血圧計,パルスオキシメーターなどが用いられ,取得したデータは無線回線を通してコンピューターに送られて管理されている。これらはいずれも物理学を応用した装置である。「マニュアルどおりの使い方さえ覚えておけばいい」「看護の仕事は生身の人間が相手であり,物理学が対象とするような無機質なものとは違う」と思う人もいるかもしれないが,さまざまな機器を用いて患者さんから得た情報の多くは,人間の身体に関する物理量とその変化であり,それらは基本的に物理法則に従うものである。
皆さんが学校教育のどこかで学習したであろう物理学というと,聞き慣れない用語と数式が出てきたり,あたり前のことをむずかしい理屈をこねまわしたりしているように感じられるもので「あまり役にたちそうもないからとりあえず単位だけは」となんとなくすませてきた方もいるかもしれない。しかし,実は私たちが日常なにげなく経験し,あたり前のこととして見過ごしてきた自然のひとコマひとコマに物理法則が潜んでいるのである。いまから300年以上も前に古典力学を大成した天才物理学者ニュートンは,リンゴが落ちるのを見て,万有引力の法則を思いついたという。日常で目にする1つの風景と宇宙のしくみが同じ物理法則に従っている,というのは当時の人びとにとって驚きであったに違いない。私たちの身体でおこることや身のまわりで見たり経験したりすることは,限りなくたくさんある。しかし,さまざまな事象は無関係におきているのではない。それほど多くはない基本的な法則があって,互いに関係づけられているのである。
本書では,複雑で多様な物理の世界について,個別の知識として覚えることよりも,日常的な経験則から出発して「納得」できる形で考え方を組みたてていくことに学習の重点をおいた。物理学では,日常のスケールから原子分子の極微のスケールまでの幅広い世界を,できるだけ統一的に理解しようとする。序章では,物理というドラマに登場する役者を紹介し,大きな量から小さな量までを統一的に扱うための物理量の単位や数値の記述および計算法について学習する。つづいて,第1章から第5章までは,基本的な運動と力の法則から入り,熱と温度,音と光,電気と磁気,放射線と進めていく。目で見て触ることができる世界から,顕微鏡でも見えないような極微の世界,音や光のような非物質の世界まで,さまざまな世界を見てまわることになる。
本書では,物理法則の数式による記述を必要最小限にとどめるよう努力し,数式を扱う場合には可能な限りかみくだいて解説するよう心がけた。これにあわせて,その範囲内で身近な題材を取り上げて数値的な計算ができるように,各章には例題やゼミナールを用意した。たんに抽象的な法則をながめるだけで通り過ぎるのではなく,手を動かすことによって物理の世界を数値的に「体験」できるように工夫している。
看護職を目ざす皆さんが,本書で学んだことを土台として,それぞれの場で自然のしくみのおもしろさに気がつき,新たな発見につながることがあれば望外の喜びである。
2014年12月
著者一同
最近では,病院に入ると受付から診察室,検査室とどこにでもコンピューターの端末が置かれているのが目につく。診察や看護においても,デジタル体温計,デジタル血圧計,パルスオキシメーターなどが用いられ,取得したデータは無線回線を通してコンピューターに送られて管理されている。これらはいずれも物理学を応用した装置である。「マニュアルどおりの使い方さえ覚えておけばいい」「看護の仕事は生身の人間が相手であり,物理学が対象とするような無機質なものとは違う」と思う人もいるかもしれないが,さまざまな機器を用いて患者さんから得た情報の多くは,人間の身体に関する物理量とその変化であり,それらは基本的に物理法則に従うものである。
皆さんが学校教育のどこかで学習したであろう物理学というと,聞き慣れない用語と数式が出てきたり,あたり前のことをむずかしい理屈をこねまわしたりしているように感じられるもので「あまり役にたちそうもないからとりあえず単位だけは」となんとなくすませてきた方もいるかもしれない。しかし,実は私たちが日常なにげなく経験し,あたり前のこととして見過ごしてきた自然のひとコマひとコマに物理法則が潜んでいるのである。いまから300年以上も前に古典力学を大成した天才物理学者ニュートンは,リンゴが落ちるのを見て,万有引力の法則を思いついたという。日常で目にする1つの風景と宇宙のしくみが同じ物理法則に従っている,というのは当時の人びとにとって驚きであったに違いない。私たちの身体でおこることや身のまわりで見たり経験したりすることは,限りなくたくさんある。しかし,さまざまな事象は無関係におきているのではない。それほど多くはない基本的な法則があって,互いに関係づけられているのである。
本書では,複雑で多様な物理の世界について,個別の知識として覚えることよりも,日常的な経験則から出発して「納得」できる形で考え方を組みたてていくことに学習の重点をおいた。物理学では,日常のスケールから原子分子の極微のスケールまでの幅広い世界を,できるだけ統一的に理解しようとする。序章では,物理というドラマに登場する役者を紹介し,大きな量から小さな量までを統一的に扱うための物理量の単位や数値の記述および計算法について学習する。つづいて,第1章から第5章までは,基本的な運動と力の法則から入り,熱と温度,音と光,電気と磁気,放射線と進めていく。目で見て触ることができる世界から,顕微鏡でも見えないような極微の世界,音や光のような非物質の世界まで,さまざまな世界を見てまわることになる。
本書では,物理法則の数式による記述を必要最小限にとどめるよう努力し,数式を扱う場合には可能な限りかみくだいて解説するよう心がけた。これにあわせて,その範囲内で身近な題材を取り上げて数値的な計算ができるように,各章には例題やゼミナールを用意した。たんに抽象的な法則をながめるだけで通り過ぎるのではなく,手を動かすことによって物理の世界を数値的に「体験」できるように工夫している。
看護職を目ざす皆さんが,本書で学んだことを土台として,それぞれの場で自然のしくみのおもしろさに気がつき,新たな発見につながることがあれば望外の喜びである。
2014年12月
著者一同
目次
開く
序章 「物理学」を学ぶための準備 (豊岡了)
A 「物」の「理」を探る
1 科学における物理学の位置づけ
2 なぜ物理学を学ぶのか
B 「科学」というドラマの役者たち-物質と光
C 量の単位と数値の扱い方
1 単位
2 数値の扱い方
第1章 運動と力 (内山豊美)
A 物体の運動
1 等速直線運動
2 等加速度運動
B 力と加速度
1 力と加速度運動
2 力・質量と加速度
3 運動量
4 等速円運動
5 次元
C 力のつり合い
1 力とベクトル
2 重力と抗力
D 力のモーメント
1 モーメントとは
2 重心
E 仕事とエネルギー
1 仕事と仕事率
2 エネルギー
F 圧力
1 力の作用する面積と圧力
2 気圧
3 水圧
4 浮力
5 圧力の測定
6 サイフォンの原理
第2章 熱 (豊岡了)
A 熱と温度
1 温度の測定と熱平衡
2 熱量
3 熱の伝わり方
B 固体・液体・気体
C 熱と仕事
1 仕事を熱にかえる
2 気体の法則
3 エネルギー保存の法則
4 熱機関の効率
5 自然は逆戻りしない
第3章 音と光 (豊岡了)
A 音と光の正体は「波」
1 波の基本は正弦波である
2 波の重ね合わせ
B 音
1 音の伝わり方と音速
2 共鳴
3 うなり
4 固有振動と音の発生
5 ドップラー効果
6 私たちが聞くことのできる音の範囲
7 超音波エコー
C 光
1 光の基本的な性質
2 光の反射と屈折
3 レンズのしくみ
4 光の干渉
5 光源
6 光と色
第4章 電気と磁気 (大鷲雄飛)
A 電気とはなにか
1 電荷のふるまい
2 電気の世界
3 電流と抵抗
B 磁気
1 電流と磁場
2 電磁誘導
第5章 放射線 (豊岡了)
A 原子の構造
B 原子核と放射線
1 放射線の発見
2 α線・β線・γ線
3 半減期
4 放射線の単位
C 放射線の人体への影響
D 医療における放射線の利用
巻末資料:基本的な計算を復習しておこう
ゼミナール解答
巻末資料解答
索引
A 「物」の「理」を探る
1 科学における物理学の位置づけ
2 なぜ物理学を学ぶのか
B 「科学」というドラマの役者たち-物質と光
C 量の単位と数値の扱い方
1 単位
2 数値の扱い方
第1章 運動と力 (内山豊美)
A 物体の運動
1 等速直線運動
2 等加速度運動
B 力と加速度
1 力と加速度運動
2 力・質量と加速度
3 運動量
4 等速円運動
5 次元
C 力のつり合い
1 力とベクトル
2 重力と抗力
D 力のモーメント
1 モーメントとは
2 重心
E 仕事とエネルギー
1 仕事と仕事率
2 エネルギー
F 圧力
1 力の作用する面積と圧力
2 気圧
3 水圧
4 浮力
5 圧力の測定
6 サイフォンの原理
第2章 熱 (豊岡了)
A 熱と温度
1 温度の測定と熱平衡
2 熱量
3 熱の伝わり方
B 固体・液体・気体
C 熱と仕事
1 仕事を熱にかえる
2 気体の法則
3 エネルギー保存の法則
4 熱機関の効率
5 自然は逆戻りしない
第3章 音と光 (豊岡了)
A 音と光の正体は「波」
1 波の基本は正弦波である
2 波の重ね合わせ
B 音
1 音の伝わり方と音速
2 共鳴
3 うなり
4 固有振動と音の発生
5 ドップラー効果
6 私たちが聞くことのできる音の範囲
7 超音波エコー
C 光
1 光の基本的な性質
2 光の反射と屈折
3 レンズのしくみ
4 光の干渉
5 光源
6 光と色
第4章 電気と磁気 (大鷲雄飛)
A 電気とはなにか
1 電荷のふるまい
2 電気の世界
3 電流と抵抗
B 磁気
1 電流と磁場
2 電磁誘導
第5章 放射線 (豊岡了)
A 原子の構造
B 原子核と放射線
1 放射線の発見
2 α線・β線・γ線
3 半減期
4 放射線の単位
C 放射線の人体への影響
D 医療における放射線の利用
巻末資料:基本的な計算を復習しておこう
ゼミナール解答
巻末資料解答
索引
更新情報
-
更新情報はありません。
お気に入り商品に追加すると、この商品の更新情報や関連情報などをマイページでお知らせいたします。