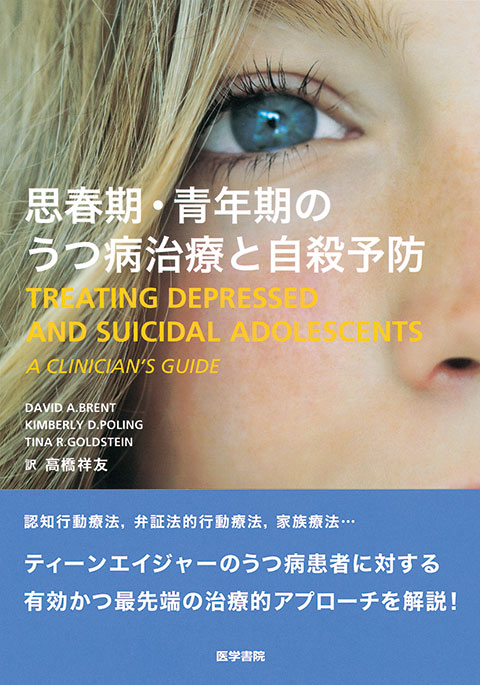思春期・青年期のうつ病治療と自殺予防
ティーンエイジャーのうつ病患者への有効かつ最先端の治療的アプローチを解説!
もっと見る
思春期・青年期のうつ病診療および自殺予防の具体的な対応のポイントについてまとめたもの。認知行動療法や弁証法的行動療法といった近年関心が高まっている治療法をベースに、希死念慮のある急性期患者へのアプローチから、患者とのラポールづくり、連鎖分析、家族への教育といった日常のうつ病診療で必要となる対応まで幅広くカバーした1冊。
| 著 | David A. Brent / Kimberly D. Poling / Tina R. Goldstein |
|---|---|
| 訳 | 高橋 祥友 |
| 発行 | 2012年05月判型:A5頁:336 |
| ISBN | 978-4-260-01556-1 |
| 定価 | 5,500円 (本体5,000円+税) |
- 販売終了
更新情報
-
更新情報はありません。
お気に入り商品に追加すると、この商品の更新情報や関連情報などをマイページでお知らせいたします。
- 序文
- 目次
- 書評
序文
開く
はじめに
うつ病で,自殺の危険の高い思春期患者についての本をどうして書こうとするのかと疑問に感じる読者もいることだろう.それに対するごく単純な答えとは,こういった患者はしばしば救急部や病院を受診し,臨床家にとって重要な挑戦となっているというものである.このような患者は臨床治験から除外されているため,実際にはこの種の患者が少なくないのに,臨床家の手引きになるような文献は多くない.したがって,10代のうつ病について多くのデータがあるものの,うつ病で自殺の危険の高い患者をどのように治療するかという点についてはかならずしも参考にならない.しかし,自殺願望や自殺行動はうつ病の患者にはきわめて普通に認められるので,気分障害の若年患者の治療では,うつ病と自殺の危険という相互に関連する状態を呈している患者を適切に評価し,治療することが,重要な要素となる.さらに,自殺願望や自殺行動は,うつ病の重症度や慢性経過と密接に関連しているのだが,けっして自殺の危険が高まらない多くのうつ病患者が存在することも明らかである.したがって,自殺の危険に関連するうつ病以外の要因が存在するはずであり,また,実際に存在するのであるから,それぞれに異なる介入が必要となるはずである.うつ病と自殺の危険という,2つの脆弱性に焦点を当てるのはきわめて独特であり,危険の高い思春期患者を適切に治療していくうえで必要であると著者らは考えている.この「はじめに」の部分で,うつ病で自殺の危険の高い若年患者をどのように著者らが治療していくべきかを考えるようになったか,いくつかの重要な点について解説していく.
1982年に私(David A. Brent)は,過去半世紀においてもっともカリスマ的で医学界の指導者の1人であったThomas Detre博士から,ピッツバーグ大学医学部のポストを与えられた.Detre博士は,精神医学も他の医学領域と同様に実際的な経験論に基づくべきであると主張をするエリートグループの1人であった.私は経験主義の重要性を理解させられたものの,同時に,「経験主義」に基づかない,非常に熟練した精神分析的なスーパーバイザーや同僚が達成した実に印象的な結果にも心を打たれた.彼らは目を見張るような価値ある何かをもたらしたのだが,しかし,それを確実に把握し,定義するのは難しかった.Detre博士が巧みに患者と面接を進めるとともに,優秀なスタッフを採用し,彼らの能力を育てていった例は数多い.私はこれは一体なんだろうと疑問を抱き始めた.個人的な特徴なのだろうか? それぞれが育てることのできる才能なのだろうか? 私は経験主義を徐々に受け入れ始めていたのだが,「何か他のものがあるとは思いませんか? 何か臨床の技のようなもの,そして今でもその価値が古くならないものがあるとは思いませんか?」と恐る恐るDetre博士に質問した.すると,彼は笑って,「答えはイエスだ.でも君はそれでもそれが何かを定義する必要がある」と答えてくださった.
本書は,20年以上も前にDetre博士が与えてくださった課題に対する答えである.すなわち,患者にとって最善の結果を得るために現在の知見と時代を超えて集積されてきた従来の知見を統合することである.最善の治療は経験的なデータに基づいていなければならない.しかし,良好な治療には臨床の技も必要とされる.患者と協力して臨床的判断を下すために,患者との間に協同的な関係を築き上げる技である.治療目標は,経験主義と協同的態度のうえに成り立つ.すなわち,現在の精神医学の創造的巨人であり,認知療法の創始者であるAaron Beck博士が言うところの協同的経験主義(collaborative empiricism)である.協同的経験主義をうつ病で自殺の危険の高い思春期患者に応用しようとするのが本書の主な焦点である.新たな知見が最善の治療の概念を変えるかもしれないが,本書で解説されるアプローチが時代を超えて支持されることを望んでいる.
Detre博士はウエスタン精神科研究所・クリニック(Western Psychiatric Institute and Clinic:WPIC)に1973年に赴任して以来,活発に質疑応答し,研究するという雰囲気を築き上げてきた.Detre博士はすぐれた才能を発掘する能力に常に長けていて,後に1983年から2009年まで精神医学部の主任教授となるDavid Kupfer博士を招聘したほどである.Kupfer博士の招聘は,おそらくWPICの成功にもっとも寄与したと思われる.Kupfer博士は他の誰よりも気分障害の治療の発展に貢献し,現在多くの者が競い合っている臨床研究を実施する土台を造った.故Joaquim Puig-Antich博士は新世代の経験主義的志向の児童精神科医であり,少し若い私たちに危険を冒し,それを楽しむように励ましてくださった.Maria Kovacs博士は今も小児期の気分障害に関して画期的な研究を実施し,私の指導者として,私が明確に自己の思考を表明できるように教えてくださる忍耐力を持っている.そして,私の意見では,もっとも創造的な米国の精神科医はAaron Beck博士であり,うつ病と自殺の危険という複雑な現象を理解し,治療するうえで画期的な業績を上げてこられた.
これらの偉大な科学の指導者たちには,失敗を恐れないという共通した性質がある.実際に,彼らは多くの失敗をしてきた.しかし,なぜ治療が成功しなかったか,あるいは理論が適合しなかったかを,彼らは進んで探ろうとした.彼らの言葉をここに引用すると,「私は教師から以上に,自分の教え子たちから多くを学んだ」というものがある.私自身の経験からも,私は患者からもっとも多くのことを学んだと認識した.とくに治療がうまくいかなかったものの,その失敗を将来の成功に結びつけることができた場合に,それが当てはまる.
本書を書こうと思いたった個人的な話がまだある.1979年に私の弟ジェームズが26歳で不整脈のため急死した.その4か月前に会話を交わしたのが最後になった.彼は音楽家であり,作曲家でもあったのだが,私は最近どんな曲を聴いているのかと尋ねた.弟は「自分自身」と答えた.私はひどく自己中心的に思ったので,率直にそう言った.すると,「兄さんにはわからないだろうな」と弟は言った.「僕の聴きたい音楽はまだできていない.僕がそれを作曲する」.そして,私はそれに応えて「僕の読みたい児童精神医学はまだ書かれていない.おそらく僕もそれを書く」と話した.
本書の構想をまとめてくれた目に見えない著者たちに感謝しなければならない.そして,両親,ロバート,リリアン,ブレント,その他にも私のためにさまざまなことをしてくれたすべての人にも私は感謝したい.彼らは精神生活が人類への貢献に資することを理想としている.両親は私に遺伝子を与えてくれて,妻のナンシーは私が成功するための環境を整えてくれた.魂の伴侶を見つけられたことで,私にはすべてが可能になったのだ.
思春期のうつ病と自殺について私が研究を始めたのは1980年頃のことであった.私はピッツバーグ小児病院コンサルテーション・リエゾン部門に所属し,毎週およそ3例の思春期の自殺未遂者の病状を評価していた.私の仕事は,どの患者を自宅に戻してよいか,自殺未遂が反復される恐れが高いためにどの患者を入院させなければならないかを判断することだった.ある日,私はそういった2人の患者について判断を迫られた.1人は帰宅させ,もう1人は入院させるように助言した.私が入院と判断した子どもの父親は私の意見に反対し,判断の根拠を知りたがった.しかし,私はうまく説明できなかった.研修がそろそろ終わる頃だったのに,私はどの患者に自殺の危険が高いと判断できるのかよくわかっていなかった.私は図書館に行き,思春期の自殺について文献を読み漁ったが,この課題についてほとんど何も書かれていないことに気づいて愕然とした.私は私の聴きたい音楽が何かわかったものの,それはまだ作曲されていないことを知ったのだ.
当時,思春期患者に対する私たちのアプローチは無知と恐怖に満ちていた.思春期の自殺率は急激に上昇していて,それまでの20年間で3倍になった.自殺未遂に及んだり,自殺したりするティーンエイジャーは単に過度のストレスに曝されていたり,親から理解されていなかったのだと一般に考えられていた.もう1つの誤解として,ティーンエイジャーの自殺は精神疾患とは関連していないというものがあった.自殺や自殺行動の危険因子についてほとんど何も知識がなかった.ただし,自殺の伝染については非常に多くの関心があった.すなわち,ある高校で自殺が1件起きたとすると,それが疫病のように広がっていくのではないかという点について関心が高かった.そして,思春期のうつ病や自殺行動に対して経験的に実証された治療法は存在しなかったために,たとえ自殺の危険が高い子どもを発見できたとしても,どのように治療したらよいかまるでわからなかったのだ.
自殺の危険を判断するためには,自殺した思春期の人についてより多くを知り,他の群と比較する必要があった.自殺研究の中心的な問題とは,自殺した人はすでに亡くなってしまっているので,このきわめて重要な情報をその人自身からは明らかにできないという点である.それでも,いくつかの成人の自殺者を対象とした研究で用いられる心理学的剖検(psychological study)という方法があり,これは遺族や他の知人に面接し,自殺に至る要因を再構築しようとするものである.私はいくつかの研究費を得て,思春期の自殺者の遺族と接触を開始し,恐る恐る彼らに面接し,何がうまくいかなくて自殺が生じたのかについてさらに学ぼうとした.
その結果,自殺者の戸口にたどり着くどころか,むしろかえってそこから遠ざかってしまったというのが私の直面した問題だった.遺族は一体何が起きたのか意味を探る必要があり,誰も自殺について話題にしないためにひどく孤立感を覚えていたので,自殺に至った過程を探る機会を得たことをむしろ歓迎した.遺族は,自殺という悲劇が起きた直後から自分の心の中で何とか自殺の意味を探ろうとしてきたことは明らかであった.
思春期の自殺者は単に誤解されていた子どもというのではないことを私たちは知った.親,兄弟姉妹,友人の報告によると,自殺者の90%以上は少なくとも1つの主要な精神障害に罹患していた.平均すると,自殺が生じる7年前には精神障害が生じていた.うつ病がもっとも高率に認められた精神医学的問題であったが,物質乱用などの他の問題もしばしば合併していた.うつ病は「ごく当たりまえのもの」とみなされることが多く,親はしばしば「思春期にはよくある気分の浮き沈みだと私は思っていました」と述べた.自殺者は,自殺願望を誰かに,一般的には友人に打ち明けていて,友人はそれを秘密にすることを約束していた.さらに,思春期の自殺者は,自殺を図ったものの命を落とすことがなかった者に比べて,準備的行動に及ぶことが多かった.また,自殺者は衝動的攻撃性の問題をしばしば呈していた.すなわち,挑発や欲求不満に刺激されて,敵意や攻撃を伴う衝動的な反応に及ぶ傾向を認めた.1/3は死の直前1週間以内に殺人の計画や威嚇も認めた.第一の自殺手段は銃であった.ティーンエイジャーの自殺が増加したほとんどは,火器によるものであり,自殺者の家庭には,対照群と比較して銃が有意に多かった.自殺者の家族には,うつ病,物質乱用,自殺行動の率がきわめて高かった.
自殺者の遺族に面接するのはひどく気分の沈むことだと思われるかもしれない.たしかに遺族の心の痛みが手に取るようにわかる.しかし,思春期の自殺について何かをすることができると私は学んだ.私たちは経験的な危険評価を改善できるだろう.うつ病に気づいて,機能障害を伴う気分の問題を単なる思春期の気分の浮き沈みではないことを人々に教育できるだろう.このようなティーンエイジャーの多くが自殺に及ぶ前に自殺願望を周囲の人々に訴えているという事実は,より早期にそれに気づいて,介入することの重要性に光を当てるだろう.よく理解できることではあるが,彼らの友人はどのように対応したらよいか知らなかった.しかし,友人の自殺の危険をけっして秘密にしてはならないとティーンエイジャーに教育すべきだろう.さらに,ティーンエイジャーが自殺について話しても,「単に関心を引こうとしているだけだ」といって無視しようとする専門家の態度も問題である.専門家はしばしば医学的に「非致死的」な自殺未遂を,自殺の意図がきわめて高いと考えるのではなく,単なる「素振り」に過ぎないと判断する.しかし,実際には,そのような自殺願望や自殺行動は,最後には自殺に至る最初の一歩かもしれない.さらに,家族的に自殺行動が多発することを考えると,自殺の危険の高い親を治療している同僚と協力することによって,ハイリスクの子どもを発見するのにも役立つ.最後に,火器による自殺率が高いことを考えると,自殺の危険の高い青少年が住んでいる自宅から銃を取り除くように家族に要請することも重要である.
このように研究を進めていった結果,自殺の危険を評価する基準を得ることができた.これはさらに他の3種の重要な領域を明らかにした.(1)ティーンエイジャーの社会的なつながりの中における自殺の衝撃を理解する,(2)自殺がどのように家族に多発するかを理解する,(3)自殺の危険を和らげるために,自殺の危険の高い若者に対する治療法を開発する.
当時,社会が自殺の伝染をヒステリーのように取り上げていたのを伝えるのは容易ではない.Kim Puig-Antich博士がこれは研究に価しない領域であると考えていたことを私は思い出す.ただし,それはここピッツバーグでまさに私たち自身が自殺の疫病を経験するまでのことだった.地元の高校で18日間で3名の自殺者と7名の自殺未遂者が出たのだ.まず,自殺行動を模倣するのは,自殺者ともっとも強い絆のあった人だと私たちは考えた.いわばティーンエイジャーの自殺の社会的つながり(親友や家族)である.私たちは研究を実施し,自殺者の親,兄弟姉妹,友人,そして友人の友人を面接した.友人や兄弟姉妹は一般人口に比べて精神医学的問題を抱えている率が高いという点を調整したとしても,思春期の自殺と密接な接触があった人の約半数は対照群(接触のなかったティーンエイジャー)と比べて自殺未遂に及ぶ危険が高かった.自殺者の友人は,過去に自殺を考えたことがあったとしても,この苦痛に満ちた余波を経験した後に,自分はけっして自殺しないと答えた.この結果をもとに,私たちは既遂自殺の話題をマスメディアはどのように報道すべきかという点について提言をまとめた.すなわち,(1)模倣を阻止する,(2)自殺者を美化してしまうと,結果的に模倣の可能性に焦点を当ててしまうので,それを控えて,自殺は本来治療可能な精神疾患の結果として生じることに焦点を当てて報道する,というものであった.
しかし,自殺は周囲の人々に長期的な影響を及ぼした.自殺が生じた後,およそ1/3の友人や兄弟姉妹が臨床的にうつ病を発病した.もっとも脆弱であったのは,自殺が起きる前の24時間に,自殺の計画を知ったり,自殺者と話をしたものの,自殺を防ぐことができなかったとして自責感を覚えていた人である.これは,友人の自殺の計画を秘密にしておいてはならないということをティーンエイジャーに教育することの重要性を物語っている.要するに,自殺者の友人や家族は自殺が起きた後,長期にわたって非常に深刻な影響を受け,中には6年経っても重度の悲嘆を呈している人さえいたのである.
1986年,私たちの研究グループが心理学的剖検の研究を実施していた頃だが,小児精神科の主任で,私たちのスーパーバイザーであったKim Puig-Antich博士は,ティーンエイジャーの自殺予防プログラムが必要であると決断した.当初,私はそういったクリニックを開くことをためらっていた.私はKimと次のような会話を交わした.
(1)アウトリーチ:これは主として,教育と予防からなる
(2)臨床:自殺の危険の高い若者への介入に焦点を当てる
アウトリーチでは,自殺の危険をいかに認識し,対応するか,そして生徒の自殺が不幸にして起きた場合にはその余波にどう対応するかという点について,Kerr博士はプログラムを作っていった.私の役割は,研究を実施し,自殺の危険の高いティーンエイジャーのためのクリニックを運営することだった.研究から何か新しい知見を得ると,Kerr博士はそれをただちに数千人の教育関係者や精神保健の専門家の研修や教育に組み入れていった.
クリニックでは,毎日1人は新たな自殺の危険の高い思春期患者を私たちは診察していた.このような患者に対して経験的に有効であると証明されている治療法がなかったため,私たちは心理学的剖検から得られた知見に頼った.すなわち,このようなティーンエイジャーは,抑うつ的で,絶望し,衝動的であり,問題解決能力が低いという点である.当時は,三環系抗うつ薬が唯一の薬物だったが,小児には効果があるとは証明されておらず,過量服用すると命を失う恐れさえあった.したがって,私たちは思春期患者を心理療法で治療しようと考えた.成人患者の治療に関する文献にあたり,Beckの認知療法(cognitive therapy)が成人のうつ病患者に有効であることを知った.そこで,私は認知療法について学び,この治療法を思春期患者に応用しようと考えた.Beckの理論的枠組みを応用し,抑うつ的になると,自己の否定的な気分をさらに強化してしまうような世界観がどのように作り上げられているか,思春期患者が理解できるように私たちは働きかけていった.すなわち,肯定的な側面を無視し,否定的な側面を過度に取り上げ,(とくに自殺の危険の高いティーンエイジャーでは)白か黒かの思考法に囚われ,最終的には生か死かといった究極的な二分割思考に陥ってしまう点について,患者が理解できるように助力していった.
当時,ある地元の精神保健センターで夜働いていた時に,私はKimberly Polingに出会った.彼女は聡明で,活発な若いソーシャルワーカーで,思春期患者との絆を作り上げる天賦の才があった.渋々治療を受けているティーンエイジャーとの間に関係を築き上げる彼女の能力に私はとくに感銘した.他の人々が欲求不満に陥り,投げ出してしまうような事例であっても,Kimは楽天的で,先を見越して行動を起こし,患者との間にラポールを築き,協力して問題を解決していく姿勢は,印象的な結果をもたらした.彼女の行動によって,私は多くを学びたいと考えた.ある日,私が彼女にWPICでの私の仕事について話すと,彼女は日曜日の午後はほとんどの時間をWPICの図書館で過ごして情報を集めていると教えてくれた.彼女もまだ作曲されていない音楽を捜し求めているように思われた.そこで私は彼女にティーンエイジャーのための自殺予防プログラムに協力してくれるように依頼した.それは当時すでに,危機にあるティーンエイジャーのためのサービス(Service for Teens at Risk:STAR)として知られていた.
Kimは他の3人のセラピストと私のスタッフに加わり,経験的に実証された評価手順やBeckの認知療法モデルに基づいた治療の手引きを協力して開発していった.治療は奏効していると感じていたが,1つ大きな問題があった.ドロップアウト率が40%にも上っていたのだ.私たちは治療から脱落した患者の家族に連絡して,治療のどの部分が気に入って,どの部分が気に入らなかったのか明らかにしようとした.その結果,親は子どもに腹を立てていて,子どもの自殺行動によって振り回されていると感じていることが明らかになった.子どもが病気であり,それを自分の力でコントロールできないことを,私たちは親に理解させられていないことに気づいた.そこで,Kimと私は,親に対してティーンエイジャーの気分障害について最新の知見を解説する冊子を作った.その冊子「ティーンエイジャーのうつ病:家族のためのサバイバルマニュアル」では,うつ病の症状,原因,治療法についての心理教育,そして,もっとも重要な点として,うつ病がどのようにして家族全体に影響するのかを解説した.家族がどのようにしてうつ病のティーンエイジャーを助力できるかという点について具体的なアドバイスを挙げた.プログラムが親に子どものうつ病について教育するうえで効果があったばかりでなく,多くの親が自分自身のうつ病にも気づいて,治療を求めてくるようになった.この介入法によって,ドロップアウト率は劇的に減少した.
私たちは,この新たな認知行動療法(cognitive-behavioral therapy:CBT)と,家族療法と支持的療法という効果的であるとされて広く実施されている2つの治療法を比較することにした.その結果,うつ病の症状を和らげるうえで,CBTは他の2つの治療法よりもすぐれていることが明らかになった.この知見から,CBTは思春期のうつ病に効果的な治療法であると認識されるようになった.さらに,(現在の,あるいは過去の)自殺の危険を認める患者においても,CBTは支持的療法よりも,うつ病を改善することが明らかになった.しかし,自殺願望や自殺行動そのものの減少という点では,CBTと他の2つの治療法の間に有意差はなかった.これは重要な問題点を明らかにした.すなわち,うつ病の治療効果と自殺行動に対する治療効果の間には乖離があるという点である.治療によって思春期のうつ病は改善したものの,衝動的な自殺未遂によって救急部に突然受診してくるということも起こり得る.一体何が起きたのかと患者に質問すると,強烈な感情に圧倒されたのだと答えるだろう.私たちはこの状態を感情統御不全(emotion dysregulation)と名づけるようになった.これは私たちが見逃していた,非常に重要な治療標的であると思われた.そこで,1996年にMarsha Linehan博士をWPICに招き,弁証法的行動療法(dialectical behavior therapy:DBT)について集中的な研修を受けた.私たちはLinehan博士から感情統御と苦悩耐性スキルについて学び,私たちの治療的アプローチを補完した.STARクリニックにおいて,CBT,DBT,家族療法を統合して実施したところ,この統合的治療こそがまさに私たちが求めていたものであると認識した.
その後の数年間,STARクリニックの臨床家たちはこの治療モデルを実践し,好結果を得た.私たちがうつ病で自殺の危険の高い思春期患者の治療に成功していることに他の臨床家たちも気づき始め,私たちに研修やワークショップを依頼してくるようになった.他の臨床家たちも,CBTだけでは十分ではないという私たちの以前の懸念に賛同するようになった.そこで,私たちのアプローチには何か独特なものがあり,他の臨床家もそれから何か有益なものを得られるかもしれないと考え,本書をまとめようと考え始めたのだ.
そして,Tina Goldsteinも私たちに参加した.彼女はコロラド大学博士課程の大学院生であったが,小児期の双極性障害について研究していて,小児期の気分障害の評価や治療の重要な領域として,感情統御不全について関心を抱いた.彼女はWPICで6か月間にわたりティーンエイジャーのための自殺予防プログラムで博士前インターンシップを受けた.私たちと同じ関心を抱いた臨床家であり研究者を見つけたことはすぐに明らかになった.思春期患者と自然なラポールを築くことができるだけでなく,彼女にはKimが協同的経験主義の軽快な防御と攻撃と呼んだ稀な能力が備わっていた.これはすなわち,治療場面において,臨床の技と経験的な研究のデータを臨機応変に統合する能力を指している.Tinaは2003年に,博士課程修了後の研究員として私たちの研究に加わり,Kimから臨床的なスーパービジョンを受けることになった.
その後,私は自殺行動についてのこれまでの研究成果やうつ病を超えた危険についてもさらに理解しようとしてきた.というのも,うつ病の治療だけでは,かならずしも自殺の危険を除去できなかったからである.ある状況の危険因子を理解する1つの方法として,集団としての家族について検証することができる.1985年に私は深刻な自殺未遂に及んだ少年を診察した.家族歴を聴取すると,その少年の家族には自殺が多発していた.数か月後,弟も深刻な自殺未遂後に私たちのクリニックに紹介されてきた.うつ病といった精神障害に関与する遺伝的危険だけでなく,自殺に関与する遺伝的素因さえ存在するのではないかと私は疑問に感じた.
この疑問に答えるために,思春期の自殺者の家族と対照群の家族における,自殺,自殺行動,精神障害の率について調査した.たとえ,精神障害の差を調整した後であっても,既遂自殺者の身内には自殺行動の率がはるかに高かった.換言すると,精神障害以外の何かがそのような家族内には伝わっていた.家族内の自殺の危険の伝播には,重要な性質として衝動的攻撃性(impulsive aggression)という概念が明らかになった.既遂自殺者の身内に認められた自殺行動の率は,非常に攻撃的な手段で自殺した人の身内で高かった.
自殺が起きるという危険の一連の結果を後から振り返って1つひとつ解きほぐしていくのは難しい.自殺行動が実際に家族的に多発するというのであれば,成人の自殺未遂者の場合,その子どもの自殺の危険も増していることを明らかにできるかもしれない.ニューヨーク州立精神科病院のJohn Mann博士らとの共同研究で,うつ病で自殺未遂歴のある成人患者の子どもと,気分障害ではあるが自殺未遂歴のない成人患者の子どもについて,子どもの自殺未遂の危険を比較した.両群間で気分障害などの率は同等であったが,自殺未遂者の子どもでは,自殺未遂の率が6倍高かった.両群の子どもを識別する主要な要因の1つが,攻撃性の高さであった.さらに,自殺行動の家族歴がある成人の自殺未遂者が,もっとも攻撃的で,その子どもは自殺未遂の率がより高く,より低年齢で未遂に及んでいた.これが強く示唆していたのは,衝動的攻撃性の傾向が自殺行動の家族パターンを説明するうえで重要であるという点である.この傾向は自殺の危険にきわめて密接に関連していると考えられるために,これに焦点を当てた介入を開発する必要があった.
これは私たちが今日も直面している課題へとつながっていった.ティーンエイジャーのうつ病に有効な治療法が今ではあるのだが,その有効性は60%程度である.そこで,第一選択薬のセロトニン再取り込み阻害薬が効果を現さなかった場合に,他の治療を試みるという研究を実施し,うつ病に反応するもっとも有効な治療法はCBTと薬物療法を併用することであることを明らかにした.さらに,望ましい反応を予測するために,私たちは遺伝的要因と薬理動態学的要因も同定した.これによって,将来は,ある患者にとって適切な治療法を選択することができるようになるかもしれない.
私たちが抱えているもう1つの難しい課題として,自殺未遂歴のある思春期患者が再企図に及ぶのを予防する有効な治療法がまだ開発されていないという点がある.STARで私たちが長年かけて開発してきた治療法は,多施設で実施されている思春期自殺未遂者に対する治療(Treatment of Adolescent Suicide Attempters:TASA)の基礎となっている.これは地理的かつ人種的にさまざまに異なる患者に対してこの治療法を有効に実施するのに役立っている.しかし,思春期の自殺未遂者に対する他の治療法と同様に,確実に有効であるとはまだ明らかにされていない.心理療法の他の先駆的な研究者たち(たとえば,Greg Brown, John Curry, Betsy Kennard, Barbara Stanley, Karen Wellsら)と協力してTASA計画に携わっていくことで,うつ病で自殺の危険の高い思春期患者の治療にとって有効な要素であると私たちが考える点を検証し,さらに明確なものにしていくことができるだろう.
私たちの試みを始めた当初は,思春期の自殺率が上昇しつつあったものの,自殺の危険因子について知識はなく,自殺の伝染についての深刻な懸念があり,思春期のうつ病に対する治療法もなかった.しかし,今では思春期の自殺率は下がってきたし,自殺の危険を評価する経験的な枠組みも手にし,思春期のうつ病に有効であると経験的に実証されたいくつかの治療法もある.現時点では,自殺行動に関連する遺伝的な危険因子を同定し,反復性の自殺行動や治療抵抗性のうつ病の発病を予防する介入も開発され,うつ病が発病しても自殺行動の発生を予防しようとするいくつかの研究も進行中である.しかし,これらの質問に対する答えを見出すことができていない現在においても,自ら命を絶ちたいと考えているうつ病の思春期患者を助力するために,私たちは自分たちが知っている最善の方法を適用することができるし,また,そうしなければならない.患者が人生の意義を理解し,人生からもっとも多くのものを得られるように助力するために,本書では最新の知見について解説したいと考えている.
著者らは,臨床的な知恵と協同的経験主義を組み合わせて,統合的な概念を創りあげることを意図している.まず,うつ病と自殺の危険の評価について総説し,この状態に対してエビデンスに基づいて有効とされている治療法について解説する.次に,うつ病で自殺の危険の高い思春期患者に有効な治療法に必要とされる要素について取り上げ,治療的関係,安全計画,治療についての症例の概念化について解説していく.そして,協同的治療関係,特殊な治療技法,思春期患者が回復し,安定した状態を維持するのを助力することなどを含めて,私たちの治療的アプローチついて概説する.最後に,この分野の将来の方向性についても述べたい.
うつ病で,自殺の危険の高い思春期患者についての本をどうして書こうとするのかと疑問に感じる読者もいることだろう.それに対するごく単純な答えとは,こういった患者はしばしば救急部や病院を受診し,臨床家にとって重要な挑戦となっているというものである.このような患者は臨床治験から除外されているため,実際にはこの種の患者が少なくないのに,臨床家の手引きになるような文献は多くない.したがって,10代のうつ病について多くのデータがあるものの,うつ病で自殺の危険の高い患者をどのように治療するかという点についてはかならずしも参考にならない.しかし,自殺願望や自殺行動はうつ病の患者にはきわめて普通に認められるので,気分障害の若年患者の治療では,うつ病と自殺の危険という相互に関連する状態を呈している患者を適切に評価し,治療することが,重要な要素となる.さらに,自殺願望や自殺行動は,うつ病の重症度や慢性経過と密接に関連しているのだが,けっして自殺の危険が高まらない多くのうつ病患者が存在することも明らかである.したがって,自殺の危険に関連するうつ病以外の要因が存在するはずであり,また,実際に存在するのであるから,それぞれに異なる介入が必要となるはずである.うつ病と自殺の危険という,2つの脆弱性に焦点を当てるのはきわめて独特であり,危険の高い思春期患者を適切に治療していくうえで必要であると著者らは考えている.この「はじめに」の部分で,うつ病で自殺の危険の高い若年患者をどのように著者らが治療していくべきかを考えるようになったか,いくつかの重要な点について解説していく.
1982年に私(David A. Brent)は,過去半世紀においてもっともカリスマ的で医学界の指導者の1人であったThomas Detre博士から,ピッツバーグ大学医学部のポストを与えられた.Detre博士は,精神医学も他の医学領域と同様に実際的な経験論に基づくべきであると主張をするエリートグループの1人であった.私は経験主義の重要性を理解させられたものの,同時に,「経験主義」に基づかない,非常に熟練した精神分析的なスーパーバイザーや同僚が達成した実に印象的な結果にも心を打たれた.彼らは目を見張るような価値ある何かをもたらしたのだが,しかし,それを確実に把握し,定義するのは難しかった.Detre博士が巧みに患者と面接を進めるとともに,優秀なスタッフを採用し,彼らの能力を育てていった例は数多い.私はこれは一体なんだろうと疑問を抱き始めた.個人的な特徴なのだろうか? それぞれが育てることのできる才能なのだろうか? 私は経験主義を徐々に受け入れ始めていたのだが,「何か他のものがあるとは思いませんか? 何か臨床の技のようなもの,そして今でもその価値が古くならないものがあるとは思いませんか?」と恐る恐るDetre博士に質問した.すると,彼は笑って,「答えはイエスだ.でも君はそれでもそれが何かを定義する必要がある」と答えてくださった.
本書は,20年以上も前にDetre博士が与えてくださった課題に対する答えである.すなわち,患者にとって最善の結果を得るために現在の知見と時代を超えて集積されてきた従来の知見を統合することである.最善の治療は経験的なデータに基づいていなければならない.しかし,良好な治療には臨床の技も必要とされる.患者と協力して臨床的判断を下すために,患者との間に協同的な関係を築き上げる技である.治療目標は,経験主義と協同的態度のうえに成り立つ.すなわち,現在の精神医学の創造的巨人であり,認知療法の創始者であるAaron Beck博士が言うところの協同的経験主義(collaborative empiricism)である.協同的経験主義をうつ病で自殺の危険の高い思春期患者に応用しようとするのが本書の主な焦点である.新たな知見が最善の治療の概念を変えるかもしれないが,本書で解説されるアプローチが時代を超えて支持されることを望んでいる.
Detre博士はウエスタン精神科研究所・クリニック(Western Psychiatric Institute and Clinic:WPIC)に1973年に赴任して以来,活発に質疑応答し,研究するという雰囲気を築き上げてきた.Detre博士はすぐれた才能を発掘する能力に常に長けていて,後に1983年から2009年まで精神医学部の主任教授となるDavid Kupfer博士を招聘したほどである.Kupfer博士の招聘は,おそらくWPICの成功にもっとも寄与したと思われる.Kupfer博士は他の誰よりも気分障害の治療の発展に貢献し,現在多くの者が競い合っている臨床研究を実施する土台を造った.故Joaquim Puig-Antich博士は新世代の経験主義的志向の児童精神科医であり,少し若い私たちに危険を冒し,それを楽しむように励ましてくださった.Maria Kovacs博士は今も小児期の気分障害に関して画期的な研究を実施し,私の指導者として,私が明確に自己の思考を表明できるように教えてくださる忍耐力を持っている.そして,私の意見では,もっとも創造的な米国の精神科医はAaron Beck博士であり,うつ病と自殺の危険という複雑な現象を理解し,治療するうえで画期的な業績を上げてこられた.
これらの偉大な科学の指導者たちには,失敗を恐れないという共通した性質がある.実際に,彼らは多くの失敗をしてきた.しかし,なぜ治療が成功しなかったか,あるいは理論が適合しなかったかを,彼らは進んで探ろうとした.彼らの言葉をここに引用すると,「私は教師から以上に,自分の教え子たちから多くを学んだ」というものがある.私自身の経験からも,私は患者からもっとも多くのことを学んだと認識した.とくに治療がうまくいかなかったものの,その失敗を将来の成功に結びつけることができた場合に,それが当てはまる.
本書を書こうと思いたった個人的な話がまだある.1979年に私の弟ジェームズが26歳で不整脈のため急死した.その4か月前に会話を交わしたのが最後になった.彼は音楽家であり,作曲家でもあったのだが,私は最近どんな曲を聴いているのかと尋ねた.弟は「自分自身」と答えた.私はひどく自己中心的に思ったので,率直にそう言った.すると,「兄さんにはわからないだろうな」と弟は言った.「僕の聴きたい音楽はまだできていない.僕がそれを作曲する」.そして,私はそれに応えて「僕の読みたい児童精神医学はまだ書かれていない.おそらく僕もそれを書く」と話した.
本書の構想をまとめてくれた目に見えない著者たちに感謝しなければならない.そして,両親,ロバート,リリアン,ブレント,その他にも私のためにさまざまなことをしてくれたすべての人にも私は感謝したい.彼らは精神生活が人類への貢献に資することを理想としている.両親は私に遺伝子を与えてくれて,妻のナンシーは私が成功するための環境を整えてくれた.魂の伴侶を見つけられたことで,私にはすべてが可能になったのだ.
思春期のうつ病と自殺について私が研究を始めたのは1980年頃のことであった.私はピッツバーグ小児病院コンサルテーション・リエゾン部門に所属し,毎週およそ3例の思春期の自殺未遂者の病状を評価していた.私の仕事は,どの患者を自宅に戻してよいか,自殺未遂が反復される恐れが高いためにどの患者を入院させなければならないかを判断することだった.ある日,私はそういった2人の患者について判断を迫られた.1人は帰宅させ,もう1人は入院させるように助言した.私が入院と判断した子どもの父親は私の意見に反対し,判断の根拠を知りたがった.しかし,私はうまく説明できなかった.研修がそろそろ終わる頃だったのに,私はどの患者に自殺の危険が高いと判断できるのかよくわかっていなかった.私は図書館に行き,思春期の自殺について文献を読み漁ったが,この課題についてほとんど何も書かれていないことに気づいて愕然とした.私は私の聴きたい音楽が何かわかったものの,それはまだ作曲されていないことを知ったのだ.
当時,思春期患者に対する私たちのアプローチは無知と恐怖に満ちていた.思春期の自殺率は急激に上昇していて,それまでの20年間で3倍になった.自殺未遂に及んだり,自殺したりするティーンエイジャーは単に過度のストレスに曝されていたり,親から理解されていなかったのだと一般に考えられていた.もう1つの誤解として,ティーンエイジャーの自殺は精神疾患とは関連していないというものがあった.自殺や自殺行動の危険因子についてほとんど何も知識がなかった.ただし,自殺の伝染については非常に多くの関心があった.すなわち,ある高校で自殺が1件起きたとすると,それが疫病のように広がっていくのではないかという点について関心が高かった.そして,思春期のうつ病や自殺行動に対して経験的に実証された治療法は存在しなかったために,たとえ自殺の危険が高い子どもを発見できたとしても,どのように治療したらよいかまるでわからなかったのだ.
自殺の危険を判断するためには,自殺した思春期の人についてより多くを知り,他の群と比較する必要があった.自殺研究の中心的な問題とは,自殺した人はすでに亡くなってしまっているので,このきわめて重要な情報をその人自身からは明らかにできないという点である.それでも,いくつかの成人の自殺者を対象とした研究で用いられる心理学的剖検(psychological study)という方法があり,これは遺族や他の知人に面接し,自殺に至る要因を再構築しようとするものである.私はいくつかの研究費を得て,思春期の自殺者の遺族と接触を開始し,恐る恐る彼らに面接し,何がうまくいかなくて自殺が生じたのかについてさらに学ぼうとした.
その結果,自殺者の戸口にたどり着くどころか,むしろかえってそこから遠ざかってしまったというのが私の直面した問題だった.遺族は一体何が起きたのか意味を探る必要があり,誰も自殺について話題にしないためにひどく孤立感を覚えていたので,自殺に至った過程を探る機会を得たことをむしろ歓迎した.遺族は,自殺という悲劇が起きた直後から自分の心の中で何とか自殺の意味を探ろうとしてきたことは明らかであった.
思春期の自殺者は単に誤解されていた子どもというのではないことを私たちは知った.親,兄弟姉妹,友人の報告によると,自殺者の90%以上は少なくとも1つの主要な精神障害に罹患していた.平均すると,自殺が生じる7年前には精神障害が生じていた.うつ病がもっとも高率に認められた精神医学的問題であったが,物質乱用などの他の問題もしばしば合併していた.うつ病は「ごく当たりまえのもの」とみなされることが多く,親はしばしば「思春期にはよくある気分の浮き沈みだと私は思っていました」と述べた.自殺者は,自殺願望を誰かに,一般的には友人に打ち明けていて,友人はそれを秘密にすることを約束していた.さらに,思春期の自殺者は,自殺を図ったものの命を落とすことがなかった者に比べて,準備的行動に及ぶことが多かった.また,自殺者は衝動的攻撃性の問題をしばしば呈していた.すなわち,挑発や欲求不満に刺激されて,敵意や攻撃を伴う衝動的な反応に及ぶ傾向を認めた.1/3は死の直前1週間以内に殺人の計画や威嚇も認めた.第一の自殺手段は銃であった.ティーンエイジャーの自殺が増加したほとんどは,火器によるものであり,自殺者の家庭には,対照群と比較して銃が有意に多かった.自殺者の家族には,うつ病,物質乱用,自殺行動の率がきわめて高かった.
自殺者の遺族に面接するのはひどく気分の沈むことだと思われるかもしれない.たしかに遺族の心の痛みが手に取るようにわかる.しかし,思春期の自殺について何かをすることができると私は学んだ.私たちは経験的な危険評価を改善できるだろう.うつ病に気づいて,機能障害を伴う気分の問題を単なる思春期の気分の浮き沈みではないことを人々に教育できるだろう.このようなティーンエイジャーの多くが自殺に及ぶ前に自殺願望を周囲の人々に訴えているという事実は,より早期にそれに気づいて,介入することの重要性に光を当てるだろう.よく理解できることではあるが,彼らの友人はどのように対応したらよいか知らなかった.しかし,友人の自殺の危険をけっして秘密にしてはならないとティーンエイジャーに教育すべきだろう.さらに,ティーンエイジャーが自殺について話しても,「単に関心を引こうとしているだけだ」といって無視しようとする専門家の態度も問題である.専門家はしばしば医学的に「非致死的」な自殺未遂を,自殺の意図がきわめて高いと考えるのではなく,単なる「素振り」に過ぎないと判断する.しかし,実際には,そのような自殺願望や自殺行動は,最後には自殺に至る最初の一歩かもしれない.さらに,家族的に自殺行動が多発することを考えると,自殺の危険の高い親を治療している同僚と協力することによって,ハイリスクの子どもを発見するのにも役立つ.最後に,火器による自殺率が高いことを考えると,自殺の危険の高い青少年が住んでいる自宅から銃を取り除くように家族に要請することも重要である.
このように研究を進めていった結果,自殺の危険を評価する基準を得ることができた.これはさらに他の3種の重要な領域を明らかにした.(1)ティーンエイジャーの社会的なつながりの中における自殺の衝撃を理解する,(2)自殺がどのように家族に多発するかを理解する,(3)自殺の危険を和らげるために,自殺の危険の高い若者に対する治療法を開発する.
当時,社会が自殺の伝染をヒステリーのように取り上げていたのを伝えるのは容易ではない.Kim Puig-Antich博士がこれは研究に価しない領域であると考えていたことを私は思い出す.ただし,それはここピッツバーグでまさに私たち自身が自殺の疫病を経験するまでのことだった.地元の高校で18日間で3名の自殺者と7名の自殺未遂者が出たのだ.まず,自殺行動を模倣するのは,自殺者ともっとも強い絆のあった人だと私たちは考えた.いわばティーンエイジャーの自殺の社会的つながり(親友や家族)である.私たちは研究を実施し,自殺者の親,兄弟姉妹,友人,そして友人の友人を面接した.友人や兄弟姉妹は一般人口に比べて精神医学的問題を抱えている率が高いという点を調整したとしても,思春期の自殺と密接な接触があった人の約半数は対照群(接触のなかったティーンエイジャー)と比べて自殺未遂に及ぶ危険が高かった.自殺者の友人は,過去に自殺を考えたことがあったとしても,この苦痛に満ちた余波を経験した後に,自分はけっして自殺しないと答えた.この結果をもとに,私たちは既遂自殺の話題をマスメディアはどのように報道すべきかという点について提言をまとめた.すなわち,(1)模倣を阻止する,(2)自殺者を美化してしまうと,結果的に模倣の可能性に焦点を当ててしまうので,それを控えて,自殺は本来治療可能な精神疾患の結果として生じることに焦点を当てて報道する,というものであった.
しかし,自殺は周囲の人々に長期的な影響を及ぼした.自殺が生じた後,およそ1/3の友人や兄弟姉妹が臨床的にうつ病を発病した.もっとも脆弱であったのは,自殺が起きる前の24時間に,自殺の計画を知ったり,自殺者と話をしたものの,自殺を防ぐことができなかったとして自責感を覚えていた人である.これは,友人の自殺の計画を秘密にしておいてはならないということをティーンエイジャーに教育することの重要性を物語っている.要するに,自殺者の友人や家族は自殺が起きた後,長期にわたって非常に深刻な影響を受け,中には6年経っても重度の悲嘆を呈している人さえいたのである.
1986年,私たちの研究グループが心理学的剖検の研究を実施していた頃だが,小児精神科の主任で,私たちのスーパーバイザーであったKim Puig-Antich博士は,ティーンエイジャーの自殺予防プログラムが必要であると決断した.当初,私はそういったクリニックを開くことをためらっていた.私はKimと次のような会話を交わした.
KIM:デビッド,あなたに自殺の危険の高いティーンエイジャーのためのクリニックを開いてほしいのです.自殺の評価や治療について私たちが参考にできるようなものはほとんどなかったのだが,ティーンエイジャーの自殺が増えているという現状に直面して,私たちは前に進んでいかなければならないのだとKimは私たちを励ました.そして,彼は私たちがピッツバーグ大学精神科のスタッフであったMary Margaret Kerr博士と協力関係を持つ仲介役を果たしてくれた.私たちはともにティーンエイジャーのための自殺予防センターを設置する提案をまとめて,ペンシルバニア州に提言した.そして,州はこのプログラムを今日まで支持してきた.プログラムは次の2つの主要な要素からなる.
DAVID:でも,私は自殺の危険の高いティーンエイジャーの治療について何も知りません.
KIM:それは構わない.少しずつ学んでいけばいい.
DAVID:でも,自殺の危険の高いティーンエイジャーの治療について知っている人なんて誰もいません.
KIM:それでいいのだよ.ということは,君を非難できる人なんて誰もいない.さあ,始めよう.何人かの命を救うのです.
(1)アウトリーチ:これは主として,教育と予防からなる
(2)臨床:自殺の危険の高い若者への介入に焦点を当てる
アウトリーチでは,自殺の危険をいかに認識し,対応するか,そして生徒の自殺が不幸にして起きた場合にはその余波にどう対応するかという点について,Kerr博士はプログラムを作っていった.私の役割は,研究を実施し,自殺の危険の高いティーンエイジャーのためのクリニックを運営することだった.研究から何か新しい知見を得ると,Kerr博士はそれをただちに数千人の教育関係者や精神保健の専門家の研修や教育に組み入れていった.
クリニックでは,毎日1人は新たな自殺の危険の高い思春期患者を私たちは診察していた.このような患者に対して経験的に有効であると証明されている治療法がなかったため,私たちは心理学的剖検から得られた知見に頼った.すなわち,このようなティーンエイジャーは,抑うつ的で,絶望し,衝動的であり,問題解決能力が低いという点である.当時は,三環系抗うつ薬が唯一の薬物だったが,小児には効果があるとは証明されておらず,過量服用すると命を失う恐れさえあった.したがって,私たちは思春期患者を心理療法で治療しようと考えた.成人患者の治療に関する文献にあたり,Beckの認知療法(cognitive therapy)が成人のうつ病患者に有効であることを知った.そこで,私は認知療法について学び,この治療法を思春期患者に応用しようと考えた.Beckの理論的枠組みを応用し,抑うつ的になると,自己の否定的な気分をさらに強化してしまうような世界観がどのように作り上げられているか,思春期患者が理解できるように私たちは働きかけていった.すなわち,肯定的な側面を無視し,否定的な側面を過度に取り上げ,(とくに自殺の危険の高いティーンエイジャーでは)白か黒かの思考法に囚われ,最終的には生か死かといった究極的な二分割思考に陥ってしまう点について,患者が理解できるように助力していった.
当時,ある地元の精神保健センターで夜働いていた時に,私はKimberly Polingに出会った.彼女は聡明で,活発な若いソーシャルワーカーで,思春期患者との絆を作り上げる天賦の才があった.渋々治療を受けているティーンエイジャーとの間に関係を築き上げる彼女の能力に私はとくに感銘した.他の人々が欲求不満に陥り,投げ出してしまうような事例であっても,Kimは楽天的で,先を見越して行動を起こし,患者との間にラポールを築き,協力して問題を解決していく姿勢は,印象的な結果をもたらした.彼女の行動によって,私は多くを学びたいと考えた.ある日,私が彼女にWPICでの私の仕事について話すと,彼女は日曜日の午後はほとんどの時間をWPICの図書館で過ごして情報を集めていると教えてくれた.彼女もまだ作曲されていない音楽を捜し求めているように思われた.そこで私は彼女にティーンエイジャーのための自殺予防プログラムに協力してくれるように依頼した.それは当時すでに,危機にあるティーンエイジャーのためのサービス(Service for Teens at Risk:STAR)として知られていた.
Kimは他の3人のセラピストと私のスタッフに加わり,経験的に実証された評価手順やBeckの認知療法モデルに基づいた治療の手引きを協力して開発していった.治療は奏効していると感じていたが,1つ大きな問題があった.ドロップアウト率が40%にも上っていたのだ.私たちは治療から脱落した患者の家族に連絡して,治療のどの部分が気に入って,どの部分が気に入らなかったのか明らかにしようとした.その結果,親は子どもに腹を立てていて,子どもの自殺行動によって振り回されていると感じていることが明らかになった.子どもが病気であり,それを自分の力でコントロールできないことを,私たちは親に理解させられていないことに気づいた.そこで,Kimと私は,親に対してティーンエイジャーの気分障害について最新の知見を解説する冊子を作った.その冊子「ティーンエイジャーのうつ病:家族のためのサバイバルマニュアル」では,うつ病の症状,原因,治療法についての心理教育,そして,もっとも重要な点として,うつ病がどのようにして家族全体に影響するのかを解説した.家族がどのようにしてうつ病のティーンエイジャーを助力できるかという点について具体的なアドバイスを挙げた.プログラムが親に子どものうつ病について教育するうえで効果があったばかりでなく,多くの親が自分自身のうつ病にも気づいて,治療を求めてくるようになった.この介入法によって,ドロップアウト率は劇的に減少した.
私たちは,この新たな認知行動療法(cognitive-behavioral therapy:CBT)と,家族療法と支持的療法という効果的であるとされて広く実施されている2つの治療法を比較することにした.その結果,うつ病の症状を和らげるうえで,CBTは他の2つの治療法よりもすぐれていることが明らかになった.この知見から,CBTは思春期のうつ病に効果的な治療法であると認識されるようになった.さらに,(現在の,あるいは過去の)自殺の危険を認める患者においても,CBTは支持的療法よりも,うつ病を改善することが明らかになった.しかし,自殺願望や自殺行動そのものの減少という点では,CBTと他の2つの治療法の間に有意差はなかった.これは重要な問題点を明らかにした.すなわち,うつ病の治療効果と自殺行動に対する治療効果の間には乖離があるという点である.治療によって思春期のうつ病は改善したものの,衝動的な自殺未遂によって救急部に突然受診してくるということも起こり得る.一体何が起きたのかと患者に質問すると,強烈な感情に圧倒されたのだと答えるだろう.私たちはこの状態を感情統御不全(emotion dysregulation)と名づけるようになった.これは私たちが見逃していた,非常に重要な治療標的であると思われた.そこで,1996年にMarsha Linehan博士をWPICに招き,弁証法的行動療法(dialectical behavior therapy:DBT)について集中的な研修を受けた.私たちはLinehan博士から感情統御と苦悩耐性スキルについて学び,私たちの治療的アプローチを補完した.STARクリニックにおいて,CBT,DBT,家族療法を統合して実施したところ,この統合的治療こそがまさに私たちが求めていたものであると認識した.
その後の数年間,STARクリニックの臨床家たちはこの治療モデルを実践し,好結果を得た.私たちがうつ病で自殺の危険の高い思春期患者の治療に成功していることに他の臨床家たちも気づき始め,私たちに研修やワークショップを依頼してくるようになった.他の臨床家たちも,CBTだけでは十分ではないという私たちの以前の懸念に賛同するようになった.そこで,私たちのアプローチには何か独特なものがあり,他の臨床家もそれから何か有益なものを得られるかもしれないと考え,本書をまとめようと考え始めたのだ.
そして,Tina Goldsteinも私たちに参加した.彼女はコロラド大学博士課程の大学院生であったが,小児期の双極性障害について研究していて,小児期の気分障害の評価や治療の重要な領域として,感情統御不全について関心を抱いた.彼女はWPICで6か月間にわたりティーンエイジャーのための自殺予防プログラムで博士前インターンシップを受けた.私たちと同じ関心を抱いた臨床家であり研究者を見つけたことはすぐに明らかになった.思春期患者と自然なラポールを築くことができるだけでなく,彼女にはKimが協同的経験主義の軽快な防御と攻撃と呼んだ稀な能力が備わっていた.これはすなわち,治療場面において,臨床の技と経験的な研究のデータを臨機応変に統合する能力を指している.Tinaは2003年に,博士課程修了後の研究員として私たちの研究に加わり,Kimから臨床的なスーパービジョンを受けることになった.
その後,私は自殺行動についてのこれまでの研究成果やうつ病を超えた危険についてもさらに理解しようとしてきた.というのも,うつ病の治療だけでは,かならずしも自殺の危険を除去できなかったからである.ある状況の危険因子を理解する1つの方法として,集団としての家族について検証することができる.1985年に私は深刻な自殺未遂に及んだ少年を診察した.家族歴を聴取すると,その少年の家族には自殺が多発していた.数か月後,弟も深刻な自殺未遂後に私たちのクリニックに紹介されてきた.うつ病といった精神障害に関与する遺伝的危険だけでなく,自殺に関与する遺伝的素因さえ存在するのではないかと私は疑問に感じた.
この疑問に答えるために,思春期の自殺者の家族と対照群の家族における,自殺,自殺行動,精神障害の率について調査した.たとえ,精神障害の差を調整した後であっても,既遂自殺者の身内には自殺行動の率がはるかに高かった.換言すると,精神障害以外の何かがそのような家族内には伝わっていた.家族内の自殺の危険の伝播には,重要な性質として衝動的攻撃性(impulsive aggression)という概念が明らかになった.既遂自殺者の身内に認められた自殺行動の率は,非常に攻撃的な手段で自殺した人の身内で高かった.
自殺が起きるという危険の一連の結果を後から振り返って1つひとつ解きほぐしていくのは難しい.自殺行動が実際に家族的に多発するというのであれば,成人の自殺未遂者の場合,その子どもの自殺の危険も増していることを明らかにできるかもしれない.ニューヨーク州立精神科病院のJohn Mann博士らとの共同研究で,うつ病で自殺未遂歴のある成人患者の子どもと,気分障害ではあるが自殺未遂歴のない成人患者の子どもについて,子どもの自殺未遂の危険を比較した.両群間で気分障害などの率は同等であったが,自殺未遂者の子どもでは,自殺未遂の率が6倍高かった.両群の子どもを識別する主要な要因の1つが,攻撃性の高さであった.さらに,自殺行動の家族歴がある成人の自殺未遂者が,もっとも攻撃的で,その子どもは自殺未遂の率がより高く,より低年齢で未遂に及んでいた.これが強く示唆していたのは,衝動的攻撃性の傾向が自殺行動の家族パターンを説明するうえで重要であるという点である.この傾向は自殺の危険にきわめて密接に関連していると考えられるために,これに焦点を当てた介入を開発する必要があった.
これは私たちが今日も直面している課題へとつながっていった.ティーンエイジャーのうつ病に有効な治療法が今ではあるのだが,その有効性は60%程度である.そこで,第一選択薬のセロトニン再取り込み阻害薬が効果を現さなかった場合に,他の治療を試みるという研究を実施し,うつ病に反応するもっとも有効な治療法はCBTと薬物療法を併用することであることを明らかにした.さらに,望ましい反応を予測するために,私たちは遺伝的要因と薬理動態学的要因も同定した.これによって,将来は,ある患者にとって適切な治療法を選択することができるようになるかもしれない.
私たちが抱えているもう1つの難しい課題として,自殺未遂歴のある思春期患者が再企図に及ぶのを予防する有効な治療法がまだ開発されていないという点がある.STARで私たちが長年かけて開発してきた治療法は,多施設で実施されている思春期自殺未遂者に対する治療(Treatment of Adolescent Suicide Attempters:TASA)の基礎となっている.これは地理的かつ人種的にさまざまに異なる患者に対してこの治療法を有効に実施するのに役立っている.しかし,思春期の自殺未遂者に対する他の治療法と同様に,確実に有効であるとはまだ明らかにされていない.心理療法の他の先駆的な研究者たち(たとえば,Greg Brown, John Curry, Betsy Kennard, Barbara Stanley, Karen Wellsら)と協力してTASA計画に携わっていくことで,うつ病で自殺の危険の高い思春期患者の治療にとって有効な要素であると私たちが考える点を検証し,さらに明確なものにしていくことができるだろう.
私たちの試みを始めた当初は,思春期の自殺率が上昇しつつあったものの,自殺の危険因子について知識はなく,自殺の伝染についての深刻な懸念があり,思春期のうつ病に対する治療法もなかった.しかし,今では思春期の自殺率は下がってきたし,自殺の危険を評価する経験的な枠組みも手にし,思春期のうつ病に有効であると経験的に実証されたいくつかの治療法もある.現時点では,自殺行動に関連する遺伝的な危険因子を同定し,反復性の自殺行動や治療抵抗性のうつ病の発病を予防する介入も開発され,うつ病が発病しても自殺行動の発生を予防しようとするいくつかの研究も進行中である.しかし,これらの質問に対する答えを見出すことができていない現在においても,自ら命を絶ちたいと考えているうつ病の思春期患者を助力するために,私たちは自分たちが知っている最善の方法を適用することができるし,また,そうしなければならない.患者が人生の意義を理解し,人生からもっとも多くのものを得られるように助力するために,本書では最新の知見について解説したいと考えている.
著者らは,臨床的な知恵と協同的経験主義を組み合わせて,統合的な概念を創りあげることを意図している.まず,うつ病と自殺の危険の評価について総説し,この状態に対してエビデンスに基づいて有効とされている治療法について解説する.次に,うつ病で自殺の危険の高い思春期患者に有効な治療法に必要とされる要素について取り上げ,治療的関係,安全計画,治療についての症例の概念化について解説していく.そして,協同的治療関係,特殊な治療技法,思春期患者が回復し,安定した状態を維持するのを助力することなどを含めて,私たちの治療的アプローチついて概説する.最後に,この分野の将来の方向性についても述べたい.
目次
開く
著者略歴
訳者略歴
謝辞
はじめに
第1章 思春期のうつ病:評価と治療についての総説
なぜ思春期のうつ病は重要な問題なのか?
うつ病について家族がよくする質問(そしていくつかの短い答え)
分類
気分障害の評価の手引き
鑑別診断と重複罹患の評価
思春期のうつ病に対するエビデンスに基づいた治療法に関する総説
第2章 自殺願望と自殺行動の評価と治療
自殺行動の重要性といくつかの重要な定義
評価の一般的原則
質問についての5つの重要な領域
緊急の自殺の危険を評価する
治療の場の決定
第3章 効果的治療の重要な要素
組織の環境
セラピストの人柄
治療関係
第4章 治療の開始
どのようにセッションを組み立てるか
どのように安全計画を立てるか
適切な治療のレベルを決定する
最初のセッションでラポールを築く
守秘義務
患者自身も治療に関与させる
治療関係を築く
患者と家族に対する心理教育
目標設定
第5章 連鎖分析と治療計画
連鎖分析とは何か?
いつ連鎖分析を利用するか
連鎖分析をする際の障害をどう克服するか
連鎖分析をどのように実施するか?
親と連鎖分析を実施する
危険因子と保護因子を取り上げる
治療計画
具体的な症例
第6章 行動賦活と感情統御
行動賦活
感情統御
感情の測定
注意を他に逸らす
自己に対する慰め
深呼吸
前進的筋肉リラクセーション
快いイメージ
家族に対する感情統御スキル
第7章 認知の再構築,問題解決,対人関係効率化
変化の仕方
認知と感情の障害
思考,感情,行動の関連
現時点の関連を把握する
認知の歪曲
自動思考,思いこみ,核の信念
自殺を考える
認知の再構築
問題解決
対人関係スキルを向上させる
第8章 治療抵抗性うつ病
治療抵抗性うつ病とは何か?
なぜ治療抵抗性うつ病が重要なのか?
7つの重要な質問
最初の抗うつ薬に反応しなかった患者に対する治療
治療抵抗性うつ病の予防
第9章 回復とその維持:強化と維持療法
なぜ急性期治療の後に追加の治療段階が必要であるのか?
強化治療
維持治療
第10章 前進!
私たちは何ができるだろうか?
近い将来に活用できる可能性のある他のアプローチ
自殺の危機を評価するための新しいアプローチ
文献
訳者あとがき
索引
訳者略歴
謝辞
はじめに
第1章 思春期のうつ病:評価と治療についての総説
なぜ思春期のうつ病は重要な問題なのか?
うつ病について家族がよくする質問(そしていくつかの短い答え)
分類
気分障害の評価の手引き
鑑別診断と重複罹患の評価
思春期のうつ病に対するエビデンスに基づいた治療法に関する総説
第2章 自殺願望と自殺行動の評価と治療
自殺行動の重要性といくつかの重要な定義
評価の一般的原則
質問についての5つの重要な領域
緊急の自殺の危険を評価する
治療の場の決定
第3章 効果的治療の重要な要素
組織の環境
セラピストの人柄
治療関係
第4章 治療の開始
どのようにセッションを組み立てるか
どのように安全計画を立てるか
適切な治療のレベルを決定する
最初のセッションでラポールを築く
守秘義務
患者自身も治療に関与させる
治療関係を築く
患者と家族に対する心理教育
目標設定
第5章 連鎖分析と治療計画
連鎖分析とは何か?
いつ連鎖分析を利用するか
連鎖分析をする際の障害をどう克服するか
連鎖分析をどのように実施するか?
親と連鎖分析を実施する
危険因子と保護因子を取り上げる
治療計画
具体的な症例
第6章 行動賦活と感情統御
行動賦活
感情統御
感情の測定
注意を他に逸らす
自己に対する慰め
深呼吸
前進的筋肉リラクセーション
快いイメージ
家族に対する感情統御スキル
第7章 認知の再構築,問題解決,対人関係効率化
変化の仕方
認知と感情の障害
思考,感情,行動の関連
現時点の関連を把握する
認知の歪曲
自動思考,思いこみ,核の信念
自殺を考える
認知の再構築
問題解決
対人関係スキルを向上させる
第8章 治療抵抗性うつ病
治療抵抗性うつ病とは何か?
なぜ治療抵抗性うつ病が重要なのか?
7つの重要な質問
最初の抗うつ薬に反応しなかった患者に対する治療
治療抵抗性うつ病の予防
第9章 回復とその維持:強化と維持療法
なぜ急性期治療の後に追加の治療段階が必要であるのか?
強化治療
維持治療
第10章 前進!
私たちは何ができるだろうか?
近い将来に活用できる可能性のある他のアプローチ
自殺の危機を評価するための新しいアプローチ
文献
訳者あとがき
索引
書評
開く
思春期・青年期患者の心理療法を扱う人々に広く読んでほしい一冊
書評者: 山本 泰輔 (防衛医科大学校防衛医学研究センター・行動科学研究部門)
「死にたい」「生きているのがつらい」「気がついたら自傷(自殺未遂)に及んでいた」…,こうした若者が目の前に現れたときにどう接するかという問題は,教育現場にいる者,または心理療法,精神療法を担当する者にとっては,避けて通れない。こうした若者は,多くの場合,希死念慮の背景に多くの問題(精神疾患,社会スキルの未熟,経験の不足,不健康な人間関係など)を抱え,同世代のコミュニティから取り残され,それがさらに将来の適切な発達過程の機会を失わせるという悪循環の中にいる。このため,自殺予防としては,急性期には精神症状に対する治療,中長期的には成長を含む包括的な戦略が必要である。
本書は,こうした急性期から中長期的に及ぶ問題点とその対処法について,具体的に,そして体系的に解説してくれている。個別のアプローチについては,患者とセラピストの実際のやりとりや有用なツールが例示されているので,それぞれ自分の扱っているケースで役に立つところを抜き出してそのまま使える。また,全体の大きな戦略について体系的に解説されており,これらをしっかり理解して実践することで,自分でケースを扱う際に,治療経過を論理的に把握し,患者と共有することを可能にしてくれる。連鎖分析による問題点や保護因子の把握,思考・感情・行動への効果的な介入といったスキルがわかりやすく解説されている。これら個別のアプローチ自体は特段新しいものではないが,体系的に理解することでこれらの組み合わせを戦略的に活用でき,また患者に説明・助言することができる。これにより,患者が抱えた問題の解決に向けて,セラピストと協力しながら,患者自身が努力し,多くを学んでいくことを可能にする。最終的に,患者は自分で健康的なサイクルへ復帰し,本来の軌道での生活を再開させることにつながる。
訳者の高橋祥友氏は,長年自殺予防に注力してきた日本を代表する精神科医である。その高橋氏のあとがきにも書かれている通り,上記にあるようなスキルの訓練を個人療法の場に統合することを本書は可能にした。米国の研究者による著作の翻訳であるため,日本での文化や会話形式にそぐわないところ(家庭に銃がある場合の保管法といった予防策が述べられていたり,患者とセラピストの会話で日本人にはピンとこない流れがあったりする)や,内容的に堅苦しいところもあるが,現実に自殺の危機にある若者と接している治療者にとって,本書は即実践可能なアプローチを提供してくれる。また,自殺予防に特化しなくても,これらの考え方は思春期・青年期患者の心理療法を扱う者にとって大いに応用し得る内容である。基本的には心理療法家,精神療法家を対象にした解説であるが,これらの体系的な理解は心に問題を抱える若者への支援に大いに役立つと思われ,それらにかかわる人々に広く読んでほしい一冊である。
思春期患者の自殺予防への寄与が期待される書
書評者: 今村 芳博 (優なぎ会森本病院精神科)
日本の自殺死亡は1990年代以降,中高年男性が中核を占めているが,最近の警察庁統計を元にした報道によれば,2011年には10-20歳代の自殺が増加している。東日本大震災の影響を受けた昨年4月以降の大学生の就職率が過去最低となるなど,その背景には雇用情勢の悪化があるという。社会構造変化の際に20歳代男性の自殺死亡率が増加するのは世界的傾向と言われる。現代は若い世代が即戦力としての働きを要求されるなど厳しい状況であるというが,社会的な要請の変質は,個人の心理的発達課題を一層複雑で達成し難いものとする。そうした時期に原著の出版から間を置かずして本書が訳出されたことは大変意義深い。
米国ではBeckがうつ病への認知療法を1979年に出版して以来,認知療法を思春期患者に応用する試みがなされてきた。著者の1人,David A. Brentが思春期のうつ病と自殺について研究を始め,ピッツバーグ大学医学部にポストを得たのは1982年であった。当時,「私たちのアプローチは無知と恐怖で満ちていた」というように,それらに対して経験的に実証された治療法はなく,救急受診したどの自殺未遂者を帰宅させてよいか,自殺未遂が反復される危険について評価することすらできなかった。そこからティーンエイジャーの自殺予防プログラムを開設し,「危機にあるティーンエイジャーのためのサービス(Service for Teens at Risk : STAR)センター」として活動を続けてきた。その基本的治療は,従来の臨床的知見と認知行動療法(cognitive-behavioral therapy : CBT)を統合した包括的なものである。それに最近注目されている弁証法的行動療法(dialectical behavior therapy : DBT)の要素も取り入れている。その中心概念は協同的経験主義である。すなわち,セラピストと患者は一致協力して,問題解決に向けて努力していく姿勢が強調されている。評価,治療段階の設定,安全計画,治療関係の構築,心理教育と目標設定,連鎖分析,治療計画,新たなスキルの獲得,スキルの応用と一般化の練習,好調の維持について,具体的かつ詳細に解説されているため本書は大変理解しやすい。印象的なのは連鎖分析で,問題行動の引き金になった出来事やそれに関与する要因を思春期患者が明確に語ることはできないところを,「どのような行為も妥当な理由があって起きている」という視点に立ち,コマ送りのように行動を分析し,危険因子と保護因子,効果的な介入方法について検討することができる。ツールとしてのCBTを有効活用する際の大きな助けとなる。DBTではスキル教育の集団療法を設定し,電話によるコンサルテーションなども行うため,日本では運用し難い部分もある。また,症例によっては言語化能力が低かったり,強度の緘黙があったりするので,すべてに応用可能とはいえないだろうが,本書のアプローチであれば思春期のうつ病に限らずとも日々の診療から少しずつ始められそうだ。
米国では思春期患者の自殺率は減少傾向にあるという。日本でもこうした心理療法の発展が思春期患者の自殺予防に寄与することに期待が持てる書である。
書評者: 山本 泰輔 (防衛医科大学校防衛医学研究センター・行動科学研究部門)
「死にたい」「生きているのがつらい」「気がついたら自傷(自殺未遂)に及んでいた」…,こうした若者が目の前に現れたときにどう接するかという問題は,教育現場にいる者,または心理療法,精神療法を担当する者にとっては,避けて通れない。こうした若者は,多くの場合,希死念慮の背景に多くの問題(精神疾患,社会スキルの未熟,経験の不足,不健康な人間関係など)を抱え,同世代のコミュニティから取り残され,それがさらに将来の適切な発達過程の機会を失わせるという悪循環の中にいる。このため,自殺予防としては,急性期には精神症状に対する治療,中長期的には成長を含む包括的な戦略が必要である。
本書は,こうした急性期から中長期的に及ぶ問題点とその対処法について,具体的に,そして体系的に解説してくれている。個別のアプローチについては,患者とセラピストの実際のやりとりや有用なツールが例示されているので,それぞれ自分の扱っているケースで役に立つところを抜き出してそのまま使える。また,全体の大きな戦略について体系的に解説されており,これらをしっかり理解して実践することで,自分でケースを扱う際に,治療経過を論理的に把握し,患者と共有することを可能にしてくれる。連鎖分析による問題点や保護因子の把握,思考・感情・行動への効果的な介入といったスキルがわかりやすく解説されている。これら個別のアプローチ自体は特段新しいものではないが,体系的に理解することでこれらの組み合わせを戦略的に活用でき,また患者に説明・助言することができる。これにより,患者が抱えた問題の解決に向けて,セラピストと協力しながら,患者自身が努力し,多くを学んでいくことを可能にする。最終的に,患者は自分で健康的なサイクルへ復帰し,本来の軌道での生活を再開させることにつながる。
訳者の高橋祥友氏は,長年自殺予防に注力してきた日本を代表する精神科医である。その高橋氏のあとがきにも書かれている通り,上記にあるようなスキルの訓練を個人療法の場に統合することを本書は可能にした。米国の研究者による著作の翻訳であるため,日本での文化や会話形式にそぐわないところ(家庭に銃がある場合の保管法といった予防策が述べられていたり,患者とセラピストの会話で日本人にはピンとこない流れがあったりする)や,内容的に堅苦しいところもあるが,現実に自殺の危機にある若者と接している治療者にとって,本書は即実践可能なアプローチを提供してくれる。また,自殺予防に特化しなくても,これらの考え方は思春期・青年期患者の心理療法を扱う者にとって大いに応用し得る内容である。基本的には心理療法家,精神療法家を対象にした解説であるが,これらの体系的な理解は心に問題を抱える若者への支援に大いに役立つと思われ,それらにかかわる人々に広く読んでほしい一冊である。
思春期患者の自殺予防への寄与が期待される書
書評者: 今村 芳博 (優なぎ会森本病院精神科)
日本の自殺死亡は1990年代以降,中高年男性が中核を占めているが,最近の警察庁統計を元にした報道によれば,2011年には10-20歳代の自殺が増加している。東日本大震災の影響を受けた昨年4月以降の大学生の就職率が過去最低となるなど,その背景には雇用情勢の悪化があるという。社会構造変化の際に20歳代男性の自殺死亡率が増加するのは世界的傾向と言われる。現代は若い世代が即戦力としての働きを要求されるなど厳しい状況であるというが,社会的な要請の変質は,個人の心理的発達課題を一層複雑で達成し難いものとする。そうした時期に原著の出版から間を置かずして本書が訳出されたことは大変意義深い。
米国ではBeckがうつ病への認知療法を1979年に出版して以来,認知療法を思春期患者に応用する試みがなされてきた。著者の1人,David A. Brentが思春期のうつ病と自殺について研究を始め,ピッツバーグ大学医学部にポストを得たのは1982年であった。当時,「私たちのアプローチは無知と恐怖で満ちていた」というように,それらに対して経験的に実証された治療法はなく,救急受診したどの自殺未遂者を帰宅させてよいか,自殺未遂が反復される危険について評価することすらできなかった。そこからティーンエイジャーの自殺予防プログラムを開設し,「危機にあるティーンエイジャーのためのサービス(Service for Teens at Risk : STAR)センター」として活動を続けてきた。その基本的治療は,従来の臨床的知見と認知行動療法(cognitive-behavioral therapy : CBT)を統合した包括的なものである。それに最近注目されている弁証法的行動療法(dialectical behavior therapy : DBT)の要素も取り入れている。その中心概念は協同的経験主義である。すなわち,セラピストと患者は一致協力して,問題解決に向けて努力していく姿勢が強調されている。評価,治療段階の設定,安全計画,治療関係の構築,心理教育と目標設定,連鎖分析,治療計画,新たなスキルの獲得,スキルの応用と一般化の練習,好調の維持について,具体的かつ詳細に解説されているため本書は大変理解しやすい。印象的なのは連鎖分析で,問題行動の引き金になった出来事やそれに関与する要因を思春期患者が明確に語ることはできないところを,「どのような行為も妥当な理由があって起きている」という視点に立ち,コマ送りのように行動を分析し,危険因子と保護因子,効果的な介入方法について検討することができる。ツールとしてのCBTを有効活用する際の大きな助けとなる。DBTではスキル教育の集団療法を設定し,電話によるコンサルテーションなども行うため,日本では運用し難い部分もある。また,症例によっては言語化能力が低かったり,強度の緘黙があったりするので,すべてに応用可能とはいえないだろうが,本書のアプローチであれば思春期のうつ病に限らずとも日々の診療から少しずつ始められそうだ。
米国では思春期患者の自殺率は減少傾向にあるという。日本でもこうした心理療法の発展が思春期患者の自殺予防に寄与することに期待が持てる書である。
更新情報
-
更新情報はありません。
お気に入り商品に追加すると、この商品の更新情報や関連情報などをマイページでお知らせいたします。