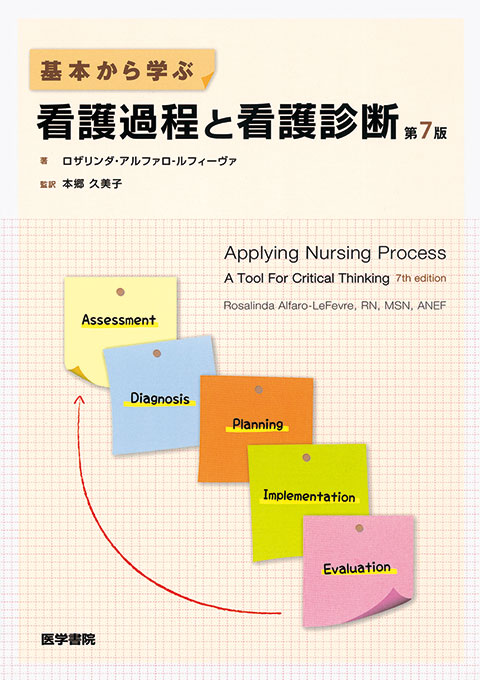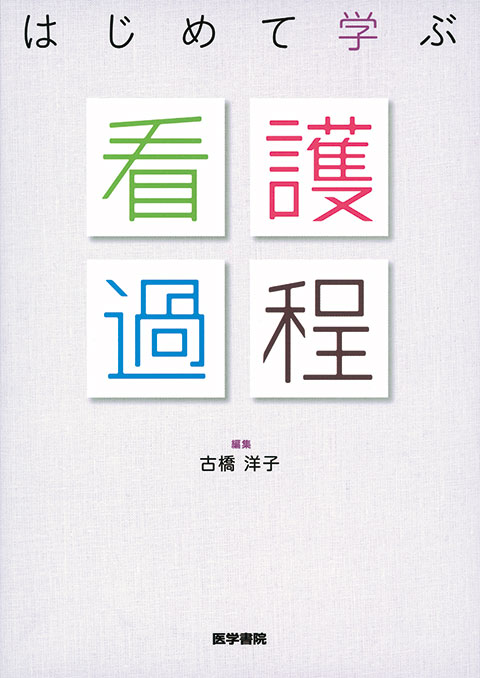基本から学ぶ看護過程と看護診断 第7版
“考える看護過程”を身につけるために
もっと見る
看護過程と看護診断を初めて学ぶ人のための教科書・参考書。第7版ではレイアウトを刷新し、より読みやすい構成となった。看護過程を段階ごとにわかりやすく説明し、アセスメントをもとに看護師が対処すべき問題を明確化する過程を特に詳しく解説している。また、全体を通してクリティカルシンキングを重視、看護過程に必要な思考や発想のヒントが数多く盛り込まれている。“考える看護過程”を身につけるのに最適な1冊。
| 著 | ロザリンダ・アルファロ-ルフィーヴァ |
|---|---|
| 監訳 | 本郷 久美子 |
| 発行 | 2012年12月判型:B5頁:368 |
| ISBN | 978-4-260-01689-6 |
| 定価 | 2,860円 (本体2,600円+税) |
更新情報
-
更新情報はありません。
お気に入り商品に追加すると、この商品の更新情報や関連情報などをマイページでお知らせいたします。
- 序文
- 目次
- 書評
序文
開く
第7版監訳者まえがき/第7版まえがき
第7版監訳者まえがき
本書は,ロザリンダ・アルファロ-ルフィーヴァ氏による『基本から学ぶ看護過程と看護診断』の第7版です。初版の発行は1987年で,今年は25年目にあたります。この間,本書は看護過程と看護診断が基本から学べるわかりやすいテキスト・参考書として,多くの看護教育や看護実践の場で親しまれてきました。
論理的な看護実践の枠組みとして看護過程を説明する姿勢はこれまでと変わっていませんが,今回の改訂では,看護過程の各段階に必要なクリティカルシンキングのスキルを,よりわかりやすく明確に解説しています。これにより,自分自身の思考を深めるための教材として,いっそう活用することができるでしょう。
また,最近では一般的になってきた電子カルテなどのコンピュータ支援による看護診断についても触れており,それらが“あなたに代わって考えてくれる”わけではないことを強調しているのも特徴的です。コンピュータにすべてを頼らず,そして看護診断が独り歩きすることがないように,看護過程のルールに基づいてクリティカルシンキングのスキルを各自が身につけなければならないのです。
第7版ではページデザインが大きく変わりました。それぞれの項目や構成がわかりやく,学習しやすいように工夫されていることに気づかれると思います。
各章の冒頭には,内容の要約と到達目標を掲載していますが,最初に看護過程を学ぶ読者にとっては難解かもしれません。冒頭部分は読み飛ばして,本文の内容の後に見直してもよいでしょう。また,初学者にとって目新しい用語も数多く出てきますので,巻末の「用語解説」を活用してください。
ロザリンダ・アルファロ-ルフィーヴァ氏とは約20年前,アトランタで開催されたNANDAのカンファレンスではじめてお会いしました。ウィットに富んでさわやかな彼女の講演に,時間が経つのも忘れてしまうほど聴き入ったことを覚えています。そうした彼女の性格は,本書からも伺い知ることができます。細やかなアセスメント・診断・計画・実施・評価という看護過程の原則だけでなく,患者に寄り添う看護師の温かい心が,本書全体から伝わってくることでしょう。
第7版の翻訳にあたり,各方面にわたり終始適切なアドバイスをいただいた医学書院看護出版部の長岡孝氏,本書の内容にふさわしい仕上げをして下さった制作部のみなさんに心から感謝申し上げます。
2012年11月
本郷久美子
第7版まえがき
独創性と情報化の時代の看護過程
アインシュタインはかつて,「今日,私たちが直面する重要な問題は,その問題をつくったときと同じ考えのレベルで解決することはできない」と述べている。今日の医療では,必然的に目まぐるしい変化が生じており,新しい考え方が求められている。本書は20年以上にわたり,この変化の時代にあって看護過程を学ぶための書として,学生・教員・看護師に支持されて続けてきた(過去にはシグマ・シータ・タウ最優秀図書賞を受賞)。
この版で,さらに新しい情報やツールを取り入れて,読者が看護過程を用いて“看護師らしく考える”ことを支援でき,とてもうれしく思っている。
情報化の時代に入ってから,エビデンスに基づく実践が要請されるようになっている。そうしたなか,看護過程の確固たる基礎を“頭のなかに入れておく”ことの理由は3つある。
1.米国看護師協会(ANA)の実践基準は,看護過程の位置づけについて,事実上あらゆるケアモデルの基礎であり,意思決定の基盤となり,十分な看護ケアを提供するためのクリティカルシンキングのモデルを提供するものとして強調されている1)。クリティカルシンキングのツールとしてはほかに有用なものもあるが,最初に看護過程を学んでおくことで,看護の基準を守り,ほかのモデルを学習するための基礎をつくることができる。
2.看護師資格試験(NCLEX)や,そのほかのほとんどの資格試験が,看護過程を基礎においている。基本的なルールと原則を知らなければ,これらの試験を自分で考えて解くことはできない。
3.電子カルテによる記録や意思決定支援システムなどが,“あなたのために多くを考えてくれる”ことが標準的になってきた。とはいえ看護師は,看護過程に基づいた思考のスキルをいっそう高め,ベッドサイドで意思決定を行い,“コンピュータとともに考える”ようにしなければならない。コンピュータは重要なツールで,クリティカルシンキングの能力を高めてくれる。しかし,あなたの代わりに考えてくれるわけではない。自分自身で自立してさまざまな思考を行うことで,入力したデータが事実で,漏れがないかを確認しなければならない。コンピュータにデータを入力するときは,どの情報がどの状況にあてはまるのかの判断が必要である。さらに,コンピュータは入力したデータが正しいという前提で処理するため,コンピュータからモニターに出力されるあらゆるデータの正確性を“第一線で守り抜く”のは自分自身ということになる。クリティカルシンキングや看護過程を学ばずに電子カルテやスタンダードケアプランを使うことは,四則演算を学ばずに電卓を使うようなものである。この場合,あなた自身が“壊れた電卓”であるといってもよいだろう。つまり,思考中心ではなく業務中心でケアを行うことで,それは“壊れたケア”となる。このような背景を理解していないと,ケアのアプローチを安全で効果的に個別化することができない。それは,患者にリスクをもたらし,あなた自身を法的な危険にさらすことになる。最後に,もう1つの問題がある。もしコンピュータがダウンしてしまったら,どうする? これは必ず起きることである。
読者対象
本書は,次のような読者のニーズを満たすことができるだろう。
1.クリティカルシンキングのツールとして看護過程を活用する方法を,米国看護師協会(ANA)の基準に沿ってアップデートしたい。
2.米国看護師資格認定センター(ANCC)から“マグネット・ホスピタル”として認定された,魅力的で質の高い病院で働くことを目指す読者。この場合,看護過程の各段階について熟知しておかなければならない2)。
3.クリティカルシンキングと看護過程の関係について,施設の全員で“共通理解”を得ようと考えている指導者。
4.学生。
・臨床の場面で十分な自信と能力を発揮したい。
・指導者にクリティカルシンキングを示したい。
・看護師資格試験(NCLEX)を解くための考え方を知りたい。
第7版の新しい内容
この版では,次のような新しい情報を掲載している。
+ 医学診断や看護診断,エラーの予防,早期警戒システム,指示系統を動かすことなどに対して増大する看護師の責任。
+ クリティカルシンキングを促す看護過程の特徴(クリティカルシンキングのツールとして看護過程をどのように活用するか)。
+ 思考の優先順位をどうつけるか,患者の重要な問題を早期に発見・予防するために迅速優先アセスメントをどう行うか。
+ 安全を優先する文化をどのようにはぐくむか。米国医学研究所(IOM)の示すコア・コンピテンシーは,安全で効果的な看護を実現させる能力とどのような関係があるか。
+ 看護過程の各段階に対応した,エビデンスに基づくクリティカルシンキングの指標(クリティカルシンキングを促す具体的な行動)。
+ ケアの調整と依頼について,看護師が担う役割。
+ “読み返し”と“繰り返し”の方法を用いて,能動的な(受動的でない)コミュニケーションを行うことの重要性。
+ 申し送りを改善するために,“SBARアプローチ”のような構造化されたツールをどう活用するか。
+ 看護過程の各段階に対応して,看護師資格試験(NCLEX)でどのような出題が想定されるか。
+ “治療・診断”から“予測・予防・管理・促進”に向かう考え方の変化。目下の健康問題を治療するだけでなく,先を見越し,危険因子の発見に焦点を絞り,典型的な健康問題をスクリーニングし,潜在的な合併症を予測するために,看護師に何が求められているか。
+ 関係性を判断し,より深く問題を理解するためにマップや図をどう活用するか。
+ 4つの円からなるクリティカルシンキングモデル(46ページ)をどのように活用してクリティカルシンキングの能力を高めるか。
+ 健全な職場環境や学習環境の必要性について。行動規範や患者・組織へのかかわり方も含む。
+ 本書全体にわたっての,さまざまな新しいルールやツールや戦略。
+ 協働的な実践,パートナーシップの促進,意思決定の共有,看護師のウェルネスなどの必要性。
+ 記録に関する詳細な情報。コンピュータや意思決定支援システムや情報科学による,ケアの管理と研究の促進について。
+ クリティカルシンキングの能力を高めるうえで,実際の経験や模擬的な経験が与える影響。
+ “事前に考え,実践しながら考え,事後に考える(振り返り)”ことの重要性。
新しい教材と学習ツール
+ 学習用のプリント,プレゼンテーション用の資料,単元ごとのシラバスが,Word形式でhttp://www.thePoint.lww.comからダウンロードできる(情報は英語のみ)。教材には,各章の主な見出し,学習の到達目標成果,本書に掲載したURLのリンクを掲載している。
+ さらにハンドアウトやツールをwww.AlfaroTeachSmart.comからダウンロードできる(情報は英語のみ)。これらのツールは個人利用であれば無料で使用してよい。
+ 新しいマップや“脳にはたらきかける学習”の原則(脳を学習モードに切り替える戦略)を活用しており,より学習がしやすくなっている。
第7版に引き継がれた内容
現在の基準に基づいた合理的なアプローチを示すように心がけ,いずれの章の内容も『看護の範囲と業務規準および臨床実践の基準』に準拠している3)。
さらに,次のような点を引き継いでいる。
+ さまざまな実例によって内容を関連づけ,理解しやすくしている。明快な内容で読者の興味を引くユーザーフレンドリーな書籍を目指している。
+ クリティカルシンキングのツールとして看護過程を活用するための方法を,おおまかな全体像で示している(付録F)。
+ 医学的な診断や治療や検査に関連した,一般的な合併症のリストを提示している(付録G・H)。
+ NANDA-I,NIC,NOCなどの標準的な看護用語の活用や誤用について,実践的な情報を掲載している。
+ そのほかに次のような内容も取り入れている。
・家庭や地域,多職種による実践における看護師の役割。
・倫理的・法的・文化的・スピリチュアルなかかわり。
・看護師が診断を行うことの役割とケースマネジャーとしての役割が,どのように高まってきているか。
・クリニカルパスウェイとクリティカルシンキングを高めるためのスタンダードケアプランをどのように活用するか。
・コミュニケーションスキルや対人スキルや技術的スキルの重要性。
本書の活用方法
制作にあたっては,ユーザーフレンドリーで,どこでも気軽に読めるような本にするために尽力した。次のような要素が,クリティカルシンキングを高め,動機づけを促し,思考を整理するために役立つはずである。
1.各章の最初に「学習の到達目標」として,講義のレベルで到達すべき目標を分析的にあげている。
2.章の最初に「この章のポイント」をまとめている。
3.重要な用語は「用語解説」で巻末にまとめ,より難解な用語などは本文中に脚注で定義,進行中の議論,使用される文脈などを説明している。
4.本文の説明の関係性や意味を明らかにするため,図を活用している。
5.情報を明確にし,重要な内容を説明するため,比喩や実例や症例を多用している。
6.図によって論理的根拠を強調し,必要に応じて本文の関連する他の部分との統合をはかっている。
7.全体を通して分析的な問いかけを行っている。 ・好奇心を刺激するような内容をもとに何が重要なのかのヒントを提供している。
・「クリティカルシンキングの練習問題」を,キーポイントの強調やテストの機会として活用することができ,知識の定着に役立つ。
8.内容を構造的に示しつつ,より創造的で自由に使うこともできるよう心がけている。
9.とくに他者からの評価を気にせずできる練習問題として,「自習コーナー」を設けている。
10.章の最後に「重要項目のまとめ」として,内容を要約している。
さらに前の版と同様,次の項目を盛り込んでいる。
+ 「考えてみよう」では,各自の思考を刺激し,内容の理解を高める題材を紹介している。
+ 「エキスパートからのアドバイス」では,主に看護師の感動的な実践や模範となる実践を引用して紹介している。
+ 「HMO(Help Me Out)」は,内容をユーモラスに強調した挿絵である(Help me out!には,何とかして!といった意味がある)。この挿絵は,実際にあったエピソードに基づいて描かれている。題材になりそうな経験があれば,著者まで連絡を(www.AlfaroTeachSmart.com)。
+ 「クリティカルシンキングの練習問題」は,すべての章に設けている。解答例は巻末の298~306ページに示している。
+ 「自習コーナー」は,より深く内容をあてはめて,意義のある学びを促すための設問である。この問題は,解答例を示していない。それぞれに個別化されるものであり,しかもきわめて長大な内容になるのがその理由である。
“患者/クライエント”,“彼/彼女”,利害関係者の用語について
本書では,“患者”や“クライエント”という用語ではなく,できるだけ“ある人”“その人”“利用者”“個人”といった用語を用いている。それぞれの患者またはクライエントは,固有のニーズ・価値観・知覚・動機をもった個人であるという考えに基づくものである。また,“利害関係者”という用語は,ケアの提供と成果の達成に関わるあらゆる人々のことをさしている(例:患者,家族,ケア提供者,保険会社)。
コメントや提案のお願い
今後も改善を重ねていくために,読者からの提案を歓迎する。重要な内容の改訂の多くが,学生や教員からの提案に基づいている。
Rosalinda Alfaro-LeFevre, RN, MSN, ANEF
www.AlfaroTeachSmart.com
第7版監訳者まえがき
本書は,ロザリンダ・アルファロ-ルフィーヴァ氏による『基本から学ぶ看護過程と看護診断』の第7版です。初版の発行は1987年で,今年は25年目にあたります。この間,本書は看護過程と看護診断が基本から学べるわかりやすいテキスト・参考書として,多くの看護教育や看護実践の場で親しまれてきました。
論理的な看護実践の枠組みとして看護過程を説明する姿勢はこれまでと変わっていませんが,今回の改訂では,看護過程の各段階に必要なクリティカルシンキングのスキルを,よりわかりやすく明確に解説しています。これにより,自分自身の思考を深めるための教材として,いっそう活用することができるでしょう。
また,最近では一般的になってきた電子カルテなどのコンピュータ支援による看護診断についても触れており,それらが“あなたに代わって考えてくれる”わけではないことを強調しているのも特徴的です。コンピュータにすべてを頼らず,そして看護診断が独り歩きすることがないように,看護過程のルールに基づいてクリティカルシンキングのスキルを各自が身につけなければならないのです。
第7版ではページデザインが大きく変わりました。それぞれの項目や構成がわかりやく,学習しやすいように工夫されていることに気づかれると思います。
各章の冒頭には,内容の要約と到達目標を掲載していますが,最初に看護過程を学ぶ読者にとっては難解かもしれません。冒頭部分は読み飛ばして,本文の内容の後に見直してもよいでしょう。また,初学者にとって目新しい用語も数多く出てきますので,巻末の「用語解説」を活用してください。
ロザリンダ・アルファロ-ルフィーヴァ氏とは約20年前,アトランタで開催されたNANDAのカンファレンスではじめてお会いしました。ウィットに富んでさわやかな彼女の講演に,時間が経つのも忘れてしまうほど聴き入ったことを覚えています。そうした彼女の性格は,本書からも伺い知ることができます。細やかなアセスメント・診断・計画・実施・評価という看護過程の原則だけでなく,患者に寄り添う看護師の温かい心が,本書全体から伝わってくることでしょう。
第7版の翻訳にあたり,各方面にわたり終始適切なアドバイスをいただいた医学書院看護出版部の長岡孝氏,本書の内容にふさわしい仕上げをして下さった制作部のみなさんに心から感謝申し上げます。
2012年11月
本郷久美子
第7版まえがき
独創性と情報化の時代の看護過程
アインシュタインはかつて,「今日,私たちが直面する重要な問題は,その問題をつくったときと同じ考えのレベルで解決することはできない」と述べている。今日の医療では,必然的に目まぐるしい変化が生じており,新しい考え方が求められている。本書は20年以上にわたり,この変化の時代にあって看護過程を学ぶための書として,学生・教員・看護師に支持されて続けてきた(過去にはシグマ・シータ・タウ最優秀図書賞を受賞)。
この版で,さらに新しい情報やツールを取り入れて,読者が看護過程を用いて“看護師らしく考える”ことを支援でき,とてもうれしく思っている。
情報化の時代に入ってから,エビデンスに基づく実践が要請されるようになっている。そうしたなか,看護過程の確固たる基礎を“頭のなかに入れておく”ことの理由は3つある。
1.米国看護師協会(ANA)の実践基準は,看護過程の位置づけについて,事実上あらゆるケアモデルの基礎であり,意思決定の基盤となり,十分な看護ケアを提供するためのクリティカルシンキングのモデルを提供するものとして強調されている1)。クリティカルシンキングのツールとしてはほかに有用なものもあるが,最初に看護過程を学んでおくことで,看護の基準を守り,ほかのモデルを学習するための基礎をつくることができる。
2.看護師資格試験(NCLEX)や,そのほかのほとんどの資格試験が,看護過程を基礎においている。基本的なルールと原則を知らなければ,これらの試験を自分で考えて解くことはできない。
3.電子カルテによる記録や意思決定支援システムなどが,“あなたのために多くを考えてくれる”ことが標準的になってきた。とはいえ看護師は,看護過程に基づいた思考のスキルをいっそう高め,ベッドサイドで意思決定を行い,“コンピュータとともに考える”ようにしなければならない。コンピュータは重要なツールで,クリティカルシンキングの能力を高めてくれる。しかし,あなたの代わりに考えてくれるわけではない。自分自身で自立してさまざまな思考を行うことで,入力したデータが事実で,漏れがないかを確認しなければならない。コンピュータにデータを入力するときは,どの情報がどの状況にあてはまるのかの判断が必要である。さらに,コンピュータは入力したデータが正しいという前提で処理するため,コンピュータからモニターに出力されるあらゆるデータの正確性を“第一線で守り抜く”のは自分自身ということになる。クリティカルシンキングや看護過程を学ばずに電子カルテやスタンダードケアプランを使うことは,四則演算を学ばずに電卓を使うようなものである。この場合,あなた自身が“壊れた電卓”であるといってもよいだろう。つまり,思考中心ではなく業務中心でケアを行うことで,それは“壊れたケア”となる。このような背景を理解していないと,ケアのアプローチを安全で効果的に個別化することができない。それは,患者にリスクをもたらし,あなた自身を法的な危険にさらすことになる。最後に,もう1つの問題がある。もしコンピュータがダウンしてしまったら,どうする? これは必ず起きることである。
読者対象
本書は,次のような読者のニーズを満たすことができるだろう。
1.クリティカルシンキングのツールとして看護過程を活用する方法を,米国看護師協会(ANA)の基準に沿ってアップデートしたい。
2.米国看護師資格認定センター(ANCC)から“マグネット・ホスピタル”として認定された,魅力的で質の高い病院で働くことを目指す読者。この場合,看護過程の各段階について熟知しておかなければならない2)。
3.クリティカルシンキングと看護過程の関係について,施設の全員で“共通理解”を得ようと考えている指導者。
4.学生。
・臨床の場面で十分な自信と能力を発揮したい。
・指導者にクリティカルシンキングを示したい。
・看護師資格試験(NCLEX)を解くための考え方を知りたい。
第7版の新しい内容
この版では,次のような新しい情報を掲載している。
+ 医学診断や看護診断,エラーの予防,早期警戒システム,指示系統を動かすことなどに対して増大する看護師の責任。
+ クリティカルシンキングを促す看護過程の特徴(クリティカルシンキングのツールとして看護過程をどのように活用するか)。
+ 思考の優先順位をどうつけるか,患者の重要な問題を早期に発見・予防するために迅速優先アセスメントをどう行うか。
+ 安全を優先する文化をどのようにはぐくむか。米国医学研究所(IOM)の示すコア・コンピテンシーは,安全で効果的な看護を実現させる能力とどのような関係があるか。
+ 看護過程の各段階に対応した,エビデンスに基づくクリティカルシンキングの指標(クリティカルシンキングを促す具体的な行動)。
+ ケアの調整と依頼について,看護師が担う役割。
+ “読み返し”と“繰り返し”の方法を用いて,能動的な(受動的でない)コミュニケーションを行うことの重要性。
+ 申し送りを改善するために,“SBARアプローチ”のような構造化されたツールをどう活用するか。
+ 看護過程の各段階に対応して,看護師資格試験(NCLEX)でどのような出題が想定されるか。
+ “治療・診断”から“予測・予防・管理・促進”に向かう考え方の変化。目下の健康問題を治療するだけでなく,先を見越し,危険因子の発見に焦点を絞り,典型的な健康問題をスクリーニングし,潜在的な合併症を予測するために,看護師に何が求められているか。
+ 関係性を判断し,より深く問題を理解するためにマップや図をどう活用するか。
+ 4つの円からなるクリティカルシンキングモデル(46ページ)をどのように活用してクリティカルシンキングの能力を高めるか。
+ 健全な職場環境や学習環境の必要性について。行動規範や患者・組織へのかかわり方も含む。
+ 本書全体にわたっての,さまざまな新しいルールやツールや戦略。
+ 協働的な実践,パートナーシップの促進,意思決定の共有,看護師のウェルネスなどの必要性。
+ 記録に関する詳細な情報。コンピュータや意思決定支援システムや情報科学による,ケアの管理と研究の促進について。
+ クリティカルシンキングの能力を高めるうえで,実際の経験や模擬的な経験が与える影響。
+ “事前に考え,実践しながら考え,事後に考える(振り返り)”ことの重要性。
新しい教材と学習ツール
+ 学習用のプリント,プレゼンテーション用の資料,単元ごとのシラバスが,Word形式でhttp://www.thePoint.lww.comからダウンロードできる(情報は英語のみ)。教材には,各章の主な見出し,学習の到達目標成果,本書に掲載したURLのリンクを掲載している。
+ さらにハンドアウトやツールをwww.AlfaroTeachSmart.comからダウンロードできる(情報は英語のみ)。これらのツールは個人利用であれば無料で使用してよい。
+ 新しいマップや“脳にはたらきかける学習”の原則(脳を学習モードに切り替える戦略)を活用しており,より学習がしやすくなっている。
第7版に引き継がれた内容
現在の基準に基づいた合理的なアプローチを示すように心がけ,いずれの章の内容も『看護の範囲と業務規準および臨床実践の基準』に準拠している3)。
さらに,次のような点を引き継いでいる。
+ さまざまな実例によって内容を関連づけ,理解しやすくしている。明快な内容で読者の興味を引くユーザーフレンドリーな書籍を目指している。
+ クリティカルシンキングのツールとして看護過程を活用するための方法を,おおまかな全体像で示している(付録F)。
+ 医学的な診断や治療や検査に関連した,一般的な合併症のリストを提示している(付録G・H)。
+ NANDA-I,NIC,NOCなどの標準的な看護用語の活用や誤用について,実践的な情報を掲載している。
+ そのほかに次のような内容も取り入れている。
・家庭や地域,多職種による実践における看護師の役割。
・倫理的・法的・文化的・スピリチュアルなかかわり。
・看護師が診断を行うことの役割とケースマネジャーとしての役割が,どのように高まってきているか。
・クリニカルパスウェイとクリティカルシンキングを高めるためのスタンダードケアプランをどのように活用するか。
・コミュニケーションスキルや対人スキルや技術的スキルの重要性。
本書の活用方法
制作にあたっては,ユーザーフレンドリーで,どこでも気軽に読めるような本にするために尽力した。次のような要素が,クリティカルシンキングを高め,動機づけを促し,思考を整理するために役立つはずである。
1.各章の最初に「学習の到達目標」として,講義のレベルで到達すべき目標を分析的にあげている。
2.章の最初に「この章のポイント」をまとめている。
3.重要な用語は「用語解説」で巻末にまとめ,より難解な用語などは本文中に脚注で定義,進行中の議論,使用される文脈などを説明している。
4.本文の説明の関係性や意味を明らかにするため,図を活用している。
5.情報を明確にし,重要な内容を説明するため,比喩や実例や症例を多用している。
6.図によって論理的根拠を強調し,必要に応じて本文の関連する他の部分との統合をはかっている。
7.全体を通して分析的な問いかけを行っている。 ・好奇心を刺激するような内容をもとに何が重要なのかのヒントを提供している。
・「クリティカルシンキングの練習問題」を,キーポイントの強調やテストの機会として活用することができ,知識の定着に役立つ。
8.内容を構造的に示しつつ,より創造的で自由に使うこともできるよう心がけている。
9.とくに他者からの評価を気にせずできる練習問題として,「自習コーナー」を設けている。
10.章の最後に「重要項目のまとめ」として,内容を要約している。
さらに前の版と同様,次の項目を盛り込んでいる。
+ 「考えてみよう」では,各自の思考を刺激し,内容の理解を高める題材を紹介している。
+ 「エキスパートからのアドバイス」では,主に看護師の感動的な実践や模範となる実践を引用して紹介している。
+ 「HMO(Help Me Out)」は,内容をユーモラスに強調した挿絵である(Help me out!には,何とかして!といった意味がある)。この挿絵は,実際にあったエピソードに基づいて描かれている。題材になりそうな経験があれば,著者まで連絡を(www.AlfaroTeachSmart.com)。
+ 「クリティカルシンキングの練習問題」は,すべての章に設けている。解答例は巻末の298~306ページに示している。
+ 「自習コーナー」は,より深く内容をあてはめて,意義のある学びを促すための設問である。この問題は,解答例を示していない。それぞれに個別化されるものであり,しかもきわめて長大な内容になるのがその理由である。
“患者/クライエント”,“彼/彼女”,利害関係者の用語について
本書では,“患者”や“クライエント”という用語ではなく,できるだけ“ある人”“その人”“利用者”“個人”といった用語を用いている。それぞれの患者またはクライエントは,固有のニーズ・価値観・知覚・動機をもった個人であるという考えに基づくものである。また,“利害関係者”という用語は,ケアの提供と成果の達成に関わるあらゆる人々のことをさしている(例:患者,家族,ケア提供者,保険会社)。
コメントや提案のお願い
今後も改善を重ねていくために,読者からの提案を歓迎する。重要な内容の改訂の多くが,学生や教員からの提案に基づいている。
Rosalinda Alfaro-LeFevre, RN, MSN, ANEF
www.AlfaroTeachSmart.com
文献
1. American Nurses Association. (2004). Nursing scope and standards of performance and standards of clinical practice. Washington, DC : American Nurses Publishing.
2. American Nurses Credentialing Center. (2005). ANCC Magnet Program-Recognizing excellence in nursing services. Silver Spring, MD : Author.
3. American Nurses Association. Op. cit.
目次
開く
著者
献辞
助言・意見をいただいた方々
謝辞
第7版訳者まえがき
初版訳者まえがき
第7版まえがき
初版まえがき
1 看護過程の概要
看護過程とは何か,なぜ看護過程を学ぶのか
看護過程の各段階
看護過程の各段階の相互関係
看護過程を用いることの利点
今日の臨床現場における看護過程
患者の安全が最優先事項
倫理:患者の権利の擁護
法律の規定に従い患者のパートナーを引き入れる
クリティカルシンキングの練習問題1
看護過程とクリティカルシンキングの違い
ケアしようとする意思とケアできる能力
クリティカルシンキングの練習問題2
重要項目のまとめ
2 アセスメント
アセスメント:健康状態を判断する第一段階
データの収集
データベースアセスメント,フォーカスアセスメント,迅速優先アセスメント
疾患と障害の管理に対するアセスメント
ヘルスプロモーション:リスクマネジメントと早期診断のためのスクリーニング
面接とフィジカルアセスメント
面接技術を高める
ガイドライン:配慮のある上手な面接の進め方
フィジカルアセスメントの技術を高める
ガイドライン:フィジカルアセスメントの実施
クリティカルシンキングの練習問題3
主観的データと客観的データの特定
キューの特定と推論
データの確認
ガイドライン:データの確認
クリティカルシンキングの練習問題4
関連するデータのクラスタリング
クリティカルシンキングの練習問題5
パターンの特定 / 第一印象の検証
データの報告と記録
ガイドライン:報告と記録
クリティカルシンキングの練習問題6
重要項目のまとめ
3 診断
アセスメントから診断へ:看護過程の中心
診断:米国看護師協会(ANA)の実践基準
看護師が診断を行うことの責任
診断・治療モデルと予測・予防・管理・増進モデル
多職種による実践
疾患と障害の管理
患者のそばで行う臨床検査
クリティカルパスウェイ(ケアマップ)
情報科学とコンピュータによる診断
診断能力を身につける
診断に関連するキーワード
危険因子を見極める:先を見越したアプローチ
診断に関連したクリティカルシンキングの指標
クリティカルシンキングの練習問題7
確定診断の方法を学ぶ
診断推論の基本原則とルール
診断のパートナーとしての患者
原因と寄与因子(危険因子)の特定
看護診断の特定
ガイドライン:看護診断の特定
看護診断のマッピング
PES 方式(PRS 方式)を使った診断文の作成
クリティカルシンキングの練習問題8
潜在的合併症の特定
ガイドライン:潜在的合併症の特定
多職種によるアプローチが必要な問題の特定
クリティカルシンキングの練習問題9
重要項目のまとめ
4 計画
計画の立案におけるクリティカルシンキング
ケアプランの4 つの主な目的
初期計画と継続計画
基準の適用
電子カルテによるスタンダードケアプラン
緊急時の優先順位の設定
期待される成果(結果)の明確化
患者中心の成果の原則
ガイドライン:患者中心の成果の判断
成果と説明責任の関係
臨床的成果,機能的成果,QOL の成果
退院時成果と退院計画
ケースマネジメント
記録すべき問題の決定
クリティカルシンキングの練習問題10
看護介入の決定
アセスメント:健康状態とケアへの反応に対するモニタリング
患者教育:患者と家族のエンパワメント
ガイドライン:教育計画
カウンセリングとコーチング:十分な情報を得たうえでの選択を支援する
相談・連絡:多職種によるケアを実現するために
看護介入の個別化
エビデンスに基づく実践:リスクと利益の兼ね合い,先を見越す
ガイドライン:看護指示の個別化
計画が適切に記録されていることの確認
多職種によるケアプラン
クリティカルシンキングの練習問題11
重要項目のまとめ
5 実施
実施:計画を実行に移す
実施に関連したクリティカルシンキングの指標
申し送りを受ける準備と受け方
1日ごとの優先順位の設定
ケアを依頼しても説明責任を果たす
ケアの調整
反応のモニタリング:アセスメントと再アセスメント
看護介入の実施
実施とエビデンスに基づく実践
ガイドライン:実施の準備
クリティカルシンキング:期待される成果が得られない場合
ケースマネジメント:クリティカルパスとケアバリアンス
倫理的・法的な注意
クリティカルシンキングの練習問題12
記録
効果的な記録を身につける
ガイドライン:実施の段階における記録
クリティカルシンキングの練習問題13
申し送りの方法
ガイドライン:申し送りの方法
計画の更新と1 日の評価
重要項目のまとめ
6 評価
クリティカルな評価:質の高い看護の鍵
評価とそれ以外の段階
個別のケアプランの評価
ガイドライン:成果の達成度の判定
成果の達成度に影響を及ぼす変数(因子)の特定
患者を退院させるかどうかの決定
クリティカルシンキングの練習問題14
質の向上(QI)
誤りと感染を防ぐ
クリティカルシンキングの練習問題15
重要項目のまとめ
クリティカルシンキングの練習問題解答例
付録
付録A 上級実践看護師(APN)の4つの職種
付録B デッド・オン! クリティカルシンキングを促すゲーム
付録C よく使われるNANDA-I 看護診断
付録D 良好な学習環境,健全な職場の規準,安全を優先する文化の確立
付録E 看護介入分類(NIC)と看護成果分類(NOC)の例
付録F 看護過程:クリティカルシンキングのツール
付録G 治療や侵襲的処置に関連した一般的な合併症
付録H 一般的な医学診断とその潜在的合併症
用語解説
索引
献辞
助言・意見をいただいた方々
謝辞
第7版訳者まえがき
初版訳者まえがき
第7版まえがき
初版まえがき
1 看護過程の概要
看護過程とは何か,なぜ看護過程を学ぶのか
看護過程の各段階
看護過程の各段階の相互関係
看護過程を用いることの利点
今日の臨床現場における看護過程
患者の安全が最優先事項
倫理:患者の権利の擁護
法律の規定に従い患者のパートナーを引き入れる
クリティカルシンキングの練習問題1
看護過程とクリティカルシンキングの違い
ケアしようとする意思とケアできる能力
クリティカルシンキングの練習問題2
重要項目のまとめ
2 アセスメント
アセスメント:健康状態を判断する第一段階
データの収集
データベースアセスメント,フォーカスアセスメント,迅速優先アセスメント
疾患と障害の管理に対するアセスメント
ヘルスプロモーション:リスクマネジメントと早期診断のためのスクリーニング
面接とフィジカルアセスメント
面接技術を高める
ガイドライン:配慮のある上手な面接の進め方
フィジカルアセスメントの技術を高める
ガイドライン:フィジカルアセスメントの実施
クリティカルシンキングの練習問題3
主観的データと客観的データの特定
キューの特定と推論
データの確認
ガイドライン:データの確認
クリティカルシンキングの練習問題4
関連するデータのクラスタリング
クリティカルシンキングの練習問題5
パターンの特定 / 第一印象の検証
データの報告と記録
ガイドライン:報告と記録
クリティカルシンキングの練習問題6
重要項目のまとめ
3 診断
アセスメントから診断へ:看護過程の中心
診断:米国看護師協会(ANA)の実践基準
看護師が診断を行うことの責任
診断・治療モデルと予測・予防・管理・増進モデル
多職種による実践
疾患と障害の管理
患者のそばで行う臨床検査
クリティカルパスウェイ(ケアマップ)
情報科学とコンピュータによる診断
診断能力を身につける
診断に関連するキーワード
危険因子を見極める:先を見越したアプローチ
診断に関連したクリティカルシンキングの指標
クリティカルシンキングの練習問題7
確定診断の方法を学ぶ
診断推論の基本原則とルール
診断のパートナーとしての患者
原因と寄与因子(危険因子)の特定
看護診断の特定
ガイドライン:看護診断の特定
看護診断のマッピング
PES 方式(PRS 方式)を使った診断文の作成
クリティカルシンキングの練習問題8
潜在的合併症の特定
ガイドライン:潜在的合併症の特定
多職種によるアプローチが必要な問題の特定
クリティカルシンキングの練習問題9
重要項目のまとめ
4 計画
計画の立案におけるクリティカルシンキング
ケアプランの4 つの主な目的
初期計画と継続計画
基準の適用
電子カルテによるスタンダードケアプラン
緊急時の優先順位の設定
期待される成果(結果)の明確化
患者中心の成果の原則
ガイドライン:患者中心の成果の判断
成果と説明責任の関係
臨床的成果,機能的成果,QOL の成果
退院時成果と退院計画
ケースマネジメント
記録すべき問題の決定
クリティカルシンキングの練習問題10
看護介入の決定
アセスメント:健康状態とケアへの反応に対するモニタリング
患者教育:患者と家族のエンパワメント
ガイドライン:教育計画
カウンセリングとコーチング:十分な情報を得たうえでの選択を支援する
相談・連絡:多職種によるケアを実現するために
看護介入の個別化
エビデンスに基づく実践:リスクと利益の兼ね合い,先を見越す
ガイドライン:看護指示の個別化
計画が適切に記録されていることの確認
多職種によるケアプラン
クリティカルシンキングの練習問題11
重要項目のまとめ
5 実施
実施:計画を実行に移す
実施に関連したクリティカルシンキングの指標
申し送りを受ける準備と受け方
1日ごとの優先順位の設定
ケアを依頼しても説明責任を果たす
ケアの調整
反応のモニタリング:アセスメントと再アセスメント
看護介入の実施
実施とエビデンスに基づく実践
ガイドライン:実施の準備
クリティカルシンキング:期待される成果が得られない場合
ケースマネジメント:クリティカルパスとケアバリアンス
倫理的・法的な注意
クリティカルシンキングの練習問題12
記録
効果的な記録を身につける
ガイドライン:実施の段階における記録
クリティカルシンキングの練習問題13
申し送りの方法
ガイドライン:申し送りの方法
計画の更新と1 日の評価
重要項目のまとめ
6 評価
クリティカルな評価:質の高い看護の鍵
評価とそれ以外の段階
個別のケアプランの評価
ガイドライン:成果の達成度の判定
成果の達成度に影響を及ぼす変数(因子)の特定
患者を退院させるかどうかの決定
クリティカルシンキングの練習問題14
質の向上(QI)
誤りと感染を防ぐ
クリティカルシンキングの練習問題15
重要項目のまとめ
クリティカルシンキングの練習問題解答例
付録
付録A 上級実践看護師(APN)の4つの職種
付録B デッド・オン! クリティカルシンキングを促すゲーム
付録C よく使われるNANDA-I 看護診断
付録D 良好な学習環境,健全な職場の規準,安全を優先する文化の確立
付録E 看護介入分類(NIC)と看護成果分類(NOC)の例
付録F 看護過程:クリティカルシンキングのツール
付録G 治療や侵襲的処置に関連した一般的な合併症
付録H 一般的な医学診断とその潜在的合併症
用語解説
索引
書評
開く
ハテナを自らチェックし「考えていくシナプス」を育てる
書評者: 久保 真知子 (市立小樽病院高等看護学院 教務主幹)
◆教科書選定の考え方
当校では次年度の教科書を選定するに当たり次のことを重要点と考えている。(1)学校のシラバスに合致している,(2)講師にも使いやすい,(3)在学中だけでなく卒業後も数年間は使用できる内容を含む,(4)カリキュラムでは直接触れないがぜひ学生に持たせたい本。(1)(2)は当然のこと,(3)は就業先のさまざまな理念や看護方式に対応できるように,(4)は学校の教育理念に合致する看護観や哲学的内容を含む副読本などがある。当校は授業料などの学校経費が比較的安いので,学生のうちにいい本を多く持たせたいと考えている。
◆考えて行動する看護師を育てる
3年間の限られた看護教育課程の中で,学生に精選して教えることは何なのか,多くの教員が悩むところだ。ともすれば詰め込みになったり,型を教えることで精一杯と感じたり,ジレンマを抱えている学校や教員も多いのではないか。特に看護学校における看護過程は,単に看護のツールでなく,看護の本質をどのように学生に伝えるかという学校の教育理念を反映する重要な科目である。
2012年に第7版を重ねた本書は,看護過程の考え方を基本からわかりやすく説明し,電子カルテやクリティカルパスなど時代の変化に対応してきている。特に今回の改訂ではクリティカルシンキングの考え方を取り入れ,「看護とは何をすればよいのか」から「何をどのようにするとよいのかを考えていく」ことに重点が置かれている。看護過程を初めて学習する看護学生には,翻訳本であることや看護診断の考え方も登場するのでちょっと難しいと思うかもしれない。当校の看護過程の授業では,事例を使って具体的に看護過程を展開させる演習に多くの時間を割きながら,本書ともう1冊の教科書を使っている。看護診断については紹介のみにとどめ,深い内容の授業はしていない。
学生は授業で学んだ知識をもとに,2年次前期に初めての看護過程を展開する臨地実習に入る。看護の現場では,慣れない環境の中,事例の"Aさん"とは違った刻々と変化する現実の対象者に触れ,学生の頭の中はハテナでいっぱいになる。学内の授業と現実の世界を埋めていくのは学生の「知りたい」という気持ちとそこから「考えていく力」だ。頭の中がハテナでいっぱいになったら,本書の「ルール」や「box」をぜひ見てほしい。今まで教員が実習指導で学生に伝えていた重要な言葉が,学生自らがチェックできる形で載っている。それを道標に自分の態度や行動を見直すことができる。指導してもらって当たり前ではなく,自ら事に当たり,考える力を身につけ「考えていくシナプス」を伸ばしていってほしい。
◆個別性のある看護のために卒業してからも使える
当校では看護過程を特定の看護理論家に限定せずにゴードンの11パターンを使って教えている。卒業生はさまざまな病院や施設に就職する。就業先では,学生時代の実習施設とは違った看護方式や記録方法を用いているところもあるだろう。就職して初めて看護診断を使うことになっても,本書に触れていれば比較的容易に移行できると考える。
電子カルテが主流となり,看護診断やクリティカルパスが多くの施設で導入され,看護の効率化や経済性が重要視される時代である。そのような中にあっても看護の対象が人間である限り,看護は最終的には対象者の望む健康や安寧をめざすものであるはずだ。卒業後,学生時代に学んだことを思い出しながら,もう一度本書を開けば,著者の言う"ワンサイズの服はだれにでもあうわけではない""常に患者の個別のニーズを明らかにする"という看護の原点に戻ることができる。
クリティカルシンキングを導く看護過程の指南書 (雑誌『看護教育』より)
書評者: 本田 育美 (京都大学大学院医学研究科)
慢性疾患が増加し,在院日数の短縮化が進む近年,患者の療養生活を支援していくうえで看護職が担う専門的役割はいっそう重要になっている。さらに,多職種の協働的なアプローチによる医療が推奨され,看護師も専門職の一員として,さまざまな場面で“看護の視点からの判断提示”が求められるようになってきた。その一方で,多くの医療施設で電子カルテの導入が進み,コンピュータ内に標準化された診断名や看護計画などが取り込まれたため,十分な思考を経ずにカルテを作成できてしまう現状もある。看護師が専門職として自律的に思考し,正確な推論や診断を導くことが,ますます重要な時代になったといえるだろう。
本書は,四半世紀にわたってすべての看護師に向けて,“看護過程”という看護の視点を導くためのプロセスを,明確かつ簡潔に示してきたテキストである。改訂を重ねるたびに,看護師の臨床推論や診断的判断のスキルを高めることにも力点が置かれるようになり,前版に引き続き第7版でも,クリティカルシンキングを強化させるための工夫が数多く盛り込まれている。各章に設けられた「練習問題」をはじめ,本文中に散りばめられた「ルール」や「エキスパートからのアドバイス」といったtipsは,学生から現場の看護師まで,あらゆる読者のクリティカルシンキングを大いに刺激することだろう。
また,今回の改訂で印象深いのは,看護過程のアセスメントの段階で“迅速優先アセスメント”という項目が加えられたことである。これまでの看護過程では,情報を網羅的に集め,それらを徹底的に検討するよう教えられることが多かったと思われる。しかし,実際の臨床現場では,その場の状況を正確につかみ,的確な予測のもと優先性を見極め,速やかな行動につなぐことがしばしば要求される。こうした側面に対応するのが,“迅速優先アセスメント”であり,現在多くの研究者が注目しているテーマでもある。
第7版になっても,看護過程に関する基本的な考え方や説明の道筋などは,これまでと何ら変わっていない。そして,学習者に対する筆者のまなざしも変わらずあたたかなままである。しかし,専門職として確かな臨床判断と確実なケア提供が求められる時代になった今日,クリティカルシンキングを促すツールとして,看護過程の重要性は高まる一方である。本書はまさに,看護が直面する課題解決に向けた能力を育成するための指南書といえるだろう。
(『看護教育』2013年6月号掲載)
書評者: 久保 真知子 (市立小樽病院高等看護学院 教務主幹)
◆教科書選定の考え方
当校では次年度の教科書を選定するに当たり次のことを重要点と考えている。(1)学校のシラバスに合致している,(2)講師にも使いやすい,(3)在学中だけでなく卒業後も数年間は使用できる内容を含む,(4)カリキュラムでは直接触れないがぜひ学生に持たせたい本。(1)(2)は当然のこと,(3)は就業先のさまざまな理念や看護方式に対応できるように,(4)は学校の教育理念に合致する看護観や哲学的内容を含む副読本などがある。当校は授業料などの学校経費が比較的安いので,学生のうちにいい本を多く持たせたいと考えている。
◆考えて行動する看護師を育てる
3年間の限られた看護教育課程の中で,学生に精選して教えることは何なのか,多くの教員が悩むところだ。ともすれば詰め込みになったり,型を教えることで精一杯と感じたり,ジレンマを抱えている学校や教員も多いのではないか。特に看護学校における看護過程は,単に看護のツールでなく,看護の本質をどのように学生に伝えるかという学校の教育理念を反映する重要な科目である。
2012年に第7版を重ねた本書は,看護過程の考え方を基本からわかりやすく説明し,電子カルテやクリティカルパスなど時代の変化に対応してきている。特に今回の改訂ではクリティカルシンキングの考え方を取り入れ,「看護とは何をすればよいのか」から「何をどのようにするとよいのかを考えていく」ことに重点が置かれている。看護過程を初めて学習する看護学生には,翻訳本であることや看護診断の考え方も登場するのでちょっと難しいと思うかもしれない。当校の看護過程の授業では,事例を使って具体的に看護過程を展開させる演習に多くの時間を割きながら,本書ともう1冊の教科書を使っている。看護診断については紹介のみにとどめ,深い内容の授業はしていない。
学生は授業で学んだ知識をもとに,2年次前期に初めての看護過程を展開する臨地実習に入る。看護の現場では,慣れない環境の中,事例の"Aさん"とは違った刻々と変化する現実の対象者に触れ,学生の頭の中はハテナでいっぱいになる。学内の授業と現実の世界を埋めていくのは学生の「知りたい」という気持ちとそこから「考えていく力」だ。頭の中がハテナでいっぱいになったら,本書の「ルール」や「box」をぜひ見てほしい。今まで教員が実習指導で学生に伝えていた重要な言葉が,学生自らがチェックできる形で載っている。それを道標に自分の態度や行動を見直すことができる。指導してもらって当たり前ではなく,自ら事に当たり,考える力を身につけ「考えていくシナプス」を伸ばしていってほしい。
◆個別性のある看護のために卒業してからも使える
当校では看護過程を特定の看護理論家に限定せずにゴードンの11パターンを使って教えている。卒業生はさまざまな病院や施設に就職する。就業先では,学生時代の実習施設とは違った看護方式や記録方法を用いているところもあるだろう。就職して初めて看護診断を使うことになっても,本書に触れていれば比較的容易に移行できると考える。
電子カルテが主流となり,看護診断やクリティカルパスが多くの施設で導入され,看護の効率化や経済性が重要視される時代である。そのような中にあっても看護の対象が人間である限り,看護は最終的には対象者の望む健康や安寧をめざすものであるはずだ。卒業後,学生時代に学んだことを思い出しながら,もう一度本書を開けば,著者の言う"ワンサイズの服はだれにでもあうわけではない""常に患者の個別のニーズを明らかにする"という看護の原点に戻ることができる。
クリティカルシンキングを導く看護過程の指南書 (雑誌『看護教育』より)
書評者: 本田 育美 (京都大学大学院医学研究科)
慢性疾患が増加し,在院日数の短縮化が進む近年,患者の療養生活を支援していくうえで看護職が担う専門的役割はいっそう重要になっている。さらに,多職種の協働的なアプローチによる医療が推奨され,看護師も専門職の一員として,さまざまな場面で“看護の視点からの判断提示”が求められるようになってきた。その一方で,多くの医療施設で電子カルテの導入が進み,コンピュータ内に標準化された診断名や看護計画などが取り込まれたため,十分な思考を経ずにカルテを作成できてしまう現状もある。看護師が専門職として自律的に思考し,正確な推論や診断を導くことが,ますます重要な時代になったといえるだろう。
本書は,四半世紀にわたってすべての看護師に向けて,“看護過程”という看護の視点を導くためのプロセスを,明確かつ簡潔に示してきたテキストである。改訂を重ねるたびに,看護師の臨床推論や診断的判断のスキルを高めることにも力点が置かれるようになり,前版に引き続き第7版でも,クリティカルシンキングを強化させるための工夫が数多く盛り込まれている。各章に設けられた「練習問題」をはじめ,本文中に散りばめられた「ルール」や「エキスパートからのアドバイス」といったtipsは,学生から現場の看護師まで,あらゆる読者のクリティカルシンキングを大いに刺激することだろう。
また,今回の改訂で印象深いのは,看護過程のアセスメントの段階で“迅速優先アセスメント”という項目が加えられたことである。これまでの看護過程では,情報を網羅的に集め,それらを徹底的に検討するよう教えられることが多かったと思われる。しかし,実際の臨床現場では,その場の状況を正確につかみ,的確な予測のもと優先性を見極め,速やかな行動につなぐことがしばしば要求される。こうした側面に対応するのが,“迅速優先アセスメント”であり,現在多くの研究者が注目しているテーマでもある。
第7版になっても,看護過程に関する基本的な考え方や説明の道筋などは,これまでと何ら変わっていない。そして,学習者に対する筆者のまなざしも変わらずあたたかなままである。しかし,専門職として確かな臨床判断と確実なケア提供が求められる時代になった今日,クリティカルシンキングを促すツールとして,看護過程の重要性は高まる一方である。本書はまさに,看護が直面する課題解決に向けた能力を育成するための指南書といえるだろう。
(『看護教育』2013年6月号掲載)