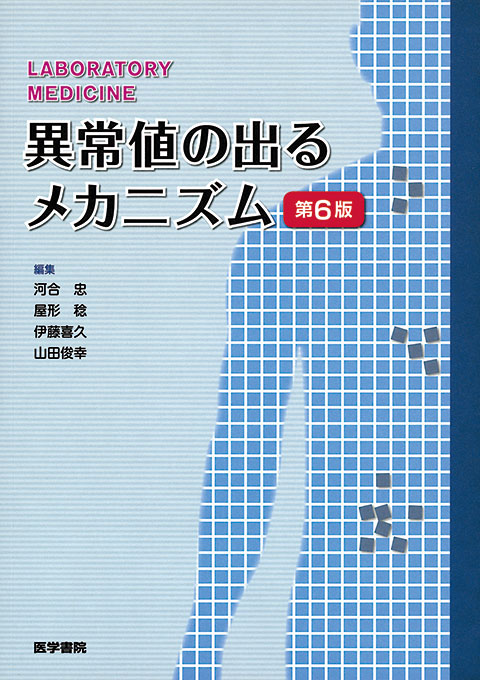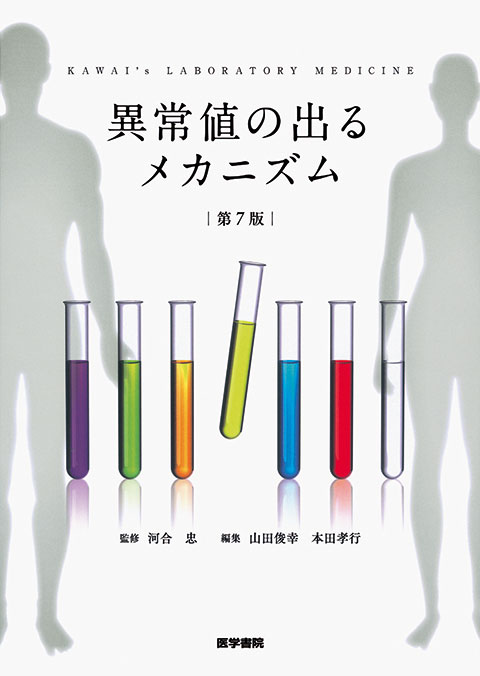異常値の出るメカニズム 第6版
検査で得られた医療情報から実像を捉え、その背景を考える能力を養う
もっと見る
日常診療で広く使われる検査項目を重点的に取り上げ、患者に負担の少ない臨床検査を重視、その検査結果を最大限に診療に生かす方策に到達するための、知識と考え方を提供する。網羅的で辞典的な本とは一線を画し、medicineを学ぶ医学生や研修医、生涯学習を続ける医療関係職が、デジタル情報に振り回されることなく、専門教育の初期段階から、“得られたさまざまな医療情報から実像を捉え、その背景を考える能力”を養う。
- 販売終了
更新情報
-
更新情報はありません。
お気に入り商品に追加すると、この商品の更新情報や関連情報などをマイページでお知らせいたします。
- 序文
- 目次
- 書評
- 正誤表
序文
開く
第6版 序
本書第1版を1985年に出版してから28年が経過し,その間版を重ねて今回第6版を発行することになった.幸い,本書は「異常メカ」の愛称で医学生諸君の間で愛用されてきたばかりでなく,臨床検査技師,看護師,保健師,薬剤師,管理栄養士など幅広い方々に親しまれ,貴重なご意見とご叱正を頂いてきた.このような長期にわたり発行を続けてこられたのは,ひとえに読者の温かいご支持の賜物であり,心からお礼申し上げたい.
初版の編者,執筆者は定年退職後すでに十数年を経過し,教育現場の第一線から引退し,医学教育環境も大きく変革していることから,第4版からは伊藤喜久,第6版からは山田俊幸が加わり,本書の構成や内容をより時代にマッチするよう努めた.手頃な重さで使いやすさを考慮し,本書の総量をできるだけ現状に維持するため,従来の内容の重複を整理し,しかも重要な内容を最新に改めるよう努めた.もちろん,初版から一貫して,日常診療の場で広く使われている検査項目を重点的に取り上げ,患者に負担の少ない臨床検査を重視し,その検査結果を最大限に診療に生かす方策に到達するための知識と考え方を提供することをモットーとしてきたが,今回もその基本方針は変わっていない.したがって,網羅的で辞典的な内容を踏襲する類書とは大きく異なっている.
近年の電子媒体による通信技術の進歩は目覚ましく,医学教育や医療現場においても,とかくデジタル化に突き進む傾向は否定できない.それはそれなりに医学・医療の近代化に大きく貢献しているが,medicine―日本語では“医学”と訳されているが,-ologyとは書かれていない―はあくまでもscienceとartの適切な融合で成り立っており,アナログ的かつ哲学的要素が現代でも大きな部分を占めている.とくにmedicineを学ぶ医学生や研修医ならびに生涯学習を続ける医療関係職にとっては,将来ともartの部分の修練を決して疎かにしてはならない.デジタル情報に振り回されることなく,専門教育の初期段階から“得られたさまざまな医療情報から実態を捉え,その背景を考える能力”を養うことが必要と考える.そうした読者の活動に本書がいささかでも役立つならば幸いである.
従来にも増して,多くの読者のご愛読とご叱正を頂きたい.
2013年1月
編者
本書第1版を1985年に出版してから28年が経過し,その間版を重ねて今回第6版を発行することになった.幸い,本書は「異常メカ」の愛称で医学生諸君の間で愛用されてきたばかりでなく,臨床検査技師,看護師,保健師,薬剤師,管理栄養士など幅広い方々に親しまれ,貴重なご意見とご叱正を頂いてきた.このような長期にわたり発行を続けてこられたのは,ひとえに読者の温かいご支持の賜物であり,心からお礼申し上げたい.
初版の編者,執筆者は定年退職後すでに十数年を経過し,教育現場の第一線から引退し,医学教育環境も大きく変革していることから,第4版からは伊藤喜久,第6版からは山田俊幸が加わり,本書の構成や内容をより時代にマッチするよう努めた.手頃な重さで使いやすさを考慮し,本書の総量をできるだけ現状に維持するため,従来の内容の重複を整理し,しかも重要な内容を最新に改めるよう努めた.もちろん,初版から一貫して,日常診療の場で広く使われている検査項目を重点的に取り上げ,患者に負担の少ない臨床検査を重視し,その検査結果を最大限に診療に生かす方策に到達するための知識と考え方を提供することをモットーとしてきたが,今回もその基本方針は変わっていない.したがって,網羅的で辞典的な内容を踏襲する類書とは大きく異なっている.
近年の電子媒体による通信技術の進歩は目覚ましく,医学教育や医療現場においても,とかくデジタル化に突き進む傾向は否定できない.それはそれなりに医学・医療の近代化に大きく貢献しているが,medicine―日本語では“医学”と訳されているが,-ologyとは書かれていない―はあくまでもscienceとartの適切な融合で成り立っており,アナログ的かつ哲学的要素が現代でも大きな部分を占めている.とくにmedicineを学ぶ医学生や研修医ならびに生涯学習を続ける医療関係職にとっては,将来ともartの部分の修練を決して疎かにしてはならない.デジタル情報に振り回されることなく,専門教育の初期段階から“得られたさまざまな医療情報から実態を捉え,その背景を考える能力”を養うことが必要と考える.そうした読者の活動に本書がいささかでも役立つならば幸いである.
従来にも増して,多くの読者のご愛読とご叱正を頂きたい.
2013年1月
編者
目次
開く
序論 検査値を正しく判断するために
A.生体情報(臨床検査)の特性-ホメオスターシスと揺らぎ
B.臨床検査の役割と検査計画
C.基準値の正しい考え方・使い方
D.検査部と登録衛生検査所-どこで検査が行われるか
E.検査依頼の仕方
1 尿・便・分泌液検査
A.尿の検査-総論
B.尿の観察
C.尿潜血と血尿
D.尿比重と尿浸透圧
E.尿pH(尿水素イオン濃度)
F.尿蛋白
G.ベンスジョーンズ蛋白
H.尿微量蛋白
I.尿糖(尿グルコース)
J.尿胆汁色素
K.尿ケトン体およびケトーシス
L.尿アミノ酸
M.細菌尿
N.尿沈渣(尿中有形成分測定を含む)
O.尿妊娠反応検査(尿排卵予知検査を含む)
P.糞便の検査-総論
Q.便潜血反応と糞便中ヘモグロビン
R.糞便脂肪
S.糞便の寄生虫・原虫
T.分泌液検査
2 穿刺液・髄液検査
A.穿刺液の検査
B.髄液検査
C.関節液検査
3 血液検査
A.血液の検査-総論
B.全血球数算定(CBC)
C.赤血球の一般検査
D.末梢血液像と赤血球形態
E.網赤血球と有核赤血球
F.白血球数と白血球分類
G.顆粒球数と機能検査
H.白血球の細胞化学的検査(特殊染色)
I.リンパ球数とリンパ球表面抗原
J.止血機構とスクリーニング
K.出血時間と血小板検査
L.全血凝固時間と血餅の観察
M.活性化部分トロンボプラスチン時間(APTT)とプロトロンビン時間(PT)
N.プロトロンビン時間(PT)
O.フィブリノゲン
P.循環抗凝血素
Q.血液凝固を制御する因子,凝固亢進状態を示すマーカー
R.フィブリン/フィブリノゲン分解産物(FDP)
S.溶血の検査-総論
T.赤血球浸透圧抵抗試験
U.赤血球酵素検査
V.赤沈検査
4 血清蛋白・含窒素化合物検査
A.含窒素化合物検査-総論
B.尿素窒素(または尿素)
C.クレアチン,クレアチニン
D.尿酸
E.アミノ酸
F.アンモニア
G.血清総蛋白と蛋白電気泳動
H.栄養アセスメント蛋白
I.シスタチンC
J.KL-6抗原
K.可溶性IL-2レセプター
L.血清ビリルビン
5 糖代謝検査
A.糖代謝とその異常
B.糖尿病の診断の進め方
C.血糖とブドウ糖負荷試験
D.インスリンとCペプチド
E.糖尿病モニター検査
6 血清脂質・アポリポ蛋白検査
A.脂質異常症の診断の進め方
B.リポ蛋白,アポリポ蛋白
C.総コレステロール
D.HDL-コレステロール
E.LDL-コレステロール
F.トリグリセリド(中性脂肪)とリポ蛋白リパーゼ(LPL)
7 血清電解質と血液ガス検査
A.水・電解質平衡と異常のメカニズム
B.カリウム(K)
C.酸塩基平衡と異常のメカニズム
D.動脈血酸素分圧(Pao2)
E.鉄とその他の鉄代謝マーカー
F.カルシウム(Ca)とカルシウムイオン
G.無機リン(P)
H.マグネシウム(Mg)
I.銅とセルロプラスミン
J.微量金属と医療行為
8 酵素検査
A.アミノトランスフェラーゼ(トランスアミナーゼ)(ASTとALT)
B.アルカリホスファターゼ(ALP)と骨代謝マーカー
C.γ-グルタミルトランスペプチダーゼ(γ-GT)
D.コリンエステラーゼ(ChE)
E.乳酸脱水素酵素(LD)
F.クレアチンキナーゼ(CK)と心筋マーカー
G.アミラーゼ(AMY)
H.リパーゼ
I.尿中N-アセチルグルコサミニダーゼ(NAG)
9 ホルモン検査
A.内分泌疾患の検査と異常のメカニズム
B.副腎皮質刺激ホルモン(ACTH),コルチゾール
C.甲状腺刺激ホルモン(TSH),甲状腺ホルモン(T3,T4)
D.黄体形成ホルモン(LH),卵胞刺激ホルモン(FSH)
E.成長ホルモン(GH),ソマトメジンC(IGF-I)
F.プロラクチン(PRL)
G.バソプレシン
H.甲状腺自己抗体
I.カルシウム調節ホルモン
J.レニン・アンジオテンシン・アルドステロン
K.アンドロゲン
L.エストロゲン,プロゲステロン
M.カテコラミン
N.膵消化管ホルモン
O.ナトリウム利尿ペプチド
P.セロトニン,5-HIAA
Q.[付表]測定可能なホルモンおよびホルモン関連物質
10 腫瘍マーカー検査
A.癌の臨床検査
B.腫瘍マーカーの基礎知識
C.腫瘍マーカーの臨床的性質
D.腫瘍マーカーの臨床的利用
E.主要な腫瘍マーカーの特性
11 免疫血清検査
A.炎症マーカーとCRP・SAA
B.免疫グロブリン(IgG,IgA,IgM)
C.IgEとIgE抗体
D.補体価と補体成分
E.自己抗体検査-総論
F.リウマトイド因子
G.抗シトルリン化抗体(抗CCP抗体)
H.マトリックスメタロプロテイナーゼ3(MMP-3)
I.抗核抗体とその成分
J.抗リン脂質抗体
K.抗赤血球抗体
L.寒冷凝集素と寒冷溶血素
M.臓器移植とHLA検査
12 感染症の検査
A.感染の成立と経過
B.感染症診断の進め方
C.病原体の確定診断
D.抗菌薬感受性試験と薬剤耐性
E.医療関連感染/院内感染(病院感染)
F.感染症の免疫血清診断
G.感染症の血清診断(抗体検査)
H.真菌感染症とそのマーカー
I.ウイルス感染症とそのマーカー
J.ウイルス肝炎
K.風疹(風しん)
L.後天性免疫不全症候群(AIDS)
M.成人T細胞性白血病/リンパ腫とHTLV-1感染症
13 遺伝学的検査
A.いわゆる“遺伝子検査”という言葉に注意
B.遺伝学的検査
C.細胞遺伝学的検査-染色体検査
D.分子遺伝学的検査
和文索引
欧文索引
A.生体情報(臨床検査)の特性-ホメオスターシスと揺らぎ
B.臨床検査の役割と検査計画
C.基準値の正しい考え方・使い方
D.検査部と登録衛生検査所-どこで検査が行われるか
E.検査依頼の仕方
1 尿・便・分泌液検査
A.尿の検査-総論
B.尿の観察
C.尿潜血と血尿
D.尿比重と尿浸透圧
E.尿pH(尿水素イオン濃度)
F.尿蛋白
G.ベンスジョーンズ蛋白
H.尿微量蛋白
I.尿糖(尿グルコース)
J.尿胆汁色素
K.尿ケトン体およびケトーシス
L.尿アミノ酸
M.細菌尿
N.尿沈渣(尿中有形成分測定を含む)
O.尿妊娠反応検査(尿排卵予知検査を含む)
P.糞便の検査-総論
Q.便潜血反応と糞便中ヘモグロビン
R.糞便脂肪
S.糞便の寄生虫・原虫
T.分泌液検査
2 穿刺液・髄液検査
A.穿刺液の検査
B.髄液検査
C.関節液検査
3 血液検査
A.血液の検査-総論
B.全血球数算定(CBC)
C.赤血球の一般検査
D.末梢血液像と赤血球形態
E.網赤血球と有核赤血球
F.白血球数と白血球分類
G.顆粒球数と機能検査
H.白血球の細胞化学的検査(特殊染色)
I.リンパ球数とリンパ球表面抗原
J.止血機構とスクリーニング
K.出血時間と血小板検査
L.全血凝固時間と血餅の観察
M.活性化部分トロンボプラスチン時間(APTT)とプロトロンビン時間(PT)
N.プロトロンビン時間(PT)
O.フィブリノゲン
P.循環抗凝血素
Q.血液凝固を制御する因子,凝固亢進状態を示すマーカー
R.フィブリン/フィブリノゲン分解産物(FDP)
S.溶血の検査-総論
T.赤血球浸透圧抵抗試験
U.赤血球酵素検査
V.赤沈検査
4 血清蛋白・含窒素化合物検査
A.含窒素化合物検査-総論
B.尿素窒素(または尿素)
C.クレアチン,クレアチニン
D.尿酸
E.アミノ酸
F.アンモニア
G.血清総蛋白と蛋白電気泳動
H.栄養アセスメント蛋白
I.シスタチンC
J.KL-6抗原
K.可溶性IL-2レセプター
L.血清ビリルビン
5 糖代謝検査
A.糖代謝とその異常
B.糖尿病の診断の進め方
C.血糖とブドウ糖負荷試験
D.インスリンとCペプチド
E.糖尿病モニター検査
6 血清脂質・アポリポ蛋白検査
A.脂質異常症の診断の進め方
B.リポ蛋白,アポリポ蛋白
C.総コレステロール
D.HDL-コレステロール
E.LDL-コレステロール
F.トリグリセリド(中性脂肪)とリポ蛋白リパーゼ(LPL)
7 血清電解質と血液ガス検査
A.水・電解質平衡と異常のメカニズム
B.カリウム(K)
C.酸塩基平衡と異常のメカニズム
D.動脈血酸素分圧(Pao2)
E.鉄とその他の鉄代謝マーカー
F.カルシウム(Ca)とカルシウムイオン
G.無機リン(P)
H.マグネシウム(Mg)
I.銅とセルロプラスミン
J.微量金属と医療行為
8 酵素検査
A.アミノトランスフェラーゼ(トランスアミナーゼ)(ASTとALT)
B.アルカリホスファターゼ(ALP)と骨代謝マーカー
C.γ-グルタミルトランスペプチダーゼ(γ-GT)
D.コリンエステラーゼ(ChE)
E.乳酸脱水素酵素(LD)
F.クレアチンキナーゼ(CK)と心筋マーカー
G.アミラーゼ(AMY)
H.リパーゼ
I.尿中N-アセチルグルコサミニダーゼ(NAG)
9 ホルモン検査
A.内分泌疾患の検査と異常のメカニズム
B.副腎皮質刺激ホルモン(ACTH),コルチゾール
C.甲状腺刺激ホルモン(TSH),甲状腺ホルモン(T3,T4)
D.黄体形成ホルモン(LH),卵胞刺激ホルモン(FSH)
E.成長ホルモン(GH),ソマトメジンC(IGF-I)
F.プロラクチン(PRL)
G.バソプレシン
H.甲状腺自己抗体
I.カルシウム調節ホルモン
J.レニン・アンジオテンシン・アルドステロン
K.アンドロゲン
L.エストロゲン,プロゲステロン
M.カテコラミン
N.膵消化管ホルモン
O.ナトリウム利尿ペプチド
P.セロトニン,5-HIAA
Q.[付表]測定可能なホルモンおよびホルモン関連物質
10 腫瘍マーカー検査
A.癌の臨床検査
B.腫瘍マーカーの基礎知識
C.腫瘍マーカーの臨床的性質
D.腫瘍マーカーの臨床的利用
E.主要な腫瘍マーカーの特性
11 免疫血清検査
A.炎症マーカーとCRP・SAA
B.免疫グロブリン(IgG,IgA,IgM)
C.IgEとIgE抗体
D.補体価と補体成分
E.自己抗体検査-総論
F.リウマトイド因子
G.抗シトルリン化抗体(抗CCP抗体)
H.マトリックスメタロプロテイナーゼ3(MMP-3)
I.抗核抗体とその成分
J.抗リン脂質抗体
K.抗赤血球抗体
L.寒冷凝集素と寒冷溶血素
M.臓器移植とHLA検査
12 感染症の検査
A.感染の成立と経過
B.感染症診断の進め方
C.病原体の確定診断
D.抗菌薬感受性試験と薬剤耐性
E.医療関連感染/院内感染(病院感染)
F.感染症の免疫血清診断
G.感染症の血清診断(抗体検査)
H.真菌感染症とそのマーカー
I.ウイルス感染症とそのマーカー
J.ウイルス肝炎
K.風疹(風しん)
L.後天性免疫不全症候群(AIDS)
M.成人T細胞性白血病/リンパ腫とHTLV-1感染症
13 遺伝学的検査
A.いわゆる“遺伝子検査”という言葉に注意
B.遺伝学的検査
C.細胞遺伝学的検査-染色体検査
D.分子遺伝学的検査
和文索引
欧文索引
書評
開く
ルーチン検査には本書の活用が欠かせない
書評者: 本田 孝行 (信州大教授・病態解析診断学)
“検査値を読んでみたい”という衝動に駆られたことはないだろうか。その知的好奇心を十二分に満たしてくれるのが,河合忠先生,他編集の『異常値の出るメカニズム 第6版』である。1985年に第1版が発売され第6版を迎えるので,超ロングセラーに間違いなく,医療従事者にとって検査値を読むためのバイブルといっても過言ではない。第5版から5年目の早い改訂であり,河合先生の意欲が感じられる。
ルーチン検査(基本的検査)は血算,生化学,凝固線溶および尿検査などを含んでおり,世界中で最も頻繁に行われている。臨床検査部では正確な検査結果を返そうと努力しているが,患者の診断,治療に必ずしも十分に活用されているとはいえない。最大の理由として,ルーチン検査を読む教育が十分でないことが挙げられる。AST,ALTが上昇すれば肝機能が悪い,UN,クレアチニンが上昇すれば腎機能が悪いなど,ごく表面的な浅い解釈に留まっており,患者の病態を深く追求できていない。結果として十分に活用されない検査が大量に行われており,医療費の無駄遣いともいえる。
ルーチン検査では,1つの検査で1つの病態を解釈することは不可能である。複数の検査を組み合わせその変動を検討することにより,詳細に患者の病態が捉えられる。まず,全身状態,そして各臓器の病態を把握していくので理学所見をとるのに似ている。ただ,複数の検査項目を結び付けて考察する必要があり,各検査の異常値の出るメカニズムを熟知していなければならない。
本書以外に,個々のルーチン検査の異常値の出るメカニズムについて詳細に解説している本を知らない。検査値を読みたい,すなわち,ルーチン検査を十分に活用したいならば,本書を活用するしかない。信州大学医学部病態解析診断学では,16年前から本書を教科書としてReversed Clinicopathological Conference(R-CPC)の授業を行っている。私はR-CPCを始めるころに本書に出会い,授業で本書の内容を学生に伝えられれば十分だと直感した。10回以上本書を精読した後,R-CPCの授業を始めたころを昨日のように思い出す。今でも,ルーチン検査でわからないことがあれば本書を開いている。
河合先生は,第6版の序文で“artの部分の修練”という言葉を使用されている。本書で検査値を読む修練を重ねることにより,検査に振り回されるのではなく,検査を道具として自由に操れるartistになれという意味だと勝手に理解させていただいた。遺伝子検査や腫瘍マーカー(カットオフ値があるのでデジタル検査と呼んでいる)は切れ味のよい検査であるが,患者の全身状態を捉えることはできない。ルーチン検査(アナログ検査と呼んでいる)は,直接診断につながらないが病態の変化が捉えられる。検査にはそれぞれ使い方がある。本書により各検査の異常値の出るメカニズムを十分に理解し,多くの検査のartistが誕生することを期待する。
書評者: 本田 孝行 (信州大教授・病態解析診断学)
“検査値を読んでみたい”という衝動に駆られたことはないだろうか。その知的好奇心を十二分に満たしてくれるのが,河合忠先生,他編集の『異常値の出るメカニズム 第6版』である。1985年に第1版が発売され第6版を迎えるので,超ロングセラーに間違いなく,医療従事者にとって検査値を読むためのバイブルといっても過言ではない。第5版から5年目の早い改訂であり,河合先生の意欲が感じられる。
ルーチン検査(基本的検査)は血算,生化学,凝固線溶および尿検査などを含んでおり,世界中で最も頻繁に行われている。臨床検査部では正確な検査結果を返そうと努力しているが,患者の診断,治療に必ずしも十分に活用されているとはいえない。最大の理由として,ルーチン検査を読む教育が十分でないことが挙げられる。AST,ALTが上昇すれば肝機能が悪い,UN,クレアチニンが上昇すれば腎機能が悪いなど,ごく表面的な浅い解釈に留まっており,患者の病態を深く追求できていない。結果として十分に活用されない検査が大量に行われており,医療費の無駄遣いともいえる。
ルーチン検査では,1つの検査で1つの病態を解釈することは不可能である。複数の検査を組み合わせその変動を検討することにより,詳細に患者の病態が捉えられる。まず,全身状態,そして各臓器の病態を把握していくので理学所見をとるのに似ている。ただ,複数の検査項目を結び付けて考察する必要があり,各検査の異常値の出るメカニズムを熟知していなければならない。
本書以外に,個々のルーチン検査の異常値の出るメカニズムについて詳細に解説している本を知らない。検査値を読みたい,すなわち,ルーチン検査を十分に活用したいならば,本書を活用するしかない。信州大学医学部病態解析診断学では,16年前から本書を教科書としてReversed Clinicopathological Conference(R-CPC)の授業を行っている。私はR-CPCを始めるころに本書に出会い,授業で本書の内容を学生に伝えられれば十分だと直感した。10回以上本書を精読した後,R-CPCの授業を始めたころを昨日のように思い出す。今でも,ルーチン検査でわからないことがあれば本書を開いている。
河合先生は,第6版の序文で“artの部分の修練”という言葉を使用されている。本書で検査値を読む修練を重ねることにより,検査に振り回されるのではなく,検査を道具として自由に操れるartistになれという意味だと勝手に理解させていただいた。遺伝子検査や腫瘍マーカー(カットオフ値があるのでデジタル検査と呼んでいる)は切れ味のよい検査であるが,患者の全身状態を捉えることはできない。ルーチン検査(アナログ検査と呼んでいる)は,直接診断につながらないが病態の変化が捉えられる。検査にはそれぞれ使い方がある。本書により各検査の異常値の出るメカニズムを十分に理解し,多くの検査のartistが誕生することを期待する。
正誤表
開く
本書の記述の正確性につきましては最善の努力を払っておりますが、この度弊社の責任におきまして、下記のような誤りがございました。お詫び申し上げますとともに訂正させていただきます。
更新情報
-
更新情報はありません。
お気に入り商品に追加すると、この商品の更新情報や関連情報などをマイページでお知らせいたします。