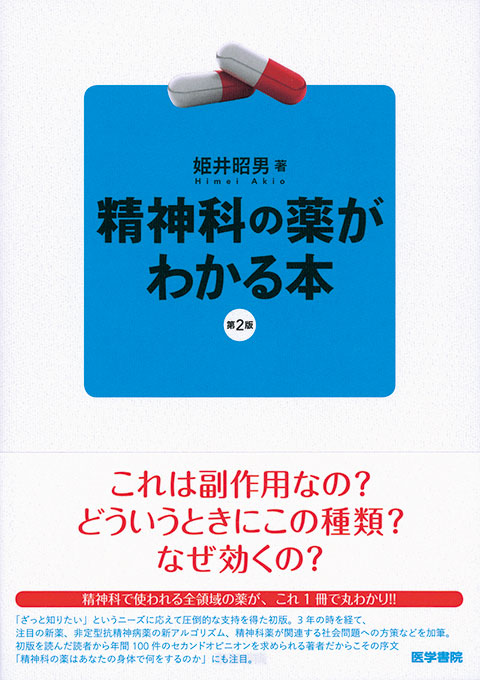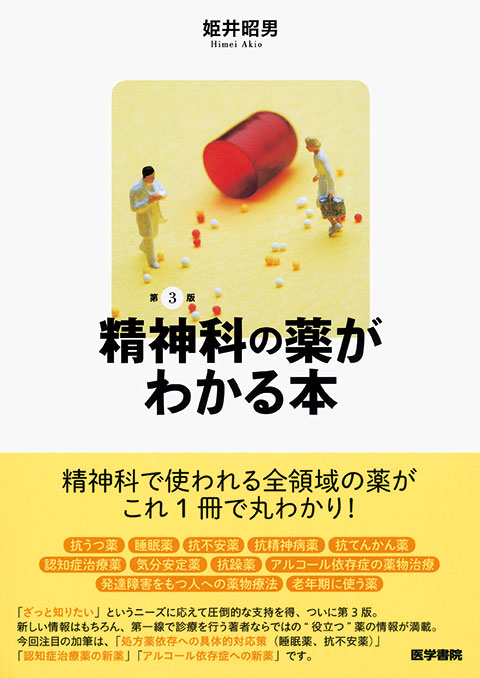精神科の薬がわかる本 第2版
精神科で使われる全領域の薬が、これ1冊で丸わかり! 好評本待望の第2版
もっと見る
精神科で使われる全領域の薬が、これ1冊で丸わかり! ざっと知っておきたい、大事なことだけ知りたい、副作用と禁忌だけは押さえたい―そんなニーズに合致して圧倒的な支持を得た初版。3年の時を経て、注目の新薬、非定型抗精神病薬の新アルゴリズム、精神科薬が関連する社会問題への方策などを加筆。
| 著 | 姫井 昭男 |
|---|---|
| 発行 | 2011年06月判型:A5頁:216 |
| ISBN | 978-4-260-01385-7 |
| 定価 | 2,200円 (本体2,000円+税) |
- 販売終了
更新情報
-
更新情報はありません。
お気に入り商品に追加すると、この商品の更新情報や関連情報などをマイページでお知らせいたします。
- 序文
- 目次
序文
開く
第2版によせて
精神科の薬はあなたの身体で何をするのか
『精神科の薬がわかる本』初版の刊行は2008年11月。すでに3年が経ちました。
初版発行時、私は精神科医療、とくに薬物療法について、“こうあってほしい”という理想を込めて書き上げました。そうした私の意図が読者にどれほど伝わるか非常に不安だったのですが、それは杞憂でした。伝わったということがわかるたくさんの反響のお手紙や書評をいただいたからです。そしてその結果として、第2版がここにあります。
声を寄せてくださったのは医療関係者だけではありません。現在治療を受けていらっしゃる当事者の方からもたくさんの質問や意見をちょうだいしました。
そのなかに、次のようなものがありました。「長い間薬を飲んでいますが、少しもよくならないのです。現在の薬は間違っているのではないでしょうか。どんな薬が私には合うのでしょうか」。
この答えに該当するような記述が初版にはなかったと思います。そしてこの質問は、多くの当事者や家族が抱いているものでありましょうし、また現在の精神科薬物治療が包含する問題を端的に示しているとも感じますので、第2版の冒頭にあたってはそのことを書きたいと思います。
「治療を受ける」という言い方があるように、一般的に“治療”には、医療者が病気を取り除いてくれるといった“受け身”なイメージが伴います。ですから“治療薬”に対して、「病を根底から治してくれるもの」というイメージをもつのも当然です。
しかし精神科の薬については、そのイメージを若干修正していただかなければなりません。
メンタル障害は、ほとんどの場合、脳内におけるニューロンネットワークにおける機能不全、つまりは神経伝達物質量の変化が原因で発現します。人間にはその問題を自己修復する機能が備わっていますが、その機能がうまくはたらかないときの“補助”や、その能力を“増強”するのが精神科の薬の役割になります。
つまり、メンタル障害からの回復の主体は「自身に備わった機能」なのです。精神科薬物療法はその回復をサポートするものであり、さらに正確にいえば対症療法に過ぎない(症状は改善させても、病気の原因そのものを取り除くものではない)のです。
このように精神科の薬の本当の役割を理解すれば、他力本願ならぬ、薬力本願という、薬に頼りすぎた治療にはならないはずです。
最近“治らないうつ”が問題になっており、私の施設にも、多くの方がうつを訴えて来院されます。精査してみると、実際には抗うつ薬が合っていないのではなく、本来もつ自己の回復力が発現されず、認知の障害を起こしているケースがほとんどです。
そのような人たちには、精神科の薬の本来の役割と、人に備わった回復の機能のことを説明し、「薬が治してくれるのを待つ」のではなく、「自分自身に備わった機能を最大限に発揮させ、メンタル障害を克服していく」ことを治療指針に決めます。するとそれだけで、患者さん自身に能動的に治療に参加する姿勢が生まれてきます。何年治療を受けても改善しなかったケースが、そうした説明をするだけで、処方内容を変えていないにもかかわらず、回復を見ることが少なくないのです。
精神科の薬とは何なのか。あなたの身体のなかで一体何を行っているのか。薬ができることとできないことの範囲は―─。そうしたことについて正しい知識をもつことが、精神科の薬の効果を最大限に引き出すことにつながると考えます。
この本は、精神科の薬を概説し、容易に理解できることを第一に考えて執筆しました。この本が、初版に引き続き、多くの人がもつ精神科の薬についてのさまざまな思い(誤解や恐れや心配や期待など)と、現実とを近づける役割を担うことを願っています。
精神科の薬はあなたの身体で何をするのか
『精神科の薬がわかる本』初版の刊行は2008年11月。すでに3年が経ちました。
初版発行時、私は精神科医療、とくに薬物療法について、“こうあってほしい”という理想を込めて書き上げました。そうした私の意図が読者にどれほど伝わるか非常に不安だったのですが、それは杞憂でした。伝わったということがわかるたくさんの反響のお手紙や書評をいただいたからです。そしてその結果として、第2版がここにあります。
声を寄せてくださったのは医療関係者だけではありません。現在治療を受けていらっしゃる当事者の方からもたくさんの質問や意見をちょうだいしました。
そのなかに、次のようなものがありました。「長い間薬を飲んでいますが、少しもよくならないのです。現在の薬は間違っているのではないでしょうか。どんな薬が私には合うのでしょうか」。
この答えに該当するような記述が初版にはなかったと思います。そしてこの質問は、多くの当事者や家族が抱いているものでありましょうし、また現在の精神科薬物治療が包含する問題を端的に示しているとも感じますので、第2版の冒頭にあたってはそのことを書きたいと思います。
「治療を受ける」という言い方があるように、一般的に“治療”には、医療者が病気を取り除いてくれるといった“受け身”なイメージが伴います。ですから“治療薬”に対して、「病を根底から治してくれるもの」というイメージをもつのも当然です。
しかし精神科の薬については、そのイメージを若干修正していただかなければなりません。
メンタル障害は、ほとんどの場合、脳内におけるニューロンネットワークにおける機能不全、つまりは神経伝達物質量の変化が原因で発現します。人間にはその問題を自己修復する機能が備わっていますが、その機能がうまくはたらかないときの“補助”や、その能力を“増強”するのが精神科の薬の役割になります。
つまり、メンタル障害からの回復の主体は「自身に備わった機能」なのです。精神科薬物療法はその回復をサポートするものであり、さらに正確にいえば対症療法に過ぎない(症状は改善させても、病気の原因そのものを取り除くものではない)のです。
このように精神科の薬の本当の役割を理解すれば、他力本願ならぬ、薬力本願という、薬に頼りすぎた治療にはならないはずです。
最近“治らないうつ”が問題になっており、私の施設にも、多くの方がうつを訴えて来院されます。精査してみると、実際には抗うつ薬が合っていないのではなく、本来もつ自己の回復力が発現されず、認知の障害を起こしているケースがほとんどです。
そのような人たちには、精神科の薬の本来の役割と、人に備わった回復の機能のことを説明し、「薬が治してくれるのを待つ」のではなく、「自分自身に備わった機能を最大限に発揮させ、メンタル障害を克服していく」ことを治療指針に決めます。するとそれだけで、患者さん自身に能動的に治療に参加する姿勢が生まれてきます。何年治療を受けても改善しなかったケースが、そうした説明をするだけで、処方内容を変えていないにもかかわらず、回復を見ることが少なくないのです。
精神科の薬とは何なのか。あなたの身体のなかで一体何を行っているのか。薬ができることとできないことの範囲は―─。そうしたことについて正しい知識をもつことが、精神科の薬の効果を最大限に引き出すことにつながると考えます。
この本は、精神科の薬を概説し、容易に理解できることを第一に考えて執筆しました。この本が、初版に引き続き、多くの人がもつ精神科の薬についてのさまざまな思い(誤解や恐れや心配や期待など)と、現実とを近づける役割を担うことを願っています。
目次
開く
第2版によせて
1.「抗うつ薬」がわかる。
◎抗うつ薬へのQ&A
2.「睡眠薬」がわかる。
◎睡眠薬へのQ&A
3.「抗精神病薬」がわかる。
1 統合失調症とは
2 定型抗精神病薬の特徴
3 非定型抗精神病薬の特徴
4 重大な副作用
5 剤型による特徴
◎抗精神病薬へのQ&A
Lecture 単剤化の方法
4.「抗てんかん薬」がわかる。
◎抗てんかん薬へのQ&A
5.「老年期に使う薬」がわかる。
1 薬を使う前に気をつけておきたいこと
2 認知症(アルツハイマー型認知症)の治療薬
3 パーキンソン病の治療薬
4 うつ病・抑うつ状態の治療薬
5 頭部外傷の後遺症の治療薬
6 夜間せん妄の治療薬
7 代謝性意識障害への対処
◎老年期に使う薬へのQ&A
6.「その他の精神科の薬」がわかる。
1 気分安定薬
2 抗躁薬
3 抗不安薬
4 抗酒薬
5 悪性症候群の治療薬
6 発達障害をもつ人への薬物療法
◎「その他の精神科の薬」へのQ&A
索引
あとがき
1.「抗うつ薬」がわかる。
◎抗うつ薬へのQ&A
2.「睡眠薬」がわかる。
◎睡眠薬へのQ&A
3.「抗精神病薬」がわかる。
1 統合失調症とは
2 定型抗精神病薬の特徴
3 非定型抗精神病薬の特徴
4 重大な副作用
5 剤型による特徴
◎抗精神病薬へのQ&A
Lecture 単剤化の方法
4.「抗てんかん薬」がわかる。
◎抗てんかん薬へのQ&A
5.「老年期に使う薬」がわかる。
1 薬を使う前に気をつけておきたいこと
2 認知症(アルツハイマー型認知症)の治療薬
3 パーキンソン病の治療薬
4 うつ病・抑うつ状態の治療薬
5 頭部外傷の後遺症の治療薬
6 夜間せん妄の治療薬
7 代謝性意識障害への対処
◎老年期に使う薬へのQ&A
6.「その他の精神科の薬」がわかる。
1 気分安定薬
2 抗躁薬
3 抗不安薬
4 抗酒薬
5 悪性症候群の治療薬
6 発達障害をもつ人への薬物療法
◎「その他の精神科の薬」へのQ&A
索引
あとがき
更新情報
-
更新情報はありません。
お気に入り商品に追加すると、この商品の更新情報や関連情報などをマイページでお知らせいたします。