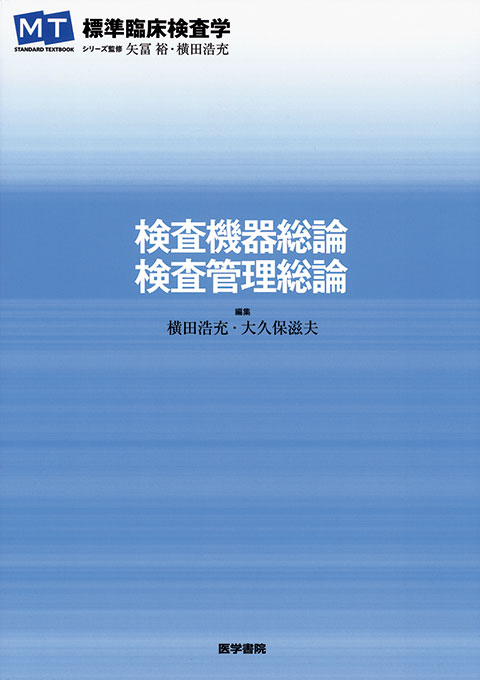検査機器総論・検査管理総論
医師と臨床検査技師のコラボによる新しい教科書【標準MT】シリーズ
もっと見る
臨床検査の実務を行う上で必須の知識である機器及び検査管理。本書ではこの2科目の内容を簡潔にまとめた。臨床現場に出た後も、また検査部の管理を司る立場になった後も、継続的に必要とされるのが本書のカバーする分野。執筆には医療現場で活躍する臨床検査技師が多数加わっている。全ページ2色刷。美麗なイラストで国家試験に向けての学習をより効果的に進められる。
*「標準臨床検査学」は株式会社医学書院の登録商標です。
医学書院の“青本”シリーズ≪標準臨床検査学≫が完全リニューアル! 臨床検査技師を志す学生向けの新しい教科書シリーズです。 ●シリーズの特徴 ・標準的なカリキュラムに対応し、使い勝手のよい編成 ・臨床検査技師国家試験出題基準に完全対応、必要にして十分な記述内容 ・医師と臨床検査技師のコラボで生まれた教科書 ●ラインナップ ≫全12巻の一覧はこちら
更新情報
-
更新情報はありません。
お気に入り商品に追加すると、この商品の更新情報や関連情報などをマイページでお知らせいたします。
- 序文
- 目次
- 正誤表
序文
開く
刊行のことば(矢冨 裕・横田浩充)/序(横田浩充・大久保滋夫)
刊行のことば
「標準臨床検査学」シリーズは,「臨床検査技師講座」(1972年発刊),「新臨床検査技師講座」(1983年発刊),さらには「臨床検査技術学」(1997年発刊)という医学書院の臨床検査技師のための教科書の歴史を踏まえ,新しい時代に即した形で刷新したものである.
臨床検査は患者の診断,治療効果の判定になくてはならないものであり,医療の根幹をなす.この臨床検査は20世紀の後半以降,医学研究,生命科学研究の爆発的進歩と歩調を合わせる形で,大きく進歩した.そして臨床検査の項目・件数が大きく増加し,内容も高度かつ専門的になるにつれ,病院には,臨床検査の専門部署である検査部門が誕生し,臨床検査技師が誕生した.臨床検査の中央化と真の専門家による実践というこの体制が,わが国の医療の発展に大きく貢献したこと,そして,今後も同じであることは明らかである.
このような発展めざましい臨床検査の担い手となることを目指す方々のための教科書となることを目指し,新たなシリーズを企画した.発刊にあたっては,(1)臨床検査の実践において必要な概念,理論,技術を俯瞰できる,(2)今後の臨床検査技師に必要とされる知識,検査技術の基礎となる医学知識などを過不足なく盛り込む,(3)最新の国家試験出題基準の内容をすべて網羅することを念頭に置いた.しかしながら国家試験合格のみを最終目的とはせず,実際の臨床現場において医療チームの重要な一員として活躍できるような臨床検査技師,研究マインドが持てるような臨床検査技師になっていただけることを願って,より体系だった深い内容となることも目指している.また,若い方々が興味を持って学習を継続できるように,レイアウトや記載方法も工夫した.
本書で学んだ臨床検査技師が,臨床検査の現場で活躍されることを願うものである.
2012年春
矢冨 裕
横田浩充
序
臨床検査の目的は患者診療と人の健康維持にかかわる臨床医のニーズを満たすために迅速で信頼性の高い検査データを提供することにある.この目的を達成するためには本書の検査機器総論から臨床検査機器の知識および適切な取り扱いを学び,検査管理総論にて品質マネジメントシステムを学ぶことが重要となる.
本書は臨床検査技師国家試験の出題範囲をベースに検査機器総論・検査管理総論を一冊に包括した.
第1部の検査機器総論は臨床検査の各分野で使用される共通機器・分析機器について,その原理,構造,使用法と取り扱いの注意点,保守管理などについて理解してもらうべく目次を構成した.これらの検査機器を理解し,適切に操作することが正確なデータを報告するうえで重要であるため,しっかり学習していただきたい.
第2部の検査管理総論では医療と臨床検査の変遷に始まり,病院と検査部門の役割,検査管理の定義,検査部門の管理と運営,臨床検査の組織の管理を前半にまとめた.検査管理は人事管理,物品管理,技術管理,経営管理,情報管理と多種にわたる.さらに客観的評価として病院機能評価,臨床検査室を対象としたISO 15189などの外部評価も策定されている.このような評価では,管理職のみが管理運営を行うのではなく医療従事者全員での運営が求められている.種々の運営に対してどのように取り組み,どのような姿勢が必要かを学習していただきたい.
実際の検査室の運用にあたっては検査の受付と報告,精度管理,検査情報の判断とその活用を取り上げた.実践での活用を学んでいただきたい.最後に臨床検査技師の生涯教育を取り上げた.臨床検査技師として相当の知識と専門性の追究,力量保持のため,卒業後も生涯にわたり必要な知識と技術を習得する自己研鑽やコミュニケーション能力が必須である.各種認定試験の取得や学位(博士)の取得を視野に入れ,日々研鑽していく姿勢が望まれる.
本書の執筆者は現役の臨床検査学教育課程の教員および大学病院医療技術部や臨床検査部において,検査室の管理運営に携わっている医療技術部長,臨床検査技師長を中心に構成した.時宜を得た内容の教科書を目指し完成したと考えている.ただし,不十分な点については忌憚のないご意見をお寄せいただきたい.ご意見をいただくことで,よりよい教科書にしていく所存である.
2012年12月
横田 浩充
大久保滋夫
刊行のことば
「標準臨床検査学」シリーズは,「臨床検査技師講座」(1972年発刊),「新臨床検査技師講座」(1983年発刊),さらには「臨床検査技術学」(1997年発刊)という医学書院の臨床検査技師のための教科書の歴史を踏まえ,新しい時代に即した形で刷新したものである.
臨床検査は患者の診断,治療効果の判定になくてはならないものであり,医療の根幹をなす.この臨床検査は20世紀の後半以降,医学研究,生命科学研究の爆発的進歩と歩調を合わせる形で,大きく進歩した.そして臨床検査の項目・件数が大きく増加し,内容も高度かつ専門的になるにつれ,病院には,臨床検査の専門部署である検査部門が誕生し,臨床検査技師が誕生した.臨床検査の中央化と真の専門家による実践というこの体制が,わが国の医療の発展に大きく貢献したこと,そして,今後も同じであることは明らかである.
このような発展めざましい臨床検査の担い手となることを目指す方々のための教科書となることを目指し,新たなシリーズを企画した.発刊にあたっては,(1)臨床検査の実践において必要な概念,理論,技術を俯瞰できる,(2)今後の臨床検査技師に必要とされる知識,検査技術の基礎となる医学知識などを過不足なく盛り込む,(3)最新の国家試験出題基準の内容をすべて網羅することを念頭に置いた.しかしながら国家試験合格のみを最終目的とはせず,実際の臨床現場において医療チームの重要な一員として活躍できるような臨床検査技師,研究マインドが持てるような臨床検査技師になっていただけることを願って,より体系だった深い内容となることも目指している.また,若い方々が興味を持って学習を継続できるように,レイアウトや記載方法も工夫した.
本書で学んだ臨床検査技師が,臨床検査の現場で活躍されることを願うものである.
2012年春
矢冨 裕
横田浩充
序
臨床検査の目的は患者診療と人の健康維持にかかわる臨床医のニーズを満たすために迅速で信頼性の高い検査データを提供することにある.この目的を達成するためには本書の検査機器総論から臨床検査機器の知識および適切な取り扱いを学び,検査管理総論にて品質マネジメントシステムを学ぶことが重要となる.
本書は臨床検査技師国家試験の出題範囲をベースに検査機器総論・検査管理総論を一冊に包括した.
第1部の検査機器総論は臨床検査の各分野で使用される共通機器・分析機器について,その原理,構造,使用法と取り扱いの注意点,保守管理などについて理解してもらうべく目次を構成した.これらの検査機器を理解し,適切に操作することが正確なデータを報告するうえで重要であるため,しっかり学習していただきたい.
第2部の検査管理総論では医療と臨床検査の変遷に始まり,病院と検査部門の役割,検査管理の定義,検査部門の管理と運営,臨床検査の組織の管理を前半にまとめた.検査管理は人事管理,物品管理,技術管理,経営管理,情報管理と多種にわたる.さらに客観的評価として病院機能評価,臨床検査室を対象としたISO 15189などの外部評価も策定されている.このような評価では,管理職のみが管理運営を行うのではなく医療従事者全員での運営が求められている.種々の運営に対してどのように取り組み,どのような姿勢が必要かを学習していただきたい.
実際の検査室の運用にあたっては検査の受付と報告,精度管理,検査情報の判断とその活用を取り上げた.実践での活用を学んでいただきたい.最後に臨床検査技師の生涯教育を取り上げた.臨床検査技師として相当の知識と専門性の追究,力量保持のため,卒業後も生涯にわたり必要な知識と技術を習得する自己研鑽やコミュニケーション能力が必須である.各種認定試験の取得や学位(博士)の取得を視野に入れ,日々研鑽していく姿勢が望まれる.
本書の執筆者は現役の臨床検査学教育課程の教員および大学病院医療技術部や臨床検査部において,検査室の管理運営に携わっている医療技術部長,臨床検査技師長を中心に構成した.時宜を得た内容の教科書を目指し完成したと考えている.ただし,不十分な点については忌憚のないご意見をお寄せいただきたい.ご意見をいただくことで,よりよい教科書にしていく所存である.
2012年12月
横田 浩充
大久保滋夫
目次
開く
第1部 検査機器総論
I 検査機器 総説
第1章 総説
A 用手法検査から自動化機器での検査
B 自動化機器による検体検査
C 自動化機器と検体搬送システムの取り扱いの注意点と心構え
II 検査機器 概論
第1章 概論 I
A 検体検査:自動化の構築
第2章 概論 II
A 物理化学量
B SI単位と慣用単位
C 標準物質の役割
D 自動化機器の管理法
E 外部精度管理への参加
F 基準範囲の取り扱い
G 検査情報システム
III 検査機器 各論 機器の原理・構造と使い方
第1章 周辺器具・装置
A 計量器具
B 天びん
C 恒温装置
D 滅菌装置
E 純水製造装置
F 温度計・湿度計
G 冷蔵庫・冷凍庫
H 顕微鏡
第2章 前処理装置
A 遠心分離装置(遠心機)
B 攪拌装置
第3章 分離分析装置
A 電気泳動装置
B クロマトグラフィ
第4章 測光・電気化学装置
A 光度計
B 電気化学装置
第5章 測定装置
A 小型卓上測定装置
第2部 検査管理総論
第1章 医療のなかでの臨床検査
A 医療と臨床検査の変遷
B 臨床検査の意義
第2章 臨床検査管理の概念
A 病院と検査部門の役割
B 検査管理の定義
C 検査の倫理
第3章 検査部門の体制・業務
A 検査体制と変遷
B 検査部門の業務
第4章 検査部門の管理・運営
A 業務管理
B 人事管理
C 検査機器管理
D 物品管理
E 情報管理
F 財務管理
G リスクマネジメント
H 安全管理
第5章 検査の受付・報告
A 検査受付
B 検体の前処理と検査
C 検査結果の報告
第6章 検査の精度保証
A 概要
B 臨床検査における測定法の標準化
C 検査法の信頼性評価と日常検査への適用
D 誤差の許容限界
E 精度管理法
第7章 検査情報の判断
A 基準範囲
B 臨床検査性能評価
第8章 検査の活用
A 予防医学
B 臨床医学
第9章 臨床検査技師の生涯教育
A 卒後教育
B 認定資格
和文索引
欧文索引
I 検査機器 総説
第1章 総説
A 用手法検査から自動化機器での検査
B 自動化機器による検体検査
C 自動化機器と検体搬送システムの取り扱いの注意点と心構え
II 検査機器 概論
第1章 概論 I
A 検体検査:自動化の構築
第2章 概論 II
A 物理化学量
B SI単位と慣用単位
C 標準物質の役割
D 自動化機器の管理法
E 外部精度管理への参加
F 基準範囲の取り扱い
G 検査情報システム
III 検査機器 各論 機器の原理・構造と使い方
第1章 周辺器具・装置
A 計量器具
B 天びん
C 恒温装置
D 滅菌装置
E 純水製造装置
F 温度計・湿度計
G 冷蔵庫・冷凍庫
H 顕微鏡
第2章 前処理装置
A 遠心分離装置(遠心機)
B 攪拌装置
第3章 分離分析装置
A 電気泳動装置
B クロマトグラフィ
第4章 測光・電気化学装置
A 光度計
B 電気化学装置
第5章 測定装置
A 小型卓上測定装置
第2部 検査管理総論
第1章 医療のなかでの臨床検査
A 医療と臨床検査の変遷
B 臨床検査の意義
第2章 臨床検査管理の概念
A 病院と検査部門の役割
B 検査管理の定義
C 検査の倫理
第3章 検査部門の体制・業務
A 検査体制と変遷
B 検査部門の業務
第4章 検査部門の管理・運営
A 業務管理
B 人事管理
C 検査機器管理
D 物品管理
E 情報管理
F 財務管理
G リスクマネジメント
H 安全管理
第5章 検査の受付・報告
A 検査受付
B 検体の前処理と検査
C 検査結果の報告
第6章 検査の精度保証
A 概要
B 臨床検査における測定法の標準化
C 検査法の信頼性評価と日常検査への適用
D 誤差の許容限界
E 精度管理法
第7章 検査情報の判断
A 基準範囲
B 臨床検査性能評価
第8章 検査の活用
A 予防医学
B 臨床医学
第9章 臨床検査技師の生涯教育
A 卒後教育
B 認定資格
和文索引
欧文索引
正誤表
開く
本書の記述の正確性につきましては最善の努力を払っておりますが、この度弊社の責任におきまして、下記のような誤りがございました。お詫び申し上げますとともに訂正させていただきます。